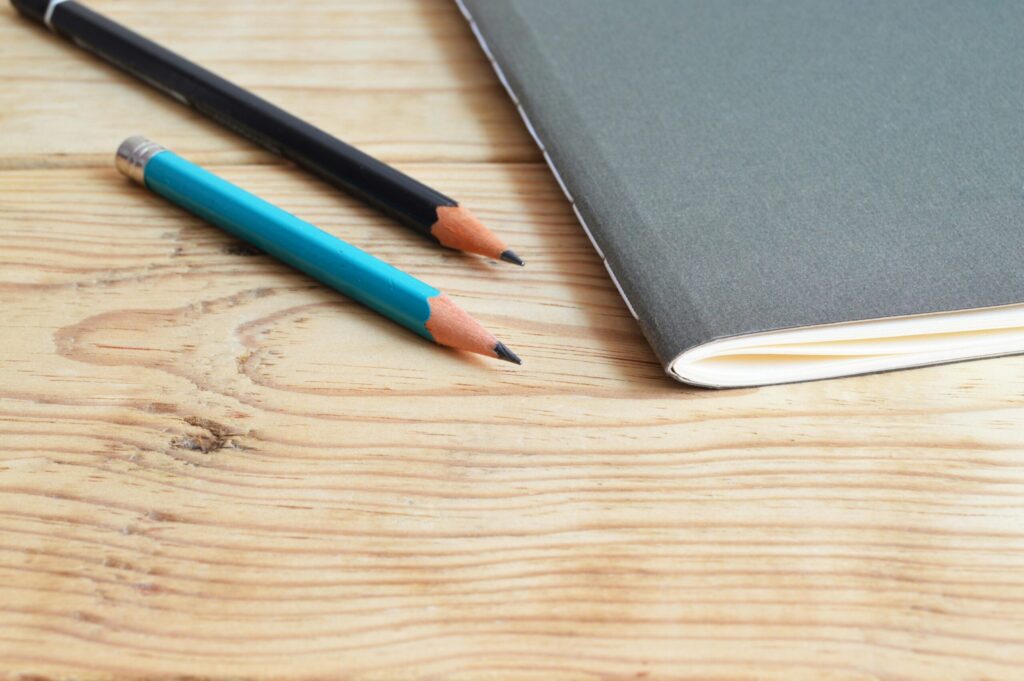近年、地域保健の重要性が高まる中で、保健師(PHN: Public Health Nurse)の役割と需要が拡大しています。
本記事では、保健師の資格概要から業務範囲、専門性、そして将来性まで、現役保健師の視点を交えながら包括的に解説します。
保健師を目指す方はもちろん、キャリアアップを考える看護師の方にとっても有益な情報をお届けします。
地域住民の健康を支える保健師という職業の魅力と可能性を探り、そのキャリア形成における実践的なアプローチを紹介していきます。
この記事で分かること
- 保健師(PHN)の資格概要と取得方法の最新情報
- 保健師の具体的な業務内容と多様な活動領域
- 保健師としての専門性を効果的に高めるための方法
- 多様なキャリアパスと将来展望の可能性
- 現場で活躍する保健師の具体的な実践例と成功事例
- 地域別の保健師活動の特徴と実践方法
- 保健師の一日の具体的なスケジュールと業務の実際
この記事を読んでほしい人
- 保健師を目指している看護学生
- 保健師資格の取得を検討している看護師
- キャリアチェンジを考えている医療従事者
- 保健師として働いているが専門性向上を目指している方
- 公衆衛生や地域保健に関心がある方
- 保健師の採用や育成に関わる管理職
- 地域医療や予防医学に興味のある医療関係者
保健師(PHN)とは?基本的な理解と資格概要

保健師(Public Health Nurse)は、地域住民の健康維持・増進を目的に活動する公衆衛生の専門家です。
個人だけでなく、家族や地域全体の健康課題に取り組み、予防医学の観点から健康支援を行います。
医療機関で患者の治療をサポートする看護師とは異なり、地域社会で健康問題の予防と解決に主体的に取り組むことが特徴です。
保健師の活動は「予防」に重点を置いており、一次予防(健康増進・疾病予防)、二次予防(早期発見・早期治療)、三次予防(リハビリテーション・再発防止)のすべての段階で活躍します。
地域住民の健康レベルを向上させるため、個人の健康問題だけでなく、社会的・環境的要因にも目を向け、健康の公平性を確保するための活動を展開しています。
保健師資格の取得方法
保健師になるためには、主に以下の2つのルートがあります。
第一のルートは大学ルートです。
看護系大学で看護師養成課程と並行して保健師養成課程(選択制)を修了することで、看護師と保健師の国家試験受験資格を同時に取得できます。
2009年のカリキュラム改正以降、多くの大学では保健師養成課程が選択制となり、定員が限られているため、成績や選考試験によって選抜されることが一般的です。
第二のルートは大学院・専門学校ルートです。
看護師資格を取得した後、保健師養成課程のある大学院や専門学校で1年間学ぶことで、保健師国家試験の受験資格を得られます。
社会人経験を経てから保健師を目指す方に適したルートであり、臨床経験を活かした実践的な保健活動ができる強みがあります。
いずれのルートでも、最終的には保健師国家試験に合格することが必要です。
2024年の保健師国家試験の合格率は約90%でしたが、試験内容は年々高度化しており、公衆衛生学や疫学、保健統計学などの専門知識が問われます。
近年は特に、地域診断能力や健康危機管理、多職種連携に関する問題が増加傾向にあります。
保健師資格の特徴と社会的意義
保健師資格の最大の特徴は、「予防」に重点を置いた公衆衛生活動ができる点です。
看護師が主に医療機関で患者の治療をサポートするのに対し、保健師は地域社会で健康問題の予防と解決に取り組みます。
また、地域全体を「対象者」として捉える視点を持ち、集団や地域全体の健康度を高めるための施策を展開することができます。
保健師の社会的意義は、健康格差の縮小と健康寿命の延伸にあります。
少子高齢化や生活習慣病の増加、メンタルヘルスの問題など、現代社会の健康課題は複雑化しており、治療だけでなく予防的アプローチが不可欠です。
保健師はその専門性を活かし、エビデンスに基づいた予防活動を推進することで、医療費の適正化や住民のQOL向上に貢献しています。
2025年現在、全国の保健師数は約5万3千人であり、その約7割が行政機関に所属しています。
近年は企業の健康経営推進に伴い、産業保健師の需要も高まっており、活躍の場は広がりつつあります。
また、災害時の健康支援や感染症対策など、健康危機管理における保健師の役割も注目されています。
保健師の業務範囲と活動領域

保健師の業務は多岐にわたり、活動領域も幅広いのが特徴です。
公衆衛生の専門家として、個人から地域全体まで様々なレベルでの健康支援を行います。
保健師の活動は、法律上は保健師助産師看護師法と地域保健法を根拠としており、地域保健対策の主要な担い手として位置づけられています。
主な業務内容
保健師の業務は大きく分けて以下の項目に分類されます。
これらの業務は相互に関連しており、総合的に展開されることで効果を発揮します。
健康相談・保健指導
保健師の業務は大きく分けて以下の項目に分類されます。
これらの業務は相互に関連しており、総合的に展開されることで効果を発揮します。
健康相談・保健指導
健康相談・保健指導は保健師の基本的な業務の一つです。
各種健診や相談事業を通じて、住民一人ひとりの健康状態を評価し、必要な保健指導を行います。
乳幼児健診では子どもの発育状態の確認と共に、育児不安を抱える保護者の心理的サポートも重要な役割です。
特定健診・特定保健指導では、メタボリックシンドロームをはじめとする生活習慣病の予防に焦点を当て、個別の生活習慣改善プログラムを提案します。
単なる知識の提供にとどまらず、行動変容を促すためのコーチング技術や動機づけ面接法などを活用し、対象者の自己効力感を高めることが重要です。
メンタルヘルス対策も重要な業務となっています。
うつ病や自殺予防の相談窓口の運営、心の健康づくり教室の開催などを通じて、地域住民の心の健康維持を支援します。
特に2023年の調査では、全国の自治体の88%が保健師によるメンタルヘルス支援事業を展開しており、その重要性が高まっています。
家庭訪問
家庭訪問は保健師の特徴的な活動の一つで、地域住民の生活の場に直接出向いて支援を行います。
新生児・乳幼児家庭への訪問では、赤ちゃんの発育状態の確認だけでなく、母親の産後うつの早期発見や育児環境の整備、必要なサービスへの連携などを行います。
2021年度の統計では、全国の市区町村で新生児の約85%に対して保健師による訪問が実施されています。
高齢者・障がい者世帯への訪問では、健康状態の確認と共に、必要な福祉サービスの紹介や調整、緊急時の対応方法の確認などを行います。
特に独居高齢者の場合は、地域包括支援センターや民生委員と連携し、地域全体で見守る体制づくりも保健師の重要な役割です。
困難事例への継続的支援も保健師ならではの業務です。
複合的な問題を抱える家庭や、支援を拒否するケースなど、通常のサービスでは対応困難な事例に対して、根気強く関わり続けることで信頼関係を築き、必要な支援につなげていきます。
こうした「アウトリーチ」の手法は、健康格差の是正においても重要な意味を持っています。
地域保健活動
地域保健活動は、地域全体の健康レベル向上を目指した取り組みです。
健康づくり教室の企画・運営では、運動習慣の定着や食生活の改善、口腔ケアなど、様々なテーマで住民参加型の教室を開催します。
最近では、オンラインを活用した健康教室も増えており、時間や場所の制約を超えた支援が可能になっています。
地域診断に基づく健康課題の抽出は保健師の重要な専門性の一つです。
人口統計や健診データ、住民の声などから地域特有の健康課題を科学的に分析し、効果的な対策を立案します。
例えば、A市では保健師による地域診断から高齢者の低栄養問題が明らかになり、地域の飲食店と連携した「健康応援メニュー」の開発につながった事例があります。
地域のネットワークづくりでは、医療機関や福祉施設、学校、企業、NPOなど様々な機関と連携し、地域全体で健康づくりを支える体制を構築します。
2023年度の調査では、効果的な地域保健活動の鍵として「多様な機関とのネットワーク構築力」が最も重要視されており、保健師のコーディネーション能力が問われています。
感染症対策
感染症対策は保健所を中心に展開される重要な業務です。
感染症発生時の調査・対応では、感染源の特定や感染拡大防止のための積極的疫学調査を実施します。
特に新型コロナウイルス感染症の流行を経て、保健師の感染症対応能力の重要性が再認識されています。
予防接種事業の運営では、定期予防接種の実施体制の整備や接種率向上のための啓発活動、副反応への対応などを行います。
特に近年は、HPVワクチンの積極的勧奨再開や、高齢者肺炎球菌ワクチンの普及活動など、科学的根拠に基づいた情報提供が求められています。
感染症予防の啓発活動では、正しい手洗いの指導や咳エチケットの普及、感染症に関する正確な情報発信などを行います。
特に学校や高齢者施設など集団生活の場での感染対策は重要で、施設職員への研修や体制整備の支援も保健師の役割となっています。
主な活動場所
保健師の活動場所は多様であり、それぞれの場所によって求められる役割や専門性が異なります。
ここでは主な活動場所と、そこでの具体的な業務内容について詳しく見ていきましょう。
行政機関
行政機関は保健師の最も一般的な就業先であり、市区町村保健センターや保健所、都道府県庁などが含まれます。
市区町村保健センターでは、母子保健、成人保健、高齢者保健などの業務を担当します。
具体的には、乳幼児健診や育児相談、特定健診・特定保健指導、介護予防事業などを実施します。
住民に最も身近な自治体として、一人ひとりの健康課題に寄り添いながら、地域特性に合わせた保健サービスを提供しています。
2024年度の全国調査によると、市区町村保健師一人あたりの担当人口は平均で約3,500人となっており、地域によって差があるものの、きめ細かな対応が求められています。
保健所では、より専門的・広域的な業務を担当します。
感染症対策、精神保健、難病対策、医事・薬事指導など、高度な専門知識を要する業務が中心です。
また、複数の市区町村にまたがる健康課題への対応や、災害時の健康危機管理の拠点としての役割も担っています。
2023年の改正地域保健法の施行により、保健所機能の強化が図られ、特に健康危機管理体制の整備において保健師の専門性が重視されるようになっています。
都道府県・国の機関では、政策立案や人材育成、市区町村支援などの業務を担当します。
広域的な視点から健康施策を展開し、市区町村保健師への技術的支援や研修会の開催などを通じて、地域保健活動の質の向上を図っています。
国立保健医療科学院や厚生労働省などでは、全国的な健康政策の策定や評価に関わる業務も行っています。
医療機関
医療機関に勤務する保健師は、主に地域連携や予防医療の分野で活躍しています。
病院では、地域連携部門や訪問看護ステーションなどで勤務し、患者の退院支援や在宅療養支援、地域の医療機関との連携強化などを担当します。
特に地域包括ケアシステムの推進において、病院と地域をつなぐコーディネーターとしての役割が重要視されています。
また、病院の健診センターでは、人間ドックなどの健診後の保健指導や生活習慣改善支援を行っています。
診療所では、かかりつけ医と連携して地域住民の健康管理を担うほか、訪問診療のサポートや在宅療養患者の生活指導なども行います。
特に在宅医療の推進において、医療と生活の両面から患者と家族を支える保健師の役割は重要です。
2023年度からは、一部の診療所で「プライマリ・ヘルスケア推進加算」が新設され、保健師が健康増進や予防活動に関わる機会が増えています。
企業・学校
企業や学校など、特定の集団を対象とした保健活動も保健師の重要な活動領域です。
産業保健の分野では、企業の健康管理室や健康保険組合などで勤務し、従業員の健康管理や職場環境改善を担当します。
具体的には、定期健康診断の事後指導、メンタルヘルス対策、過重労働対策、健康経営の推進など、働く人々の健康保持増進に関わる様々な業務を行います。
特に近年は「健康経営」の概念が広まり、企業の経営戦略として従業員の健康づくりを推進する動きが強まっており、産業保健師の専門性が注目されています。
2023年度の調査では、健康経営優良法人認定企業の約75%が産業保健師を雇用しており、その経済効果も実証されつつあります。
学校保健の分野では、教育委員会や学校に勤務し、児童・生徒の健康管理や健康教育を担当します。
学校健診の企画・実施、感染症対策、アレルギー対応、性教育やメンタルヘルス教育など、成長期にある子どもたちの健康課題に対応します。
特に近年は、子どもの貧困やヤングケアラー、不登校などの社会的問題に対して、保健室を拠点とした支援体制の構築が求められており、保健師の専門性を活かした取り組みが期待されています。
福祉施設
福祉施設に勤務する保健師は、高齢者施設や障がい者施設などで利用者の健康管理や職員への保健指導を担当します。
高齢者施設では、入所者の健康状態のモニタリングや感染症対策、看取りケアなどを行うほか、介護予防プログラムの企画・実施なども担当します。
特に医療ニーズの高い入所者が増加する中、医療と介護をつなぐ役割として保健師の専門性が求められています。
また、施設内の感染管理においても、保健師の疫学的知識や予防的視点が重要視されています。
障がい者施設では、利用者の健康管理や生活習慣病予防、性教育などを担当するほか、地域生活への移行支援や就労支援においても保健師の視点を活かした支援を行います。
特に医療的ケアが必要な障がい者への支援では、医療と福祉をつなぐコーディネーターとしての役割が期待されています。
保健師の専門性を高める方法

保健師としてキャリアを積む上で、専門性の向上は不可欠です。
高度化・複雑化する健康課題に対応するためには、保健師としての基本的能力を土台としながら、さらに専門性を深めていくことが重要です。
ここでは、保健師の専門性を高めるための効果的な方法について詳しく解説します。
専門分野の選択と深化
保健師の活動領域は広いため、特定の分野に特化することで専門性を高めることができます。
自分の興味や強みを活かせる分野を選び、集中的に知識と技術を深めていくことが効果的です。
母子保健分野では、周産期メンタルヘルスや発達障害支援、児童虐待予防などの専門性を高めることができます。
特に近年は「産後ケア」や「子育て世代包括支援センター」の取り組みが全国的に広がりつつあり、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を提供できる保健師の需要が高まっています。
専門性を高めるために、ペアレントトレーニングや発達アセスメントなどの専門的技術を習得することも有効です。
成人・高齢者保健分野では、生活習慣病予防や介護予防、在宅医療などの専門性を高めることができます。
特に高齢社会が進展する中で、フレイル予防や認知症対策、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の推進など、新たな健康課題に対応できる専門的知識が求められています。
具体的には、フレイルチェックや栄養アセスメント、認知症サポーターキャラバンなどの研修を受講することで専門性を高めることができます。
精神保健分野では、うつ病や自殺対策、ひきこもり支援、依存症対策などの専門性を高めることができます。
メンタルヘルスの問題は年々複雑化しており、医療だけでなく福祉や教育、労働など様々な分野と連携した包括的支援が必要とされています。
精神保健福祉士の資格取得や認知行動療法、ゲートキーパー研修などを通じて専門性を高めることが有効です。
感染症対策分野では、疫学調査や健康危機管理、予防接種事業などの専門性を高めることができます。
新型コロナウイルス感染症の流行を経て、感染症対策における保健師の役割の重要性が再認識される中、PCR検査や疫学調査、リスクコミュニケーションなどの専門的知識が求められています。
感染制御の専門研修や疫学統計の学びを深めることで、専門性を高めることができます。
災害保健分野では、災害時の健康支援や復興支援、平常時の備えなどの専門性を高めることができます。
近年、自然災害が多発する中で、災害時の保健活動の重要性が高まっており、避難所の環境整備や要配慮者への支援、心のケアなど、様々な健康課題に対応できる専門的知識が求められています。
災害支援ナースの研修や災害時の公衆衛生対応研修などを受講することで専門性を高めることができます。
専門資格の取得
保健師としての専門性を証明するためには、関連する専門資格の取得も効果的です。
専門資格は、キャリアアップや転職の際にも強みとなります。
保健師助産師看護師実習指導者講習会修了は、保健師学生の実習指導を行うための資格です。
将来的に後進の育成に関わりたい保健師にとって有用な資格であり、教育的視点を身につけることで自身の実践の振り返りにもつながります。
全国の都道府県で開催される講習会(約240時間)を修了することで取得でき、実習指導者として活躍することができます。
第一種衛生管理者は、労働安全衛生法に基づく事業場の安全衛生管理のための国家資格です。
特に企業の健康管理部門や産業保健分野での活躍を目指す保健師にとって有用な資格であり、労働安全衛生の専門知識を証明することができます。
保健師資格を持っていれば、筆記試験のみで取得可能です。
健康経営アドバイザーは、東京商工会議所が認定する民間資格で、企業の健康経営推進を支援するための知識を証明します。
企業の経営戦略と連動した健康施策の立案・実施に関する専門性を示すことができ、産業保健師としてのキャリアアップに役立ちます。
オンライン講座と認定試験を経て取得することができます。
産業保健師は、日本産業保健師会が認定する資格で、産業保健の専門知識と実践力を証明します。
産業保健の分野で5年以上の実務経験と、所定の研修受講や事例報告などの要件を満たすことで認定されます。
企業の健康管理部門のリーダーやコンサルタントとしてのキャリアを目指す上で有用な資格です。
認定保健師は、日本看護協会が認定する資格で、保健師の専門性を公式に認証するものです。
2016年に創設された比較的新しい制度ですが、保健師として5年以上の実務経験と、所定の研修受講や業績評価などの厳格な審査を経て認定されます。
「地域看護」「産業看護」「学校看護」の3分野があり、それぞれの分野での高度な実践能力を証明することができます。
2024年現在、全国で約500名の認定保健師が活躍しており、専門性の証明として注目されています。
継続的な学習と研究活動
保健師の専門性を高めるためには、継続的な学習と研究活動も重要です。
常に最新の知見やエビデンスを取り入れることで、科学的根拠に基づいた保健活動を展開することができます。
大学院での学びは、保健師の専門性を学術的に深める有効な方法です。
公衆衛生学や地域看護学を専攻することで、理論的背景や研究手法を学び、実践の科学的基盤を強化することができます。
特に社会人大学院は働きながら学べるプログラムが充実しており、実践と研究を往還させながら専門性を高めることが可能です。
2023年の調査では、管理職保健師の約15%が大学院修士以上の学位を持っており、今後さらに増加することが予想されています。
学会や研修会への参加も専門性向上に欠かせません。
日本公衆衛生看護学会や日本地域看護学会などの学術団体が定期的に開催する学会では、最新の研究成果や実践事例を学ぶことができます。
また、全国保健師長会や日本看護協会などが主催する研修会も、専門知識の更新や実践力の向上に役立ちます。
オンライン研修が普及したことで、地理的制約なく継続教育を受けられる環境が整いつつあります。
自治体や職能団体の研修プログラムも活用価値が高いです。
各都道府県が実施する保健師現任教育や、日本看護協会の認定研修など、体系的な研修プログラムが整備されています。
特に新人期から管理職まで、キャリアステージに応じた研修を計画的に受講することで、段階的に専門性を高めることができます。
2024年度からは全国的に「保健師人材育成ガイドライン」に基づく研修体系の整備が進められており、より効果的な人材育成が期待されています。
事例検討会への積極的な参加も専門性向上に有効です。
複雑な保健課題に対する支援方法や評価方法を多角的に検討することで、実践力を高めることができます。
特に他の保健師や多職種との意見交換は、新たな視点や支援方法の発見につながります。
オンラインでの事例検討会も増えており、地域を超えた学び合いの機会が広がっています。
自己研鑽として、最新の文献や書籍を定期的に読むことも大切です。
公衆衛生や疫学、保健指導などに関する専門書だけでなく、社会学や心理学、行動経済学など関連分野の知見も取り入れることで、複合的な健康課題に対応する力が養われます。
インターネット上の専門サイトやジャーナルも活用し、最新のエビデンスを常にキャッチアップするよう心がけましょう。
実践能力の向上手法
専門的知識だけでなく、それを実践に活かす能力の向上も重要です。
保健師の実践能力は日々の業務の中で培われますが、意識的に経験を振り返り、成長につなげることが大切です。
PDCAサイクルを意識した活動評価は、実践能力向上の基本です。
自身の保健活動を計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のサイクルで振り返ることで、効果的な支援方法を見出すことができます。
特に「評価」の視点を持つことで、活動の成果や課題を客観的に分析し、次の実践に活かすことができます。
例えば、健康教室の実施後にアンケート調査を行い、参加者の満足度や行動変容の意欲などを評価し、次回のプログラム改善に活かすといった取り組みが効果的です。
ポートフォリオの作成も実践能力向上に役立ちます。
自身の実践事例や研修受講歴、業績などを体系的にまとめることで、キャリアの振り返りと今後の目標設定が容易になります。
特に難しいケースへの対応方法や成功体験を文書化しておくことで、暗黙知を形式知に変換し、自身の専門性の可視化につながります。
デジタルツールを活用したポートフォリオ作成も増えており、クラウド上で継続的に更新・管理することが可能になっています。
メンターやロールモデルの存在も実践能力向上には欠かせません。
経験豊富な先輩保健師からの指導・助言を受けることで、実践のコツや専門的視点を学ぶことができます。
組織内にメンター制度がない場合でも、学会や研修会などで知り合った保健師とのネットワークを構築し、定期的に情報交換や相談ができる関係を作ることが大切です。
2023年の調査では、メンターを持つ保健師は持たない保健師に比べて職務満足度が25%高いという結果も報告されています。
多職種連携プロジェクトへの参画も実践能力向上の機会となります。
医師、ケアマネジャー、社会福祉士、栄養士など様々な専門職と協働することで、多角的な視点や連携のスキルを身につけることができます。
特に地域包括ケアシステムの構築が進む中、多職種連携は不可欠であり、保健師には「つなぎ役」としての調整能力が求められています。
積極的にプロジェクトリーダーやファシリテーターの役割を担うことで、実践能力をさらに高めることができます。
保健師のキャリアパスと将来展望

保健師は多様なキャリアパスを描くことが可能です。
近年の社会情勢の変化に伴い、保健師の役割は拡大しており、様々な分野での活躍が期待されています。
ここでは、保健師のキャリアパスの例と、将来展望について詳しく解説します。
多様なキャリアパスの例
保健師のキャリアパスは、勤務先や専門分野によって様々なルートがあります。
自分の強みや価値観に合ったキャリア形成を考えることが大切です。
行政保健師としてのキャリア
行政保健師は、市区町村や保健所などの公的機関で働く保健師で、最も一般的なキャリアパスです。
保健センターでの実務経験を積むことからキャリアがスタートします。
母子保健や成人保健、高齢者保健など様々な業務を経験することで、地域保健活動の基礎を身につけます。
新人期(1~3年目)は、先輩保健師の指導のもとで基本的な保健活動を学び、中堅期(4~10年目)には、特定の事業担当として企画・運営能力を高めていきます。
保健所などでの専門分野担当になると、より専門的な知識と技術が求められます。
感染症対策や難病対策、精神保健などの専門部署で経験を積むことで、特定分野のエキスパートとしての道が開けます。
中堅後期(10年目以降)には、複数の事業を統括するチームリーダーやプロジェクトリーダーとしての役割も担うようになります。
管理職(保健センター長、保健所長)への昇進は、行政保健師のキャリアの一つの到達点です。
管理職では、組織マネジメントや人材育成、予算管理などの能力が求められます。
特に保健所長には、地域の健康危機管理の最高責任者としての役割があり、医師か保健師の資格を持つことが条件となっています。
2023年度の調査では、全国の保健所長のうち保健師出身者は約15%であり、増加傾向にあります。
政策立案に関わる行政職へのキャリアチェンジも選択肢の一つです。
厚生労働省や都道府県庁の政策部門で、保健医療福祉政策の企画・立案に携わる道も開かれています。
特に保健師の実践経験を活かした政策提言は、現場のニーズを反映した実効性の高い施策につながるため、重要視されています。
行政職としてのキャリアを積むためには、行政学や政策科学の知識を身につけることも有効です。
産業保健師としてのキャリア
産業保健師は、企業や健康保険組合などで働く保健師で、近年特に注目されているキャリアパスです。
企業の健康管理室での実務経験からキャリアがスタートします。
健康診断の事後指導や保健指導、メンタルヘルス対策などの基本的な業務を経験しながら、産業保健の知識を深めていきます。
中小企業では保健師が1人のみというケースも多く、初期から幅広い業務を担当することになります。
健康経営推進の中心的役割を担うようになると、経営層と連携した全社的な健康施策の企画・運営が求められます。
健康投資の費用対効果分析や健康経営度評価への対応など、経営的視点を持った活動が必要となります。
特に近年は健康経営優良法人認定制度の普及に伴い、企業の健康施策を統括できる保健師の需要が高まっています。
統括産業保健師としての活躍は、複数事業所や関連会社を含めた健康管理体制の構築や、産業医や人事部門と連携した全社的な健康戦略の立案などが主な役割です。
グローバル企業では、海外拠点の健康管理支援や国際的な健康施策の展開に携わることもあります。
2024年度の調査では、従業員1,000人以上の大企業の約60%が統括産業保健師ポジションを設置しており、その専門性が高く評価されています。
健康経営コンサルタントへの発展は、多くの企業経験を積んだ後のキャリアパスの一つです。
独立してコンサルタント業を営むケースや、健康経営支援企業に所属するケースなど様々な形態があります。
企業の健康課題分析から施策立案、評価までをトータルでサポートする専門家として、高度な専門性と実績が求められます。
特に中小企業向けの健康経営支援は需要が高く、今後も成長が見込まれる分野です。
教育・研究分野でのキャリア
実践経験を積んだ後、教育者や研究者としてのキャリアを選択する保健師も増えています。
大学や専門学校での教育者としては、保健師養成課程での講義や実習指導を担当します。
実践経験を学生に伝えることで、理論と実践をつなぐ教育を展開できることが強みです。
教育職としてのキャリアを築くためには、大学院での学位取得が基本的な要件となります。
特に研究能力を高めるために博士課程まで進学するケースも増えており、2023年度の調査では、保健師養成課程の教員の約40%が博士号を取得しています。
研究機関での研究職としては、国立保健医療科学院や大学附属研究所などで、地域保健に関する研究活動を行います。
実践に根ざした研究テーマを追究することで、エビデンスに基づく保健活動の発展に貢献します。
研究費の獲得や論文発表などの研究業績を積み重ねることが、研究者としてのキャリア発展につながります。
特に社会的ニーズの高い研究テーマ(健康格差の是正、災害時の健康支援など)は、研究費獲得の可能性も高まります。
国際保健分野での活動は、WHOやJICAなどの国際機関や国際NGOで、グローバルヘルスに関わる活動を展開するキャリアパスです。
発展途上国の保健システム強化や健康課題への対応などを支援します。
語学力や国際的な公衆衛生の知識、異文化理解力などが求められます。
特にSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて、保健分野の国際協力は重要性を増しており、保健師の国際的な活躍の場も広がっています。
起業・独立というキャリア
近年は、起業・独立というキャリアを選択する保健師も増えています。
豊富な経験と専門性を活かして、自らの理念に基づいた活動を展開することができます。
健康コンサルタントとしての独立は、企業や自治体、個人に対して健康支援サービスを提供するビジネスモデルです。
企業向けの健康経営支援や自治体向けの保健事業コンサルティング、個人向けの健康コーチングなど、様々なサービス展開が可能です。
特定の分野(糖尿病予防、女性の健康支援など)に特化したスペシャリストとしてのポジショニングが効果的です。
オンラインを活用したサービス提供も増えており、地理的制約を超えた活動が可能になっています。
保健指導事業の立ち上げは、特定保健指導や企業の健康支援事業を請け負う会社を設立するというキャリア選択です。
複数の保健師や管理栄養士などを雇用し、組織的にサービスを提供することで、より大規模な事業展開が可能になります。
2023年度の調査では、特定保健指導の約40%が外部委託されており、専門的なサービスを提供できる事業者への需要は高い状況です。
ICTを活用した効率的な保健指導プログラムの開発など、独自性のあるサービス展開が成功の鍵となります。
NPO法人などの設立・運営は、公益性の高い健康支援活動を展開するキャリア選択です。
行政サービスでは対応困難な健康課題(難病患者の支援、若年層の自殺予防など)に特化した活動を展開します。
助成金や寄付金の獲得、ボランティアの組織化など、非営利組織の運営スキルも求められます。
行政や医療機関、企業など様々な機関と連携することで、社会的インパクトの大きな活動を展開することができます。
2024年現在、全国で約500のヘルスケア関連NPO法人が活動しており、保健師がリーダーを務める団体も増加しています。
保健師の将来展望
社会の変化に伴い、保健師の役割はさらに重要性を増しています。
今後、保健師にはどのような活躍の場が広がるのでしょうか。
少子高齢化対策の中心的役割
少子高齢化が進行する日本社会において、保健師は地域包括ケアシステムの中核を担うことが期待されています。
医療・介護・福祉・住まい・生活支援の5要素を統合的に提供する地域包括ケアシステムでは、「予防」の視点を持つ保健師の役割が重要です。
特に介護予防事業の企画・運営や、フレイル対策、認知症予防などの分野で、保健師の専門性が発揮されます。
また、少子化対策としての子育て支援においても、保健師の役割は拡大しています。
妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を提供する「子育て世代包括支援センター」の設置が全国的に進む中、保健師はその中心的な役割を担っています。
産前産後ケアの充実や育児不安への対応、発達支援など、子どもの健やかな成長を支える活動がさらに重要になっています。
健康格差の是正への取り組み
社会経済的要因による健康格差の是正は、保健師の重要な使命の一つです。
貧困、教育、就労などの社会的決定要因が健康に与える影響が明らかになる中、健康の公平性を確保するための取り組みが求められています。
特に社会的に弱い立場にある人々(貧困世帯、外国人、障がい者など)への支援強化が重要です。
アウトリーチ活動の充実を通じて、健康サービスにアクセスしにくい人々への支援を展開することが期待されています。
従来の「来所型」のサービスだけでなく、「出向く型」のサービスを戦略的に展開することで、健康格差の是正を図る取り組みが増えています。
2023年度の調査では、「健康格差の是正」を重点課題と位置づける自治体が全体の70%に達しており、今後さらに重要性が高まる分野です。
健康経営の推進
企業における健康経営の推進は、産業保健師の活躍の場として拡大しています。
従業員の健康を「コスト」ではなく「投資」として捉える健康経営の考え方が浸透する中、その推進役として保健師への期待が高まっています。
特に「健康経営銘柄」や「健康経営優良法人」の認定制度の普及に伴い、企業の健康施策を統括できる保健師の需要が増加しています。
テレワークの普及や働き方の多様化に伴い、新たな健康課題(運動不足、コミュニケーション不足、仕事と生活の境界の曖昧化など)も生じています。
これらの課題に対応した健康支援策の立案・実施においても、保健師の専門性が求められています。
2024年度の調査では、従業員の健康管理において「テレワーク対応の健康支援」を重点課題とする企業が85%を超えており、新たな働き方に対応した保健活動の展開が急務となっています。
災害対応の強化
近年、自然災害が多発する中、災害時の健康支援と復興支援における保健師の役割が注目されています。
災害発生時の避難所運営支援や要配慮者への対応、被災者の心のケアなど、様々な健康課題に対応できる専門職として、保健師への期待は大きいものです。
特に複合災害(自然災害と感染症の同時発生など)への対応力強化が求められています。
新型コロナウイルス感染症の流行を経て、避難所における感染対策や要配慮者の避難支援など、複合的な健康危機に対応できる能力が必要とされています。
2023年度から全国の自治体で「災害時保健活動マニュアル」の改訂が進められており、保健師を中心とした災害時の健康支援体制の強化が図られています。
デジタル化への対応
保健活動のデジタル化は、今後の保健師に求められる重要な課題です。
ICTやAIなどのデジタル技術を活用した保健活動の効率化と質の向上が期待されています。
特に遠隔保健指導やオンライン健康相談、健康アプリを活用した健康支援など、新たな支援方法の開発と普及が進んでいます。
健康データの活用も重要な課題です。
ビッグデータ解析やAIを活用した健康リスク予測など、データサイエンスの手法を取り入れた科学的な保健活動の展開が求められています。
保健師には、こうしたデジタル技術を使いこなすデジタルリテラシーと、データを読み解く分析力が必要とされています。
2024年度から始まった「全国保健師デジタル研修」には、初年度だけで全国の保健師の約20%が参加しており、デジタルスキル向上への関心の高さがうかがえます。
現役保健師に学ぶ実践事例

保健師の仕事の魅力や専門性をより具体的に理解するために、現役保健師の実践事例を詳しく見ていきましょう。
ここでは、異なる分野で活躍する保健師の実践例をご紹介します。
A保健師の事例:地域の健康課題を解決するプロジェクト
A保健師は市の保健センターで10年の経験を持つ中堅保健師です。
地域の高齢化に伴う健康課題、特に高齢者の孤立と運動不足が引き起こす心身の機能低下に問題意識を持っていました。
課題発見のプロセス
A保健師は地域診断の手法を用いて、課題を科学的に把握することから始めました。
まず、地域の高齢者健診データを分析したところ、一人暮らし高齢者の約40%が運動機能の低下傾向にあることが判明しました。
次に、地区踏査と高齢者へのインタビューを実施し、「バスの本数が少なく外出が困難」「一人では運動を続ける意欲が維持できない」といった生の声を収集しました。
さらに、民生委員や地域包括支援センターとの情報交換から、「独居高齢者の孤立化が進んでいる」「既存の体操教室は会場が遠く参加者が限られている」といった課題も明らかになりました。
事業計画と実施
これらの地域診断の結果を踏まえ、A保健師は「まちの健康サロン」事業を企画しました。
この事業の特徴は以下の点です。
- 徒歩15分圏内の小学校区ごとに身近な場所(公民館や集会所など)で開催
- 体操だけでなく、お茶会や季節の行事など社交の要素を取り入れる
- 地域のボランティアを「健康リーダー」として養成し、住民主体の運営を目指す
- 理学療法士やケアマネジャーなど多職種と連携した専門的サポートの提供
事業開始にあたっては、地域の様々な資源を活用しました。
地元スーパーの空きスペースを会場として提供してもらったり、退職した体育教師をボランティアリーダーとして巻き込んだりと、地域のネットワークを最大限に活用しました。
また、庁内の連携として、福祉部門や教育委員会とも協力関係を構築し、横断的な支援体制を作りました。
評価と成果
A保健師は事業の効果を客観的に評価するため、以下の指標を設定しました。
- 参加者の身体機能(握力、歩行速度など)の変化
- 社会的交流の頻度と満足度の変化
- 主観的健康感の変化
- 地域の支え合い意識の変化
3年間の取り組みの結果、以下のような成果が得られました。
- 参加者の運動習慣が25%向上(週1回以上の運動実施率)
- 社会的交流が40%増加(「週に複数回、人と会話する機会がある」と回答した割合)
- 要介護認定率が地域全体で前年比2%減少
- 健康リーダーとして活躍する住民が30名に増加
特筆すべき点は、当初は保健師が主導していた活動が、次第に住民主体の活動へと発展していったことです。
健康リーダーとなった住民たちが自主的に企画運営を行うようになり、保健師はアドバイザー的な役割に徐々に移行していきました。
この「支援から見守りへ」の移行は、保健師活動の理想形でもあります。
成功のポイントと学び
A保健師の事例から学べるポイントは以下の通りです。
- データに基づく課題抽出:感覚や思い込みではなく、統計データや住民の声など客観的な情報に基づいて課題を特定
- 住民との協働による問題解決:「住民のための活動」ではなく「住民とともに行う活動」という視点
- 多職種・多機関との連携:保健・医療・福祉・教育など様々な分野の専門職や機関と連携した包括的アプローチ
- PDCAサイクルを意識した活動評価:計画・実施・評価・改善のサイクルによる継続的な事業の質向上
- 持続可能な仕組みづくり:保健師が不在でも継続できる住民主体の活動基盤の構築
A保健師は「保健師の最大の役割は、住民の力を引き出し、つなげることだと実感しました。地域には様々な資源や人材が眠っています。それらを発掘し、活性化させることで、持続可能な健康づくりの仕組みが生まれるのです」と語っています。
B保健師の事例:産業保健分野での成功事例
B保健師は製造業の大手企業で産業保健師として8年の経験を持つキャリア保健師です。
同社の工場では、作業員の腰痛問題が深刻化しており、欠勤や生産性低下の要因となっていました。
課題分析と戦略立案
B保健師はまず、問題の実態把握からスタートしました。
健康診断データや傷病手当金データを分析したところ、工場勤務者の約35%が腰痛を訴えており、年間の腰痛関連の欠勤日数は延べ450日に達していることが判明しました。
また、産業医と協力して腰痛に関するアンケート調査を実施し、「重量物の持ち上げ作業が多い」「同じ姿勢で長時間作業する」といった作業環境の問題点を特定しました。
これらのデータを基に、B保健師は「作業環境改善プロジェクト」を立ち上げることを経営層に提案しました。
提案にあたっては、腰痛による生産性低下と欠勤の経済的損失を試算し、約8,000万円/年のコストが発生していることを可視化しました。
この経済的インパクトを示したことで、経営層の理解と予算確保につながりました。
多職種連携による対策実施
プロジェクトを進めるにあたり、B保健師は様々な専門家とのチームを形成しました。
産業医、人間工学専門家、作業療法士、安全管理者、現場のリーダーなど多様なメンバーで構成されるプロジェクトチームを編成し、それぞれの専門性を活かした対策を検討しました。
実施された主な対策は以下の通りです。
- 人間工学的視点からの作業環境改善
- 作業台の高さ調整機能の導入
- リフト機器の導入による重量物取扱いの負担軽減
- 床面の衝撃吸収マットの設置
- 作業者への健康教育
- 腰痛予防のための正しい姿勢と動作の指導
- 作業の合間に行うストレッチプログラムの導入
- 腰痛のセルフケア方法の指導
- 組織的な取り組み
- 作業ローテーションの導入による負担の分散
- 小休止制度の導入(2時間ごとに5分の休憩)
- 腰痛予防リーダーの養成と配置
特に注目すべき点は、B保健師が現場作業者の声を丁寧に聞き取り、対策に反映させたことです。
「現場を知らない専門家の提案」ではなく、「現場の実情に合わせた実践可能な対策」を重視したことで、作業者からの協力も得られました。
効果測定と成果
B保健師は取り組みの効果を客観的に評価するため、以下の指標を設定しました。
- 腰痛有訴率の変化
- 腰痛による欠勤日数の変化
- 作業者の満足度と自己効力感
- 生産性指標(不良品率、生産スピードなど)の変化
- 費用対効果(投資額と欠勤減少・生産性向上による経済効果の比較)
プロジェクト開始から1年後の評価では、以下のような成果が報告されました。
- 腰痛有訴率が35%から22%に減少
- 腰痛による欠勤が年間450日から315日へと30%減少
- 作業者の「作業のしやすさ」満足度が68%向上
- 生産性が平均15%向上(特に重量物取扱い作業での向上が顕著)
- 投資額2,500万円に対し、3,800万円の経済効果(投資回収期間8ヶ月)
特に経営層を納得させたのは、明確な費用対効果の提示でした。
健康対策が「コスト」ではなく「投資」であることを数値で示したことで、その後の健康経営施策の拡大にもつながりました。
成功のポイントと学び
B保健師の事例から学べるポイントは以下の通りです。
- 職場巡視による問題の可視化:実際に現場に足を運び、作業環境や作業者の動きを観察することの重要性
- データを活用した経営層への効果的なプレゼンテーション:健康問題の経済的インパクトを可視化し、経営的視点で説明
- 多職種連携(人間工学専門家、作業療法士等):様々な専門性を活かした総合的なアプローチ
- 現場の意見を尊重した実践的な対策:トップダウンではなく、現場参加型の改善活動
- 費用対効果の明確化:投資と効果を数値で示す評価手法
B保健師は「産業保健師の強みは、健康の専門家でありながら、経営的視点も持てること。従業員の健康と企業の生産性向上という一見異なる目標を、共通の価値として提示できた点が成功の鍵でした」と語っています。
C保健師の事例:災害支援における実践
C保健師は県庁に勤務する15年のキャリアを持つ保健師です。
大規模な地震災害の発生時に、被災地支援チームのリーダーとして活動した経験を持っています。
災害発生時の初動対応
大規模地震発生直後、C保健師は県の災害対策本部保健医療班の一員として直ちに活動を開始しました。
まず取り組んだのは、被災地の保健医療ニーズの把握です。
被災自治体からの情報収集と並行して、DHEAT(災害時健康危機管理支援チーム)と協力し、避難所の状況や医療機関の稼働状況などを迅速に把握しました。
次に、県内外からの支援チーム(保健師チーム、医療チームなど)の受け入れ調整を行いました。
被災地のニーズと支援チームの専門性をマッチングさせ、効果的な配置計画を立案しました。
特に注力したのは、支援の「空白地帯」を作らないことと、支援の「偏り」を防ぐことでした。
避難所における健康支援活動
C保健師自身も被災地に入り、避難所での健康支援活動を展開しました。
まず実施したのは避難所の環境アセスメントです。
居住スペースの過密状況、トイレや手洗い場の衛生状態、空調の状況などを確認し、感染症リスクや熱中症リスクなどを評価しました。
避難者の健康ニーズ把握のため、以下の活動を実施しました。
- 避難者全員の健康状態スクリーニング(特に高齢者、妊婦、乳幼児、持病のある方などハイリスク者の把握)
- 生活不活発病や深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群)のリスク評価
- 心理的ストレスの評価と心のケアが必要な方の把握
これらの評価結果を基に、以下の支援活動を展開しました。
- 慢性疾患(高血圧、糖尿病など)の方への継続治療支援
- 感染症予防のための衛生管理指導(手洗い、消毒、トイレ使用方法など)
- エコノミークラス症候群予防のための簡易体操の実施
- 夜間の安眠のための環境調整(パーティションの設置、消灯時間の設定など)
- 乳幼児のいる家族向けの育児支援スペースの設置
特に効果的だったのは、避難者の中から「健康リーダー」を選出し、日々の体操や健康チェックの実施を依頼する取り組みでした。
これにより、避難者自身が主体的に健康管理に取り組む意識が高まりました。
被災者の心のケア対策
災害発生から2週間が経過した頃から、避難者の心理的問題(不眠、不安、抑うつ症状など)が顕在化してきました。
C保健師は精神保健福祉士や臨床心理士と連携し、以下の心のケア対策を実施しました。
- 避難所内に「こころの相談コーナー」を設置(プライバシーに配慮した相談スペース)
- 「睡眠と心の健康」をテーマにした健康教育の実施
- ハイリスク者(強い喪失体験がある方、既往に精神疾患がある方など)への個別訪問
- 子どもの心のケアのための遊びの広場の運営
また、支援者(自治体職員、ボランティアなど)のメンタルヘルスケアも重要な課題でした。
C保健師は支援者向けのリフレッシュスペースの設置や、定期的なミーティングでの心理的デブリーフィングの実施など、支援者支援にも取り組みました。
復興期における地域の健康づくり
避難所が閉鎖され、仮設住宅への移行が進む中、新たな健康課題(孤立、生活不活発、アルコール問題など)が生じてきました。
C保健師は「復興期の健康支援計画」を立案し、中長期的な支援体制を構築しました。
主な取り組みは以下の通りです。
- 仮設住宅集会所での「健康サロン」の定期開催
- 被災者の見守り支援ネットワークの構築(民生委員、社会福祉協議会、NPOなどとの連携)
- 生活再建支援員への健康支援研修の実施
- 地域の医療機関との連携による巡回診療体制の構築
特に注力したのは、被災前のコミュニティの絆を再構築する取り組みでした。
地域の伝統行事や農作業などの活動を支援することで、住民同士のつながりを維持・強化し、社会的孤立を防ぐことに成功しました。
成功のポイントと学び
C保健師の災害支援事例から学べるポイントは以下の通りです。
- 平時からの準備の重要性:災害マニュアルの整備、訓練、関係機関とのネットワーク構築
- フェーズに応じた支援の切り替え:初動期、避難所期、復興期など時期に応じた支援内容の変化
- 「見える化」によるニーズ把握:健康マップやリスト作成による支援の優先順位づけ
- 住民の力を活かした支援:避難者自身が主体的に取り組める仕組みづくり
- 多機関・多職種連携:様々な専門職や支援団体と協働した包括的支援
C保健師は「災害支援で最も大切なのは、被災者一人ひとりの尊厳を守ること。物資や医療の提供だけでなく、その人らしい生活を取り戻すための支援が保健師の役割です。また、災害は地域の健康課題を鮮明に浮かび上がらせます。その経験から平時の活動を見直すことで、より強靭な地域づくりにつなげることができます」と語っています。
保健師の一日のスケジュール

保健師の日常業務は、勤務先や担当業務によって大きく異なります。
ここでは、代表的な3つの職場における保健師の一日のスケジュールをご紹介します。
これらの事例を通して、保健師の実際の業務内容や働き方をイメージしていただければと思います。
行政保健師の一日(市区町村保健センター)
市区町村保健センターで母子保健を担当するD保健師の一日をご紹介します。
【午前】
8:30 出勤、メールチェックと当日の予定確認
9:00 朝のミーティング(係内での情報共有、当日の業務確認)
9:30 乳幼児健診の準備(会場設営、カルテ確認、スタッフミーティング)
10:00~12:00 4か月児健診(問診、発達確認、育児相談、要フォロー児の判定会議)
【午後】
13:00~14:00 健診後のカンファレンス(医師、歯科医師、栄養士等との情報共有)
14:00~15:00 要フォロー児の支援計画立案、記録整理
15:00~16:00 家庭訪問(発達に心配のある乳児宅を訪問)
16:00~17:00 育児相談電話対応
17:00~17:30 記録整理、翌日の準備
D保健師が日々大切にしているのは、「一人ひとりの子どもの発達と家族の状況を丁寧に見極めること」です。
健診は集団で行いますが、その中で個別の課題を見逃さないよう、常にアンテナを高く持っています。
特に初めての子育てで不安を抱える母親には、余裕を持って話を聴くよう心がけているそうです。
「表面的な会話から一歩踏み込んで、本当の悩みを引き出すことが保健師の腕の見せどころ」とD保健師は語ります。
また、健診後のカンファレンスでは、多職種の視点を統合して支援方針を決定する調整役を担っています。
「医師の医学的見解、栄養士の食生活評価、心理士の発達評価などを踏まえて、家族に寄り添った支援計画を立てることが重要です」と話します。
家庭訪問では、家庭環境や家族関係を直接確認できる貴重な機会として、細かな観察を大切にしています。
「家の中の様子、親子の関わり方、兄弟姉妹の様子など、健診ではわからない情報が得られます。また、家庭という場所だからこそ、お母さんが本音を話してくれることも多いです」とその意義を強調しています。
D保健師が最もやりがいを感じるのは、「支援を続けた親子が元気に成長していく姿を見られること」だそうです。
「最初は育児に自信がなかったお母さんが、少しずつ自分なりの子育てを確立していく過程に寄り添えることは、保健師冥利に尽きます」と笑顔で語ってくれました。
産業保健師の一日(大企業の健康管理室)
大手製造業の健康管理室で働くE保健師の一日をご紹介します。
【午前】
8:15 出勤、メールチェックと当日のスケジュール確認
8:30 産業医との打ち合わせ(要対応者の状況確認、面談予定者の情報共有)
9:00~10:00 健康診断事後措置面談(有所見者への保健指導)
10:00~11:00 職場巡視(製造現場の作業環境確認、改善提案)
11:00~12:00 安全衛生委員会資料作成(健康課題の分析、対策立案)
【午後】
13:00~14:00 メンタルヘルス不調者の面談(復職支援計画の作成)
14:00~15:30 健康経営推進会議(経営層への健康施策の提案、進捗報告)
15:30~16:30 健康教育準備(生活習慣病予防セミナーの資料作成)
16:30~17:30 新任管理職向けラインケア研修(部下のメンタルヘルス管理研修)
17:30~18:00 記録整理、翌日の準備
E保健師の業務の特徴は、「個人の健康支援」と「組織への働きかけ」の両方を担っている点です。
健康診断後の保健指導では、一人ひとりの健康リスクに合わせたアドバイスを行うと同時に、職場環境や働き方の問題点がないかも確認しています。
「生活習慣の改善だけでなく、長時間労働や人間関係のストレスなど、職場に起因する健康リスクにも注目することが大切です」とE保健師は話します。
職場巡視では、作業環境の人間工学的な評価や、有害要因(騒音、化学物質など)のチェックを行います。
「現場を知ることで、健康データの背景が見えてきます。例えば、腰痛が多い部署では作業姿勢や重量物の取り扱いを確認し、具体的な改善につなげています」と現場重視の姿勢を強調しています。
健康経営推進会議では、データに基づく健康課題の可視化と解決策の提案を行います。
「経営層に理解してもらうには、健康施策の費用対効果を示すことが重要です。健康問題を経営課題として位置づけ、投資価値を明確に伝えることを心がけています」とビジネス視点の重要性を語ります。
E保健師が最もやりがいを感じるのは、「個人の健康改善と会社の生産性向上の両方に貢献できること」だそうです。
「社員一人ひとりの健康リスクを低減しながら、会社全体の健康文化を醸成していくプロセスは、まさに産業保健師ならではの醍醐味です」と熱く語ってくれました。
教育・研究分野の保健師の一日(大学教員)
看護系大学で保健師養成課程を担当するF保健師(教授)の一日をご紹介します。
【午前】
8:30 出勤、メールチェックと当日の授業準備
9:00~10:30 公衆衛生看護学概論の講義(保健師の役割と理念について)
10:40~12:10 学部生の卒業研究指導(地域診断に関する研究指導)
12:10~13:00 昼食兼研究室会議(助教・大学院生との研究進捗確認)
【午後】
13:00~14:30 保健師学生の実習記録指導
14:40~16:10 大学院生の研究指導(地域包括ケアに関する研究)
16:20~17:30 地域連携会議(地元自治体との共同研究プロジェクト打ち合わせ)
17:30~19:00 学会発表原稿の執筆、研究データ分析
F保健師(教授)の業務は、「教育」「研究」「社会貢献」の3つの柱で構成されています。
公衆衛生看護学の講義では、自身の実務経験を交えながら、保健師活動の理論と実践を統合した教育を行っています。
「学生には、単なる知識の習得ではなく、保健師としての思考プロセスやアセスメント能力を身につけてほしい。そのために、実際の地域の健康課題を題材にしたPBL(問題基盤型学習)を取り入れています」と教育へのこだわりを語ります。
実習指導では、学生が地域で体験したことを理論と結びつけて理解できるよう支援しています。
「実習で見聞きしたことを『点』として捉えるのではなく、地域全体を見る『面』の視点で解釈できるよう導いています。保健師にとって最も重要な『地域を診る目』を養ってほしいのです」と指導方針を説明します。
研究活動では、地域包括ケアシステムにおける保健師の役割や、健康格差の是正に関する研究に取り組んでいます。
「研究者としての役割は、保健師活動のエビデンスを構築し、実践の質向上に貢献すること。常に現場とのつながりを大切にしながら、実践に役立つ研究を心がけています」と研究に対する姿勢を語ります。
地域連携会議では、大学の知見を地域に還元するプロジェクトを推進しています。
「大学と地域が協働することで、双方にメリットがあります。学生の学びの場となると同時に、地域の健康課題解決にも貢献できるwin-winの関係を目指しています」と社会貢献の意義を強調しています。
F保健師(教授)が最もやりがいを感じるのは、「育てた学生が現場で活躍する姿を見ること」だそうです。
「教え子が保健師として地域に貢献し、時には新たな保健活動のモデルを生み出していく。そんな姿を見ることが、教育者として最高の喜びです」と笑顔で語ってくれました。
地域別の保健師活動の特徴

保健師活動は地域の特性によって大きく異なります。
地域の人口構成、健康課題、社会資源などによって、保健師に求められる役割や活動方法も変わってきます。
ここでは、都市部と郡部(地方)における保健師活動の特徴と、それぞれの地域特性に応じた実践方法について解説します。
都市部と郡部の活動比較
都市部の保健師活動の特徴
都市部(大都市や中核市など)における保健師活動の特徴は以下の通りです。
人口規模と保健師配置
都市部では人口規模が大きく、保健師一人あたりの担当人口も多い傾向にあります。
2023年の調査では、政令指定都市の保健師一人あたりの担当人口は平均約6,000人と、全国平均(約3,500人)を大きく上回っています。
一方で、保健師の配置数が多いため、母子保健担当、成人保健担当など業務の専門分化が進んでいることも特徴です。
健康課題の特徴
都市部特有の健康課題としては、以下のようなものが挙げられます。
- 単身世帯や核家族の増加に伴う社会的孤立
- 地縁的なつながりの希薄化による互助機能の低下
- 経済格差による健康格差の拡大
- 多文化共生に関する課題(外国人住民の増加)
- 若年層のメンタルヘルス問題
活動の特徴
都市部の保健師活動の特徴としては、以下の点が挙げられます。
- 社会資源が豊富で、専門機関や民間サービスとの連携機会が多い
- 対象者の匿名性が高く、プライバシーへの配慮が重要
- 人口流動性が高く、継続的な支援が難しいケースがある
- ICTを活用した健康支援の導入が進んでいる
- 健康格差に対応するためのハイリスクアプローチの重要性
活動事例
東京都G区では、単身高齢者の孤立防止を目的とした「おとなりさんプロジェクト」を展開しています。
このプロジェクトでは、保健師が中心となり、マンションの管理組合や商店街と連携して、緩やかな見守りネットワークを構築しました。
特徴的なのは、伝統的な町内会組織に頼らず、マンション単位やフロア単位での「ミニ・コミュニティ」を形成する点です。
保健師は住民主体の活動をサポートする黒子役に徹し、持続可能な仕組みづくりに成功しています。
郡部(地方)の保健師活動の特徴
郡部(町村部や過疎地域など)における保健師活動の特徴は以下の通りです。
人口規模と保健師配置
郡部では人口規模が小さく、保健師一人あたりの担当人口は少ない傾向にあります。
2023年の調査では、町村部の保健師一人あたりの担当人口は平均約2,500人と、全国平均を下回っています。
一方で、保健師の配置数自体が少なく(小規模町村では1~3名程度)、一人の保健師が複数の業務を担当する「オールラウンド型」の活動が求められます。
健康課題の特徴
郡部特有の健康課題としては、以下のようなものが挙げられます。
- 高齢化率の高さと後期高齢者の増加
- 過疎化による地域コミュニティの弱体化
- 若年層の流出による地域活力の低下
- 医療資源の不足(無医地区、専門医不足)
- 交通アクセスの問題による受診困難
活動の特徴
郡部の保健師活動の特徴としては、以下の点が挙げられます。
- 住民との距離が近く、顔の見える関係づくりがしやすい
- 既存の地縁組織(自治会、老人会など)との連携が取りやすい
- 限られた資源の中での創意工夫が求められる
- 移動手段の確保が重要(訪問活動の比重が大きい)
- 多機関・多職種が協働したケアシステムの構築
活動事例
人口5,000人のH町では、保健師2名が中心となり「まるごと健康プロジェクト」を展開しています。
このプロジェクトでは、町内にある複数の小さな集落ごとに健康拠点(「まめな家」)を設け、住民主体の健康づくり活動を支援しています。
特徴的なのは、高齢者の知恵や経験を活かした健康づくり(伝統食の継承、薬草活用など)を取り入れ、世代間交流の場としても機能している点です。
また、町の唯一の診療所と連携し、医師の往診日に合わせて健康相談を実施するなど、限られた医療資源を効果的に活用しています。
地域特性に応じた保健活動の実践方法
保健師は地域特性を十分に理解し、それに応じた効果的な保健活動を展開することが重要です。
ここでは、地域特性に応じた保健活動の実践方法について具体的に解説します。
地域診断の重要性
効果的な保健活動の第一歩は、地域の特性と健康課題を正確に把握することです。
地域診断は保健師の専門性の核心とも言える技術であり、以下のプロセスで実施します。
情報収集
地域の人口統計、健康統計、社会経済指標などの量的データと、住民の声や地域の歴史・文化などの質的データを幅広く収集します。
都市部では大量のデータを効率的に分析する能力が、郡部では少ないデータから本質を見抜く洞察力が求められます。
分析と評価
収集したデータを多角的に分析し、地域の健康課題と強みを明らかにします。
特に重要なのは、単なる「問題点の列挙」ではなく、「なぜその健康課題が生じているのか」という要因分析です。
都市部では健康格差の要因分析、郡部では地理的・社会的孤立の要因分析などが重要となります。
優先課題の設定
分析結果を基に、地域の特性に応じた優先課題を設定します。
課題の重要性、緊急性、解決可能性などを総合的に判断し、限られた資源の中で最も効果的に取り組むべき課題を特定します。
住民参加型のワークショップなどを通じて、住民自身の声を課題設定に反映させることも重要です。
活動計画の立案と実施
地域診断に基づいて、地域特性に応じた活動計画を立案します。
都市部と郡部では、同じ健康課題に対しても異なるアプローチが必要となる場合があります。
都市部での効果的なアプローチ
- 多様な社会資源の連携と協働:専門機関、NPO、企業などの多様な社会資源をネットワーク化し、複合的な支援体制を構築します。例えば、企業の健康経営推進部門と連携した働き盛り世代の健康づくりや、多文化共生センターと協働した外国人住民への健康支援などが効果的です。
- ICTを活用した健康支援:都市部はデジタルリテラシーの高い住民が多いため、健康アプリやオンライン健康相談などのICTを活用した支援が効果的です。特に若年層や働き盛り世代へのアプローチとして、SNSを活用した健康情報の発信やウェブセミナーの開催などが有効です。
- ハイリスクアプローチの強化:社会的孤立や健康格差など、都市部特有の課題に対応するため、ハイリスク者へのアウトリーチを強化します。例えば、住民登録情報や医療・介護データの分析からハイリスク地域を特定し、重点的な訪問活動を展開する「データ駆動型アウトリーチ」が注目されています。
- 「小さなコミュニティ」の形成支援:都市部では地縁的なつながりが希薄なため、共通の関心や課題を持つ人々による「小さなコミュニティ」の形成を支援します。マンションの一室を活用した「ご近所サロン」や、公園を拠点とした「まちの保健室」など、気軽に参加できる場づくりが効果的です。
郡部での効果的なアプローチ
- 既存の地縁組織の活性化:郡部では自治会や老人会などの地縁組織が残っていることが多いため、これらを健康づくりの拠点として活性化します。例えば、公民館を拠点とした「健康づくり委員会」の組織化や、地区単位での健康目標設定など、既存の組織を活用した取り組みが効果的です。
- 移動型サービスの展開:交通アクセスの問題がある郡部では、保健師が出向く「移動型サービス」が効果的です。例えば、集落の集会所を巡回する「移動保健室」や、商店や郵便局と連携した「まちの健康ステーション」など、住民の生活動線上にサービスを展開する工夫が重要です。
- 多機能型の拠点づくり:限られた資源を効果的に活用するため、保健・医療・福祉・教育などの機能を統合した「多機能型拠点」の整備が有効です。例えば、診療所、保健センター、介護予防施設、子育て支援センターなどの機能を一か所に集約し、世代間交流も促進する「共生型拠点」が注目されています。
- 遠隔医療との連携:医療資源が限られた郡部では、遠隔医療システムとの連携が重要です。保健師が遠隔医療の窓口となり、専門医とのオンライン診療をサポートすることで、住民の医療アクセスを向上させる取り組みが広がっています。
評価と改善
実施した活動の効果を適切に評価し、継続的に改善していくことが重要です。
地域特性に応じた評価指標の設定と評価方法の工夫が必要となります。
都市部での評価の工夫
- 量的データ(健診受診率、有所見率など)と質的データ(住民の満足度、行動変容など)を組み合わせた多面的評価
- デジタルツールを活用したリアルタイム評価(健康アプリのデータ分析など)
- 費用対効果分析による事業の優先順位づけ
- 地域間比較による健康格差の可視化と対策評価
郡部での評価の工夫
- 少数データでも意味のある分析ができる質的評価の重視
- 住民参加型の評価会議(成果や課題を住民と共有し、次の活動に反映)
- 中長期的な視点での効果測定(短期的な数値変化だけでなく、地域の変化を捉える)
- 他の類似地域とのベンチマーキング(人口規模や高齢化率が近い自治体との比較)
看護師さんからのQ&A「おしえてカンゴさん!」
保健師に関するよくある質問に、経験豊富な「カンゴさん」がお答えします。
キャリア形成や資格取得、実務に関する疑問など、保健師を目指す看護師さんや現役保健師の皆さんに役立つ情報をお届けします。
Q1: PHNの主な役割は何ですか?
カンゴさん:保健師(PHN)の主な役割は「予防」と「地域全体の健康支援」です。
個人の健康問題だけでなく、家族や地域全体の健康課題を把握し、予防的なアプローチを行います。
保健師活動の核心は「地域診断」です。
人口統計や健康データの分析、地区踏査、住民へのインタビューなどを通して地域の健康課題を科学的に把握し、効果的な対策を立案・実施します。
また、「つなぐ」役割も重要です。
医療機関、福祉施設、学校、企業、行政機関など様々な組織と連携し、地域全体の健康を支えるネットワークを構築します。
2024年の保健師活動指針改定では、この「つなぐ力」が特に強調されています。
さらに、健康危機管理(感染症対策、災害時の健康支援など)の担い手としての役割も重要性を増しています。
近年の健康危機を通じて、予防的視点を持つ保健師の役割が社会的に再認識されています。
Q2: 保健師の専門性を高めるポイントは何ですか?
カンゴさん:保健師の専門性を高めるポイントは、①特定分野の専門知識を深める、②データ分析・活用能力を磨く、③コミュニケーション・コーディネート力を向上させる、の3つが重要です。
特定分野の専門性を高めるには、自分の関心や強みを活かせる分野(母子保健、精神保健、災害保健など)を選び、集中的に学ぶことが効果的です。
専門研修や認定資格の取得、学会活動などを通じて、系統的に専門性を高めていきましょう。
データ分析・活用能力は、科学的根拠に基づく保健活動を展開するために不可欠です。
疫学や保健統計の基礎知識はもちろん、近年はGISを活用した地域診断や、ビッグデータ解析の基礎知識なども求められています。
このスキルは研修や実践を通して段階的に身につけていくとよいでしょう。
コミュニケーション・コーディネート力は、多様な住民や関係機関との協働に必要な能力です。
特に「聴く力」「伝える力」「調整する力」の3つが重要です。
これらは日々の実践の振り返りやロールプレイ研修などを通じて磨いていくことができます。
保健師の専門性向上には「アクション・リフレクション・ラーニング」のサイクルが効果的です。
実践(アクション)と振り返り(リフレクション)を繰り返しながら、経験から学び(ラーニング)、次の実践に活かしていくプロセスを大切にしてください。
Q3: 看護師から保健師へのキャリアチェンジは可能ですか?
カンゴさん:もちろん可能です!看護師として臨床経験を積んだ後、保健師養成課程のある大学院や専門学校で学び、国家試験に合格すれば保健師になれます。
臨床経験は地域での活動にも活かせる貴重な強みになります。
特に疾患や治療に関する知識、医療機関との連携方法、患者心理の理解など、臨床で培った経験は保健師活動でも大いに役立ちます。
キャリアチェンジの具体的なステップとしては、まず保健師養成課程のある大学院(修士課程)や専門学校を選び、1年間の専門教育を受けます。
社会人向けの夜間・土日開講のコースもあるので、働きながら学ぶことも可能です。
ただし、思考の転換(個別ケアから地域全体の視点へ)が必要になります。
臨床では目の前の患者さんへの直接的なケアが中心ですが、保健師活動では「地域全体を見る視点」や「予防的思考」が求められます。
この視点の転換はチャレンジングですが、臨床経験があるからこそ見えてくる地域の健康課題もあります。
2023年の調査では、看護師から保健師にキャリアチェンジした方の約65%が「視野が広がった」「予防の重要性を実感できるようになった」とポジティブな変化を実感しているそうです。
キャリアチェンジのハードルは決して低くはありませんが、新たな専門性を身につける貴重な機会となるでしょう。
Q4: 保健師として働く際の給与水準はどうですか?
カンゴさん:保健師の給与は勤務先によって異なります。
一般的な水準をご紹介します。
行政機関(市区町村・保健所)では公務員として安定した給与体系があり、経験年数に応じて昇給します。
初任給は約22〜25万円程度、10年目で約30〜35万円程度が目安です。
地域手当や扶養手当、住居手当などの各種手当も加わります。
また、公務員は定期的なボーナス(期末・勤勉手当)があり、年間4〜5ヶ月分が支給されることが一般的です。
福利厚生も充実しており、ワークライフバランスを重視する方には魅力的な環境といえるでしょう。
民間企業の産業保健師は、企業規模や業種によりますが、公務員よりやや高めの傾向があります。
初任給は約25〜30万円程度、10年目で約35〜45万円程度が目安です。
特に大企業や外資系企業では、専門職としての評価が高く、管理職になると年収800万円を超えるケースもあります。
医療機関に勤務する保健師は、基本的に看護師と同等の給与体系となることが多いですが、専門性を評価する手当が付く場合もあります。
平均的な初任給は約22〜26万円程度です。
教育・研究機関(大学など)の保健師は、教員としての給与体系となり、学位や経験に応じて決定されます。
准教授や教授になると比較的高い水準となります。
2024年の調査では、保健師の平均年収は約520万円で、看護師(約490万円)より若干高い傾向にあります。
ただし、勤務先や地域による差が大きいことに留意が必要です。
Q5: 保健師に向いている人の特徴はありますか?
カンゴさん:保健師に向いている人の特徴としては、以下のような点が挙げられます。
まず、予防医学や公衆衛生に関心があることが大切です。
「病気になる前に健康を守りたい」「地域全体の健康レベルを向上させたい」という思いを持つ方は保健師の仕事にやりがいを感じることができるでしょう。
次に、地域や社会全体を見る視点を持っていることも重要です。
個人の健康問題だけでなく、その背景にある環境要因や社会的要因にも目を向け、「点」ではなく「面」で捉える視点を持つ方は保健師の思考に適しています。
長期的な関わりを大切にできる方も向いています。
保健師活動は即効性のある成果が見えにくく、地道な活動の積み重ねが求められます。
「継続は力なり」という姿勢で粘り強く活動できる方に向いています。
コミュニケーション能力が高い方も保健師に適しています。
特に、相手の話をじっくり「聴く力」や、様々な背景を持つ人々に分かりやすく「伝える力」、多様な関係者との「調整力」が求められます。
データ分析や企画力がある方も保健師の仕事に向いています。
統計データを読み解き、地域診断を行い、効果的な保健活動を企画・立案する能力は保健師の専門性の核心部分です。
最後に、チーム作りや関係調整が得意な方も向いています。
保健師は「つなぐ」役割を担うことが多く、様々な機関や職種をコーディネートする能力が求められます。
「黒子役」を厭わず、全体の調和を大切にできる方は保健師活動で力を発揮できるでしょう。
Q6: 保健師として働く上での課題は何ですか?
カンゴさん:保健師として働く上での課題としては、以下のような点が挙げられます。
まず、業務の幅広さによる負担増があります。
特に小規模自治体では、少ない人数で多様な業務を担当することが多く、一人の保健師が母子保健から高齢者保健、感染症対策まで幅広く対応することもあります。
2023年の調査では、保健師の約65%が「業務量の多さ」を課題として挙げています。
次に、成果が見えにくい予防活動の評価の難しさがあります。
保健師活動は「病気にならなかった」「健康問題が起きなかった」という「起こらなかった事象」を成果とするため、その効果を可視化することが難しい側面があります。
そのため、活動の意義や重要性を関係者に理解してもらうことに苦労することもあります。
地域の多様なニーズへの対応も課題です。
少子高齢化、貧困、外国人住民の増加など、地域社会の変化に伴い健康課題も複雑化・多様化しています。
従来の画一的な保健サービスでは対応しきれないケースも増えており、個別性の高い支援が求められています。
他機関・多職種との連携調整の複雑さも挙げられます。
地域包括ケアシステムの構築が進む中、医療・介護・福祉・教育など様々な分野との連携が不可欠ですが、組織間の壁や専門職間の考え方の違いなどから、スムーズな連携が難しいこともあります。
また、自治体の財政状況により事業展開に制約があることも少なくありません。
予算や人員の制約の中で、いかに効果的な保健活動を展開するかが常に課題となっています。
これらの課題に対して、エビデンスを示しながら活動の重要性をアピールする力も必要です。
データに基づく説得力のある提案や、費用対効果を示すなど、保健師活動の価値を可視化する取り組みが求められています。
Q7: 最近の保健師に求められる新しいスキルはありますか?
カンゴさん:最近の保健師に求められる新しいスキルとしては、以下のようなものが注目されています。
まず、データサイエンスの基礎知識が重要です。
健康データの分析・活用能力は、科学的根拠に基づく保健活動の展開に不可欠です。
特に、GIS(地理情報システム)を活用した地域診断や、RESASなどの地域経済分析システムを用いた社会経済要因の分析なども求められるようになっています。
2024年からは、全国の自治体で「データヘルス」の取り組みが強化されており、保健師のデータ活用能力の重要性が高まっています。
次に、ICTを活用した健康支援能力も重要です。
オンライン保健指導やテレヘルスの普及に伴い、デジタルツールを活用した健康支援スキルが求められています。
また、健康アプリやウェアラブルデバイスのデータを活用した個別化された健康支援なども、これからの保健師に期待される新たな役割です。
災害時の健康危機管理能力も必須スキルとなっています。
近年の自然災害の多発や感染症の流行を受けて、平常時からの備えと災害発生時の迅速な対応力が求められています。
特に複合災害(地震と感染症の同時発生など)への対応力や、避難所における公衆衛生管理能力などが重要視されています。
多文化共生社会への対応力も必要です。
在留外国人の増加に伴い、言語や文化の壁を越えた健康支援が課題となっています。
やさしい日本語の使用や、多言語対応の健康教材の活用など、文化的感受性を持った支援スキルが求められています。
2023年の調査では、約70%の自治体が外国人住民への健康支援を課題と認識しています。
政策立案・提言力も重要です。
保健師の専門性を活かした政策提言や、地域の健康課題を施策に反映させる能力が求められています。
特に「健康影響評価(HIA)」の視点を持ち、様々な政策が健康に与える影響を評価・提言できる保健師の役割が注目されています。
特にデジタル技術を活用した保健活動は今後ますます重要になるでしょう。
一方で、技術に頼りすぎず、対面でのコミュニケーションや地域に飛び出すフィールドワークの大切さも忘れてはなりません。
新しいスキルと従来の保健師の強みをバランスよく組み合わせることが理想的です。
Q8: 保健師の仕事で最もやりがいを感じる瞬間はどんな時ですか?
カンゴさん:保健師の仕事でやりがいを感じる瞬間は様々ですが、多くの保健師が共感する場面をいくつかご紹介します。
まず、「長期的な関わりの中で変化が見られた時」にやりがいを感じる保健師が多いです。
例えば、育児に自信がなかった母親が少しずつ成長し、笑顔で子育てするようになった姿を見た時、何年も生活習慣の改善に取り組んできた方の健診結果が良くなった時など、地道な支援が実を結ぶ瞬間は格別の喜びがあります。
次に、「地域に変化が生まれた時」も大きなやりがいとなります。
例えば、健康づくりの活動が住民主体で広がり、自分がいなくても継続する仕組みができた時や、地域診断から見つけた健康課題に対する取り組みが成果を上げた時などは、保健師冥利に尽きる瞬間です。
「予防活動の成果を感じられた時」もやりがいの一つです。
例えば、感染症対策が功を奏して大きな流行を防げた時、早期発見・早期対応によって重症化を防げた時など、「起こらなかった健康被害」という目に見えにくい成果を実感できた時は大きな達成感があります。
「信頼関係の構築ができた時」も重要なやりがいです。
特に、初めは支援を拒否していた方が徐々に心を開き、自ら健康について相談してくれるようになった時や、地域の関係機関との連携が円滑になり、チームとして支援ができるようになった時などは、保健師としての存在意義を感じられます。
「政策や地域システムに影響を与えられた時」も大きなやりがいです。
現場での気づきや実践を基に政策提言を行い、それが実際の制度やシステムの改善につながった時は、より広範な住民の健康に貢献できた実感が得られます。
ある30年のキャリアを持つベテラン保健師は「保健師の醍醐味は、一人の命を救うだけでなく、地域全体の健康を守る仕組みを作れること。
個人への支援と地域への働きかけを行き来しながら、『誰一人取り残さない健康なまちづくり』に貢献できる点が、この仕事の最大の魅力です」と語っています。
Q9: 保健師として最初の1年間で身につけるべきことは何ですか?
カンゴさん:保健師として最初の1年間で身につけるべきことをご紹介します。
まず「基本的な保健師活動の流れを理解すること」が最重要です。
地域診断→計画立案→実施→評価というPDCAサイクルを実際の業務を通して体験し、保健師活動の全体像を把握しましょう。
特に地域診断の基本的な手法(統計データの読み解き方、地区踏査の方法、住民からの情報収集など)は、早い段階で習得することが望ましいです。
次に「担当地区・業務の特性を知ること」も大切です。
担当する地域の人口構成、健康課題、社会資源、キーパーソンなどを把握することで、効果的な保健活動の基盤が作られます。
先輩保健師に同行訪問させてもらったり、地域の会合に参加したりして、積極的に地域を知る機会を作りましょう。
「基本的な面接技術と家庭訪問の技術」も1年目で身につけたい重要なスキルです。
対象者との信頼関係の構築、効果的な聴き方と伝え方、家庭環境のアセスメント方法などは、保健師活動の基本となります。
最初は緊張するかもしれませんが、先輩保健師の同行指導を受けながら、徐々に自信をつけていきましょう。
「記録の書き方」も重要なスキルです。
家庭訪問記録、事例検討資料、事業報告書など、様々な場面で記録を作成する機会があります。
単なる事実の羅列ではなく、アセスメントと今後の支援方針が明確に伝わる記録を心がけましょう。
優れた記録は、チーム内での情報共有や継続的な支援の質向上に不可欠です。
「関係機関との連携方法」も1年目から少しずつ学んでいくべき点です。
医療機関、福祉施設、教育機関など、様々な関係機関とのネットワークづくりは保健師の重要な役割です。
まずは所属組織内の連携の仕組みを理解し、徐々に外部機関との連携方法も学んでいきましょう。
「所属組織の仕組みと行政職員としての基本」も行政保健師の場合は特に重要です。
予算の仕組み、決裁の流れ、法令や条例の基礎知識など、行政職員として必要な知識を身につけることで、より効果的な保健活動が展開できるようになります。
1年目は「分からないことを素直に質問できる謙虚さ」と「新鮮な視点で気づきを言語化する積極性」のバランスが大切です。
一人で抱え込まず、先輩保健師に相談しながら、少しずつ自分の保健師としてのスタイルを形成していくとよいでしょう。
Q10: 将来的に保健師の需要はどうなりますか?
カンゴさん:保健師の将来的な需要については、全体としては拡大する方向にあると予測されています。
その背景と分野別の見通しについてご説明します。
全体的な需要拡大の背景には、以下のような社会的要因があります。
- 予防医療の重要性の高まり(医療費適正化の観点から)
- 地域包括ケアシステムの推進(地域での生活を支える体制づくり)
- 健康格差の拡大(社会経済的要因による健康の不平等への対応)
- 健康危機管理の強化(感染症や災害への対応)
- 健康経営の普及(企業における従業員の健康投資の拡大)
分野別に見ると、特に以下の領域での需要増加が予測されています。
行政分野では、地域包括ケアシステムの中核を担う専門職として、保健師の需要は安定的に推移すると見られています。
特に今後は、データヘルスの推進や複合的な健康課題への対応など、より高度な専門性を持つ保健師の需要が高まると予測されています。
2024年度に厚生労働省が示した「保健師人材確保ガイドライン」では、人口1万人あたり保健師数の目安が引き上げられ、多くの自治体で保健師の増員が課題となっています。
産業保健分野では、健康経営の普及に伴い、企業の健康管理部門や健康保険組合などでの需要が拡大しています。
特に従業員の健康を企業の重要な「資産」と位置づける経営思想が広まる中、産業保健師の役割は重要性を増しています。
2023年度の調査では、健康経営優良法人認定企業の約75%が産業保健師の増員を計画しており、今後5年間で約20%の需要増が見込まれています。
医療機関では、地域連携の強化に伴い、病院と地域をつなぐコーディネーターとしての保健師の役割が注目されています。
特に退院支援や在宅医療の推進において、医療と生活の両面から支援できる保健師の専門性が評価されつつあります。
ただし、医療機関全体での採用数は限定的であり、今後も緩やかな増加にとどまると予測されています。
新興分野として、以下の領域での需要創出も期待されています。
- デジタルヘルス企業(健康支援アプリ等の開発・運営)
- ヘルスケアコンサルティング企業
- 地域包括ケア関連ビジネス
- 健康まちづくり関連事業
2023年の調査では「公衆衛生人材確保戦略」として5年間で保健師数を現状の約1.2倍に増やす方針が示されており、総じて保健師の需要は拡大傾向にあると言えるでしょう。
ただし、需要の拡大に対して養成数が追いついていない状況もあります。
保健師養成課程の選択制移行により、新卒保健師の供給数は減少傾向にあります。
そのため、今後は看護師からのキャリアチェンジなど多様なルートでの人材確保が重要になると考えられています。
保健師を目指す方や現役保健師の方は、社会のニーズの変化に応じて専門性を高め、変化に対応する柔軟性を持つことが大切です。
特に予防と地域全体を見る視点という保健師の強みを活かしながら、新たな分野や技術も取り入れていくことで、将来的にも社会に必要とされる専門職として活躍できるでしょう。
まとめ
保健師は予防医学の専門家として、個人から地域社会まで幅広く健康を支援する重要な専門職です。
資格取得から専門性の向上、多様なキャリアパスまで、保健師という職業には様々な可能性が広がっています。
社会の変化に伴い保健師の役割も拡大しており、今後もさらなる専門性と柔軟性が求められるでしょう。
皆さんの保健師としてのキャリア形成に、この記事が少しでも参考になれば幸いです。
保健師としてのキャリアをさらに深めたい方、具体的な転職相談や資格取得についてもっと知りたい方は、看護師専門のキャリア支援サイト【はたらく看護師さん】をぜひご活用ください。
当サイトでは保健師に関する最新情報や、実際に活躍している保健師へのインタビュー、資格取得のための学校情報など、さらに詳しい情報を提供しています。
また、保健師資格取得を目指す看護師向けの特別セミナーや個別キャリア相談も実施していますので、ぜひ会員登録して各種サービスをご利用ください。
あなたの保健師としての一歩を、【はたらく看護師さん】が全力でサポートします。