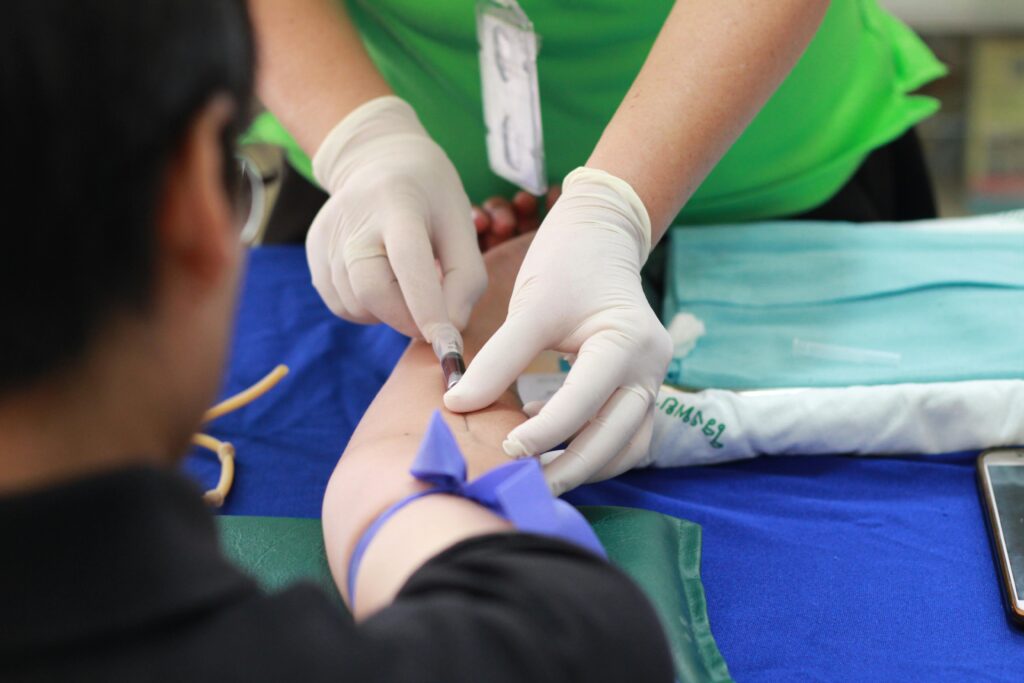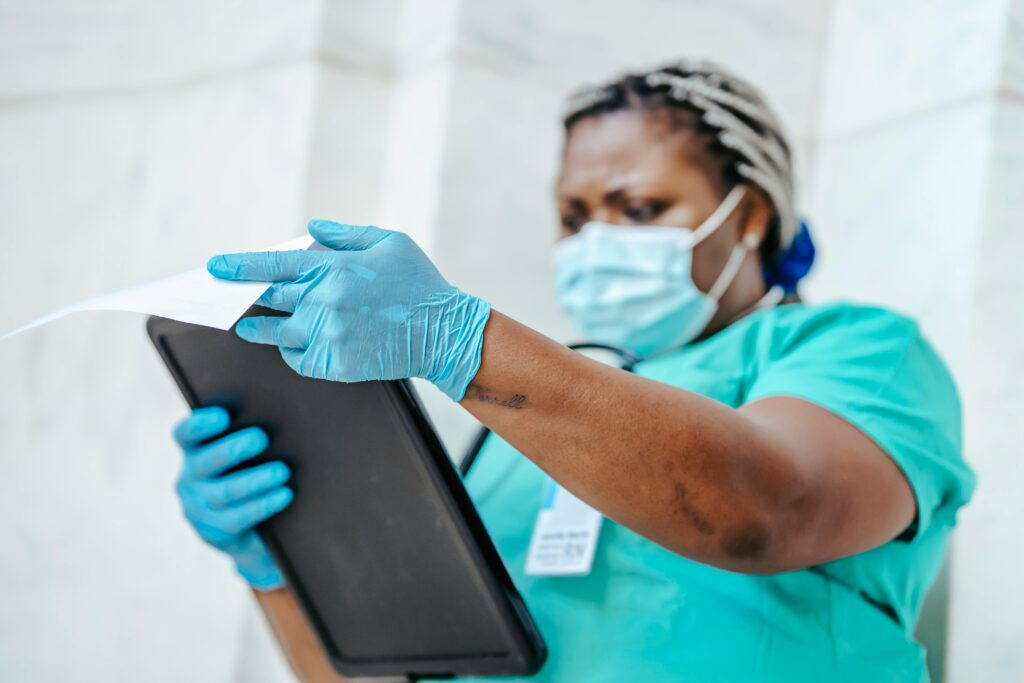訪問看護ステーションの経営者・管理者必見。
看護師確保の悩みを解決する実践的なノウハウを詳しく解説します。
実例とデータに基づいた具体的な施策で、採用から定着までをサポートします。
この記事で分かること
- 看護師採用における具体的な数値目標の設定方法と採用計画の立て方
- 採用から定着までの一貫した支援体制の構築方法とポイント
- 教育研修プログラムの設計から実施までの具体的なステップ
- 実際の成功事例から学ぶ効果的なアプローチと応用方法
- デジタルツールを活用した最新の採用手法と運用のコツ
この記事を読んでほしい人
- 訪問看護ステーションの経営者や管理者の方
- 看護師の採用や人材育成に携わる担当者の方
- 看護師の定着率向上に課題を感じている方
- 採用コストの削減と採用効率の向上を目指している方
- 教育研修制度の整備を検討している方
訪問看護ステーションにおける看護師確保の現状と課題

医療ニーズの多様化と在宅医療の需要増加に伴い、訪問看護ステーションにおける看護師確保は年々重要性を増しています。
2025年の地域包括ケアシステムの本格始動を控え、より戦略的な人材確保と育成が求められる中、現場が抱える課題と解決策を詳しく見ていきましょう。
看護師不足の実態と背景
訪問看護業界における看護師不足は深刻な状況が続いています。
日本看護協会の調査によると、訪問看護ステーションの約75%が看護師確保に困難を感じているとの結果が出ています。
2024年度の調査では、特に経験年数5年以上の中堅看護師の確保が困難であることが明らかになっています。
人材不足の主な要因
労働環境の課題や処遇面での懸念が、人材確保を困難にしている大きな要因となっています。
一人で訪問する際の責任の重さや、24時間対応による負担感も影響しています。
特に小規模な訪問看護ステーションでは、給与水準や福利厚生面での競争力不足が課題となっています。
地域による格差
都市部と地方では、看護師確保における課題が異なります。
都市部では人材の流動性が高く、競合との差別化が課題となる一方、地方では絶対的な人材不足が深刻です。
採用市場の変化と対応
近年のデジタル化の進展により、採用手法も大きく変化しています。
従来の求人媒体に加え、SNSやオンライン採用説明会など、新たな採用チャネルの活用が求められています。
採用手法の多様化
オンライン面接やウェブ説明会の導入により、採用活動の効率化が進んでいます。
デジタルツールを活用した採用活動は、特に若手看護師層へのアプローチに効果を発揮しています。
効果的な採用計画の策定と実施

採用計画の成否は、綿密な準備と実行可能な戦略立案にかかっています。
ここでは、具体的な数値目標の設定から、採用手法の選定、さらには採用後のフォローアップまで、段階的に解説します。
採用目標の設定と分析
目標設定においては、現状の正確な把握が不可欠です。2025年に向けた人員計画を立てる際は、以下の要素を考慮して策定していきます。
現状分析の実施方法
現在の職員構成や年齢分布、退職予定者数などの基礎データを収集することから始めます。
直近3年間の離職率や採用実績などのデータを分析し、今後の採用必要数を算出します。
地域の人口動態や競合施設の状況なども含めた、包括的な分析が重要です。
採用目標数の算出
必要人員数は、利用者数の増加予測と、サービス提供体制の整備計画から導き出します。
余裕を持った人員配置を実現するため、予測される離職率に基づいた補充人員も考慮します。
採用チャネルの選定と活用
効果的な採用活動を展開するためには、複数の採用チャネルを適切に組み合わせることが重要です。
従来型メディアの活用
看護師専門の求人媒体は、依然として高い効果を発揮しています。
媒体ごとの特性を理解し、予算に応じた効果的な出稿計画を立てることが成功のポイントです。
デジタル採用の展開
SNSを活用した情報発信では、職場の雰囲気や実際の業務内容を具体的に伝えることができます。
オンライン説明会や職場見学会は、より多くの候補者にアプローチできる効果的な手段となっています。
採用予算の策定と管理
採用活動の効果を最大化するには、適切な予算配分と管理が欠かせません。
予算項目の設定
求人広告費、採用イベント開催費、採用関連ツールの導入費など、必要経費を細かく洗い出します。
採用一人あたりのコストを算出し、費用対効果を測定できる体制を整えます。
コスト管理の実践
月次での予算執行状況を確認し、効果の低い施策は見直しを行います。
季節変動を考慮した予算配分を行い、採用効果の最大化を図ります。
面接・選考プロセスの確立
選考プロセスは、応募者の適性を見極めるだけでなく、組織の魅力を伝える機会でもあります。
面接官の育成
面接官には、適切な評価基準と面接技術に関する研修を実施します。
組織の理念や求める人材像について、面接官間で認識を統一することが重要です。
選考基準の明確化
技術面のスキルだけでなく、組織との価値観の適合性も重要な評価ポイントとなります。
具体的な評価シートを作成し、公平な選考を実現します。
定着支援の具体的施策

看護師の定着率向上には、キャリア支援から働きやすい環境整備まで、総合的なアプローチが必要です。
ここでは、実践的な定着支援策と、その導入・運用方法について詳しく解説します。
キャリア支援体制の構築
看護師一人ひとりの将来像に寄り添ったキャリア支援は、長期的な定着を促進する重要な要素です。
キャリアパスの明確化
入職後の成長過程を可視化し、具体的な目標設定ができる仕組みを整えます。
スペシャリストコースとマネジメントコースなど、複数のキャリアパスを用意することで、個々の希望に応じた成長を支援します。
資格取得支援制度の整備
専門性の向上につながる資格取得を、金銭面と時間面の両方からサポートします。
資格取得後の処遇改善や役割付与を明確にし、学習意欲の向上を図ります。
労働環境の改善
働きやすい職場づくりは、看護師の定着率向上に直結する重要な施策です。
勤務体制の柔軟化
ライフステージに応じた多様な勤務形態を整備することで、長期的な就業継続を支援します。
短時間勤務やフレックスタイム制など、個々のニーズに対応できる制度を導入します。
業務効率化の推進
ICTツールの活用により、記録業務や情報共有の効率化を図ります。
移動時間の最適化など、訪問看護特有の課題に対する改善策を実施します。
待遇面での支援強化
適切な待遇は、モチベーション維持と定着率向上の基盤となります。
給与体系の整備
経験や能力を適切に評価する給与体系を構築します。
業績連動型の賞与制度など、努力が報われる仕組みを導入します。
福利厚生の充実
休暇制度の拡充や健康管理支援など、総合的な福利厚生プログラムを整備します。
子育て支援や介護支援など、ライフイベントに応じた支援制度を確立します。
コミュニケーション体制の強化
良好な職場関係の構築は、定着率向上の重要な要素です。
定期面談の実施
キャリアプランや職場環境に関する定期的な面談を実施します。
課題の早期発見と解決に向けた、双方向のコミュニケーションを重視します。
チーム力の向上
定期的なカンファレンスやケース検討会を通じて、チーム全体のスキルアップを図ります。
スタッフ間の相互理解を深める交流機会を創出します。
メンタルヘルスケアの整備
心身の健康管理は、継続的な就業支援の基盤となります。
相談体制の確立
専門家による相談窓口を設置し、心理面でのサポート体制を整えます。
管理者向けのメンタルヘルス研修を実施し、早期発見・対応を可能にします。
ストレス管理支援
定期的なストレスチェックを実施し、職場環境の改善に活用します。
リフレッシュ休暇の取得促進など、予防的なアプローチも重視します。
育成体制の確立

看護師の専門性向上と組織の質の向上には、体系的な育成プログラムの整備が不可欠です。
ここでは、新人からベテランまで、段階に応じた効果的な育成方法を解説します。
教育研修プログラムの設計
効果的な人材育成には、明確な目標設定と体系的なプログラム設計が重要です。
カリキュラムの構築
経験年数や役割に応じた段階的な学習内容を設定します。
実践的なスキル習得に重点を置いた、現場で活きる研修内容を企画します。
評価基準の設定
具体的な到達目標と評価指標を設定し、成長過程を可視化します。
定期的な評価とフィードバックにより、継続的な改善を図ります。
新人教育体制の整備
新人看護師の早期戦力化と定着促進には、手厚い支援体制が必要です。
プリセプター制度の活用
経験豊富な先輩看護師による、マンツーマンの指導体制を確立します。
日々の業務指導に加え、精神面のサポートも重視します。
段階的な実務導入
基本的な訪問看護スキルから、徐々に難易度を上げていく実践プログラムを実施します。
個々の習熟度に応じて、担当ケースを慎重に選定します。
中堅職員の育成強化
組織の中核を担う中堅職員には、より高度な専門性の習得が求められます。
専門スキルの向上
疾患別の専門知識や、高度な医療処置のスキルアップを支援します。
事例検討会や研究発表の機会を通じて、実践力の向上を図ります。
リーダーシップ研修
後輩指導や組織運営に必要なマネジメントスキルを習得します。
チームリーダーとしての役割を果たすための研修を実施します。
管理者育成プログラム
次世代の管理者育成は、組織の持続的な発展に不可欠です。
マネジメント能力の開発
経営的視点とリーダーシップスキルの習得を支援します。
財務管理や人材マネジメントなど、実践的な知識を学ぶ機会を提供します。
経営参画機会の創出
経営会議への参加や企画立案など、実践的な経験を積む機会を設けます。
管理者としての意思決定能力を養成します。
継続教育の実施体制
学びの機会を継続的に提供することで、組織全体の質の向上を図ります。
外部研修の活用
専門性の高い外部研修への参加を支援し、最新の知識と技術の習得を促進します。
学会や研究会への参加を通じて、広い視野と新しい知見を得る機会を提供します。
内部勉強会の開催
定期的な事例検討会や勉強会を通じて、組織内での知識共有を促進します。
スタッフ自身が講師を務める機会を設け、教える側の成長も支援します。
実践的なケーススタディ

これまでご紹介した施策の効果をより具体的に理解するため、実際の成功事例を詳しく見ていきましょう。
各事例から得られる学びを、皆様の施設での取り組みにも活かしていただければと思います。
A訪問看護ステーションの事例
都市部で開設5年目を迎えたA訪問看護ステーションは、看護師の定着率向上と採用効率化に成功しました。
課題と背景
開設当初は看護師の定着率が低く、年間離職率が35%に達していました。
人材確保に多額のコストがかかり、経営を圧迫する要因となっていました。
具体的な取り組み
まず、現職スタッフへの詳細なヒアリングを実施し、働く上での課題を明確化しました。
勤務シフトの柔軟化や、ICTツールの導入による業務効率化を段階的に実施しました。
教育支援制度を充実させ、資格取得支援や外部研修参加の補助を強化しました。
取り組みの成果
3年間で年間離職率を8%まで低下させることに成功しました。
採用コストを60%削減し、経営の安定化にも貢献しています。
B訪問看護ステーションの事例
地方都市で10年の実績を持つB訪問看護ステーションは、独自の採用戦略で人材確保に成功しています。
採用における課題
地域の看護師不足が深刻で、従来の採用手法では必要な人材が確保できない状況でした。
競合施設との差別化が難しく、採用面での優位性を発揮できていませんでした。
革新的な取り組み
地域の医療機関や教育機関とのネットワークを構築し、潜在看護師の発掘に注力しました。
SNSを活用した情報発信で、職場の魅力や働きやすさを積極的にアピールしています。
実習生の受け入れを強化し、将来の採用につながる関係づくりを行っています。
成果と今後の展開
年間採用目標の達成率が95%を超え、安定的な人材確保を実現しています。
地域における認知度も向上し、応募者の質も改善傾向にあります。
C訪問看護ステーションの取り組み
大都市圏で複数の事業所を展開するC訪問看護ステーションは、教育体制の整備で成長を実現しました。
人材育成の課題
急速な事業拡大に伴い、教育の質の維持が困難な状況でした。
事業所間で教育内容にばらつきが生じ、サービスの統一性が損なわれていました。
統合的な育成システム
全事業所共通の教育プログラムを整備し、統一的な人材育成を実現しました。
オンライン研修システムの導入により、場所を問わない学習環境を整備しています。
システム導入の効果
新人看護師の育成期間を30%短縮し、早期戦力化を実現しています。
事業所間の連携が強化され、ノウハウの共有がスムーズになりました。
おしえてカンゴさん!Q&A
現場で実際に直面する疑問や課題について、経験豊富な看護師が具体的にお答えします。
皆様からよくいただく質問を中心に、実践的なアドバイスをご紹介します。
採用に関する質問
採用活動の効果的な進め方について、具体的な方法をご紹介します。
Q1:効果的な採用面接のポイントを教えてください
面接では、技術面の確認だけでなく、応募者の価値観や意欲を丁寧に確認することが重要です。
具体的な事例を用いた質問を通じて、実践力とコミュニケーション能力を評価します。
Q2:採用媒体の選び方のコツを教えてください
採用媒体は、ターゲットとする年齢層や経験年数によって使い分けることをお勧めします。
費用対効果を測定しながら、複数の媒体を組み合わせることで相乗効果が期待できます。
定着支援に関する質問
定着率向上のための具体的な施策について解説します。
Q3:新人看護師の早期離職を防ぐにはどうすればよいですか
入職後3ヶ月間は特に手厚いサポート体制を整え、不安や課題を早期に発見することが大切です。
プリセプター制度と定期面談を組み合わせた、重層的なサポート体制が効果的です。
Q4:中堅看護師のモチベーション維持のコツは何ですか
キャリアビジョンに応じた役割付与と、それに見合った待遇改善を計画的に実施します。
後輩育成の機会を提供することで、やりがいと責任感を持って働ける環境を整備します。
育成に関する質問
効果的な教育研修の実施方法についてお答えします。
Q5:効果的な研修プログラムの作り方を教えてください
現場のニーズを反映した実践的な内容を中心に、段階的な学習プログラムを設計します。
定期的な評価とフィードバックを通じて、プログラムの改善を継続的に行います。
Q6:リモート研修を効果的に行うポイントは何ですか
オンラインツールの特性を活かし、インタラクティブな要素を取り入れた研修設計が重要です。
事前課題と事後フォローを充実させることで、学習効果を高めることができます。
労務管理に関する質問
適切な労務管理の実践方法について解説します。
Q7:効果的なシフト管理の方法を教えてください
スタッフの希望を最大限考慮しながら、サービスの質を維持できるバランスの取れたシフト設計が重要です。
ICTツールを活用した効率的なシフト管理システムの導入も検討に値します。
まとめ:看護師確保の未来に向けて
本記事で解説した採用・定着・育成の各施策は、いずれも看護師確保の重要な要素となります。
特に2025年に向けて、戦略的な人材確保がますます重要となってきます。
皆様の施設でも、まずは現状分析から始め、できるところから段階的に施策を導入していただければと思います。
より詳しい情報や、実践的なツール、転職相談は【はたらく看護師さん】をご活用ください。
▼詳しくは【はたらく看護師さん】公式サイトへ