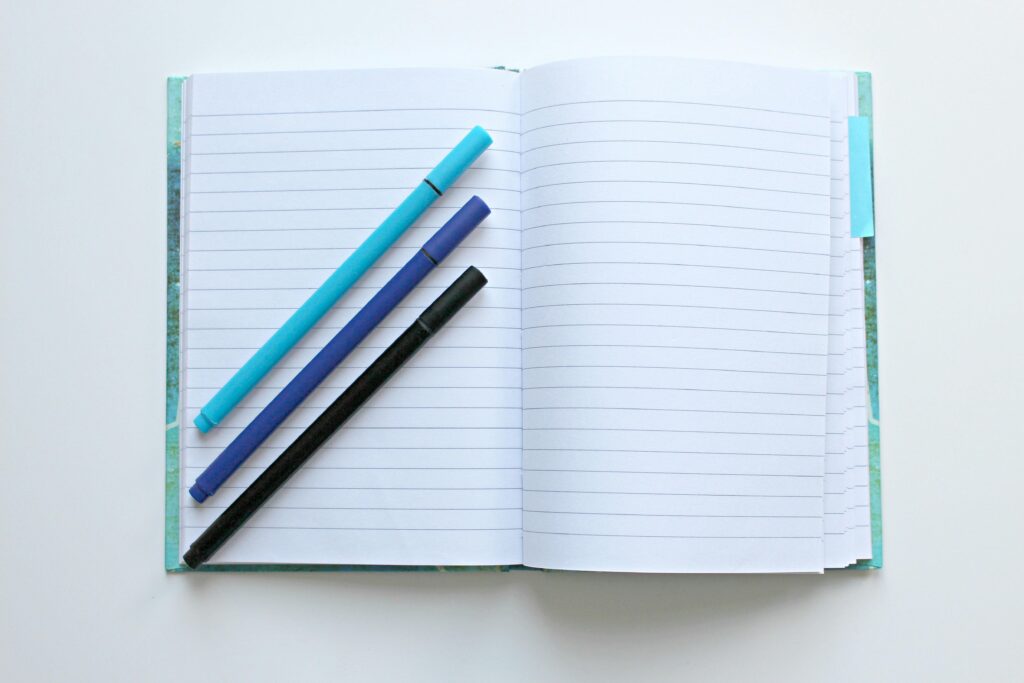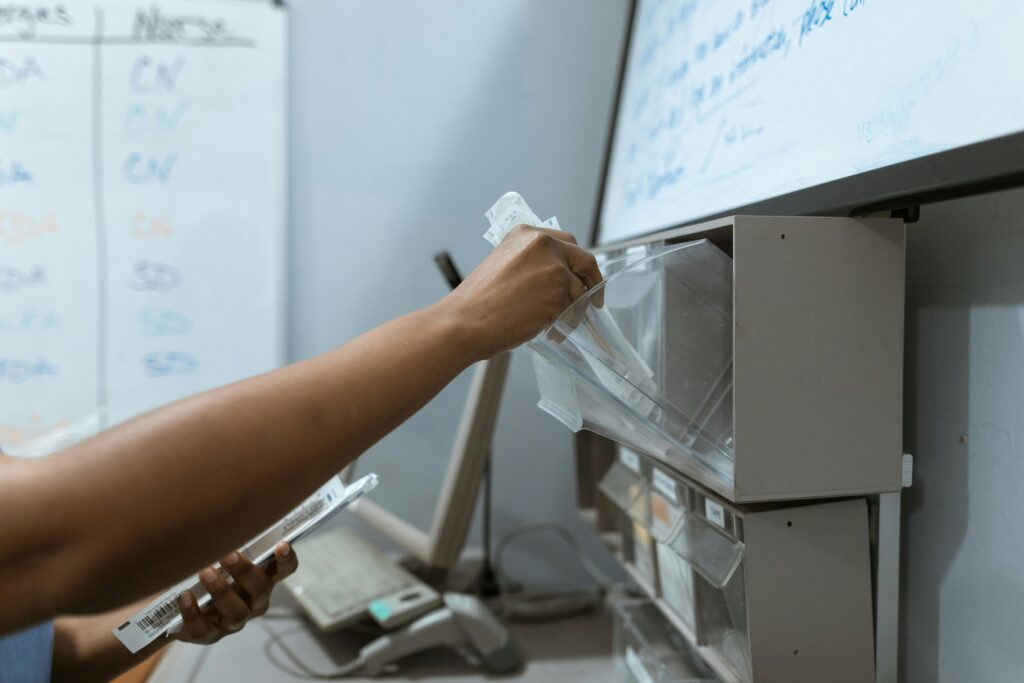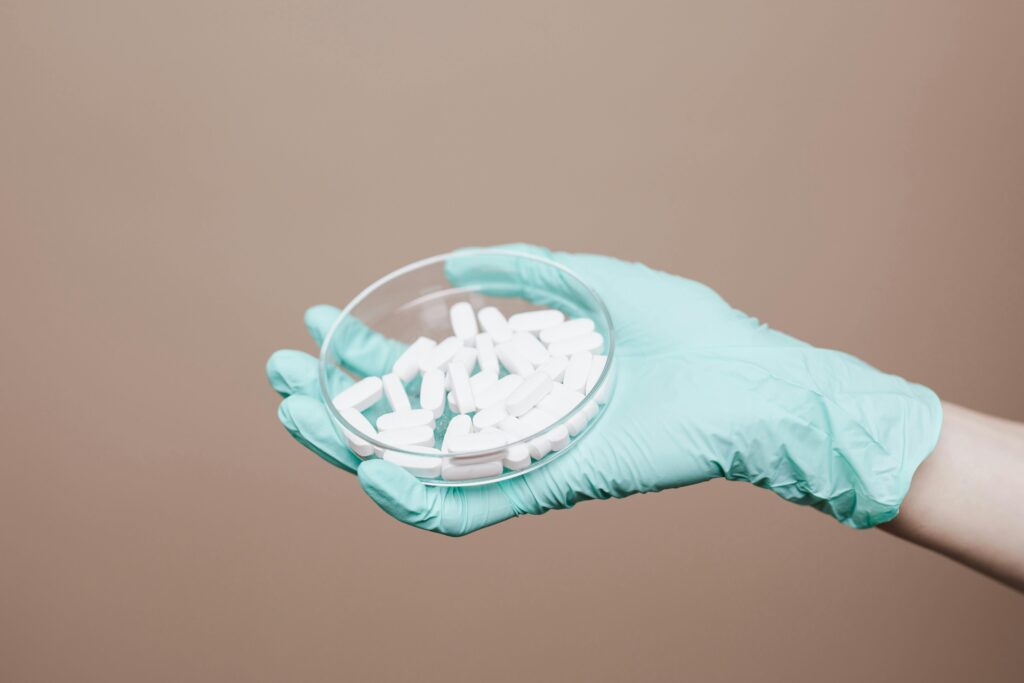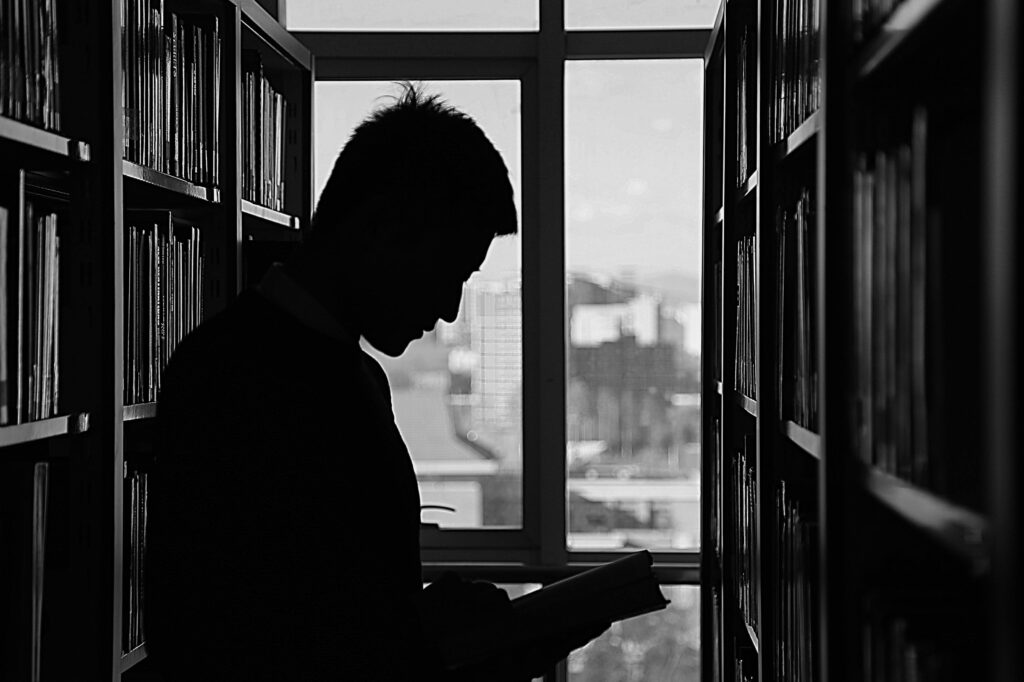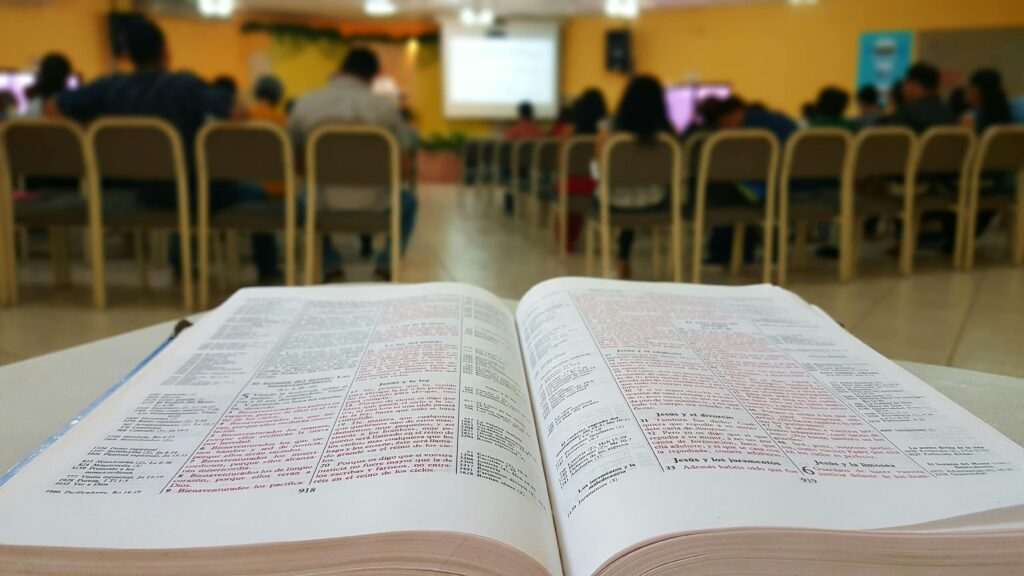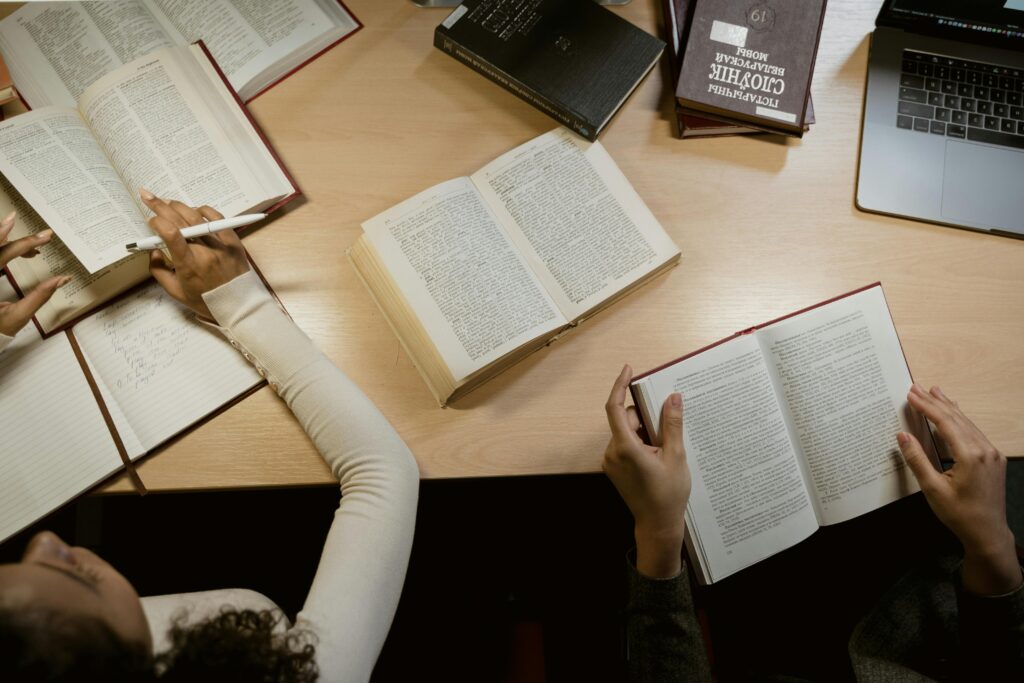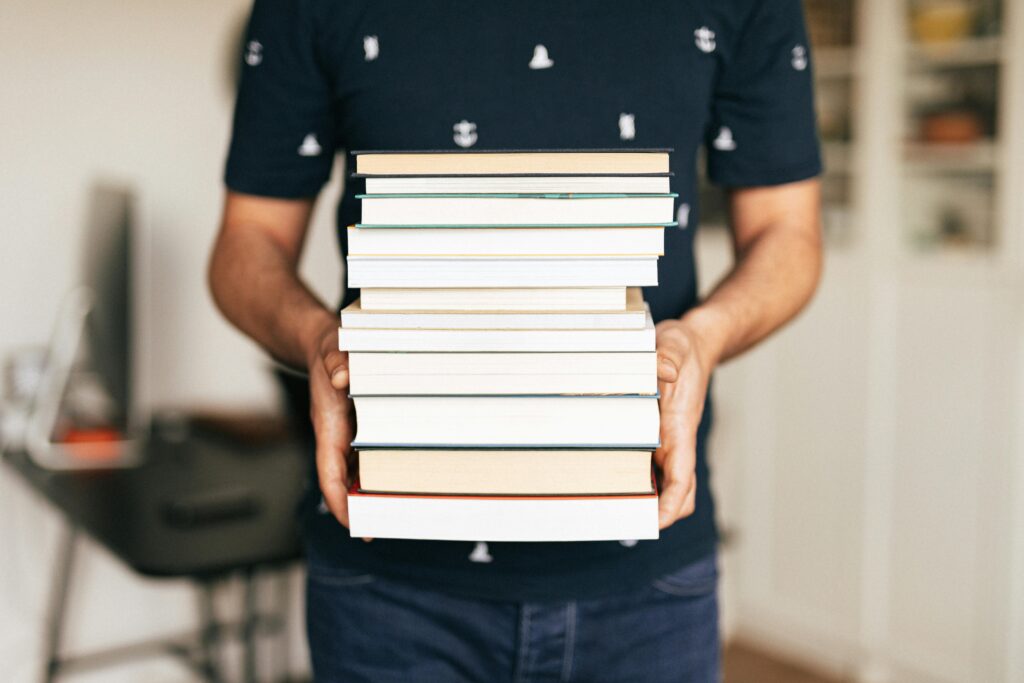医療機関における診療報酬の適切な管理と算定は、質の高い医療サービスの提供と健全な病院経営の両立に欠かせない要素となっています。
本記事では、看護師の視点から診療報酬の算定要件と効果的な管理方法について、実践的なアプローチを交えながら解説します。
2024年度の改定内容を踏まえ、現場で活用できる具体的な施策や改善事例もご紹介します。
この記事で分かること
- 看護師に関連する診療報酬の加算項目と最新の算定要件
- 算定漏れを防ぐための効果的な記録管理手法と体制整備
- 電子カルテシステムを活用した業務効率化の具体的方法
- 実例に基づく収益改善のポイントと実践的なチェックリスト
- 多職種連携における看護師の役割と情報共有の重要性
この記事を読んでほしい人
- 診療報酬の管理を担当する看護管理者
- 算定要件の理解と適切な記録管理を目指す看護師
- 医療機関の収益改善に関わる医療従事者
- 効率的な体制整備を検討している看護部門のリーダー
- 診療報酬改定に対応するための知識を得たい医療スタッフ
看護師関連の主要診療報酬加算項目

2024年度の診療報酬改定において、看護師に関連する加算項目は多岐にわたります。本セクションでは、入院基本料関連の加算から在宅医療関連の加算まで、現場で特に重要となる項目について詳しく解説します。
それぞれの算定要件や算定のポイントを理解することで、適切な診療報酬管理を実現しましょう。
入院基本料関連の加算
入院基本料に関連する加算は、医療機関の基本的な収益を支える重要な要素です。看護職員の配置状況や勤務体制に応じて、さまざまな加算を算定することができます。
看護職員夜間配置加算
夜間における手厚い看護体制を評価する加算です。入院基本料等加算として算定され、夜間の看護職員配置数に応じて12対1から16対1までの区分があります。算定にあたっては、月平均夜勤時間数や勤務実績の記録が必要となります。
施設基準と算定要件
施設基準には、夜間における看護職員の数が所定の数以上であることや、夜勤時間帯の看護職員の勤務体制が確保されていることなどが定められています。
具体的な要件として、夜間に看護を行う看護職員の数が、所定の入院患者数に対して必要な数以上であることが求められます。月平均夜勤時間数は、1人当たり72時間以下とする必要があります。
看護補助体制加算
看護職員と看護補助者との連携による看護体制を評価する加算です。患者サービスの向上と看護職員の負担軽減を図ることを目的としています。
具体的な算定方法
看護補助者の配置数に応じて25対1から75対1までの区分があり、それぞれの基準を満たすことで算定が可能です。看護補助者の勤務実績や研修受講歴の記録を適切に管理することが重要です。
外来関連の加算
外来診療における看護師の役割に応じた加算項目について解説します。患者指導や在宅支援など、多岐にわたる看護業務が評価対象となっています。
外来看護体制加算
外来における手厚い看護体制を評価する加算です。専門性の高い看護師による患者指導や相談対応が算定要件となります。
算定における注意点
外来患者数に対する看護職員の配置基準や、患者への指導実績の記録が必要です。算定漏れを防ぐため、日々の看護記録との連動が重要となります。
在宅医療関連の加算
在宅医療の推進に伴い、訪問看護や在宅患者指導に関連する加算項目が重要性を増しています。
在宅患者訪問看護指導料
在宅療養中の患者に対する看護師の訪問指導を評価する加算です。患者の状態や指導内容に応じて、複数の区分が設定されています。
訪問看護の実施要件
訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示に基づく看護計画の作成と、実施した看護内容の詳細な記録が必要です。また、他職種との連携状況についても記録を残すことが求められます。
退院時共同指導料
入院患者の退院時における多職種連携を評価する加算です。在宅療養支援の充実を図ることを目的としています。
算定のための体制整備
退院時カンファレンスの実施や指導内容の記録など、具体的な要件を満たす必要があります。また、関係機関との連携体制の構築も重要となります。
その他の特定入院料等
特定の病棟や診療内容に応じた加算項目について解説します。
救急医療管理加算
救急医療を必要とする患者に対する医療提供体制を評価する加算です。看護師の役割も重要な要素となっています。
救急医療体制の要件
24時間体制での救急医療の提供や、必要な医療機器の配備など、具体的な施設基準を満たす必要があります。看護師の配置基準も定められており、適切な勤務体制の確保が求められます。
重症度、医療・看護必要度加算
患者の状態に応じた看護必要度を評価する加算です。適切な評価と記録が算定の基本となります。
評価方法と記録の重要性
看護必要度の評価は、所定の評価項目に基づいて日々実施する必要があります。評価結果の定期的な確認と、適切な記録管理が求められます。
診療報酬改定のポイント

2024年度の診療報酬改定では、医療機関の機能分化や医療従事者の働き方改革の推進、医療の質の向上などが重点的に評価されています。本セクションでは、看護師に特に関係する改定内容について、実務への影響と対応策を含めて解説します。
看護配置基準の見直し
看護職員の配置基準について、より柔軟な勤務体制の構築を可能とする改定が行われています。これにより、各医療機関の実情に応じた効率的な人員配置が可能となりました。
夜間看護体制の評価
夜間における看護体制の充実を図るため、看護職員夜間配置加算の要件が一部変更されています。より現場の実態に即した評価体系となっています。
算定要件の具体的変更点
月平均夜勤時間数の計算方法が見直され、より実態に即した運用が可能となりました。また、夜勤専従者の配置に関する評価も新設されています。
看護補助者の活用推進
看護業務の効率化を図るため、看護補助者の活用に関する評価が拡充されています。看護職員の負担軽減と、より質の高い看護の提供を両立することが期待されます。
看護補助体制加算の充実
看護補助者の配置に関する評価が見直され、より手厚い体制を評価する区分が新設されています。医療機関の規模や機能に応じた柔軟な対応が可能となりました。
新規算定における留意点
新たな区分の算定にあたっては、看護補助者の研修実施や業務範囲の明確化など、具体的な要件を満たす必要があります。体制整備の計画的な実施が求められます。
在宅医療の推進
地域包括ケアシステムの構築に向けて、在宅医療に関する評価が充実されています。訪問看護ステーションとの連携強化も重要なポイントとなっています。
訪問看護に関する改定内容
訪問看護指示料や訪問看護管理療養費について、多様な患者ニーズに対応するための見直しが行われています。医療機関との連携強化も評価の対象となっています。
算定方法の変更点
指示内容や実施計画の記載要件が明確化され、より適切な評価が可能となっています。多職種連携の重要性も一層強調されています。
医療安全対策の強化
医療安全に関する取り組みの評価が強化され、より実効性の高い体制整備が求められています。看護部門の役割も重要視されています。
医療安全対策加算の見直し
医療安全対策に関する評価項目が追加され、より包括的な安全管理体制の構築が求められています。具体的な実施基準も明確化されています。
体制整備のポイント
医療安全管理者の配置や研修実施など、具体的な要件を満たす必要があります。記録管理の重要性も増しています。
経過措置への対応
一部の改定項目については経過措置が設けられており、段階的な対応が可能となっています。計画的な体制整備が重要です。
経過措置期間中の対応
経過措置の対象となる項目について、期間内に必要な体制整備を行うことが求められます。具体的なスケジュール管理が重要となります。
具体的な準備事項
施設基準の届出や必要書類の整備など、期限内に対応すべき事項を明確にしています。チェックリストを活用した進捗管理が効果的です。
算定要件の理解と管理体制の整備

診療報酬の適切な算定には、各加算項目の算定要件を正確に理解し、それを満たすための管理体制を整備することが不可欠です。効果的な管理体制の構築と運用により、算定漏れを防ぎ、適切な収益確保を実現できます。
基本的な算定要件の理解
施設基準と個別の算定要件は、診療報酬算定の両輪となります。日々の業務の中で、これらの要件を確実に満たすことで、安定した医療提供体制を維持できます。
施設基準への対応
医療機関の施設基準において、看護職員の配置基準は特に重要な要素です。基準を満たすための具体的な方策として、月間の勤務表作成時に必要人数を確保し、急な欠勤にも対応できる余裕を持った人員配置を行います。
人員配置基準の管理
看護職員の実働時間を正確に把握するため、タイムカードと勤務実績表の突合を毎月実施します。変形労働時間制を導入している場合は、シフト管理表を用いて4週8休の確保状況を確認します。
施設設備要件の確認
医療機器や設備の配置状況については、月1回の定期点検時に確認表を用いて実施します。保守点検の実施状況は専用の管理台帳に記録し、次回点検日を明確にします。
個別の算定要件管理
患者ごとの算定要件の確認は、電子カルテのチェック機能を活用して実施します。特に重要な項目については、看護師長による二重チェックの体制を構築します。
診療録への記載事項
算定に必要な観察項目や実施内容は、具体的な数値やケアの詳細を含めて記載します。バイタルサインの変化や患者の反応など、評価に必要な情報を漏れなく記録します。
効果的な管理体制の構築
管理体制の中核となる専任者を配置し、組織的な取り組みとして展開することで、持続可能な体制を実現します。
専任管理者の配置
診療報酬管理の専任者には、5年以上の臨床経験を持つ看護師を配置します。算定要件や管理手法について、定期的な外部研修への参加を必須とします。
業務範囲の明確化
専任管理者は、算定状況の確認、記録内容の点検、スタッフ教育の実施を主な業務とします。医事課との週1回のカンファレンスで、算定漏れや記録不備の改善を図ります。
チェック体制の確立
毎日の算定確認は日勤終了時に実施し、週1回の総点検で見落としを防ぎます。月末には算定率の分析と改善策の検討を行います。
チェックリストの活用
電子カルテと連動したチェックリストにより、必要な記録項目を自動的に抽出します。未記入項目があれば、担当看護師にアラートを送信する仕組みを導入します。
記録管理の実践方法
記録の標準化と効率化により、確実な算定と業務負担の軽減を両立します。
記録様式の標準化
看護記録は、SOAP形式を基本とし、算定要件に関する項目を明確に識別できる形式で記載します。観察項目ごとにコード化を行い、データの抽出を容易にします。
テンプレートの作成
頻出する記録項目については、必要な観察点を含むテンプレートを用意します。患者の状態変化や実施したケアの詳細を、効率的に記録できる形式とします。
データの分析と活用
月次の算定状況を分析し、算定率の低い項目については原因分析と対策立案を行います。部署ごとの算定率を比較し、好事例の水平展開を図ります。
分析手法の選択
算定率、記録完成度、要件充足率などの指標を設定し、月次でモニタリングを実施します。特に重要な指標については、日次での確認体制を構築します。
教育研修体制の整備
算定要件の理解度向上と記録スキルの向上を目的とした教育プログラムを実施します。
研修プログラムの作成
新人看護師向けの基礎研修、中堅看護師向けの実践研修、管理者向けの専門研修など、対象者のレベルに応じたプログラムを提供します。
研修内容の選定
算定要件の基礎知識、記録の書き方、チェックポイントなど、実務に直結する内容を中心に構成します。実際の記録例を用いた演習も取り入れ、実践力の向上を図ります。
電子カルテシステムの活用

電子カルテシステムは、診療報酬の算定管理において重要なツールとなります。適切な設定と運用により、算定漏れの防止と業務効率の向上を実現できます。ここでは、具体的な活用方法と効果的な運用のポイントをお伝えします。
システム活用の基本設定
電子カルテシステムの基本設定を最適化することで、日々の業務がスムーズになります。必要な情報をすぐに取り出せる環境を整えましょう。
算定要件の設定
システム内に算定要件のマスタを作成し、必要な記録項目を自動的に表示します。診療報酬改定時には、速やかにマスタの更新を行います。
必須入力項目の設定
重要度、医療・看護必要度の評価項目など、算定に必須となる項目は必ず入力しないと先に進めない設定とします。入力忘れを防ぐため、未入力項目は赤字で表示されます。
テンプレートの効果的活用
業務の標準化と効率化のため、状況に応じたテンプレートを用意します。よく使用する文例や評価項目をあらかじめ設定しておきます。
基本テンプレートの作成
看護記録の基本となるテンプレートには、算定に必要な項目を漏れなく含めます。患者の状態観察や実施したケアの内容を簡潔に記録できる形式とします。
テンプレートの使用方法
患者の状態に合わせて適切なテンプレートを選択し、必要に応じて内容を追加修正します。定型的な記録は効率的に入力し、個別性の高い内容は詳細に記載します。
アラート機能の設定
算定要件を満たしていない場合や記録が不十分な場合に、アラートを表示する設定を行います。早期の対応により、算定漏れを防ぎます。
アラートの種類と設定
緊急度に応じて異なるアラート表示を設定します。重要度の高い項目は画面上部に赤字で表示し、確認するまでアラートが消えない設定とします。
アラート確認の運用
アラートが表示された場合は、その日のうちに対応を完了します。対応が難しい場合は、看護師長に報告し、解決策を検討します。
データの抽出と分析
システムに蓄積されたデータを活用し、算定状況の分析や業務改善に役立てます。定期的なデータ確認により、課題の早期発見が可能となります。
分析レポートの作成
月次の算定状況や記録完成度について、部署ごとの比較が可能なレポートを作成します。グラフや表を用いて、傾向を視覚的に把握できるようにします。
データの活用方法
分析結果は、月1回の診療報酬管理会議で共有し、改善策を検討します。好事例については、具体的な運用方法を他部署にも展開します。
システムトラブルへの対応
システムダウン時の対応手順を明確にし、業務の継続性を確保します。緊急時対応マニュアルを整備し、定期的な訓練を実施します。
バックアップ体制の整備
システム障害時は、紙の記録用紙を使用して記録を継続します。システム復旧後、速やかにデータの入力を行い、算定に影響が出ないようにします。
緊急時の連絡体制
システム管理者や保守業者との連絡体制を整備し、24時間対応可能な体制を構築します。連絡先リストは最新の状態に保ち、定期的に更新します。
具体的な改善事例

実際の医療機関における診療報酬算定の改善事例をご紹介します。それぞれの事例から、効果的な取り組みのポイントと成功要因を学ぶことができます。これらの事例を参考に、各施設の状況に合わせた改善策を検討しましょう。
C病院の事例
C病院は、病床数300床の中規模総合病院です。算定漏れの防止と記録業務の効率化を目的とした改善プロジェクトを実施し、大きな成果を上げることができました。
取り組みの背景と課題
看護記録の不備による算定漏れが月平均で約150件発生し、推定で年間1,200万円の機会損失が発生していました。特に夜勤帯での記録漏れが顕著でした。
具体的な問題点
夜勤帯における重症度、医療・看護必要度の評価において、30%の記録が翌日以降の入力となっていました。また、看護師による記録内容にばらつきが見られ、算定要件を満たす記録になっていないケースが散見されました。
改善策の実施内容
電子カルテのテンプレート改修と、リアルタイムチェック機能の導入を行いました。夜勤帯の記録については、巡回時に携帯端末で入力できる体制を整備しました。
システムの改修内容
必要度評価項目を簡単に入力できるようタブレット端末を導入し、ベッドサイドでの記録を可能にしました。また、未入力項目のアラート機能を強化し、日勤リーダーが確認できる仕組みを構築しました。
取り組みの成果
改善策の実施により、記録の完成度が95%まで向上し、算定漏れは月平均20件まで減少しました。年間の増収効果は約1,000万円となっています。
D施設の改善事例
D施設は、療養病床150床を有する医療施設です。看護補助体制加算の算定強化と記録の標準化に取り組み、大きな成果を上げることができました。
課題と取り組みの経緯
看護補助者の配置は基準を満たしていたものの、業務実績の記録が不十分で加算の算定ができていないケースが多く見られました。
具体的な問題状況
看護補助者の業務内容が明確に記録されておらず、算定要件の充足を証明できない状況でした。また、研修実績の管理も不十分で、加算の要件を満たせていませんでした。
実施した対策
看護補助者の業務記録テンプレートを作成し、日々の業務内容を15分単位で記録する体制を整備しました。また、研修プログラムを体系化し、受講管理を徹底しました。
記録方法の改善
タブレット端末を導入し、業務の開始終了時刻と具体的な内容を簡単に入力できる仕組みを構築しました。入力された内容は自動的に集計され、月次の実績管理が容易になりました。
改善後の変化
看護補助体制加算の算定率が100%となり、月額約200万円の増収となりました。看護補助者の業務内容も「見える化」され、より効率的な人員配置が可能となっています。
E医療センターの取り組み
E医療センターは、急性期病床400床を有する地域の中核病院です。医療・看護必要度加算の算定強化に取り組み、継続的な改善を実現しています。
取り組みのきっかけ
重症度、医療・看護必要度の評価において、記録の不備による算定漏れが多発していました。特に休日夜間の記録に課題がありました。
当初の問題点
必要度評価の記録が遅れがちで、正確な評価ができていないケースが多く見られました。また、評価者による判断のばらつきも大きな課題となっていました。
改善プログラムの内容
評価者の教育プログラムを整備し、部署ごとに必要度評価のリーダーを育成しました。また、電子カルテのチェック機能を強化し、入力忘れを防止する仕組みを導入しました。
具体的な取り組み内容
毎日の必要度評価を日勤・夜勤それぞれの勤務終了時に完了させる運用とし、評価の正確性を確保しました。また、週1回の監査体制を構築し、評価の質を担保しています。
実現された成果
必要度加算の算定率が25%向上し、年間約3,000万円の増収となりました。また、評価の正確性が向上したことで、より適切な看護配置が可能となっています。
おしえてカンゴさん!よくある質問
診療報酬の算定に関して、現場の看護師から多く寄せられる質問について、具体的な対応方法を交えながらお答えします。これらの質問と回答は、実際の医療現場での経験に基づいています。
算定漏れの防止について
Q1:算定漏れを効果的に防ぐにはどうすればよいですか?
日々の記録時に算定要件を意識することが重要です。電子カルテのテンプレートに算定要件のチェック項目を組み込み、記録と同時に確認できる仕組みを作ります。また、夜勤帯の記録については、早出の看護師が確認し、必要に応じて記録の補完を行います。
Q2:特に夜勤帯での算定漏れが多いのですが、対策はありますか?
夜勤帯専用の簡易記録テンプレートを作成し、必須項目を中心とした記録ができるようにします。また、夜勤者の引き継ぎ時に記録内容の相互確認を行い、記録漏れを防ぎます。
記録の効率化について
Q3:記録に時間がかかりすぎて困っています。効率化のコツはありますか?
患者の状態に応じた記録テンプレートを活用することで、入力時間を短縮できます。また、ベッドサイドでタブレット端末を使用し、観察と同時に記録を行うことで、二重作業を防ぎます。
施設基準の管理
Q4:施設基準の管理で特に注意すべき点は何ですか?
看護職員の配置数と勤務時間の管理が最も重要です。月間の勤務表作成時に、必要人数を確保できているか確認し、急な欠勤にも対応できる余裕を持った配置計画を立てます。また、夜勤時間の管理も重要で、72時間以下となるよう調整します。
算定要件の確認
Q5:算定要件の変更をどのように把握すればよいですか?
診療報酬改定情報は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。また、関連する研修会への参加や、医療事務部門との定期的な情報共有の場を設けることで、最新の情報を入手できます。
教育・研修について
Q6:スタッフへの教育はどのように行うのが効果的ですか?
実際の記録例を用いたケーススタディ形式の研修が効果的です。月1回の部署会で、算定できなかった事例を検討し、proper記録の方法を共有します。新人看護師には、プリセプターによる個別指導の中で、記録の書き方を重点的に指導します。
多職種連携
Q7:他職種との連携で気をつけることはありますか?
医事課との週1回のカンファレンスで、算定状況の確認と課題の共有を行います。また、リハビリ部門や栄養部門との情報共有も重要で、各部門の記録が算定要件を満たしているか相互にチェックする体制を作ります。
システムトラブル対応
Q8:システムダウン時の対応はどうすればよいですか?
紙ベースの記録用紙を準備し、必要な項目を漏れなく記録できるようにします。システム復旧後、優先順位をつけて電子カルテへの入力を行い、算定に影響が出ないよう対応します。
監査対策について
Q9:指導監査への対応で重要なポイントは何ですか?
日々の記録を適切に保管し、算定の根拠となる書類をいつでも提示できる状態にしておきます。特に施設基準に関する書類は、人員配置や研修実績など、必要な証拠書類を整理して保管します。
収益改善について
Q10:収益改善のために特に注目すべき加算はありますか?
重症度、医療・看護必要度加算や看護補助体制加算は、収益への影響が大きい項目です。これらの加算を確実に算定できるよう、記録の質を高め、必要な人員配置を維持します。
まとめ
診療報酬の適切な算定は、医療機関の健全な運営と質の高い医療サービスの提供に不可欠です。本記事でご紹介した具体的な管理方法や改善事例を参考に、各施設の状況に合わせた取り組みを進めていただければと思います。
効果的な算定管理の実現には、現場スタッフの理解と協力が重要です。
より詳しい情報や、現場で活躍する看護師さんの声については、【はたらく看護師さん】の会員専用コンテンツでご覧いただけます。診療報酬に関する最新情報や、実践的な管理ツールのダウンロードなど、さらに充実した内容をご用意しています。
【はたらく看護師さん】
ぜひ【はたらく看護師さん】に会員登録いただき、みなさまの看護キャリアをさらに充実させてください