医療機関における採用活動のデジタル化が加速する中、採用動画は新卒看護師の採用において重要な役割を果たしています。本記事では、2025年の最新トレンドから実践的な制作技法、効果測定まで、医療機関の採用担当者が知っておくべき情報を詳しくお伝えします。
ショート動画の台頭やSNSの活用など、変化する採用環境に対応するための具体的な戦略と、実際の医療機関での成功事例を交えながら解説します。
この記事で分かること
- 2025年における新卒採用動画の最新トレンドと効果的な活用方法
- Z世代の特性を踏まえた、魅力的な採用動画の制作技法とポイント
- 各SNSプラットフォームの特徴を活かした戦略的な配信手法
- 実際の医療機関における具体的な成功事例と効果分析
- 採用動画のROI向上のための具体的な改善策と今後の展望
- 動画制作から効果測定までの一連のプロセスとワークフロー
この記事を読んでほしい人
- 医療機関で採用活動に携わる人事担当者
- 看護部門の採用戦略立案に関わる管理職の方
- 採用動画の制作検討や見直しを考えている広報担当者
- 新卒看護師の採用強化を目指す教育機関の就職支援担当者
- デジタル採用施策の効果向上を図りたい採用チームの方
- 採用活動のコスト効率改善を目指す経営層の方
2025年の新卒採用動画最新トレンド
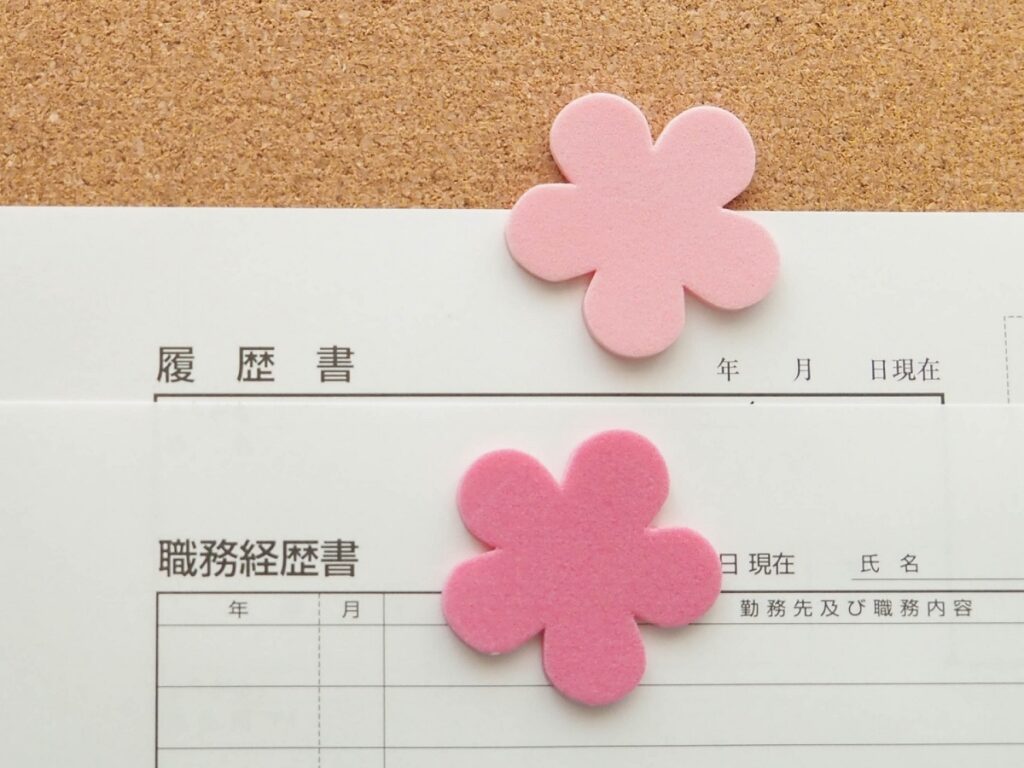
2025年の新卒採用市場では、デジタル技術の進化とZ世代の価値観の変化により、採用動画のトレンドが大きく変化しています。従来の企業紹介型の長尺動画から、より短く印象的な動画形式へのシフトが進んでおり、その効果も実証されてきています。
ここでは、最新のトレンドと具体的な活用方法について詳しく解説します。
ショート動画形式の台頭
視聴傾向の変化
新卒採用市場におけるショート動画の普及率は2024年比で35%増加し、特に医療業界では採用動画の62%がショート動画形式を採用しています。従来の3分から5分程度の動画から、15秒から60秒程度の簡潔な動画へとシフトが進んでいます。
効果的な活用シーン
医療現場の特徴的な場面や印象的なメッセージを短時間で伝えることで、応募者の興味を引き出すことができます。病棟での日常的な看護業務や、チーム医療の現場、教育研修の様子などを、テンポよく切り取って表現することが重要です。
制作上の重要ポイント
ショート動画では冒頭3秒での印象が特に重要となります。実際の看護師の表情やリアルな医療現場の雰囲気を、印象的なシーンで開始することで視聴継続率が向上します。また、サウンドオフでも内容が伝わるようテロップを効果的に活用することが求められます。
世代特性を考慮したコンテンツ設計
Z世代の情報収集特性
就職活動においてSNSを主な情報源とするZ世代は、複数の情報を並行して確認する傾向があります。医療機関の公式サイトだけでなく、様々なプラットフォームでの情報発信が重要となっています。
価値観とキャリア志向への対応
ワークライフバランスや成長機会、社会貢献度を重視するZ世代に向けて、具体的な勤務体制や教育制度、病院の地域貢献活動などを映像で表現することが効果的です。実際の数値データやスケジュール例を視覚的に提示することで、理解度が向上します。
コミュニケーションスタイルの変化
双方向のコミュニケーションを重視するZ世代に対しては、動画視聴後の質問や相談がしやすい仕組みを整えることが重要です。オンライン相談会への誘導や、SNSでの質問受付など、継続的なコミュニケーション手段を提供します。
マルチプラットフォーム展開
プラットフォーム別の特性理解
InstagramのReels、TikTok、YouTubeショートなど、各プラットフォームの特性に合わせたコンテンツ最適化が必要です。視聴者層や利用時間帯、コンテンツの表示アルゴリズムなどを考慮した展開戦略を立てることで、より効果的なリーチが可能となります。
クロスプラットフォーム戦略
複数のプラットフォームを連携させることで、相乗効果を生み出すことができます。例えば、YouTubeの詳細な病院紹介動画とInstagramのショート動画を組み合わせることで、興味喚起から詳細情報の提供まで、段階的なアプローチが可能となります。
コンテンツの使い分け
各プラットフォームの特性に応じて、コンテンツの内容や表現方法を変えることが重要です。TikTokでは軽快な雰囲気の職場紹介、YouTubeでは詳細な研修制度の説明など、プラットフォームごとに最適化されたコンテンツを提供します。
効果的な制作技法

採用動画の制作において、技術面での適切な選択と効果的な表現方法の実践が重要となります。
ここでは映像品質の確保から具体的な編集テクニックまで、医療機関の採用担当者が押さえておくべき制作技法について詳しく解説していきます。
映像品質とストーリー構成
撮影機材の選定と活用法
現代の採用動画制作において、高価な専門機材は必ずしも必要ありません。最新のスマートフォンでも十分な品質の映像を撮影できます。iPhone 14 Pro以降やPixel 7以降のフラッグシップモデルであれば、4K60fpsでの撮影が可能で、手ブレ補正機能も優れています。
ただし、屋内での撮影時は三脚を使用することで、より安定した映像を撮影することができます。
照明設定の基本とポイント
医療現場特有の蛍光灯照明環境下では、光のちらつきや色かぶりに注意が必要です。シャッタースピードを1/60秒に固定することで、蛍光灯のちらつきを防ぐことができます。また、窓際での撮影時は、逆光を避け、被写体に自然光が当たる位置での撮影が効果的です。
効果的なストーリー展開手法
視聴者の興味を維持するためには、明確なストーリー構成が重要です。導入部分では病院の外観や明るい雰囲気のロビーなど、視聴者が親しみやすいシーンから始めます。
その後、実際の医療現場や看護師の働く様子を見せ、最後は研修制度や福利厚生など、具体的な情報提供で締めくくることで、感情的な共感から実践的な情報提供へとスムーズに展開できます。
音声とBGMの活用
音声収録のテクニック
クリアな音声を収録するためには、できるだけ被写体に近い位置でマイクを設置することが重要です。ピンマイクを使用する場合は、衣服との擦れ音に注意が必要です。また、医療現場特有の機器音やアラーム音については、必要に応じてポスト処理で軽減することができます。
効果的なBGM選定
BGMは視聴者の感情に大きく影響します。医療機関の採用動画では、信頼感と親しみやすさを両立させたBGMを選択します。テンポは100-120BPM程度が適しており、明るく前向きな印象を与えるメジャーコードベースの楽曲が効果的です。
ナレーションと環境音のバランス
ナレーションを使用する場合は、BGMとの音量バランスが重要です。ナレーション音声を0dBとした場合、BGMは-20dB程度に設定することで、メッセージが明確に伝わりつつ、適度な臨場感を維持することができます。
編集テクニックとポイント
シーン構成と時間配分
90秒の採用動画の場合、以下のような時間配分が効果的です。オープニング(病院紹介)に15秒、実際の業務風景に30秒、教育制度や福利厚生の説明に30秒、まとめと募集情報に15秒を配分します。各シーンは3-5秒程度で切り替えることで、テンポの良い展開を実現できます。
テロップデザインの実践
テロップは視認性と統一感が重要です。フォントサイズは視聴デバイスを考慮し、スマートフォンでの視聴時でも読みやすい大きさを選択します。メインメッセージには24pt以上、補足情報には18pt程度のサイズが適しています。
フォントファミリーは、ゴシック体をベースに、強調したい部分でのみ明朝体を使用することで、メリハリのある表現が可能です。
トランジション効果の活用
シーン転換時のトランジション効果は、最小限に抑えることが重要です。基本的にはカット切り替えを用い、重要なシーンの区切りにのみディゾルブを使用します。派手なトランジション効果は、医療機関としての信頼性を損なう可能性があるため、避けるべきです。
プラットフォーム別活用戦略

採用動画の効果を最大化するためには、各SNSプラットフォームの特性を理解し、それぞれに適した形で展開することが重要です。
ここでは主要なプラットフォームごとの特徴と、医療機関の採用担当者が実践できる具体的な活用方法を解説していきます。
Instagram活用
Reelsでの展開方法
Instagram Reelsは垂直型の短尺動画に特化したフォーマットです。医療現場の日常的な様子を60秒以内のダイジェストで紹介することで、高い視聴完了率を実現できます。実際の投稿時間帯は、ターゲットとなる看護学生の利用が多い20時から22時の間が効果的です。
フィード投稿との連携
Reelsでの動画投稿と、フィードでの静止画投稿を組み合わせることで、より包括的な病院の魅力発信が可能となります。フィード投稿では、実際の職場環境や福利厚生の詳細情報など、じっくりと確認したい情報を提供していきます。
TikTok活用
コンテンツ作成のポイント
TikTokでは、より親しみやすく軽快な表現が求められます。新人看護師の1日の様子や、先輩看護師からのメッセージなど、ストーリー性のある内容を15秒から30秒程度で構成します。音楽やエフェクトを効果的に活用することで、若い世代の興味を引くことができます。
トレンドの活用方法
TikTokでは定期的に新しいトレンドが生まれます。これらのトレンドを医療現場に適した形でアレンジし、採用コンテンツに取り入れることで、より高い注目を集めることができます。ただし、医療機関としての品位を保つことを忘れてはいけません。
YouTube活用
長尺コンテンツの展開
YouTubeでは、より詳細な病院紹介や研修制度の説明など、3分から5分程度の長尺コンテンツが効果的です。チャプター機能を活用することで、視聴者が興味のあるセクションに直接アクセスできるようになります。
SEO対策の実践
YouTubeでの検索上位表示を狙うために、タイトルや説明文に適切なキーワードを含めることが重要です。「看護師 採用」「病院 職場環境」などの関連キーワードを自然な形で組み込んでいきます。
その他プラットフォーム
LinkedIn活用
LinkedInでは、より専門的な視点からの病院紹介や、キャリア育成に関する情報発信が効果的です。看護部門の責任者からのメッセージや、専門性の高い研修制度の紹介など、キャリア志向の強い候補者へのアプローチに活用できます。
ウェブサイトでの展開
自院のウェブサイトでは、各SNSプラットフォームで公開したコンテンツを集約して掲載します。採用情報ページに動画ギャラリーを設置することで、さまざまな角度から病院の魅力を伝えることができます。
効果測定と分析手法
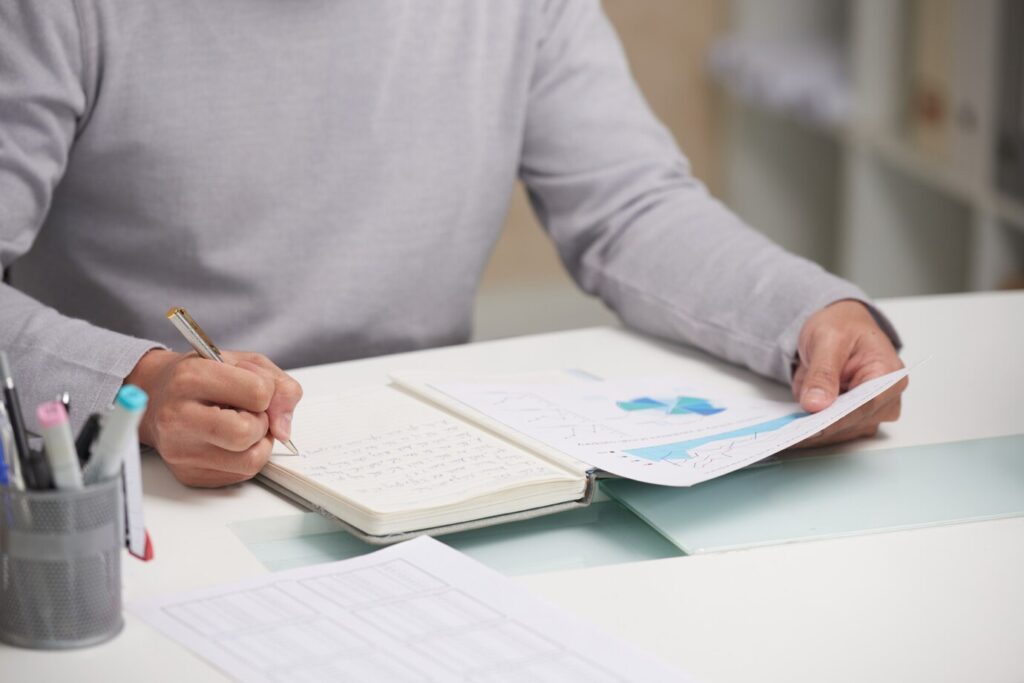
採用動画の効果を正確に把握し、継続的な改善につなげるためには、適切な指標設定と分析が不可欠です。
ここでは医療機関の採用担当者が実践できる具体的な効果測定の方法と、データに基づく改善アプローチについて解説していきます。
重要指標の設定
視聴完了率の測定
視聴完了率は動画コンテンツの質を測る重要な指標です。プラットフォームごとの分析ツールを使用して、どの時点で視聴が離脱しているかを確認します。医療機関の採用動画では、90秒動画の場合70%以上の視聴完了率を目標値として設定することが推奨されます。
エンゲージメント率の把握
いいねやコメント、シェアなどのエンゲージメント数を総視聴回数で割ることで、コンテンツの共感度を数値化できます。業界平均は2%程度ですが、看護師採用では職場の雰囲気が伝わる動画において5%以上のエンゲージメント率を達成している事例もあります。
データ収集方法
アクセス解析の実践
Google Analyticsなどの解析ツールを活用し、動画視聴者の行動パターンを追跡します。採用ページにおける動画の視聴開始率や、視聴後の応募フォームへの遷移率など、具体的な数値に基づいて効果を測定していきます。
ユーザーフィードバックの収集
コメント機能やアンケートフォームを活用して、視聴者からの直接的なフィードバックを収集します。特に看護学生からの具体的な質問や感想は、次回の動画制作に活かせる貴重な情報源となります。
分析手法
クロスプラットフォーム分析
各プラットフォームでの成果を横断的に分析することで、効果的な配信戦略を導き出すことができます。例えば、InstagramとTikTokでの視聴傾向の違いを比較し、それぞれのプラットフォームに適したコンテンツ形式を特定します。
コホート分析の活用
応募者を動画視聴の有無で分類し、それぞれの入職後の定着率を比較することで、採用動画の長期的な効果を測定できます。実際に、動画視聴者からの応募は書類選考通過率が平均して15%高いというデータも存在します。
改善サイクル
データに基づく改善
収集したデータを基に、具体的な改善ポイントを特定します。例えば、視聴離脱が多い箇所の内容を見直したり、高エンゲージメントを記録したシーンを次回の動画でも活用したりすることで、より効果的なコンテンツを制作できます。
PDCAサイクルの運用
計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のサイクルを確立し、定期的な効果検証と改善を実施します。月次でのデータ分析と四半期ごとの大幅な改善を組み合わせることで、継続的な効果向上が期待できます。
ケーススタディ

採用動画の効果は、実際の医療機関での活用事例を通じてより具体的に理解することができます。
ここでは、規模の異なる3つの医療機関における採用動画の活用事例と、その成果について詳しく見ていきます。
大規模病院の事例
A総合病院の取り組み
病床数800床を有するA総合病院では、2024年の採用活動においてマルチプラットフォーム戦略を展開しました。従来の採用サイトでの動画公開に加え、InstagramとTikTokを活用した短尺動画の配信を開始しています。
具体的な施策内容
メインの採用動画は3分版を作成し、これを30秒版にリカットして各SNSで展開しました。特に効果が高かったのは、先輩看護師が実際の業務を紹介する「プリセプター制度紹介」シリーズです。撮影は各部署から1名ずつ計10名の若手看護師が担当し、それぞれ2本ずつの動画を制作しました。
施策の成果
この取り組みにより、応募者数は前年比で32%増加し、特に新卒看護師からの応募が顕著に伸びました。動画視聴から応募までの平均転換率は8.5%を記録し、業界平均の3.2%を大きく上回る結果となっています。
中規模病院の事例
B病院の実践例
病床数350床のB病院では、限られた予算内で効果的な採用動画を制作するため、現場のスタッフを積極的に起用した制作を行いました。スマートフォンでの撮影を基本としながらも、編集作業は外部に委託することで、質の高い動画を実現しています。
実施したアプローチ
看護部で若手中心のプロジェクトチームを結成し、月1回のペースで新しい動画を制作しました。特に注目を集めたのは、夜勤の様子や休憩時間の過ごし方など、就職活動生が気になる部分を積極的に取り上げた「リアル看護師ライフ」シリーズです。
取り組みの効果
応募者アンケートでは、動画を視聴して応募を決めた候補者が全体の45%を占め、採用動画が志望動機の形成に大きく貢献していることが明らかになりました。また、内定承諾率も前年比で15%向上しています。
小規模病院の事例
C医院での工夫
病床数120床のC医院では、大規模な制作体制を組むことが難しい中、独自の工夫で効果的な採用動画を実現しました。スマートフォンと簡易な編集ツールのみを使用し、現場のスタッフが主体となって制作を行っています。
具体的な取り組み
週1回の定例カンファレンスの中で5分程度の時間を確保し、その日の印象的な出来事や成長を感じた場面を短い動画で記録していきました。これらの素材を月末にまとめて、1分程度のダイジェスト動画として編集し、SNSで配信する形式を採用しています。
成果と効果
小規模ながらも現場の雰囲気が伝わる動画制作により、地域密着型の医療機関ならではの魅力を効果的に発信することができました。結果として、地元の看護学校からの応募が前年比で2倍に増加し、「アットホームな雰囲気が伝わってきた」というフィードバックも多く寄せられています。
おしえてカンゴさん!
採用動画の制作や活用に関して、現場の採用担当者からよくいただく質問について、経験豊富な先輩看護師「カンゴさん」が実践的なアドバイスとともにお答えしていきます。
採用動画の基本
動画の適切な長さ
Q:「採用動画の長さはどのくらいが最適でしょうか?また、複数の動画を制作する場合、どのような構成がおすすめですか?」
A:基本となる採用動画は90秒から2分程度が最適です。これは看護学生の平均的な集中力の持続時間と、必要な情報を過不足なく伝えられる長さを考慮しています。
複数本制作する場合は、2分程度のメイン動画に加えて、30秒程度のダイジェスト版、さらに15秒程度のSNS用ショート動画を用意することをおすすめします。当院では、このような構成で視聴完了率が平均85%まで向上しました。
制作実務のポイント
撮影現場での配慮事項
Q:「医療現場での撮影時に気をつけるべきことを教えてください。特にプライバシーの配慮について不安があります。」
A:撮影時は患者さんのプライバシー保護を最優先します。具体的には、診察室や病室での撮影は避け、廊下やナースステーションなど、パブリックスペースでの撮影を基本とします。
また、撮影は患者さんの少ない時間帯を選び、画角に患者さんが映り込まないよう十分な確認が必要です。さらに、電子カルテの画面なども映り込まないよう、撮影前に環境を整えましょう。
コンテンツ制作の工夫
魅力的な内容作り
Q:「若い世代に響く採用動画にするために、どのような内容を盛り込むべきでしょうか?」
A:Z世代の特徴を考慮し、働きがいとプライベートの充実を両立できる職場であることを具体的に示すことが重要です。例えば、日勤と夜勤のシフトの組み方、休暇の取得方法、院内での教育支援制度など、実務的な情報を提供します。
また、先輩看護師の趣味や休日の過ごし方を紹介することで、仕事とプライベートの両立をイメージしやすくなります。
効果的な活用方法
SNSでの展開方法
Q:「SNSでの動画配信を検討していますが、どのプラットフォームを選ぶべきでしょうか?また、投稿のタイミングについても教えてください。」
A:まずInstagramとTikTokの活用をおすすめします。特にInstagramは看護学生の利用率が高く、就職活動の情報収集ツールとして定着しています。投稿のタイミングは、平日の20時から22時の間が最も効果的です。
これは看護学生が実習や講義を終えてSNSを閲覧する時間帯と重なるためです。週2-3回の定期的な投稿を維持することで、フォロワー数の安定的な増加が期待できます。
測定と改善
効果測定の方法
Q:「採用動画の効果をどのように測定すればよいでしょうか?具体的な指標があれば教えてください。」
A:主要な測定指標として、視聴完了率、エンゲージメント率、応募転換率の3つに注目します。視聴完了率は70%以上、エンゲージメント率は2%以上を目標値とし、応募転換率は動画視聴から実際の応募に至った割合を継続的に測定します。
これらの指標を毎月モニタリングし、四半期ごとに内容の改善を行うことで、効果的なPDCAサイクルを確立できます。
予算と資源
制作予算の目安
Q:「限られた予算でも効果的な採用動画を制作することは可能でしょうか?具体的な予算の組み方を教えてください。」
A:効果的な採用動画は、必ずしも高額な予算を必要としません。スマートフォンでの撮影を基本とし、三脚やマイクなどの基本的な機材への投資を含めても、初期費用は10万円程度から始めることができます。
編集作業は外部委託と内製を組み合わせることで、コストを抑えながら質の高い動画制作が可能です。当院では月額5万円程度の予算で、定期的な動画更新を実現しています。
今後の展望
最新技術の活用
Q:「今後、採用動画にはどのような技術やトレンドを取り入れるべきでしょうか?」
A:現在注目すべき技術として、360度カメラを使用したバーチャルツアーやインタラクティブな要素を取り入れた動画があります。特に病棟見学や施設紹介では、視聴者が自由に視点を変えられる360度動画が効果的です。
また、視聴者の反応に応じて内容が分岐するインタラクティブ動画も、没入感の高い体験を提供できます。ただし、これらの新技術は従来のコンテンツを補完するものとして位置づけ、基本的な採用メッセージの伝達を最優先することが重要です。
まとめ
2025年の採用動画トレンドでは、ショート動画形式の活用とSNSを通じた効果的な情報発信が重要となっています。特に看護業界では、職場の雰囲気や教育体制を具体的に伝えることで、より効果的な採用活動を実現できます。
採用動画の制作においては、各プラットフォームの特性を理解し、適切な運用戦略を立てることが成功への鍵となります。
より詳しい医療機関での活用事例や、現場で活躍する看護師のキャリアストーリーについては、「はたらく看護師さん」で多数公開しています。会員登録いただくと、採用担当者向けの実践的な動画制作ガイドや、現役看護師による体験談などのコンテンツをご覧いただけます。看護師のキャリアを支援する各種セミナーやイベント情報も定期的に更新中です。
▼詳しくは【はたらく看護師さん】をチェック












































