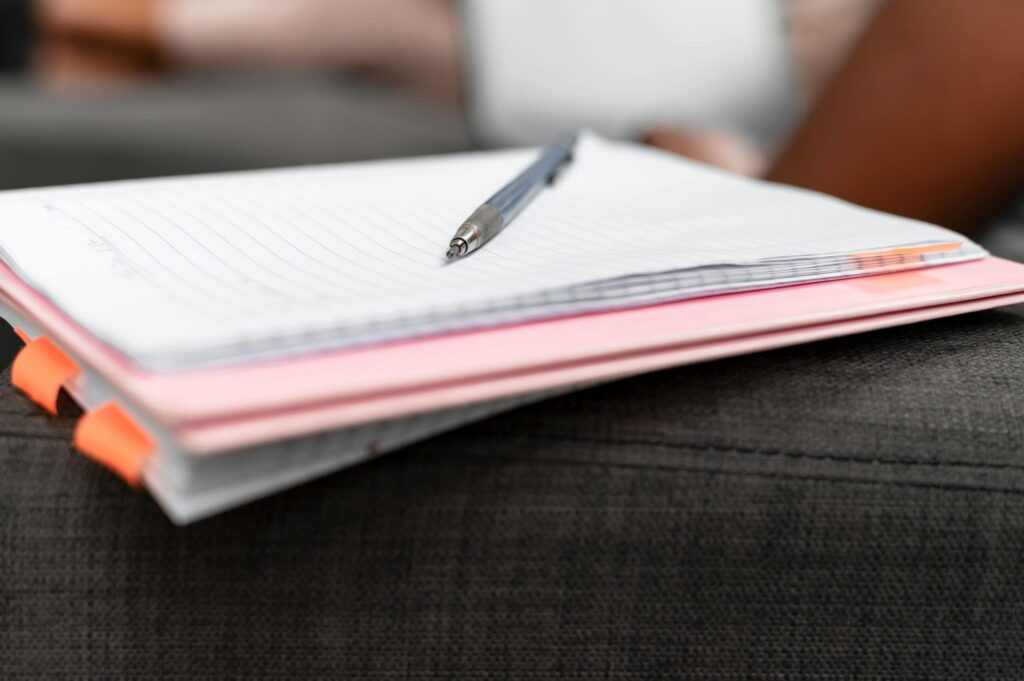助産師は女性の妊娠・出産をサポートする重要な専門職であり、その需要は年々変化しています。
本記事では、2025年最新の助産師求人状況と働き方について、詳細かつ具体的な情報をお届けします。転職を考えている方はもちろん、新卒の方や復職を検討している方にも役立つ情報が満載です。
現場で活躍するための選択肢を広げ、あなたのキャリアプランニングをサポートします。
この記事を読んでほしい人
- 助産師資格を取得したばかりで就職先を探している方
- 現在助産師として働いているが転職を考えている方
- 助産師を目指す看護学生の方
- ブランクがあり復職を検討している助産師の方
- ワークライフバランスを重視した働き方を探している助産師の方
- キャリアアップを目指している助産師の方
- 地方や都市部での就職機会について知りたい方
この記事で分かること
- 2025年現在の助産師求人市場の最新動向と傾向
- 勤務先別の具体的な雇用条件や給与水準の比較
- フルタイムからパートタイムまで多様な働き方のメリット・デメリット
- 助産師としてのキャリアパスと成長機会
- 地域別の就職状況と求人傾向の違い
- 効果的な就職活動のためのアドバイスとポイント
- 現役助産師の体験談と実際の就職事例
2025年の助産師求人市場の最新動向

助産師の求人市場は2025年、いくつかの重要な変化を見せています。少子化という社会課題がある一方で、高齢出産の増加や専門的なケアへのニーズが高まり、質の高い助産師への需要は依然として堅調です。
現在の市場動向を詳しく見ていきましょう。
全国的な求人状況と地域差
2025年現在、全国的に見ると助産師の求人数は安定しています。しかし、地域によって大きな差があることも事実です。都市部では比較的求人数が多い傾向にありますが、地方では貴重な専門職として高い需要があります。
特に地方の中核病院や唯一の産科施設となる病院では、助産師の確保に力を入れているケースが増えています。
都市部の求人状況
東京、大阪、名古屋などの大都市圏では、大学病院や総合病院を中心に常に一定数の求人が出ています。
競争は激しいものの、専門性を活かせる職場が多いのが特徴です。都市部では分娩件数の多い大規模な医療機関だけでなく、バースセンターや助産院など、働き方の選択肢も豊富です。
地方の求人状況
地方では産科医不足を背景に、助産師の役割がより重要になっています。地域の中核病院や唯一の産科施設では継続的に求人を出している場合が多く、移住支援制度などを設けている自治体もあります。
また、地域密着型の小規模な産科クリニックでも、地元出身者を優先的に採用する傾向があります。
施設別求人傾向と特徴
助産師が活躍できる場所は多岐にわたります。それぞれの施設タイプによって求人の特徴も異なりますので、詳しく見ていきましょう。
総合病院・大学病院の求人
総合病院や大学病院では、ハイリスク分娩への対応や新生児集中治療室(NICU)との連携など、高度な医療を提供できる助産師を求める傾向があります。新卒採用も積極的に行っており、教育体制が充実している施設が多いです。
一方で、夜勤や当直を含むシフト制での勤務が基本となります。
産科クリニックの求人
産科クリニックでは、より家庭的な雰囲気での出産をサポートできる助産師が求められています。院長との相性も採用の重要なポイントになり、小規模な職場ならではの人間関係の良さが特徴です。
また、正常分娩が中心となるため、助産師の専門性を発揮しやすい環境といえるでしょう。
助産院の求人
助産院では、自然分娩に対する深い理解と経験を持つ助産師が特に重宝されます。経験年数を重視する傾向があり、新卒での就職は難しい場合もあります。
一方で、助産師としての裁量権が最も大きく、自分のスタイルで出産をサポートできる魅力があります。
母子保健センター・保健所の求人
行政機関では、妊産婦支援や新生児訪問、育児相談などを担当する助産師の求人があります。臨床経験を活かしながら、地域の母子保健向上に貢献できる役割です。夜勤がなく、比較的規則正しい勤務形態が多いのが特徴です。
助産師の需給バランスと今後の展望
少子化という社会的背景がある一方で、出産の高齢化やハイリスク妊娠の増加により、専門的なケアを提供できる助産師の需要は高まっています。
また、産後ケアや女性のライフサイクルに応じた健康支援など、助産師の活躍の場は広がりつつあります。
専門性の高い助産師への需要
特に母乳育児支援や新生児蘇生法(NCPR)、産後うつのスクリーニングなど、専門的なスキルを持つ助産師への需要が増加しています。継続的な学習や認定資格の取得が、キャリアアップにつながる傾向が強まっています。
多様な勤務形態への対応
働き方改革の影響もあり、病院でもフレックスタイム制や短時間勤務など、柔軟な勤務形態を導入する施設が増えています。
また、オンコールでの対応や非常勤としての勤務など、自分のライフスタイルに合わせた働き方を選べる環境が整いつつあります。
勤務先別の雇用条件と給与水準

助産師として働く場所によって、雇用条件や給与水準は大きく異なります。
ここでは、主な勤務先別の具体的な条件を比較してみましょう。
総合病院・大学病院の雇用条件
総合病院や大学病院では、基本的に安定した雇用条件が提供されています。公立病院であれば公務員としての身分保障もあります。
給与水準と手当
総合病院や大学病院での助産師の平均年収は、経験年数にもよりますが約450万円〜650万円程度です。
基本給に加えて、夜勤手当(1回あたり10,000円〜15,000円程度)、当直手当、時間外手当、資格手当などが支給されることが一般的です。公立病院では賞与も充実しており、年間4〜5ヶ月分が支給される場合もあります。
勤務時間と休日
三交代制(日勤・準夜勤・深夜勤)または二交代制(日勤・夜勤)が一般的です。週休2日制を採用している施設が多く、年間休日は110日〜120日程度です。
有給休暇は初年度で10日前後、勤続年数に応じて増加します。産前産後休暇や育児休業の取得率も高い傾向にあります。
福利厚生
大規模病院では福利厚生が充実しており、住宅手当、扶養手当、通勤手当などの各種手当に加え、病院内保育所を設置している施設も増えています。また、退職金制度や健康保険、年金などの社会保障も整っています。
産科クリニックの雇用条件
産科クリニックは規模や経営方針によって条件が大きく異なりますが、一般的な傾向としては以下のようになります。
給与水準と手当
産科クリニックでの助産師の平均年収は約400万円〜550万円程度です。総合病院と比べると基本給はやや低めですが、分娩手当(1件あたり3,000円〜10,000円程度)が別途支給されるところも多く、分娩件数の多いクリニックでは総支給額が高くなることもあります。
また、オンコール対応に対する手当も設定されていることが一般的です。
勤務時間と休日
日勤と待機(オンコール)を組み合わせた勤務形態が多く、完全シフト制の施設もあります。
週休2日制を基本としていますが、小規模クリニックでは人員の都合で不規則になることもあります。年間休日は100日〜110日程度のところが多いようです。
福利厚生
クリニックの規模によって異なりますが、社会保険完備は基本的に整っています。住宅手当や家族手当などはクリニックによって差があります。小規模な職場ならではのアットホームな雰囲気や、院長との距離の近さもメリットといえるでしょう。
助産院の雇用条件
助産院での勤務は、雇用される形態と自ら開業する形態があります。ここでは雇用される場合の条件を見ていきます。
給与水準と手当
助産院で雇用される場合の平均年収は約350万円〜500万円程度と幅があります。
分娩介助を担当した場合の分娩手当が大きな割合を占め、1件あたり15,000円〜30,000円程度が支給されるところが多いです。基本給は比較的低めに設定されていることが多いのが特徴です。
勤務時間と休日
分娩の進行状況に合わせた不規則な勤務となることが多く、オンコール体制が基本です。小規模な助産院では少人数で回すため、休日が取りにくいこともありますが、逆に融通が利きやすい面もあります。
担当制を取っている場合は、担当妊婦の出産に合わせて勤務することになります。
福利厚生
小規模な施設が多いため、大規模病院のような充実した福利厚生は期待できないことが多いです。しかし、助産師としての専門性を最大限に発揮できる環境であり、やりがいを重視する方には魅力的な職場といえるでしょう。
母子保健センター・保健所の雇用条件
行政機関での勤務は、安定した条件が特徴です。
給与水準と手当
公務員として働く場合の平均年収は約450万円〜550万円程度です。夜勤がないため夜勤手当はありませんが、扶養手当や住居手当などの各種手当が支給されます。また、公務員なので賞与も安定しており、年間4.5ヶ月程度が一般的です。
勤務時間と休日
基本的に平日の日勤のみで、土日祝日は休みとなります。年間休日は120日以上と恵まれています。また、時間外勤務も少なく、ワークライフバランスを重視したい方に適した職場といえるでしょう。
福利厚生
公務員としての福利厚生が適用され、住居手当、扶養手当、通勤手当などが支給されます。また、育児休業や介護休暇などの制度も充実しており、長期的なキャリア形成がしやすい環境です。
多様な働き方とワークライフバランス

助産師として働く上で、ライフステージに合わせた働き方を選択できることは重要です。
ここでは、さまざまな働き方のメリット・デメリットを検討していきましょう。
フルタイム勤務のメリットとデメリット
フルタイムでの勤務は、経済的な安定や経験の蓄積というメリットがある一方で、プライベートとの両立に課題が生じることもあります。
メリット
フルタイム勤務の最大のメリットは、安定した収入が得られることです。また、多くの症例を経験できるため、スキルアップやキャリア形成にも有利です。職場内での信頼関係も築きやすく、責任ある立場を任されることも多くなります。
デメリット
夜勤や当直を含む不規則な勤務形態になることが多く、体力的な負担は小さくありません。また、育児や介護との両立が難しいケースもあります。
特に分娩の多い施設では、予定外の残業が発生することもあり、プライベートの予定が立てにくいこともあります。
パートタイム・非常勤での働き方
育児や介護など、ライフステージの変化に合わせてパートタイムや非常勤として働く選択肢もあります。
時短勤務の活用方法
子育て中の助産師にとって、時短勤務は大きな助けとなります。多くの病院では育児短時間勤務制度を設けており、子どもが小学校に入学するまで、あるいは小学校3年生までといった期間、1日6時間程度の勤務が可能です。
給与は比例して減少しますが、キャリアを継続しながら育児との両立が図れます。
週2〜3日勤務の実態
週に2〜3日のみ勤務するパートタイムの形態も、多くの施設で受け入れられています。特に経験豊富な助産師は、パートタイムであっても重宝される傾向にあります。
日勤のみの勤務や、特定の曜日だけの勤務など、自分のライフスタイルに合わせた働き方が選べるのが魅力です。
オンコール体制での勤務
産科クリニックや助産院では、オンコール体制を取っていることが多くあります。
オンコール勤務の実際
オンコール勤務では、自宅待機の状態から呼び出しがあった場合に勤務先に向かいます。分娩の進行状況に合わせた対応が求められるため、柔軟性と即応性が重要です。
また、担当制を取っている場合は、担当妊婦の分娩に合わせて待機することになります。
メリットとデメリット
オンコール体制のメリットは、常に職場にいる必要がなく、呼び出しがない時間は自由に使えることです。しかし、いつ呼び出しがあるか分からないため、心理的な負担や拘束感を感じることもあります。
また、深夜の呼び出しも多く、睡眠パターンが不規則になりやすいのがデメリットです。
複数施設での掛け持ち勤務
経験豊富な助産師の中には、複数の施設で勤務する「掛け持ち」のスタイルを選ぶ方もいます。
掛け持ち勤務の実態
例えば、平日は病院でパートタイム勤務、週末は助産院でのサポートなど、複数の職場を組み合わせて働くことで、収入の確保とさまざまな経験の獲得が可能になります。
特に独立志向の強い助産師にとっては、多様な現場での経験が将来の糧となります。
メリットとデメリット
複数の職場で働くことで、多様な症例や異なる環境での助産ケアを経験できるのが大きなメリットです。また、収入面でも安定させやすくなります。
一方で、それぞれの職場でのルールや方針の違いに適応する必要があり、スケジュール管理も複雑になるというデメリットもあります。
助産師のキャリアパスと専門性の向上

助産師として長く活躍するためには、自分自身のキャリアパスを描き、専門性を高めていくことが重要です。
ここでは、助産師が目指せるキャリアの方向性と、専門性を高めるための方法を紹介します。
臨床現場でのキャリアアップ
病院や産科クリニックなど、臨床現場での成長には様々な道があります。
管理職への道
臨床経験を積んだ後、主任助産師や看護師長などの管理職を目指すことができます。管理職は臨床業務に加えて、スタッフの教育やシフト管理、病棟運営などの役割も担うことになります。
リーダーシップや組織管理のスキルが求められますが、より広い視点で母子医療に貢献できるやりがいがあります。
専門・認定助産師の取得
日本助産評価機構が認定する「アドバンス助産師」や、日本看護協会が認定する「専門看護師」「認定看護師」の資格取得も、キャリアアップの重要な選択肢です。
専門分野としては、新生児集中ケア、母性看護、不妊症看護などがあり、それぞれの分野でより高度な知識と技術を身につけることができます。
教育・研究分野へのキャリア展開
臨床以外にも、教育や研究の分野で活躍する道もあります。
助産師教育機関での教員
助産師学校や看護大学の教員として、次世代の助産師を育成する道もあります。教員になるためには、大学院修士課程以上の学位が求められることが一般的です。
臨床経験を活かして実践的な教育を行うことで、助産師教育の質の向上に貢献できます。
研究者としての道
大学院で学び、研究者として助産学の発展に寄与する道もあります。エビデンスに基づいた助産ケアの確立や、新たな助産技術の開発など、学術的な側面から助産師の専門性を高める役割を担うことができます。
開業助産師・独立開業への道
自分自身の理想とする助産ケアを提供するため、開業助産師として独立する道もあります。
開業までのステップ
開業助産師になるためには、一般的に5年以上の臨床経験が推奨されています。その後、助産所開設に必要な手続きや設備投資、地域でのネットワーク構築などを経て開業します。
初期投資や経営面でのリスクはありますが、自分の理念に基づいた助産ケアを提供できる大きな魅力があります。
開業助産師の実態
開業助産師は分娩介助だけでなく、妊婦健診、産後ケア、母乳相談、育児相談など、妊娠・出産・育児の全過程をサポートします。
24時間対応が基本となるため、体力的な負担は大きいですが、妊産婦との深い信頼関係を築きながら、継続的なケアを提供できる喜びがあります。
海外での活躍機会
グローバル化が進む中、海外で助産師として活躍する選択肢も広がっています。
国際機関での活動
WHO(世界保健機関)やUNICEF(国連児童基金)、JICA(国際協力機構)などの国際機関では、開発途上国の母子保健向上のためのプロジェクトに携わる助産師を求めています。
語学力に加えて、異文化への適応力や国際的な視点が求められますが、グローバルな課題解決に貢献できるやりがいがあります。
海外の医療機関での就労
欧米諸国やオーストラリアなど、助産師の資格が相互認証されている国では、現地の医療機関で働くチャンスもあります。
各国の資格要件や就労ビザの取得など、クリアすべき課題はありますが、異なる医療システムや文化の中で助産ケアを提供する貴重な経験が得られます。
地域別の就職状況と求人傾向

日本全国で見ると、地域によって助産師の求人状況や働く環境には大きな違いがあります。
ここでは地域別の特徴を詳しく見ていきましょう。
都市部の就職事情
大都市圏では、大学病院や総合病院、専門産科病院など、様々な選択肢があります。
東京・大阪・名古屋の求人動向
三大都市圏では、大規模病院を中心に常に一定数の求人があります。特に東京では、大学病院や周産期センターなどの高度医療施設が多く、専門性の高い分野で活躍できる機会が豊富です。
しかし、競争も激しく、新卒者は採用試験の倍率が高いことも珍しくありません。
都市部のメリット・デメリット
都市部で働くメリットは、最先端の医療に触れられることや、教育・研修の機会が充実していることです。
また、複数の勤務先から選択できる自由度の高さもあります。一方、通勤時間が長くなりがちなことや、生活コストが高いというデメリットもあります。
地方での就職機会
地方では、助産師不足が深刻な地域も多く、貴重な専門職として重宝されます。
地方の求人特徴と待遇
地方の中核病院や地域の産科クリニックでは、助産師確保のために住居手当の上乗せや赴任手当の支給など、独自の優遇措置を設けているところも少なくありません。また、UIターン者向けの自治体の支援制度も活用できる場合があります。
地方で働くメリット・デメリット
地方で働くメリットは、地域に密着したケアを提供できることや、生活コストの低さ、通勤時間の短さなどが挙げられます。また、人間関係が濃密になりやすく、地域社会との繋がりを感じられることも魅力です。
一方、研修機会の減少や、緊急時のバックアップ体制が都市部より弱い場合があるというデメリットもあります。
地域医療構想と助産師の需要
地域によって周産期医療の体制は大きく異なります。
周産期医療の地域差
都市部では高度な周産期医療を提供する施設が多い一方、地方では産科医不足により分娩取扱施設が減少している地域もあります。
このような地域では、助産師外来や院内助産の整備を進めている施設も増えており、助産師の専門性を発揮できる環境が広がっています。
今後の展望と対策
少子化が進む中でも、分娩施設の集約化や助産師の役割拡大により、質の高い助産師への需要は続くと予想されます。
特に地域包括ケアシステムの中で、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を担う助産師の役割は、今後さらに重要性を増すでしょう。
効果的な就職活動のポイント

助産師として理想の職場を見つけるためには、効果的な就職活動が欠かせません。
ここでは、成功するための具体的なポイントを紹介します。
求人情報の探し方
求人情報を効率よく収集することが、選択肢を広げる第一歩です。
有効な求人サイトと情報源
助産師専門の求人サイトや、看護師向け求人サイトの助産師カテゴリーを活用しましょう。また、日本助産師会や日本看護協会のホームページ、各医療機関の採用ページも貴重な情報源です。地方自治体の医療従事者募集情報も見逃せません。
ネットワークの活用方法
助産師の世界は意外と狭く、人脈を通じて良い求人情報が得られることも少なくありません。同窓会や研修会、学会などで出会った先輩や同僚とのつながりを大切にしましょう。SNSの専門グループも情報収集に役立ちます。
履歴書・職務経歴書の書き方
応募書類は、あなたの第一印象を左右する重要なアイテムです。
助産師としてのスキルをアピールするコツ
単に経験年数や担当した分娩件数を記すだけでなく、得意とする分野(例:ハイリスク妊婦のケア、母乳育児支援など)や、取得している認定資格(NCPR、IBCLC、アドバンス助産師など)を具体的にアピールしましょう。
また、研修会や学会での発表経験があれば、それも貴重なアピールポイントになります。
志望動機の書き方
志望動機は、単に「スキルアップしたい」「家から近い」といった一般的な理由ではなく、その施設の特色や理念に触れながら、あなたがどのように貢献できるかを具体的に記すことが重要です。
事前の施設研究が、説得力のある志望動機につながります。
面接対策と準備
面接では、専門職としての姿勢と人間性の両方が評価されます。
よくある質問と回答例
「なぜ助産師になったのか」「あなたの助産観は」「困難な状況をどう乗り越えたか」「チーム医療についてどう考えるか」といった質問は頻出です。具体的なエピソードを交えながら、あなたの考えを簡潔に伝える準備をしておきましょう。
専門知識のアピール方法
面接では、最新の医療動向や助産ガイドラインに関する知識を示すことも重要です。たとえば「最近の周産期医療で注目している取り組み」や「エビデンスに基づいた助産ケア」について質問されることがあります。
日頃から専門誌や学会の情報をチェックし、自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。また、これまでの臨床経験で学んだことや、印象に残った症例についても、個人情報に配慮しながら具体的に語れるよう準備しておくと良いでしょう。
施設見学と情報収集
実際に働く環境を事前に知ることは、ミスマッチを防ぐために非常に重要です。
施設見学でチェックするポイント
施設見学の機会がある場合は、単に設備や環境を見るだけでなく、実際に働いているスタッフの様子や雰囲気にも注目しましょう。
特に、スタッフ同士のコミュニケーションの様子や、妊産婦さんへの対応は、その施設の文化や価値観を反映しています。また、助産ケアの方針(例:会陰切開の考え方、フリースタイル分娩への対応など)についても確認できるとベストです。
先輩助産師への質問例
施設見学や面接の際に、先輩助産師に質問できる機会があれば、「新人教育体制はどうなっているか」「勉強会や研修の機会はあるか」「夜勤体制や休日の取りやすさはどうか」「産後ケアや母乳外来などの外来業務の機会はあるか」といった実務的な質問が役立ちます。
これらの情報は、公式な求人情報だけではわからない、実際の職場環境を知る貴重な手がかりとなります。
助産師の就職事例とキャリアストーリー

実際の助産師のキャリアパスを見ることで、自分自身の将来像を描くヒントが得られます。
ここでは、様々な背景を持つ助産師の就職事例を紹介します。
新卒助産師の就職事例
看護学校や助産師学校を卒業したばかりの新卒助産師の事例を見てみましょう。
Aさんの場合:大学病院での新人教育
Aさん(25歳)は助産師学校を卒業後、大学病院の産科病棟に就職しました。就職先を選んだ理由は「ハイリスク妊娠や合併症のある妊婦さんのケアも学びたかった」というもの。
入職後は1年間のプリセプター制度のもとで指導を受け、段階的に分娩介助を担当。夜勤は3か月目から開始し、1年後には単独での分娩介助ができるようになりました。
教育体制が整っている大学病院は、基礎をしっかり身につけたい新卒者にとって良い選択肢となっています。
Bさんの場合:地元の産科クリニックへの就職
Bさん(24歳)は地元に戻って助産師として働きたいと考え、地元の産科クリニックに就職しました。クリニックは年間分娩数300件程度の中規模施設。
新卒でも積極的に採用しており、教育担当の先輩助産師がマンツーマンで指導してくれる体制が整っています。
「アットホームな雰囲気で、疑問点をすぐに相談できる環境」がBさんのやりがいになっています。また、地元で働くことで、プライベートの時間も充実させることができています。
経験者の転職事例
臨床経験を積んだ後に転職を選択した助産師の事例も参考になります。
Cさんの場合:総合病院からバースセンターへ
Cさん(32歳)は総合病院で7年間勤務した後、自然分娩を大切にしたいという思いから、バースセンターへ転職しました。
「医療介入を最小限にした出産をサポートしたい」という自身の助産観に合った職場を探した結果です。バースセンターでは、妊婦健診から分娩、産後ケアまで一貫して担当する機会が増え、「助産師としての専門性を発揮できる喜びを感じている」とのこと。
一方で、オンコール体制での勤務は体力的な負担も大きいそうです。
Dさんの場合:育児との両立を目指した就職先の変更
Dさん(35歳)は第1子出産後、育児と両立するために夜勤のない助産師外来専従のポジションに転職しました。
週4日の時短勤務で、主に妊婦健診や母乳外来、産後ケアを担当。「分娩介助の機会は減ったものの、妊産婦さんとじっくり向き合える時間が増えた」と新たなやりがいを見出しています。
子どもの成長に合わせて、将来的には夜勤も含めた勤務に戻ることも視野に入れているとのことです。
復職・ブランク明けの事例
出産や育児、他分野での就労などでブランクがあった後に復職した助産師の事例を紹介します。
Eさんの場合:10年のブランク後の復職
Eさん(45歳)は子育てのために10年間のブランクがありましたが、子どもの手が離れたタイミングで助産師として復職しました。
復職にあたっては、地域の医療機関が実施する「潜在助産師再就職支援プログラム」を活用。3か月間の研修を経て、最新の知識と技術を身につけた後、週3日のパートタイムから勤務を開始しました。
「最初は不安でしたが、経験を活かしながら新しい知識も吸収できる充実感があります」と語っています。
Fさんの場合:海外生活後の復職
Fさん(38歳)は配偶者の海外赴任に伴い5年間の海外生活を経験。帰国後、日本の助産師として復職しました。海外での経験を活かし、外国人妊産婦のサポートも担当。
「言葉や文化の壁を越えて助産ケアを提供する難しさと喜びを感じています」とのこと。復職前には日本助産師会の研修や、所属先の病院が提供する研修プログラムを活用し、日本の最新の周産期医療事情をキャッチアップしました。
キャリアチェンジの事例
助産師の資格や経験を活かして、新たな分野に挑戦した事例も見てみましょう。
Gさんの場合:臨床から教育現場へ
Gさん(42歳)は15年間の臨床経験を経て、助産師学校の教員にキャリアチェンジしました。大学院で助産学を学び直した後、教壇に立つ道を選択。
「臨床で得た知識と経験を次世代に伝えることで、助産師としての専門性を別の形で社会に還元できる喜びがあります」と話しています。
学生の指導にやりがいを感じる一方で、最新の臨床現場の感覚を失わないよう、定期的に臨床現場での研修も続けているそうです。
Hさんの場合:起業して産後ケア専門の施設を開業
Hさん(40歳)は病院勤務を経て、産後ケアに特化した小規模施設を開業しました。「病院では退院後のフォローが十分でないと感じることが多かった」という経験から、産後の母子をサポートする場所の必要性を痛感したのがきっかけです。
開業にあたっては、助成金や融資制度を活用し、経営や会計の知識も学び直したとのこと。「助産師としての専門性を活かしながら、地域の子育て支援の拠点となれることにやりがいを感じています」と語っています。
助産師求人に関する最新トレンドと動向

2025年現在、助産師の求人市場には様々な変化や新しい動きが見られます。
ここでは最新のトレンドや動向を紹介します。
リモートワークと遠隔保健指導
コロナ禍を経て、医療分野でもリモートワークや遠隔医療の導入が進みました。
オンライン母乳相談・育児相談の普及
助産師による母乳相談や育児相談をオンラインで提供するサービスが急速に普及しています。一部の医療機関では、退院後のフォローアップをオンラインで行うシステムを導入。
これに伴い、「オンライン相談可能な助産師」の求人も増加傾向にあります。デジタルツールを活用したコミュニケーションスキルが、新たな助産師のコンピテンシーとして注目されています。
在宅勤務の可能性
事務作業や記録の入力、オンライン相談対応などは、必ずしも施設内で行う必要がないことから、一部の業務を在宅で行う「ハイブリッド型勤務」の試みも始まっています。
特に育児中の助産師やシニア世代の助産師の活躍の場を広げる可能性があります。
地域包括ケアシステムにおける助産師の役割拡大
地域包括ケアシステムの中で、助産師の役割は従来の妊娠・出産支援から拡大しています。
子育て世代包括支援センターでの求人
各自治体が設置する「子育て世代包括支援センター」では、保健師と並んで助産師の専門性が重視されています。
妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を提供する役割を担う、地域密着型の求人が増加しています。公務員としての身分保障や、規則的な勤務形態が魅力とされています。
地域の産後ケア事業への参画
産後ケア事業が全国的に展開される中、助産師の専門性を活かした求人も増えています。自治体との連携による産後ケア施設や、訪問型の産後ケアサービスなど、多様な勤務形態での募集が見られます。
助産師の専門性を活かした新たな職域
助産師の活躍の場は、従来の産科領域を超えて広がりつつあります。
女性のライフサイクル全般をサポートする役割
思春期から更年期まで、女性のライフサイクル全般にわたる健康支援を担う助産師への需要が高まっています。企業の健康経営の一環として、女性社員向けの健康相談窓口を設置する動きも見られ、助産師の新たな職域として注目されています。
企業や教育機関との連携
健康教育や性教育の講師として学校や企業から依頼を受けるなど、教育的役割を担う機会も増えています。
また、妊活支援や女性の健康増進プログラムを提供する企業との連携も進んでおり、フリーランスとして活動する助産師の選択肢も広がっています。
多様な勤務形態と柔軟な働き方
働き方改革や価値観の多様化を背景に、助産師の勤務形態も多様化しています。
ジョブシェアリングの導入
1つのポジションを複数の助産師で分担する「ジョブシェアリング」の導入も始まっています。例えば、勤務時間や担当業務を複数の助産師で分け合うことで、それぞれのライフスタイルに合わせた働き方が可能になります。
特に子育て中やプライベートとの両立を重視する助産師にとって、魅力的な選択肢となっています。
シニア世代の活躍推進
経験豊富なシニア世代の助産師を積極的に採用する施設も増えています。若手への技術伝承や、妊産婦への精神的サポートなど、豊富な経験を活かせる役割で活躍するシニア助産師も少なくありません。
週2〜3日の短時間勤務や、夜勤免除など、体力面に配慮した勤務条件を提示する求人も見られます。
看護師からのQ&A「おしえてカンゴさん!」

助産師求人に関する皆さんからのよくある質問に、現役助産師のカンゴさんがお答えします。
Q1: 助産師の主な就職先はどこですか?
A1: 助産師の主な就職先は、総合病院、大学病院、地域の産科クリニック、助産院が中心です。近年では、自治体が運営する子育て世代包括支援センターや産後ケア施設なども増えています。
また、助産師学校などの教育機関や、研究機関で活躍する助産師もいますよ。自分の理想とする助産ケアやライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。
Q2: 新卒助産師でも助産院に就職することは可能ですか?
A2: 助産院では一般的に経験者を求める傾向が強いため、新卒での就職はやや難しい面があります。助産院では少人数で運営されていることが多く、即戦力となる助産師を求めているケースが多いからです。
ただし、中には新卒でも受け入れてくれる助産院もありますので、研修制度や教育体制が整っているかどうかを確認した上で応募してみるのも良いでしょう。
まずは病院などで基礎的な経験を積んでから助産院を目指すというキャリアパスが一般的です。
Q3: 助産師の給与水準は看護師と比べてどうですか?
A3: 一般的に助産師は看護師よりも給与水準が高い傾向にあります。これは専門性の高さや、夜勤・オンコール体制による不規則な勤務形態に対する評価とも言えます。
具体的には、助産師としての資格手当(月額1万円〜3万円程度)が別途支給されることが多いです。
また、分娩件数に応じた分娩手当が支給される施設も多く、分娩件数が多い施設では収入増につながります。ただし、施設によって給与体系は大きく異なりますので、求人情報では細かく確認することをお勧めします。
Q4: ブランクがある場合、復職するためにはどうすればよいですか?
A4: ブランクがあっても、復職のためのサポート体制は整ってきています。まず、日本助産師会や各都道府県の看護協会が実施している「潜在助産師再就職支援プログラム」を活用するのがおすすめです。
実技演習や最新知識の講習を受けることができます。また、病院によっては独自の復職支援プログラムを設けているところもあります。
最初は短時間勤務やパートタイムから始めて、徐々に慣れていくという方法も有効です。復職に不安がある場合は、地域の助産師会に相談してみるのも良いでしょう。
Q5: 育児中でも働きやすい助産師の職場はありますか?
A5: 育児中の助産師にとって働きやすい環境は確実に増えています。例えば、育児短時間勤務制度を導入している病院や、夜勤免除の制度がある施設は育児との両立がしやすいでしょう。
また、院内保育所を設置している総合病院や大学病院も増えています。助産師外来や母乳外来など、外来業務がメインの部署であれば、比較的規則的な勤務が可能です。産科クリニックでも、日勤のみの勤務形態を選べる場合があります。
求人に応募する際は、育児支援制度の有無や、実際の取得状況について確認することをおすすめします。
Q6: 助産師として開業するためには、どのような準備が必要ですか?
A6: 助産師としての開業には、一定の臨床経験(最低でも5年程度が望ましい)と行政手続きが必要です。
まず、「助産所開設届」を管轄の保健所に提出する必要があります。また、設備や安全基準に関する様々な要件を満たさなければなりません。経営面では、開業資金の準備や経営計画の策定、会計や税務の知識も必要です。
加えて、地域の産婦人科医療機関との連携体制を構築することも重要です。開業前には、日本助産師会の「開業助産師研修」を受講したり、すでに開業している先輩助産師の元で研修を受けることをおすすめします。
Q7: 海外で助産師として働くことは可能ですか?
A7: 海外で助産師として働くことは可能ですが、国によって資格要件や手続きが異なります。英語圏の国(アメリカ、イギリス、オーストラリアなど)では、現地の資格試験や審査を通過する必要があるケースが多いです。
また、途上国支援の国際機関(WHO、UNICEF、JICAなど)で働く場合は、一定の臨床経験に加えて語学力も求められます。まずは興味のある国の助産師資格制度を調査し、必要に応じて語学力の向上や追加の教育を受けることをおすすめします。
実際に渡航前に、短期の海外研修プログラムなどに参加してみるのも良い方法です。
まとめ
2025年の助産師求人市場は、少子化の中でも専門性の高い助産師への需要は堅調です。総合病院、産科クリニック、助産院、行政機関など多様な就職先があり、それぞれ給与体系や勤務条件が異なります。
フルタイムから時短勤務、オンコール体制まで多様な働き方が可能です。キャリアパスも臨床現場での成長、教育・研究分野への展開、開業など選択肢が豊富です。自分の価値観やライフステージに合わせた職場選びが重要です。
より詳しい情報や、現役看護師の体験談、奨学金情報など、看護師を目指す方々へのキャリアサポート情報は【ナースの森】でご覧いただけます。経験豊富な先輩看護師たちがあなたの悩みにお答えします。就職情報や最新の医療トレンド、継続的な学習サポートなど、看護師としてのキャリアをトータルでサポートいたします。
会員登録いただくと、以下のような特典もご利用いただけます。
- 看護学生向けの学習支援コンテンツ
- 現役看護師によるキャリア相談
- 奨学金情報の優先案内
- 実習お役立ち情報
- 就職活動サポート
▶︎【ナースの森】看護師のためのキャリア支援サイトはこちら