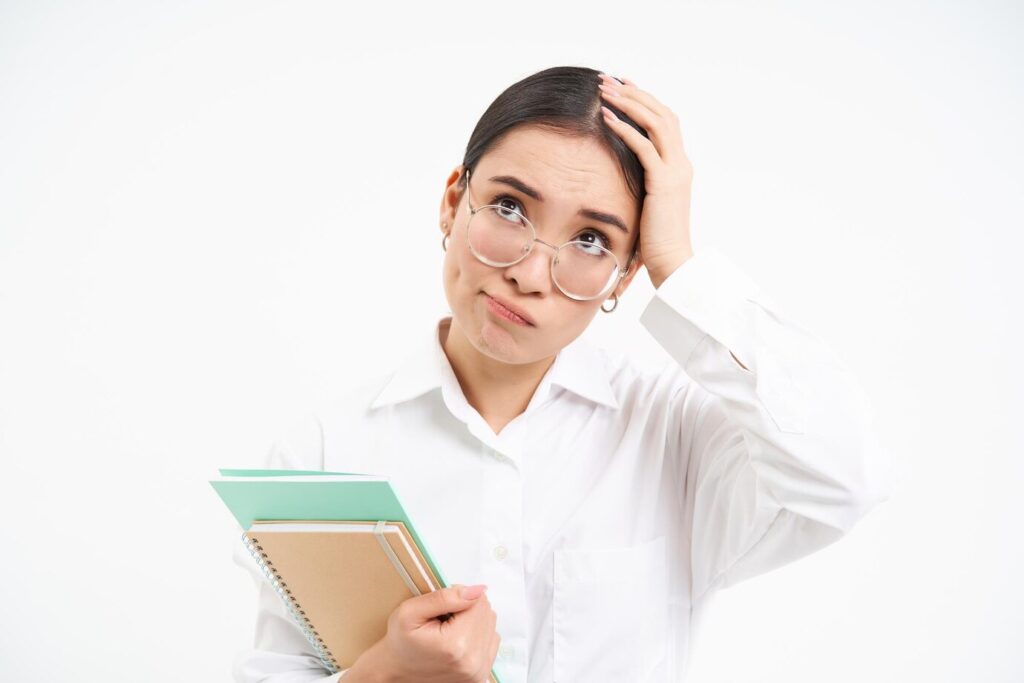「どの診療科が本当に大変なの?」「自分に合った診療科はどこ?」
看護師として働く中で、診療科選びは将来のキャリアを左右する重要な選択です。各診療科によって業務内容や負担度は大きく異なり、それぞれ特有のストレス要因が存在します。
本記事では、現役看護師の声をもとに、業務負担の大きい診療科をランキング形式で紹介。それぞれの特徴やストレス要因を詳しく解説するとともに、効果的な対処法や支援体制についても具体的に提案します。
この記事で分かること
- 看護師にとって業務負担が大きい診療科トップ10
- 各診療科特有のストレス要因と業務特性
- 診療科別の効果的なストレス対策と負担軽減方法
- 自分に合った診療科を選ぶためのポイント
- 職場環境改善のための具体的な取り組み事例
この記事を読んでほしい人
- 転職や配属先を検討中の看護師
- 現在の職場環境に疲弊を感じている看護師
- 新卒で診療科選択に悩んでいる看護師
- 職場のストレスマネジメントを改善したい看護師長・管理職
- 看護師のワークライフバランス向上を目指す医療機関
看護師が大変と感じる診療科ランキングTOP10

現役看護師300名へのアンケート調査と臨床現場の現場をもとに、業務負担が大きいと感じる医療科をランキング形式でご紹介します。
1.救急科(救命救急センター)
業務負担度:★★★★★
救急科は圧倒的に業務負担が大きい診療科として、ほとんどの看護師が一致して挙げる部門です。
24時間体制での緊急対応が基本となり、重症度・緊急度の高い患者さんへの迅速な対応が求められます。
生死に直結する判断の連続と突発的な患者急変への対応、時間的な切迫感と常に高い緊張状態、患者家族の精神的ケアの負担、夜勤・休日出勤の多さなど、複合的なストレス軽減が存在します。
このような環境では、アドレナリンが常に分泌されるような状態が続き、心身ともに大きな負担がかかります。
救急看護師のAさん(30代)は「救急車のサイレンが鳴るたびに全身に力が入る感覚が、常にアドレナリンが出ている状態です。1年目は毎日がのようでした。でも、命を救う最前線で働く充実感も大きいです」と語ります。
生命の危機に瀕した患者さんを救命できた時の達成感が、この診療科で働く看護師の大きなモチベーションとなっています。
2. 集中治療室(ICU/CCU)
業務負担度:★★★★☆
重症患者を24時間体制で管理するICU/CCUは、常に緊張感が漂う環境です。 生命維持装置の管理と観察、継続的な全身管理と集中的なケア、複雑な医療機器の操作などが日常的な業務となります。
さらに、厳密なバイタルサイン管理と急変時に迅速な対応も求められるため、高い知識と判断力が必要とされます。
高度な知識の継続的な学習も必要とされるため、判断面での負荷も軽減されません。
ICU看護師のBさん(40代)は「一人の患者さんに対して行っている観察項目が考えられますが、常に緊張感があります。でも、患者さんの回復が近づいて見られることにやりがいを感じます」と話しています。
3. 外科病棟
業務負担度:★★★★☆
手術後の患者ケアを担当する外科病棟は、身体の負担が特に大きい診療科です。 術前・術後の全身管理や頻繁な行為と観察、創部管理とドレーン管理など、専門的な知識と技術が求められます。
身体の負担に加えて、術後合併症の初期発見プレッシャーや複数患者の同時管理、術前・術後の詳細な観察項目の確認、緊急手術への対応など、精神的な負荷も大きいです。
特に急性期病院の外科病棟では、患者の入れ替わりに気をつけ、常に新しい患者の情報を把握する必要があります。
外科病棟看護師のCさん(20代)は「術後の観察項目が多く、複数の患者さんを同時に見られるために常に走り回っています。体力的にはきついですが、患者さんの回復過程を見られるのは魅力です」と進んでいます。
手術劇的な回復を目に直接できることが、外科病棟看護師のやりがいとなっています。
4. 小児科/NICU
業務負担度:★★★★☆
小さな命を預かる責任と独特のコミュニケーション方法が求められる診療科です。年齢に応じた細やかなケアや家族を含めた支援、成長発達に合わせた対応が基本となります。
また、感染症対策の徹底や正確な投薬量計算など、細心の注意を払う必要があるため、常に高い集中力が求められます。
障害の痛みや不安への対応、保護者との関係構築、小児特有の急変リスクへの対応など、精神的な負担は非常に大きいものがあります。
また、子どもの苦痛に対する感情移入による精神的な負担や、言葉にならない症状の正確な把握の難しさも特有の課題です。
小児科看護師のDさん(30代)は「子どもの言葉にならない時間を理解する難しさがあります。また、保護者の不安に寄り添うことも大切な仕事です。でも子どもの笑顔に救われることも多いです」と話します。
彼らの子どもの回復力や純粋な反応が、小児科看護の大きな魅力となっています。
5. 精神科
業務負担度:★★★☆☆
身体的負担よりも精神的な負荷が大きい独特の診療科です。患者との視点での関係構築や行動制限の判断と実施、自傷害リスクの評価など、高度なコミュニケーション能力と観察力が求められます。
また、服薬管理と副作用観察、リハビリテーション支援など、長期的な視点でのケアも重要な業務となります。
予測困難な患者の迅速な対応への対応や暴言・暴力リスクへの緊張感、継続観察による精神疲労など、心理的な負担が特徴的です。
精神科看護師のEさん(40代)は「患者さんとの関係を築くのに時間がかかり、心が折れそうになることもあります。でも、少しずつ回復していく姿と、この仕事をしていていいと思います」と語ります。
6. 産婦人科
業務負担度:★★★☆☆
命の誕生に立ち会う喜びがある有線、急変リスクと対面緊張も大きい診療科です。分娩の介助と経過観察、母子の健康管理、妊婦・産婦へのケア指導などが主な業務となります。
また、新生児の観察とケアや緊急帝王切開への対応なども含まれ、母子のケアを同時に行う必要があります。
分娩時の急変対応や母子両方のケアの複雑さ、医療事故のリスクの高さなど、責任重大が特徴的です。また、夜間出産の不規則勤務や家族の強い期待への対応なども、産科看護師特有のストレス軽減となっています。
産科看護師のFさん(30代)は「出産は喜びの瞬間ですが、一瞬で緊急事態に変わることも、常に緊張感があります。でも新しい命の誕生に立ち会えることは何にも代えがたい経験です」と話します。
人生の大きな節目である出産に寄り添える喜びが、この診療科で働く看護師のエネルギー源となっています。
7. 透析室
業務負担度:★★★☆☆
高度な専門知識と繊細な技術が求められる特殊な診療科です。透析機器の管理と操作、穿刺技術の習得、患者の長期フォローなどが主な業務となります。また、合併症の早期発見や水分・食事管理の指導なども重要な役割です。
穿刺の失敗への精神的プレッシャーや長期患者との関係性構築と維持、機器トラブル対応の緊張感など、特有のストレス軽減があります。また、計算・数値管理の正確さや慢性疾患患者の心理的サポートなど、専門性の高い対応も求められます。
透析室看護師のGさん(40代)は「穿刺の失敗は患者さんの痛みにつながるため、毎回緊張します。時々通院される患者さんとの関係構築は難しい面もありますが、信頼関係ができると非常にやりがいを感じます」と語っています。
8. 緩和ケア/終末期ケア
業務負担度:★★★☆☆
身体の負担よりも精神的・感情の負担が大きい特殊な診療科です。 痛み管理とケア、患者と家族の心理的サポート、残された時間の質の向上などが中心的な業務となります。
また、グリーフケア(悲嘆ケア)や多区域チームでの連携も重要な役割です。
死との向き合い方や感情移入による精神的消費、家族の悲しみへの共感疲労など、感情面での負荷が特徴的です。また、患者に対する苦痛無力感やバーンアウトのリスクも他科より高い傾向があります。
緩和ケア看護師のHさん(50代)は「患者さんの死に定期的に向き合うことで、自分自身の感情と向き合う難しさがあります。でも、最期までしっかりを持って生きられるよう支援できることにやりがいを感じています」と話します。
人生の最終段階に寄り添い、その人らしい最期を支えることができる貴重な役割を担っています。
9. 手術室
業務負担度:★★★☆☆
高度な専門性と集中力が求められる特殊な環境での勤務です。手術介助と器械出し、無菌操作の徹底、術中の患者管理などが主な業務です。
長時間の立ち仕事による身体的疲労や高い精神集中の持続、緊急手術への対応など、身体的・精神的負担が大きいです。また、ミス許容度の低さやチーム内の人間関係構築など、特有のストレス軽減もあります。
手術室看護師のIさん(30代)は「一日中立ちっぱなしで体力的にはきついですが、手術という特殊な環境で働く専門性の高さにやりがいを感じています。正確さと集中力が常に求められる環境です」と語ります。
手術を通して直接患者さんの回復に貢献できる喜びがあります。
10. 循環器内科
業務負担度:★★☆☆☆
急変リスクの高い患者を扱う緊張感のある診療科です。心電図モニター管理、急性期心疾患の観察、心臓カテーテル検査の介助などが主な業務となります。また、心不全患者のケアや精密な投薬管理も重要な役割です。
急変リスクへの定期注意やモニターの継続的な緊張、生活指導の難しさなどが特徴的なストレス課題です。
循環器内科看護師のJさん(40代)は「心臓は一瞬で止まることもあるので、常に緊張感があります。でも、専門性を高めることで患者さんの命を守るという責任とやりがいがあります」と話しています。
急性期から慢性期までずっと循環器疾患患者のケア、専門的な知識と技術を磨ける環境です。
診療科によるストレス要因の違い

1. 時間的プレッシャー型ストレス
時間との闘いが常にある環境では、判断の速さと正確さが同時に求められます。一分一秒が患者の予後を左右するケースも少なくありません。
該当する診療科: 救急科、手術室、ICU/CCU、産婦人科
救急科では患者の容態が急変する可能性が常にあり、迅速な判断と処置が求められます。「もう少し早く対応していれば」という思いが看護師の心理的負担になることも少なくありません。
特に複数の重症患者が同時に搬送されるような状況では、限られた人員と時間の中で優先順位を判断する責任も重くのしかかります。
手術室では、術中の急変対応や、厳密な時間管理、正確な器械出しなど、常に高い集中力と緊張感が求められます。長時間に及ぶ手術では、この緊張状態が持続することによる精神的疲労も蓄積します。
ICU/CCUでは生命維持装置の管理や微細な変化への対応など、常に警戒状態を維持する必要があり、この持続的な緊張が自律神経系に大きな負担をかけます。また、患者の急変リスクが高いため、一時も目を離せない状況が続くストレスも特徴的です。
産婦人科では、分娩の進行状況に応じた対応や、母子両方の命を守る責任があります。特に異常分娩への対応では、時間との勝負になることも多く、迅速かつ冷静な判断が求められます。
対策: 時間的プレッシャー型ストレスに対しては、チームでの明確な役割分担と情報共有が重要です。定期的な緊急時シミュレーションを行うことで、実際の場面での判断スピードと的確さを向上させることができます。
また、個人レベルでは呼吸法やマインドフルネスなどのストレス軽減テクニックを習得し、瞬時にリセットする能力を養うことが有効です。短時間でも質の高い休息を確保するために、チーム内での声かけや交代制の徹底も大切です。
2. 身体的負荷型ストレス
長時間の立ち仕事や患者の体位変換、移動介助など、身体的負担が大きい診療科では、腰痛などの職業病リスクも高まります。
該当する診療科: 外科病棟、整形外科、リハビリテーション科、手術室
外科病棟では術後患者の体位変換や移乗介助など、身体的負担の大きい業務が多くあります。特に腹部手術後の患者は自力での体動が制限されるため、看護師の介助負担が増大します。また、頻回な観察項目や処置も多く、常に動き回る必要があります。
整形外科では、ギプスや牽引装置を装着した患者の介助、重い医療器具の運搬など、特に腰や肩への負担が大きくなります。患者自身の可動域が制限されているケースが多いため、介助の際に無理な姿勢を取ることも少なくありません。
リハビリテーション科では患者の歩行訓練や日常生活動作の援助など、看護師自身が身体を使ってサポートする場面が多くあります。特に片麻痺などの患者支持には大きな力が必要となる場合もあります。
手術室では長時間の立ち仕事に加え、患者の体位変換や移動、重い機材の準備や片付けなど、身体的負担が大きい業務が続きます。また、無影灯の下での緊張した姿勢の維持も、頸部や肩のこりにつながります。
対策: 身体的負荷型ストレスに対しては、正しい姿勢と動作の習得が基本となります。ボディメカニクスを意識した介助方法の練習や、リフトなどの介助機器の積極的活用が効果的です。
また、こまめなストレッチや筋力トレーニングによる自己ケアも重要です。職場環境面では、十分な人員配置と応援体制の確立、休憩時間の確実な確保など、組織的な対策も必要となります。定期的な腰痛予防講座の開催なども効果的な取り組みです。
3. 感情労働型ストレス
患者や家族の感情に寄り添い、自分の感情をコントロールしながら仕事をする「感情労働」の負担が大きい診療科では、共感疲労やバーンアウトのリスクが高まります。
該当する診療科: 緩和ケア、小児科、精神科、がん病棟
緩和ケアでは終末期患者とその家族の心理的ケアが重要な業務となります。死と向き合う患者の苦しみや不安に寄り添いながら、専門的なケアを提供し続けることは大きな感情的負担となります。
また、看護師自身も喪失体験を繰り返すことになり、グリーフ(悲嘆)が蓄積することもあります。
小児科では子どもの痛みや恐怖に対する共感性が強く求められます。特に侵襲的な処置を行う際には、子どもの泣き声や恐怖の表情に直面しながらも、冷静に処置を完遂する必要があります。
また、不安を抱える保護者への対応も感情労働の一面を持ちます。
精神科では患者との適切な距離感を保ちながら、信頼関係を構築する難しさがあります。時に患者から攻撃的な言動を受けることもありますが、それに感情的に反応せず専門的な対応を続ける必要があります。
また、自殺リスクのある患者への継続的な関わりは大きな精神的負担となります。
がん病棟では、長期にわたる闘病生活を送る患者の苦痛や不安、怒りなど様々な感情に向き合います。治療の副作用による苦痛の緩和や、再発・転移という厳しい現実を受け止める患者・家族のサポートなど、感情面での支援が大きな割合を占めます。
対策: 感情労働型ストレスに対しては、感情を適切に表現し処理する場の確保が重要です。定期的なデブリーフィング(振り返り)セッションやピアサポートグループの活用が効果的です。
また、セルフコンパッション(自己への思いやり)の実践や、仕事と私生活の境界を明確にする習慣も大切です。組織レベルでは、専門的なスーパービジョン体制の整備や、定期的なメンタルヘルスチェックと早期介入のシステム構築が求められます。
4. 専門性・責任型ストレス
高度な専門知識と技術が求められる診療科では、常に最新の知識をアップデートし続ける必要があり、また小さなミスも許されない環境によるプレッシャーがあります。
該当する診療科: ICU/CCU、NICU、透析室、手術室
ICU/CCUでは複雑な生命維持装置の管理や高度な薬剤投与の調整など、専門的知識と技術が必要とされます。また、重症患者の微細な変化を察知し適切に対応する能力も求められ、常に高度な判断を下すプレッシャーがあります。
NICUでは未熟児や重症新生児のケアに特化した専門知識が必要です。体格の小さな患者への繊細な処置技術や、成長発達を促す専門的ケアの習得が求められます。また、家族支援においても専門的なアプローチが必要となります。
透析室では血液浄化療法に関する専門知識と技術が求められます。特に穿刺技術は高度な熟練を要し、失敗すれば患者に直接的な痛みを与えるプレッシャーがあります。また、透析中の急変対応や合併症の早期発見なども重要な責任となります。
手術室では手術の種類に応じた専門的な器械出しや患者管理が必要です。無菌操作の徹底や正確なカウント、チーム内での的確な連携など、高度な専門性と集中力が求められます。また、医療安全上の厳格なプロトコル遵守も重要な責任です。
対策: 専門性・責任型ストレスに対しては、継続的な学習機会の確保と段階的なスキルアップシステムの構築が効果的です。メンター制度やプリセプター制度の活用により、経験者から学ぶ環境を整えることも重要です。
また、チーム内でのダブルチェック体制の徹底や、ミスを個人の責任ではなくシステムの問題として捉える安全文化の醸成も必要です。定期的なスキルアップ研修や認定資格取得の支援など、組織的なキャリア開発支援も効果的な対策となります。
診療科横断的なストレス要因
上記の4つの分類に加え、多くの診療科に共通して見られるストレス要因もあります。これらは診療科の特性に関わらず、看護職全体に影響を与える要素です。
人間関係とコミュニケーション
チーム医療が基本となる現代の医療現場では、医師、他の看護師、多職種との良好な関係構築が重要となります。特に医師とのコミュニケーションギャップや、看護チーム内の人間関係の難しさは、どの診療科でも大きなストレス要因となる可能性があります。
また、患者や家族とのコミュニケーションにおいても、期待と現実のギャップから生じる摩擦や、限られた時間の中での信頼関係構築の難しさがあります。特に高齢化社会において、認知症患者や多様なバックグラウンドを持つ患者との意思疎通の困難さも増加しています。
ワークライフバランスの課題
24時間体制の医療を支える看護師にとって、不規則な勤務シフトやワークライフバランスの維持は共通の課題です。特に夜勤を含む交代制勤務は、サーカディアンリズム(体内時計)の乱れを引き起こし、身体的・精神的健康に影響を与えます。
また、人員不足による残業や休日出勤も、どの診療科でも起こり得る問題です。
さらに、育児や介護などのライフイベントと仕事の両立も大きな課題となります。特に女性が多い職業であることから、出産・子育てと看護師としてのキャリア継続の両立は重要なテーマとなっています。
業務量と責任の増大
医療の高度化・複雑化に伴い、看護師に求められる業務内容も拡大し続けています。医療機器の操作、詳細な記録、多様な医療処置に加え、患者教育や退院支援、多職種連携のコーディネーションなど、業務範囲は広がる一方です。
また、医療安全意識の高まりとともに、インシデントやアクシデント防止への責任も増大しています。ミスが許されない環境での継続的な緊張感は、どの診療科においても大きな精神的負担となります。
自分に合った診療科を選ぶためのポイント

自己分析:あなたの強みと弱み
まずは自分自身の特性を客観的に分析しましょう。自分の得意なこと、苦手なこと、価値観などを理解することが、適切な診療科選びの第一歩となります。
自分のスキルと適性を見極める
看護師としての自分の強みは何でしょうか。例えば、細かい作業が得意な方は手術室や集中治療室などの精密なケアが求められる環境に向いているかもしれません。コミュニケーション能力が高い方は、患者や家族との関わりが多い小児科や精神科などが適しているでしょう。逆に、苦手とする業務が多い診療科は、日々のストレスが蓄積しやすい環境となりがちです。
自分自身の性格特性も重要な判断材料です。例えば、臨機応変な対応が得意で変化を楽しめる方は救急科のような予測不能な環境でも活躍できるでしょう。一方、計画的に業務を進めることを好む方は、定時性のある外来や透析室などの環境が合っているかもしれません。
ストレス耐性を考慮する
各診療科特有のストレス要因に対する自分の耐性も重要な判断ポイントです。時間的プレッシャーに弱い方が救急科を選ぶと日々の業務が大きな負担となる可能性があります。
同様に、感情移入しやすい方が終末期ケアの多い環境で働く場合は、感情労働のストレスに対する対処法を持っておく必要があります。
自分がストレスを感じやすい状況を理解し、それが少ない環境を選ぶか、または対処法を身につけた上で挑戦するかを検討しましょう。どのような場面で燃え尽きそうになるか、どのような状況でやりがいを感じるかを振り返ることも有効です。
価値観とやりがい:何があなたを満たすか
診療科によって得られるやりがいや達成感は異なります。自分にとって「仕事の意味」は何かを考えましょう。長く働き続けるためには、自分の価値観と合った環境で働くことが重要です。
診療科別のやりがいを考える
各診療科には、それぞれ特有のやりがいがあります。救急科やICUでは危機的状況からの回復を支えることのダイナミックさと達成感があります。一方、リハビリテーション科では患者さんの長期的な回復過程を見守ることができる喜びがあります。
小児科では子どもの成長発達を支える楽しさ、精神科では人間の心と向き合う深さ、緩和ケアでは人生の最終段階を尊厳を持って支える意義深さがあります。産科では新しい命の誕生に立ち会うという特別な経験ができます。
自分がどのようなケアに最もやりがいを感じるのか、深く考えてみましょう。患者さんの急性期の回復を支えることに喜びを感じるのか、それとも長期的な関係を築きながら慢性疾患と付き合う患者さんを支えることに充実感を見出すのか。
自分の価値観に合ったやりがいが得られる環境を選ぶことで、ストレスへの耐性も高まります。
自分のキャリアビジョンとの整合性
将来どのような看護師になりたいのか、そのビジョンと診療科選択の整合性も考慮すべきポイントです。専門看護師や認定看護師などの資格取得を目指すなら、その分野の臨床経験が積める診療科を選ぶことが重要です。
また、将来的に看護管理者を目指すのであれば、様々な診療科での経験を積むことも一つの選択肢となります。教育担当を志望するなら、教育システムが充実した環境を選ぶことも考慮すべきでしょう。
5年後、10年後の自分をイメージし、そこに到達するためのステップとして今の診療科選びを位置づけてみましょう。短期的な大変さだけでなく、長期的なキャリア形成の視点も大切です。
ライフスタイルとの調和:ワークライフバランスを考える
仕事と私生活のバランスも重要な選択ポイントです。自分のライフスタイルや家庭環境に合った勤務形態の診療科を選ぶことで、長く健康に働き続けることができます。
診療科別の勤務特性を理解する
診療科によって勤務形態や労働負荷は大きく異なります。救急科やICU、産科などは24時間体制での対応が必要なため、夜勤や不規則な勤務が多くなる傾向があります。一方、外来や透析室、検診センターなどは比較的規則的な勤務形態となることが多いです。
また、手術室は基本的に日勤中心ですが、緊急手術の可能性もあります。訪問看護では日勤がメインですが、オンコール対応が必要なこともあります。このような勤務特性と自分のライフスタイルとの相性を考慮することが大切です。
小さなお子さんがいる方や家族の介護をしている方は、勤務時間が予測しやすい環境の方が両立しやすいかもしれません。一方、学業と両立したい方はパートタイムで働きやすい診療科を選ぶことも一案です。
身体的・精神的健康との兼ね合い
自分の健康状態と診療科の業務負荷の関係も考慮すべきポイントです。腰痛持ちの方が持ち上げ動作の多い病棟を選ぶと、症状が悪化する可能性があります。また、睡眠障害がある方にとって、交代制勤務の多い環境は大きな負担となるでしょう。
精神的な健康面では、高ストレス環境と自分のメンタルヘルス状態の相性も重要です。自分のストレス管理能力と診療科のストレス要因を照らし合わせ、持続可能な選択をすることが大切です。
健康であることが良質なケアを提供するための基盤です。自分の心身を守りながら働ける環境を選ぶことは、長期的なキャリア形成においても重要な要素となります。
体験からの学び:実習やローテーションを活かす
理論上の想像と実際の経験には、しばしば大きなギャップがあります。可能であれば、実際に複数の診療科を経験してから最終的な選択をすることをお勧めします。
実際の経験を通して判断する
新卒者研修やローテーション研修は、様々な診療科を体験できる貴重な機会です。各診療科の実際の業務内容、雰囲気、人間関係などを肌で感じることで、自分との相性を判断する材料が得られます。
この経験を積極的に活用し、「想像していた」診療科と「実際に経験した」診療科のギャップを認識しましょう。
また、学生時代の臨地実習の経験も参考になります。どの診療科実習が最も充実していたか、どのような患者さんとの関わりに喜びを感じたかを振り返ってみましょう。
先輩看護師の経験から学ぶ
実際に様々な診療科で働いた経験を持つ先輩看護師の話を聞くことも、大きな参考になります。各診療科の実情や、キャリアを通じての学び、診療科選択の決め手となった要素などを聞くことで、自分では気づかなかった視点を得ることができます。
可能であれば、複数の病院や診療科で働いた経験を持つ看護師の話を聞き比べることも有益です。同じ診療科でも、病院の規模や地域性、病棟の特性によって業務内容や環境は大きく異なります。幅広い情報を収集することで、より適切な判断ができるでしょう。
選択肢を柔軟に考える:キャリアは一本道ではない
看護師のキャリアは一直線ではなく、様々な選択肢と可能性に満ちています。診療科選びも「一度決めたら一生」というものではありません。キャリアステージや人生の状況に応じて、柔軟に選択を変えていく視点も大切です。
複数の診療科経験の価値を理解する
一つの診療科に特化することも、複数の診療科を経験することも、どちらも価値のあるキャリアパスです。複数の診療科を経験することで、幅広い視野と応用力が身につき、総合的な判断力が向上します。特に将来、看護管理職や教育担当を目指す方には有利かもしれません。
一方、一つの診療科で専門性を高めることで、その分野のエキスパートとして認められ、専門看護師や認定看護師などの道も開けます。どちらの道を選ぶにしても、学び続ける姿勢が最も重要です。
ライフステージに合わせた選択
人生のステージによって、仕事に求めるものや優先順位は変化します。子育て中は規則的な勤務の診療科を選び、子どもが独立した後に本来興味のある分野にチャレンジするという選択肢もあります。
また、体力のあるうちに身体的負荷の大きい診療科を経験し、年齢を重ねるごとに経験を活かせる指導的立場や専門的分野に移行するというキャリアプランも考えられます。
人生の各段階で自分が大切にしたいものを明確にし、それに合った環境を選ぶ柔軟さを持つことで、看護師としての長いキャリアを充実させることができるでしょう。
職場環境改善のための取り組み事例

事例1:多職種連携による業務効率化(C大学病院 小児科病棟)
小児科は特有の業務負担が大きい診療科ですが、C大学病院では多職種連携による効率化を進めることで看護師の負担軽減に成功しました。
小児患者への説明や処置の介助に専門的に関わる「チャイルド・ライフ・スペシャリスト」を導入し、子どもの不安軽減と処置への協力を促す役割を担ってもらうことで、看護師は医療処置に集中できるようになりました。
また、薬剤師による病棟常駐体制を強化し、服薬指導や薬剤管理の一部を担当してもらうことで、看護師の薬剤関連業務が30%削減されました。
さらに、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士などの多職種カンファレンスを週1回定例化することで、情報共有の質が向上し、退院支援がスムーズになりました。これにより、予定入院の受け入れ準備時間が短縮され、看護師の時間外労働が平均で週2時間減少しています。
事例2:ICT活用による情報共有と記録業務の効率化(D総合病院 全病棟)
看護記録や情報共有に関わる間接業務は、看護師の業務時間の大きな部分を占めています。D総合病院では、ICT(情報通信技術)を積極的に活用することで、これらの業務効率化に取り組みました。
まず、音声入力システムを導入し、看護記録の入力時間を短縮しました。看護師はヘッドセットを装着しながら、患者ケアの観察内容や実施した処置を音声で記録することができるようになり、従来のキーボード入力と比較して記録時間が40%削減されました。
また、ベッドサイド端末を活用したバイタルサイン自動記録システムを導入し、測定値の転記ミスを防止するとともに、データ入力時間を短縮しました。
さらに、タブレット端末を活用した申し送りシステムにより、勤務交代時の引き継ぎ時間が平均15分短縮され、患者ケアに集中できる時間が増加しました。
この結果、看護師の間接業務時間が全体で25%削減され、直接ケアに使える時間が増加したことで、患者満足度の向上にもつながっています。また、時間外労働の減少により、看護師の離職率が前年比15%減少するという効果も見られました。
事例3:メンタルヘルスケア体制の強化(E地域医療センター 全部署)
E地域医療センターでは、看護師のメンタルヘルスケアを組織的に支援する体制を構築し、職場環境の改善に取り組みました。
全職員を対象としたストレスチェックの実施に加え、結果に基づく部署別の改善計画立案と実施を義務付けました。特にストレス度が高いと判断された部署には、産業医と精神保健専門家による職場環境改善コンサルテーションを提供し、具体的な改善策の実施を支援しています。
また、24時間利用可能な匿名電話相談サービスを導入し、仕事上の悩みや個人的な問題について専門家に相談できる環境を整えました。さらに、定期的なリラクゼーション研修やストレスマネジメント講座を開催し、セルフケアスキルの向上を図っています。
これらの取り組みにより、看護師のメンタル不調による休職者が50%減少し、職場満足度調査でのスコアが23%向上しました。また、患者からのクレーム件数も減少しており、看護師のメンタルヘルス向上が医療サービスの質向上にも寄与していることが示されています。
看護師さんからのQ&A「おしえてカンゴさん!」
看護師の皆さんが日常的に抱える疑問や悩みに、長年の臨床経験を持つカンゴさんがアドバイスします。診療科選びやストレス対策、キャリア形成など、実践的な質問と回答をお届けします。

Q1:診療科を選ぶ際、業務負担よりもやりがいを優先すべきでしょうか?
カンゴさんの回答: 「これは多くの看護師が悩むポイントですね。結論からいうと、『やりがい』と『自分の適性・生活スタイル』のバランスが大切です。どんなに業務負担が大きくても、その分野に強い情熱があれば乗り越えられることも多いです。
しかし、長く看護師として働き続けるためには、自分の心身の健康や家庭との両立も考慮する必要があります。
まずは短期的なローテーションや研修で複数の診療科を経験してみることをお勧めします。実際に働いてみると、イメージと現実のギャップに気づくことも多いものです。また、同じ診療科でも病院によって業務環境は大きく異なります。
人間関係や組織文化、サポート体制なども重要な選択要素になるでしょう。
理想的なのは、自分の価値観に合ったやりがいを見つけつつ、自分のライフスタイルと両立できる職場環境を選ぶことです。無理に高負担の環境で燃え尽きるよりも、持続可能な形で看護に携わり続けられる選択をしてほしいと思います。」
Q2:業務量の多さで常に残業していますが、どうすれば効率よく仕事を終わらせられますか?
カンゴさんの回答: 「業務効率化は多くの看護師が直面する課題ですね。まず、自分の業務の流れを客観的に見直してみましょう。『何に時間がかかっているのか』を1日記録してみると、意外な発見があるものです。
具体的な効率化のコツとしては、まず『タスクのグルーピング』が有効です。例えば、同じ時間帯にまとめて実施できる処置はグループ化する、記録は患者ケアの直後にすぐ行うなどの工夫が役立ちます。
また、業務の優先順位付けも重要です。緊急性と重要性のマトリックスで考え、本当に必要なタスクから取り組むようにしましょう。
チームでの協力体制も大切です。忙しい時間帯の応援ルールを明確にしたり、得意分野で助け合う文化を作ったりすることで、全体の業務効率が向上します。また、遠慮せずに『手伝ってほしい』と声をかける勇気も必要です。
そして、病棟全体の業務改善にも目を向けてみましょう。不要な業務や重複作業がないか、カンファレンスなどで提案することも大切です。小さな改善の積み重ねが、大きな変化につながります。何より、一人で抱え込まず、チーム全体の課題として取り組む姿勢が重要ですよ。」
Q3:新人時代に比べて5年目になってもストレスが減りません。これは普通のことですか?
カンゴさんの回答: 「キャリアが進むにつれてストレスの質が変化するのは自然なことです。新人時代は技術的な不安やミスへの恐怖など、直接的なケアに関するストレスが多いでしょう。
一方、中堅になると後輩指導、複雑な患者対応、組織内の調整役など、責任の幅が広がることでストレスの質が変わってきます。
5年目というのは、多くの看護師にとって『一人前』と見なされ、様々な役割を任されるようになる時期です。それに伴い、一時的にストレスが増加することも珍しくありません。
特に、これまでのスキルだけでは対応できない新たな課題に直面することで、再び不安を感じる『セカンドキャリアショック』を経験する方もいます。
このようなストレスに対しては、自分のキャリアステージに合わせたスキルアップが効果的です。例えば、後輩指導に不安があれば指導者研修を受ける、組織内の調整に苦手意識があればコミュニケーションスキルを磨くなど、新たな課題に対応するための知識や技術を習得しましょう。
また、この時期は自分のキャリアビジョンを見直す良い機会でもあります。今後どのような看護師になりたいのか、専門性を高めたい分野はあるのか、じっくり考えてみることで、新たなモチベーションが生まれることもあります。
ストレスは成長の証でもありますが、一人で抱え込まず、メンターに相談したり、同期と共有したりすることも大切ですよ。」
Q4:夜勤中の集中力低下を防ぐ良い方法はありますか?
カンゴさんの回答: 「夜勤中の集中力維持は安全なケア提供のために欠かせない課題ですね。まず、夜勤前の準備が重要です。十分な睡眠時間を確保し、カフェインの摂取タイミングを工夫しましょう。
夜勤開始4〜5時間前に軽いカフェインを摂り、夜勤中盤でもう一度摂取すると効果的です。
夜勤中は、特に午前2時から5時にかけて生理的に眠気が強まる時間帯があります。この時間帯には意識的に体を動かす業務を入れたり、短時間でも立ち上がってストレッチを行ったりすることが有効です。
また、明るい照明の下で過ごす時間を作ることも覚醒維持に役立ちます。
食事面では、夜勤中の食事は消化の良い軽めのものを選び、炭水化物中心の重い食事は避けましょう。タンパク質や少量の良質な脂質を含む食事が集中力維持に効果的です。また、適度に水分補給をすることも大切です。
チーム内での声かけや短時間の会話も覚醒維持に効果的です。特に集中力が低下しやすい時間帯には、互いに声をかけ合う習慣をつけると良いでしょう。どうしても強い眠気に襲われた場合は、安全を確保した上で10〜15分程度の短時間仮眠(パワーナップ)を取ることも検討してみてください。
夜勤を定期的に行う看護師にとって、自分に合った眠気対策を見つけることが長期的な健康維持につながります。」
Q5:ベテラン看護師とのコミュニケーションが難しいと感じます。どうすれば良い関係を築けますか?
カンゴさんの回答: 「世代間のコミュニケーションギャップは、多くの職場で見られる課題ですね。まず大切なのは、ベテラン看護師の豊富な経験と知識を尊重する姿勢です。長年の臨床経験から培われた『暗黙知』は非常に価値があります。
質問する際も、「なぜそうするのか」という理由を丁寧に聞くことで、単なる作業手順だけでなく、その背景にある考え方も学ぶことができます。
また、コミュニケーションスタイルの違いを理解することも重要です。ベテラン世代は対面での直接的なコミュニケーションを好む傾向がある一方、若い世代はデジタルツールでの効率的な情報共有を好む傾向があります。
状況に応じて、相手が心地よいと感じるコミュニケーション方法を選ぶ配慮も大切です。
さらに、単に業務上の関係だけでなく、時には休憩時間などを利用して個人的な会話を持つことも関係構築に役立ちます。ベテラン看護師の看護観や仕事観について聞いてみると、思わぬ共通点が見つかることもあるでしょう。
何より、「教えてください」と素直に学ぶ姿勢を示すことが最も効果的です。同時に、新しい知識や技術についてはあなたから提案する機会もあるかもしれません。お互いの強みを認め合い、補い合う関係を築くことが、世代を超えたチーム力の向上につながります。」
Q6:診療科による給与の違いはありますか?高給与を狙うならどの診療科が良いでしょうか?
カンゴさんの回答: 「基本的に、病院の給与体系では診療科による基本給の違いはあまりありません。多くの病院では、経験年数や資格、役職などに基づいて給与が決定されます。しかし、実質的な収入という観点では、診療科によって差が生じることがあります。
例えば、夜勤や時間外勤務の多い救急科やICU、産科などでは、夜勤手当や時間外手当が加算されることで、結果的に月収が高くなるケースがあります。また、特殊な技術や知識が求められる手術室、透析室、内視鏡室などでは、特殊業務手当が支給される病院もあります。
ただし、単に給与だけで診療科を選ぶことはお勧めしません。高給与の背景には、身体的・精神的負担の大きさが伴うことが多いからです。
長期的なキャリア形成と収入のバランスを考えるなら、まずは自分の適性や興味に合った診療科で経験を積み、その上で専門看護師や認定看護師などの資格取得を目指す方が、キャリアの安定性と収入アップの両方が見込めるでしょう。
また、病院によって給与体系は大きく異なります。同じ診療科でも、大学病院と一般病院、都市部と地方では待遇が違うことも多いです。転職を考える際には、給与だけでなく、残業の実態、休暇取得状況、教育体制なども含めて総合的に判断することをお勧めします。」
Q7:看護師としての燃え尽き症候群を防ぐコツはありますか?
カンゴさんの回答: 「看護師のバーンアウト(燃え尽き症候群)は、継続的なストレスや過度な業務負担、感情労働の蓄積などから生じることが多いです。予防のためには、「仕事と私生活の境界線を明確にする」ことが何より重要です。
勤務終了後は意識的に仕事のことを考えない時間を作り、趣味や家族との時間など、自分を充電する活動に時間を使いましょう。
また、「完璧主義から卒業する」ことも大切です。全ての患者に完璧なケアを提供することは現実的に不可能です。「今日できる最善を尽くす」という考え方に切り替えることで、不必要な自責感から解放されます。
職場環境の面では、一人で抱え込まず「サポートネットワークを構築する」ことが効果的です。信頼できる同僚や上司、メンターなどに気持ちを打ち明けられる関係を作りましょう。場合によっては、病院内の産業医やカウンセラーなどの専門家に相談することも有効です。
さらに、定期的に「自分のキャリアビジョンを見直す」ことも重要です。現在の環境で成長できているか、目指したい方向に進んでいるかを確認し、必要に応じて異動や配置転換、働き方の変更を検討することも一つの選択肢です。
最後に、身体的健康も精神的健康の基盤となります。十分な睡眠、バランスの取れた食事、定期的な運動など、基本的な健康習慣を大切にすることが、長く看護師として活躍し続けるための土台となります。看護師である前に、一人の人間として自分を大切にすることを忘れないでくださいね。
まとめ
看護師にとって診療科選びは、キャリア満足度とワークライフバランスに大きく影響します。本記事では業務負担の大きい診療科ランキングとその特徴を解説し、各診療科特有のストレス要因(時間的プレッシャー型、身体的負荷型、感情労働型、専門性・責任型)を分析しました。
自分の強み・弱み、価値観、ライフスタイルに合った診療科を選ぶことが、長く看護師として働き続けるための鍵です。また、個人レベル、チームレベル、組織レベルでの多層的なストレス対策アプローチの重要性も明らかになりました。
- 医療経済研究機構 (2023)「病院経営と看護職員の労働環境に関する調査研究」https://www.ihep.jp/publications/research/2023/
- 厚生労働省「看護職員確保対策」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html
看護師キャリアの次のステップに
診療科選びやキャリアプランにさらに悩んでいる方は、【はたらく看護師さん】ではより詳しい情報や個別相談サービスをご提供しています。
会員登録をしていただくと、診療科別の詳細な業務内容や給与相場、実際に働く看護師のインタビュー、転職成功事例など、さらに充実したコンテンツにアクセスいただけます。
また、定期的に開催している「診療科別キャリアセミナー」や「ストレスマネジメント研修」などのイベント情報もいち早くお届けします。同じ悩みを持つ仲間との交流の場にもなりますので、ぜひ会員登録してご参加ください。
自分に最適な診療科選びやキャリアアップについて個別相談も承っています。経験豊富なキャリアアドバイザーが、あなたの経験やスキル、希望に合わせたアドバイスを提供します。
あなたの看護師としてのさらなる活躍を【はたらく看護師さん】は応援しています!