
医療の高度化と専門分化が進む現代において、看護師のキャリアパスは多様化しています。なかでも注目を集めているのが、診療看護師(NP:Nurse Practitioner)と特定看護師(特定行為研修修了者)という二つの道です。
両者は共に高度な医療行為を担う存在として期待されていますが、その役割や業務範囲、必要な資格要件には重要な違いがあります。
医療現場では、医師の働き方改革や地域医療の充実化に向けて、これらの専門性の高い看護師の需要が年々高まっています。2025年現在、診療看護師は約2,800名、特定看護師は約5,000名が活躍していますが、今後さらなる増加が見込まれています。
このような状況の中、キャリアアップを考える看護師にとって、どちらの道を選択するかは重要な決断となります。本記事では、両者の違いを実践的な視点から詳しく解説し、あなたに最適なキャリア選択のための具体的な指針を提供します。
この記事で分かること
- 診療看護師と特定看護師それぞれの役割と責任範囲の詳細な違い
- 資格取得に必要な要件と教育課程の具体的な内容
- 実際の医療現場での業務範囲と活躍事例
- キャリアパスの選び方と将来性に関する具体的な展望
- 資格取得から実践までの具体的なステップとアドバイス
この記事を読んでほしい人
- より高度な医療行為に携わりたいと考えている看護師
- キャリアアップの方向性を探している医療従事者
- 診療看護師か特定看護師かの選択に迷っている方
- 医療チームでのリーダーシップを目指している看護師
- 地域医療の質向上に貢献したいと考えている方
- 専門性を活かした新しいキャリアを築きたい方
診療看護師と特定看護師の基本的な違い

医療現場における診療看護師と特定看護師は、それぞれが異なる役割と特徴を持つ専門職として位置づけられています。両者の違いを理解することは、キャリア選択において重要な判断材料となります。
ここでは、制度的背景から実践的な役割まで、両者の違いを多角的に解説していきます。
役割の本質的な違い
診療看護師と特定看護師は、その成り立ちから求められる役割が大きく異なります。診療看護師は、医師の包括的な指示のもとで診療の補助を行う高度実践看護師として位置づけられています。医師が不在の場合でも、一定の範囲内で医療行為を行うことができ、より自律的な判断と実践が求められます。
一方、特定看護師は、医師が作成した手順書に基づいて特定の医療行為を実施する看護師です。実施できる医療行為は特定行為として明確に定められており、それぞれの行為について詳細な手順書が必要となります。
診療の範囲と自律性
診療看護師は包括的な患者アセスメントから診断の補助、治療計画の立案まで、幅広い診療プロセスに関与します。患者の状態を総合的に評価し、必要な検査のオーダーや治療方針の提案を行うことができます。また、慢性疾患の管理や予防医療においても重要な役割を果たします。
特定看護師は、手順書に基づく特定の医療行為に特化しており、その範囲内での迅速な対応が可能です。例えば、術後の疼痛管理や血糖コントロール、創傷管理などの特定行為を、定められた手順に従って実施することができます。
制度的位置づけと法的根拠
診療看護師の法的位置づけ
診療看護師は、日本NP教育大学院協議会が認定する資格を持つ高度実践看護師です。現在の日本の法制度では、診療看護師という職種は法的に規定されていませんが、実際の医療現場では、その高度な知識と技術を活かした実践が認められています。
特定看護師の法的位置づけ
特定看護師は、2014年の保健師助産師看護師法の改正により法制化された制度です。特定行為に係る看護師の研修制度として確立され、研修修了者は特定行為を実施する権限が付与されます。
医療チームにおける位置づけ
診療看護師の役割
診療看護師は、医師と看護師の間を橋渡しする存在として、チーム医療のコーディネーターとしての役割も担います。診療方針の決定から治療計画の立案、他職種との連携まで、包括的な視点でチーム医療を推進します。また、看護師教育や臨床研究においても中心的な役割を果たすことが期待されています。
特定看護師の役割
特定看護師は、特定の医療行為において、タイムリーな医療提供を実現する要となります。手順書に基づく特定行為の実施により、医師の指示を待つことなく必要な医療を提供できることから、医療の効率化に大きく貢献します。また、特定行為研修で得た知識と技術を活かし、看護チームのリーダーとしても活躍します。
実践における判断基準
診療看護師の判断基準
診療看護師は、包括的な医学的知識と高度な臨床推論能力に基づいて判断を行います。患者の状態を総合的に評価し、必要な医療介入を判断することができます。ただし、最終的な診断や治療方針の決定は医師が行い、診療看護師はその補助的役割を担います。
特定看護師の判断基準
特定看護師は、手順書に定められた範囲内で判断を行います。手順書には、実施する医療行為の適応判断や実施時の留意点、中止基準などが明確に示されており、それに従って実践を行います。状態の変化や予期せぬ事態が発生した場合は、速やかに医師に報告し、指示を仰ぐことが求められます。
資格要件と取得プロセス

診療看護師と特定看護師、それぞれの資格を取得するためには、特定の要件を満たし、定められた教育課程を修了する必要があります。
ここでは、資格取得に必要な要件から実際の取得プロセス、さらには準備すべき事項まで、詳しく解説していきます。
診療看護師の資格要件
診療看護師の資格取得には、複数の要件を段階的に満たしていく必要があります。まず基本となるのは、看護師としての実務経験です。一般的に5年以上の臨床経験が求められ、そのうち3年以上は急性期医療もしくは専門領域での経験が推奨されています。
学歴要件と受験資格
診療看護師を目指すためには、看護系大学院修士課程のNP教育課程に進学する必要があります。入学試験では、英語の試験や小論文、面接などが実施され、臨床推論能力や医療に対する考え方なども評価されます。
必要な証明書類
出願時には、看護師免許証の写しに加え、実務経験証明書、推薦書などの提出が必要となります。また、TOEIC等の英語スコアを求められる大学院もあります。これらの書類は早めに準備を進めることが推奨されます。
特定看護師の資格要件
特定看護師になるためには、厚生労働大臣が指定する指定研修機関で特定行為研修を修了する必要があります。受講の要件として、看護師免許を有していることが前提となり、実務経験は3年以上が推奨されています。
研修受講の条件
特定行為研修を受講するためには、所属する医療機関からの推薦や承認が必要となることが一般的です。また、研修期間中の勤務調整や費用面での支援を得られるかどうかも、事前に確認が必要です。
区分別パッケージの選択
特定行為研修では、自身の専門領域や希望する実践分野に応じて、複数の区分別パッケージから必要な科目を選択することができます。選択に際しては、現在の業務内容や将来のキャリアプランを考慮することが重要です。
資格取得までのステップ
診療看護師の取得プロセス
診療看護師の資格取得までには、通常2年以上の期間を要します。大学院での学習では、高度な医学知識と臨床実践能力の習得が求められます。講義や演習に加え、実習では実際の医療現場での経験を積みます。
修了要件と認定試験
大学院修了後には、日本NP教育大学院協議会が実施する認定試験に合格する必要があります。試験では、臨床推論能力や医療面接技術、基本的な診療技術などが評価されます。
特定看護師の取得プロセス
特定行為研修は、共通科目と区分別科目で構成されています。共通科目では、臨床病態生理学や医療安全学などの基礎的な知識を学びます。区分別科目では、各特定行為に必要な知識と技術を習得します。
研修期間と形態
研修期間は、選択する区分数や研修形態によって異なりますが、通常8ヶ月から2年程度です。e-learningを活用した通信制や、週末のみの集中講義など、働きながら学べる形態も用意されています。
実践的な準備と心構え
学習準備と時間管理
資格取得に向けては、事前の準備と計画的な学習が重要です。特に、解剖生理学や薬理学などの基礎医学の復習は、学習をスムーズに進めるために有効です。また、働きながら学ぶ場合は、業務との両立を図るための時間管理スキルも必要となります。
経済的準備
資格取得には相応の費用が必要となります。診療看護師の場合、大学院の学費に加え、教材費や実習費用などで総額200-300万円程度が必要です。特定看護師の場合は、研修費用として50-150万円程度が必要となります。医療機関からの支援制度や奨学金の活用も検討することをお勧めします。
メンタル面での準備
新たな知識と技術の習得には相応の努力と時間が必要です。特に、臨床実習では、これまでとは異なる役割や責任を求められることもあります。同期の仲間や先輩からのサポートを得ながら、着実に学びを積み重ねていくことが重要です。
教育課程の違い

診療看護師と特定看護師では、その役割の違いを反映して、教育課程にも大きな特徴があります。それぞれの課程で学ぶ内容や教育方法、実習の進め方など、詳細な違いを理解することは、自身のキャリアプランを考える上で重要な要素となります。
ここでは、両者の教育課程について、カリキュラムの内容から実際の学習体験まで、詳しく見ていきます。
診療看護師の教育課程
診療看護師の教育は、看護系大学院の修士課程で行われます。2年以上の課程で、総時間数は3,000時間以上に及びます。医学的知識と高度な実践能力の習得を目指し、体系的なカリキュラムが組まれています。
基礎医学教育
診療看護師教育の基盤となるのが、充実した基礎医学教育です。解剖学、生理学、病態生理学などの科目では、医学部と同等レベルの知識習得が求められます。講義では、臨床現場での応用を意識した実践的な内容が展開され、症例を用いた討議なども積極的に取り入れられています。
臨床推論と診断学
臨床推論は診療看護師教育の核となる部分です。患者の症状や検査データから適切な診断へと導く思考プロセスを、段階的に学んでいきます。実際の症例を用いたケーススタディでは、エビデンスに基づいた判断力を養います。また、医療面接技法や身体診察技術の習得も重要な要素となっています。
薬理学と治療学
薬物療法に関する深い理解は、診療看護師に不可欠な能力です。薬理学では、薬物の作用機序から副作用、相互作用まで、包括的な知識を習得します。また、各疾患の治療戦略について学び、適切な治療法の選択や提案ができる能力を養います。
実習と技能習得
実習は1,000時間以上が必要とされ、様々な診療科でローテーションを行います。実習では、指導医の下で実際の診療に参加し、医療面接から診察、治療計画の立案まで、段階的に経験を積みます。また、シミュレーション教育も積極的に取り入れられ、安全な環境で高度な技術を習得することができます。
特定看護師の教育課程
特定看護師の教育は、特定行為研修として実施されます。研修は共通科目と区分別科目で構成され、選択する区分に応じて8ヶ月から2年程度の期間で修了することができます。
共通科目の構成
共通科目は315時間の学習が必要です。臨床病態生理学、医療安全学、臨床推論、フィジカルアセスメントなどの科目で構成されています。これらの科目では、特定行為を安全に実施するための基礎的な知識と判断力を養います。e-learningを活用した学習も可能で、働きながら効率的に学習を進めることができます。
区分別科目の特徴
区分別科目は、選択した特定行為の区分ごとに必要な知識と技術を学びます。各区分で15時間から72時間の講義と演習が設定されており、特定行為の実施に必要な具体的手技やモニタリング方法などを習得します。実践的な演習を通じて、確実な技術の習得を目指します。
実習による技能の確立
区分別実習では、各特定行為について5から10症例程度の実施が求められます。実習では、実際の医療現場で手順書に基づいた特定行為を実施し、安全かつ確実な実践能力を身につけます。指導医や指導看護師の下で、段階的に実践経験を積み重ねていきます。
学習支援体制
診療看護師課程の支援体制
診療看護師教育では、少人数制の教育体制が採用されており、きめ細かな指導が受けられます。また、臨床経験豊富な教員による個別指導や、同期生との学習グループ活動なども重要な支援となっています。医学的知識の習得には相応の努力が必要ですが、充実した支援体制により、着実な成長が期待できます。
特定看護師研修の支援体制
特定行為研修では、各研修機関に専任の指導者が配置されており、実践的な指導を受けることができます。また、e-learningシステムを活用することで、自己のペースで学習を進めることが可能です。
実習期間中は、指導医による直接指導に加え、指導看護師からのサポートも得られ、確実な技能の習得をサポートする体制が整っています。
修了後の継続教育
診療看護師の継続教育
診療看護師は、修了後も定期的な研修や学会参加を通じて、最新の医学知識と技術の習得に努めます。また、症例検討会や臨床研究への参加を通じて、実践能力の向上を図ります。日本NP教育大学院協議会による更新制度もあり、5年ごとの資格更新が必要となります。
特定看護師の継続教育
特定看護師も、定期的な研修参加や新たな区分の追加取得など、継続的な学習が推奨されています。また、所属施設での症例検討会や、特定行為研修指導者としての活動を通じて、さらなる専門性の向上を図ることができます。医療の進歩に対応するため、最新の知識と技術の習得が求められています。
実際の医療現場での業務範囲

診療看護師と特定看護師は、それぞれの専門性を活かして医療現場で重要な役割を果たしています。両者の業務範囲は制度上明確に区分されており、その特性を活かした実践が行われています。
ここでは、実際の医療現場における具体的な業務内容から、チーム医療における役割まで、現場の実態に即して詳しく解説していきます。
診療看護師の業務実践
診療看護師は、医師の包括的指示のもと、より独立的な判断で医療行為を実施することができます。その業務は診療の補助から患者管理まで、幅広い範囲に及びます。
外来診療での役割
外来診療では、医師の診察前の予診から始まり、患者の状態を包括的に評価します。問診では患者の主訴を詳しく聴取し、バイタルサインの測定や身体診察を行います。また、検査の必要性を判断し、医師と相談の上で検査オーダーの提案も行います。
慢性疾患の患者さんに対しては、症状の変化や服薬状況の確認、生活指導なども重要な業務となっています。
病棟での実践
入院患者の管理では、毎日の回診で患者の状態を評価し、必要な医療介入を判断します。患者の状態変化に応じて、検査データの解釈や治療方針の提案を行い、医師と協議しながら最適な医療を提供します。
また、他職種とのカンファレンスでは、患者の治療方針やケアの方向性について、リーダーシップを発揮することも期待されています。
救急外来での対応
救急外来では、来院時のトリアージから初期対応まで、重要な役割を担います。患者の緊急度と重症度を適切に判断し、必要な検査や処置の提案を行います。また、軽症患者に対しては、医師の包括的指示のもと、診察から治療計画の立案まで、主体的に対応することもあります。
特定看護師の業務実践
特定看護師は、医師が作成した手順書に基づいて、特定の医療行為を実施します。それぞれの特定行為について、実施の判断から実施後の評価まで、一連のプロセスを担当します。
術後管理における実践
手術後の患者管理では、疼痛コントロールや創部管理など、多くの特定行為が必要となります。例えば、硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与や、創部の状態に応じた抗菌薬の選択と投与など、手順書に基づいて適切な医療を提供します。また、術後の合併症予防にも重要な役割を果たしています。
慢性期管理での活動
慢性疾患患者の管理では、病状の安定化に向けた様々な特定行為を実施します。例えば、糖尿病患者のインスリン投与量の調整や、心不全患者の利尿薬の調整など、患者の状態に応じた薬物療法の管理を行います。また、状態が変化した際の早期対応も重要な業務となっています。
在宅医療での実践
在宅医療の現場では、医療処置の実施から状態管理まで、幅広い対応が求められます。褥瘡の処置や栄養管理、呼吸管理など、患者の生活の質を維持・向上させるための特定行為を実施します。また、患者や家族への指導・教育も重要な役割です。
チーム医療における連携実践
診療看護師の連携モデル
診療看護師は、医師と看護師の間を繋ぐ存在として、チーム医療のコーディネーターの役割を果たします。医師との定期的なカンファレンスでは、患者の状態や治療方針について詳細な報告と提案を行い、看護チームに対しては具体的なケア方針を示します。
また、他職種との連携においても、患者の全体像を把握した上で、適切な情報共有と調整を行います。
特定看護師の連携実践
特定看護師は、手順書に基づく医療行為を通じて、チーム医療の効率化に貢献します。医師との定期的な報告・相談を行いながら、状態の変化に応じた特定行為を実施します。また、看護チームのリーダーとして、特定行為に関する知識と技術を共有し、チーム全体のスキルアップにも貢献します。
医療安全と質の保証
診療看護師の安全管理
診療看護師は、高度な医療行為を行う上で、常に医療安全を意識した実践を行います。医療面接や身体診察、検査データの解釈など、それぞれの場面で適切なリスク評価を行い、必要に応じて医師への報告や相談を行います。また、インシデントやアクシデントの予防に向けた取り組みも重要な業務となっています。
特定看護師の安全管理
特定看護師は、手順書に基づく実践において、確実な安全管理を行います。特定行為の実施前には、患者の状態を慎重に評価し、実施の可否を判断します。また、実施中・実施後のモニタリングを徹底し、異常の早期発見と適切な対応に努めます。定期的な手順書の見直しや、安全管理に関する検討会にも積極的に参加します。
教育・指導者としての役割
診療看護師の教育活動
診療看護師は、その高度な知識と技術を活かして、看護スタッフの教育にも携わります。臨床推論や身体診察技術、薬物療法の管理など、実践的な教育を提供します。また、医学生や研修医の教育支援も行い、チーム全体の医療の質向上に貢献します。
特定看護師の指導活動
特定看護師は、特定行為に関する実践的な指導者として、看護スタッフの育成に携わります。手順書に基づく医療行為の実施方法や注意点について、具体的な指導を行います。また、新人看護師の教育支援や、特定行為研修の実習指導者としても活動します。
キャリアパスと将来性
医療を取り巻く環境が大きく変化する中、診療看護師と特定看護師のキャリアパスはますます多様化しています。医師の働き方改革や地域医療の充実化に向けて、両者の需要は着実に高まっており、将来的な発展可能性も広がっています。
ここでは、それぞれの職種における具体的なキャリアパスと将来展望について詳しく見ていきます。
診療看護師のキャリア展望
急性期医療での発展
急性期医療の現場では、診療看護師の専門性を活かした活躍の場が広がっています。救急外来や集中治療室での実践はもちろん、各診療科においても、医師との協働のもと、より高度な医療実践が期待されています。経験を積むことで、専門領域でのエキスパートとして認められ、医療チームのキーパーソンとしての役割を担うことができます。
専門分野での活動
特定の診療科や疾患領域に特化したスペシャリストとしての道も開かれています。例えば、糖尿病看護や心不全看護など、専門分野での実践を深めることで、その領域における高度実践看護師としての地位を確立することができます。また、専門外来の開設や、患者教育プログラムの立案・運営なども重要な活動領域となっています。
特定看護師のキャリア展望
実践領域の拡大
特定看護師は、習得した特定行為区分を活かしながら、実践領域を段階的に拡大していくことができます。新たな区分の追加取得により、より包括的な医療提供が可能となり、活躍の場も広がっていきます。また、在宅医療や地域包括ケアの分野でも、その専門性を活かした実践が期待されています。
指導的立場への成長
経験を積むことで、特定行為研修の指導者としての道も開かれています。後進の育成に携わりながら、自身の実践能力も向上させることができます。また、施設内での医療安全管理や質改善活動のリーダーとしても重要な役割を果たすことができます。
処遇とキャリアアップ
給与体系の変化
資格取得後は、一般的に基本給に資格手当が加算されます。診療看護師の場合、月額3万円から8万円程度、特定看護師の場合は2万円から5万円程度の増額が一般的です。また、実践能力や経験年数に応じて、段階的な昇給も期待できます。
昇進の可能性
両資格とも、実践能力の向上に伴い、管理職としてのキャリアも展開できます。看護部門の管理者として、より大きな視点から医療の質向上に貢献することも可能です。また、教育機関での教員や、医療政策に関わる行政職など、活躍の場は医療現場に限定されません。
今後の展望
医療の高度化と専門分化が進む中、診療看護師と特定看護師の役割はさらに重要性を増すことが予想されます。特に、地域医療の充実化や在宅医療の推進において、両者の専門性を活かした実践が不可欠となっています。また、医療のデジタル化やAIの導入など、新しい技術への対応も求められる中、継続的な学習と実践能力の向上により、さらなるキャリアの発展が期待できます。
実践者に学ぶキャリア選択
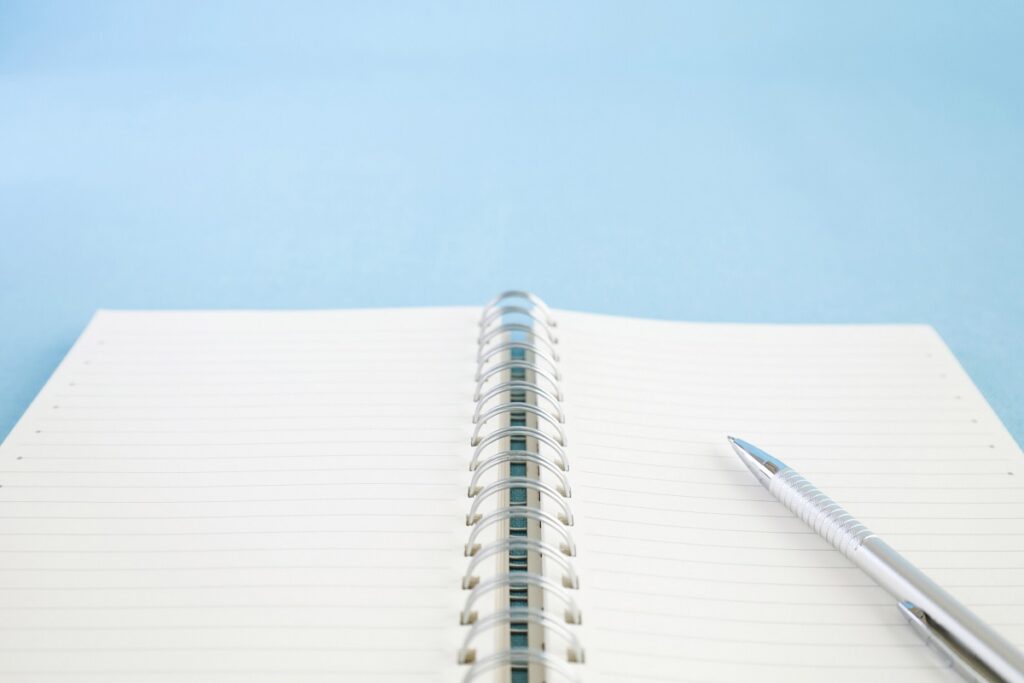
診療看護師と特定看護師、それぞれの道を選択した方々の実例から、実践的な学びを得ることができます。
ここでは、様々な背景や目標を持って資格を取得し、現場で活躍している5名の方々の経験を紹介していきます。それぞれのケースから、キャリア選択のヒントを見つけていただければと思います。
救急医療の質向上を目指したAさんの選択
背景と動機
救命救急センターで7年間の経験を持つAさんは、より迅速な救急対応の必要性を感じ、診療看護師の道を選択しました。特に、夜間の救急外来において、医師の到着を待つ間の初期対応の重要性を強く認識していたことが、この選択の大きな要因となっています。
資格取得までの道のり
大学院での2年間は、働きながらの学習となりましたが、所属病院の支援制度を活用することで、実習期間中は十分な学習時間を確保することができました。特に臨床推論と救急医療に関する実習では、これまでの経験を活かしながら、新たな視点での学びを深めることができました。
現在の活動
現在は救命救急センターの診療看護師として、トリアージから初期治療の開始まで、包括的な救急医療を提供しています。医師との密接な連携のもと、緊急度の高い患者さんの初期対応から、軽症患者の診療補助まで、幅広い実践を行っています。また、救急看護の質向上に向けた教育活動にも力を入れています。
在宅医療の充実を目指したBさんの選択
背景と動機
訪問看護ステーションで5年の経験を持つBさんは、在宅療養患者への迅速な医療提供を実現するため、特定看護師の資格取得を決意しました。医療処置が必要な場面で、その都度医師の指示を待つ状況を改善したいという思いが、この選択につながりました。
資格取得までの道のり
e-learningを活用した学習により、働きながらの資格取得が可能となりました。特に在宅医療で必要性の高い創傷管理や感染管理、栄養および水分管理の区分を重点的に学習しました。実習では、様々な在宅療養環境での経験を積むことができました。
現在の活動
訪問看護ステーションの管理者として、特定行為を活用した質の高い在宅医療の提供に取り組んでいます。医師との連携のもと、患者さんの状態変化に迅速に対応し、必要な医療処置を提供することで、在宅療養の継続を支援しています。
急性期病棟でのキャリアを築いたCさんの選択
背景と動機
循環器内科病棟で10年の経験を持つCさんは、より専門的な患者管理を行いたいという思いから、診療看護師を目指しました。特に、急性期の患者さんの状態管理や、退院に向けての包括的な支援の必要性を感じていたことが、この選択の背景にありました。
資格取得までの道のり
大学院では、循環器疾患の病態生理から最新の治療法まで、深い学びを得ることができました。実習では、CCUでの重症患者管理から、専門外来での慢性疾患管理まで、幅広い経験を積むことができました。
現在の活動
循環器内科専門病院の診療看護師として、急性期から慢性期まで、継続的な患者管理を行っています。また、心不全患者さんの専門外来を担当し、症状管理や生活指導を通じて、再入院予防にも取り組んでいます。
地域医療に貢献するDさんの選択
背景と動機
地域の中核病院で8年間勤務したDさんは、医療過疎地域での医療提供体制の充実を目指して、特定看護師の道を選びました。特に、高齢化が進む地域での迅速な医療提供の必要性を強く感じていたことが、この選択につながりました。
資格取得までの道のり
複数の区分の特定行為研修を段階的に受講することで、地域医療に必要な幅広い知識と技術を習得しました。特に、呼吸器関連や創傷管理、循環動態に係る医療行為など、地域のニーズに応じた区分を選択しました。
現在の活動
地域医療支援病院で、外来から入院、在宅支援まで、切れ目のない医療提供に携わっています。特に、高齢者の急性増悪時の対応や、在宅療養支援において、特定行為を活用した迅速な医療提供を実現しています。
教育者としての道を選んだEさんの選択
背景と動機
大学病院で12年の経験を持つEさんは、次世代の医療者育成に携わりたいという思いから、診療看護師の資格を取得しました。臨床経験を活かしながら、実践的な教育を提供したいという目標が、この選択の原動力となりました。
資格取得までの道のり
大学院では、臨床実践能力の向上に加え、教育方法論についても深く学びました。実習では、臨床現場での実践に加え、学生指導や新人教育にも携わる機会を得ることができました。
現在の活動
看護系大学の教員として、診療看護師育成プログラムに携わっています。臨床経験と高度実践能力を活かし、次世代の医療人材の育成に貢献しています。また、臨床現場での実習指導も担当し、理論と実践を結びつけた教育を展開しています。
おしえてカンゴさん!よくある質問
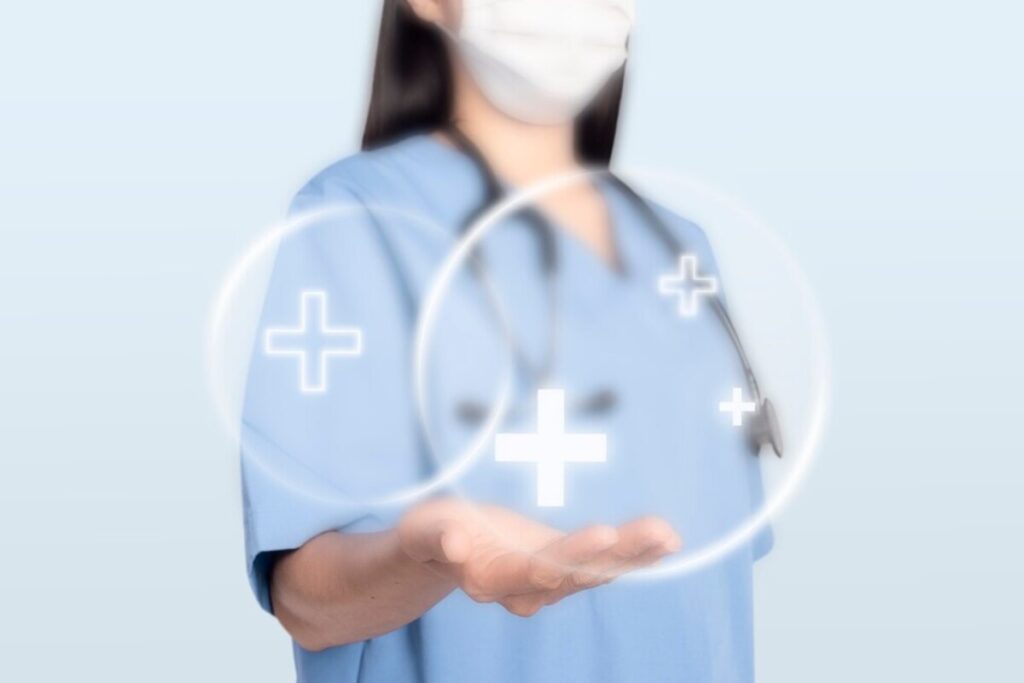
診療看護師と特定看護師に関して、多くの看護師の皆さんから質問が寄せられています。
ここでは、経験豊富な先輩看護師「カンゴさん」が、実践的な視点からよくある疑問にお答えします。
資格取得に関する質問
両方の資格を同時に取得することは可能ですか?
カンゴさん:同時取得は現実的ではありませんが、段階的な取得は可能です。例えば、まず特定看護師の資格を取得し、その後診療看護師を目指すというキャリアパスを選択する方もいます。
ただし、それぞれの資格取得には相応の時間と費用が必要となりますので、自身のキャリアプランに合わせて計画的に進めることをお勧めします。
働きながらの資格取得は現実的ですか?
カンゴさん:両資格とも、働きながらの取得を支援する教育プログラムが用意されています。特定看護師の場合、e-learningを活用した学習が可能で、実習期間も比較的調整しやすい傾向にあります。
一方、診療看護師の場合は、大学院での学習が基本となりますが、週末コースや夜間コースを設けている教育機関もあります。ただし、実習期間中は一定期間の休職や勤務調整が必要となることが多いです。
実践に関する質問
資格取得後の待遇はどのように変わりますか?
カンゴさん:一般的に、基本給に加えて資格手当が支給されます。金額は施設によって異なりますが、診療看護師で月額3万円から8万円程度、特定看護師で2万円から5万円程度の増額が一般的です。
また、キャリアアップに伴う昇給や、管理職への登用機会も増える傾向にあります。具体的な待遇については、所属施設の制度を確認することをお勧めします。
特定行為区分の選択はどのように考えればよいですか?
カンゴさん:現在の業務内容や、将来のキャリアプランに応じて選択することをお勧めします。例えば、急性期病棟で働く場合は、術後管理や呼吸器関連の区分が有用です。
在宅医療を視野に入れている場合は、創傷管理や感染管理、栄養および水分管理などの区分が重要となります。また、所属施設のニーズや、地域医療の特性なども考慮に入れると良いでしょう。
キャリア展望に関する質問
将来的にどのような分野で活躍できますか?
カンゴさん:両資格とも、臨床現場での実践はもちろん、教育、研究、管理職など、多様なキャリアパスが開かれています。特に、地域医療の充実化や在宅医療の推進に伴い、その専門性を活かした活躍の場が広がっています。
また、医療政策への参画や、国際的な活動など、活躍の場は医療現場に限定されません。自身の興味や強みを活かしたキャリア展開が可能です。
まとめ
診療看護師と特定看護師は、それぞれが異なる特徴と価値を持つ専門性の高いキャリアパスです。診療看護師は包括的な医療実践を担い、特定看護師は手順書に基づく特定の医療行為に特化しています。
どちらを選択するかは、ご自身の目指す看護の形や、キャリアビジョンによって決まってきます。医療を取り巻く環境が変化する中、両者の需要は今後さらに高まることが予想されます。
【はたらく看護師さん】は、あなたの理想のキャリアを実現するためのパートナーです。会員登録いただくと、より詳細な情報やオリジナルコンテンツにアクセスいただけます。これからのキャリアプランについて、一緒に考えていきましょう。
▼詳しくは【はたらく看護師さん】をチェック

