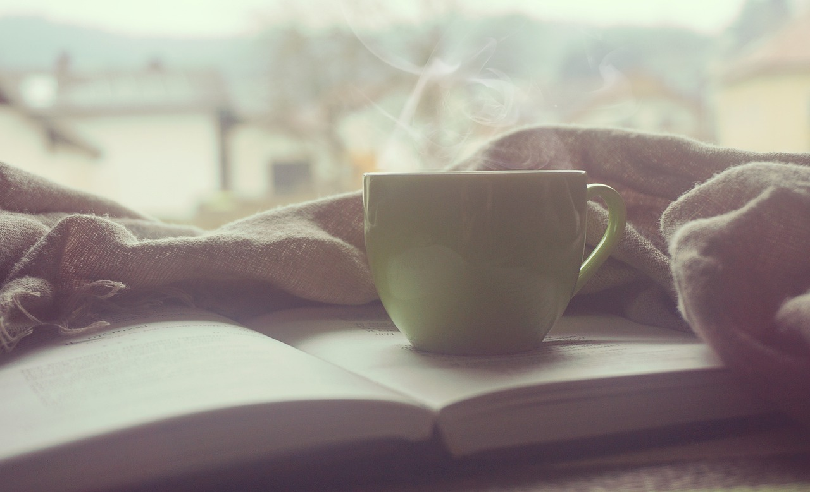医療現場の第一線で活躍する看護師の皆様にとって、公立病院と私立病院の選択は、将来の生活やキャリアプランを大きく左右する重要な決断となります。
本記事では、両者の給与体系や待遇の違い、そして賢明な選択のための判断基準について、2024年の最新データを基に詳しく解説していきます。
この記事でわかること
- 公立病院と私立病院の具体的な年収差(最大60万円以上)と詳細な給与体系
- 賞与、手当、福利厚生における重要な違いと具体的な金額
- 設置主体別のキャリアパスと長期的な将来性の展望
- 転職・就職時の具体的な選択ポイントと判断基準
この記事を読んでほしい人
- 公立病院と私立病院の待遇の違いを詳しく知りたい看護師
- 転職を検討している看護師 ・長期的なキャリアプランを考えている看護師
- 就職活動中の看護学生
- ワークライフバランスを重視している看護師
公立vs私立病院の給与体系

公立病院と私立病院では、給与体系に大きな違いがあります。このセクションでは、基本給の構造から年収の比較まで、具体的な数字を交えながら詳しく解説していきます。
基本給の違いと特徴
公立病院の給与体系は地方公務員給与表に基づいて設計されており、経験年数や職位による昇給が明確に定められています。一方、私立病院は独自の給与体系を採用しており、より柔軟な運用が特徴となっています。
公立病院の基本給体系
公立病院では、地方公務員給与表に基づく明確な給与体系が採用されています。初任給は都内で経験3年の場合、248,000円からスタートし、毎年4月に定期昇給が行われます。
また、地域手当も充実しており、都市部では基本給の最大20%が追加支給されます。昇給は年功序列的な要素が強く、経験年数に応じて着実に上がっていくのが特徴です。
私立病院の基本給体系
私立病院の場合、病院独自の給与体系が採用されており、初任給は都内で経験3年の場合、235,000円からとなっています。昇給は病院の経営方針や評価制度に基づいて決定され、より実力主義的な傾向があります。
ただし、病院の規模や経営状況によって給与水準に大きな差が生じることがあります。
年収比較と具体的な差額
病院種別による年収の違い
2024年の最新データによると、病院の種別によって看護師の年収には明確な差が見られます。国立大学病院の平均年収は498万3,270円、公立大学病院は497万2,674円、私立大学病院は525万6,537円となっています。
看護師全体の平均年収が508万円であることを考慮すると、大学病院で働く看護師は総じて高い年収を得ていることがわかります。
特に私立大学病院の年収が高くなっている背景には、基本給に加えて充実した手当体系があります。夜勤手当や特殊勤務手当など、様々な手当が年収の上積みにつながっています。
一方、公立大学病院と国立大学病院はほぼ同等の年収水準となっており、安定した給与体系と充実した福利厚生が特徴となっています。
経験年数による年収推移
新卒から3年目までの一般病院における年収は、公立病院が平均450万円、私立病院が平均390万円となっており、約60万円の差が生じています。5年目になると公立病院が平均480万円、私立病院が平均420万円と、その差は維持される傾向にあります。
さらに10年目では公立病院が平均550万円、私立病院が平均480万円と、差が70万円に広がることもあります。
地域による年収の違い
都市部と地方では年収に大きな差が生じます。東京都の場合、地域手当が基本給の20%となるため、公立病院では年収が更に増加します。一方、地方では地域手当が少なくなり、年収の差は縮まる傾向にあります。
この地域差は、生活費や物価の違いを反映したものとなっています。
昇給システムの違い
公立病院の昇給制度
公立病院における昇給は、地方公務員の給与制度に準じて運用されています。毎年1月の勤務評定を経て、4月に定期昇給が実施されます。
標準的な昇給額は年間で約8,000円から12,000円程度となっており、勤務成績が特に優秀な場合は特別昇給の対象となることもあります。
また、職位が上がると号俸の上がり幅も大きくなり、副師長や看護師長への昇進時には大幅な給与アップが期待できます。
私立病院の昇給制度
私立病院では、独自の人事評価制度に基づいて昇給が決定されます。評価項目には、看護技術や知識に加え、チームワークや患者対応力なども含まれます。昇給額は病院によって大きく異なりますが、平均的な昇給額は年間で6,000円から15,000円程度です。
特に実績を上げた看護師には、年間20,000円以上の昇給が適用されるケースもあります。
諸手当の計算方法と実例
時間外勤務手当の計算
公立病院の時間外勤務手当は、基本給をもとに計算されます。平日の残業では時給の125%、休日勤務では135%が支給されます。
例えば、基本給30万円の場合、時給約2,000円となり、1時間の残業で2,500円程度が支給されます。私立病院でも同様の計算方法が採用されていますが、割増率は病院によって異なります。
夜勤手当の詳細
夜勤手当の計算方法も設置主体によって異なります。公立病院では、深夜勤務(22時から5時)の場合、基本給の25%増しとなり、これに夜勤手当の基本額が加算されます。
例えば、基本給30万円の看護師が月8回の夜勤を行った場合、夜勤手当だけで月額96,000円程度となります。私立病院の場合、一律の金額設定が多く、一回あたり10,000円から15,000円程度となっています。
給与モデルケース
新卒看護師の場合
新卒看護師の初年度給与をモデルケースとして示します。公立病院では、基本給21万円に地域手当4.2万円(都市部の場合)、夜勤手当8万円(月8回)、その他手当2万円を加えると、月収は約35.2万円となります。
年間賞与4.45ヶ月分を加えると、年収は約500万円となります。一方、私立病院では、基本給20万円に夜勤手当7万円、その他手当1.5万円を加えた月収約28.5万円で、年間賞与3.5ヶ月分を加えると、年収は約420万円程度となります。
経験10年目看護師の場合
経験10年目の看護師の場合、公立病院では基本給32万円に各種手当を加えた月収が45万円程度となり、賞与を含めた年収は約650万円に達します。
私立病院では基本給28万円に各種手当を加えた月収が40万円程度で、年収は約580万円となります。ただし、これらの金額は病院の規模や地域、個人の実績によって変動することがあります。
賞与・手当の比較

看護師の実収入を大きく左右する要素として、賞与と各種手当があります。公立病院と私立病院では、これらの支給体系や金額に大きな違いがあり、年収に大きな影響を与えています。このセクションでは、両者の違いを詳しく解説していきます。
賞与(ボーナス)制度の詳細
公立病院の賞与支給
公立病院の賞与は2024年度実績で年4.45か月分となっています。6月と12月の2回に分けて支給され、期末手当と勤勉手当に分かれています。期末手当は2.6か月分、勤勉手当は1.85か月分が標準となっており、勤務実績による増減も考慮されます。
具体的な計算方法は、基本給に扶養手当を加えた額に支給月数を乗じる形となります。勤続20年以上のベテラン看護師の場合、さらに0.15か月分が加算されます。
私立病院の賞与支給
私立病院の賞与は年3.0から4.0か月分が一般的で、病院の経営状況により変動します。また、評価制度との連動性が強く、個人の実績が反映されやすい傾向にあります。
大規模な私立病院では公立病院と同等かそれ以上の支給実績がありますが、中小規模の病院では3.0か月分程度となることが多いです。支給時期は公立病院と同様に6月と12月が一般的ですが、病院によっては3月に決算賞与が追加支給されるケースもあります。
各種手当の制度と金額
夜勤手当の詳細
公立病院の夜勤手当は一回あたり8,000円から12,000円程度で、準夜勤と深夜勤で異なります。具体的には、準夜勤(16時から24時)が8,000円程度、深夜勤(0時から8時)が12,000円程度となっています。
また、2交代制と3交代制で金額が異なることもあります。私立病院では6,000円から10,000円程度となっており、やや低めの設定となっていますが、夜勤回数の制限が緩やかな場合もあります。
住宅手当の運用
公立病院では最大28,500円まで支給される地域が多く、世帯主の場合は更に加算されることがあります。
具体的には、賃貸の場合は家賃の額に応じて支給され、持ち家の場合も一定額が支給されます。私立病院では平均20,000円程度の設定が一般的で、単身者と世帯主で支給額に差をつけている場合もあります。
ただし、病院独自の職員寮を完備している場合は、住宅手当の代わりに家賃補助として運用されることもあります。
通勤手当の支給
公立病院では実費支給が基本となっており、電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合は全額が支給されます。自家用車通勤の場合も、距離に応じた支給額が定められており、月額上限は55,000円程度となっています。
私立病院では上限を設けているケースが多く、一般的に月額55,000円程度が上限となっています。また、自家用車通勤の場合は、ガソリン代や車両維持費の一部として、距離に応じた金額が設定されています。
その他の手当
その他にも様々な手当が設定されています。公立病院では、扶養手当(配偶者13,000円、子一人につき6,500円)、特殊勤務手当(感染症病棟など)、時間外勤務手当(基本給の125%から135%)などが整備されています。
私立病院でも同様の手当制度はありますが、金額や支給条件は病院によって大きく異なります。特徴的なものとして、私立病院では資格手当(認定看護師、専門看護師など)が充実している傾向にあります。
このように、賞与や手当は病院の設置主体によって大きく異なり、実収入に大きな影響を与えます。特に公立病院は制度が明確で安定している一方、私立病院は病院の方針や経営状況によって柔軟に設定されていることが特徴となっています。
福利厚生と退職金制度

看護師の長期的な経済基盤を支える重要な要素として、福利厚生と退職金制度があります。公立病院と私立病院では、これらの制度設計に大きな違いがあり、生涯賃金に影響を与えます。
このセクションでは、両者の制度の違いと具体的な内容について詳しく解説します。
福利厚生制度の詳細比較
社会保険制度の違い
公立病院では地方公務員共済組合に加入し、医療保険や年金制度が整備されています。掛け金は給与の約11%程度ですが、手厚い保障が特徴です。共済組合では、医療費の自己負担が2割に抑えられ、付加給付も充実しています。
また、年金については、厚生年金に職域加算が上乗せされる形となっています。私立病院では健康保険組合または協会けんぽに加入し、掛け金は給与の約12%程度となっています。
医療費の自己負担は3割が基本ですが、付加給付の内容は加入している保険者によって異なります。
職員寮と住居支援
公立病院では単身寮や世帯寮が完備されていることが多く、寮費は月額10,000円から30,000円程度に抑えられています。築年数は比較的古い施設が多いものの、立地条件の良い物件が多いのが特徴です。
また、寮費補助や住宅手当との併用が可能な場合もあります。私立病院でも職員寮を提供していますが、設置状況や家賃補助の程度は病院によって大きく異なります。
最近では、新築や築浅の寮を整備する私立病院も増えており、福利厚生の充実を図っています。
休暇制度の運用
公立病院の年次有給休暇は初年度から20日付与され、最大40日まで繰り越しが可能です。さらに、夏季休暇(5日程度)、結婚休暇(5日程度)、忌引休暇などの特別休暇も充実しています。
育児休業は3年まで取得可能で、復職後の短時間勤務制度も整備されています。私立病院の年次有給休暇は労働基準法に準じて初年度10日からスタートし、勤続年数に応じて最大20日まで増加します。
特別休暇の日数は病院によって異なりますが、近年は公立病院に準じた制度を整備する病院が増えています。
退職金制度の詳細
公立病院の退職金制度
公立病院の退職金は、地方公務員退職手当法に基づいて支給されます。退職時の基本給に支給率を掛けて計算され、勤続20年で概ね給与の2年分となります。
具体的な計算例として、基本給40万円で20年勤続の場合、約960万円の退職金となります。また、定年退職の場合は割増があり、さらに増額されます。
公立病院の退職金は、安定した金額が保証されている点が特徴です。
私立病院の退職金制度
私立病院の退職金は、病院独自の規定または中小企業退職金共済制度に基づいて支給されます。一般的な支給水準は、勤続20年で給与の1から1.5年分程度となっています。
大規模病院では公立病院に近い水準を設定していることもありますが、中小規模の病院では金額が抑えられる傾向にあります。
ただし、近年は人材確保の観点から、退職金制度を充実させる私立病院が増えています。
この福利厚生と退職金制度の違いは、長期的なキャリア形成を考える上で重要な判断材料となります。
特に若手看護師の方々は、将来的な生活設計を考慮しながら、これらの制度の違いを考慮することをお勧めします。
福利厚生施設の利用
院内保育所の整備状況
公立病院の院内保育所は、公的助成を受けて運営されているケースが多く、利用料金は月額2万円から3万円程度に設定されています。
また、24時間保育や病児保育にも対応している施設が多く、夜勤のある看護師でも安心して子育てと仕事を両立できる環境が整っています。
私立病院でも院内保育所の設置は進んでいますが、運営方式や利用料金は病院によって異なります。近年は保育所に加えて、学童保育施設を併設する病院も増えています。
職員食堂と休憩施設
公立病院の職員食堂は、補助金により食事代が抑えられており、一食400円から600円程度で利用できます。
また、24時間利用可能な休憩室や仮眠室も整備されています。私立病院では、アウトソーシング業者による運営が一般的で、食事代は600円から800円程度となっています。
ただし、最近では職員の健康管理の観点から、栄養バランスの良い食事を提供する病院が増えています。
教育研修制度の充実度
継続教育システム
公立病院では、年間教育計画に基づいた体系的な研修制度が整備されています。院内研修は勤務時間内に実施され、参加費用も病院負担となります。
また、学会参加や資格取得に対する助成制度も充実しており、年間5万円から10万円程度の補助が受けられます。私立病院でも同様の教育制度を設けていますが、補助金額や研修時間の設定は病院によって異なります。
キャリアアップ支援
公立病院では、認定看護師や専門看護師の資格取得を目指す看護師に対して、学費補助や長期休職制度を設けています。
具体的には、学費の半額程度(上限100万円程度)の補助と、最長2年間の休職制度が利用できます。私立病院でも同様の支援制度を整備する施設が増えていますが、支援内容や条件は病院の方針によって大きく異なります。
このように、福利厚生と退職金制度は、単なる待遇面だけでなく、キャリア形成や生活の質に大きな影響を与える重要な要素となっています。
特に長期的なキャリアプランを考える際には、これらの制度の違いを十分に考慮することが重要です。
キャリアパスと将来性

看護師のキャリア形成において、公立病院と私立病院では異なる特徴と機会が存在します。このセクションでは、両者のキャリアパスの違いや将来性について、具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。
昇進制度の特徴
公立病院の昇進システム
公立病院では、経験年数と実績に基づいた明確な昇進制度が確立されています。
一般的なキャリアパスとして、入職後3年程度でリーダー看護師、5年程度で主任看護師、7年から10年程度で副看護師長、そして15年程度で看護師長というステップを踏んでいきます。
各職位への昇進には、院内外での研修受講や資格取得が必要となることもあります。
私立病院の昇進システム
私立病院では、より柔軟な昇進制度が採用されています。実力主義の傾向が強く、若手でも優秀な人材は早期に管理職への道が開かれています。
一般的に、入職後2年程度でリーダー看護師、4年程度で主任看護師、6年から8年程度で副看護師長、そして12年程度で看護師長への昇進機会があります。
専門性の向上機会
公立病院での専門キャリア
公立病院では、専門看護師(CNS)や認定看護師の資格取得を積極的に支援しています。資格取得にかかる費用の補助制度が充実しており、教育課程への通学時間も確保されやすい環境です。
また、取得した資格を活かせる専門外来の設置や、院内教育者としての役割も期待されます。診療科の異動も計画的に行われ、幅広い経験を積むことが可能です。
私立病院での専門キャリア
私立病院では、病院の特色や専門性に応じた資格取得支援が行われています。特定の診療科に特化した病院では、その分野でのスペシャリストとして成長できる機会が多くあります。
また、チーム医療のリーダーとしての役割や、病院経営への参画機会も提供されています。
教育体制と成長機会
公立病院の教育システム
公立病院では、体系的な教育プログラムが整備されています。新人教育では、プリセプター制度による1年間の手厚い指導が行われ、2年目以降も段階的な教育計画に基づいて成長をサポートします。
また、他の公立病院との人事交流や、行政との連携による研修機会も豊富です。
私立病院の教育システム
私立病院では、病院の規模や特色に応じた独自の教育システムが構築されています。大規模病院では公立病院同様の体系的な教育が行われ、中小規模の病院ではよりきめ細かな個別指導が特徴となっています。
また、最新の医療技術や機器の導入に伴う専門的な研修機会も多く設けられています。
長期的なキャリア展望
公立病院でのキャリア展望
公立病院では、看護部門のトップである看護部長への道筋が明確です。また、病院管理者としての道も開かれており、医療行政職へのキャリアチェンジも可能です。
定年後も、非常勤職員として経験を活かした働き方を続けることができ、安定した長期キャリアを築くことができます。
私立病院でのキャリア展望
私立病院では、看護部長に加えて、病院経営陣の一員として参画する機会も増えています。また、グループ病院間での人事異動や、関連施設での新たな役割にチャレンジする機会も豊富です。
起業や診療所の立ち上げなど、独立志向の看護師にとっても貴重な経験を積むことができます。
このように、公立病院と私立病院では、キャリアパスや将来性に異なる特徴があります。自身の目指すキャリアや働き方に合わせて、適切な環境を選択することが重要です。
選択のポイント

公立病院と私立病院の選択は、看護師としてのキャリアを大きく左右する重要な決断となります。このセクションでは、それぞれの特徴を踏まえた上で、自身に適した病院を選択するための具体的なポイントについて解説します。
適性による選択基準
公立病院が向いている看護師の特徴
公立病院は、長期的な視点でキャリアを築きたい看護師に適しています。具体的には、段階的な昇進を望む方、安定した給与体系を重視する方、行政との連携に興味がある方などが該当します。
また、ワークライフバランスを重視する看護師にとっても、休暇制度が充実している公立病院は魅力的な選択肢となります。
私立病院が向いている看護師の特徴
私立病院は、より柔軟なキャリア形成を望む看護師に向いています。実力主義による早期昇進を目指す方、特定の診療科でスペシャリストとして成長したい方、病院経営に参画したい方などにとって、私立病院は大きな可能性を提供します。
また、給与面での交渉の余地が大きく、実力次第で高収入を得られる機会も多くあります。
生活スタイルに応じた選択
育児との両立を考える場合
育児との両立を考える看護師にとって、院内保育所の有無や育児支援制度の充実度は重要な判断材料となります。公立病院では制度が標準化されており、育児休業の取得や復職後の短時間勤務などがスムーズに行えます。
私立病院でも近年は支援体制を強化しており、24時間保育や病児保育などの独自のサービスを提供する施設も増えています。
転居を伴う異動の可能性
公立病院では、同一自治体内での異動が発生する可能性があります。特に都道府県立病院などでは、広域での異動も考慮する必要があります。
一方、私立病院では基本的に本人の希望を考慮した異動となりますが、グループ病院間での異動の可能性もあります。
経験年数による選択の違い
新卒看護師の場合
新卒看護師にとって、教育体制の充実度は重要な判断基準となります。公立病院では標準化された新人教育プログラムが整備されており、基礎からしっかりと学ぶことができます。
私立病院でも独自の教育システムを構築しており、より実践的な経験を早期から積むことができる環境も整っています。
中堅看護師の場合
経験5年以上の中堅看護師は、自身の専門性や将来のキャリアビジョンに基づいた選択が重要となります。
公立病院では資格取得支援や専門外来の設置など、専門性を高める機会が充実しています。
私立病院では、より専門的な分野での活躍や、管理職への早期登用などの機会が提供されています。
このように、公立病院と私立病院の選択は、個人の価値観やライフスタイル、キャリアビジョンによって最適な答えが異なってきます。
それぞれの特徴を十分に理解した上で、自身に合った環境を選択することが重要です。
働き方の優先度による選択
残業時間を重視する場合
公立病院では労働時間管理が厳格で、残業時間は月平均10時間から15時間程度に抑えられています。また、残業代は確実に支給され、休日出勤の振替休日取得も徹底されています。
私立病院では病院によって残業時間にばらつきがありますが、近年は働き方改革の影響で労働時間管理を強化する施設が増えています。
夜勤回数を考慮する場合
公立病院では夜勤回数が月8回程度と標準化されており、妊娠中や育児中の軽減制度も整備されています。私立病院では病院の規模や方針によって夜勤回数が異なり、月4回から10回程度とばらつきがあります。
ただし、夜勤専従制度を導入している私立病院もあり、自身の希望する働き方を選択できる可能性が高くなっています。
長期的な経済面での選択
退職後の生活を見据えた場合
公立病院では共済年金が適用され、退職金も比較的高額となるため、老後の経済的な安定が期待できます。また、再雇用制度も整備されており、定年後も継続して働くことができます。
私立病院では企業年金の導入や退職金制度の充実度は様々ですが、高度な専門性を活かしたセカンドキャリアの構築がしやすい環境にあります。
このように、公立病院と私立病院の選択においては、現在の状況だけでなく、将来のライフプランも含めて総合的に判断することが重要となります。
自身のキャリアビジョンや生活スタイル、価値観に合わせて、最適な環境を選択していただければと思います。
地域別の公私立病院比較

公立病院と私立病院の待遇は、地域によって大きな差があります。このセクションでは、地域ごとの特徴や給与水準の違い、そして地域特有の制度について詳しく解説していきます。
都市部の特徴と待遇
東京都の場合
東京都では公立病院、私立病院ともに給与水準が高く設定されています。公立病院では地域手当が基本給の20%と全国最高水準で、年収は新卒で420万円、経験10年で650万円程度となっています。
私立病院も競争力維持のため、公立病院に近い、もしくはそれ以上の給与水準を設定している施設が多く見られます。特に大学病院では年収700万円を超えるケースもあります。
大阪府の場合
大阪府の公立病院では地域手当が16%で、年収は新卒で400万円、経験10年で620万円程度となっています。
私立病院は施設による差が大きく、大規模病院では公立病院並みの待遇がある一方、中小規模病院では年収が15%程度低くなる傾向があります。
地方都市の特徴と待遇
県庁所在地の場合
県庁所在地の公立病院では地域手当が10%前後となり、年収は新卒で380万円、経験10年で580万円程度です。
私立病院では公立病院の90%程度の給与水準が一般的ですが、看護師不足を補うため、独自の手当や福利厚生の充実で差別化を図っています。
その他の地方都市の場合
地方都市では地域手当が3%から6%程度となり、公立病院の年収は新卒で360万円、経験10年で540万円程度です。
私立病院では更に給与水準が低くなる傾向にありますが、住宅手当の充実や、都市部より相対的に安い生活費を考慮する必要があります。
地域特有の制度と特徴
過疎地域の優遇制度
過疎地域の公立病院では、医療従事者確保のため、特別地域手当や赴任手当などの独自の手当が設けられています。具体的には、月額20,000円から50,000円程度の特別手当や、赴任時の一時金として100,000円から300,000円程度が支給されます。
私立病院でも同様の制度を設けているケースがありますが、金額は公立病院より低めとなっています。
離島・へき地の待遇
離島やへき地の医療機関では、特殊勤務手当が充実しています。公立病院では月額50,000円程度の離島手当に加え、住居費の全額補助や赴任費用の補助などが整備されています。
私立病院でも同様の制度はありますが、補助額は公立病院の80%程度となることが多いです。
このように、地域による待遇の違いは、単純な給与額の比較だけでなく、地域手当や特別手当、生活費なども含めて総合的に判断する必要があります。
特に地方での就職を考える場合は、給与面だけでなく、生活環境や将来的なキャリアプランも含めて検討することをお勧めします。
都道府県別の特徴的な制度
独自の支援制度がある地域
神奈川県では、公立病院において独自の人材確保支援制度を設けており、基本給に加えて最大月額50,000円の特別支援手当が支給されます。
また、千葉県では新規採用看護師に対して、最大200,000円の就職支援金制度を設けている公立病院もあります。
私立病院でも地域の実情に応じて、独自の支援制度を設けているケースが増えています。
都道府県独自の奨学金制度
北海道や東北地方の自治体では、看護師確保のための独自の奨学金制度を設けています。公立病院に一定期間勤務することを条件に、返済免除制度が適用される仕組みとなっています。
私立病院でも同様の制度を導入する動きが出てきており、地域医療の担い手確保に向けた取り組みが進んでいます。
地域における福利厚生の違い
住宅補助の地域差
首都圏の公立病院では、高額な家賃に対応するため、住宅手当の上限が月額60,000円に設定されているケースもあります。一方、地方都市では月額20,000円から30,000円程度が一般的です。
私立病院でも地域の家賃相場に応じて同様の対応を行っていますが、病院独自の寮を完備することで、実質的な住居費補助を行っているケースも多く見られます。
このように、地域によって給与体系や福利厚生制度には大きな違いがあり、また同じ地域内でも公立・私立で異なる特徴があります。
転職や就職を考える際は、これらの地域特性を十分に理解した上で、判断することが重要です。
病院規模別の待遇比較

病院の規模によって、看護師の待遇には大きな差が生じます。このセクションでは、病床数や施設規模による給与体系の違い、福利厚生の充実度について、具体的な数値を交えながら解説していきます。
大規模病院の待遇(500床以上)
公立大規模病院の特徴
500床以上の公立大規模病院では、充実した給与体系が整備されています。基本給は一般的な公立病院より5%から10%高く設定されており、夜勤手当も一回あたり12,000円から15,000円と高水準です。
また、三次救急や高度専門医療に対する特殊勤務手当も充実しており、月額で30,000円から50,000円程度が追加されます。
私立大規模病院の特徴
私立の大規模病院では、公立病院に匹敵する、もしくはそれ以上の給与水準を設定しているケースが多くあります。特に大学病院では、教育手当や研究手当など、独自の手当体系を備えており、年収では公立病院を上回ることもあります。
具体的には、経験10年目の看護師で年収650万円から700万円程度となっています。
中規模病院の待遇(200-499床)
公立中規模病院の特徴
200床から499床規模の公立病院では、標準的な公務員給与体系が適用されます。
地域の中核病院として、安定した給与水準が保たれており、夜勤手当は一回あたり10,000円から12,000円程度です。救急対応や専門外来での勤務に対する手当も整備されています。
私立中規模病院の特徴
私立の中規模病院では、地域や病院の経営状況によって待遇に大きな差が生じます。
大規模病院の90%程度の給与水準を確保している病院がある一方で、基本給を抑え、実績に応じた手当で調整している病院もあります。夜勤手当は一回あたり8,000円から10,000円程度が一般的です。
小規模病院の待遇(200床未満)
公立小規模病院の特徴
200床未満の公立病院でも、基本的な給与体系は他の公立病院と同様です。ただし、夜勤回数や時間外勤務が多くなる傾向があり、実質的な年収は中規模病院と同程度となることも多いです。
地域医療を支える重要な役割を担っているため、特別地域手当などが設定されているケースもあります。
私立小規模病院の特徴
私立の小規模病院では、給与水準は公立病院より15%から20%程度低くなる傾向にあります。その代わり、働き方の自由度が高く、個人の希望に応じた勤務形態を選択できるケースが多いです。
また、病院独自の評価制度により、能力や実績に応じた昇給や賞与の上乗せを行っている施設もあります。
このように、病院の規模によって待遇面では大きな差が生じますが、それぞれの規模に応じた特徴や利点があります。自身のキャリアプランや希望する働き方に合わせて、適切な規模の病院を選択することが重要です。
診療科別の特徴と待遇

診療科によって看護師の業務内容や必要なスキル、そして待遇には大きな違いがあります。このセクションでは、主要な診療科ごとの特徴と待遇の違いについて、公立・私立病院それぞれの視点から解説していきます。
救急科・集中治療室の特徴
公立病院の救急部門
公立病院の救急部門では、高度な専門性が求められることから、基本給に加えて月額20,000円から40,000円程度の専門手当が支給されます。
また、夜勤や時間外勤務も多いため、実質的な年収は一般病棟勤務と比べて15%から20%高くなる傾向にあります。三次救急を担う施設では更に特殊勤務手当が加算され、年収は一般病棟勤務より100万円程度高くなることもあります。
私立病院の救急部門
私立病院の救急部門でも、専門性の高さから独自の手当体系が設けられています。救急専門手当として月額15,000円から35,000円程度が支給され、夜勤手当も一般病棟より割増率が高く設定されています。
特に救急専門病院では、年収ベースで公立病院と同等またはそれ以上の待遇を提供しているケースもあります。
手術室・外来部門の特徴
公立病院の手術室
手術室勤務では、清潔管理や器械出しなど専門的なスキルが必要となります。公立病院では手術室勤務手当として月額15,000円から25,000円が支給され、オンコール対応がある場合は更に待機手当が加算されます。
また、心臓手術や臓器移植など高度な手術に対する特別手当も設定されています。
私立病院の手術室
私立病院の手術室でも専門手当は充実しており、月額10,000円から30,000円程度が支給されます。特に美容外科やレーザー治療など、特殊な手術を多く扱う私立病院では、技術手当として更に高額の手当が設定されているケースもあります。
産婦人科・小児科の特徴
公立病院の産婦人科・小児科
周産期医療を担う公立病院では、ハイリスク分娩への対応や新生児集中ケアなど、高度な専門性が求められます。そのため、月額20,000円程度の専門手当に加え、分娩件数に応じた手当が支給されます。
小児科では、夜間の緊急対応も多いため、特殊勤務手当が加算され、年収は一般病棟より50万円から80万円程度高くなることがあります。
私立病院の産婦人科・小児科
私立病院の産婦人科でも専門手当は充実しており、分娩件数に応じた実績手当が設定されています。特に産科専門病院では、年間分娩件数に応じたインセンティブ制度を設けているケースもあります。
小児科専門病院では、夜間対応手当や専門資格手当など、独自の手当体系が整備されています。
このように、診療科によって求められる専門性や業務内容が異なり、それに応じて待遇も変わってきます。自身の興味や適性に合わせて診療科を選択することで、より充実したキャリアを築くことができます。
慢性期病棟・療養型病棟の特徴
公立病院の慢性期病棟
公立病院の慢性期病棟では、長期的な患者ケアが中心となります。夜勤回数は一般病棟より少なめですが、介護度の高い患者が多いため、身体的負担に対する手当として月額10,000円から15,000円程度が支給されます。
また、リハビリテーション連携や在宅移行支援など、多職種連携に関する業務手当も設定されています。
私立病院の慢性期病棟
私立病院の慢性期病棟では、きめ細かな患者ケアが評価され、独自の評価制度に基づく手当が支給されるケースが増えています。
特に在宅復帰率の向上に貢献した場合には、実績手当として月額5,000円から15,000円程度が追加支給される制度を設けている病院もあります。
精神科病棟の特徴
公立病院の精神科
公立病院の精神科では、患者対応の特殊性から精神科専門手当として月額25,000円程度が支給されます。また、措置入院患者の対応や急性期治療病棟での勤務には、追加の特殊勤務手当が設定されています。
保護室対応や行動制限時の対応など、高度な専門性が求められる業務に対しては、別途手当が加算されます。
私立病院の精神科
私立の精神科専門病院では、基本給は一般病院より若干低めの設定となることが多いものの、精神科経験や専門資格に応じた手当体系が整備されています。
特に認知症ケアや精神科救急など、特定の専門分野に特化した病院では、それぞれの分野に応じた独自の手当制度を設けています。
このように、各診療科にはそれぞれの特徴があり、求められる専門性や業務内容に応じて待遇も異なってきます。自身の志向や将来のキャリアプランに合わせて、診療科を選択することが重要です。
ライフステージ別の選択ポイント

看護師のキャリアは、ライフステージによって優先すべき条件が変化します。このセクションでは、年代や生活状況に応じた公立・私立病院の選択ポイントについて、具体的に解説していきます。
新卒・若手看護師の選択ポイント
新卒1-3年目の特徴
新卒看護師にとって、教育体制の充実度は最も重要な選択基準となります。公立病院では、プリセプター制度による1年間の手厚い指導体制が整備されており、基本的な看護技術の習得に時間をかけることができます。
また、初任給は都市部で月給24万円程度からスタートし、3年目には28万円程度まで昇給します。私立病院では、より実践的な経験を早期から積むことができ、能力に応じた昇給も期待できます。
初任給は公立病院より若干低めですが、夜勤手当などの実務手当が充実している傾向にあります。
結婚・出産期の選択ポイント
育児との両立を考える時期
結婚・出産期の看護師にとって、仕事と家庭の両立支援制度は重要な判断材料となります。公立病院では、産前産後休暇や育児休業の取得実績が豊富で、復職後の短時間勤務制度も充実しています。
また、院内保育所の利用料も月額2万円程度と比較的安価に設定されています。私立病院でも両立支援制度は整備されていますが、病院によって利用のしやすさに差があり、事前の確認が必要です。
特に大規模な私立病院では、24時間保育や病児保育など、独自の支援制度を設けているケースも増えています。
中堅看護師の選択ポイント
キャリアアップを目指す時期
中堅期は専門性を高め、キャリアアップを図る重要な時期となります。公立病院では、認定看護師や専門看護師の資格取得支援制度が充実しており、学費補助や長期休職制度を利用できます。
資格取得後は月額2万円から3万円程度の資格手当も支給されます。私立病院では、より実践的な専門性を身につける機会が多く、特定の診療科でのスペシャリストとして評価される傾向にあります。
また、管理職への昇進も公立病院と比べて早い段階で検討することができます。
このように、ライフステージに応じて重視すべきポイントは変化していきます。自身の状況と将来のプランを考慮しながら、最適な環境を選択することが重要です。
ベテラン看護師の選択ポイント
40代以降のキャリア展開
ベテラン期には、これまでの経験を活かした働き方を選択できます。公立病院では、看護師長などの管理職として安定したキャリアを築くことができ、職位手当として月額4万円から6万円が追加されます。
また、教育担当として後進の指導にあたることで、教育手当が月額2万円程度支給されるケースもあります。私立病院では、病院経営への参画機会が増え、より幅広い役割を担うことができます。
さらに、グループ病院間での異動や関連施設での新たな挑戦など、多様なキャリアパスを選択できます。
定年前後の選択ポイント
60代のキャリア継続
定年を控えた時期には、働き方の柔軟性が重要な選択基準となります。公立病院では、定年後も再任用制度を利用して65歳まで継続勤務が可能で、給与水準も一定程度維持されます。
具体的には、定年前の70%から80%程度の給与が保障されます。私立病院では、より柔軟な勤務形態を選択でき、短時間勤務やパートタイム勤務など、体力や生活スタイルに合わせた働き方が可能です。
また、専門性を活かした非常勤職員としての雇用機会も豊富です。
シニア世代の新たな選択肢
65歳以降も、経験を活かした働き方を選択できます。公立病院では、会計年度任用職員として、外来や健診部門での勤務機会があります。時給は2,000円から2,500円程度で、週2-3日程度の勤務が一般的です。
私立病院では、看護師不足を補うため、経験豊富なシニア看護師の採用を積極的に行っているケースも多く、勤務時間や業務内容について柔軟な対応が可能です。
このように、年齢やキャリアステージによって、公立・私立病院それぞれの特徴を活かした選択が可能です。長期的なキャリアプランを考える上で、各ライフステージにおける優先順位を明確にすることが重要です。
実際の転職事例集

公立病院と私立病院の選択は、個々の状況によって最適な答えが異なります。このセクションでは、実際の転職事例を詳しく分析し、転職を考える看護師の方々の参考となる具体的な情報を提供していきます。
私立から公立病院への転職事例
都内大学病院からの転職事例
Aさん(34歳・女性)は、都内の私立大学病院で10年間勤務後、公立病院への転職を決意しました。私立病院では年収580万円でしたが、夜勤が月10回以上あり、仕事と育児の両立に困難を感じていました。
公立病院への転職後は、夜勤が月8回に減少し、年収は540万円とやや減少したものの、有給休暇の取得がしやすくなり、ワークライフバランスが大きく改善しました。
また、地方公務員共済組合の加入により、医療費の自己負担も軽減されています。
地方私立病院からの転職事例
Bさん(29歳・男性)は、地方の私立病院から県立病院への転職を果たしました。
私立病院では年収420万円でしたが、公立病院では初年度から460万円となり、安定した給与体系と確実な昇給を実現することができました。
また、教育体制が充実しており、認定看護師の資格取得支援制度を利用して、キャリアアップを目指しています。
公立から私立病院への転職事例
市立病院からの転職事例
Cさん(42歳・女性)は、15年間勤務した市立病院から私立の専門病院への転職を決意しました。公立病院では年功序列の昇進が一般的でしたが、私立病院では専門性を活かした役職に就くことができました。
年収は620万円から680万円に増加し、自身の専門分野でより充実したキャリアを築くことができています。
公立病院新人からの早期転職事例
Dさん(25歳・女性)は、公立病院で2年間の勤務経験を経て、私立の急性期病院へ転職しました。公立病院では基礎的な看護技術は習得できましたが、より実践的なスキルを身につけたいという思いから転職を決意。
私立病院では救急対応や専門的な治療に関わる機会が増え、技術向上のスピードが格段に上がりました。年収は若干減少しましたが、実務経験の充実度は大きく向上しています。
規模の異なる私立病院間の転職事例
中規模から大規模病院への転職事例
Eさん(38歳・女性)は、200床規模の私立病院から500床以上の大規模私立病院へ転職しました。以前の病院では年収450万円でしたが、転職後は520万円に増加。
また、専門性の高い医療に携わる機会が増え、キャリアアップの選択肢も広がりました。充実した教育制度により、新しい医療技術の習得もスムーズに進んでいます。
地域を跨いだ転職事例
都市部から地方への転職事例
Fさん(45歳・女性)は、東京の私立病院から地方の公立病院へ転職しました。年収は650万円から580万円に減少しましたが、住宅手当や赴任手当の支給があり、地方での生活費の低さを考慮すると、実質的な生活水準は向上しています。
さらに、地域医療に貢献できる充実感も得られ、仕事への満足度が高まっています。
このように、転職の成功事例は個々の状況や目的によって様々です。重要なのは、単純な給与比較だけでなく、働き方や将来のキャリアプラン、生活環境なども含めて総合的に判断することです。
これらの事例を参考に、自身の状況に最適な選択をすることをお勧めします。
おしえてカンゴさん!よくある質問

看護師の皆様から日頃多く寄せられる質問について、豊富な経験を持つベテラン看護師「カンゴさん」が詳しく回答します。実践的なアドバイスと具体的な対応方法について解説していきます。
給与・待遇に関する質問
公立病院の給与は本当に安定しているのでしょうか?
公立病院の給与は地方公務員の給与体系に基づいているため、非常に安定しています。毎年の昇給も確実で、勤続年数に応じて着実に給与が上がっていきます。
また、ボーナスも年間4.45か月分(2024年現在)が保証されており、長期的な生活設計が立てやすい環境となっています。
私立病院で給与交渉はできますか?
私立病院では、前職の給与や経験年数、保有資格などを考慮した給与交渉が可能です。特に転職時には、具体的な実績や専門性をアピールすることで、基本給や各種手当の増額を検討してもらえるケースが多くあります。
勤務条件に関する質問
公立病院は残業が多いと聞きますが、本当ですか?
公立病院では労働時間管理が厳格で、不必要な残業は認められない傾向にあります。ただし、救急対応や急変時の対応など、やむを得ない残業は発生します。
その場合は、必ず残業手当が支給され、代休取得も推奨されています。
私立病院の夜勤回数は調整できますか?
私立病院では、夜勤回数について個別の事情を考慮した調整が可能なケースが多くあります。育児や介護など、個人の状況に応じて夜勤回数を減らすことや、逆に夜勤専従として回数を増やすことも検討できます。
キャリアアップに関する質問
認定看護師の資格は公立・私立どちらが取得しやすいですか?
両者とも資格取得支援制度は整備されていますが、公立病院では体系的な支援制度があり、学費補助や長期休職制度が確立されています。
一方、私立病院では病院の方針により支援内容が異なりますが、より柔軟な対応が期待できるケースもあります。
このように、公立・私立病院それぞれの特徴を理解し、自身の状況に合わせた選択をすることが重要です。
まとめ

公立病院と私立病院の選択は、看護師としてのキャリアを左右する重要な決断となります。本記事で解説してきた内容を総括し、最適な選択のためのポイントを確認していきましょう。
重要な選択ポイントの整理
公立病院は安定した給与体系と充実した福利厚生が特徴で、長期的なキャリア形成を目指す方に適しています。地方公務員としての身分が保障され、年功序列での昇進や退職金制度も確立されています。
一方、私立病院は柔軟な給与体系と実力主義の評価制度が特徴で、専門性を活かしたキャリアアップや、より実践的な経験を積みたい方に向いています。
これからの展望
2024年現在、看護師の働き方は大きな転換期を迎えています。働き方改革の推進により、公立・私立病院ともに労働環境の改善が進んでおり、選択の幅は更に広がっています。
自身のキャリアプランやライフスタイルに合わせて、それぞれの特徴を活かした選択をすることで、より充実した看護師人生を送ることができるでしょう。