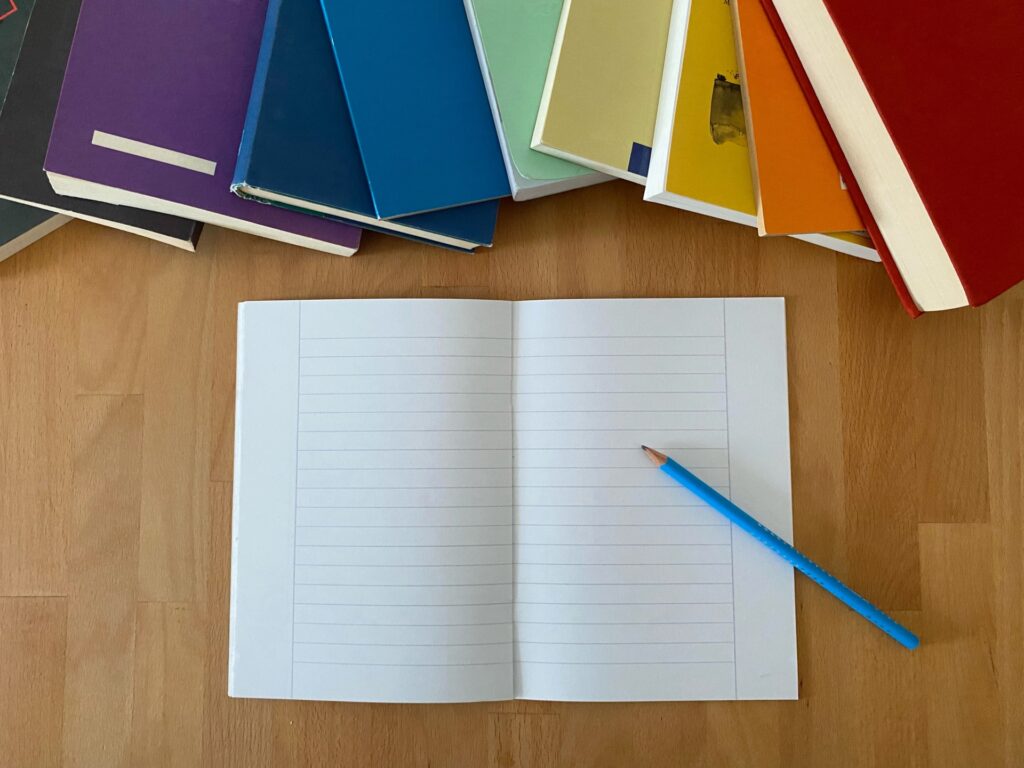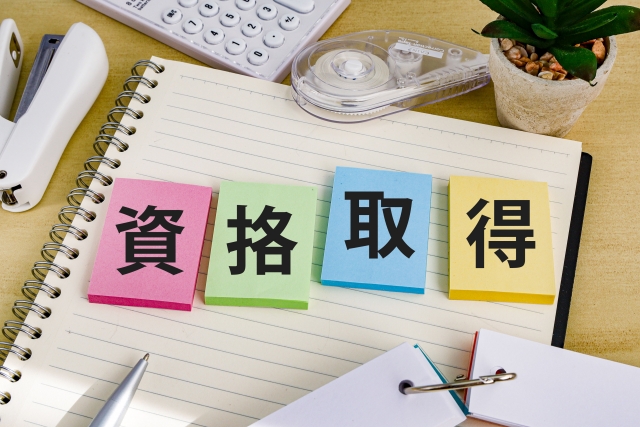看護師の転職における保険手続きは、将来の保障に関わる重要な要素です。本記事では、必要な保険の種類から具体的な手続き方法、実際の転職事例まで、保険の専門家と現役看護師への取材をもとに詳しく解説します。手続きの漏れがないよう、しっかりと確認していきましょう。
この記事で分かること
・転職時に必要な保険手続きの全体像と具体的な流れ
・手続きの期限と必要書類の完全リスト
・施設形態別の具体的な対応方法
・実際の転職事例と成功のポイント
この記事を読んでほしい人
・総合病院から診療所への転職を考えている看護師
・クリニック間での転職を検討している看護師
・訪問看護ステーションへの転職を予定している看護師
・初めての転職で保険手続きに不安がある看護師
1. 転職時に確認すべき保険の種類と基本知識

看護師の転職において、保険の切り替えは将来の生活保障に直結する重要な手続きです。2024年の制度改正により、電子申請の義務化やマイナンバーカードの活用が進んでいます。このセクションでは、実務経験豊富な社会保険労務士の監修のもと、保険の基礎知識から具体的な手続きの流れまで、最新の情報を交えて詳しく解説していきます。
1-1. 健康保険制度の理解と手続きのポイント
健康保険は医療費の自己負担を軽減し、病気やケガの際の経済的な支えとなる制度です。2024年度の制度改正により、特に電子申請の方法や保険料率に大きな変更が加えられています。
健康保険の基本的な仕組み
医療費の自己負担割合は原則として3割ですが、年齢や所得によって2割や1割になる場合もあります。70歳以上の方は、一定以上の所得がある場合を除き、2割または1割の負担となります。また、高額療養費制度を利用することで、月ごとの自己負担額に上限が設定されます。
2024年度の改正では、高額療養費制度の所得区分が見直され、より細かな区分が設定されました。具体的な自己負担限度額は以下のようになっています:
一般所得の場合(年収約370万円〜約770万円)
・入院時の限度額:月額80,100円+(医療費−267,000円)×1%
・外来時の限度額:月額18,000円
給付内容と申請方法
傷病手当金は、業務外の傷病により就労できない場合に支給される重要な給付金です。支給額は、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額の3分の2相当額となります。看護師の場合、夜勤手当なども標準報酬月額に含まれるため、一般的な事務職と比べて給付額が高くなる傾向があります。
具体的な計算例:
基本給:250,000円
夜勤手当:80,000円
その他手当:40,000円 の場合、
標準報酬月額は370,000円となり、 傷病手当金の日額は、370,000円÷30日×2/3=8,222円となります。
電子申請の活用とマイナンバーカード
2024年4月からの制度改正により、健康保険の給付申請はマイナポータルを通じた電子申請が標準となっています。従来の紙での申請と比べ、以下のメリットがあります。
申請から給付までの期間が短縮され、従来の2〜3週間から最短1週間程度になっています。また、申請状況のリアルタイム確認が可能で、不備があった場合も迅速な修正対応が可能です。特に、看護師の深夜勤務に対応し、24時間申請が可能な点は大きなメリットとなっています。
1-2. 厚生年金保険の重要性と手続きの実際
厚生年金保険は老後の年金受給額に直結する重要な制度です。2024年度の制度改正により、パートタイム労働者の加入要件が変更され、より多くの看護師が加入対象となっています。
加入期間の継続性確保
年金受給権に関わる加入期間の継続性は特に重要です。加入期間が25年以上あることが年金受給の要件となりますが、看護師の場合、結婚や育児による離職期間が生じやすいため、以下の点に注意が必要です。
第3号被保険者への切り替え:配偶者の扶養に入る場合、国民年金第3号被保険者への切り替え手続きが必要です。この手続きを怠ると、将来の年金受給額に影響を与える可能性があります。手続きは配偶者の勤務先を通じて行い、マイナンバーカードを利用した電子申請も可能です。
育児休業中の特例:育児休業中は申請により保険料が免除されますが、将来の年金額には影響しません。ただし、事業主を通じた申請が必要で、休業開始前に手続きを済ませておく必要があります。
標準報酬月額の決定方法
看護師の場合、基本給に加えて夜勤手当や特殊勤務手当などが加算されるため、標準報酬月額の決定には特に注意が必要です。
基本的な計算方法: 毎月の給与総額(基本給+諸手当)を報酬月額として、それを標準報酬月額の等級表にあてはめます。2024年度の等級表は、以下のように改定されています。
第1級:63,000円(報酬月額 〜63,000円) 第2級:73,000円(報酬月額 63,001円〜73,000円) (以降、等級ごとの詳細な金額を記載)
実際の計算例: 基本給:280,000円 夜勤手当(月8回):96,000円 その他手当:54,000円 合計:430,000円の場合 → 標準報酬月額は440,000円(第24級)に決定されます。
1-3. 雇用保険制度の適用と給付内容
雇用保険は失業時の生活保障だけでなく、育児休業給付金や介護休業給付金など、看護師のライフステージに応じた給付を受けられる重要な制度です。2024年度からは、デジタル化による手続きの簡素化が進んでいます。
適用要件と被保険者資格
2024年度の制度改正により、雇用保険の適用要件が見直されました。現在は以下の条件を満たす場合、原則として全ての労働者が被保険者となります。
勤務時間要件: 週20時間以上の勤務であること。複数の医療機関で勤務する場合、それぞれの勤務時間は合算されません。例えば、A病院で週15時間、B診療所で週10時間勤務する場合、いずれの勤務先でも雇用保険の対象とはなりません。
雇用期間要件: 31日以上の雇用見込みがあること。短期間の派遣や非常勤であっても、この要件を満たせば被保険者となります。特に看護師の場合、繁忙期の応援体制や夜勤専従など、多様な勤務形態があるため、個々のケースで確認が必要です。
各種給付金の内容と申請手続き
看護師に特に関係の深い給付金について、2024年度の給付内容と申請手続きを解説します。
育児休業給付金: 休業開始時の給与の67%(180日経過後は50%)が支給されます。夜勤手当等を含む賃金をベースに計算されるため、給付額が一般職と比べて高くなる傾向があります。
具体的な計算例:
基本給:300,000円
夜勤手当:80,000円
その他手当:40,000円
合計:420,000円の場合
休業開始後180日までの月額給付: 420,000円×67%=281,400円
180日経過後の月額給付: 420,000円×50%=210,000円
1-4. 労災保険の補償内容と請求手続き
医療現場特有のリスクに対応する労災保険は、看護師にとって特に重要な保険制度です。2024年度は新型感染症への対応も含め、補償内容が拡充されています。
業務上の災害認定基準
看護業務における特徴的な災害について、認定基準が明確化されています。
針刺し事故の場合: 事故発生後の感染症検査や予防的投薬も補償対象となります。具体的な補償内容は以下の通りです。
医療費:全額補償
休業補償:給与の80%相当額
通院費:実費支給
腰痛など慢性的な症状の場合:
患者の移乗介助や長時間の立ち仕事による腰痛は、業務との因果関係が認められやすくなっています。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
発症前の3ヶ月間に、重量物取扱いや同一姿勢での作業が通常の看護業務より過重であったこと。 基礎疾患や加齢による要因が主ではないことが医学的に認められること。
給付金の種類と請求方法
労災保険の給付金は、事故や疾病の種類によって複数の組み合わせが可能です。2024年度の制度では、以下のような給付内容が定められています。
療養補償給付: 業務上の負傷や疾病の治療にかかる費用が全額補償されます。看護師特有の事例として、以下のようなケースが補償対象となります。
感染症発症時の治療費: 新型コロナウイルスやその他の感染症に罹患した場合、業務との因果関係が認められれば補償対象となります。予防接種後の副反応による治療も、一定の条件下で対象となります。
メンタルヘルス不調の治療: 過重労働やハラスメントが原因のメンタルヘルス不調も、労災認定の対象です。特に夜勤を含む不規則な勤務体制による睡眠障害なども、業務起因性が認められやすくなっています。
休業補償給付: 療養のために休業を余儀なくされた場合、給与の80%相当額が支給されます。看護師の場合、夜勤手当等を含めた算定基礎額を基に計算されるため、以下のような計算となります。
算定例: 基本給:280,000円 夜勤手当:90,000円 職務手当:30,000円 合計:400,000円の場合
1日あたりの休業補償: 400,000円÷30日×80%=10,666円
1-5. 保険切り替えのタイミングと注意点
転職に伴う保険の切り替えは、退職日と入職日のタイミングが重要です。2024年度からは電子申請の普及により、手続きの簡素化が進んでいますが、以下の点には特に注意が必要です。
資格喪失と取得の時期
保険の切り替えは、それぞれ以下のタイミングで発生します。
健康保険・厚生年金保険:
資格喪失日:退職日の翌日
資格取得日:入職日当日
雇用保険:
資格喪失日:退職日の翌日
資格取得日:入職日当日
具体的なスケジュール例:
3月31日退職、4月1日入職の場合:
3月31日まで:前職の保険資格継続
4月1日:資格喪失と新規取得が同日
(健康保険証の切り替えまでのつなぎとして、資格喪失証明書を使用)
5月1日入職の場合:
4月1日〜4月30日:任意継続被保険者または国民健康保険に加入
5月1日:新規事業所での資格取得
保険料の精算と控除
月の途中で資格を喪失または取得した場合、保険料は日割り計算となります。具体的な計算方法は以下の通りです。
日割り計算の例:
標準報酬月額:360,000円
保険料率:健康保険13.3%、厚生年金18.3%
4月15日入職の場合:
健康保険料: 360,000円×13.3%×16日÷30日=25,536円
(労使折半のため、実際の個人負担は12,768円)
2. 転職時の保険手続き完全マニュアル

転職時の保険手続きは、退職から入職までの一連の流れを正確に把握し、期限内に必要な対応を行うことが重要です。2024年度は電子申請の本格導入により、手続き方法が大きく変更されています。このセクションでは、実際の手続きの流れを時系列で解説すると共に、看護師特有の注意点についても詳しく説明していきます。
2-1. 退職時の手続き準備と対応
退職が決まったら、まず保険関連の手続きスケジュールを立てることが重要です。2024年度からは電子申請が標準となりましたが、書類での手続きも併用されているため、両方の準備が必要です。
退職決定直後の必要手続き
退職の意思が固まった時点で、以下の順序で手続きを進めていきます。マイナンバーカードを利用した電子申請の場合でも、基本的な流れは同じです。
退職日の決定と通知:
退職日は保険の資格喪失日に直結するため、慎重に設定する必要があります。特に看護師の場合、夜勤シフトの調整も考慮する必要があります。具体的には、夜勤が月末にある場合、その勤務終了時刻が翌日になることも考慮して退職日を設定します。
健康保険証の使用可能期間:
退職後は速やかに保険証を返却する必要がありますが、2024年度からはマイナ保険証への移行が進んでいます。マイナ保険証を利用している場合は、オンラインで資格確認が可能なため、従来の保険証の返却は不要です。
必要書類の準備と取得
転職先で必要となる書類は、事前に漏れなく準備しておくことが重要です。2024年度の電子化に伴い、書類の発行方法も変更されています。
資格喪失証明書の取得:
健康保険の資格喪失証明書は、新しい職場での保険加入手続きに必要不可欠な書類です。2024年度からは電子発行にも対応しており、マイナポータルを通じて取得することが可能となっています。電子発行の場合、従来の書面発行と比べて発行までの時間が大幅に短縮され、最短で即日発行も可能です。ただし、マイナンバーカードの健康保険証利用の事前登録が必要となります。
雇用保険被保険者離職票の受け取り:
離職票は事業主が作成し、ハローワークでの手続きを経て発行されます。2024年度からは電子申請による手続きが可能となり、発行までの期間が短縮されています。特に看護師の場合、夜勤手当など変動的な賃金が含まれるため、賃金支払状況等証明書の記載内容を必ず確認する必要があります。
2-2. 健康保険・厚生年金の切り替え手続き
医療費の自己負担や将来の年金受給に直結する重要な手続きとなります。2024年度は電子申請の義務化に伴い、手続き方法が大きく変更されています。
資格喪失手続きの詳細
資格喪失手続きは、原則として事業主が行いますが、手続きの進捗状況は自身でも確認できるようになっています。マイナポータルを通じて、手続きの進捗状況をリアルタイムで確認することが可能です。
手続きの進捗確認方法:
マイナポータルにログイン後、申請状況の確認画面から手続きの進捗を確認できます。申請が受理されると、資格喪失証明書の電子発行が可能となります。電子発行された証明書は、スマートフォンやタブレットで表示することも可能で、新しい職場での手続きにも利用できます。
任意継続被保険者制度の活用
退職後、すぐに次の職場が決まっていない場合は、任意継続被保険者制度の利用を検討します。2024年度の制度改正により、申請手続きが簡素化され、オンラインでの手続きが可能となっています。
保険料の試算例:
直近の標準報酬月額が450,000円の場合、月々の保険料は以下のように計算されます。
健康保険料:
450,000円×13.3%=59,850円(2024年度の協会けんぽの平均保険料率を使用)
介護保険料(40歳以上の場合):
450,000円×1.82%=8,190円
合計月額保険料:68,040円
2-3. 雇用保険の手続きとポイント
雇用保険の手続きは、特に給付金の継続受給に関わる重要な手続きです。2024年度からは電子申請システムが刷新され、より使いやすくなっています。
離職票の受け取りと確認
離職票は失業給付を受ける際に必要となる重要な書類です。2024年度からは電子発行も可能となっていますが、記載内容の確認は特に慎重に行う必要があります。
賃金支払状況の確認:
看護師の場合、基本給に加えて夜勤手当や特殊勤務手当など、複数の手当が含まれることが一般的です。離職票の賃金支払状況欄には、これらの手当を含めた総支給額が正しく記載されているか確認が必要です。具体的には、直近6ヶ月分の給与明細と照らし合わせることで、記載漏れや計算ミスを防ぐことができます。
離職理由の確認:
離職理由は失業給付の受給資格に大きく影響します。特に夜勤の負担や勤務時間の調整など、看護師特有の理由がある場合は、その状況が適切に記載されているか確認することが重要です。2024年度からは、より詳細な離職理由コードが設定され、状況をより正確に表現できるようになっています。
失業給付の手続き方法
失業給付の申請は、居住地を管轄するハローワークで行います。2024年度からは、事前予約システムが導入され、待ち時間の短縮が図られています。
受給資格の決定:
失業給付の受給資格は、離職前2年間の勤務実績に基づいて決定されます。看護師の場合、夜勤を含む変則勤務があるため、勤務時間の算定が複雑になることがあります。具体的な算定方法は以下の通りです。
基本手当日額の計算例:
離職前6ヶ月の賃金総額が以下の場合。
4月:420,000円(基本給280,000円+夜勤手当100,000円+その他手当40,000円)
5月:450,000円
6月:380,000円
7月:410,000円
8月:430,000円
9月:400,000円
賃金日額は、これらの合計2,490,000円を180日で除した13,833円となります。この金額から、年齢に応じた給付率(45〜59歳の場合は80%、60〜64歳の場合は70%)を乗じて基本手当日額が決定されます。
2-4. 新職場での保険加入手続き
新しい職場での保険加入手続きは、入職日から5日以内に完了することが求められます。2024年度からは、マイナンバーカードを活用した電子申請が標準となっています。
加入手続きに必要な書類
保険加入手続きには、本人確認書類や前職での資格喪失証明書など、複数の書類が必要となります。2024年度からは、マイナンバーカードによる本人確認が標準となり、手続きの簡素化が進んでいます。
マイナンバーカードの活用方法:
マイナンバーカードのICチップに格納された情報を読み取ることで、氏名や生年月日などの基本情報を自動入力することができます。顔写真付きの本人確認書類としても利用できるため、従来必要だった住民票の写しなどが不要となっています。カードリーダーを設置している医療機関では、その場で読み取りが可能です。設置されていない場合でも、スマートフォンのNFC機能を利用した読み取りに対応しています。
標準報酬月額の決定方法:
新職場での標準報酬月額は、当初は見込み額に基づいて決定されます。看護師の場合、夜勤手当などの変動的な賃金が含まれるため、以下のような計算方法が採用されています。
初月の見込み額算定例:
基本給:300,000円
想定夜勤回数:8回(1回12,000円)
夜勤手当見込み:96,000円
その他手当:50,000円
総支給見込み額:446,000円
この場合、標準報酬月額は450,000円(第25級)に決定されます。実際の勤務実績により、3ヶ月後に改めて標準報酬月額が見直されることになります。
2-5. 給付金関連の手続き
傷病手当金や育児休業給付金など、継続中の給付金がある場合は、新旧の保険者間での引き継ぎが必要となります。2024年度からは、オンラインでの申請継続が可能となり、手続きの利便性が向上しています。
給付金の継続申請手続き
給付金の継続申請には、新旧の保険者間での情報連携が必要です。マイナポータルを通じた電子申請では、以下のような手順で手続きが進められます。
傷病手当金の継続受給手続き:
医師の診断書と新職場での就労状況証明書を電子申請システムにアップロードします。診断書は指定の医療機関であればオンラインでの発行が可能です。就労状況証明書も、新職場の人事担当者による電子署名に対応しています。受給期間が6ヶ月を超える場合は、詳細な医師の所見が必要となりますが、これもオンラインでの提出が可能です。
育児休業給付金の継続手続き:
子どもの年齢に応じた支給要件の確認が必要です。保育所の入所状況など、支給要件に関わる証明書類もオンラインでの提出に対応しています。ただし、初回申請時は原本の提出が必要となる場合があります。
2-6. デジタル化への対応と注意点
2024年度は保険手続きのデジタル化が大きく進展していますが、システムの操作に不慣れな場合は、以下のようなサポート体制を活用することができます。
オンライン申請のサポート体制
電子申請に不慣れな場合でも、様々なサポート体制が整備されています。2024年度からは、24時間対応のサポートデスクが設置され、夜勤シフトの看護師でも相談が可能となっています。
電話サポートの利用方法:
専用のサポートダイヤルでは、画面の操作方法から申請内容の確認まで、きめ細かなサポートを受けることができます。特に初めての電子申請時には、オペレーターが画面を共有しながら手順を説明してくれるサービスも提供されています。
チャットボットによる支援:
簡単な操作方法の確認や一般的な質問については、AI搭載のチャットボットが24時間対応しています。質問内容に応じて、動画マニュアルや操作手順書が自動的に表示される仕組みとなっています。
システムトラブル時の対応
システムトラブルが発生した場合の代替手段として、従来の書面での申請も並行して受け付けています。緊急性の高い手続きについては、FAXでの仮申請も可能となっています。
緊急時の書類送付方法:
FAXによる仮申請の場合、原本は後日郵送する必要があります。ただし、マイナンバーカードで電子署名された書類については、電子メールでの送付も認められています。電子署名付き書類の作成方法は、専用アプリケーションを通じて行うことができます。
2-7. 手続き完了後の確認事項
全ての手続きが完了した後も、いくつかの確認が必要です。特に給付金の受給や保険料の控除については、最初の数ヶ月は念入りにチェックすることが推奨されています。
保険料控除の確認方法
新職場での最初の給与明細では、保険料の控除額が正しく計算されているか確認が必要です。特に標準報酬月額の決定に夜勤手当が含まれる場合は、以下の点に注意が必要です。
控除額の計算方法:
標準報酬月額が450,000円の場合の月々の保険料は、健康保険料と厚生年金保険料を合わせて約140,000円となります。これを労使で折半するため、給与からの控除額は約70,000円となります。ただし、介護保険料が加算される40歳以上の場合は、さらに約8,000円が追加されます。
被扶養者の認定確認
被扶養者がいる場合は、認定が正しく行われているか確認が必要です。特に配偶者の扶養から外れる場合は、国民年金の種別変更手続きも必要となります。確認後は、被保険者証の記載内容が正しいかどうかを必ず確認します。
3. 施設形態別の注意点とポイント

医療施設の形態によって保険手続きの特徴や注意点が異なります。このセクションでは、総合病院、診療所・クリニック、訪問看護ステーションそれぞれの特徴と、実務担当者への取材から得た具体的なポイントを解説します。特に2024年の制度改正に伴う変更点や、デジタル化に対応した新しい手続き方法についても詳しく説明していきます。
3-1. 総合病院における保険手続きの特徴
大規模医療機関では、専門の人事部門が保険手続きを担当することが一般的です。2024年4月からの電子申請義務化に伴い、多くの総合病院では手続きのデジタル化が進んでいます。システムへの慣れが必要となりますが、書類の提出や進捗確認が容易になるメリットがあります。
人事部門との連携方法
人事部門との連絡方法は、従来の対面や電話での対応から、専用ポータルサイトやチャットツールを活用した方法へと変化しています。特に500床以上の大規模病院では、独自の電子申請システムを導入していることが多く、スマートフォンやタブレットからの申請にも対応しています。入職時のオリエンテーションでは、これらのシステムの使用方法について詳しい説明があります。また、システムトラブル時の代替手段についても確認しておくことが重要です。紙での提出が必要な場合は、専用の提出ボックスが設置されている場合が多いですが、提出期限に注意が必要です。
書類提出の期限管理
大規模施設での書類提出は、給与計算のスケジュールと密接に関連しています。特に月末の入職では、給与計算に間に合うよう、入職日から3日以内に必要書類を提出することが求められます。書類の不備があった場合、給与支払いや保険加入に遅れが生じる可能性があるため、事前の確認が重要です。提出が必要な書類には以下のようなものがあります:
健康保険・厚生年金保険関連では、資格取得届、被扶養者異動届、国民年金第3号被保険者関係届などが必要となります。特に被扶養者がいる場合は、収入証明や同居証明などの添付書類も必要です。雇用保険関連では、雇用保険被保険者資格取得届や、前職での離職票の写しなどを提出します。
電子申請システムの利用方法
総合病院では専用の電子申請システムを通じて各種手続きを行います。システムへのログインには専用のIDとパスワードが必要で、通常は入職時のオリエンテーションで発行されます。申請の際は、スキャンした書類のアップロードが必要となる場合もあり、スマートフォンでの書類スキャンに対応しているシステムも増えています。電子申請後は、人事部門での確認状況がリアルタイムで確認できる仕組みになっています。
3-2. 診療所・クリニックでの手続きポイント
小規模医療機関では、事務担当者が少ないため、看護師自身が手続きの進捗を把握しておく必要があります。2024年の制度改正により、20名以下の小規模事業所でも電子申請が推奨されていますが、対応状況は施設によって異なります。
事務担当者との確認事項
保険手続きの担当者は通常1〜2名で、院長の配偶者が事務長を務めているケースも少なくありません。そのため、手続きの確認や書類の提出は、担当者の勤務時間に合わせる必要があります。特に重要な確認事項として、書類の提出期限、提出方法、不備があった場合の連絡方法があります。また、担当者の休暇中の対応方法についても確認が必要です。
緊急時の連絡方法として、担当者の携帯電話番号やメールアドレスを確認しておくことも推奨されます。ただし、プライバシーに配慮し、緊急時以外の連絡は通常の勤務時間内に行うようにします。
社会保険労務士との連携
診療所やクリニックの約70%が外部の社会保険労務士に手続きを委託しています。この場合、書類の提出期限は社労士の事務所スケジュールにも影響されます。特に月末や年度末は書類が集中するため、余裕を持った提出が必要です。
社労士事務所とのやり取りは、原則として医療機関の事務担当者を通じて行います。ただし、確認事項がある場合は社労士から直接連絡が入ることもあります。その際の対応方法についても、事前に確認しておくことが望ましいです。
3-3. 訪問看護ステーションの特殊性
訪問看護ステーションは、2024年の診療報酬改定により機能強化型の要件が見直され、常勤換算や勤務形態の多様化が進んでいます。これに伴い、保険加入の条件も複雑化しているため、特に慎重な確認が必要です。
勤務形態による保険適用の違い
訪問看護ステーションでは、常勤、非常勤、登録型など多様な勤務形態があります。保険の適用条件は以下のように勤務形態によって異なります。
常勤職員の場合は、通常の健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。週40時間勤務が基本ですが、変形労働時間制を採用している施設も多く、月単位での労働時間管理が行われます。
非常勤職員の場合、2024年10月からの制度改正により、週20時間以上の勤務であれば原則として社会保険の加入対象となります。ただし、月額賃金が8.8万円以上という条件も満たす必要があります。
登録型の場合、勤務時間が変動するため、月ごとに保険適用の判断が必要となることがあります。特に繁忙期は勤務時間が増加し、保険加入の要件を満たす可能性があるため、毎月の勤務時間を慎重に確認する必要があります。
複数事業所勤務の場合の対応
2024年の制度改正により、複数の訪問看護ステーションで勤務する場合の保険加入要件が明確化されました。労働時間の合算による社会保険の適用が可能となり、より柔軟な働き方に対応できるようになっています。
主たる勤務先の決定は、原則として労働時間が最も長い事業所となりますが、給与額や通勤の利便性なども考慮することができます。特に注意が必要なのは、月々の勤務時間が変動する場合です。この場合、3ヶ月平均の労働時間で判断されるため、記録の保管が重要となります。
また、複数の事業所で勤務する場合、労働保険の手続きも複雑になります。労災保険は事業所ごとの加入となりますが、通勤災害の認定には主たる勤務先の判断が影響します。そのため、勤務先ごとの通勤経路を明確に記録しておく必要があります。
3-4. 施設共通の重要確認事項
施設形態に関わらず、2024年度から導入された新制度への対応が必要です。特にマイナンバーカードを活用した電子申請の普及により、手続き方法が大きく変化しています。
各種保険料の負担割合
保険料の負担割合は、原則として事業主と被保険者で折半となりますが、実際の運用は施設によって異なります。2024年度の健康保険料率改定により、都道府県ごとの保険料率の差が広がっているため、特に都道府県をまたぐ転職の場合は注意が必要です。
標準報酬月額の決定方法も重要なポイントです。基本給に各種手当を加えた額がベースとなりますが、夜勤手当や特殊業務手当など、変動的な給与をどのように算入するかは施設ごとの規定に従います。特に訪問看護手当や緊急時対応手当など、訪問看護特有の手当については、算入方法を明確に確認する必要があります。
給付金の申請手続き
給付金の申請は、原則として施設を経由して行いますが、電子申請の導入により直接申請が可能なケースも増えています。ただし、初回申請は従来通り施設を通じて行う必要があるため、手続きの流れを事前に確認しておくことが重要です。
傷病手当金の申請では、医師の証明が必要となります。施設内の診療所や契約医療機関での受診の場合、証明書の発行手続きが簡略化されている場合もあります。ただし、自己負担が発生する可能性もあるため、事前に確認が必要です。
3-5. 施設変更時の移行期間の対応
施設を変更する際は、保険の切り替えに伴う一時的な保障の空白を防ぐ必要があります。特に施設形態が大きく異なる場合は、手続きに時間がかかることを考慮に入れる必要があります。
保険の切り替えスケジュール
退職から入職までの期間が空く場合、健康保険の任意継続被保険者制度を利用するかどうかの判断が必要です。この制度を利用する場合、退職後20日以内に手続きを行う必要があります。2024年からは電子申請も可能となり、手続きの利便性が向上しています。
また、民間の医療保険との併用を検討する場合は、契約内容の確認が重要です。特に入院給付金や手術給付金の支払い条件は、保険会社によって異なります。また、新たな保険に加入する場合は、既往症の告知が必要となることもあります。
4. 具体的な転職事例と成功のポイント

実際の転職事例を通じて、保険手続きの具体的な流れと注意点を解説します。2024年の制度改正に対応した最新の事例を含め、様々なケースにおける成功のポイントを詳しく見ていきましょう。
4-1. 総合病院から診療所への転職事例
総合病院から診療所への転職は、施設規模の違いによる手続きの差異に注意が必要です。以下の事例では、そのポイントを具体的に解説します。
A看護師の事例(33歳・夜勤あり)
基本情報:
前職は500床規模の総合病院で7年間勤務し、月8回の夜勤をこなしていました。転職先は内科・小児科の診療所で、夜勤はありませんが、週1回の遅番勤務があります。扶養家族として配偶者と2歳の子どもがいます。
具体的な手続きの流れ:
退職の2ヶ月前から準備を開始し、マイナポータルを活用した電子申請を基本としながら、必要に応じて従来の書面での手続きも併用しました。標準報酬月額は夜勤手当がなくなることで大幅に変更となりましたが、基本給の増額により、最終的な手取り額は前職とほぼ同水準を維持できています。
成功のポイント分析
転職に伴う収入の変化を事前に試算し、家計への影響を把握していました。具体的には、夜勤手当の喪失分を基本給でカバーする交渉を行い、結果として標準報酬月額を以下のように調整することができました。
前職での標準報酬月額:
基本給(280,000円)+夜勤手当(96,000円)+その他手当(54,000円)=430,000円
→標準報酬月額:440,000円
転職後の標準報酬月額:
基本給(380,000円)+遅番手当(20,000円)+その他手当(40,000円)=440,000円
→標準報酬月額:440,000円
4-2. クリニック間の転職事例
小規模医療機関間の転職では、社会保険労務士との連携が重要となります。実際の事例を通じて、スムーズな手続きのポイントを解説します。
B看護師の事例(28歳・パートタイムからフルタイムへ)
基本情報:
前職は耳鼻科クリニックで週30時間のパートタイム勤務を3年間続けていました。転職先は皮膚科クリニックで、フルタイム勤務となります。扶養家族はおらず、マイナンバーカードを活用した電子申請に対応できる環境がありました。
具体的な手続きの流れ:
勤務形態の変更に伴い、社会保険の適用区分が変更となるため、特に慎重な対応が必要でした。前職では育児中の同僚の補助として主に午前中の勤務でしたが、転職を機にフルタイム勤務への移行を決意しました。
退職時の状況:
週30時間勤務で標準報酬月額は220,000円でした。月収の内訳は基本給180,000円、職務手当20,000円、その他手当20,000円となっていました。雇用保険は被保険者でしたが、社会保険は2024年10月からの制度改正により新たに加入することとなっていました。
成功のポイント分析
勤務形態の変更に伴う保険料負担の増加について、事前に詳細な試算を行いました。フルタイム勤務への移行により、給与は大幅に増額となりましたが、社会保険料の負担も増えるため、手取り額の変化を正確に把握することが重要でした。
転職後の状況:
フルタイム勤務となり、基本給は320,000円、職務手当40,000円、その他手当30,000円の合計390,000円となりました。標準報酬月額は390,000円となり、社会保険料の負担は月額約70,000円が新たに発生することとなりました。
4-3. 訪問看護ステーションへの転職事例
在宅医療の特性を考慮した保険手続きが必要となる訪問看護への転職について、実例を基に解説します。
C看護師の事例(45歳・複数施設勤務)
基本情報:
前職は一般病棟での勤務を15年間継続していましたが、ワークライフバランスの見直しを機に訪問看護への転職を決意しました。2つの訪問看護ステーションでの勤務を組み合わせる形態を選択しています。
具体的な手続きの流れ:
二つの訪問看護ステーションでの勤務開始にあたり、主たる勤務先の決定が重要なポイントとなりました。A訪問看護ステーションでは週24時間、B訪問看護ステーションでは週16時間の勤務となるため、労働時間の長いA訪問看護ステーションを主たる勤務先として各種手続きを進めました。
保険手続きの特徴:
複数の事業所で勤務する場合の社会保険の適用関係について、2024年の制度改正を踏まえた対応が必要でした。主たる勤務先となるA訪問看護ステーションでの標準報酬月額は、基本給210,000円、訪問看護手当60,000円、オンコール手当30,000円の合計300,000円となりました。
成功のポイント分析
複数の事業所での勤務における保険手続きのポイントとして、労働時間と給与の管理を徹底しました。特に訪問看護特有の各種手当について、標準報酬月額への算入方法を事前に確認したことが、手続きをスムーズに進める鍵となりました。
4-4. 産休・育休関連の転職事例
妊娠・出産・育児と仕事の両立を目指す看護師の転職事例について、保険手続きの観点から解説します。
D看護師の事例(32歳・育休明け転職)
基本情報:
第一子の育児休業を終え、よりワークライフバランスの取れる職場への転職を決意しました。前職は大学病院での勤務でしたが、育児との両立を考慮し、院内保育所のある総合病院への転職を選択しています。
具体的な手続きの流れ:
育児休業給付金の受給中の転職となるため、手続きは特に慎重に進める必要がありました。育児休業給付金の受給資格の確認から始め、新職場での両立支援制度の利用申請まで、一連の手続きを計画的に進めました。
給付金関連の手続き:
育児休業給付金の受給期間中の転職となったため、ハローワークでの手続きが必要でした。具体的には、育児休業給付金受給資格確認通知書の写しを新しい事業所に提出し、育児休業給付金の支給申請を行いました。
転職後の両立支援:
新しい職場では、短時間勤務制度を利用しながら、段階的に勤務時間を延ばしていく計画を立てました。これに伴い、標準報酬月額も段階的に変更となることを考慮し、将来的な収入の見通しを立てることができました。
4-5. 複数施設勤務への転職事例
ワークシフトの柔軟性を求めて複数施設での勤務を選択するケースが増えています。2024年の制度改正により、より柔軟な働き方が可能となった事例を紹介します。
E看護師の事例(35歳・複数科掛け持ち)
基本情報:
前職では透析クリニックで常勤として5年間勤務していましたが、スキルアップを目指して、透析クリニックと救急クリニックの掛け持ち勤務に転職しました。特に救急医療のスキル習得を目指しながら、専門性の高い透析看護も継続する選択をしています。
具体的な手続きの流れ:
主たる勤務先となる透析クリニックでの勤務は週24時間、救急クリニックでの勤務は週20時間となり、両施設での社会保険の加入要件を満たすこととなりました。2024年の制度改正により、この場合の保険手続きは以下のように整理されました。
社会保険の適用:
透析クリニックを主たる勤務先として社会保険に加入し、標準報酬月額は以下のように設定されました。基本給240,000円、透析業務手当45,000円、その他手当25,000円の合計310,000円を基に、標準報酬月額は310,000円となっています。救急クリニックでの収入は別途確定申告が必要となりました。
成功のポイント分析
複数の医療機関での勤務における最大のポイントは、労働時間と社会保険の適用関係の正確な把握でした。特に2024年の制度改正により、より柔軟な働き方が認められるようになったことで、専門性を活かした複数施設での勤務が実現可能となっています。
4-6. 特殊なケースの転職事例
一般的な転職パターンとは異なる、特殊な状況での転職について、実例を基に解説します。2024年の制度改正により、より多様な働き方に対応した保険制度となっています。
F看護師の事例(40歳・海外勤務からの帰国)
基本情報:
国際医療支援団体での3年間の海外勤務を終え、日本国内の医療機関への転職を決意しました。海外勤務中は任意加入の海外医療保険に加入していましたが、帰国後は日本の社会保険制度への再加入が必要となりました。
具体的な手続きの流れ:
帰国後の医療機関への就職にあたり、国民年金と国民健康保険からの切り替え手続きが必要となりました。マイナンバーカードを活用した電子申請により、手続きの多くをオンラインで完了することができました。
特殊な状況での対応:
海外勤務中の年金加入期間については、帰国後に年金事務所での確認が必要となりました。特に海外の医療機関での勤務期間について、年金の通算制度が適用されるかどうかの確認が重要なポイントとなっています。社会保険労務士のアドバイスを受けながら、年金事務所との調整を進めました。
成功のポイント分析
海外勤務後の転職における最大のポイントは、日本の社会保険制度への円滑な移行でした。特に年金の継続性について、事前に十分な情報収集を行い、必要な手続きを計画的に進めることができました。新しい職場となった総合病院では、人事部門のサポートを受けながら、各種手続きをスムーズに完了することができています。
4-7. 事例から学ぶ共通のポイント
これまでの6つの事例から、転職時の保険手続きにおける重要なポイントが見えてきました。2024年の制度改正を踏まえ、特に注意が必要な点について整理します。
マイナンバーカードの活用
全ての事例において、マイナンバーカードを活用した電子申請が有効活用されていました。特に複数の手続きが必要なケースでは、オンラインでの一括申請が可能となり、手続きの効率化が図られています。具体的には、健康保険の資格取得届、厚生年金の被保険者資格取得届、雇用保険の被保険者資格取得届などを、マイナポータルを通じて一括で申請することが可能となっています。
給付金の継続性確保
育児休業給付金や傷病手当金など、各種給付金の受給中に転職する場合は、給付の継続性確保が重要となっています。特に事例4のように育児休業給付金の受給中の転職では、ハローワークと新旧の事業所との連携が不可欠でした。手続きの期限や必要書類について、事前に十分な確認を行うことで、給付の中断を防ぐことができています。
標準報酬月額の調整
夜勤手当や特殊勤務手当など、変動的な賃金が発生する看護職特有の給与体系において、標準報酬月額の適正な設定が重要となっています。特に事例1のように、夜勤の有無による収入の変動が大きいケースでは、基本給の調整により、年金額や各種給付金の算定基礎となる標準報酬月額を維持する工夫が見られました。
これらの事例を通じて、2024年の制度改正に対応した効率的な手続きの進め方や、看護職特有の勤務形態に応じた保険手続きのノウハウが蓄積されています。
5. おしえてカンゴさん!よくある質問と回答

看護師の転職における保険手続きについて、現役の社会保険労務士と看護師への取材をもとに、よくある質問とその回答をまとめました。2024年の制度改正に関する最新の疑問点についても解説していきます。
5-1. 健康保険に関する質問
Q1:保険証の切り替え期間中の受診について
質問:退職後、新しい保険証が手元に届くまでの間に病院を受診する必要がある場合はどうすればよいでしょうか。
回答:資格喪失証明書を医療機関の窓口で提示することで、保険診療を受けることが可能です。2024年からはマイナ保険証を利用している場合、オンラインで資格確認ができるため、スムーズな対応が可能となっています。なお、やむを得ず10割負担で受診した場合は、後日、払い戻しの申請を行うことで、自己負担分以外の医療費が返還されます。手続きは新しい保険者に対して行います。
Q2:傷病手当金の継続受給について
質問:傷病手当金を受給中の転職となりましたが、給付は継続されますか。
回答:傷病手当金の受給は、新しい保険者に引き継がれます。ただし、手続きには医師の診断書など、改めて書類の提出が必要となります。2024年からは電子申請に対応しており、オンラインでの継続申請が可能です。なお、標準報酬月額が変更となる場合は、給付額も変更となる可能性があります。具体的な給付額は、新しい保険者に確認することをお勧めします。
5-2. 厚生年金に関する質問
Q3:標準報酬月額の変更について
質問:夜勤のある病院から日勤のみのクリニックに転職する予定です。夜勤手当がなくなることで、将来の年金額は減少しますか。
回答:標準報酬月額が低下すると、将来の年金額に影響する可能性があります。ただし、2024年の制度改正により、過去の標準報酬月額の平均値を基に年金額が計算されるため、一時的な変動の影響は限定的です。転職先との給与交渉の際は、基本給に夜勤手当相当額を組み込むなどの工夫も検討できます。実際に、総合病院からクリニックへの転職事例では、基本給の増額により標準報酬月額を維持しているケースも多く見られます。
Q4:育児休業中の年金保険料について
質問:現在育児休業中ですが、復職を機に転職を考えています。年金保険料の免除は新しい職場でも継続されますか。
回答:育児休業中の年金保険料免除は、転職先でも申請により継続が可能です。2024年からは電子申請に対応しており、マイナポータルを通じてオンラインで手続きができます。ただし、新しい職場での申請は入職後速やかに行う必要があります。保険料が免除される期間は、子どもが3歳になるまでとなります。この期間は将来の年金額の計算では、休業前の標準報酬月額に基づいて計算されるため、年金額への影響はありません。実際の申請手続きは、新しい職場の人事担当者に確認することをお勧めします。
5-3. 雇用保険に関する質問
Q5:複数の医療機関で働く場合の雇用保険について
質問:2つの診療所で非常勤として勤務する予定です。雇用保険はどちらで加入すべきでしょうか。
回答:2024年の制度では、主たる勤務先となる医療機関で雇用保険に加入することとなります。主たる勤務先は原則として労働時間の長い方となりますが、同じ労働時間の場合は賃金の多い方となります。例えば、A診療所で週20時間、B診療所で週15時間勤務する場合は、A診療所での加入となります。なお、どちらの勤務先でも週20時間未満の場合は、雇用保険の対象とはなりません。ただし、合算して週20時間以上となる場合の特例制度について、2024年度から試験的な運用が開始されているため、詳細はハローワークに確認することをお勧めします。
Q6:育児休業給付金の受給中の転職について
質問:育児休業給付金を受給中ですが、より子育てと両立しやすい職場に転職を考えています。給付金は継続して受けられますか。
回答:育児休業給付金は、一定の条件を満たせば転職先でも継続して受給できます。2024年からは、マイナポータルを通じた電子申請により、手続きがより簡便になっています。ただし、転職前に必ずハローワークで手続きを行い、受給資格の確認を受ける必要があります。具体的には、現在の職場での育児休業給付金の支給状況を証明する書類と、転職先での雇用契約書や育児休業申請の写しなどが必要となります。また、転職先での育児休業は、子どもが1歳(特別な事情がある場合は最長2歳)に達するまでの期間となります。給付額は、休業開始時賃金の67%(180日経過後は50%)ですが、転職に伴い賃金が変更となった場合は、給付額も変更となる可能性があります。
5-4. 労災保険に関する質問
Q7:治療中の労災案件がある場合の転職について
質問:腰痛で労災認定を受けて治療中ですが、転職することは可能でしょうか。また、治療は継続できますか。
回答:労災保険による治療は、転職後も継続して受けることが可能です。2024年からは、電子申請システムを通じて転医手続きがスムーズになっています。ただし、転職先の業務内容が現在の症状に影響を与える可能性がある場合は、主治医に相談することをお勧めします。実際の手続きとしては、転職前に労働基準監督署に転医手続きの申請を行い、新しい勤務先の近隣の医療機関を指定することになります。なお、休業補償給付については、転職に伴い給与額が変更となった場合でも、従前の給付額が維持されます。
5-5. マイナンバーカードと電子申請に関する質問
Q8:電子申請の具体的な方法について
質問:マイナンバーカードを使った電子申請の具体的な手順を教えてください。高齢の看護師でも簡単に行えますか。
回答:2024年の電子申請システムは、スマートフォンからでも簡単に操作できるように設計されています。具体的には、マイナポータルにログイン後、画面の案内に従って必要事項を入力していくだけで手続きが完了します。スマートフォンのカメラ機能を使って必要書類を撮影し、そのまま添付することも可能です。また、各地域の年金事務所やハローワークでは、電子申請の支援窓口が設置されており、操作方法がわからない場合でも専門スタッフのサポートを受けることができます。夜勤シフトの看護師でも24時間いつでも申請が可能なため、便利に活用できます。実際に50代以上の看護師の方々からも、わかりやすいシステムだとの声が多く寄せられています。
6. まとめ:確実な保険手続きのために

転職時の保険手続きを成功に導くため、本記事で解説した重要ポイントを最終チェックリストとしてまとめました。以下の項目を順に確認し、手続きの漏れを防ぎましょう。
退職前の準備(1ヶ月前まで)
退職届の提出と同時に、保険資格喪失証明書の発行を依頼しましょう。マイナンバーカードの健康保険証利用の事前登録も忘れずに行います。夜勤シフトがある場合は、最終勤務日と退職日の調整も重要です。
退職時の対応(退職日まで)
健康保険証の返却と資格喪失証明書の受け取りを確実に行います。傷病手当金や育児休業給付金など、継続中の給付金がある場合は、継続手続きの確認を忘れずに。マイナポータルでの電子申請利用の準備も進めましょう。
入職時の手続き(入職後5日以内)
新しい職場での各種保険の加入手続きは、入職後5日以内に必ず完了させます。被扶養者がいる場合は、扶養認定申請も同時に行います。標準報酬月額が適切に設定されているか、確認することも重要です。
入職後の確認(1ヶ月以内)
初回の給与明細で保険料控除が正しく行われているか確認します。各種保険証や年金手帳の新規発行も忘れずにチェックしましょう。不明な点があれば、すぐに人事担当者に確認することが大切です。
次のステップとして、以下の行動を推奨します。
- マイナンバーカードの取得と健康保険証利用の登録を済ませる。
- マイナポータルへのログイン方法を確認し、電子申請の手順を把握する。
- 新しい職場の社会保険担当者の連絡先を確認しておく。
- 保険に関する重要書類は期限と共にスケジュール管理する。
- 不明点は社会保険労務士など専門家に早めに相談する。
これらの準備と確認を着実に行うことで、安心して新しい職場でのスタートを切ることができます。ご不明な点は、本記事の該当箇所に戻って再確認してください。
参考文献・引用
- 厚生労働省「我が国の医療保険について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html - 日本年金機構「年金の制度・手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/index.html - ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_summary.html - 厚生労働省「労災保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken.html - マイナポータル「健康保険証情報を確認する」
https://img.myna.go.jp/manual/03-01/0169.html - 日本看護協会「看護職の働き方改革」
https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/hatarakikata/index.html - 全国健康保険協会(協会けんぽ)「各種申請書・届出書」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/