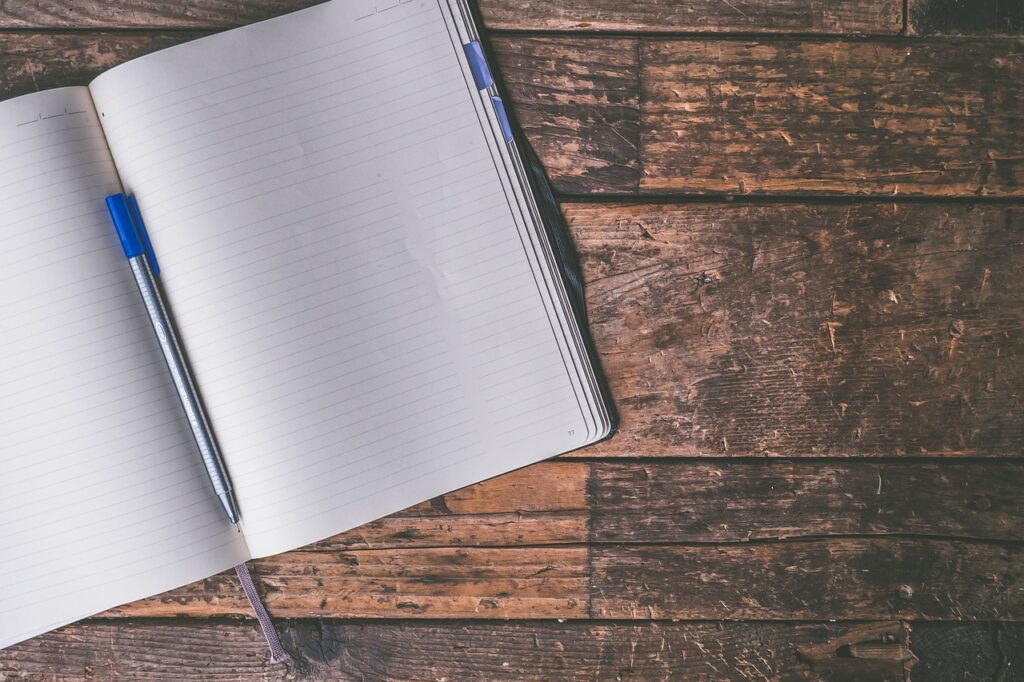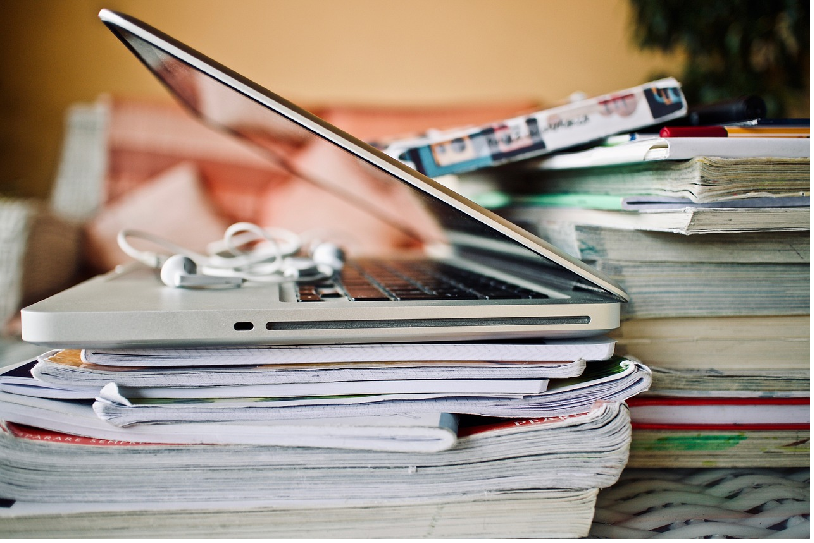新人看護師にとって、医師からの指示確認は最も緊張する業務の一つです。患者さんの安全な医療を提供するためには、確実な指示確認が不可欠ですが、実際の現場では様々な課題に直面することも少なくありません。
本記事では、新人看護師の皆さんが自信を持って指示確認を行えるよう、基本的な確認手順から実践的なテクニックまで、具体的に解説していきます。先輩看護師の経験に基づいた実践的なアドバイスを参考に、確認精度の向上を目指しましょう。
この記事で分かること
- 医師指示確認における5Rightsの具体的な実践方法
- 電子カルテと紙媒体それぞれの効果的な記録管理の方法
- 指示確認時の効果的な質問技術とコミュニケーション方法
- 実際の現場で活用できる具体的なケーススタディ
- 多職種連携における確認のポイントと実践テクニック
この記事を読んでほしい人
- 医師指示の確認に不安を感じている新人看護師の方々
- より正確な指示確認方法を身につけたい2年目以降の看護師の方々
- プリセプターとして新人指導を担当している看護師の方々
- 医療安全管理に関心のある医療従事者の方々
医師指示確認の基本フレームワーク

医師指示の確認は患者さんの安全を守る最も重要な業務の一つです。新人看護師の方々にとって、この業務は特に緊張と不安を伴うものかもしれません。
このセクションでは、確実な指示確認を行うための基本的な枠組みと、実践的なテクニックについてご説明します。さらに、起こりやすいミスとその防止策、現場での具体的な対処方法まで、詳しく解説していきます。
5Rightsの徹底確認
基本的な確認事項の詳細
医師指示を受ける際の基本となる5Rightsは、単なるチェック項目ではありません。それぞれの項目について、なぜ確認が必要なのか、どのように確認すべきなのかを理解することが重要です。
正しい患者さんに、正しい薬剤を、正しい用量で、正しい時間に、正しい投与経路で投与する。この5つの要素は、医療安全の基本となります。特に新人の方は、この確認手順を必ず身につけていただきたいと思います。
各Rightの具体的確認手順
まず「Right Patient(正しい患者)」の確認では、患者さんのフルネーム、生年月日、患者IDの3点照合が基本となります。この際、リストバンドの確認も必須です。また、意識清明な患者さんの場合は、ご本人に名乗っていただくことも重要な確認方法の一つとなります。
「Right Drug(正しい薬剤)」の確認においては、薬剤名を正式名称で確認します。特に似た名称の薬剤が存在する場合は要注意です。
例えば、カルシウム拮抗薬の「アムロジピン」と「アゼルニジピン」、β遮断薬の「アテノロール」と「メトプロロール」など、類似名称による誤認を防ぐため、必ず薬剤の現物を確認します。
「Right Dose(正しい用量)」については、数値と単位の両方を明確に確認します。特に小数点の位置や単位の違い(mgとμg、mLとLなど)には細心の注意を払います。計算が必要な場合は、必ず電卓を使用し、可能であれば同僚にもダブルチェックを依頼します。
デジタルツールの効果的活用
電子カルテシステムの活用においては、システムの特性を理解することが重要です。
例えば、オーダリングシステムでは、過去の指示内容が自動的に表示される機能があります。これは便利な機能である一方、古い情報を誤って参照してしまうリスクもあります。そのため、必ず指示の日時を確認し、最新の情報であることを確認します。
確認精度を高めるための3ステップ
事前準備の具体的アプローチ
指示確認の精度を高めるためには、十分な事前準備が欠かせません。まず、担当患者さんの以下の情報を把握しておきます。
現病歴と主な症状:現在の治療方針を理解する上で重要な情報となります。
バイタルサインの推移:治療効果や患者さんの状態変化を判断する基準となります。
検査データの推移:特に腎機能や肝機能の値は、投薬量の調整に関わる重要な指標となります。
アレルギー歴:薬剤アレルギーだけでなく、食物アレルギーや造影剤アレルギーなども確認します。
確認時の基本姿勢と実践テクニック
指示を受ける際の基本姿勢は、医療安全の要となります。まずは、適切なタイミングでの確認が重要です。医師が多忙な場合でも、曖昧なまま指示を受けることは避けましょう。
具体的には、「少々お時間をいただいてもよろしいでしょうか」と確認し、指示内容をメモできる環境を整えます。
また、復唱確認の際は、単に聞いた内容を繰り返すだけでなく、理解した内容を自分の言葉で確認することも効果的です。
例えば「〇〇mg/時で持続投与を開始し、血圧が収縮期90mmHg以下になった場合は一旦止めて報告、という理解でよろしいでしょうか」というように具体的に確認します。
記録と伝達の標準化
指示受け後の記録は、5W1Hを意識して行います。いつ(When)、誰が(Who)、誰に(Whom)、何の(What)指示を受け、なぜ(Why)その指示が出され、どのように(How)実施するのかを明確に記載します。特に口頭指示の場合は、その場で記録することが重要です。
時間帯別の確認ポイント拡充
日勤帯での効果的な確認方法
日勤帯は様々な職種が勤務している時間帯であり、確認がしやすい反面、業務が輻輳するリスクも高まります。そのため、以下のような時間管理が重要となります。
朝の申し送り直後:夜間の指示内容の再確認と、朝一番の指示確認を行います。特に検査前の絶食指示や内服薬の変更には注意が必要です。
回診時:医師との直接的なコミュニケーションの機会として活用します。不明点や疑問点をまとめておき、効率的に確認を行います。
昼休み前後:午前中の検査結果に基づく新規指示の確認や、午後の予定の最終確認を行います。
夜勤帯での安全確保
夜間の指示受けでは、特に電話での口頭指示が多くなります。その際は必ずメモを取り、復唱確認を徹底します。緊急性の高い指示については、実施までの時間的余裕を確認し、必要に応じて応援を要請します。
また、深夜帯での指示内容は、可能な限り準夜勤の看護師とも共有し、ダブルチェックを行います。
診療科別の特徴と実践的対応
内科系における詳細確認事項
内科系での指示確認では、特に以下の点に注意が必要です。
投薬スケジュールの管理:時間依存性の薬剤(抗生物質など)は、投与間隔を厳密に守る必要があります。
併用薬の確認:ポリファーマシーによる相互作用のリスクを考慮し、新規薬剤の追加時は特に注意深く確認します。
外科系での術前術後管理
手術前後の指示確認では、時系列での管理が特に重要です。術前指示(絶飲食開始時期、前投薬、抗生剤など)、術中指示(輸液、抗生剤追加など)、術後指示(観察項目、ドレーン管理、疼痛コントロールなど)を明確に区分して確認します。
精神科での留意点
精神科では、患者さんの状態に応じた柔軟な対応が必要となります。特に、以下の点について詳細な確認が求められます。
頓用指示の条件:不穏時や不眠時の指示について、実施基準を具体的に確認します。
行動制限に関する指示:必要性と解除基準について明確に確認し、定期的な評価を行います。
小児科での確認ポイント
小児科では、年齢や体重による投与量の調整が必須となります。また、発達段階に応じた投与方法の工夫も必要です。特に以下の点について入念な確認を行います。
体重換算での投与量:計算式を明確にし、必ずダブルチェックを行います。
投与経路の適切性:年齢や発達段階に応じた投与方法(シロップ剤の選択など)を確認します。
このように、基本フレームワークを理解し、各診療科の特性に応じた確認を行うことで、医師指示確認の精度を向上させることができます。次のセクションでは、これらの指示内容を確実に記録し、管理していくための具体的な方法についてご説明します。
効果的な記録管理システム

医師からの指示を正確に受けることと同様に重要なのが、その内容を適切に記録し管理することです。
このセクションでは、電子カルテと紙媒体それぞれにおける効果的な記録方法と、記録の質を向上させるためのポイントについて解説します。
また、よくある記録上のトラブルとその対処法、さらには長期的な記録管理の方法まで、実践的な視点から詳しく説明していきます。
電子カルテでの記録のポイント
システム活用の基本原則
電子カルテシステムは、正確な記録管理を支援する重要なツールです。まず基本となるのは、リアルタイムでの入力です。指示を受けたその場で記録することで、情報の欠落や誤記を防ぐことができます。
入力時は必ず一度内容を見直し、誤字脱字がないか確認します。特に医療用語や薬剤名については、システムの入力補助機能に頼りすぎず、必ず最終確認を行います。
テンプレートの効果的活用
電子カルテの各種テンプレート機能は、記録の標準化と効率化に大きく貢献します。しかし、テンプレートの過度な依存は、個別性のある情報の見落としにつながる可能性があります。テンプレートを使用する際は、患者さんの固有の状況や特記事項を必ず追記します。
また、施設独自のテンプレートを作成する際は、必要な情報項目を部署内で十分に検討し、定期的な見直しも行います。
時系列データの管理
電子カルテの大きな利点は、時系列での情報管理が容易なことです。特に継続指示や期間限定の指示については、開始日時と終了予定日時を明確に記録します。
また、指示変更の履歴を追跡できる機能を活用し、変更理由や経過も含めた包括的な情報管理を行います。システムの検索機能を活用することで、過去の類似事例や治療パターンの参照も容易になります。
システム間連携の活用
多くの医療機関では、電子カルテと他のシステム(オーダリングシステム、看護支援システムなど)が連携しています。これらのシステム間でのデータ連携を理解し、効果的に活用することで、より確実な記録管理が可能になります。
特に、患者安全に関わる重要情報(アレルギー情報など)については、システム間で確実に共有されているか確認します。
紙媒体での記録方法
指示受けノートの活用法
紙媒体での記録において、指示受けノートは重要な役割を果たします。ノートには日時、指示を出した医師名、指示内容、確認者名を必ず記載します。特に口頭指示の場合は、その場で記録し、後で医師のサインをもらうことを忘れずに行います。
緊急時の対応においても、簡潔かつ正確な記録を心がけ、落ち着いた後で詳細な補足を加えます。
情報の視認性向上
紙媒体での記録では、情報の視認性が特に重要です。文字は丁寧に書き、数字は特に明確に記載します。
また、重要な情報には下線を引くなどの視覚的な工夫を加えることで、情報の見落としを防ぎます。記録用紙の余白には、特記事項や注意点を記載するスペースを確保し、重要な情報が埋もれないようにします。
紙媒体特有の注意点
紙媒体の記録では、記載スペースの制限や保管場所の問題など、特有の課題があります。これらに対応するため、重要度に応じた情報の整理や、効率的なファイリングシステムの構築が必要です。また、記録の経年劣化を防ぐため、適切な保管環境の整備も重要です。
トラブルシューティング
システムトラブル時の対応
電子カルテシステムのダウン時には、あらかじめ定められた手順に従って対応します。システム復旧までの一時的な記録方法として、専用の用紙やノートを使用し、システム復旧後の入力漏れを防ぐため、チェックリストを活用した確認を行います。
また、定期的なバックアップデータの確認や、システムダウン時の訓練を実施することで、緊急時にも混乱なく対応できる体制を整えます。
記録の修正方法
電子カルテでの誤入力を発見した場合は、速やかに修正を行います。修正履歴が残るシステムの機能を使用し、修正理由を明確に記載します。
紙媒体の場合は、二重線で消して訂正印を押し、正しい内容を記載します。特に重要な数値の修正については、必ずダブルチェックを行い、修正履歴を残します。
記録の質向上のためのチェックリスト
記録時の確認項目
基本的な記録項目の確認に加えて、記録の質を向上させるための具体的な確認ポイントがあります。
日時や指示者の明記はもちろんのこと、指示の具体性、実施条件、評価方法なども明確に記載します。医療者間で共通認識を持つために、略語の使用は最小限に抑え、標準化された用語を使用します。
また、記録内容が第三者にも理解できる明確な表現となっているかも重要なポイントとなります。
定期的な記録監査の実施方法
記録監査は、単なるチェックではなく、記録の質を向上させるための重要な機会です。監査では、記録の正確性、完全性、適時性などを評価します。
特に重要な指示内容については、実施記録との整合性も確認します。監査結果は、スタッフ間で共有し、改善点について具体的な対策を検討します。
記録の長期的な管理と活用
効果的なアーカイブ方法
長期的な記録管理では、検索性と保管性の両立が重要です。電子カルテでは、キーワード検索や時系列表示などの機能を活用し、必要な情報に素早くアクセスできるようにします。
また、定期的なバックアップと、アクセス権限の適切な設定により、情報セキュリティも確保します。
データの分析と活用方法
蓄積された記録は、医療の質向上のための貴重なデータとなります。定期的なデータ分析により、よくある指示内容のパターンや、エラーが発生しやすい状況を把握することができます。この分析結果を基に、業務プロセスの改善や、新たな記録テンプレートの作成などを行います。
多職種間での情報共有
効果的な申し送り方法
記録された情報を多職種間で効果的に共有することは、チーム医療の基盤となります。申し送り時には、重要度に応じた情報の優先順位付けを行い、確実な情報伝達を心がけます。また、対面での申し送りに加えて、記録システムを活用した情報共有も積極的に行います。
職種間連携における記録の活用
多職種がそれぞれの視点で記録を残すことで、患者さんの状態をより包括的に把握することができます。そのため、他職種の記録内容も積極的に確認し、ケアの方向性を共有します。
また、カンファレンスなどの場で記録内容を基に討議することで、より質の高い医療の提供が可能となります。
このように、効果的な記録管理システムの構築と運用は、医療安全と質の向上に直結する重要な要素です。次のセクションでは、より良い医師とのコミュニケーションを実現するための質問技術について解説していきます。
質問技術の向上

医師への質問は、指示内容を正確に理解し、安全な医療を提供するために不可欠なスキルです。このセクションでは、効果的な質問方法や、状況に応じたコミュニケーション技術、さらには実践的なトレーニング方法まで、具体的に解説していきます。
新人看護師からベテランまで、それぞれのレベルに応じたスキルアップのポイントについても詳しく説明します。
効果的な質問方法
質問の基本姿勢
効果的な質問を行うためには、まず適切な姿勢で臨むことが重要です。医師が多忙な状況であっても、患者さんの安全のために必要な確認は確実に行う必要があります。
質問する際は、これまでの経過や検査データなど、必要な情報を整理した上で行うことで、より的確な回答を得ることができます。特に新人の方は、質問することをためらわず、分からないことはその場で確認する習慣を身につけることが大切です。
質問のタイミング
質問のタイミングも重要な要素です。緊急性の高い内容については、その場で即座に確認を行います。一方、緊急性の低い内容については、医師の業務の状況を考慮し、適切なタイミングを選んで質問します。
例えば、手術直前や救急対応中などは避け、一段落した時点で質問するなどの配慮が必要です。特に夜間帯の質問については、事前に相談内容を整理し、できるだけ要点を絞って行うことが望ましいです。
質問の構造化
質問を行う際は、必要な情報を漏れなく確認できるよう、構造化された方法で行います。まず状況を簡潔に説明し、その上で具体的な質問を行います。複数の質問がある場合は、優先順位を付けて整理します。
医師の回答についても、必要に応じてメモを取り、後で確認できるようにします。質問の際は、患者さんの現在の状態、バイタルサイン、関連する検査データなども含めて説明することで、より適切な回答を得ることができます。
効果的な質問フレーズ
状況に応じた適切な質問フレーズを使用することも重要です。例えば「〇〇の状態なのですが、△△の対応でよろしいでしょうか」というように、自分の判断も含めて確認する方法があります。
また、複雑な状況では「現在の状態をご報告させていただき、今後の方針について相談させていただきたいのですが」といった形で、会話の目的を明確にしてから詳細な説明に入ることも効果的です。
コミュニケーションの注意点
非言語コミュニケーションの活用
声のトーンや表情、姿勢などの非言語的要素も、効果的なコミュニケーションには重要です。特に緊急時には、自身の焦りが相手に伝わらないよう、落ち着いた態度で臨むことを心がけます。
また、医師の表情や態度からも、指示内容の重要度や緊急性を読み取ることができます。相手の反応を観察しながら、必要に応じて説明の方法を変更することも大切です。
状況に応じた伝え方
患者さんの状態や場面に応じて、適切な伝え方を選択することが重要です。緊急時には簡潔かつ明確に、複雑な状況を説明する際には段階的に情報を整理して伝えます。
例えば、急変時には「バイタルサインの変化」「現在の対応状況」「必要な指示内容」を順序立てて報告します。また、周囲の環境にも配慮し、必要に応じて場所を変えて確認を行うことも考慮します。
多職種間のコミュニケーション
チーム医療において、多職種間での効果的なコミュニケーションは不可欠です。薬剤師や理学療法士など、他職種からの情報も積極的に収集し、医師への質問や報告に活かします。
また、カンファレンスなどの場では、それぞれの職種の専門性を尊重しながら、建設的な意見交換を心がけます。
ロールプレイング例
基本的な質問シーン
日常的によくある質問シーンについて、具体的な会話例を用いて解説します。
例えば、新規薬剤の開始時には「この薬剤の投与量について確認させていただきたいのですが、〇〇mg/時での開始で間違いありませんでしょうか」といった形で、具体的な数値を示しながら確認を行います。
また、不明点がある場合は「申し訳ありません。もう一度ご説明いただけますでしょうか」と素直に確認を求めることが重要です。
緊急時の質問対応
緊急時には、より簡潔で明確なコミュニケーションが求められます。「患者さんの血圧が80/40まで低下しています。昇圧剤の使用を検討していただけますでしょうか」というように、状況と必要な対応を明確に伝えます。
また、「今の血圧低下に対して、〇〇の投与を考えていますが、いかがでしょうか」というように、自身の判断も含めて確認することで、より迅速な対応が可能となります。
コミュニケーション演習
実践的なトレーニング方法
質問技術の向上には、実践的なトレーニングが効果的です。先輩看護師と定期的にロールプレイを行い、様々な状況での対応を練習します。
具体的には、日常的な報告場面、緊急時の連絡、複雑な症例の相談など、様々なシチュエーションを設定して練習を行います。特に新人看護師は、基本的な質問パターンを習得することから始め、徐々に複雑な状況への対応も練習していきます。
シミュレーション訓練の活用
実際の医療現場を想定したシミュレーション訓練も、質問技術の向上に効果的です。例えば、急変時のチーム医療を想定し、医師への報告や指示確認を含めた総合的な訓練を行います。訓練後は必ずデブリーフィングを行い、コミュニケーションの課題や改善点について話し合います。
特殊な状況での質問技術
夜間・休日の対応
夜間や休日など、通常と異なる体制での質問には特に注意が必要です。電話での質問が主となるため、より明確な説明と確認が求められます。状況を簡潔に説明し、具体的な数値や観察結果を伝えた上で、必要な指示を確認します。
また、電話でのやり取りは記録に残りにくいため、メモを取りながら確認することが重要です。
多忙時の対応
医師が多忙な場合でも、患者さんの安全に関わる重要な確認は必ず行う必要があります。その際は「申し訳ありません。重要な確認がございますので、少々お時間をいただいてもよろしいでしょうか」と断った上で、要点を絞って質問を行います。
また、複数の確認事項がある場合は、優先順位を付けて効率的に確認を行います。
このように、質問技術の向上は、安全で効率的な医療の提供に直結する重要なスキルです。日々の実践と振り返りを通じて、さらなるスキルアップを目指していきましょう。次のセクションでは、実際の現場で活用できる具体的なケーススタディについて解説していきます。
ケーススタディ

医師指示の確認において、実際の現場では様々な状況に遭遇します。このセクションでは、新人看護師がよく経験する典型的なケースから、より複雑な対応が必要となるケースまで、具体的な事例を通して学んでいきます。
それぞれのケースについて、状況設定、対応のポイント、振り返りのポイントを詳しく解説します。また、その後のフォローアップや、類似事例への応用方法についても説明していきます。
Case A:夜間の急変時対応
状況設定
夜勤帯で担当している患者さん(70代男性、心不全にて入院中)の血圧が急激に低下し、医師への電話連絡が必要となった場面です。
夜間当直の医師は、別の救急対応中という状況でした。患者さんは入院後、利尿薬の投与により心不全のコントロールを行っており、この日の夜間帯で収縮期血圧が140mmHgから90mmHgまで低下しました。
具体的な対応手順と会話例
まず、患者さんのバイタルサインを再確認し、心不全の増悪を示唆する症状(呼吸困難感の増強、下腿浮腫の増悪など)の有無を確認します。次に、直近の検査データや内服薬の内容を確認した上で、医師への報告準備を整えます。
医師への報告時の会話例: 「夜間当直の田中先生でしょうか。7階東病棟の山田です。申し訳ありませんが、救急対応の合間に心不全で入院中の鈴木さんについてご相談させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
患者さんの血圧が2時間前から徐々に低下し、ただいま90/50まで低下しています。脈拍は84回/分で整、意識レベルクリアです。心不全症状の増悪は認めていません。」
具体的な指示確認
医師からの指示を受ける際は、以下の点について明確に確認します。
報告に対する医師からの返答例: 「分かりました。現在の利尿薬は中止してください。生理食塩水500mLを2時間かけて投与してください。血圧が80mmHg未満となった場合は、至急連絡してください。」
この指示に対する確認: 「承知いたしました。それでは、現在投与中のラシックスを中止し、生理食塩水500mLを2時間で投与します。血圧が80mmHg未満になった場合は至急ご連絡させていただきます。このような理解で間違いありませんでしょうか。」
振り返りのポイントと今後の対策
このケースでは、緊急性の判断と情報の優先順位付けが重要でした。特に夜間帯での急変対応においては、事前準備と情報収集が極めて重要です。
日勤帯からの申し送り内容の確認、夜間帯での観察ポイントの明確化、緊急時の対応手順の確認などを、勤務開始時に行っておくことが推奨されます。また、医師への報告内容を事前に整理し、緊急性と重要性を明確に伝えられるよう準備しておくことも大切です。
Case B:複数指示の管理
状況設定
手術後1日目の患者さん(50代女性、胃切除術後)に対して、疼痛管理、輸液管理、早期離床など、複数の指示が同時に出された場面です。
日勤帯での受け持ち看護師として、これらの指示を適切に管理する必要がありました。患者さんは手術直後のため、状態の変化にも注意が必要な状況です。
具体的な対応手順と指示内容の整理
疼痛管理については、硬膜外麻酔の持続投与と、レスキューとしてのNSAIDsの使用基準を確認します。輸液管理では、維持輸液の投与速度と、必要に応じた追加輸液の基準を確認します。早期離床については、リハビリテーション科との連携も含めて、段階的な進め方を確認します。
具体的な指示内容の例: 「疼痛時はジクロフェナク坐薬25mgを使用可能。4時間あけること。硬膜外麻酔の持続投与は2ml/時で継続。輸液は維持液を60ml/時で継続。尿量が0.5ml/kg/時未満の場合は報告。離床は今日からベッド上座位開始。バイタルサイン安定していれば、端座位まで可能。」
チーム内での情報共有方法
これらの複数の指示内容は、電子カルテへの入力だけでなく、看護師間でのホワイトボードを活用した視覚的な情報共有も行います。また、担当看護師が不在時の対応についても、具体的な手順を明確にしておきます。
Case C:指示内容の不明確な事例
状況設定
入院中の患者さん(60代男性、糖尿病性腎症)に対する降圧薬の指示内容が不明確で、確認が必要となった場面です。
医師の記載した指示には「血圧値を見て適宜調整」とだけ書かれており、具体的な数値基準が明記されていませんでした。患者さんは腎機能の低下もあり、慎重な血圧管理が必要な状況でした。
具体的な対応手順と確認内容
医師への確認時の会話例: 「循環器内科の山田先生でしょうか。本日ご指示いただいた鈴木さんの降圧薬についてご確認させていただきたいのですが、お時間よろしいでしょうか。血圧値の具体的な管理目標と、投薬基準について教えていただきたいのですが。」
確認すべき具体的な内容: 「血圧の目標値は140/90mmHg未満とし、180/100mmHg以上で降圧薬を追加投与。収縮期血圧が100mmHg未満となった場合は投与を中止し、報告してください。」
その後の対応とチーム内での共有
確認した指示内容は、電子カルテに詳細を記載するとともに、看護師間の申し送りノートにも記載します。また、次回の病棟カンファレンスで、同様のケースに関する対応手順についても検討を行うことにしました。
Case D:継続指示の見直し
状況設定
長期入院中の患者さん(80代女性、脳梗塞後のリハビリテーション目的)の継続指示について、定期的な見直しが必要となった場面です。入院時からの指示内容が、現在の状態に適していない可能性が出てきました。
特に、活動度の拡大に伴い、転倒リスクの評価と予防策の見直しが必要な状況となっていました。
チーム内での情報共有と対応策
まず、リハビリテーションスタッフと看護チームで、現在の患者さんの状態について情報共有を行います。その上で、医師との定期的なカンファレンスの場で、指示内容の見直しを提案します。特に、活動度の拡大に伴う安全管理について、具体的な提案を行います。
このように、実際の現場では様々な状況に応じた対応が求められます。これらのケーススタディを参考に、自身の経験も振り返りながら、より良い指示確認の方法を身につけていきましょう。
特に新人看護師の方は、先輩看護師の対応方法も参考にしながら、徐々にスキルを向上させていくことが重要です。次のセクションでは、医療安全管理との連携について解説していきます。
医療安全管理との連携

医師指示の確認と実施において、医療安全管理との連携は非常に重要な要素となります。
このセクションでは、医療安全の観点から見た指示確認の重要性や、具体的な安全管理の方法、さらにはインシデント発生時の対応について解説していきます。安全で質の高い医療を提供するために必要な、組織的な取り組みについても説明します。
医療安全管理体制との協働
安全管理部門との連携
医療安全管理部門は、病院全体の安全管理を統括する重要な部門です。指示確認に関するインシデントやヒヤリハットの報告は、適切に安全管理部門へ報告し、組織全体での改善活動につなげることが重要です。
また、定期的な安全管理研修への参加を通じて、最新の安全管理手法を学ぶ機会を得ることができます。
リスクマネジメントの実践
日々の業務の中で、リスクを予測し、未然に防ぐ取り組みが重要です。特に指示受け時には、指示内容の妥当性や安全性について、常に注意を払う必要があります。
疑問点があれば、その場で確認することを躊躇せず、患者安全を第一に考えた行動をとることが求められます。
インシデント予防と報告体制
予防的な取り組み
指示確認に関連するインシデントを予防するためには、システムとしての対策が重要です。例えば、ハイリスク薬剤の指示受けには必ずダブルチェックを行う、口頭指示は原則として避けるなど、具体的なルールを設定し、遵守することが必要です。
また、電子カルテシステムのアラート機能なども、積極的に活用していきます。
報告システムの活用
インシデントやヒヤリハットが発生した際は、速やかに報告システムを通じて情報を共有します。報告の際は、単なる事実の記載だけでなく、発生要因の分析や改善策の提案も含めることで、より効果的な対策につながります。
また、定期的な事例検討会を通じて、組織全体での学習機会を設けることも重要です。
安全文化の醸成
チーム内でのコミュニケーション
医療安全の基盤となるのは、開かれたコミュニケーションです。指示内容に疑問を感じた際に、職種や経験年数に関係なく、自由に質問や確認ができる環境づくりが重要です。また、定期的なカンファレンスなどを通じて、安全に関する意識の共有と向上を図ります。
継続的な改善活動
医療安全は、継続的な改善活動を通じて実現されます。インシデントレポートの分析結果や、安全管理部門からのフィードバックを基に、具体的な業務改善を行っていきます。また、改善活動の効果を定期的に評価し、必要に応じて方法の見直しを行うことも重要です。
教育・研修体制
基本的な安全教育
新人看護師に対しては、基本的な安全確認の手順や、報告の仕方などについて、段階的な教育を行います。特に、指示確認における重要ポイントや、疑問点の確認方法については、具体的な事例を用いながら丁寧に指導を行います。
また、定期的な確認テストなどを通じて、理解度の評価も行っていきます。
継続的なスキルアップ
経験年数に応じた段階的な教育プログラムを通じて、より高度な安全管理スキルの習得を目指します。また、医療安全に関する最新の知見や、他施設での取り組み事例なども積極的に学び、実践に活かしていきます。
このように、医療安全管理との連携は、安全で質の高い医療を提供するための重要な要素となります。次のセクションでは、多職種連携におけるポイントについて解説していきます。
多職種連携におけるポイント

医師指示の確認と実施は、看護師だけでなく、薬剤師、理学療法士、管理栄養士など、多くの医療職種が関わる業務です。
このセクションでは、多職種間での効果的な情報共有方法や、チーム医療を成功させるためのポイントについて解説します。特に、それぞれの職種の専門性を活かしながら、より質の高い医療を提供するための具体的な方策を説明していきます。
職種間の効果的な情報共有
カンファレンスの活用
多職種カンファレンスは、患者さんの情報を共有し、治療方針を検討する重要な場となります。各職種がそれぞれの専門的な視点から意見を出し合い、総合的な治療計画を立案します。
カンファレンスでは、患者さんの現状だけでなく、今後の目標や予測される課題についても話し合うことが重要です。
情報共有ツールの活用
電子カルテやクリニカルパスなどの情報共有ツールを効果的に活用することで、リアルタイムでの情報共有が可能となります。特に、指示内容の変更や、患者さんの状態変化については、関係する職種全員が迅速に把握できるよう、確実な記録と伝達が必要です。
各職種との連携のポイント
薬剤師との連携
薬物療法に関する指示内容については、薬剤師との密接な連携が不可欠です。特に、ハイリスク薬や新規薬剤の使用時には、投与方法や注意点について、積極的に薬剤師に確認を行います。
また、薬剤師からの情報提供や助言を、患者さんのケアに活かしていくことも重要です。
リハビリテーションスタッフとの連携
理学療法士や作業療法士との連携では、患者さんの活動状況や運動機能の評価を共有することが重要です。
リハビリテーション中の観察ポイントや、病棟での動作方法について、具体的な確認を行います。特に、活動度の拡大や制限に関する指示については、リハビリテーションスタッフと綿密な情報共有が必要です。
チーム医療の実践
効果的なチームビルディング
チーム医療を成功させるためには、各職種が互いの専門性を理解し、尊重し合う関係性が重要です。定期的なチームミーティングを通じて、コミュニケーションを深め、チームとしての一体感を醸成していきます。
また、職種間の垣根を超えた建設的な意見交換ができる環境づくりも大切です。
患者中心の医療の実践
多職種連携の ultimate goal は、質の高い患者中心の医療を提供することです。そのためには、各職種がそれぞれの専門性を活かしながら、患者さんの目標達成に向けて協働することが重要です。
定期的なカンファレンスでは、患者さんの希望や生活背景も考慮しながら、具体的な支援計画を立案していきます。
継続的な質の向上
定期的な評価と改善
多職種連携の効果を高めるためには、定期的な評価と改善が必要です。チーム医療の成果や課題について、客観的な評価を行い、必要に応じて連携方法の見直しを行います。また、他施設での成功事例なども参考にしながら、より効果的な連携方法を模索していきます。
このように、多職種連携は、安全で質の高い医療を提供するための重要な要素となります。次のセクションでは、新人看護師の成長過程に応じた段階的アプローチについて解説していきます。
新人看護師の成長過程に応じた段階的アプローチ

医師指示の確認と実施は、新人看護師にとって最も緊張する業務の一つです。
このセクションでは、新人看護師の成長段階に応じた効果的な学習方法と、段階的な実践方法について解説します。プリセプターや指導者の方々にとっても、新人看護師の指導における重要なポイントを理解する参考となります。
入職直後の基本習得期
基本的な確認手順の習得
入職後1~2ヶ月は、基本的な指示確認の手順を確実に身につける時期です。まずは指示受けの基本的な流れを理解し、5Rightsの確認を確実に行えるようになることを目指します。
この時期は必ずプリセプターと共に指示確認を行い、一つ一つの手順を丁寧に確認していきます。また、電子カルテの基本的な操作方法も、この時期に習得します。
記録の基本
基本的な記録方法についても、この時期に習得します。特に必須項目の漏れがないよう、具体的な記載例を用いながら練習を重ねます。プリセプターは記録内容を確認し、適切なフィードバックを行うことで、記録の質を向上させていきます。
実践力向上期(3~6ヶ月)
状況に応じた判断力の育成
基本的な手順を習得した後は、様々な状況での対応力を養う時期となります。この時期には、日常的な指示確認は一人で行えるようになりますが、新しい状況や複雑な指示については、先輩看護師の支援を受けながら対応します。
また、確認の優先順位付けや、緊急性の判断についても、実践を通して学んでいきます。
コミュニケーション能力の向上
医師とのコミュニケーションについても、徐々に自信を持って行えるよう練習します。最初は先輩看護師の対応を見学し、その後、先輩看護師の同席のもとで実践するなど、段階的にスキルを向上させていきます。
自立期(7~12ヶ月)
独立した実践
この時期には、通常の指示確認業務を独立して行えるようになります。特に、日常的な指示内容については、確実な確認と実施が可能となります。ただし、複雑な症例や緊急時の対応については、必要に応じて上司や先輩看護師に相談することを忘れずに行います。
後輩への指導
自身の経験を活かし、新しく入職してくる後輩の指導にも関わるようになります。特に、自分が苦労した点や、効果的だった学習方法などを共有することで、後輩の成長支援にも貢献できます。
このように、新人看護師の成長に合わせた段階的なアプローチを行うことで、確実なスキルの習得が可能となります。次のセクションでは、よくある質問についてQ&A形式で解説していきます。
継続的なスキルアップ
自己評価と目標設定
定期的に自己の成長を振り返り、次の目標を設定することが重要です。特に、苦手な分野や、さらなる向上が必要な部分を明確にし、具体的な学習計画を立てていきます。
また、プリセプターや上司との定期的な面談を通じて、客観的な評価とアドバイスを受けることも大切です。
生涯学習への意識
看護師としてのキャリアを通じて、常に新しい知識とスキルを習得していく姿勢が重要です。院内外の研修や勉強会への参加、専門書の学習など、継続的な学習機会を活用していきます。また、他職種との交流を通じて、様々な視点や知識を得ることも、スキルアップにつながります。
このように、新人看護師の成長過程に応じた段階的なアプローチを行うことで、確実なスキルの習得と、継続的な成長が可能となります。それぞれの段階で適切な支援を受けながら、着実にスキルアップを図っていくことが大切です。
おしえてカンゴさん!よくある質問Q&A

新人看護師の皆さんから寄せられる、医師指示確認に関する疑問や不安について、経験豊富な先輩看護師が分かりやすく解説します。日々の業務で感じる素朴な疑問から、具体的な対応方法まで、実践的なアドバイスをお届けします。
Q1:電話での指示受けに自信がありません
A:多くの新人看護師が不安を感じる場面ですね。電話での指示受けの際は、必ずメモを用意し、聞きながら要点を書き留めることが大切です。
また、指示内容は必ず復唱して確認し、不明な点はその場で質問するようにしましょう。特に数値や固有名詞は、一字一字はっきりと確認することをお勧めします。
Q2:指示の優先順位の判断に迷います
A:指示の優先順位は、患者さんの安全と治療の重要度を基準に判断します。バイタルサインに関する指示や、時間的な制約のある指示(検査前の絶食指示など)は、優先度が高くなります。判断に迷った場合は、必ず先輩看護師に相談してください。経験を重ねることで、適切な優先順位付けができるようになります。
Q3:医師への質問のタイミングが分かりません
A:基本的に、患者さんの安全に関わる確認は、どのような時間帯でも躊躇せずに行ってください。
ただし、緊急性の低い確認については、医師の業務状況を考慮して、適切なタイミングを選ぶことが望ましいです。特に手術直前や救急対応中は避け、余裕のある時間帯を選んで確認するようにしましょう。
Q4:指示が曖昧で判断に迷う場合はどうすればよいですか
A:指示内容が曖昧な場合は、必ずその場で確認することが重要です。
「〇〇の場合は、どのように対応すればよろしいでしょうか」というように、具体的な状況を示しながら確認するとよいでしょう。また、確認した内容は必ず記録に残し、チーム内で共有するようにしてください。
Q5:夜間の指示受けで気をつけることは何ですか
A:夜間の指示受けでは、特に正確な情報伝達が重要です。必ずメモを取りながら指示を受け、復唱して確認します。
また、緊急性の判断も重要で、状況に応じて他のスタッフの支援を求めることも必要です。夜間帯は人員が限られるため、事前に緊急時の連絡体制を確認しておくことをお勧めします。
Q6:申し送り時の注意点を教えてください
A:申し送りの際は、受けた指示内容を正確に伝達することが重要です。特に、実施条件や注意点は具体的に伝え、実施状況も含めて報告します。
また、継続中の指示については、次の確認や実施のタイミングも明確に伝えるようにしましょう。不明な点があれば、その場で確認し合うことが大切です。
Q7:指示受け後に不安を感じた場合はどうすればよいですか
A:指示を受けた後でも、不安や疑問を感じた場合は、必ず確認するようにしましょう。
「申し訳ありません。先ほどの指示内容について、もう一度確認させていただいてもよろしいでしょうか」と伝え、具体的な不安点を説明します。患者さんの安全のために必要な確認であれば、遠慮する必要はありません。
このように、医師指示の確認に関する疑問や不安は、新人看護師の皆さんにとって共通の課題となっています。一つ一つの経験を大切にしながら、確実なスキルを身につけていってください。分からないことがあれば、必ず先輩看護師に相談することを心がけましょう。
まとめ
医師指示の確認と実施は、患者さんの安全な医療を提供するための基本となる重要な業務です。本稿で解説した5Rightsの確実な実践、効果的な記録管理、適切な質問技術の習得により、指示確認の精度を向上させることができます。
新人看護師の皆さんは、一つ一つの経験を大切にしながら、段階的にスキルを向上させていってください。
より詳しい情報や、実践的なケーススタディ、経験豊富な先輩看護師からのアドバイスをお求めの方は、看護師専門サイト【ナースの森】をご覧ください。サイトでは、新人看護師の方々の成長をサポートする様々なコンテンツをご用意しています。