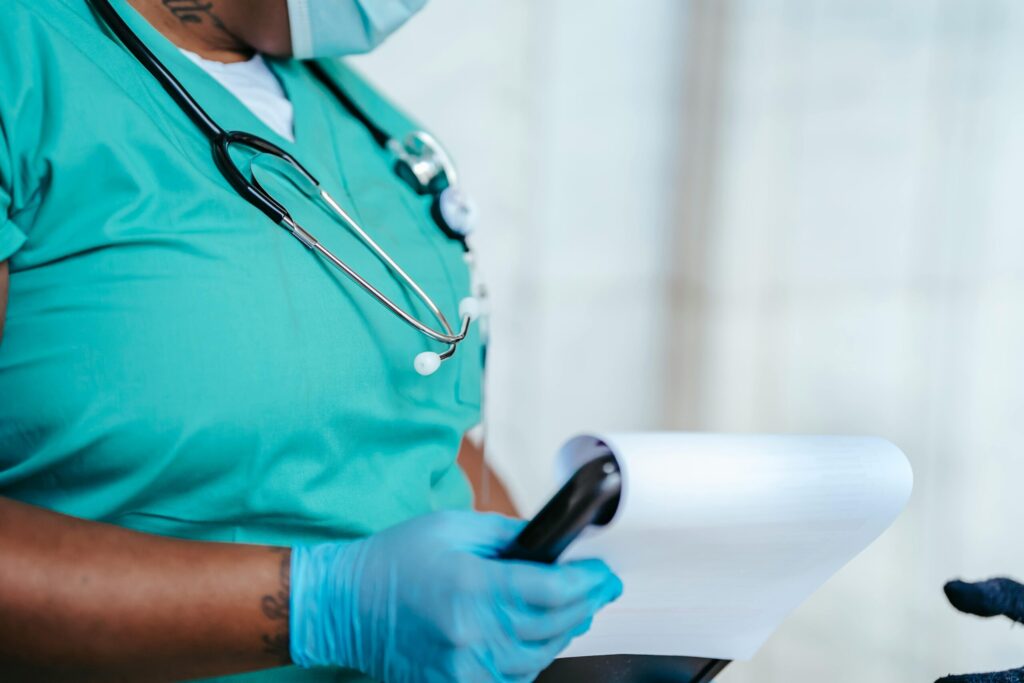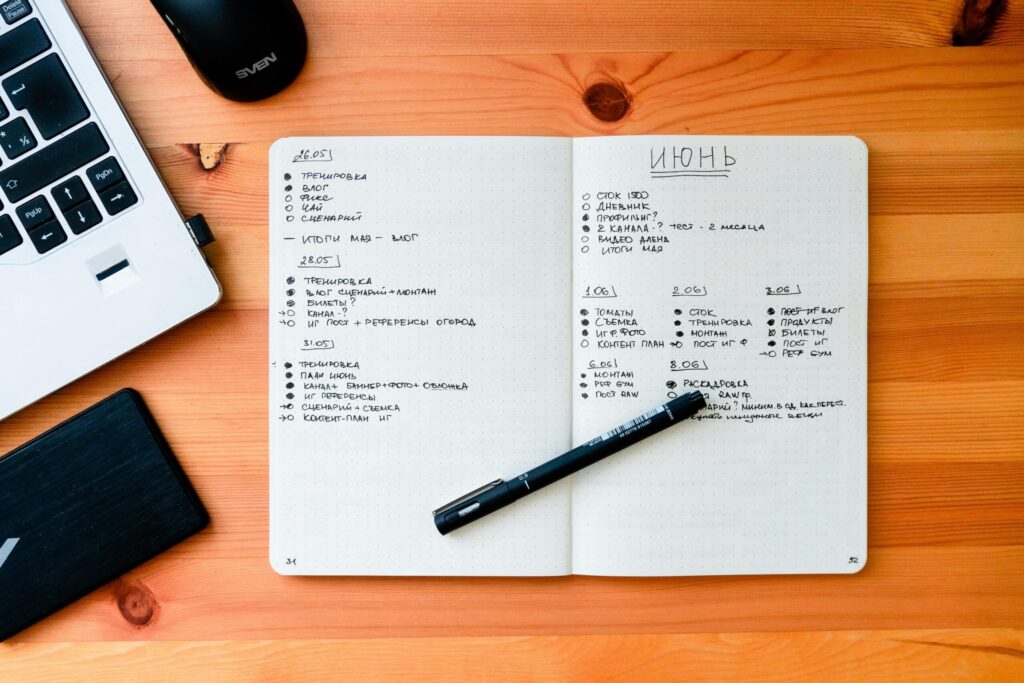助産師の給与体系や待遇について、最新の情報をもとに徹底解説します。
初任給から経験年数による昇給、各種手当の詳細まで、現場で働く助産師の声も交えながら、具体的な事例とともにお伝えします。
これから助産師を目指す方から、すでに現場で活躍されている方まで、キャリアプランの参考になる情報が満載です。
この記事で分かること
- 助産師の標準的な給与水準と病院・施設ごとの違い
- 夜勤手当や分娩手当など、実際の手取りに関わる各種手当の詳細
- 経験年数やキャリアアップによる昇給の具体的な事例
- 働き方の違いによる収入の変化と長期的なキャリア展望
- 施設別の待遇比較と転職時の給与交渉のポイント
この記事を読んでほしい人
- 助産師として働いている方
- 助産師を目指す看護学生の方
- 転職を考えている方
- より良い待遇を目指してキャリアアップを検討している方
- 出産・育児との両立を考えている方
助産師の基本給与体系

助産師の基本給与体系
医療機関における助産師の給与体系は、基本給を軸に様々な手当や賞与が加算される仕組みとなっています。施設の種類や地域、経験年数によって異なる給与水準について、詳しく解説していきます。
初任給の水準と給与体系
施設別の初任給の実態
助産師の初任給は、医療機関の規模や種類によって大きく異なります。大学病院では月給24万円から27万円、総合病院では22万円から25万円が一般的な水準となっています。
診療所では20万円から24万円、助産院では19万円から23万円というのが現状です。基本給に加えて、夜勤手当や住宅手当などの諸手当が加算されることで、実際の手取り額はこれより増額となります。
地域による給与差
首都圏や大都市圏では地域手当が加算され、基本給が高めに設定されている傾向があります。東京都では平均して月給が2万円から3万円ほど高くなり、特に23区内では更に上乗せされるケースも見られます。
一方、地方都市では若干低めの設定となりますが、生活費の違いを考慮すると実質的な収入は大きく変わらないことが多いです。
基本給の構成要素
本給の計算方法
基本給は一般的に、職務給と年齢給(経験給)で構成されています。職務給は資格や職位に応じて決定され、年齢給は経験年数に応じて加算されていきます。新卒の場合、職務給が約15万円、年齢給が約5万円というのが一般的な例となっています。
諸手当の基本構造
基本給に加えて、職務手当、資格手当、調整手当などの固定的な手当が設定されています。これらの手当は施設によって金額や種類が異なりますが、基本給の15%から30%程度が追加されるのが一般的です。
給与体系の種類
年功序列型給与体系
多くの医療機関で採用されている従来型の給与体系です。経験年数に応じて基本給が自動的に上昇していく仕組みとなっています。毎年の昇給額は3,000円から8,000円程度で、勤続年数が長くなるほど給与が安定的に上がっていきます。
職能給型給与体系
近年増加している実力主義的な給与体系です。スキルや実績に応じて給与が決定されます。特に高度な専門性を持つ助産師や、管理職として活躍する助産師には有利な制度となっています。
公立・私立の違い
公立病院の特徴
公立病院では地方公務員としての給与体系が適用されます。初任給は比較的控えめですが、定期昇給が確実で、長期的には安定した収入が見込めます。また、各種手当も充実しており、総支給額では私立を上回るケースも多くみられます。
私立病院の給与体系
私立病院では独自の給与体系を採用しているため、施設による違いが大きくなっています。初任給は公立より高めに設定されているケースが多く、実績に応じた昇給や賞与の支給など、柔軟な待遇設定が特徴です。
充実の手当制度

充実の手当制度
助産師の収入を考える上で、基本給と同様に重要なのが各種手当制度です。実際の手取り額に大きく影響する手当の種類や計算方法について、実例を交えながら詳しく解説していきます。
夜勤手当の詳細
夜勤手当の基本
夜勤手当は助産師の収入を大きく左右する重要な要素です。
一般的な夜勤手当は1回あたり20,000円から30,000円程度で設定されており、深夜時間帯(22時から翌5時)は25%増しで計算されます。月間の夜勤回数は通常4回から8回程度で、本人の希望を考慮して決定されます。
二交代制と三交代制の違い
二交代制の場合は1回の夜勤が16時間程度となり、手当も約25,000円から35,000円と高めに設定されます。三交代制では1回の勤務時間が短くなるため、手当は15,000円から25,000円程度となっています。
分娩手当の仕組み
分娩手当の計算方法
分娩介助1件あたりの手当は、平日日中で3,000円から10,000円、夜間休日では5,000円から15,000円が一般的です。分娩件数の多い施設では、月額で50,000円以上の追加収入となることも珍しくありません。
施設による差異
大学病院や総合病院では比較的低めの設定となっていますが、診療所や助産院では高額な手当を設定しているケースが多くみられます。ただし、分娩件数自体が少ない施設もあるため、実際の収入額は施設によって大きく異なります。
資格手当の種類
専門資格による手当
助産師の基本資格に加えて、専門看護師や認定看護師の資格を取得すると、月額10,000円から30,000円程度の手当が加算されます。特に周産期医療や新生児集中ケアの専門資格は優遇されており、キャリアアップの重要な要素となっています。
その他の技能手当
母乳育児支援やペリネイタルケアなどの特定の技能に対しても、手当が設定されているケースがあります。これらは月額5,000円から15,000円程度で、施設の方針によって金額が決定されます。
住宅手当・扶養手当
住宅手当の条件
賃貸住宅の場合、実費の半額程度(上限20,000円から30,000円)が支給されるのが一般的です。持ち家の場合は定額(月額10,000円程度)が支給される制度が多くなっています。
扶養手当の内容
配偶者で月額10,000円から13,000円、子供一人につき5,000円から6,000円程度が一般的な支給額です。ただし、配偶者の収入制限など、各施設で定められた条件を満たす必要があります。
特殊勤務手当
周産期医療センターでの手当
ハイリスク妊婦の管理や新生児集中ケアを行う場合、通常の勤務に対して追加で手当が支給されます。一日あたり2,000円から5,000円程度が加算されるケースが多くみられます。
緊急呼び出し手当
オンコール体制での緊急呼び出しに対しては、待機手当(日額1,000円から2,000円)と実際の出動手当(1回あたり5,000円から10,000円)が別途支給されます。
時間外勤務手当
残業手当の計算方法
時間外労働に対しては、通常の時給の125%(深夜は150%)で計算されます。管理職を除き、実際に働いた時間に応じて適切に支給される制度が整備されています。
休日勤務との組み合わせ
休日の時間外勤務となる場合は、更に割増率が上乗せされ、最大で時給の160%まで上がることもあります。
休日勤務手当
休日出勤の手当体系
休日勤務の場合、通常の時給の135%で計算されるのが一般的です。また、祝日出勤に対しては、さらに割増率が上乗せされるケースも多くみられます。
代休制度との関係
休日勤務の振替が可能な場合でも、原則として休日勤務手当は支給されます。ただし、施設によって運用方法が異なるため、採用時に確認が必要です。
キャリアアップと昇給システム

キャリアアップと昇給システム
助産師のキャリアパスには、経験年数に応じた自動的な昇給に加え、スキルアップや役職への登用による給与アップの機会が用意されています。ここでは実際の昇給例や評価制度について詳しく解説します。
経験年数による昇給の実例
新人から中堅までの昇給パターン
新卒1年目から5年目までは、年間で基本給が約15,000円から20,000円ずつ上昇していきます。特に3年目までは技術の習得に応じて昇給幅が大きく、月給で見ると毎年約2万円から3万円の上昇が期待できます。
ベテラン助産師の給与水準
経験10年以上のベテラン助産師の場合、基本給は新卒時より40万円から50万円増加しているのが一般的です。さらに、様々な専門資格の取得や役職手当により、年収600万円を超えるケースも珍しくありません。
昇進・昇格のシステム
主任助産師への昇進
一般的に経験5年から7年程度で主任助産師への昇進機会が訪れます。主任手当として月額20,000円から30,000円が追加され、基本給も同時に昇給するため、年収ベースで50万円から80万円程度の増加となります。
副師長・師長クラスの待遇
副師長では主任手当に加えて役職手当が付き、師長になると更に管理職手当が加算されます。ただし、管理職となると時間外手当は原則として支給されなくなります。
評価制度の仕組み
人事評価の基準
多くの医療機関では、技術面、業務遂行能力、リーダーシップ、後輩指導など、複数の評価項目に基づいて定期的な評価が行われます。評価結果は賞与や昇給、昇進に反映されます。
目標管理制度の活用
年度初めに個人目標を設定し、達成度に応じて評価される仕組みを導入している施設も増えています。特に専門性の向上や業務改善に関する目標が重視されます。
資格取得による給与変動
専門資格取得後の待遇
周産期専門の認定看護師資格を取得すると、月額30,000円程度の資格手当が追加されます。また、助産師外来担当者としての認定を受けると、外来手当として月額10,000円から20,000円が加算されるケースが多くみられます。
実習指導者の待遇
実習指導者講習会を修了し、学生の実習指導を担当する場合、指導手当として月額5,000円から15,000円が追加されます。
キャリアラダーの活用
段階的な能力開発
多くの医療機関では、キャリアラダーに基づいて能力開発を進めています。レベルⅠからレベルⅤまでの5段階が一般的で、各レベルの到達時に基本給が増額されます。
専門性の評価
母乳育児支援や新生児蘇生法などの専門的なスキルを習得し、実践できる段階に応じて評価が上がり、給与に反映される仕組みとなっています。
勤務形態による給与比較

勤務形態による給与比較
助産師の働き方は多様化しており、それぞれの生活スタイルやキャリアプランに合わせて選択できる勤務形態が増えています。ここでは、各勤務形態における具体的な給与体系や収入の特徴について解説します。
常勤と非常勤の比較
常勤助産師の給与体系
常勤助産師の場合、月給制が基本となり、基本給に各種手当が加算される形で給与が構成されます。賞与は年2回から3回で、年間4.0か月から5.0か月分が一般的です。社会保険も完備されており、福利厚生面でも充実しています。
非常勤助産師の収入例
非常勤の場合は時給制となり、経験年数に応じて1,800円から2,500円程度の設定となっています。月の勤務日数や時間は相談により決定でき、常勤と同様の夜勤手当や分娩手当が支給される施設も多くみられます。
夜勤専従の特徴
夜勤専従の給与設定
夜勤専従者は基本給に加えて、高額の夜勤手当が保証されます。一般的な夜勤手当に20%から30%程度の割増が設定されており、月収40万円から50万円程度を見込むことができます。
勤務スケジュールと収入
月間の夜勤回数は10回から12回程度が標準的で、日中の会議や研修への参加も考慮されています。休日は十分に確保され、ワークライフバランスを重視した働き方が可能です。
パートタイムの時給設定
時給の計算方法
パートタイム助産師の時給は、常勤助産師の月給を基準に算出されます。一般的な計算式では、月給の1/155から1/165程度で時給が設定され、これに経験年数による加算が行われます。
短時間正社員との違い
短時間正社員制度を導入している施設では、常勤の給与体系を基準に勤務時間比例で給与が決定されます。賞与や昇給も常勤と同様の制度が適用されるため、長期的なキャリア形成が可能です。
フレックスタイムの特徴
給与計算の仕組み
フレックスタイム制を採用している施設では、月の所定労働時間を基準に基本給が設定されます。コアタイム(必ず勤務する時間帯)とフレキシブルタイム(自由に選択できる時間帯)が設定され、超過時間は翌月に調整されます。
時間管理と手当
変形労働時間制と組み合わせることで、繁忙期と閑散期の勤務時間を効率的に調整できます。時間外手当は月の規定時間を超えた場合に支給され、夜勤や休日勤務の割増賃金も通常通り適用されます。
変則勤務の実態
シフト制による給与変動
変則勤務では、日中勤務と夜勤を組み合わせたシフトを組むことで、効率的な人員配置が可能となります。シフトの種類に応じて異なる手当が設定され、月によって収入に変動が生じます。
休日・祝日の扱い
変則勤務者の休日は週単位ではなく、月単位で管理されることが多くなっています。祝日勤務の場合は、通常の135%増しの給与に加えて、代休が付与されるのが一般的です。
施設別の待遇比較

施設別の待遇比較
助産師の待遇は勤務する医療機関の種類によって大きく異なります。ここでは、各施設における給与体系や待遇の特徴について、実際のデータを基に詳しく解説していきます。
大学病院の特徴
給与水準とベースアップ
大学病院では、初任給が24万円から27万円と比較的高めに設定されています。定期昇給は年1回で、毎年約15,000円から20,000円のベースアップがあります。また、研究手当として月額10,000円から20,000円が別途支給されるケースも多くみられます。
教育・研究機会
大学病院では教育・研究活動への参加機会が多く、学会発表や論文執筆に対する手当も充実しています。専門資格取得のためのサポート体制も整っており、キャリアアップを目指しやすい環境となっています。
総合病院の制度
手当体系の特徴
総合病院では、基本給に加えて様々な手当が設定されています。特に救急医療に関連する手当が充実しており、夜間の緊急対応や休日勤務に対する待遇が手厚くなっています。
キャリアパスの整備
職位や職能に応じた給与体系が明確に定められており、昇進・昇格の基準も明確です。特に周産期センターを有する病院では、ハイリスク分娩への対応能力が評価され、それに応じた給与設定となっています。
診療所の給与体系
基本給と分娩手当
診療所では分娩件数に応じた手当が重視され、1件あたり5,000円から15,000円の分娩手当が支給されます。基本給は総合病院より若干低めですが、分娩手当を含めると総支給額は同等以上となることも多くみられます。
福利厚生の特徴
規模は小さいものの、アットホームな雰囲気の中で働きやすい環境が整っています。有給休暇の取得率も高く、産休・育休後の復帰プログラムも充実している施設が増えています。
助産院独自の制度
独立開業支援
助産院での勤務経験は、将来の独立開業に向けた重要なステップとなります。経営ノウハウの習得機会も多く、開業資金の積立制度を設けている施設もみられます。
収入の変動要因
分娩件数による収入変動が大きいのが特徴です。基本給は20万円程度からですが、分娩介助や母乳外来などの実績に応じて、大幅な収入アップが期待できます。
行政機関での待遇
公務員としての給与体系
保健所や市町村の母子保健部門で働く場合は、地方公務員としての給与体系が適用されます。初任給は一般の医療機関より控えめですが、定期昇給が確実で、長期的には安定した収入が見込めます。
行政特有の手当
地域手当や扶養手当など、公務員特有の手当が充実しています。また、時間外勤務は少なめで、ワークライフバランスを重視した働き方が可能となっています。
実践的なケーススタディ

助産師の給与や待遇は、経験年数や勤務形態、働く施設によって大きく異なります。ここでは実際の事例を基に、様々なキャリアステージにおける収入モデルを詳しく解説していきます。
新卒助産師の1年目
Aさんの給与事例
関東圏の大学病院に就職したAさんの事例をご紹介します。基本給は23万円でスタートし、夜勤手当(月4回)と各種手当を含めると、月の総支給額は32万円となっています。年間賞与は基本給の4.2ヶ月分で、年収は約480万円です。
初年度の給与変動
入職後3ヶ月間は夜勤がなく、基本給と基本手当のみの支給でしたが、夜勤開始後は収入が大幅に増加しました。年度末には習熟度に応じた評価が行われ、翌年度の給与に反映される仕組みとなっています。
経験10年のベテラン事例
Bさんのキャリア形成
総合病院で10年の経験を積んだBさんは、主任助産師として活躍しています。基本給38万円に、主任手当2.5万円、夜勤手当(月3回)を加えると、月の総支給額は48万円に達します。年間賞与は基本給の5ヶ月分で、年収は約720万円となっています。
スキルアップによる収入増
母乳育児支援の認定資格を取得し、専門外来も担当することで、追加の資格手当と外来手当が支給されています。後輩指導も担当しており、指導手当も加算されています。
転職による待遇改善
Cさんの転職事例
経験5年目で診療所から総合病院への転職を果たしたCさんの事例です。基本給は2万円のアップに加えて、分娩件数の増加により手当も増額となり、月の総支給額で5万円の収入増を実現しました。
転職時の交渉ポイント
前職での経験と実績を活かし、給与交渉では基本給に加えて、専門性を活かした外来担当手当の新設を提案し、受け入れられました。
給与交渉の成功例
Dさんの交渉術
産休から復帰したDさんは、短時間正職員としての勤務を希望し、基本給は据え置きのまま、時間外勤務を減らすことで、時給ベースでは実質的な待遇改善を実現しました。
効果的な交渉方法
事前に自身の貢献度や実績を数値化して準備し、施設側のニーズも考慮した提案を行うことで、双方にとって満足できる結果となりました。
おしえてカンゴさん!Q&A
助産師の給与や待遇について、現場で働く先輩助産師のカンゴさんに、よくある疑問や気になる点について詳しく解説してもらいました。これから助産師を目指す方や、キャリアアップを考えている方の参考になる情報をQ&A形式でお届けします。
給与に関する疑問解決
初任給について
Q:「新卒で就職する場合、どのくらいの初任給が一般的でしょうか?」
A:2025年現在、大学病院や総合病院では基本給が22万円から25万円程度となっています。これに夜勤手当や各種手当が加わることで、月の手取りは25万円から30万円程度となるのが一般的です。ただし、地域や施設によって差があることも覚えておきましょう。
賞与の相場
Q:「賞与はどのくらいもらえますか?」
A:一般的な医療機関では年2回から3回の支給があり、年間で基本給の4.0から5.0ヶ月分程度です。業績連動型の賞与制度を導入している施設では、個人やチームの評価によって増減する仕組みとなっています。
待遇に関する質問
福利厚生について
Q:「福利厚生はどのような制度が一般的ですか?」
A:社会保険完備はもちろん、住宅手当や扶養手当、さらに認定資格取得支援制度や学会参加費用の補助など、様々な制度が用意されています。最近では、産休・育休後の復職支援プログラムを充実させている施設も増えています。
キャリアアップの方法
Q:「給与アップにつながるキャリアアップの方法を教えてください」
A:専門性の高い認定資格の取得や、主任・師長などの役職への昇進が代表的です。特に周産期医療や新生児集中ケアの専門資格は、月額2万円から3万円程度の手当につながることが多いです。
転職に関するアドバイス
転職のタイミング
Q:「転職で給与アップを狙うなら、何年目がベストですか?」
A:経験3年から5年が転職の好機とされています。この時期は基本的なスキルが身についており、なおかつ新しい環境での成長可能性も高く評価されます。ただし、現在の職場で十分なキャリアを積んでからの方が、よりよい条件での転職が可能になることもあります。
将来の展望
開業までの道のり
Q:「将来の開業を考えています。その準備として今から始めることはありますか?」
A:まずは総合病院で基礎的な経験を積み、その後助産院での勤務経験を重ねることをお勧めします。また、経営や会計の知識も必要となるため、関連する研修や講座への参加も検討するとよいでしょう。
今後の展望と給与動向
助産師の給与体系は、医療制度の変更や社会のニーズの変化により、今後も大きく変わっていく可能性があります。ここでは、今後予想される変化や動向について詳しく解説していきます。
給与トレンドの変化
専門性の評価向上
医療の高度化に伴い、助産師の専門性に対する評価は今後さらに高まると予想されています。特に周産期医療や新生児集中ケアの分野では、専門的なスキルを持つ助産師への需要が増加し、それに応じた給与体系の見直しが進むと考えられます。
成果主義の導入
従来の年功序列型から、実績や能力を重視した給与体系への移行が進んでいます。分娩介助件数や母乳育児支援の成果など、具体的な実績に基づく評価制度の導入が増えています。
将来的な変化の予測
働き方改革の影響
労働時間の適正化や、夜勤回数の制限により、基本給の見直しや各種手当の増額が検討されています。特に時間外労働の削減に伴う給与保障制度の整備が進められています。
新しい働き方への対応
オンライン相談や遠隔での保健指導など、新しい業務形態に対応した給与体系の整備も進んでいます。これらの業務に対する適切な評価と報酬の設定が、今後の課題となっています。
政策による影響
医療制度改革の影響
診療報酬改定や医療制度改革により、助産師の業務範囲や責任が拡大する可能性があります。これに伴い、給与体系の見直しや新たな手当の創設が検討されています。
地域医療構想との関連
地域における周産期医療体制の整備に伴い、助産師の役割や待遇にも変化が予想されます。特に地域医療連携における助産師の貢献度が評価され、それに応じた処遇改善が期待されています。
まとめ
以上、助産師の給与体系と待遇について詳しく解説してきました。基本給に加えて様々な手当が用意されており、経験やスキルに応じたキャリアアップの機会も充実しています。
さらに詳しい情報や、実際の転職事例、キャリアアドバイスをお求めの方は、【はたらく看護師さん】の会員登録がおすすめです。
より詳しい情報は【はたらく看護師さん】で
助産師の求人情報や給与相場、転職成功事例など、さらに詳しい情報を【はたらく看護師さん】で公開しています。