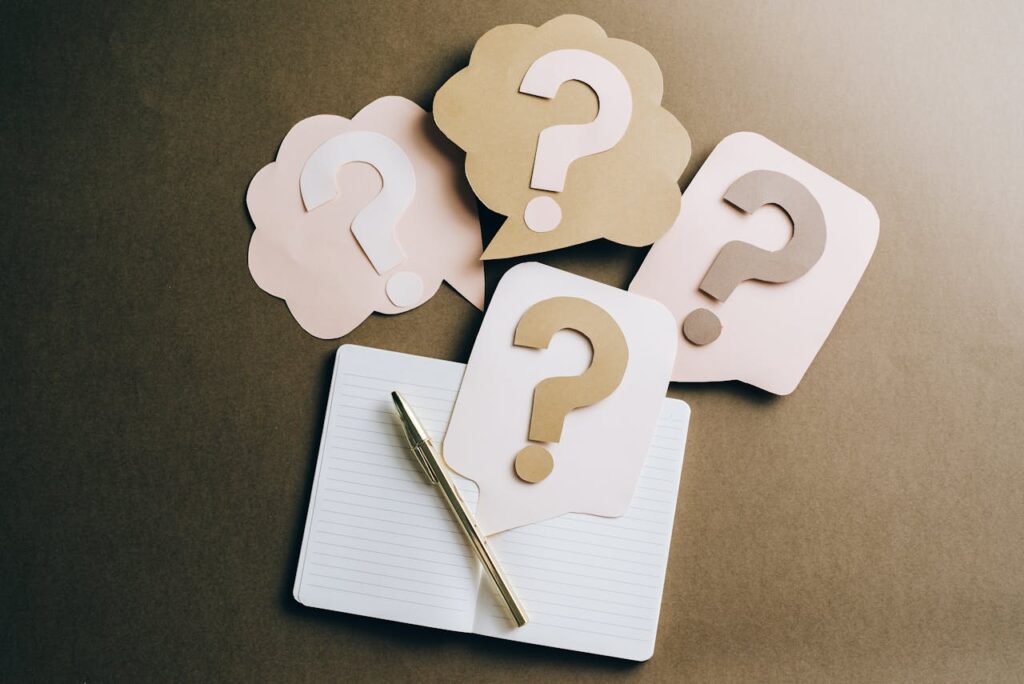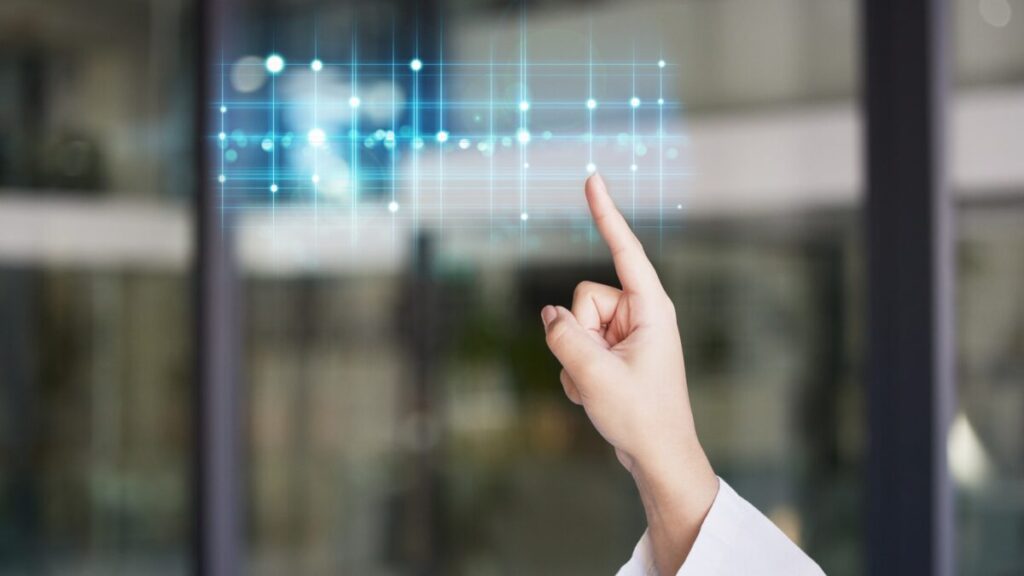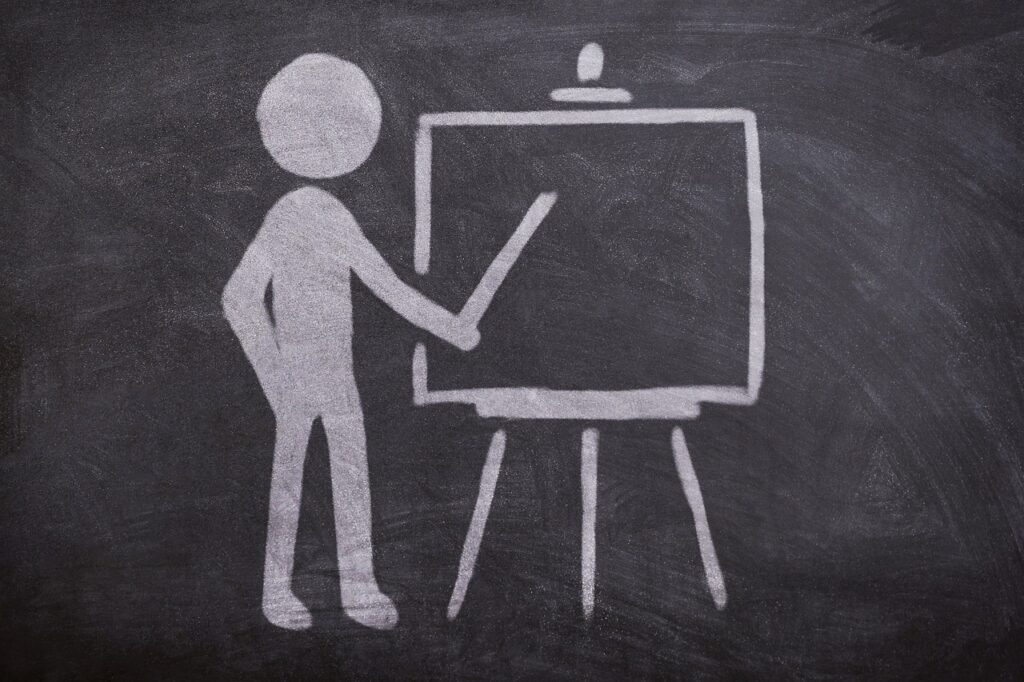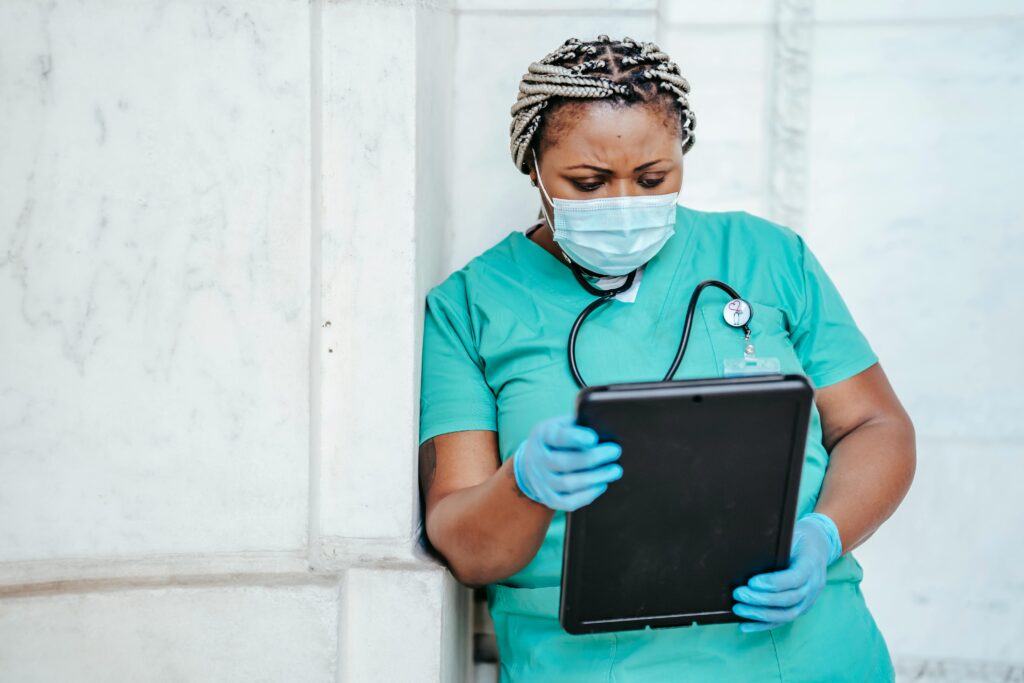医療機関の経営効率化が求められる昨今、手術室の効率的な運用は病院経営の要となっています。
本記事では、一般病院における手術室稼働率向上のための実践的な方法と、具体的な改善事例をご紹介します。
運用効率化によって収益改善を実現するためのポイントを、現場の視点から詳しく解説していきます。
この記事で分かること
- 手術室稼働率の正確な測定と分析手法
- 具体的な運用効率化の施策と実施手順
- 予約管理システムの最適化アプローチ
- 収益改善につながる運用体制の構築方法
- 改善効果の測定と評価の具体的手法
この記事を読んでほしい人
- 手術部長として稼働率向上を目指している方
- 看護部長として運営改善に取り組む方
- 手術室の運営管理に携わる医療従事者
- 病院経営の効率化を検討している管理職の方
- 手術室看護師として業務改善に関心がある方
手術室稼働率の現状分析と課題抽出

手術室の効率的な運用を実現するためには、まず現状を正確に把握し、課題を特定することが不可欠です。ここでは、データに基づく分析手法と、よくある課題についてご説明します。
データ収集と分析の基礎
手術室の現状を把握するためには、適切なデータ収集と分析が重要です。収集すべきデータには手術実施時間、準備時間、片付け時間などが含まれます。これらのデータは、手術室運営の改善に向けた基礎となります。
データ収集のポイント
手術室稼働率を正確に測定するためには、実際の手術時間だけでなく、準備や片付けにかかる時間も含めた総合的なデータ収集が必要です。手術部スタッフと連携し、正確なデータを継続的に記録することで、信頼性の高い分析が可能となります。
タイムスタディの実施方法
タイムスタディを実施する際は、手術室入室から退室までの全プロセスを細分化して記録します。具体的には入室時刻、麻酔開始時刻、執刀開始時刻、執刀終了時刻、覚醒時刻、退室時刻などを正確に記録していきます。
稼働率算出の手法
手術室稼働率は、利用可能な手術室時間に対する実際の使用時間の割合として算出します。算出には定時間内手術と時間外手術を区別し、それぞれの実績を把握することが重要です。
稼働率の計算方法
稼働率の計算には、手術実施時間に加えて、準備時間と片付け時間を含めた総使用時間を考慮します。これにより、より実態に即した稼働率を把握することができます。
現状分析における重要指標
手術室の運営状況を評価する際は、稼働率以外にも複数の重要な指標があります。これらの指標を総合的に分析することで、より正確な現状把握が可能となります。
予定手術と緊急手術の割合
予定手術と緊急手術の適切なバランスを把握することは、効率的な運営のために重要です。緊急手術の発生頻度や時間帯を分析することで、必要な対応体制を検討することができます。
キャンセル率の分析
手術のキャンセルは稼働率に大きな影響を与えます。キャンセルの原因を分類し、対策を立てることで、稼働率の向上につなげることができます。
課題の特定と優先順位付け
現状分析により明らかになった課題には、優先順位をつけて取り組むことが効果的です。課題の影響度と改善の実現可能性を考慮しながら、計画的に対応を進めていきます。
共通的な課題の整理
多くの医療機関で見られる共通的な課題として、手術時間の予測精度の低さ、診療科間の調整不足、緊急手術への対応体制の不備などが挙げられます。これらの課題に対して、具体的な改善策を検討していく必要があります。
改善の方向性検討
特定された課題に対しては、短期的な対応と中長期的な対応を区分けして検討します。例えば、手術時間の予測精度向上は短期的な課題として、システム導入は中長期的な課題として位置づけることができます。
効率的な運用体制の構築

手術室の効率的な運用を実現するためには、適切な組織体制の構築と、それを支えるシステムの導入が不可欠です。このセクションでは、具体的な運用体制の構築方法と、それを成功に導くためのポイントについて解説します。
手術室運営委員会の設置と役割
効果的な運営改善を実現するためには、部門横断的な運営委員会の設置が重要です。運営委員会では、現場の課題や改善策について多角的な視点から検討を行います。
委員会メンバーの構成
運営委員会のメンバーには、手術部長、看護部長、各診療科の代表医師、手術室看護師長、麻酔科医師、医事課職員など、関連する部門の代表者を含める必要があります。それぞれの立場から意見を出し合うことで、バランスの取れた運営が可能となります。
各メンバーの役割と責任
委員会の各メンバーには明確な役割と責任を設定します。手術部長は全体の統括を、看護部長は看護体制の整備を、医事課職員は収益面での分析を担当するなど、それぞれの専門性を活かした役割分担を行います。
予約管理システムの最適化
効率的な手術室運営には、適切な予約管理システムの導入と運用が欠かせません。システムの選定から運用ルールの策定まで、計画的に進めていく必要があります。
システム選定のポイント
予約管理システムを選定する際は、使いやすさ、他システムとの連携性、カスタマイズ性などを考慮します。また、導入後のサポート体制も重要な選定基準となります。
システム機能の要件定義
必要な機能として、手術予約の登録・変更、リソース管理、統計分析、レポート作成などが挙げられます。これらの機能を実現できるシステムを選定することで、効率的な運用が可能となります。
スタッフ教育プログラムの確立
運用体制の改善には、スタッフの能力向上が不可欠です。計画的な教育プログラムを通じて、必要なスキルとナレッジの習得を支援します。
教育内容の設計
教育プログラムには、システムの操作方法、運用ルール、緊急時の対応など、実務に即した内容を含みます。また、定期的な更新研修も重要です。
研修スケジュールの立案
新人研修、定期研修、専門研修など、段階的な教育プログラムを設計します。各スタッフのレベルに応じた適切な研修機会を提供することで、効果的な学習が可能となります。
KPIの設定と管理
運用改善の効果を測定するためには、適切なKPIの設定と継続的なモニタリングが重要です。実態を正確に把握できる指標を選定し、定期的な評価を行います。
主要KPIの設定
手術室稼働率、準備時間、キャンセル率など、重要な指標を設定します。これらの指標を定期的にモニタリングすることで、改善の効果を可視化することができます。
データ収集と分析方法
KPIの測定に必要なデータを正確に収集し、分析する体制を整備します。分析結果は定期的に運営委員会で共有し、必要な改善策を検討します。
コミュニケーション体制の整備
効率的な運用には、部門間の円滑なコミュニケーションが不可欠です。情報共有の仕組みづくりと、定期的なミーティングの実施が重要となります。
情報共有の仕組み
日々の運営状況や課題について、関係者間で適切に情報共有できる仕組みを構築します。電子カルテシステムやグループウェアなどを活用し、効率的な情報共有を実現します。
定例ミーティングの設計
週次や月次での定例ミーティングを設定し、運営状況の確認と課題の共有を行います。参加者の役割と議題を明確にし、効率的な会議運営を心がけます。
実践的な改善事例

手術室の稼働率向上を実現した医療機関の具体的な取り組みをご紹介します。これらの事例は、規模や地域性が異なる医療機関でも応用可能な示唆に富んだ内容となっています。
S病院における改革事例
S病院は、地域の中核を担う500床規模の総合病院です。手術室の運営効率化に向けた包括的な改革を実施し、大きな成果を上げることができました。
改革前の状況と課題
改革前のS病院では、手術室稼働率が65%程度に留まっており、診療科間の調整や準備時間の標準化などに課題を抱えていました。特に午前中の手術開始時刻の遅れと、診療科間での手術枠の偏りが大きな問題となっていました。
具体的な問題点の分析
手術部長を中心とした分析チームが、三か月間にわたって詳細な現状分析を実施しました。その結果、手術準備時間のばらつきが大きいこと、緊急手術の受け入れ体制が整っていないこと、診療科間の連携が不十分であることなどが明らかになりました。
改善策の立案と実施
現状分析の結果を踏まえ、S病院では段階的な改善策を実施していきました。まず、手術室運営委員会を設置し、部門横断的な改善活動を開始しています。
改善の具体的なステップ
第一段階として、データに基づく標準手術時間の設定を行いました。過去一年間の手術データを分析し、術式ごとの標準時間を算出しています。この作業には、手術部スタッフと医事課が協力して取り組みました。
運用ルールの見直し
手術枠の配分ルールを見直し、各診療科の実績と需要に応じた柔軟な運用を可能にしました。また、緊急手術用の専用枠を設定し、予定手術への影響を最小限に抑える工夫を行っています。
T医療センターの成功事例
T医療センターは、都市部に位置する300床規模の専門病院です。手術室の効率化に特化した改善プロジェクトを実施し、顕著な成果を上げることができました。
プロジェクトの概要
T医療センターでは、手術室の運用効率化を経営改善の重点課題として位置づけ、外部コンサルタントも交えた本格的なプロジェクトを立ち上げています。プロジェクト期間は6か月間で、明確な数値目標を設定して取り組みました。
具体的な施策内容
予約システムの電子化や、手術準備作業の標準化、スタッフ教育プログラムの確立など、包括的な改善施策を実施しています。特に、手術準備のための標準作業手順書(SOP)の作成と運用は、大きな効果を上げることができました。
改善効果の検証
両医療機関とも、改善活動の効果を定量的に測定し、継続的な改善につなげています。具体的な成果指標として、手術室稼働率の向上、キャンセル率の低下、超過時間の短縮などが挙げられます。
S病院の改善結果
S病院では、改善活動の結果、手術室稼働率が78%まで向上し、キャンセル率も5%減少しました。また、一日あたりの超過時間が平均30分短縮され、スタッフの時間外勤務も大幅に削減することができました。
継続的な改善活動
改善効果を維持するため、月次での進捗確認と課題の洗い出しを行っています。新たな課題が発見された場合は、速やかに対策を検討し、実施する体制を整えています。
失敗事例からの学び
成功事例だけでなく、改善活動が思うような成果を上げられなかった事例からも、重要な教訓を得ることができます。ここでは、他院での失敗事例とその要因分析についてもご紹介します。
典型的な失敗パターン
改善活動の開始時に現場の意見を十分に聴取せず、トップダウンで施策を押し付けてしまったケースや、データに基づかない感覚的な改善を行ってしまったケースなどが報告されています。
失敗を防ぐポイント
改善活動を成功に導くためには、現場スタッフの巻き込みと、データに基づく客観的な分析が重要です。また、段階的な改善アプローチを採用し、小さな成功体験を積み重ねていくことが効果的です。
地域性による特徴と対応
手術室の運用改善には、医療機関の立地する地域の特性も考慮する必要があります。都市部と地方では、医療ニーズや人材確保の状況が大きく異なる場合があります。
都市部の医療機関の特徴
都市部の医療機関では、高度な医療ニーズへの対応と、競合医療機関との差別化が求められます。また、救急搬送の受け入れも多いため、柔軟な運用体制の構築が必要となります。
地方医療機関の工夫
地方の医療機関では、限られた医療資源を効率的に活用する工夫が必要です。地域の医療機関との連携を強化し、適切な機能分担を行うことで、効率的な運営を実現している事例もあります。
具体的なツールと実践方法

手術室の効率的な運営を実現するためには、適切なツールの活用と実践的な手法の導入が重要です。このセクションでは、現場で即座に活用できる具体的なツールと、その効果的な使用方法についてご説明します。
手術室稼働率管理シート
日々の手術室の稼働状況を正確に把握し、改善につなげるためには、専用の管理シートの活用が効果的です。エクセルベースの管理シートを用いることで、データの収集と分析を効率的に行うことができます。
管理シートの基本構成
管理シートには、日付、診療科、術式、予定時間、実施時間、差異、原因分析などの項目を設定します。これらのデータを日々入力することで、稼働状況の推移を視覚的に把握することが可能となります。
データ入力のポイント
入力担当者を明確にし、データの精度を担保することが重要です。また、入力ルールを標準化し、スタッフ間での認識の違いがないようにする必要があります。
手術室運営委員会議事録テンプレート
効果的な委員会運営のためには、適切な議事録の作成と管理が不可欠です。テンプレートを活用することで、重要な議題や決定事項を漏れなく記録することができます。
テンプレートの構成要素
日時、参加者、議題、決定事項、課題、次回アクションなどの項目を設定します。また、進捗管理のための項目も含めることで、継続的な改善活動を支援します。
記録方法の標準化
議事録作成の担当者が変更になっても一貫性のある記録が行えるよう、記入例や注意点をテンプレートに含めておくことが推奨されます。
標準手順書(SOP)の作成ガイド
手術室での作業を標準化するためには、詳細な手順書の整備が重要です。手順書の作成には、現場スタッフの意見を十分に取り入れ、実践的な内容とすることが求められます。
手順書の基本構成
目的、適用範囲、責任者、具体的な手順、注意事項、関連文書などの項目を含みます。図や写真を活用することで、より分かりやすい手順書となります。
改訂管理の方法
手順書は定期的な見直しと更新が必要です。改訂履歴を管理し、最新版が必ず使用されるよう、文書管理システムを整備することが重要となります。
KPI管理表のフォーマット
手術室の運営状況を可視化し、改善活動の効果を測定するためには、適切なKPI管理表の活用が不可欠です。データの収集から分析、報告までを効率的に行うためのフォーマットを整備します。
KPI管理表の基本要素
稼働率、キャンセル率、超過時間など、重要な指標を設定し、日次、週次、月次での推移を記録します。グラフや図表を活用することで、傾向分析が容易になります。
データの活用方法
収集したデータは、定期的な運営委員会での報告や、改善活動の効果測定に活用します。また、スタッフへのフィードバックにも使用し、モチベーション向上につなげることができます。
チェックリストの整備
手術室での業務を確実に実施するためには、適切なチェックリストの活用が効果的です。手術前、手術中、手術後の各段階で必要な確認項目を整理し、標準化されたチェックリストを作成します。
チェックリストの種類
手術準備チェックリスト、タイムアウトチェックリスト、術後確認チェックリストなど、場面に応じた複数のチェックリストを整備します。各チェックリストには、必要な確認項目を漏れなく記載します。
運用ルールの設定
チェックリストの使用タイミングや記入方法、保管方法などについて、明確なルールを設定します。また、定期的な見直しを行い、必要に応じて項目の追加や修正を行います。
コミュニケーションツール
効率的な手術室運営には、スタッフ間の円滑なコミュニケーションが不可欠です。電子カルテシステムやグループウェアなど、適切なツールを活用することで、情報共有の効率化を図ります。
情報共有の方法
日々の予定変更や緊急案件の連絡など、リアルタイムでの情報共有が必要な場面では、院内メッセージングシステムやPHSなどを活用します。重要度に応じて、適切な連絡手段を選択することが重要です。
記録の管理方法
情報共有の記録は、後から参照できるよう適切に管理します。電子カルテシステムへの記載や、専用の記録用紙の活用など、確実な記録方法を確立します。
おしえてカンゴさん!Q&A

手術室の稼働率向上に関して、現場でよく聞かれる質問とその回答をまとめました。実務に即した具体的なアドバイスを、経験豊富な先輩看護師「カンゴさん」が分かりやすく解説します。
稼働率の基準について
Q1:適正な手術室稼働率はどのくらいですか?
医療機関の規模や特性によって最適な稼働率は異なりますが、一般的には75-80%が理想的とされています。これより高すぎると緊急手術への対応が困難になり、低すぎると経営効率が悪化する傾向にあります。
地域の救急医療体制や診療科の構成なども考慮して、適切な目標値を設定することが重要です。
準備時間の短縮について
Q2:手術準備時間を短縮するためのコツを教えてください。
効率的な準備のためには、標準化された手順書の作成と、それに基づく作業の実施が重要です。よく使用する器械や器具をキット化することで、準備時間を大幅に短縮できます。
また、前日までに必要物品のチェックリストを確認し、不足している物品を補充しておくことも効果的です。
緊急手術への対応
Q3:緊急手術を受け入れながら、定期手術の予定も守るにはどうすればよいですか?
緊急手術に対応するためには、あらかじめ適切な枠を確保しておくことが重要です。過去のデータを分析し、緊急手術の発生頻度が高い時間帯を把握した上で、緊急手術用の専用枠を設定することをお勧めします。
また、診療科間で柔軟な調整が可能な体制を整えることも必要です。
スタッフ教育について
Q4:新人スタッフの教育で特に注意すべき点は何ですか?
新人教育では、基本的な手技の習得とともに、チーム医療の重要性を理解してもらうことが大切です。段階的な教育プログラムを作成し、経験豊富なスタッフがマンツーマンで指導する体制を整えることをお勧めします。
また、定期的な振り返りの機会を設け、課題や不安点を早期に把握することも重要です。
診療科との連携
Q5:診療科との良好な関係を築くためのポイントを教えてください。
定期的なコミュニケーションの機会を設けることが重要です。手術室運営委員会などの場で、各診療科の要望や課題を共有し、解決策を一緒に検討していくことをお勧めします。
また、データに基づく客観的な分析結果を提示することで、建設的な話し合いが可能となります。
業務の効率化
Q6:日々の業務をより効率化するためのアドバイスをください。
業務の効率化には、現場スタッフの意見を積極的に取り入れることが重要です。定期的なカンファレンスを開催し、業務上の課題や改善案について話し合う機会を設けましょう。また、ICTツールの活用も効率化に有効です。
手術予約システムや物品管理システムなど、適切なツールの導入を検討することをお勧めします。
感染対策との両立
Q7:効率化を進めながら、感染対策も徹底するにはどうすればよいですか?
感染対策と効率化は、相反するものではありません。むしろ、標準化された手順書に感染対策の要素を組み込むことで、より確実な実施が可能となります。手洗いや器材の取り扱いなど、基本的な感染対策手順を明確化し、効率的な動線を設計することが重要です。
キャンセル対策について
Q8:手術のキャンセルを減らすための工夫を教えてください。
キャンセル対策には、術前評価の充実と患者さんとのコミュニケーション強化が重要です。術前外来での丁寧な説明と、必要な検査の確実な実施により、直前のキャンセルを防ぐことができます。
また、キャンセルが発生した場合の代替手術の受け入れ体制を整えておくことも効果的です。
まとめ
手術室の稼働率向上は、現状分析、適切な改善策の立案、効果的な運用体制の構築が重要です。本記事でご紹介した具体的な施策と事例を参考に、皆様の医療機関に合わせた改善活動を進めていただければと思います。
さらに詳しい実践方法や、他の医療機関の取り組み事例については、【はたらく看護師さん】の会員専用コンテンツでご覧いただけます。
より詳しい情報とサポート
手術室の運営改善や看護師のキャリアアップについて、さらに詳しい情報をお求めの方は、【はたらく看護師さん】の会員登録がおすすめです。