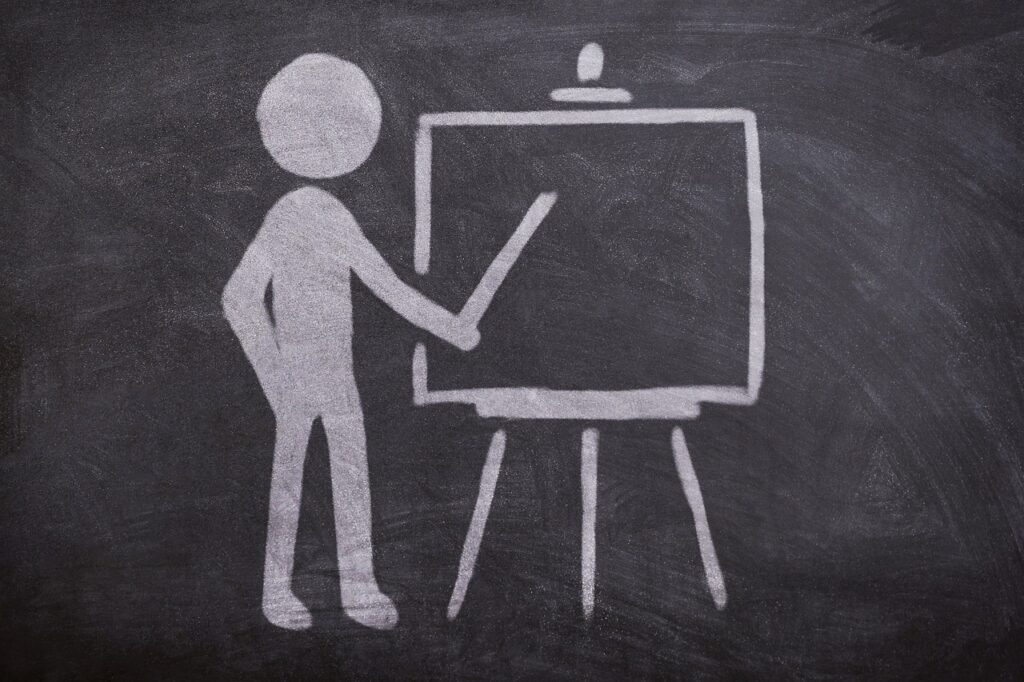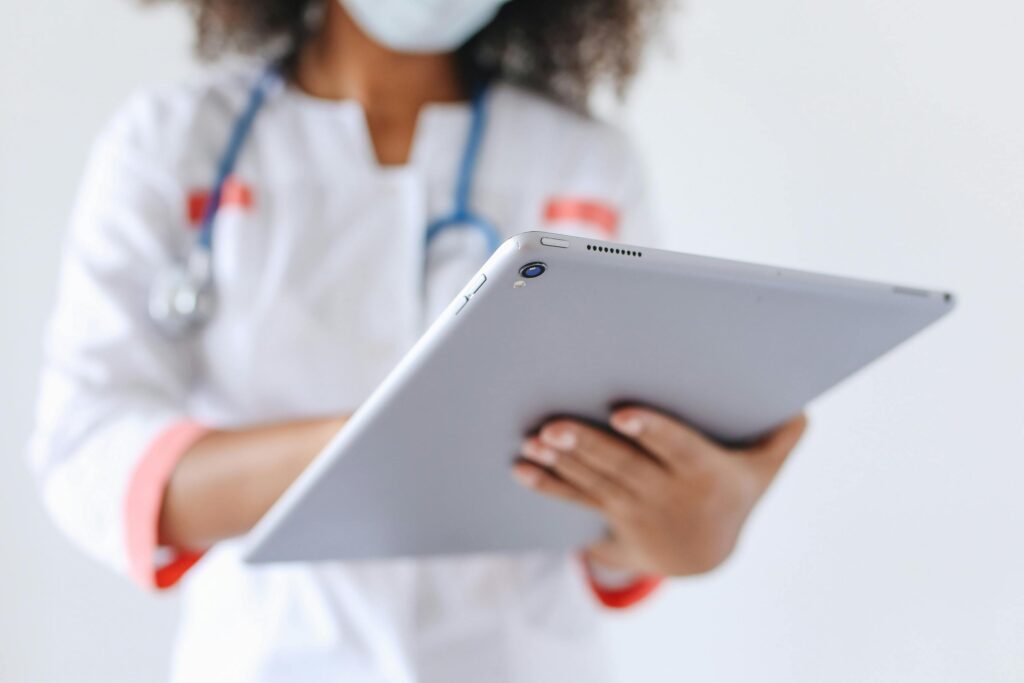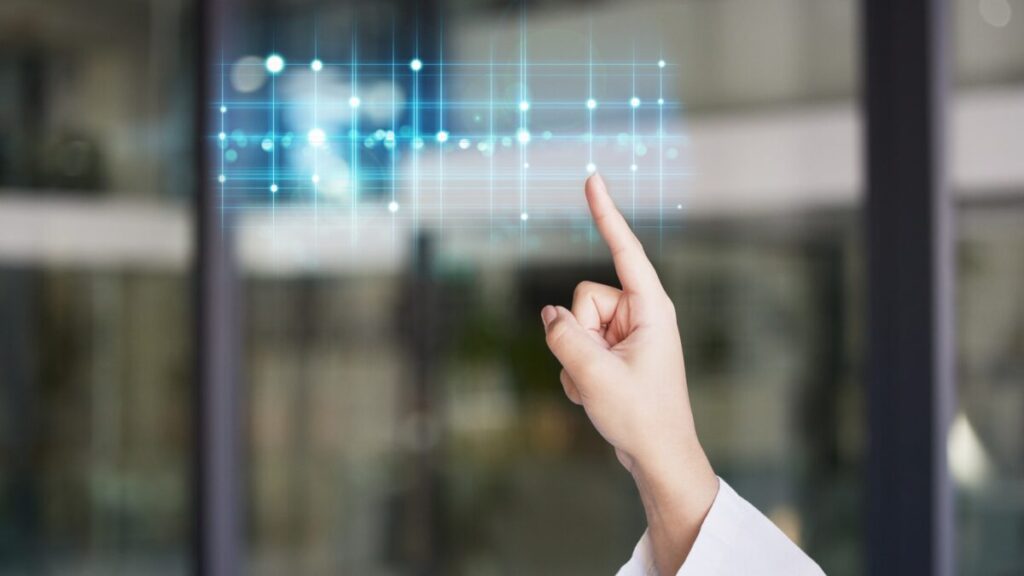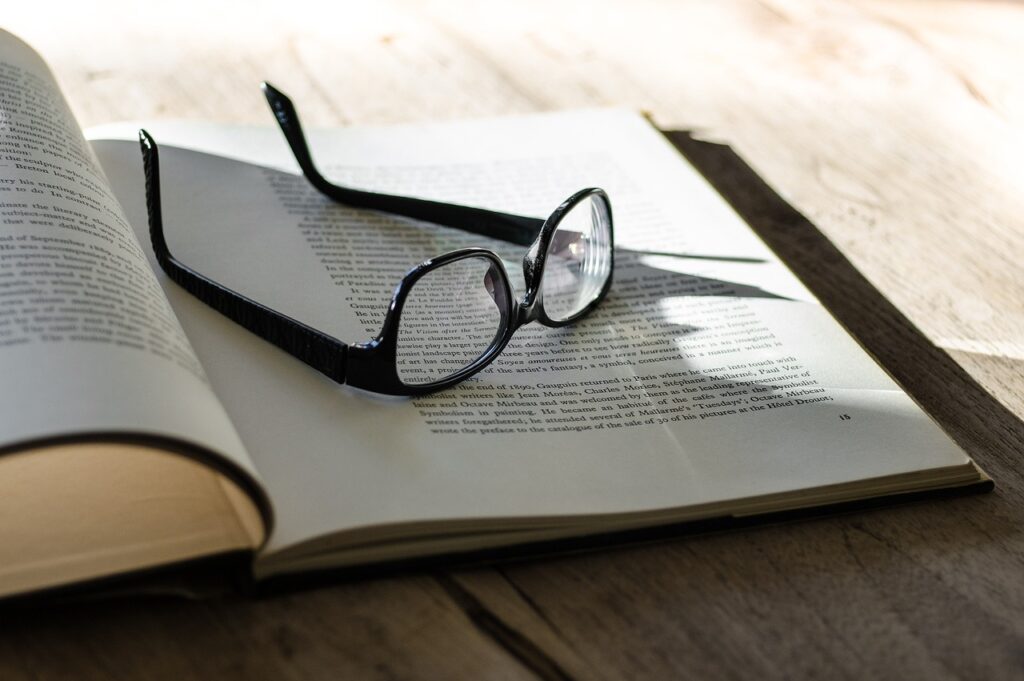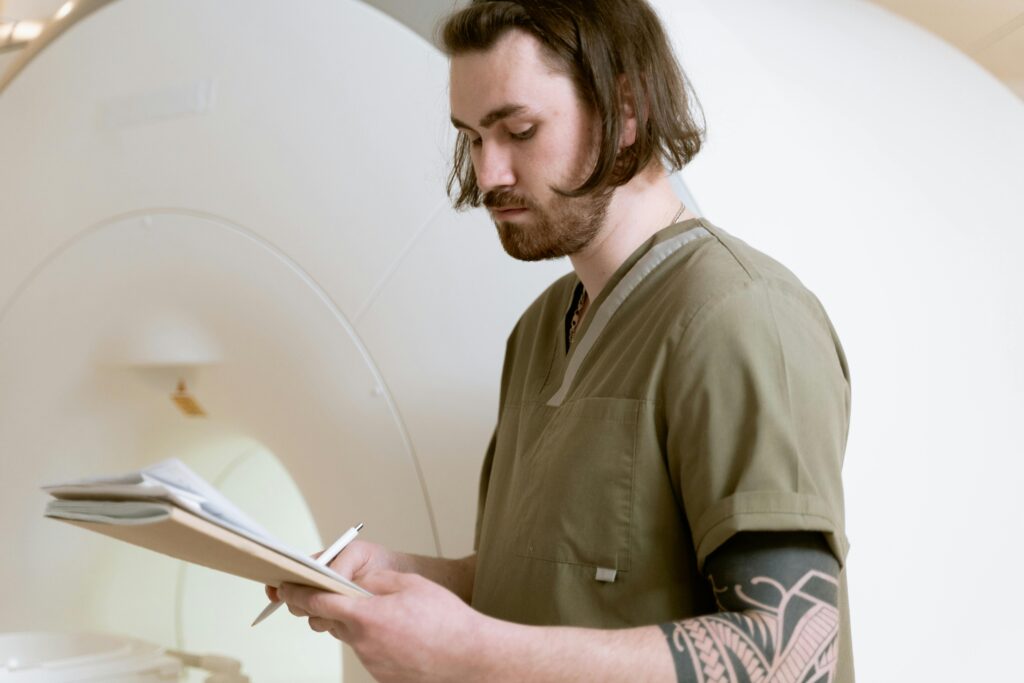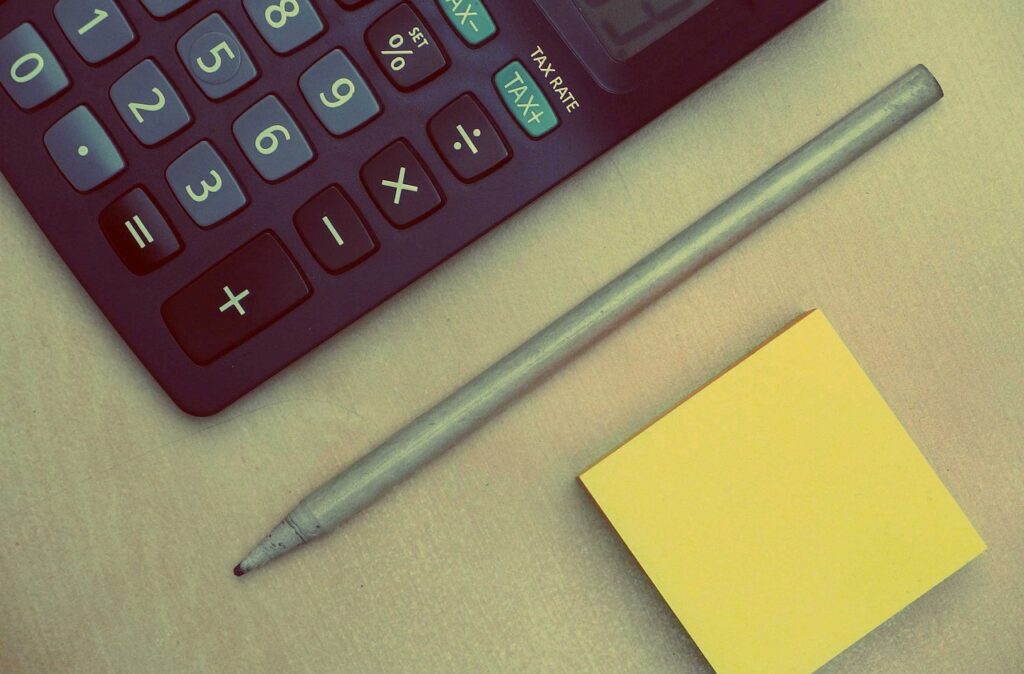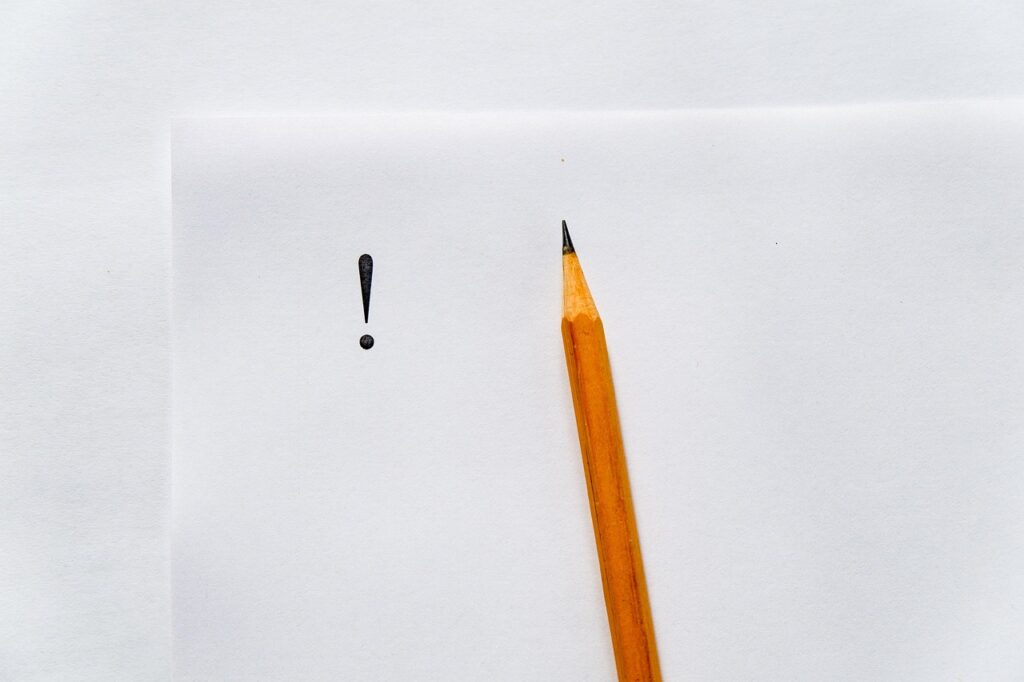医療機関を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、効率的な病院経営の実現は喫緊の課題となっています。本記事では、一般病院における実践的な経営効率化施策と収益改善のための具体的な方策をご紹介します。
現場の看護管理者の視点も交えながら、実効性の高い改善計画の立て方と実施方法について詳しく解説していきます。
この記事で分かること
- 病院経営の効率化に必要な重要指標と分析手法
- 収益改善とコスト最適化の具体的な実施手順
- 各部門における経営効率化の実践例と成功のポイント
- 規模別・診療科別の効果的な経営戦略
- 経営改善施策の効果測定方法と PDCAサイクルの回し方
この記事を読んでほしい人
- 看護部長・副看護部長
- 病棟管理者・主任看護師
- 経営企画部門で働く看護職
- 病院経営に関心のある医療従事者
- 経営改善プロジェクトに関わる医療スタッフ
病院経営効率化の現状分析と重要指標

経営効率化を進めるためには、まず現状を正確に把握し、改善すべきポイントを明確にすることが重要です。
ここでは、病院経営における重要な管理指標とその分析方法について詳しく説明していきます。
重要管理指標の理解と活用
医業利益率の分析と改善
医業利益率は病院経営の根幹を示す指標です。医業収益から医業費用を差し引いた医業利益を医業収益で除して算出します。一般的に急性期病院では5%以上、回復期病院では10%以上が望ましいとされています。改善には診療報酬の適切な算定と費用の効率化が重要となります。
人件費率のコントロール
医療機関における最大の支出項目である人件費は、通常医業収益の50-55%が適正範囲とされています。これを超える場合は、業務効率化や配置の最適化を検討する必要があります。具体的には勤務シフトの見直しや、業務の標準化による時間外労働の削減などが効果的です。
病床稼働率の最適化
安定した経営には85%以上の病床稼働率が望ましいとされています。地域連携の強化や救急受入体制の整備、効率的な退院調整により、この水準の維持を目指します。季節変動も考慮した病床運用計画の策定が重要です。
平均在院日数の適正化
診療報酬制度上、平均在院日数の短縮は重要な課題です。ただし、単純な短縮ではなく、在宅復帰率や再入院率なども考慮した適正化が必要です。クリニカルパスの活用や退院支援体制の強化が有効な手段となります。
現状分析の実施プロセス
データ収集と分析手法
経営データの収集には、医事システム、人事システム、物品管理システムなど、複数のソースからの情報統合が必要です。収集したデータは、月次推移、前年同月比較、ベンチマーク比較など、多角的な分析を行います。
問題点の抽出方法
データ分析により明らかになった課題は、以下の観点から整理します。収益面では算定漏れや加算取得状況、費用面では各種経費の推移や部門別収支などを詳細に確認します。現場スタッフへのヒアリングも重要な情報源となります。
改善目標の設定プロセス
分析結果に基づき、具体的な数値目標を設定します。目標は、達成可能性と改善インパクトを考慮して優先順位をつけます。例えば、診療報酬加算の新規取得による増収額や、材料費削減による費用減少額などを具体的に算出します。
効果測定の仕組み作り
目標達成度を定期的に評価するため、モニタリング体制を構築します。日次、週次、月次など、指標の特性に応じた評価頻度を設定し、関係者間で情報共有を行います。予実管理を徹底し、計画と実績の乖離がある場合は速やかに対策を講じることが重要です。
分析ツールの活用
経営分析システムの選定
経営データの分析には、専用のBIツールやデータ分析ソフトの活用が効果的です。導入時は、既存システムとの連携性や、操作性、コストパフォーマンスなどを総合的に評価します。
ダッシュボードの構築
日々の経営状況を可視化するため、重要指標をダッシュボード化します。リアルタイムでのモニタリングにより、早期の課題発見と対応が可能となります。部門別、診療科別など、多様な切り口でのデータ表示が有効です。
部門別の具体的施策

病院経営の効率化を実現するためには、各部門が連携しながら改善施策を実行することが重要です。
ここでは部門ごとの具体的な取り組みについて、実践的なアプローチを詳しく説明していきます。
看護部門における経営効率化
看護必要度の適切な評価と記録
看護必要度は入院基本料の算定に直結する重要な要素です。評価の標準化と記録の徹底により、適切な加算取得を実現します。具体的には、看護必要度研修の定期的な実施や、評価者間での判定基準の統一、記録の相互チェック体制の構築などが効果的です。
勤務シフトの最適化
人件費の適正化には、病棟稼働状況に応じた効率的な人員配置が不可欠です。時間帯別の業務量分析に基づき、繁忙時間帯への重点配置や、夜勤帯の適正人数配置を実現します。また、有給休暇の計画的取得や時間外労働の削減にも配慮します。
診療材料の適正使用
看護部門での材料費削減には、使用量の適正化と在庫管理の効率化が重要です。定数配置の見直しや、使用実績に基づく発注量の調整、期限切れ防止のための在庫ローテーションなどを実施します。
医事部門の効率化戦略
レセプト精度向上
請求漏れや査定減の防止は直接的な収益改善につながります。レセプトチェックシステムの活用や、査定事例の分析と対策立案、保険請求研修の実施などにより、精度向上を図ります。
未収金対策の強化
未収金の発生予防と回収率向上のため、入院時の支払い相談や、分割払いの提案、早期の督促対応などを実施します。また、クレジットカード決済や電子マネー対応により、支払い方法の多様化も進めます。
薬剤部門の改善施策
後発医薬品の使用促進
後発医薬品の採用拡大により、薬剤費の削減を図ります。採用品目の選定には、品質評価や供給安定性、価格面での優位性などを総合的に判断します。
薬剤在庫の適正化
在庫金額の圧縮と期限切れロスの防止のため、適正在庫量の設定や、使用頻度に応じた発注管理を実施します。また、高額医薬品については、メーカーとの価格交渉や分割納入の活用も検討します。
検査部門の効率化
検査機器の運用最適化
高額な検査機器の効率的な運用のため、検査項目の集約化や、機器の稼働率分析に基づく運用スケジュールの見直しを行います。また、保守契約の見直しによるランニングコストの削減も重要です。
外注検査の適正化
院内検査と外注検査の適切な振り分けにより、コスト効率の向上を図ります。検査数や緊急性、採算性などを考慮し、定期的な見直しを実施します。
事務部門の効率化推進
業務プロセスの標準化
定型業務の効率化のため、業務フローの見直しやマニュアル整備を進めます。また、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入により、作業時間の短縮を図ります。
委託業務の見直し
委託業務の範囲や仕様の見直し、複数業者からの見積り比較により、委託費用の適正化を図ります。また、業務の内製化と外部委託のバランスを定期的に検討します。
診療科別の経営効率化戦略

各診療科には特有の診療パターンや収益構造があり、それぞれに適した経営効率化戦略が求められます。
ここでは主要な診療科における具体的な効率化アプローチについて説明していきます。
内科系診療科の効率化
外来診療の最適化
内科系診療科では、慢性疾患の管理や生活習慣病の指導など、継続的な診療が中心となります。診察時間の標準化や予約枠の適正配置により、待ち時間の削減と診療効率の向上を図ります。また、看護師による療養指導の充実により、医師の負担軽減と収益向上を両立させます。
検査計画の効率化
定期的な検査が多い内科診療において、検査の適正化は重要な課題です。患者ごとの検査計画を最適化し、重複検査の防止や検査の集約化を進めます。また、検査の保険算定要件を確認し、適切な診療報酬請求を行います。
外科系診療科の戦略
手術室運用の効率化
手術室は高額な設備投資と運営コストが必要となる部門です。手術枠の柔軟な運用や、手術準備の標準化により、稼働率の向上を図ります。また、手術材料の適正使用と在庫管理の効率化も重要です。
周術期管理の最適化
クリニカルパスの活用により、入院期間の適正化と医療の質の向上を両立させます。術前検査の外来移行や、早期離床プログラムの導入により、在院日数の短縮を図ります。また、術後合併症の予防に注力し、再入院率の低減を目指します。
救急部門の効率化
救急受入体制の整備
救急医療は病院経営において重要な役割を果たします。救急車受入れの適正化や、初期対応の迅速化により、応需率の向上を図ります。また、救急外来での適切な重症度判定により、入院判断の精度向上を目指します。
時間外診療の効率化
夜間休日の医療スタッフ配置を最適化し、人件費の効率化を図ります。また、時間外診療の適切な診療報酬算定により、収益性の向上を目指します。地域の医療機関との連携強化も重要な要素となります。
専門外来の展開
特殊外来の運営効率化
専門性の高い診療による診療単価の向上を図ります。糖尿病外来やフットケア外来など、チーム医療による専門外来を展開し、加算算定の機会を増やします。また、患者教育プログラムの充実により、継続的な診療につなげます。
紹介患者の管理強化
地域連携の強化により、専門性の高い症例の受入れを促進します。紹介患者の診療情報管理を徹底し、逆紹介も適切に行うことで、地域医療における高度医療機関としての役割を果たします。
規模別の経営戦略

病院の規模によって直面する課題や活用できる経営資源は大きく異なります。
ここでは病院規模別の効果的な経営戦略について、それぞれの特性を踏まえながら具体的な方策を説明していきます。
大規模病院(500床以上)の経営戦略
高度医療機能の強化
大規模病院では高度な医療機器や専門性の高い医療スタッフを活かした診療体制の構築が重要です。がん診療や救急医療など、地域における中核的機能を担うことで、診療単価の向上を図ります。高額な医療機器の導入については、投資回収計画を綿密に立案し、稼働率の目標設定と実績管理を行います。
組織マネジメントの効率化
複雑な組織構造を持つ大規模病院では、部門間の連携強化と意思決定の迅速化が課題となります。経営企画部門を中心とした管理体制の整備や、部門横断的なプロジェクトチームの活用により、組織全体の効率化を進めます。
また、電子カルテシステムやオーダリングシステムの高度な活用により、業務の標準化と効率化を実現します。
中規模病院(200-499床)の経営戦略
地域ニーズへの対応
中規模病院では、地域の医療ニーズに応じた機能分化が重要です。回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟など、地域に必要な機能を戦略的に展開します。また、地域の診療所との連携強化により、紹介患者の増加を図ります。病床機能の最適化により、安定した病床稼働率の維持を目指します。
経営資源の効率的活用
限られた経営資源を効果的に活用するため、業務の優先順位付けと効率化が重要です。医療機器の共同利用や、非常勤医師の効率的な配置など、柔軟な運営体制を構築します。また、多職種連携によるチーム医療の推進により、医療の質向上と効率化の両立を図ります。
小規模病院(200床未満)の経営戦略
特色ある医療の展開
小規模病院では、特定の診療分野に特化した診療体制の構築が有効です。整形外科専門病院や眼科専門病院など、専門性を活かした差別化戦略を展開します。また、在宅医療支援病院としての機能強化など、地域のニーズに応じた特色づくりを進めます。
コスト管理の徹底
経営基盤が比較的脆弱な小規模病院では、きめ細かなコスト管理が不可欠です。医薬品や診療材料の共同購入、業務の内製化推進など、固定費の削減に注力します。また、人員配置の効率化や、パート職員の活用により、人件費の適正化を図ります。
規模転換時の戦略
病床規模の適正化
地域の医療ニーズや経営状況に応じて、病床規模の見直しを検討します。病床削減による経営効率化や、診療科の再編による機能強化など、状況に応じた転換戦略を立案します。規模変更に伴う施設基準の変更や人員配置の見直しについても、計画的に進めていきます。
転換期の運営管理
規模変更時には、収益構造の変化に応じた運営体制の構築が必要です。段階的な移行計画の立案や、職員教育の充実により、円滑な転換を実現します。また、地域の医療機関や行政機関との連携強化により、新たな役割に応じた患者確保を進めます。
経営効率化のための具体的なツール紹介

病院経営の効率化を実現するためには、適切なツールの活用が不可欠です。
ここでは実務で活用できる具体的なツールとその効果的な導入・運用方法について説明していきます。
経営分析ツール
BIツールの活用方法
経営データの可視化と分析には、Tableau、Power BIなどのBIツールが効果的です。これらのツールでは、部門別収支や診療科別実績などを、インタラクティブなダッシュボードとして表示できます。
特に経営会議での意思決定支援や、現場へのフィードバックに有用性が高く、データドリルダウン機能により、課題の詳細分析も容易に行えます。
経営シミュレーションツール
診療報酬改定の影響や新規事業の収支予測には、専用のシミュレーションツールが有効です。収入予測、人件費計算、設備投資の採算性評価など、多角的な分析が可能となります。感度分析機能により、様々なシナリオでの収支予測を行うことができます。
スケジューリングソフト
勤務管理システム
看護師など医療スタッフの勤務シフト作成には、専用の勤務管理システムを活用します。労働基準法の遵守チェックや、スキルミックスを考慮した人員配置、有給休暇管理など、複雑な要件を効率的に管理できます。また、勤怠データの自動集計により、給与計算業務の効率化も実現します。
手術室管理システム
手術室の効率的な運用には、手術室管理システムが不可欠です。手術予定の一元管理や、手術材料の準備リスト作成、手術時間の実績管理など、包括的な運用管理が可能となります。また、麻酔科医や看護師の配置調整も効率的に行えます。
在庫管理システム
医薬品管理システム
医薬品の在庫管理には、発注から消費までを一元管理できるシステムを導入します。使用期限管理や在庫金額の適正化、発注業務の自動化など、効率的な在庫管理を実現します。また、医薬品の使用実績分析により、採用品目の見直しも容易になります。
診療材料管理システム
診療材料の在庫管理では、バーコード管理システムの活用が効果的です。定数配置の最適化や、使用実績に基づく発注管理、部署別の消費分析など、きめ細かな管理が可能となります。また、SPDシステムとの連携により、さらなる効率化を図ることができます。
原価計算システム
部門別原価計算
診療科別や部門別の収支分析には、原価計算システムが重要です。直接費と間接費の適切な配賦により、より正確な採算性分析が可能となります。また、DPC分析との連携により、疾患別の収支分析も実現できます。
診療行為別原価計算
個々の診療行為や手術の原価を算出することで、より詳細な採算性分析が可能となります。これにより、診療報酬改定への対応や、新規医療技術の導入判断をより適切に行うことができます。
ケーススタディ

実際の病院における経営効率化の取り組みを通じて、具体的な改善手法とその効果について見ていきます。
ここでは、異なる規模や特性を持つ病院の事例を詳しく分析していきます。
AA総合病院の成功事例(500床)
改善前の課題
AA総合病院では医業利益率が2%を下回り、特に人件費率の高さが経営を圧迫していました。また、高額医療機器の稼働率が低く、投資効率の改善が急務となっていました。病床稼働率も80%を下回る状況が続いていました。
実施した改善策
経営改善プロジェクトチームを立ち上げ、全部門での業務効率化を推進しました。具体的には看護師の勤務シフト最適化による時間外労働の削減、手術室の効率的運用による手術件数の増加、地域連携強化による紹介患者の増加などを実施しました。また、高額医療機器の共同利用促進により、稼働率の向上を図りました。
成果と効果測定
取り組みの結果、2年間で医業利益率が4.5%まで改善しました。人件費率は58%から53%に低下し、病床稼働率も88%まで向上しています。高額医療機器の稼働率は平均30%向上し、投資効率も大幅に改善しました。
BB地域医療センターの事例(300床)
当初の経営状況
地域の中核病院として機能していたBB医療センターでは、救急受入れの増加に伴う医師の疲弊と、病棟運営の非効率さが課題となっていました。また、診療材料費の上昇も収益を圧迫していました。
改革への取り組み
救急体制の再構築と病棟機能の見直しを実施しました。救急専門医の増員と当直体制の整備により、医師の負担軽減を図りました。また、地域包括ケア病棟の導入により、急性期病床の回転率向上を実現しました。診療材料の標準化とSPDシステムの導入も並行して進めました。
改善結果の検証
これらの取り組みにより、救急受入れ件数を維持しながら医師の時間外労働を30%削減することに成功しました。また、平均在院日数は2日短縮され、診療材料費は15%削減されています。医業利益率は3.2%から6.8%まで改善しました。
CC専門病院の失敗事例(150床)
問題の背景
整形外科専門病院として開設されたCC病院では、急激な施設拡大により経営が悪化していました。新規設備投資に伴う借入金の返済負担が重く、人材確保も困難な状況でした。
誤った対応策
コスト削減を優先するあまり、必要な人材投資を抑制したことで、医療の質低下を招きました。また、病床規模の適正化を検討せず、無理な病床維持を続けたことで、さらなる経営悪化を招いています。
教訓と対策
この事例からは、急激な投資判断の危険性と、収支バランスを考慮した段階的な成長の重要性を学ぶことができます。また、医療の質を維持しながら効率化を進めることの必要性も示唆されています。現在は、病床規模の適正化と、重点診療分野への資源集中により、徐々に経営改善が進んでいます。
おしえてカンゴさん!よくある質問
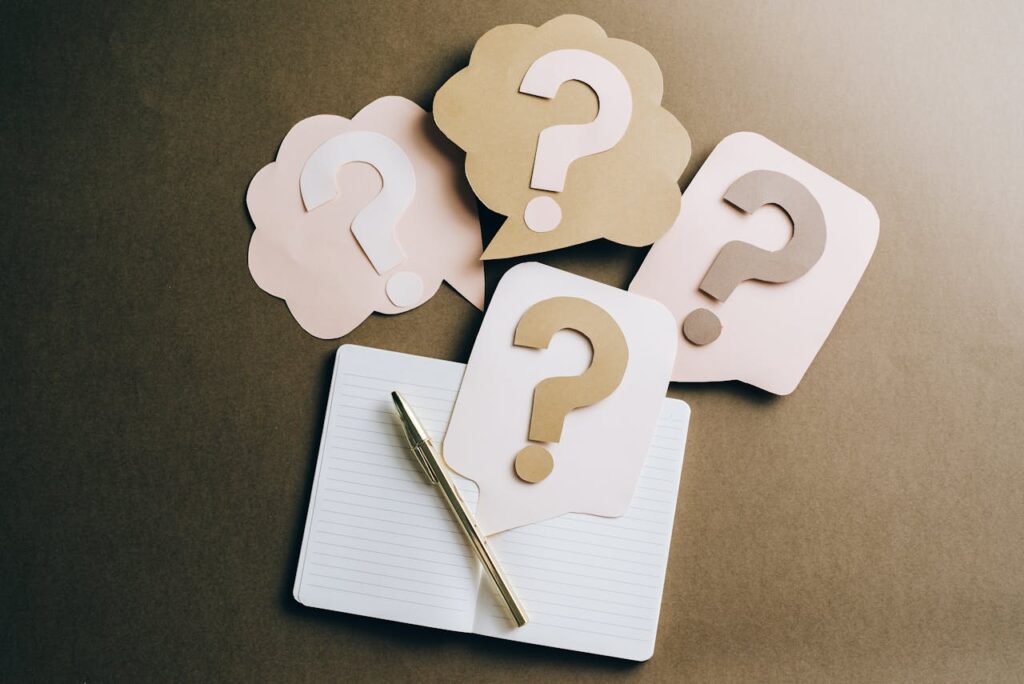
病院の経営効率化に関して、現場のスタッフから多く寄せられる質問について、経験豊富な看護師長「カンゴさん」が分かりやすく回答していきます。
実践的な内容から制度面まで、幅広い疑問に答えていきます。
経営指標に関する質問
Q:医業利益率はどのくらいが適正なのでしょうか?
医業利益率は病院の機能や規模によって異なりますが、一般的に急性期病院では5%以上、回復期病院では10%以上を目標とすることが望ましいです。ただし、地域の特性や病院の役割によって、適正な値は変動する可能性があります。
Q:人件費率が高いのですが、どのように改善すればよいでしょうか?
人件費率の改善には、まず業務の棚卸しを行い、無駄な業務を削減することが重要です。具体的には、勤務シフトの最適化、業務の標準化、ICTツールの活用などが効果的です。ただし、単純な人員削減は医療の質低下につながる可能性があるため、慎重な検討が必要です。
業務効率化に関する質問
Q:看護記録の効率化と質の向上を両立するにはどうすればよいですか?
テンプレートの活用や、記録内容の標準化が有効です。特に診療報酬上重要な項目については、チェックリストを活用するなど、漏れのない記録方法を工夫します。また、定期的な記録監査を行い、質の維持向上を図ることも重要です。
Q:多職種連携を進める上で、気をつけるべきポイントは何ですか?
情報共有の仕組みづくりが最も重要です。定期的なカンファレンスの開催や、電子カルテを活用した情報共有の効率化などが効果的です。また、各職種の専門性を尊重しながら、共通の目標設定を行うことも大切です。
経営改善活動に関する質問
Q:現場スタッフの経営参画意識を高めるには、どうすればよいでしょうか?
経営データの可視化と共有が効果的です。部署ごとの収支状況や、改善活動の成果を定期的にフィードバックすることで、スタッフの意識向上につながります。また、改善提案制度の導入など、現場の声を経営に反映する仕組みづくりも重要です。
Q:病棟再編を行う際の注意点を教えてください。
患者への影響を最小限に抑えることが最優先です。十分な準備期間を設け、段階的な移行計画を立てることが重要です。また、スタッフへの説明と教育も丁寧に行い、新体制への円滑な移行を図ります。
診療報酬に関する質問
Q:施設基準の維持管理で特に注意すべき点は何ですか?
定期的なセルフチェックと、必要書類の適切な管理が重要です。特に人員配置に関する基準は、離職や異動の影響を受けやすいため、余裕を持った体制整備が必要です。また、新たな加算取得の機会も常に検討します。
Q:看護必要度の評価精度を上げるにはどうすればよいですか?
定期的な評価者研修の実施と、評価の標準化が重要です。特に判断に迷いやすい項目については、具体的な事例を用いた研修を行います。また、記録の相互チェック体制を構築し、評価の質を維持します。
コスト管理に関する質問
Q:材料費の削減と医療の質の両立は可能ですか?
可能です。同等の品質を持つ代替品の採用や、適正在庫の管理により、質を落とさずにコスト削減を実現できます。また、使用実績の分析により、無駄な使用を防ぐことも効果的です。
まとめ
病院の経営効率化には、現状分析に基づく具体的な改善計画の立案と、全部門が連携した実行が不可欠です。特に看護部門では、看護必要度の適切な評価や業務効率化、多職種連携の推進など、経営改善に大きく貢献できる機会が数多くあります。
本記事で紹介した方策を参考に、それぞれの医療機関に適した改善活動を展開していくことで、持続可能な経営基盤の構築が可能となります。
より詳しい経営効率化のノウハウや、看護管理者向けの実践的な情報は【はたらく看護師さん】で随時更新しています。当サイトでは、経営やマネジメントに関する最新情報、実践事例、専門家による解説など、看護管理者の皆様に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。
▼詳しくは【はたらく看護師さん】をチェック