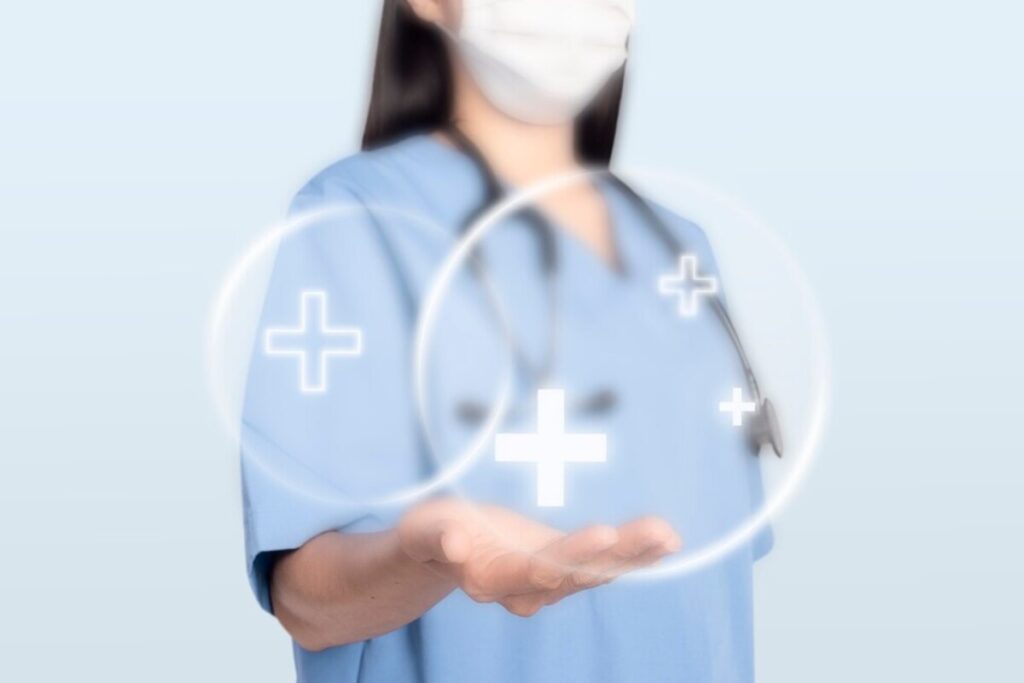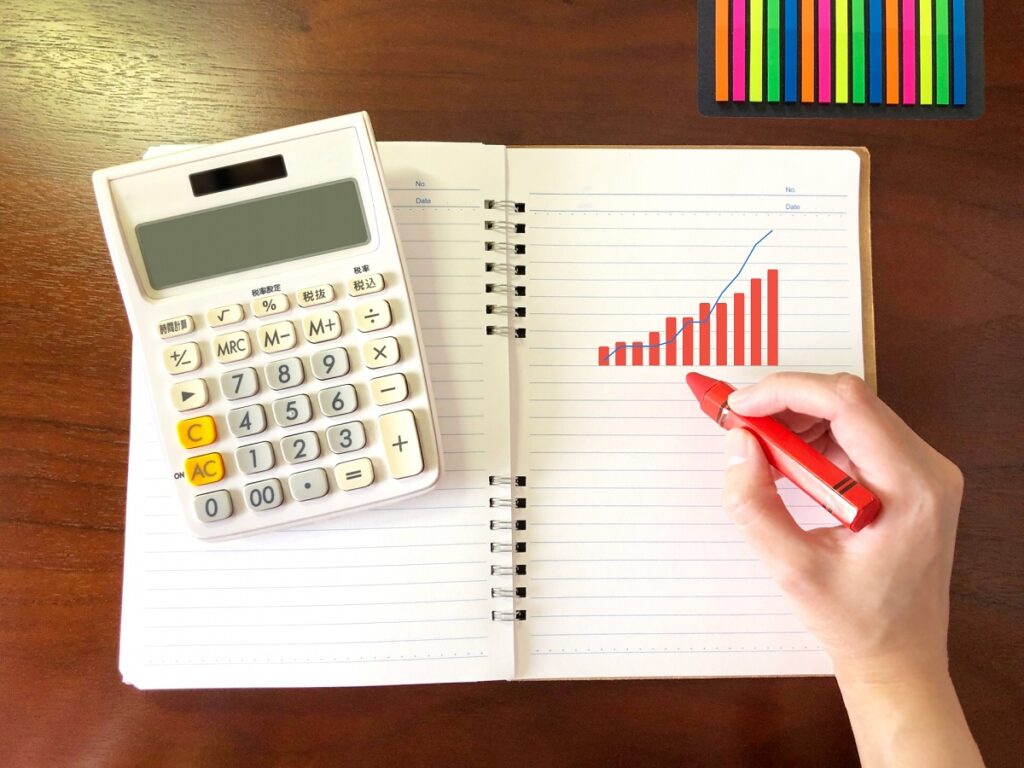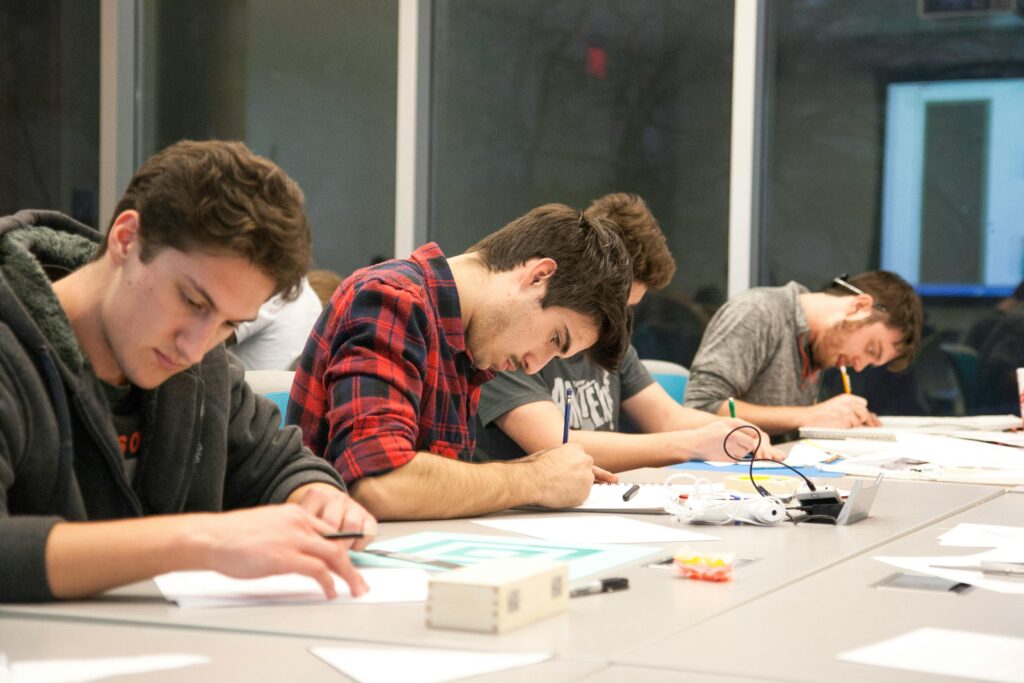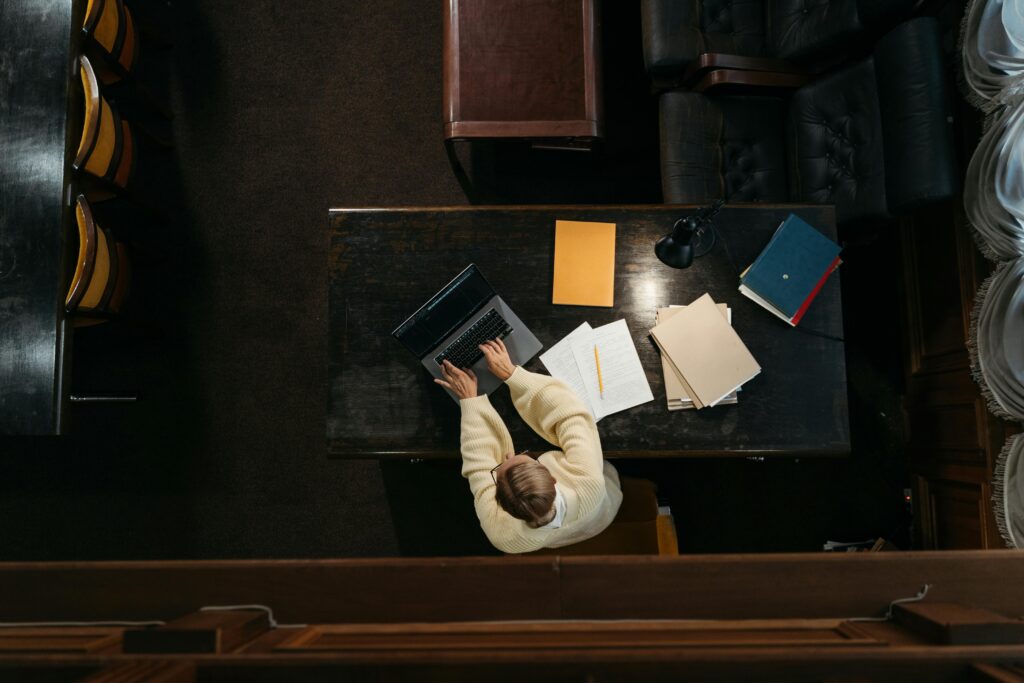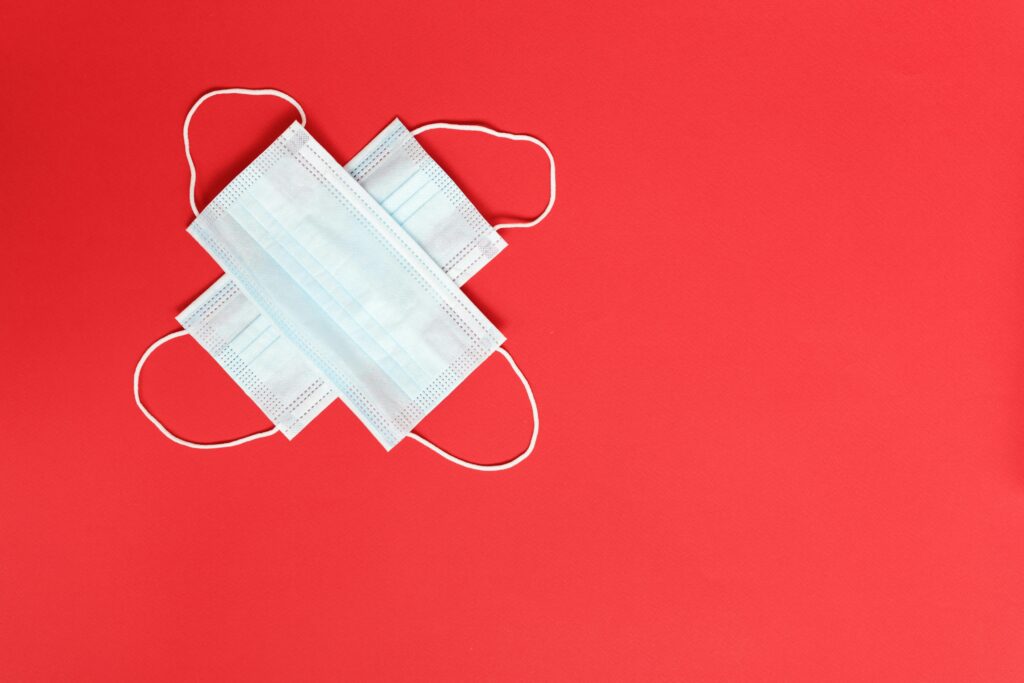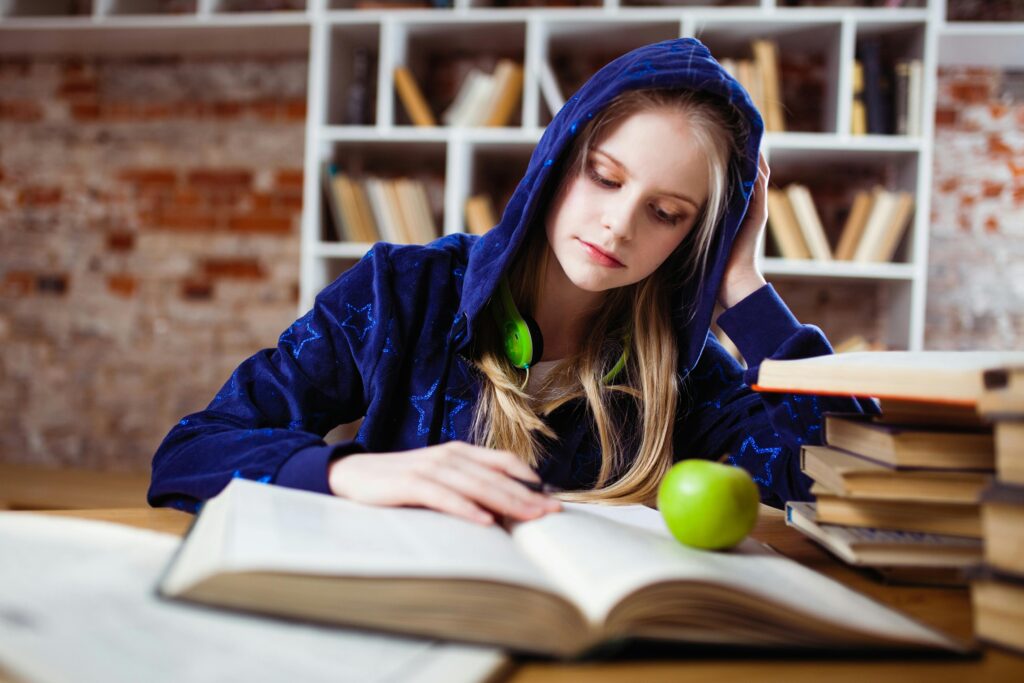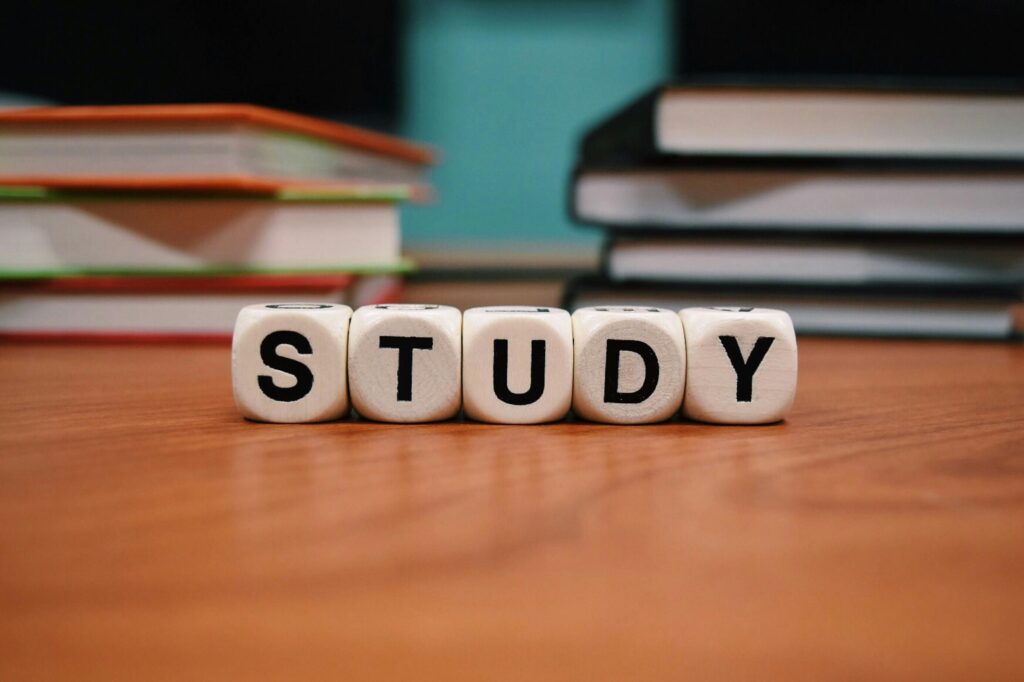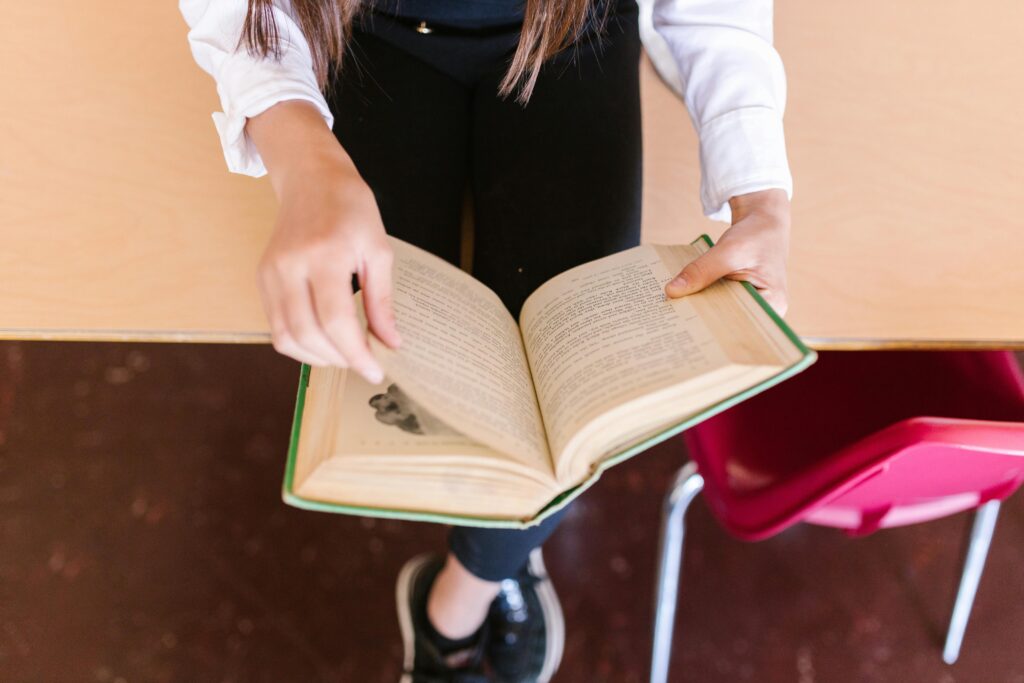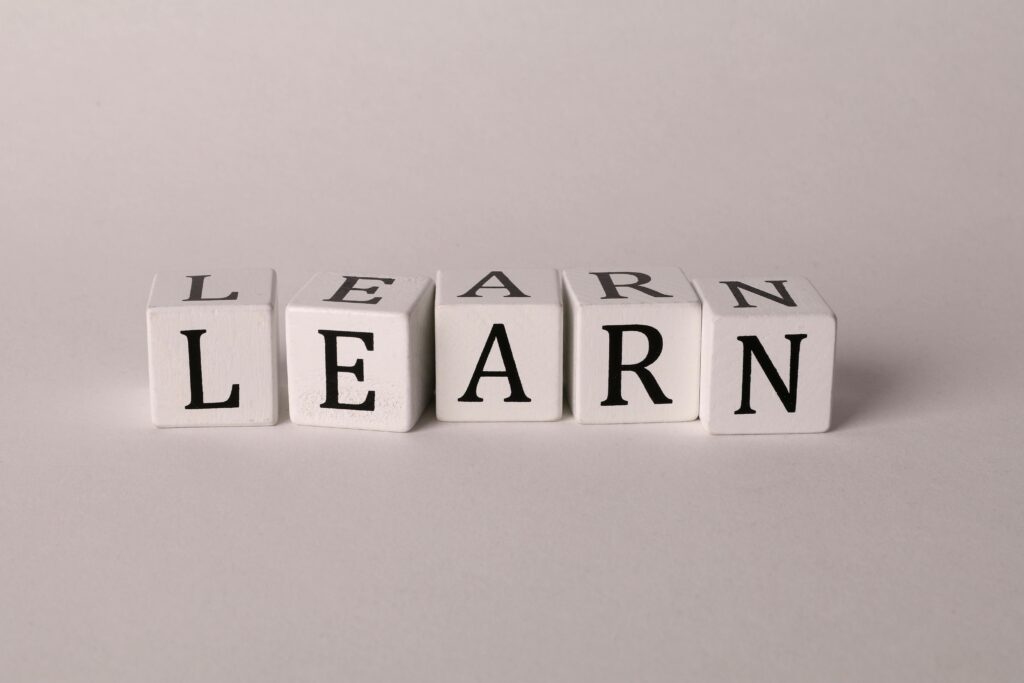在宅医療のニーズが高まる中、訪問診療の現場で活躍する看護師の需要が急増しています。
本記事では、訪問診療における看護師採用の最新動向から、希望する条件に合った求人の見つけ方、実践的な転職活動のポイントまで、詳しく解説します。
豊富な実例と共に、あなたのキャリアプランに最適な職場選びをサポートします。
この記事で分かること
- 訪問診療看護師の採用市場における最新動向と今後の展望について
- 給与水準や勤務条件の詳細な比較と評価方法について
- 希望する条件に合った求人を効率的に探すための具体的な方法について
- 実際の就職成功事例から学ぶ選考突破のポイントについて
- 面接対策や条件交渉での具体的なアプローチ方法について
この記事を読んでほしい人
- 訪問診療での勤務に関心を持っている看護師の方
- 現在の職場からの転職を検討している看護師の方
- より良いワークライフバランスの実現を目指している看護師の方
- 訪問診療の分野でキャリアアップを考えている看護師の方
- ブランクがあり、訪問診療での復職を考えている看護師の方
訪問診療看護師の採用市場動向

訪問診療における看護師の採用市場は、社会的なニーズの高まりとともに大きく変化しています。ここでは最新の市場動向と、それに伴う求人傾向の変化について詳しく解説します。
需要拡大の背景
高齢化社会の進展に伴い、在宅医療のニーズは年々増加の一途をたどっています。特に訪問診療において、看護師の果たす役割はますます重要性を増しています。
社会的背景
在宅医療を必要とする高齢者の増加に加え、病院の機能分化が進む中、訪問診療の重要性は高まる一方です。2024年の統計によると、65歳以上の高齢者のうち、約15%が何らかの在宅医療サービスを利用しており、この数字は年々上昇傾向にあります。
制度的背景
医療制度改革により、在宅医療の推進が国の施策として位置づけられています。診療報酬改定でも在宅医療の充実が図られ、訪問診療を行う医療機関への支援が強化されています。
人材需要の現状
2024年現在、訪問診療を行う医療機関の約75%が看護師の採用に意欲的です。特に、在宅療養支援診療所(在支診)においては、常勤看護師の募集が前年比で20%増加しています。
医療機関の規模や地域による差はありますが、総じて採用意欲は高く、待遇面での改善も進んでいます。
採用条件の変化
従来は訪問診療での経験を重視する傾向がありましたが、近年は未経験者の採用にも積極的な医療機関が増えています。研修制度の充実や段階的な業務移行など、経験の少ない看護師のサポート体制も整備されつつあります。
地域別の需要動向
地域によって訪問診療の需要には大きな差があり、それに伴い看護師の採用状況も異なっています。各地域の特性を理解することは、効果的な就職活動を行う上で重要なポイントとなります。
都市部の特徴
東京、大阪、名古屋などの大都市圏では、訪問診療を提供する医療機関の数が多く、それに比例して看護師の求人も豊富です。一方で、人材の競争も激しく、より専門的なスキルや経験が求められる傾向にあります。
都市部の給与水準は地方と比較して10%から15%程度高くなっていますが、生活費などのコストも考慮する必要があります。
地方都市の状況
地方都市では、高齢化率の上昇に伴い訪問診療のニーズが急速に高まっています。看護師の採用難度は都市部より低い傾向にありますが、一方で求人数は限られています。
ただし、地域に密着した医療機関が多く、じっくりとキャリアを築ける環境が整っているケースも少なくありません。
過疎地域の課題と機会
過疎地域では、訪問診療の重要性が特に高く、看護師の需要も切実です。そのため、給与面での優遇や住宅手当の支給など、独自の待遇改善策を講じている医療機関も増えています。
また、地域包括ケアシステムの中核を担う存在として、やりがいを感じられる環境も特徴です。
診療科別の求人傾向
訪問診療における看護師の役割は、診療科によって大きく異なります。それぞれの特性を理解することで、自身のキャリアプランに合った職場選びが可能となります。
内科系訪問診療の特徴
内科系の訪問診療では、慢性疾患の管理や生活習慣病の予防指導が中心となります。看護師には、患者の日常生活全般をサポートする幅広い知識と経験が求められます。特に高齢者の健康管理や服薬指導などのスキルが重視されます。
在宅緩和ケアの需要
がん患者の在宅療養ニーズの高まりに伴い、緩和ケアの経験を持つ看護師の需要が増加しています。痛みのコントロールや精神的ケア、家族支援など、専門的なスキルが必要とされる一方で、やりがいを感じられる分野として注目されています。
小児在宅医療の展開
医療的ケア児の在宅療養支援において、小児看護の経験を持つ看護師の需要が高まっています。専門性の高さから、給与水準も比較的高く設定されているケースが多く見られます。
将来予測と必要スキル
訪問診療看護師に求められる役割は、医療技術の進歩や社会のニーズの変化とともに進化を続けています。将来的な展望を見据えたスキル開発が、キャリアの長期的な成功につながります。
テクノロジーの活用
オンライン診療の普及に伴い、ICTスキルの重要性が増しています。電子カルテの操作やタブレット端末を使用した遠隔モニタリングなど、デジタル技術への適応力が求められています。
コミュニケーション能力の重要性
多職種連携がますます重要となる中、チーム医療のコーディネーターとしての役割も期待されています。医師や他の医療専門職、介護スタッフとの円滑な情報共有や連携が必須となっています。
専門性の深化
特定の疾患や症状に関する専門的な知識・技術の習得が、キャリアアップの重要な要素となっています。認定看護師や専門看護師の資格取得を支援する医療機関も増加傾向にあります。
訪問診療看護師の具体的な求人条件

訪問診療における看護師の求人条件は、医療機関の規模や地域性によって大きく異なります。ここでは、具体的な給与水準から勤務形態、福利厚生まで、実際の求人情報に基づいた詳細な条件を解説します。
給与条件の詳細分析
訪問診療看護師の給与体系は、経験年数や保有資格、勤務形態などによって設定されています。医療機関の特性によっても差異がありますが、一般的な病院勤務と比較して好条件な場合が多いのが特徴です。
基本給与の構成
基本給与は経験年数に応じて設定され、一般的に3年以上の経験者では月給28万円から35万円の範囲となっています。これに各種手当が加算され、年収ベースでは400万円から550万円程度となることが多いです。
未経験者の場合でも、充実した研修制度と併せて、月給25万円以上からスタートできる医療機関も増えています。
各種手当の内訳
訪問診療特有の手当として、訪問手当が設定されているケースが一般的です。1件あたり1,000円から2,000円程度が基準となっています。また、オンコール対応手当は、1回あたり5,000円から10,000円が相場となっています。
賞与・昇給制度
賞与は年2回から3回の支給が一般的で、基本給の3.5ヶ月から4.5ヶ月分が平均的な水準です。昇給は年1回実施される医療機関が多く、経験や実績に応じて基本給の3%から5%程度の上昇が期待できます。
勤務形態の種類と特徴
訪問診療看護師の勤務形態は、ライフスタイルに合わせて選択できる柔軟性が特徴です。それぞれの形態に応じた特徴と、実際の働き方について詳しく見ていきましょう。
常勤正社員の勤務形態
週5日勤務が基本となり、1日の訪問件数は平均4件から6件程度です。勤務時間は一般的に9時から17時または8時30分から16時30分などが多く、残業は月平均10時間程度と比較的少なめです。
時短常勤の特徴
育児や介護との両立を考える看護師向けに、週3日から4日の時短常勤制度を設けている医療機関が増えています。1日6時間勤務などの時間短縮も可能な場合が多く、徐々に勤務時間を増やしていける柔軟な体制を整えています。
非常勤パートの働き方
週1日から3日程度の勤務が一般的で、時給は1,800円から2,500円の範囲で設定されています。訪問件数は1日2件から4件程度と、常勤より少なめに設定されることが多いです。
福利厚生の比較
福利厚生制度は医療機関によって大きく異なり、選択の重要な判断材料となります。実際の事例を基に、主な福利厚生制度について見ていきましょう。
保険・年金制度
社会保険、厚生年金は常勤職員には完備されています。また、医療保険組合に加入している医療機関では、手厚い医療費補助を受けられるケースも多くあります。
休暇制度の詳細
年次有給休暇は初年度から10日以上が付与され、勤続年数に応じて最大20日まで増加します。その他、夏季休暇、年末年始休暇、バースデー休暇なども設定されている医療機関が増えています。
研修・資格取得支援
専門性の向上を支援する制度として、研修費用の補助や資格取得支援制度を設けている医療機関が多く見られます。認定看護師資格の取得に向けた学習支援や、各種セミナー参加費用の補助なども充実しています。
夜間・オンコール体制
訪問診療特有の勤務体制として、夜間対応やオンコール体制があります。これらの体制は医療機関によって異なりますが、待遇面での配慮も重要なポイントとなります。
オンコール体制の実際
オンコール当番は通常チーム制で実施され、1人あたり月4回から6回程度が一般的です。緊急時の対応手順や医師との連携体制が明確に定められており、安心して対応できる体制が整えられています。
夜間対応の仕組み
夜間の緊急往診に同行するケースもありますが、その場合は別途手当が支給されます。往診同行手当は1回あたり5,000円から10,000円程度が相場となっています。
負担軽減の取り組み
オンコールや夜間対応の負担を軽減するため、当番制の工夫や代休制度の充実、手当の増額など、様々な取り組みが行われています。また、経験の浅い看護師には段階的に責任を増やしていく配慮も見られます。
求人選びのポイント

訪問診療の現場で活躍するためには、自身のキャリアプランや生活スタイルに合った職場を選ぶことが重要です。ここでは、求人選びの具体的なポイントと、選考から条件交渉までの実践的なアドバイスをご紹介します。
重視すべき条件の詳細
訪問診療の求人を検討する際には、通常の病院勤務とは異なる視点での評価が必要となります。医療機関の特性や勤務条件に加え、訪問診療特有の環境要因についても慎重に検討しましょう。
訪問エリアの範囲
訪問エリアの広さや地理的特性は、日々の業務効率に大きく影響します。都市部では移動距離は短いものの、交通渋滞を考慮する必要があります。一方、郊外では訪問件数は少なめですが、移動距離が長くなる傾向にあります。
自動車やバイクでの移動が基本となりますので、運転に対する負担も考慮に入れましょう。
患者層と診療内容
対象となる患者層や主な診療内容は、医療機関によって特色があります。高齢者中心の一般的な訪問診療から、がん患者の緩和ケア、小児在宅医療まで、様々な専門性があります。自身の経験や興味のある分野との適合性を確認することが重要です。
教育体制の充実度
特に訪問診療未経験の場合、教育研修体制の充実度は重要な判断材料となります。新人研修プログラムの内容、プリセプター制度の有無、定期的な勉強会の開催など、具体的な教育支援体制を確認しましょう。
事業所選びのチェックポイント
医療機関の選択にあたっては、表面的な条件だけでなく、実際の運営体制や職場環境についても詳しく確認することが重要です。
医療機関の安定性
開設年数や患者数の推移、スタッフの定着率などは、医療機関の安定性を判断する重要な指標となります。また、訪問診療に対する医療機関の方針や将来展望についても確認することで、長期的なキャリア形成の可能性を判断できます。
チーム体制と連携
医師、看護師、その他のメディカルスタッフとの連携体制は、日々の業務を円滑に進める上で重要です。カンファレンスの頻度や内容、情報共有の方法、緊急時の対応体制など、具体的な連携の仕組みを確認しましょう。
働きやすさの実態
実際に働いているスタッフの様子や職場の雰囲気は、見学や面接時に確認することが大切です。休暇の取得状況、残業の実態、育児や介護との両立支援制度など、実際の運用面についても詳しく質問することをお勧めします。
面接・条件交渉のポイント
採用選考では、訪問診療特有の課題や期待される役割について、具体的な質疑応答が行われます。事前の準備と適切な対応が、希望条件の獲得につながります。
面接での重要ポイント
面接では、訪問診療に対する理解と意欲を具体的に伝えることが重要です。これまでの看護経験をどのように訪問診療で活かせるか、また、未経験分野についてはどのように学んでいく意向があるかを、具体的に説明できるよう準備しましょう。
条件交渉の進め方
給与や勤務条件の交渉は、市場相場を踏まえた上で、自身の経験やスキルを適切にアピールすることが重要です。特に、訪問診療特有の手当や福利厚生については、詳細な確認と具体的な交渉が必要となります。
入職後のキャリアパス
将来的なキャリアアップの可能性について、具体的な確認を行うことも重要です。専門資格の取得支援制度や、管理職への登用機会など、長期的なキャリア展望について、医療機関の方針を確認しましょう。
採用決定から入職までの準備
採用が決定してから実際の入職までの期間は、円滑な業務開始のための重要な準備期間となります。計画的な準備により、スムーズな職場適応が期待できます。
必要な手続きと準備
資格証明書の準備や各種保険の手続き、必要な予防接種の確認など、入職に必要な諸手続きを計画的に進めることが重要です。また、訪問診療用の携行品や備品についても、医療機関の指示に従って準備を進めましょう。
事前学習の進め方
入職までの期間を活用して、訪問診療に関する基礎知識の学習や、必要なスキルの復習を行うことをお勧めします。特に、訪問診療未経験の場合は、在宅医療に関する書籍や資料で、基本的な知識を補強しておくことが有効です。
ケーススタディ:転職成功例

実際の転職成功事例から、訪問診療看護師としてのキャリアをスタートさせた方々の経験を詳しくご紹介します。それぞれの事例から、効果的な転職活動のポイントや、新しい環境での適応方法について学んでいきましょう。
Case A:病院から訪問診療への転職
総合病院の外科病棟で7年間勤務した後、訪問診療の世界へ転身したAさんの事例をご紹介します。ワークライフバランスの改善を目指して転職を決意し、見事に希望の職場で活躍されています。
転職の背景と動機
外科病棟での経験を活かしながら、より患者さんに寄り添った看護を実践したいという思いから、訪問診療への転職を決意されました。夜勤による生活リズムの乱れや、慢性的な人手不足による過重労働が転職の直接のきっかけとなりました。
転職活動のプロセス
転職活動は在職中に開始し、約3ヶ月かけて希望の職場を見つけることができました。訪問診療の経験がなかったため、見学会や職場体験に積極的に参加し、実際の業務内容や職場の雰囲気を確認しました。
成功のポイント
外科での急性期看護の経験が、訪問診療でも高く評価されました。特に、医療処置の技術や緊急時の対応能力が評価のポイントとなりました。また、研修制度が充実している医療機関を選んだことで、訪問診療特有のスキルを段階的に習得することができました。
Case B:クリニックから訪問診療への転職
内科クリニックで5年間勤務したBさんが、より専門性の高い在宅医療の分野にチャレンジした事例です。緩和ケアに特化した訪問診療所への転職を実現されました。
専門分野への挑戦
内科クリニックでの勤務中に、在宅での緩和ケアに関心を持ち、専門的なケアを提供できる環境を求めて転職を決意されました。がん患者さんとその家族へのケアに特化した訪問診療所で、現在はスペシャリストとして活躍されています。
キャリアアップの実現
転職後は緩和ケア研修を受講し、認定看護師の資格取得も視野に入れた活動を続けています。医療機関からの支援体制も整っており、専門性を深めながらキャリアを築いています。
Case C:訪問看護から訪問診療への転職
訪問看護ステーションで3年間の経験を持つCさんが、より医療に特化した環境を求めて訪問診療所への転職を実現した事例です。
転職の決め手
訪問看護での経験を活かしながら、より医療的な介入が必要なケースに携わりたいという思いから転職を決意されました。医師との連携がより密接な環境で、専門的なスキルを磨きたいという希望が叶いました。
スムーズな環境移行
訪問看護での経験が大きな強みとなり、在宅での看護技術やコミュニケーションスキルを活かして、スムーズに新しい環境に適応することができました。
Case D:ブランクがあっての復職
出産・育児のため5年のブランクがあったDさんが、訪問診療看護師として復職を果たした事例です。ワークライフバランスを重視した働き方を実現されています。
復職までの準備
育児との両立を考慮し、時短勤務が可能な訪問診療所を選択されました。復職前に電子カルテの操作研修や、基本的な医療技術の復習を行い、不安なく業務をスタートすることができました。
段階的なスキルアップ
最初は週3日の時短勤務からスタートし、子どもの成長に合わせて徐々に勤務日数を増やしていきました。医療機関の理解もあり、無理のないペースでキャリアを再スタートすることができました。
Case E:新卒での就職
新卒でいきなり訪問診療の世界に飛び込んだEさんの挑戦的な事例です。充実した教育体制のもと、着実にスキルを磨いています。
新卒採用のメリット
基礎からじっくりと訪問診療の知識とスキルを学べる環境が整っていたことが、新卒での就職を決めた大きな理由でした。プリセプター制度による手厚い指導のもと、確実に成長を実感できています。
成長のプロセス
入職後6ヶ月間は先輩看護師との同行訪問を中心に、基本的なスキルの習得に専念しました。その後、徐々に独り立ちし、現在では中心的なスタッフとして活躍されています。
おしえてカンゴさん!よくある質問

訪問診療看護師として働くことに関する疑問や不安について、経験豊富な先輩看護師がお答えします。実際の現場で役立つ情報や、転職活動に向けたアドバイスをご紹介していきましょう。
応募・採用に関する質問
Q1:訪問診療の経験がなくても応募できますか?
はい、多くの医療機関では、病院での実務経験があれば未経験でも応募可能です。特に急性期病棟での経験は、医療処置の技術面で高く評価されることが多いです。ただし、採用後は訪問診療特有のスキルを習得するための研修期間が設けられます。
研修制度が充実している医療機関を選ぶことをお勧めします。
Q2:ブランクがある場合、どのような準備が必要ですか?
ブランクがある場合でも、多くの医療機関が復職支援プログラムを用意しています。応募前に、基本的な医療知識の復習や、電子カルテの操作研修を受講することをお勧めします。また、訪問診療に特化した勉強会や研修会に参加することで、現場の雰囲気を掴むこともできます。
働き方に関する質問
Q3:残業は多いのでしょうか?
訪問診療は比較的定時で帰宅できる職場が多いです。ただし、緊急時の対応や記録作成により、occasional(時折)の残業は発生することがあります。一般的な残業時間は月10時間程度で、病院勤務と比較すると大幅に少なくなっています。
Q4:オンコール対応は必須ですか?
医療機関によって対応は異なりますが、多くの場合チーム制でのオンコール体制を取っています。ただし、入職後すぐにオンコール当番が入るわけではなく、段階的に担当していく形が一般的です。
また、育児中のスタッフへの配慮として、オンコール免除制度を設けている医療機関も増えています。
スキルアップに関する質問
Q5:専門資格の取得は可能ですか?
多くの医療機関が、認定看護師や専門看護師の資格取得を支援しています。特に在宅ケア、緩和ケア、認知症ケアなどの分野で、専門性を高めるキャリアパスが用意されています。
資格取得に向けた研修費用の補助や、勤務調整など、具体的なサポート体制が整っているケースが多いです。
給与・待遇に関する質問
Q6:給与は病院勤務と比べてどうですか?
一般的に、訪問診療の給与水準は病院勤務と比較して同等かやや高めとなっています。特に、訪問手当やオンコール手当などの各種手当が充実している点が特徴です。また、残業が少ないことで、時間当たりの実質収入は高くなる傾向にあります。
仕事内容に関する質問
Q7:1日の訪問件数はどのくらいですか?
経験や勤務形態にもよりますが、常勤の場合、1日平均4〜6件程度の訪問を担当します。ただし、入職後しばらくは2〜3件からスタートし、徐々に件数を増やしていく形が一般的です。
訪問時間は1件あたり30分〜1時間程度で、移動時間も考慮した無理のないスケジュール管理が行われています。
今後のキャリアに関する質問
Q8:将来的なキャリアアップの可能性はありますか?
訪問診療の現場では、経験を積むことでさまざまなキャリアアップの道が開かれています。
例えば、複数のスタッフのマネジメントを担当する主任職や、新人教育を担当する教育担当者、さらには管理者として医療機関の運営に携わるなど、多様なキャリアパスが用意されています。
また、前述の専門資格取得による専門性の向上も、重要なキャリアアップの選択肢となっています。
まとめ
訪問診療看護師は、高齢化社会における重要な役割を担う専門職として、今後ますます需要が高まることが予想されます。給与水準や勤務条件も魅力的で、ワークライフバランスを重視したキャリア形成が可能です。
未経験やブランクがある方でも、充実した研修制度を備える医療機関も多く、着実にスキルアップを図ることができます。
より詳しい情報は【はたらく看護師さん】で
訪問診療看護師としてのキャリアについて、さらに詳しい情報をお求めの方は、【はたらく看護師さん】の会員登録がおすすめです。実践的なキャリアアドバイスや、先輩看護師の体験談など、お役立ち情報が満載です。