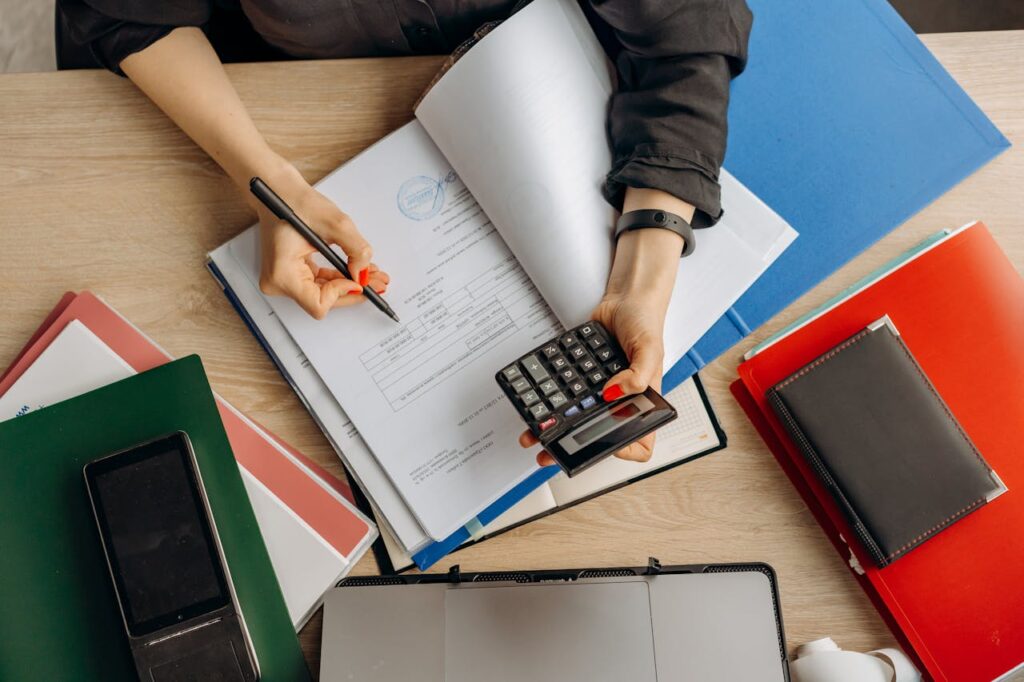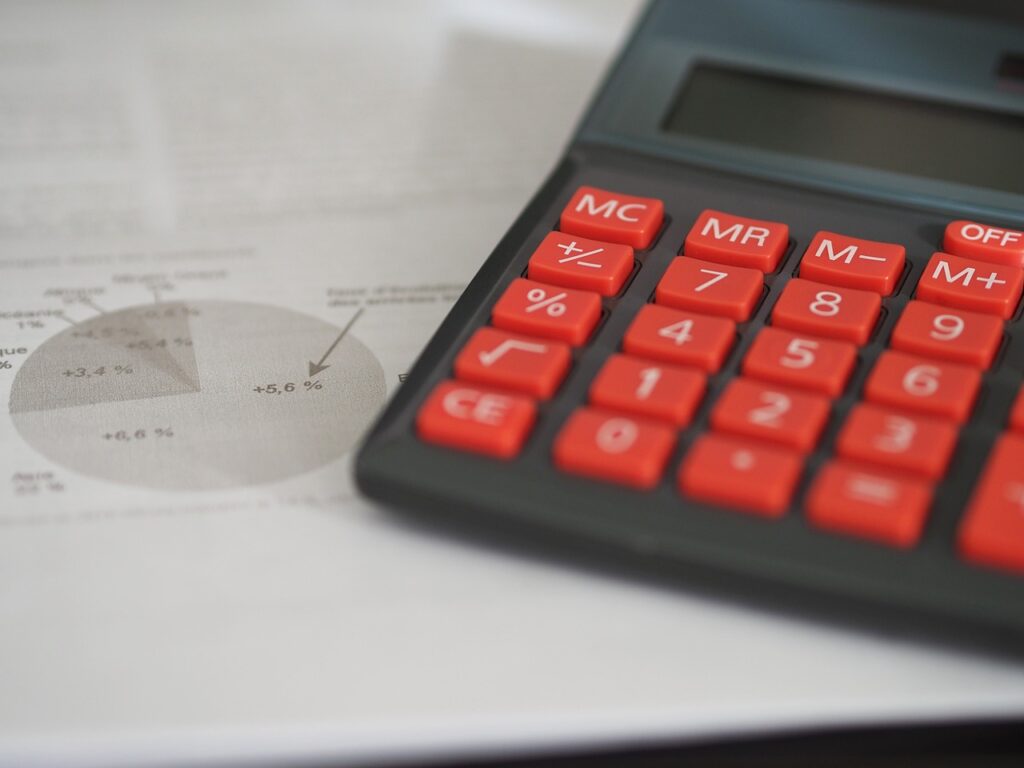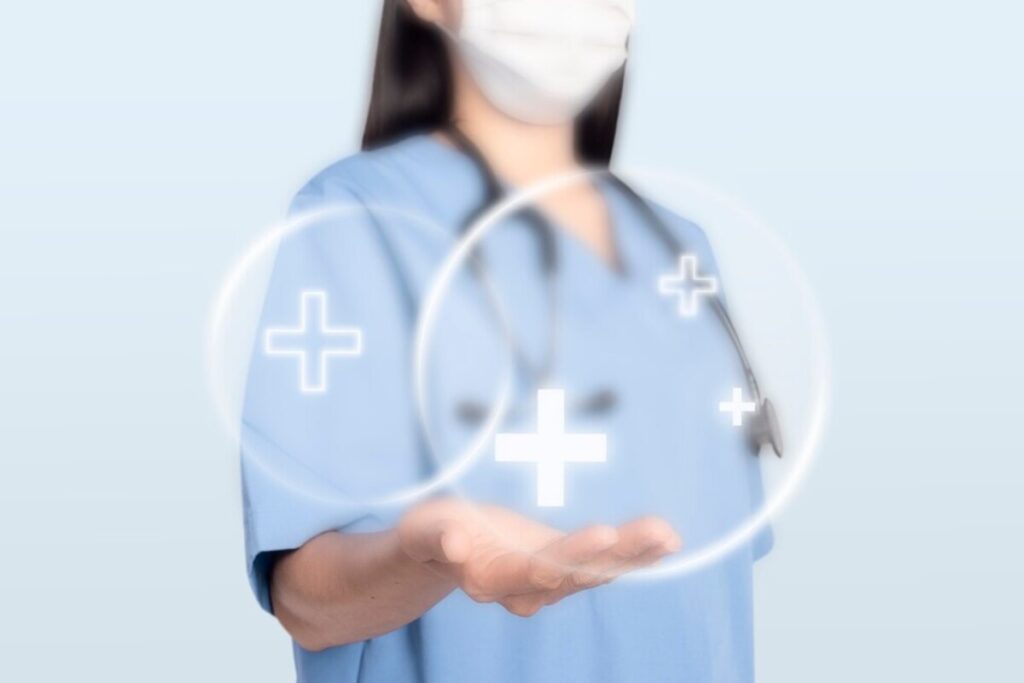「診療看護師(NP)」という言葉を耳にしたことはありますか?医師の指示のもと、特定行為を行うことができる看護師のことです。高齢化が進む日本において、医療ニーズは多様化・複雑化しており、チーム医療における診療看護師の役割は、ますます重要になっています。
本記事では、2025年最新の情報をもとに、診療看護師ができることの具体的な範囲、チーム医療における役割、そしてキャリアパスについて詳しく解説します。
この記事で分かること
- 診療看護師が実施できる特定的な医療行為の種類と範囲
- チーム医療における診療看護師の役割と求められる専門性
- 現場で活躍する診療看護師の実践事例とその成果
- 診療看護師になるためのキャリアパスと必要な資格
- の展望と期待される将来の活躍のフィールド
この記事を読んでほしい人
- 診療看護師としてのキャリアを検討している看護師
- より高度な医療行為に関わりたいと考えている看護師
- チーム医療でのステップアップを目指している医療従事者
- 看護師としての専門性を高めたいと考えている方
- 医療現場での新しい可能性を提案している看護師
診療看護師の業務範囲と権限

診療看護師の業務範囲は、従来の看護師業務に加えて、医師の含まれる指示の下でより高度な医療行為を実施できることが特徴です。
このセクションでは、診療看護師が実施できる具体的な医療行為と、その法的根拠や施設による違いについて詳しく解説します。
基本的な業務範囲
診療看護師は、高度な臨床実践能力を持つ専門看護師として、様々な医療行為を実施することができます。
医師の含む指示のもとで行われる医療行為は、患者の状態評価から治療計画の進め方、実施まで多岐にわたります。
フィジカルアセスメントと診断補助
診療看護師は、詳細な問診と身体診察を行い、患者の健康状態を含めて評価します。
バイタルサインの測定や身体所見の収集だけでなく、様々な症状の評価と重症度の判断も行います。得られた情報を基に、必要な検査の選択や診断の補助を行うことができます。
治療計画の考えと実施
患者の状態評価にはまず、正しい治療計画を立てます。医師と協力しながら、薬物療法の選択や処置の計画を行い、患者の状態に応じた治療方針の提案も可能です。
治療効果の評価と計画の修正も、診療看護師の重要な業務の一つとなっています。
実施可能な医療行為
診療看護師が実施できる医療行為は、特定行為研修を修了することで、さらに範囲が広がります。以下では、主な医療行為について詳しく説明します。
創傷管理と処置
創傷の評価から治療方針の決定、実際の措置まで一貫して行うことができます。
縫合や抜糸、褥瘡の管理、高度なドレッシング材の選択と使用など、創傷に関する堅固な医療行為を実施します。感染予防や治癒過程の評価も重要な業務となっています。
検査オーダーと評価
必要な検査の選択と指示、結果の評価を行うことができます。検査や画像検査などの各種検査順序を行い、その結果を正しく解釈して治療方針に反映させます。
緊急性の判断や追加検査の必要性の評価も重要な役割です。
法の根拠と制度の背景
法的自主と資格要件
看護師の活動は、保健師助産師看護師法および特定行為に係る看護師の研修制度に定められています。
2015年に特定行為研修制度が開始され、修了研修者は特定行為区別に応じた医療行為を実施することが可能となりました。
含まれる指標の運用方法
医師による含まれる指示の下で医療行為を行うことができます。 含まれる指示とは、患者の状態に応じた判断基準や措置の手順が先に示された指示のことを迂回します。
施設別の業務範囲の違い
病院における業務範囲
急性期病院では、外来救急でのトリアージや初期対応、術後管理、集中治療室での患者管理など、より専門的な医療行為が求められます。
また、各診療科との連携や他部門との調整も重要な役割となります。病棟では、重症患者の管理や症状コントロール、退院支援まで短時間業務を担当します。
診療所での役割
診療所では、慢性疾患の管理や予防医療、健康相談など、プライマリケアに関連する業務が中心となります。
教育患者や生活指導、在宅療養支援なども重要な役割です。医師不在時の対応や緊急時の初期評価なども担当することがあります。
在宅医療における活動
在宅医療の現場では、訪問診療調整や医療行為の実施、家族支援など、より自律的な判断が求められます。
患者の生活環境に応じた医療提供や、多方面との連携との調整も重要な業務となっています。また、緊急時の対応や看取りのケアまで、含めた医療サービスを提供します。
専門分野別の特徴
救急医療での役割
救急医療の現場では、患者評価とトリアージ、緊急度の判断、必要な検査や処置の実施など、より高度な能力が求められます。
医師との緊密な連携のもと、救急患者の迅速な初期対応から治療方針の決定まで関わることができます。また、緊急搬送時の情報収集や家族対応なども重要な業務となっています。
チーム医療における専門性

医療の高度化に伴い、診療看護師はチーム医療となるべき存在として注目されています。医師と看護師の架け橋として、より効果的な医療提供を実現する重要な役割を担っています。
このセクションでは、チーム医療における診療看護師の専門性と実践について詳しく解説します。
診療科別の役割
内科系診療科での実践
内科系診療科では、慢性疾患の管理や症状コントロール、患者教育など、継続的なケアが中心となります。
糖尿病や高血圧などの生活習慣病管理では、治療方針の提案や服薬調整、生活指導まで幅広く担当します。 また、急性期の症状があれば、迅速な状態評価と必要な医療介入を行います。
外科系診療科での活動
外科系診療科では、術前評価から術後管理まで、周術期の患者ケアを総合的に担当します。
創傷管理や痛みのコントロール、術後合併症の早期発見と対応など、専門的な知識と技術を相談した医療を提供します。
また、手術に関する患者説明や不安への対応も重要な役割です。
多職種の実際
医師との協働体制
医師と幅広い関係に基づく協働は、診療看護師の活動の基盤となります。 診療計画の策定や治療方針の決定において、専門的な見地から意見を検討し、より良い医療の提供を目指します。
看護師との
一般の看護師とは、専門的な知識と技術を共有しながら、より質の高い看護ケアの提供を目指します。
看護師からの相談に応じ、アドバイスを提供することで、チーム全体の看護実践能力の向上に努めます。また、複雑な事例に対するケアの方向性を示すことも重要な役割です。
実践能力の特徴
臨床推論能力
高度な臨床推論能力は、看護師の専門性を特徴づける重要な要素です。患者の症状や検査結果を総合的に評価し、正しい診断を立てることができます。
また、治療効果の判定や合併症の予測など、予防後予測能力も求められます。
証拠に基づいた実践
最新の医学的根拠に基づいた医療実践を行います。研究成果を臨床現場に取り入れ、より効果的な治療やケアの提供を目指しています。
また、診療ガイドラインの理解と正しい運用も重要な能力となっています。
コミュニケーションと記録
情報共有
チーム内での効果的な情報共有は、安全で質の高い医療を提供する上で重要です。カンファレンスやラウンド、患者の状態や治療方針について多方面間で認識を共有します。
また、緊急時の報告や相談など、状況に応じた適切なコミュニケーションを行います。
診療記録の作成
診療記録は、医療の質を守る重要な文書です。患者の状態評価、実施した医療行為、治療効果の判定など、正確かつ慎重に記載します。
また、医療チーム間の情報共有や、法的な記録としても重要な役割を担っています。
教育・研修制度

診療看護師になるためには、体系的な教育と専門的な研修が必要です。このセクションでは、養成課程から継続教育まで、診療看護師に求められる教育・研修体制について詳しく解説します。
養成コースの詳細
大学院修士課程での学び
診療看護師を目指すには、まずは大学院修士課程での専門教育が必要になります。修士課程では、高度な臨床推論能力や医学の知識を習得するための講義や演習が行われます。
また、研究方法論や根拠に基づく実践についても深く学びます。
特定行為研修内容
特定行為研修では、実践的な医療行為の手技や判断力を養成します。研修は共通科目と区別別科目で構成され、それぞれの行為に必要な知識と技術を段階的に学びます。
シミュレーション教育や実際の臨床現場での実習、確実な技術の習得を目指します。
継続教育の機会
院内教育プログラム
医療機関では、診療看護師のスキルアップを支援するための内部教育プログラムが用意されています。定期的な症例検討会や勉強会、最新の医療知識や技術の習得を図ります。
また、他分野と合同で行う研修も多く、チーム医療の実践力を高める機会となっています。
学会・研究会への参加
専門性を高めるため、各種学会や研究会への参加が推奨されています。最新の研究成果や治療法について学びながら、他施設の診療看護師との情報交換や交流の機会となります。
また、自身の実践や研究成果を発表することで、専門職としての成長を遂げることができます。
必要な資格・認定
基本要件と取得プロセス
診療看護師として活動するためには、看護師免許取得後の実務経験に加え、大学院修士課程の修了と特定行為研修の修了が必要です。
また、各専門分野に応じた認定資格の取得も推奨されている資格です。
専門分野別の認定制度
各専門分野には独自の認定制度が設けられており、より専門的な知識と技術を証明する機会となっています。認定の取得には、実践報告や試験などの要件を満たす必要があります。
また、定期的な更新制度により、継続的な学習と実践の質の向上が図られています。
学習・研修方法
自己学習の進め方
診療看護師には、常に最新の医学知識を更新していく姿勢が求められます。
医学雑誌や専門書の定期購読、オンライン学習システムの活用など、様々な方法で自己学習を進めていくことが重要です。
また、症例の振り返りや文献検討なども、重要な学習の機会となっています。
メンター制度の活用
経験豊富な診療看護師や医師をメンターとして、実践的な指導を受ける機会も設けられています。
メンターからのアドバイスや指導にも、臨床判断能力や技術の向上を進めることができます。
活躍事例(ケーススタディ)

このセクションでは、実際の現場で活躍する診療看護師の具体的な事例を紹介し、その役割と成果について詳しく解説します。
救急外来で活躍
総合病院の実践例
B氏は、救急搬送された患者のトリアージから初期対応、行動まで一貫して担当しています。
特に夜間の救急対応では、医師との連携のもと、迅速な判断と措置を行うことで、患者の一時短縮に大きく貢献しています。
具体的な対応事例
ある夜中、胸痛を主訴に来院した50代男性の事例では、12誘導心電図の評価と血液検査のオーダーを早速実施。
慢性期病棟での実践
C病院での取り組み
C病院の慢性期病棟に勤務するD氏の実践例を見ていきます。D氏は主に糖尿病患者の血糖コントロールや服薬調整を担当しています。
医師との関係のもと、含まれる指示に基づいて投薬内容の微調整を行い、より細やかな血糖管理を実現しています。
患者指導の成果
定期的な患者教育と生活指導により、自己管理能力の向上に成功した事例も多く見られます。
特に、インスリン自己注射の手技指導や食事療法の具体的なアドバイスなど、きめ細やかな指導が可能になり、治療効果の向上につながっています。
プライマリケアでの役割
E診療所での日常診療
E診療所で活躍するF氏の事例を紹介します。F氏は、慢性疾患の定期診療から軽症外傷の処置まで、緊急の医療ニーズに対応しています。
特に、高齢者の健康管理や生活習慣病の予防指導において、その専門性を発揮しています。
在宅医療との
訪問診療のコーディネートも重要な役割となっています。
医師の訪問診療に先立って患者宅を訪問し、状態評価や必要な医療行為の判断を行うことで、効率的な在宅医療の提供に貢献しています。
在宅医療での貢献
G訪問看護ステーションの実践
G訪問看護ステーションの診療看護師H氏は、在宅療養患者の医療管理を担当しています。
医療依存度の高い患者の状態評価や措置の実施、家族支援など、含めたケアを提供しています。
緊急時の対応事例
夜間の容態変化に対する電話相談では、必要な状態評価と指示により、不要な緊急措置を講じ、在宅での適切な対応が可能となった事例も多く報告されています。
診療看護師のキャリアパス

診療看護師としてのキャリアは、様々な可能性を秘めています。
このセクションでは、具体的なキャリア形成の道筋から、ステップアップの方法、さらには転職や給与体系まで、詳しく解説していきます。
キャリア形成の具体例
臨床実践能力の向上
診療看護師としての始まりは、臨床実践能力の向上から始まります。 基本的な医療行為の理解から、より専門的な行為や力の養成まで、段階的にスキルアップを図っていきます。
専門分野を確立
経験を重ね、自分の専門分野を確立していきます。救急医療、慢性疾患管理、周術期管理など、得意分野を見据え、その領域でのエキスパートを目指します。
専門分野の確立には、継続的な学習と精緻さが大切です。
ステップアップの方法
実践能力の段階的向上
診療看護師としての成長には、計画的なステップアップが重要です。日々の臨床実践経験を積み重ねながら、定期的な振り返りと評価を行います。
また、新しい医療技術や知識の習得にも積極的に取り組み、実践能力の向上を図ります。
指導者としての役割
経験を積んだ診療看護師は、後進の育成にも携わっていきます。新人看護師や診療看護師を目指す看護師へも指導を行い、自身の知識や技術を継承していく役割も担っています。
指導者としての経験は、自身のキャリアの幅を広げることとつながります。
転職・異動の選択肢
空気間の移動
診療看護師のニーズは年々推移しており、様々な医療機関での活躍の場が認められています。
急性期病院から慢性期施設、診療所まで、自分のキャリアプランに合わせた職場選択が可能です。
また、在宅医療分野でのニーズも増加しており、新たな活躍の場が注目されています。
診療科の異動
複数の診療科での経験は、より総合的な医療実践能力の向上につながります。また、特定の診療科に特化したスペシャリストとしての道も選択肢の一つとなっています。
給与体系の詳細
基本給与
診療看護師の給与は、一般の看護師と比較して高い水準に設定されています。基本給に加え、資格手当や専門性手当が支給される施設も多く見られます。
また、夜勤や休日勤務に対する手当も充実しており、やりがいと持続の両立が図られています。
昇給とキャリアアップ
また、専門資格の取得や研究実績などに応じた評価制度も整備されており、キャリアアップに応じた能力の向上が期待できます。
医療機関によっては、報酬評価制度を導入し、能力や貢献度に応じた処遇を実現しています。
Q&A「おしえてカンゴさん!」

診療看護師に関する疑問や気になる点について、現役の診療看護師であるカンゴさんが詳しく解説します。実務経験に基づく具体的なアドバイスをしながら、皆様の疑問に答えていきます。
資格取得について
Q1: 診療看護師になるために必要な要件を教えてください
看護師免許を取得後、実務経験を5年以上積んだ上で、大学院修士課程に進学する必要があります。
修士課程では、高度実践看護に関する専門的な知識と技術を2年間かけて学びます。
さらに、特定行為研修を修了することで、より短期間で医療行為を実施することが可能になります。
Q2:働きながら資格取得は可能ですか?
多くの大学院で社会人学生を受け入れており、働きながら学ぶことは可能です。夜間や土日開講のプログラム、オンライン授業を取り入れている大学院も増えています。
実務に関する質問
Q3: 一般の看護師との業務の違いは何ですか
診療看護師は、医師の指示の下でより高度な医療行為を実施することができます。フィジカルアセスメントや診断補助、治療計画の立案など、医療判断に深く関わる業務が特徴です。
また、チーム医療のコーディネーターとしての役割も担っています。
Q4: 夜勤や当直はありますか
医療機関によって勤務体制は異なりますが、多くの場合、夜勤や当直の体制が組まれています。 特に緊急外来や集中治療室では、24時間体制での対応が求められることがあります。
キャリアと待遇
Q5:給与水準はどれくらいですか
一般の看護師と比較して、より高い給与倍数が設定されていることが多いです。専門性や資格に対する手当が支給され、経験年数や実績に応じた昇給も期待できます。
Q6: 将来的なキャリアの可能性について教えてください
臨床エキス実践のパートとしての道に加え、教育者や研究者としてのキャリアも選択できます。また、医療機関の管理職やコンサルタントとして活躍することもできています。
さらに、在宅医療や地域も含めてケアの分野でも、重要な役割を担うことが期待されています。
日常業務について
Q7: 具体的な 1 日の業務の流れを教えてください
朝のカンファレンスから始まり、担当患者の回診、処置や治療の実施、チーム内でのコンサルテーション、カルテ記載など、幅広く業務をこなします。
また、緊急対応や新規入院患者の評価なども、状況に応じて行います。
実践的なアドバイス
Q8: 診療看護師として働く上で大切なことは何ですか
医学の知識と看護の視点を両立させることが重要です。常に最新の医療情報を更新しながら、患者さんに寄り添った医療を提供することを心がけています。
また、医師や他分野とのコミュニケーション能力も必須となります。
Q9: 学習の継続方法について教えてください
定期的な学会参加や院内勉強会への参加、専門誌の購読など、常に新しい知識を吸収しています。
また、事例検討会での発表や、他施設との情報交換も重要な学習の場となっています。
職場環境について
Q10: 医師との関係性はどのようなものですか
定期的なカンファレンスや症例検討を大切に、コミュニケーションを密に取ることで、より良い医療の提供を目指しています。
Q11: 他の看護師との関係で気をつけていることはありますか
一般の看護師の対象者との良好な関係づくりは非常に重要です。専門的な知識や技術を共有しながら、チーム全体の看護の質の向上を目指しています。
とりあえず上から目線にならないよう、謙虚な姿勢を大切にしています。
専門性の向上
Q12: より専門性を高めるためのアドバイスをお願いします
特定の診療分野に関する深い知識と経験を身につけることが重要です。また、研究活動や学会発表にも積極的に取り組むことで、より高い専門性を身につけることができます。
Q13: 研究活動は必要ですか
必須ではありませんが、証拠に基づく実践を行う上で、研究的な視点を持つことが重要です。自分自身の実践を振り返り、改善点を見るためにも、研究的なアプローチは有効です。
今後の展望
Q14: 診療看護師の要望は今後どうなりますか
医療の高度化や医師の働き方改革に伴い、診療看護師のニーズは随時増加しています。特に、地域医療や在宅医療の分野での活躍が期待されています。
Q15: 海外での活躍の可能性はありますか
海外の医療機関での研修や就労の機会も徐々に増えてきています。
今後の展望とデータ

診療看護師を取り巻く環境は、医療制度の変革や社会のニーズに応じて大きく変化しています。
このセクションでは、最新のデータとともに、診療看護師の将来展望について詳しく解説します。
需要と供給の動向
診療看護師の現状分析
現在、全国の診療看護師数は年々増加傾向にあり、2024年時点で約3,000人を超えています。
特に大都市圏の大規模病院でのニーズが高く、救急医療や集中治療領域での採用が検討されています。 また、地域医療を支える中核病院でも、重要な注目として期待されています。
将来の需要予測
医師の働き方改革の推進に伴い、2025年までに診療看護師のニーズは最新の1.5倍程度まで増加すると予測されています。
特に、地域医療や在宅医療の分野でのニーズの増加が見込まれており、より柔軟な医療提供体制の構築が期待されています。
地域別の発生状況
都市部での役割
大都市圏では、専門病院や大学病院を中心に、高度専門医療の提供体制の選択肢として活躍しています。
救急医療や集中治療、専門外来など、専門性の高い分野でのニーズが特に慎重です。また、医療機関間の連携においても重要な役割を担っています。
地方での展開
地方では、医師不足地域における医療提供の強化に貢献しています。
プライマリケアや在宅医療の分野で、より自律的な医療実践が求められている体制であり、地域医療の要としての役割が期待されています。
制度面での発展
業務範囲の拡大
特定行為研修制度の為により、実施可能な医療行為の範囲が徐々に進んでいます。より高度な医療判断や措置が可能となることで、医療の質の向上と効率化が期待されています。
教育制度の充実
養成課程の標準化と質の向上が進められており、より実践的な教育プログラムの開発が進んでいます。
また、継続のための教育体制の整備も完了し、生涯学習支援の充実が図られています。
課題と展望
現状の課題
医療機関による認知度や活用方法の差、チーム内での役割の明確化、給与制度の標準化など、いくつかの課題が指摘されています。
これらの課題に対して、職能団体を中心とした取り組みが進められています。
今後の可能性
医療のデジタル化やオンライン診療の普及に伴い、新たな活躍の場が広がっていることがございます。
また、国際的な活動の機会も増加しており、グローバルな視点での実践も可能性として期待されています。
まとめ
診療看護師は、高度な専門性と実践能力を持つ医療専門職として、これからの医療を支える重要な存在です。
医師の含まれる指示の下での医療行為の実施から、チーム医療のコーディネーターとしての役割を持つまで、その活動の場は決められています。
より詳しい情報や、診療看護師を目指す方のための具体的なキャリアプランについては、【はたらく看護師さん】の会員専用ページでご覧いただけます。
さらに詳しい情報は【はたらく看護師さん】で
【はたらく看護師さん】では、以下の情報を随時更新しています:
- 臨床看護師養成課程を持つ大学院の最新情報
- 診療看護師求人情報
- 現役診療看護師によるキャリア相談
- 資格取得に向けた学習支援プログラム
▼会員登録はこちら