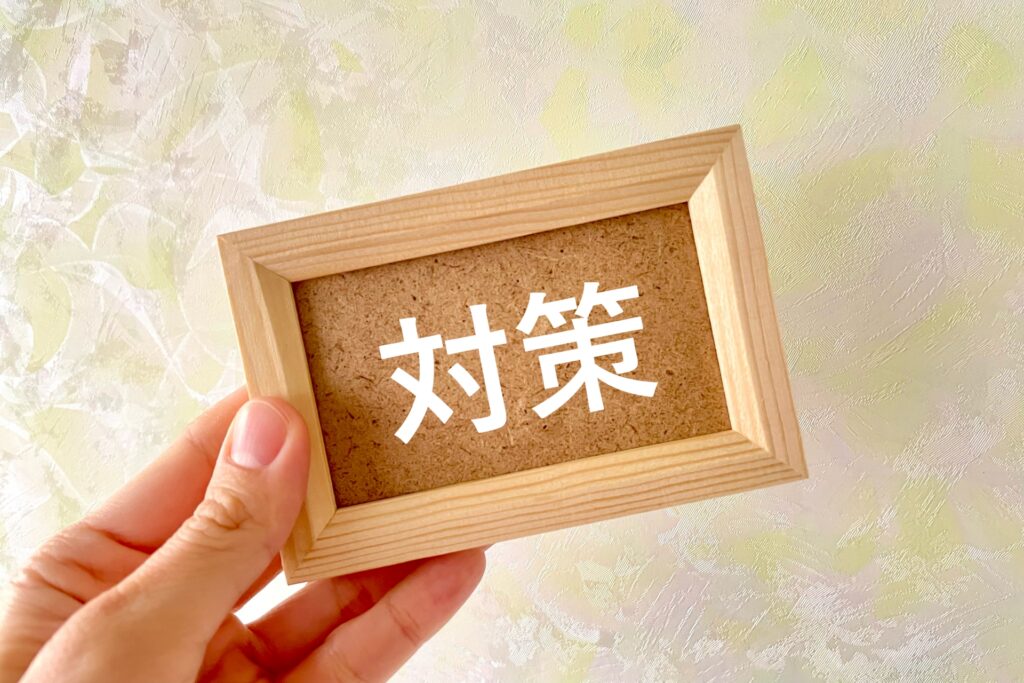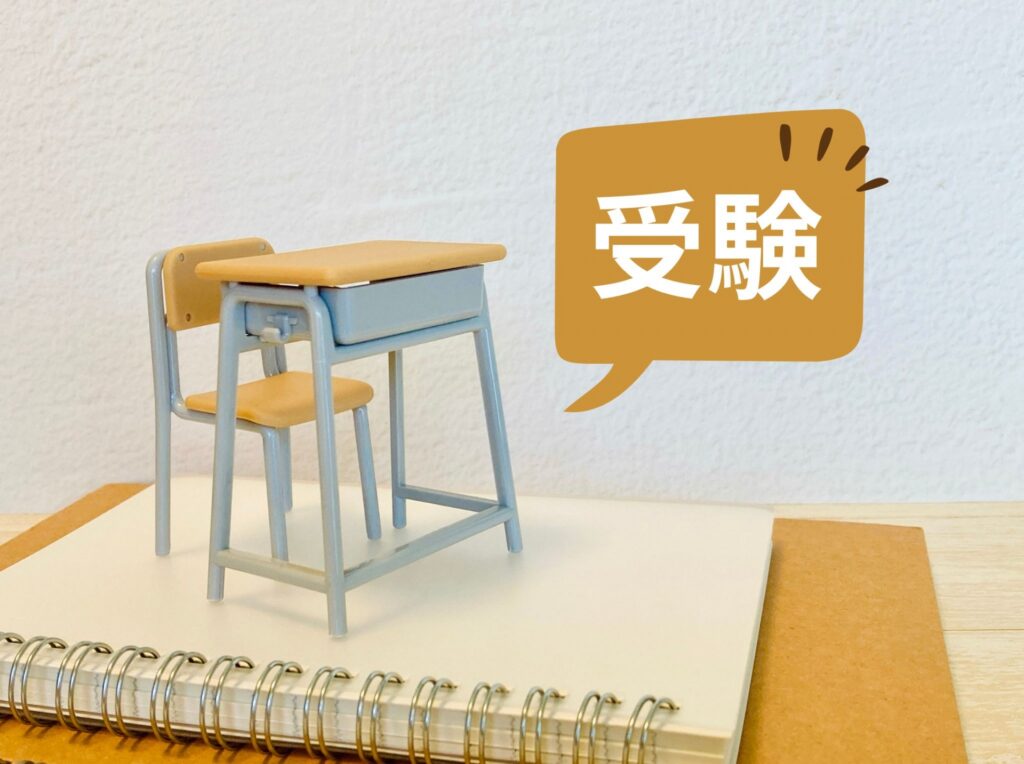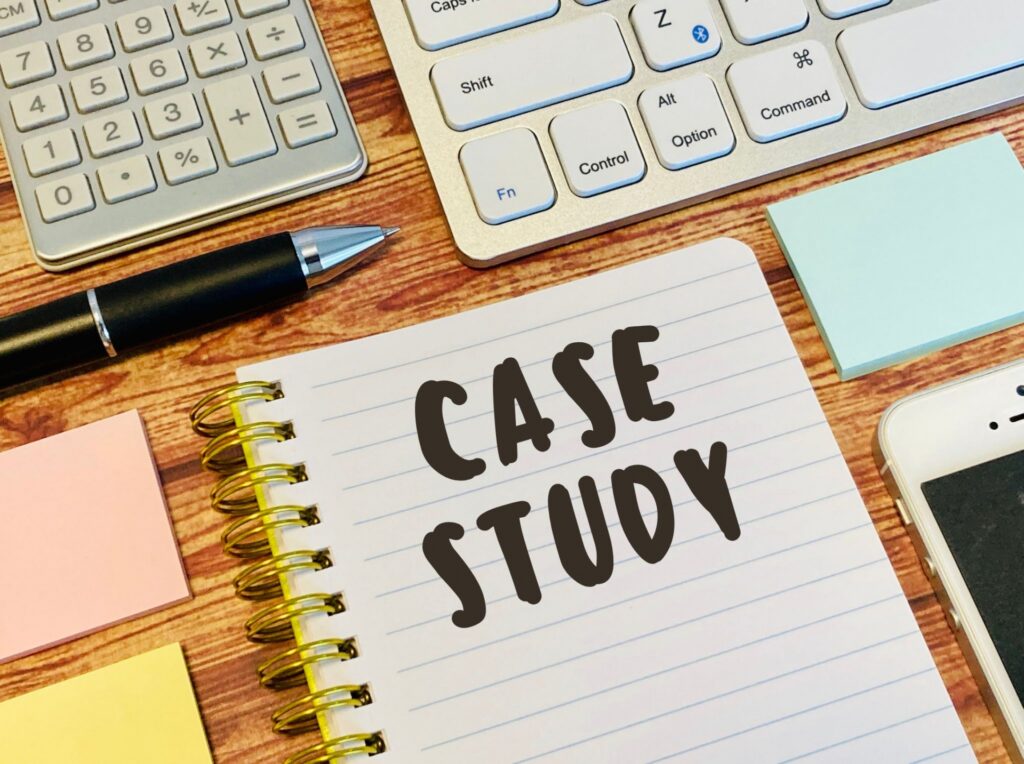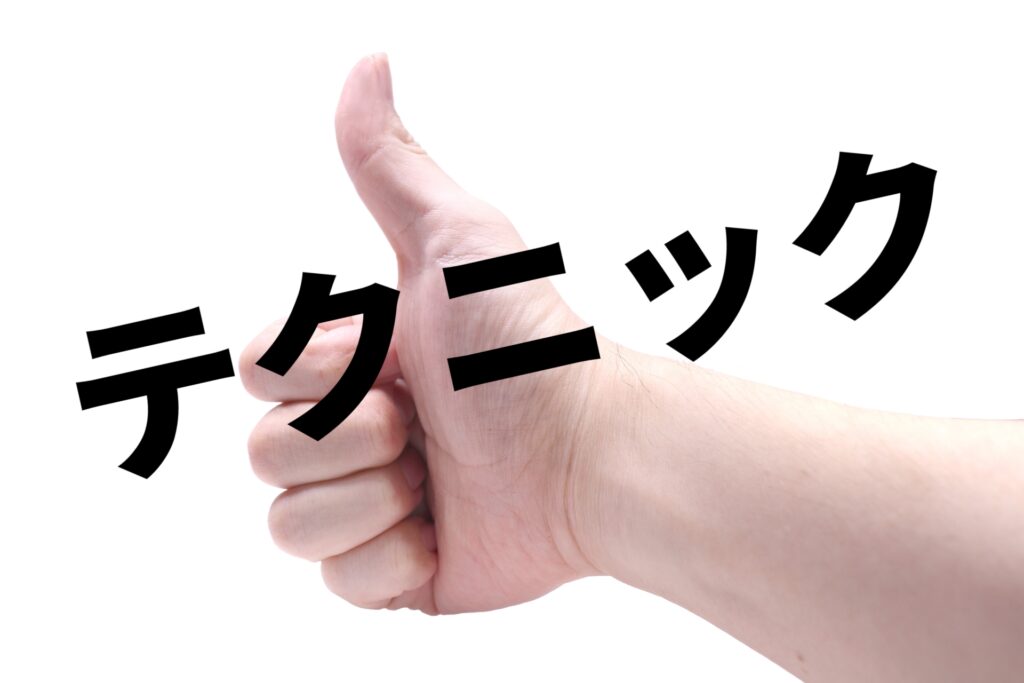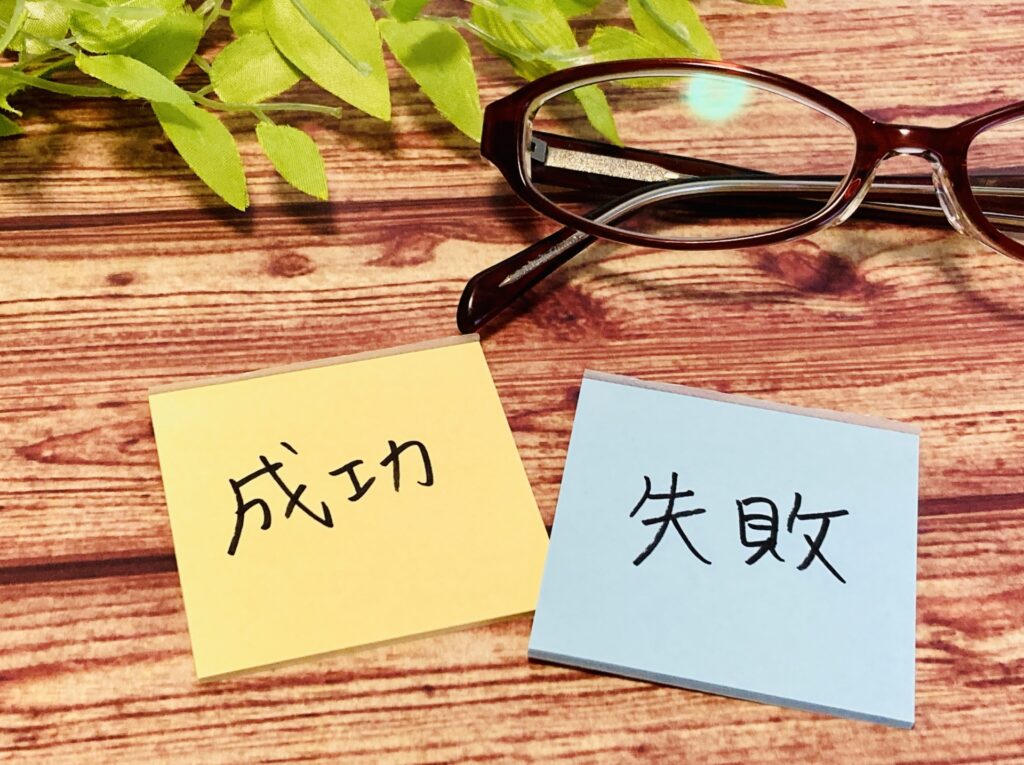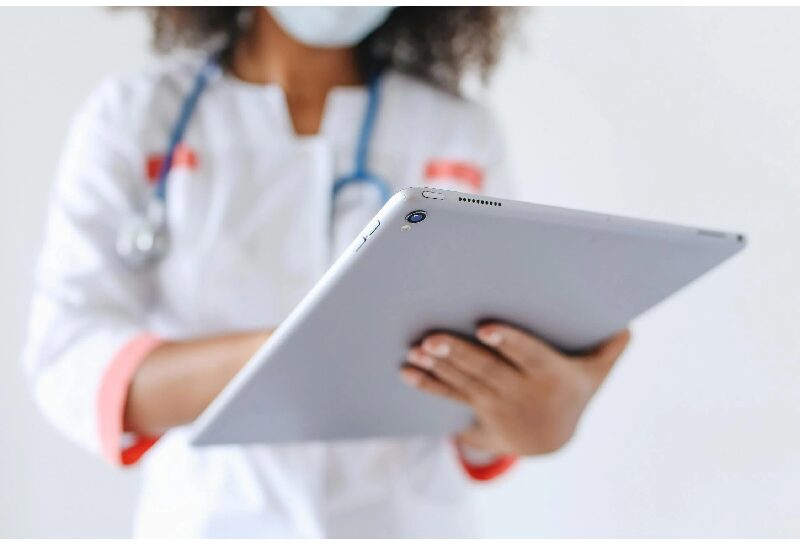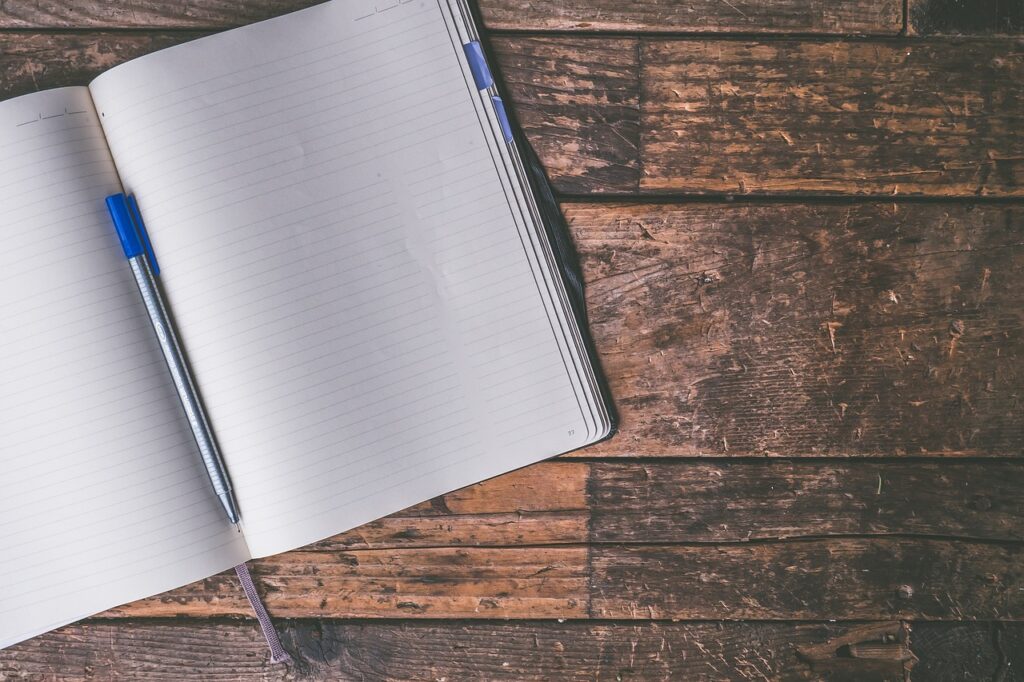労災看護専門学校は、充実した実習環境と高い国家試験合格率を誇る看護専門学校として知られています。本記事では、入試から卒業後のキャリアまで、学校選びに必要な情報を詳しく解説します。
この記事で分かること
- 教育方針、カリキュラム内容、充実した実習プログラムによる実践的な学び
- 入試情報と受験対策、就職支援体制による万全のサポート体制
- 奨学金制度と学費情報で具体的な進学プラン
この記事を読んでほしい人
- 看護師を目指す高校生、社会人の方と保護者
- 労災看護専門学校への進学を検討している受験生
- 看護教育に関心のある医療従事者や教育関係者
1. 労災看護専門学校の特徴と教育方針
労働者健康安全機構が運営する本校は、労働衛生分野に強い看護師の育成に特化した教育を提供しています。充実した実習環境と経験豊富な教員陣による実践的な指導が特徴です。
学校の概要と歴史
労災看護専門学校は1975年の設立以来、4000名以上の看護師を輩出してきました。労災病院グループとの密接な連携により、最新の医療現場で求められる知識と技術を習得できる環境を整えています。入学定員は80名で、全国から意欲的な学生が集まっています。
教育課程は3年制で、1学年から段階的に専門性を高められるよう工夫されています。特に実習では、労災病院グループの施設を中心に、急性期から慢性期まで幅広い看護実践を学ぶことができます。
教育理念とビジョン
本校は「人間性豊かで実践力のある看護師の育成」を教育理念に掲げています。この理念のもと、確かな専門知識と技術、豊かな人間性と倫理観、地域医療への貢献意識を持った看護師の育成を目指しています。
施設・設備の特徴
本校では、実践的な看護技術を習得するための最新設備を完備しています。シミュレーション教育用の高機能患者模型や、電子カルテシステムを導入した演習室など、実際の医療現場を想定した学習環境が整っています。
図書室には看護・医学分野の専門書や学術雑誌が豊富に揃えられており、24時間利用可能なオンラインデータベースも完備しています。
2. 2025年度入試情報と対策

2025年度の入試では、多様な受験機会を提供するため、複数の入試区分を設けています。それぞれの特徴を理解し、自分に適した受験方法を選択することが重要です。
入試概要と選考方法
2025年度入試では、推薦入試、一般入試、社会人特別選抜の3つの区分で募集を行います。推薦入試は指定校推薦と公募推薦があり、高校での成績や課外活動が評価対象となります。
一般入試は前期と後期に分かれており、学科試験と面接による総合評価で合否を判定します。社会人特別選抜では、職務経験を踏まえた小論文と面接を重視しています。
科目別対策のポイント
入試では国語、数学、英語の3教科が課されます。国語では医療系の文章読解が重視され、的確な要約力と論理的思考力が問われます。数学では基礎的な計算力に加え、医療統計の基礎となる確率・統計の理解が必要です。英語では医療英語の基礎知識と、医療系記事の読解力が評価されます。
試験対策のための準備と心構え
看護師を目指す皆様にとって、入試準備は重要となります。本校の入試では、基礎学力に加えて看護師としての適性や意欲も重視しています。
面接試験では、医療や看護に対する関心度、コミュニケーション能力、将来のビジョンなどについて質問されます。事前に自己分析を行い、志望動機を明確にすることが重要です。また、医療ニュースや看護に関する時事問題にも目を通し、幅広い知識を身につけることをお勧めします。
3. カリキュラムと実習内容

本校のカリキュラムは、看護師として必要な知識と技術を段階的に習得できるよう設計されています。基礎から応用へと体系的に学びを深め、確かな実践力を身につけることができます。
年次別カリキュラムの特徴
1年次では、看護の基礎となる知識と技術の習得に重点を置いています。人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進など、専門基礎分野の学習を通じて、看護の土台となる医学的知識を学びます。
基礎看護学では、看護の本質や基本的な看護技術について学習します。また、コミュニケーション論や心理学などの教養科目を通じて、豊かな人間性を育みます。
2年次からは、専門分野の学習が本格的に始まります。成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学などの各領域で、対象に応じた看護の特徴と実践方法を学びます。臨地実習も始まり、講義で学んだ知識を実践の場で活用する機会が増えていきます。
3年次では、これまでの学びを統合し、より実践的な能力を養います。在宅看護論や看護の統合と実践など、現代の医療ニーズに対応した科目を学習します。また、各専門領域での実習を通じて、臨床での実践力を高めていきます。
特色ある実習プログラム
本校の実習プログラムは、労災病院グループとの連携を活かした特徴的な内容となっています。急性期から慢性期まで、様々な健康段階にある対象者の看護を経験できます。
産業保健の視点を持った労働衛生看護の実習も特徴的で、企業の健康管理部門での実習なども含まれています。実習指導は経験豊富な臨床指導者と教員が担当し、きめ細かな指導を受けることができます。
実習施設における学び
実習は主に労災病院グループの施設で行われます。高度医療を提供する急性期病院での実習では、手術前後の患者ケアや救急看護の実際を学びます。
回復期リハビリテーション病院では、患者さんの社会復帰に向けた支援について理解を深めます。地域医療支援病院での実習では、地域包括ケアシステムにおける看護師の役割について学びます。
実践力を高める統合実習
最終学年では、チーム医療の一員としての役割を学ぶ統合実習を行います。夜間実習や複数患者の受け持ちなど、より実践的な経験を通じて、就職後にスムーズに臨床現場に適応できる力を養います。また、看護研究の基礎を学び、根拠に基づいた看護実践について理解を深めます。
4. 就職支援とキャリア形成

本校では、学生一人ひとりの希望に沿ったキャリア実現を支援するため、充実した就職支援体制を整えています。早期からのキャリア教育と、きめ細かな個別サポートにより、高い就職率を維持しています。
体系的な就職支援プログラム
就職支援は1年次から段階的に行われます。1年次では自己分析やキャリアデザインの基礎を学び、2年次からは具体的な就職活動に向けた準備を始めます。3年次では個別面談を重ねながら、それぞれの希望に合った就職先の選択をサポートしています。
充実の就職実績データ
2024年度の就職実績では、就職希望者の98.5%が希望の職場に就職を果たしています。就職先の内訳として、労災病院グループへの就職が全体の60%を占めており、その他の総合病院が25%、大学病院が10%、診療所やその他の医療施設が5%となっています。
特に労災病院グループへの就職では、実習でのつながりを活かした採用も多く見られます。
卒業後のキャリア支援
卒業後も継続的なキャリア支援を行っています。専門看護師や認定看護師を目指す卒業生には、進学相談や専門的なアドバイスを提供しています。
また、定期的に開催される卒後研修会では、最新の医療知識や技術を学ぶ機会があります。卒業生同士のネットワークづくりにも力を入れており、年に一度の同窓会では情報交換や交流の場を設けています。
キャリアアップの具体例
本校の卒業生は、臨床現場での経験を積みながら、様々な形でキャリアを発展させています。例えば、救急看護認定看護師として救急医療の最前線で活躍する卒業生や、産業保健師として企業の健康管理部門でリーダーシップを発揮している卒業生もいます。
また、教育者として看護学校で後進の育成に携わる卒業生も増えています。
継続教育プログラム
現役の看護師として働きながらスキルアップを目指す卒業生向けに、様々な継続教育プログラムを提供しています。
週末や夜間に開催される専門的な講座や、オンラインでの学習機会を通じて、最新の医療知識や技術を習得することができます。また、海外研修プログラムを通じて、国際的な視野を広げることも可能です。
5. 学費・奨学金情報

本校では、経済的な面でも学生をサポートするため、様々な制度を用意しています。入学から卒業までにかかる費用を計画的に準備できるよう、詳しい情報を提供いたします。
学費の詳細と納入時期
2025年度入学生の初年度納入金は総額で105万円となります。これには入学金20万円、授業料60万円、実習費15万円、施設設備費10万円が含まれています。
2年次以降は入学金を除く90万円が年間の学費となります。学費の納入は年2回に分けて行うことができ、前期と後期でそれぞれ45万円ずつの納入となります。
充実した経済支援制度
本校では独自の奨学金制度を設けており、成績優秀者には年間30万円の給付型奨学金を支給しています。また、遠方からの入学者向けに月額3万円の生活支援制度も用意しています。
さらに、切迫時には緊急支援奨学金の申請が可能です。これらの制度に加えて、日本学生支援機構の奨学金や都道府県の修学資金など、外部の奨学金制度も積極的に活用できます。
きめ細かな支援体制
入学前から個別の経済相談に応じており、それぞれの状況に合わせた支援プランを提案しています。学費の分割納付制度では、最大12回までの分割が可能で、実質的な月々の負担を軽減することができます。また、兄弟姉妹が同時に在学する場合には、授業料の一部を減免する制度も設けています。
6. 在校生・卒業生の声
在校生の体験談
在校生の声A:高校からの進学者として
一年生の山田美咲です。私は高校で進路を考える際、実践的な看護技術を学べる環境を重視して本校を選びました。入学してまず驚いたのは、最新のシミュレーション設備が整っていることです。
基礎看護技術の授業では、高機能な患者シミュレーターを使用した実践的な演習が行われ、緊張感を持って臨むことができます。また、先生方の指導も丁寧で、分からないことがあれば放課後も個別に指導していただけます。
クラスメイトとも切磋琢磨しながら、充実した毎日を送っています。コロナ禍での入学でしたが、オンライン学習と対面授業を効果的に組み合わせた学習環境が整備されており、学習の質を落とすことなく進めることができています。
在校生の声B:実習を経験して
二年生の佐藤健一です。現在、成人看護学実習の真っ只中にあり、日々新しい発見と課題に向き合っています。実習では、これまで座学で学んだ知識を実践の場で活用する機会が多く、理論と実践の結びつきを実感しています。
特に印象的だったのは、患者さんとのコミュニケーションの重要性です。教科書だけでは学べない、一人ひとりの患者さんに合わせた対応の仕方を、実習指導者の先生から丁寧に教えていただいています。
また、カンファレンスでは他の学生との意見交換を通じて、多角的な視点で看護を考える力が養われていると感じています。実習期間中の体調管理も含め、担当教員のサポートが心強い存在となっています。
在校生の声C:社会人経験を経て
三年生の鈴木由美子です。営業職として10年間働いた後、看護師を目指して入学しました。当初は年齢差や学習面での不安がありましたが、教員の方々の手厚いサポートと、同じ社会人経験者の仲間との出会いにより、充実した学生生活を送ることができています。
特に基礎医学の学習では、社会人としての経験を活かしながら、効率的な学習方法を見つけることができました。
また、前職でのコミュニケーション能力が実習でも活きており、患者さんやスタッフとの関係構築にも自信が持てるようになってきました。年齢を重ねてからの挑戦でしたが、新たな夢に向かって学べる環境に感謝しています。
在校生の声D:寮生活の経験から
一年生の中村香織です。地方から上京して入学し、現在は学生寮で生活しています。寮生活では、同じ目標を持つ仲間との共同生活を通じて、互いに支え合いながら学習に取り組むことができています。
朝は一緒に登校し、夜は自習室で勉強会を開くなど、充実した環境で過ごしています。寮費も手頃で、朝夕の食事付きなので、学業に専念できる環境が整っています。
また、寮母さんが常駐しており、生活面でのサポートも充実しています。地元を離れての一人暮らしに不安もありましたが、寮での生活を通じて、自立心と協調性を身につけることができています。
在校生の声E:クラブ活動との両立
二年生の高橋美樹です。私は看護研究会に所属しながら、学業との両立を図っています。看護研究会では、先生方のご指導のもと、最新の看護研究に触れる機会があり、視野を広げることができています。
また、上級生からの学習アドバイスも受けられ、効率的な学習方法を身につけることができました。定期的に開催される研究発表会では、プレゼンテーション能力も養うことができます。
部活動を通じて得られる経験は、将来の看護師としての成長にもつながると感じています。学業との両立は大変ですが、時間管理の大切さを学ぶ良い機会となっています。
在校生の声F:国際交流プログラムを経験して
二年生の加藤春菜です。本校の国際交流プログラムに参加し、オンラインで海外の看護学生との交流を行っています。異なる文化背景を持つ学生との意見交換を通じて、グローバルな視点で看護を考える機会を得ることができました。
特に印象的だったのは、各国の医療システムの違いや、看護師の役割の多様性についての学びです。また、英語でのコミュニケーション能力も向上し、将来的な可能性も広がったと感じています。このプログラムでの経験は、看護の普遍的な価値と文化的な多様性について深く考えるきっかけとなりました。
在校生の声G:オンライン学習の活用
一年生の渡辺太郎です。本校のICT環境の充実さに驚いています。タブレット端末が貸与され、電子教科書やオンライン学習システムを活用することで、効率的な学習が可能になっています。特に基礎医学の学習では、3D解剖モデルを使用した学習が非常に効果的です。
また、オンデマンド配信される講義は、自分のペースで繰り返し学習できる点が魅力です。授業で使用するスライドや資料もすべてデジタル化されており、復習がしやすい環境が整っています。ICTツールの活用により、学習効率が大幅に向上したと実感しています。
在校生の声H:就職活動を控えて
三年生の木村直子です。就職活動に向けて、キャリアサポートセンターの支援を受けています。個別面談では、自己分析から具体的な就職先の選択まで、丁寧なアドバイスをいただいています。
また、実習での経験を活かした就職活動のアプローチ方法も学ぶことができ、自信を持って準備を進めることができています。
特に労災病院グループへの就職を考えている私にとって、実習での経験が大きな強みとなっています。就職ガイダンスや、卒業生との交流会などのイベントも充実しており、将来のキャリアプランを具体的に描くことができています。
在校生の声I:学校行事への参加
二年生の小林美咲です。学園祭の実行委員として活動する中で、リーダーシップとチームワークの大切さを学んでいます。企画から運営まで、学生主体で取り組むことで、責任感と達成感を味わうことができました。
特に印象的だったのは、医療系の展示企画を通じて、一般の方々に看護の魅力を伝える機会を得たことです。また、球技大会やクリスマス会などの行事を通じて、学年を越えた交流も深めることができています。これらの経験は、将来チーム医療の一員として働く上での貴重な学びとなっています。
在校生の声J:奨学金制度の活用
一年生の田中裕子です。本校の独自の奨学金制度を利用して学業に励んでいます。経済面での不安がありましたが、給付型奨学金の支援により、学業に専念できる環境が整っています。また、授業料の分割納付制度も利用しており、計画的な学費の納入が可能となっています。
奨学金の説明会では、利用可能な制度について詳しい情報提供があり、自分に合った支援制度を選択することができました。経済的な支援体制が充実していることは、学業への集中力を高める大きな要因となっています。
卒業生からのメッセージ
卒業生の活躍
卒業生の声A:急性期病院での活躍
労災病院の救急外来で勤務して3年目の山本健一です。本校での学びは、現場での実践に直結するものでした。特に実習での経験は、急性期医療の現場で大いに活きています。シミュレーション教育で培った基礎的な技術力は、緊急時の対応にも冷静に取り組める自信につながっています。
また、在学中に学んだチーム医療の考え方は、多職種との連携が必要な現場で非常に重要です。本校の教育方針である「実践力のある看護師の育成」は、まさに現場のニーズに応えるものだと実感しています。後輩たちには、積極的に実習に取り組んでほしいと思います。
卒業生の声B:認定看護師としての道
がん化学療法看護認定看護師として活躍する中島優子です。本校での基礎教育が、専門性を高める上での確かな土台となりました。特に研究的視点を養う教育は、認定看護師の資格取得にも大きく貢献しました。
本校の卒後教育支援も充実しており、認定看護師を目指す際には、進学相談や情報提供など、きめ細かなサポートを受けることができました。現在は、がん患者さんの療養生活の質の向上に貢献できるよう、日々研鑽を重ねています。専門性を高めることで、看護の奥深さを実感する日々を送っています。
卒業生の声C:訪問看護ステーションでの経験
訪問看護ステーションを開設して5年目の伊藤由美です。本校で学んだ在宅看護の基礎知識は、現在の仕事の核となっています。特に実習で経験した多様な患者さんとの関わりは、在宅での看護実践に大きく活きています。
また、労働衛生看護の視点は、在宅で療養する方々の生活環境を整える上で重要な指針となっています。経営者としての視点も必要な現在、本校で培った問題解決能力や、多職種との連携能力が役立っています。地域に根ざした看護を実践できることにやりがいを感じる毎日です。
卒業生の声D:教育者としての歩み
看護専門学校の教員として5年目を迎える斉藤明子です。本校での学生生活は、教育者としての原点となっています。特に印象的だったのは、教員の方々の熱心な指導姿勢です。その経験は、現在の教育実践に大きな影響を与えています。
また、本校の実習プログラムの構造的な学びは、教育カリキュラムを考える上での参考となっています。現在は、次世代の看護師育成に携わる立場として、本校で学んだ「実践と理論の融合」を大切にした教育を心がけています。教え子たちの成長を見守ることができる喜びを感じています。
卒業生の声E:産業保健師への転身
大手企業の健康管理室で産業保健師として活躍する村上直子です。本校で学んだ労働衛生看護の知識は、現在の業務の基盤となっています。特に実習で経験した企業の健康管理部門での実習は、キャリアの方向性を考える上で大きな影響を与えました。
現在は、従業員の健康管理から職場環境の改善まで、幅広い業務に携わっています。本校での学びは、産業保健の専門家として活動する上での確かな土台となっています。働く人々の健康を支える立場として、やりがいのある日々を送っています。
卒業生の声F:海外での活躍
シンガポールの総合病院で勤務して4年目の藤田雄一です。本校での国際交流プログラムの経験が、海外での就職を決意するきっかけとなりました。基礎的な看護技術はもちろん、異文化理解の視点も含めた教育は、グローバルな環境での適応に大きく役立っています。
特に、本校で培ったコミュニケーション能力は、多国籍のスタッフや患者さんとの関係構築に不可欠です。海外で働く中で、日本の看護教育の質の高さを実感しています。国際的な視野を持った看護師として、さらなる成長を目指しています。
卒業生の声G:研究者としての道
看護大学の研究者として活動する岡田真理です。本校での看護研究の基礎教育が、研究者としての道を選ぶきっかけとなりました。特に印象的だったのは、研究的視点で看護実践を捉える姿勢を学べたことです。
卒業研究では、指導教員から丁寧な指導を受け、研究手法の基礎を身につけることができました。現在は、臨床現場での課題を研究テーマとして取り組んでおり、実践に根ざした研究活動を展開しています。
本校で培った探究心は、研究者としての活動の原動力となっています。次世代の看護研究者の育成にも力を入れています。
卒業生の声H:災害看護の最前線で
災害医療センターで災害支援ナースとして活動する野田健司です。本校での災害看護の学びは、現在の専門性を高める基盤となりました。特に印象的だったのは、災害時のトリアージ演習や、多職種連携訓練です。
実践的な演習を通じて、緊急時の判断力と対応力を養うことができました。現在は、災害発生時の医療支援活動に携わり、平時には災害への備えとして、地域との連携強化に取り組んでいます。本校で学んだ「臨機応変な対応力」は、災害医療の現場で大きな強みとなっています。
卒業生の声I:小児専門病院での活躍
小児専門病院の小児救急看護認定看護師として働く松本さやかです。本校での小児看護学実習での経験が、現在の専門性を選択する決め手となりました。特に印象的だったのは、子どもと家族への包括的な支援の重要性を学べたことです。
実習では、年齢に応じたコミュニケーション方法や、家族支援の実際を学ぶことができました。現在は、重症度の高い小児患者の看護に携わり、家族を含めた支援を実践しています。本校での学びは、専門性を高める上での確かな土台となっています。
卒業生の声J:国際医療支援の現場から
国際医療支援NGOで活動する山口恵子です。本校での国際看護の学びが、現在の活動につながっています。特に印象的だったのは、グローバルヘルスの視点から看護を考える機会が多かったことです。
また、異文化理解やコミュニケーション能力の育成にも力を入れた教育は、国際支援の現場で大きな強みとなっています。現在は、発展途上国での医療支援活動に従事し、現地の医療従事者への教育支援も行っています。本校で培った「看護の普遍的価値」を大切にしながら、活動を続けています。
7. おしえてカンゴさん!よくある質問Q&A

Q1: 社会人入試の年齢制限について教えてください
社会人入試では年齢制限を設けていないため、20代から40代まで幅広い年齢層の方が受験されています。実際に昨年度は22歳から45歳までの方が入学されました。社会人の方には、これまでの職務経験を活かした学習アプローチが可能で、教員による個別指導体制も充実しています。
また、働きながら学ぶ方のために、夜間部での学習も検討しており、2026年度からの開設を予定しています。仕事との両立に不安がある方には、入学前の個別相談で具体的なアドバイスを提供していますので、ぜひご活用ください。
Q2: 入試の選考方法と試験内容を詳しく教えてください
入試では、一般入試、推薦入試、社会人特別選抜の3つの区分を設けています。一般入試では国語、数学、英語の3教科の筆記試験と面接を実施します。特に医療系の文章読解や、基礎的な数学力を重視しています。
推薦入試では、調査書と面接に加えて、小論文試験を課しています。社会人特別選抜では、職務経験を踏まえた小論文と面接を中心に選考を行います。面接試験では、医療や看護に対する関心度、コミュニケーション能力、将来のビジョンなどについて質問させていただきます。
学習環境とサポート体制
Q3: 図書館やシミュレーション施設の利用について教えてください
図書館には看護・医学分野の専門書が12,000冊以上所蔵されており、電子ジャーナルも24時間利用可能です。シミュレーション施設では、最新の医療機器や高機能患者模型を使用した実践的な演習が行えます。
特に基礎看護技術の習得には力を入れており、放課後も自主練習ができます。また、定期的に開催される特別講座では、現役の医療従事者による実践的な指導も受けられます。施設はすべて学生証で入退室管理されており、セキュリティ面でも安心です。
Q4: 教員による学習支援体制について具体的に教えてください
クラス担任制を採用しており、各学年2名の担任教員が学習面から生活面まできめ細かなサポートを行っています。定期的な個別面談では、学習の進捗状況や課題の確認、進路相談などを行います。また、看護技術の習得に不安がある場合は、放課後に個別指導を受けることができます。
国家試験対策では、弱点分野の把握と克服のための個別指導プログラムを実施しており、一人ひとりの学習状況に合わせた支援を提供しています。
実習について
Q5: 臨地実習の具体的な内容と期間を教えてください
臨地実習は2年次から本格的に始まり、総時間数は1,035時間に及びます。基礎看護学実習から始まり、成人看護学実習、老年看護学実習、小児看護学実習、母性看護学実習、精神看護学実習、在宅看護論実習と段階的に進みます。
実習先は主に労災病院グループの施設となりますが、地域の診療所や訪問看護ステーションでの実習も含まれています。各実習では、経験豊富な臨床指導者と教員が連携して指導を行い、実践的な看護技術の習得をサポートします。
学生生活について
Q6: 通学方法と寮生活について詳しく教えてください
最寄り駅から徒歩15分の場所に立地しており、朝夕の時間帯にはスクールバスも運行しています。遠方からの入学生のために、セキュリティを完備した女子寮を用意しています。寮費は月額3万円で、朝夕2食付きのプランも選択可能です。
寮は全室個室で、共用スペースにはキッチンやランドリールーム、談話室を完備しています。一人暮らしを希望する学生には、学校指定の不動産業者を通じて、安全で通学に便利なアパートやマンションの紹介も行っています。
経済的支援について
Q7: 奨学金制度と経済的支援の詳細を教えてください
本校独自の奨学金制度として、成績優秀者向けの給付型奨学金(年間30万円)を設けています。また、日本学生支援機構の奨学金も利用可能で、第一種(無利子)、第二種(有利子)ともに申請できます。授業料の分割納付制度では、年間の学費を最大12回まで分割して納入することができます。
さらに、家計急変時には緊急支援奨学金の申請も可能です。入学前から経済面での相談に応じており、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを提案しています。
就職支援について
Q8: 就職支援体制と進路先について教えてください
キャリアサポートセンターでは、1年次からキャリア教育を実施し、個別面談を通じて希望の進路実現をサポートしています。労災病院グループへの就職希望者には、実習での経験を活かした就職活動が可能です。
その他の医療機関への就職も積極的に支援しており、昨年度の就職率は98.5%を達成しました。卒業後も継続的なキャリア支援を行っており、専門看護師や認定看護師を目指す卒業生には、進学相談や専門的なアドバイスを提供しています。
学習内容について
Q9: 専門科目の学習内容と進め方について教えてください
1年次では基礎医学(解剖学、生理学、病理学など)と基礎看護技術を中心に学習します。2年次からは各専門領域(成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学など)の講義と実習が始まります。
3年次では、これまでの学びを統合し、より実践的な看護技術の習得を目指します。各科目では、グループワークやシミュレーション演習を取り入れた参加型の授業を展開しており、主体的な学びを重視しています。
Q10: 国家試験対策の具体的な支援内容を教えてください
国家試験対策は1年次から計画的に実施しています。2年次からは定期的な模擬試験を実施し、弱点分野の把握と克服に努めます。3年次には特別講座を開講し、試験直前期には集中的な補習も行います。
また、個別指導では一人ひとりの学習進度に合わせた支援を提供し、必要に応じて学習計画の見直しも行います。昨年度の国家試験合格率は98.2%を達成しており、高い合格率を維持しています。
入学後の生活について
Q11: クラス運営と学校行事について教えてください
1学年80名を2クラスに分けて運営しており、クラスごとに担任教員を配置しています。学校行事としては、4月のオリエンテーション合宿、6月の看護の日イベント、10月の学園祭、12月の球技大会などを実施しています。
また、看護研究会やボランティアサークルなどの課外活動も活発で、学年を超えた交流の機会となっています。行事の企画・運営は学生主体で行われ、リーダーシップやチームワークを養う機会となっています。
Q12: 実習期間中の生活支援について教えてください
実習期間中は、実習グループごとに担当教員が付き、学習面だけでなく生活面でもサポートを行います。実習先への通学は、学校が手配する送迎バスを利用することができます。実習中の昼食は実習先の職員食堂が利用可能で、実習衣のクリーニングサービスも提供しています。
体調管理も重要なため、保健室では実習期間中の健康相談も随時受け付けており、必要に応じて実習スケジュールの調整も行います。
サポート体制について
Q13: メンタルヘルスケアの体制について教えてください
学生相談室には専門のカウンセラーが常駐しており、学業や実習、進路、対人関係など、様々な悩みの相談に応じています。相談は予約制で、プライバシーは厳重に保護されます。また、定期的なストレスチェックを実施し、必要に応じて早期の支援介入を行います。
実習期間中は特にストレスが高まりやすいため、実習担当教員と学生相談室が連携して、きめ細かなケアを提供しています。メンタルヘルス講座も定期的に開催しています。
Q14: 障害のある学生への支援体制について教えてください
障害のある学生の受け入れにあたっては、入学前から個別相談を行い、必要な支援内容を確認します。授業では座席位置の配慮や資料の拡大提供、ノートテイクサポートなど、個々の状況に応じた支援を行います。
実習においても、実習先との事前調整を行い、適切な環境整備を図ります。また、バリアフリー化された校舎内では、エレベーターや多目的トイレを完備し、安心して学習できる環境を整えています。定期的な面談で支援内容の見直しも行います。
卒業後のキャリアについて
Q15: 卒業後のキャリアアップ支援について教えてください
卒業後も継続的なキャリア支援を提供しています。専門看護師や認定看護師を目指す卒業生には、資格取得に向けた情報提供や進学相談を行います。また、定期的に開催される卒後研修会では、最新の医療知識や技術を学ぶ機会を設けています。
海外研修プログラムへの参加機会もあり、グローバルな視点での看護実践を学ぶことができます。同窓会ネットワークを通じた情報交換や交流の場も定期的に設けています。
Q16: 認定看護師取得のサポート体制について教えてください
認定看護師を目指す卒業生向けに、専門的な支援プログラムを用意しています。資格取得に向けた学習相談や、受験対策講座の開催、実務経験に関するアドバイスなど、きめ細かなサポートを提供します。
また、現役の認定看護師による講演会や相談会も定期的に開催し、実践的なアドバイスを得る機会を設けています。労災病院グループとの連携により、認定看護師教育課程への進学支援も行っており、実績も豊富です。
その他の支援体制について
Q17: 留学生サポート体制について教えてください
留学生の受け入れにあたっては、入学前から日本語支援や生活支援を含めた総合的なサポートを提供しています。日本語教育の専門スタッフによる個別指導や、日本語での医療用語学習支援も行います。また、在留資格に関する手続きのサポートや、住居の紹介、生活習慣の適応支援なども実施しています。
チューター制度を導入しており、日本人学生との交流を通じて、スムーズな学校生活への適応を支援します。奨学金情報の提供も積極的に行っています。
Q18: 研究活動のサポート体制について教えてください
3年次には看護研究の基礎を学び、実践的な研究手法を習得します。研究テーマの選定から論文作成まで、指導教員が丁寧にサポートします。図書館では文献検索のガイダンスを実施し、研究に必要な資料収集をサポートします。
また、学内の研究発表会では、専門家からの助言を受ける機会もあります。優れた研究は学会での発表を推奨しており、発表準備のサポートも行っています。研究費の助成制度も設けています。
施設・設備について
Q19: 実習室の設備と利用方法について教えてください
実習室には最新の医療機器や高機能シミュレーターを完備しています。基礎看護実習室、成人看護実習室、母性・小児看護実習室などを用途別に整備し、それぞれの実習室で実践的な技術習得が可能です。
実習室は放課後も20時まで利用可能で、予約制で自主練習の時間を確保できます。各実習室には指導教員が常駐しており、技術指導や質問への対応を行っています。また、実習室には電子カルテシステムも導入されており、実際の医療現場を想定した演習が可能となっています。
Q20: ICT環境と情報支援について教えてください
校内全域で高速Wi-Fiを完備し、学生一人ひとりにタブレット端末を貸与しています。電子教科書やオンライン学習システムを導入しており、時間や場所を問わず学習できる環境を整えています。また、情報処理室にはパソコンを50台設置し、レポート作成や文献検索に活用できます。
医療情報システムの基礎も学べる環境を整備しており、電子カルテの操作訓練も可能です。情報セキュリティ教育も実施し、医療情報の取り扱いについて実践的に学ぶ機会を提供しています。
8. 看護師への第一歩を支える学び舎として
労災看護専門学校は、設立以来4000名を超える優秀な看護師を医療現場へ送り出してきました。その実績を持つ教育機関として、確固たる地位を築いてきました。
特に労働衛生分野における専門的な知識と技術を持つ看護師の育成において、他に類を見ない教育プログラムを展開しています。労災病院グループとの密接な連携により実現される充実した実習環境は、実践的な看護技術の習得を可能にしています。
教育システムの特色と実績
実践的な学習環境の整備
最新のシミュレーション設備を完備した実習室では、高機能患者模型を使用した実践的な演習が可能です。電子カルテシステムを導入した演習室では、実際の医療現場さながらの環境で学習を進めることができます。
図書室には12,000冊を超える専門書が所蔵され、24時間利用可能なオンラインデータベースにより、学生の自主的な学習をサポートしています。
段階的な実習プログラム
1年次から3年次まで、体系的に組み立てられた実習プログラムにより、確実な技術の習得が可能となっています。基礎看護学実習から始まり、各専門領域の実習へと段階的に進む中で、実践的な看護技術と判断力を養うことができます。
特に労災病院グループの施設における実習では、急性期から慢性期まで、幅広い看護実践を経験することができます。
充実した学生支援体制
経済的支援の充実
独自の給付型奨学金制度や授業料の分割納付制度など、学生の経済的負担を軽減するための様々な支援制度を整備しています。特に成績優秀者向けの給付型奨学金は年間30万円を支給し、学業に専念できる環境を提供しています。また、遠方からの入学者向けには、月額3万円の生活支援制度も用意されています。
キャリア支援の体制
就職支援センターでは、1年次からキャリア教育を実施し、個別面談を通じて将来の進路実現をサポートしています。特に労災病院グループへの就職を希望する学生に対しては、実習での経験を活かした就職活動が可能となります。
2024年度の就職実績では、就職希望者の98.5%が希望の職場に就職を果たしており、高い就職率を維持しています。
国際性を重視した教育展開
グローバルな視点の育成
国際交流プログラムを通じて、グローバルな視点での看護を学ぶ機会を提供しています。海外の看護学生とのオンライン交流や、国際医療支援の現場で活躍する卒業生による特別講義など、国際的な視野を広げるためのプログラムを実施しています。
卒業後のキャリア形成支援
継続的な学習支援
卒業後も継続的な学習支援を提供しており、専門看護師や認定看護師を目指す卒業生には、資格取得に向けた情報提供や進学相談を行っています。定期的に開催される卒後研修会では、最新の医療知識や技術を学ぶ機会を設けています。
多様なキャリアパスの実現
本校の卒業生は、臨床現場での第一線の看護師として活躍するだけでなく、専門看護師、認定看護師、教育者、研究者など、様々な分野で活躍しています。特に労働衛生分野では、企業の健康管理部門で活躍する産業保健師として、独自の専門性を発揮している卒業生も多いです。
次世代の医療を見据えた展望
最新技術への対応
医療技術の進歩に対応するため、常に最新の医療機器や教育設備の導入を行っています。ICT教育の充実により、電子カルテシステムの操作や医療情報の管理など、現代の医療現場で必要とされるスキルの習得を可能にしています。
研究マインドの育成
3年次には看護研究の基礎を学び、エビデンスに基づいた看護実践の重要性を理解する機会を設けています。研究的視点を持った看護師の育成により、医療の質の向上に貢献できる人材を輩出することを目指しています。
地域医療への貢献
地域との連携強化
地域医療支援病院での実習を通じて、地域包括ケアシステムにおける看護師の役割について学ぶ機会を提供しています。また、地域の健康イベントへの参加や、高齢者施設でのボランティア活動など、地域との連携を深める取り組みを行っています。
未来を見据えた教育理念の実現
本校は「人間性豊かで実践力のある看護師の育成」という教育理念のもと、確かな専門知識と技術、豊かな人間性と倫理観、地域医療への貢献意識を持った看護師の育成を目指しています。この理念は、日々進化する医療現場においても普遍的な価値を持ち続けています。
今後も本校は、変化する医療ニーズに対応しながら、次世代の医療を担う看護師の育成に尽力していきます。充実した実習環境と手厚い学習支援により、確かな実践力を持つ看護師を育成し、医療の質の向上に貢献していきます。
そして、労働衛生看護の分野における独自の強みを活かしながら、卒業後のキャリア形成においても幅広い選択肢を提供していきます。
看護師を目指す皆様にとって、本校での学びが確かな一歩となることを願っています。そして、本校で学んだ看護の精神が、未来の医療を支える力となることを確信しています。
まとめ
労災看護専門学校は、1975年の設立以来、労働衛生分野に特化した看護教育を提供し、実績ある教育機関です。
充実した実習環境と経験豊富な教員陣による実践的な指導が特徴で、特に労災病院グループとの密接な連携により、最新の医療現場で求められる知識と技術を習得できる環境が整っています。
看護師としてのキャリアをさらに詳しく知りたい方は、「はたらく看護師さん」をご覧ください。現役看護師の声や、様々な分野で活躍する先輩たちのキャリアストーリー、より詳しい学校情報など、看護師を目指す方に役立つ情報が満載です。
▼はたらく看護師さん [はたらく看護師さんの最新コラムはこちら]
参考文献
- 労災看護専門学校学則
- 厚生労働省「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」
- 日本看護協会「看護教育制度について」