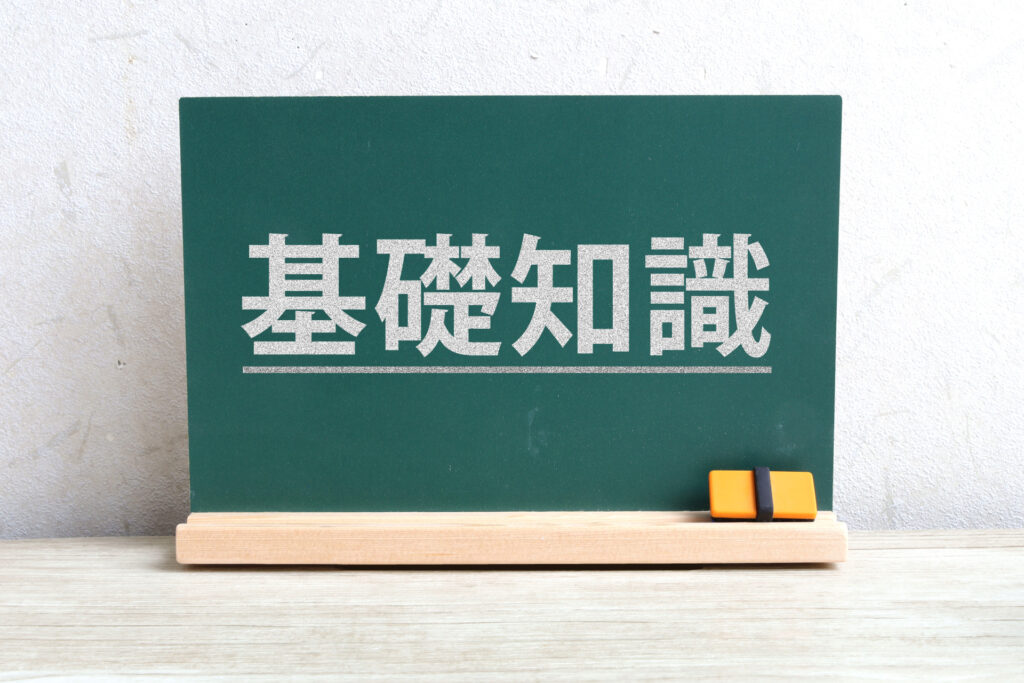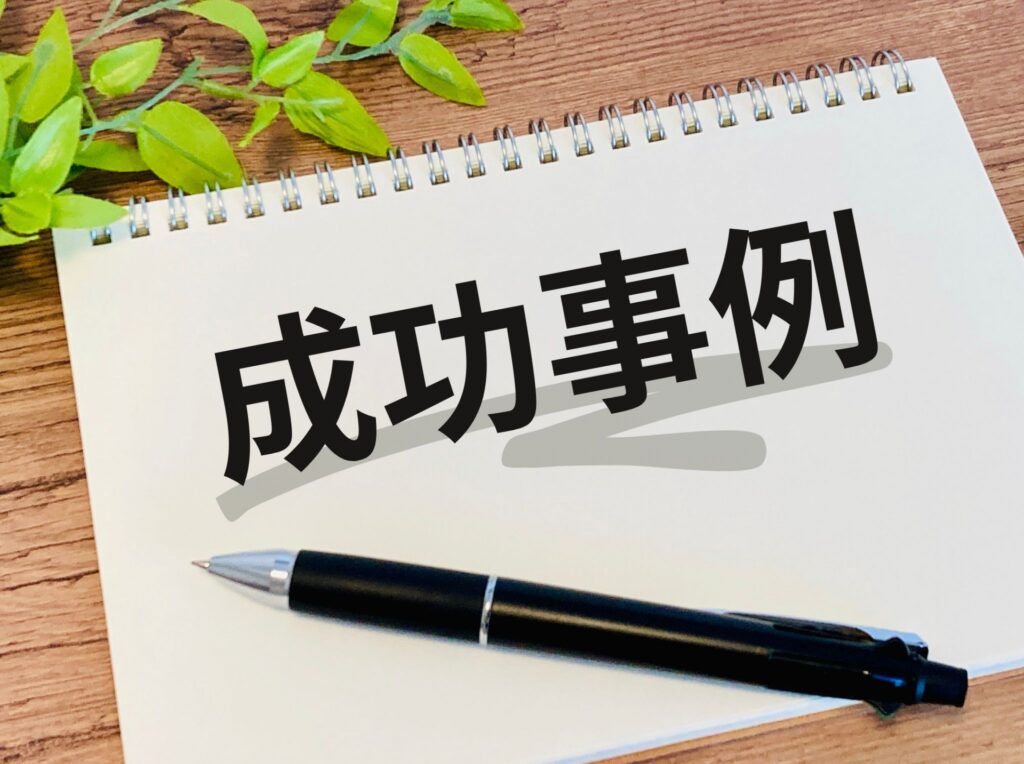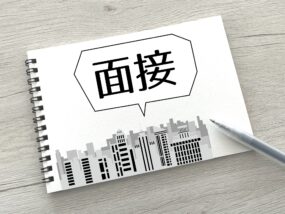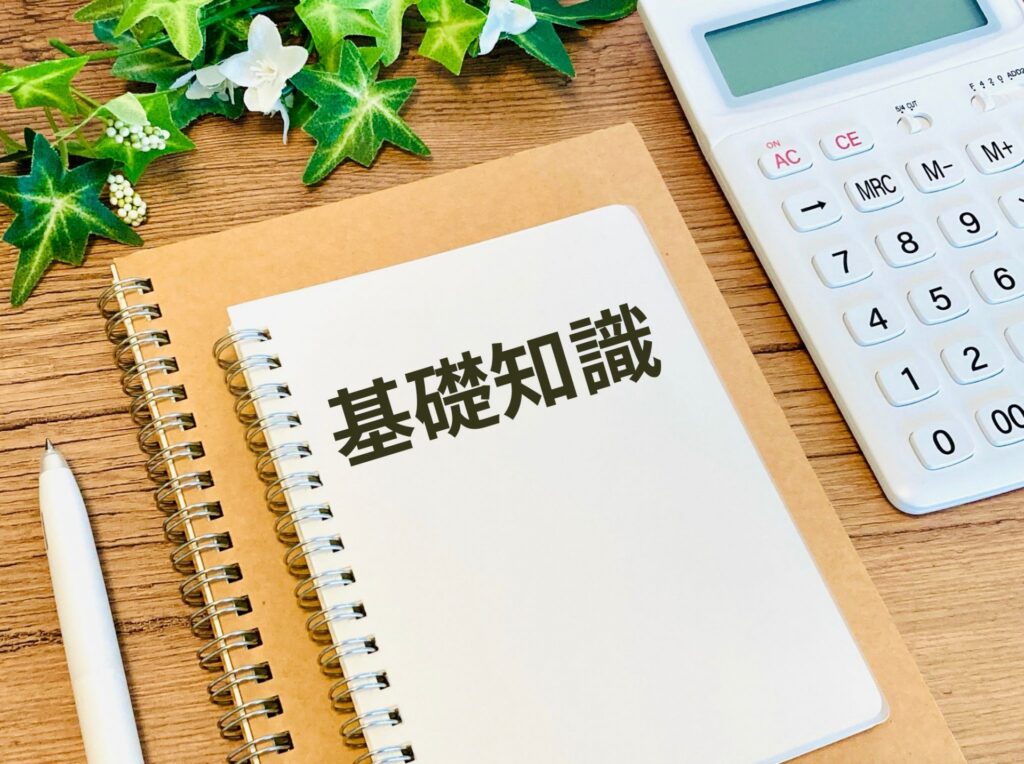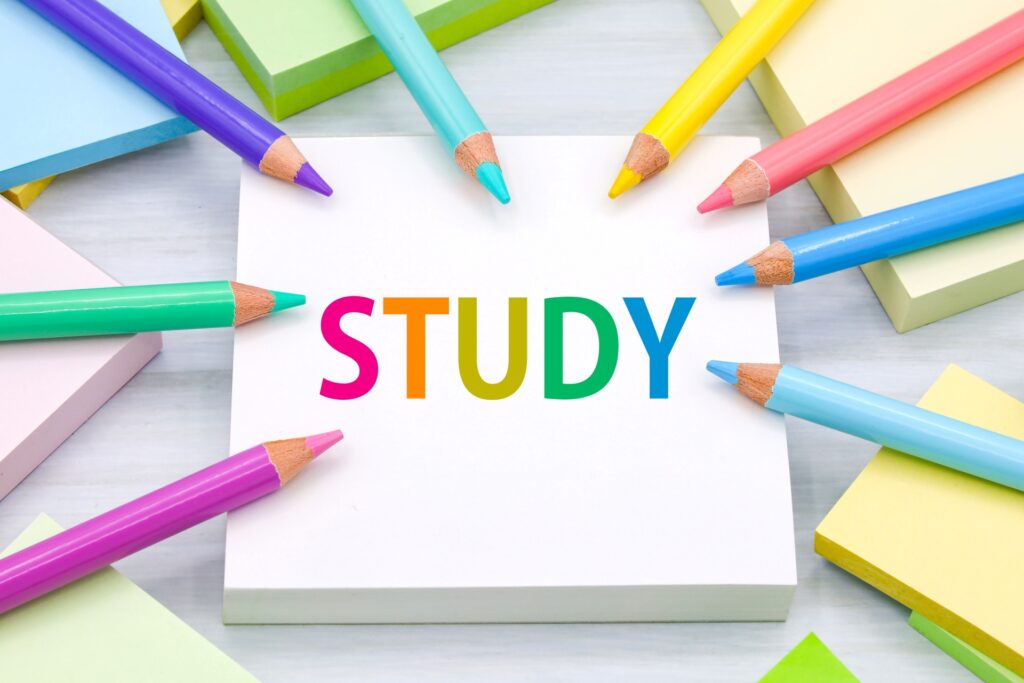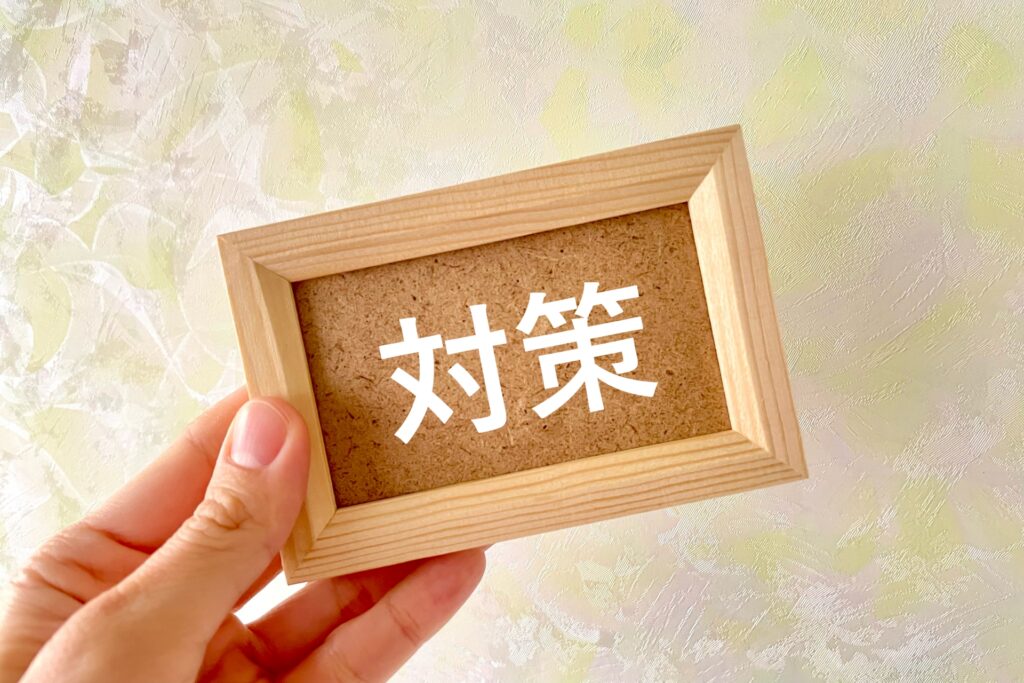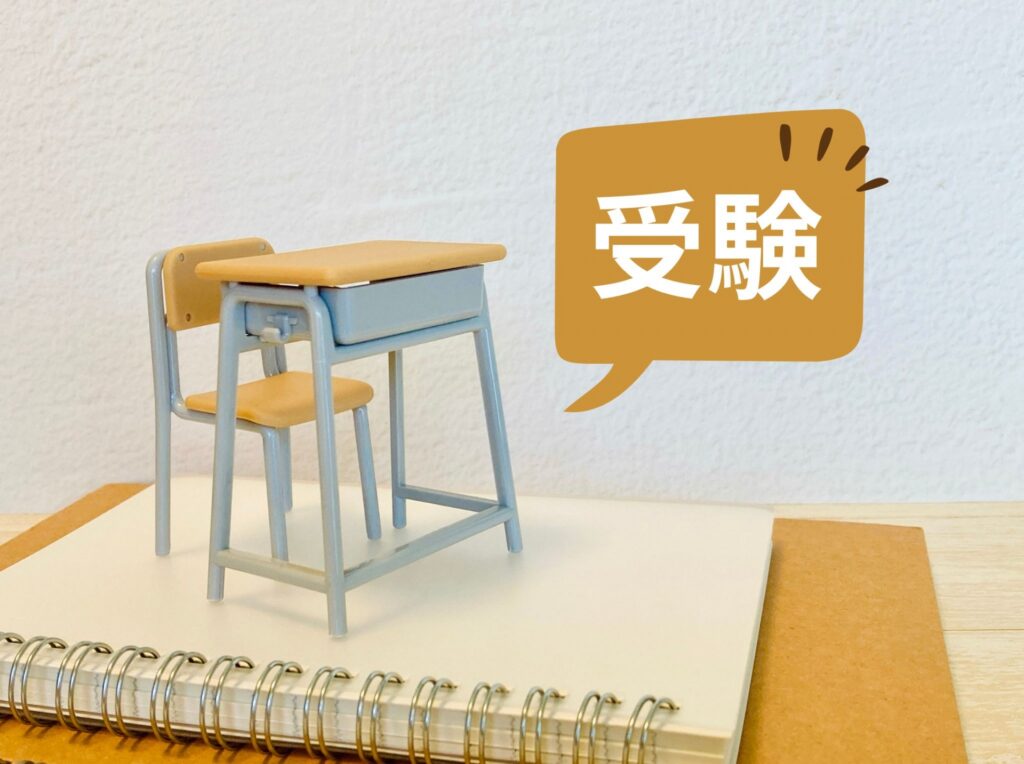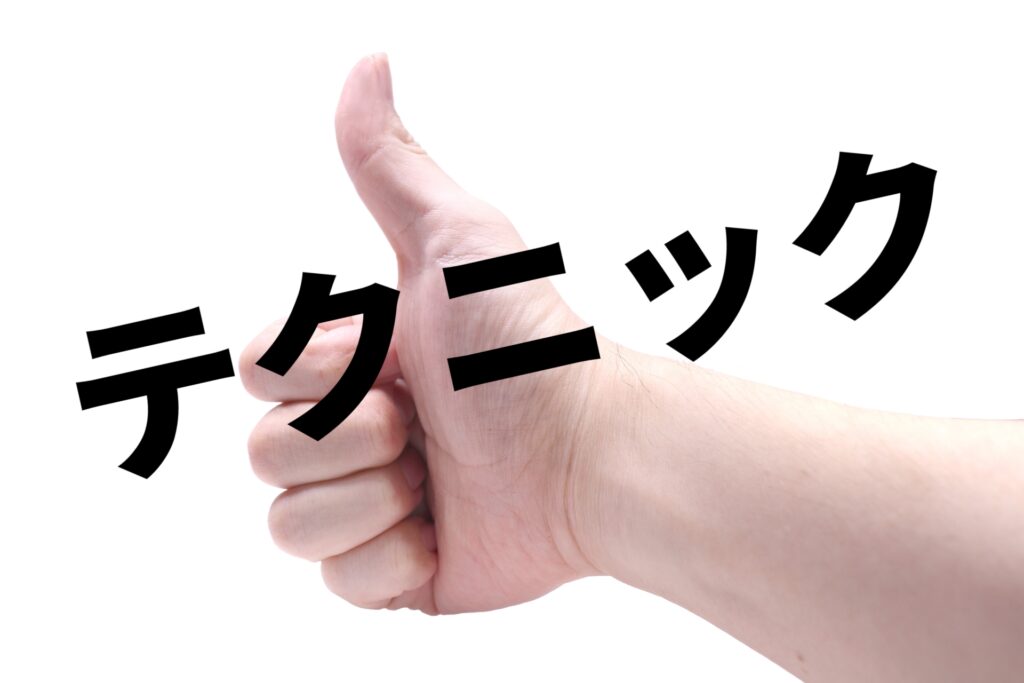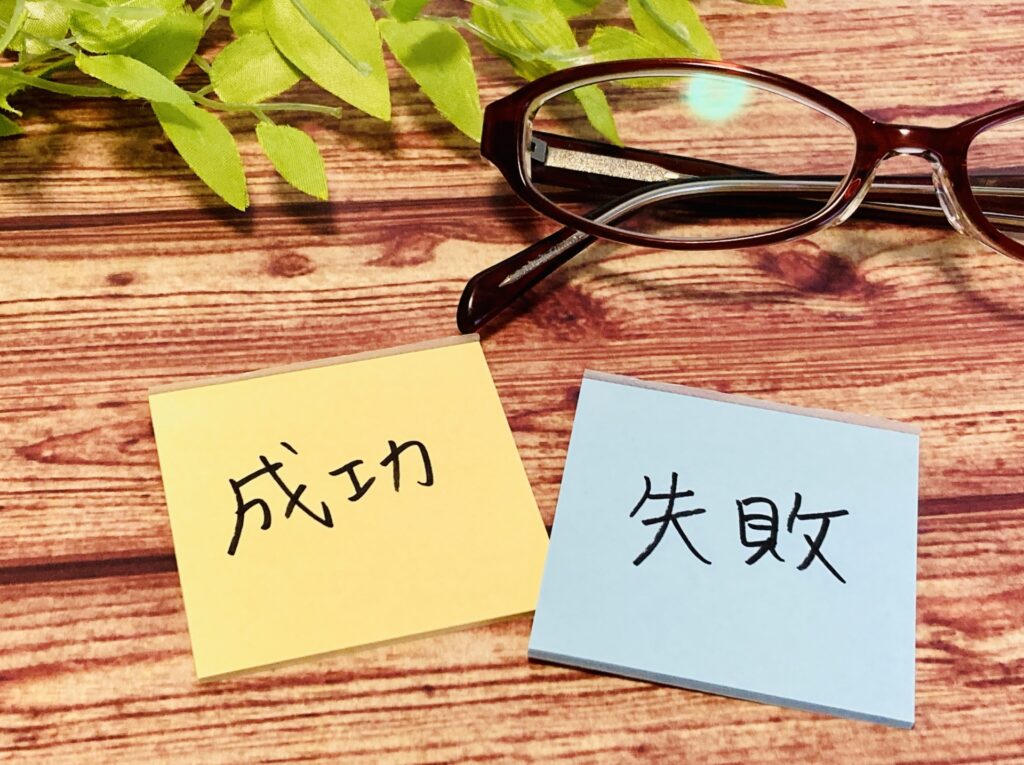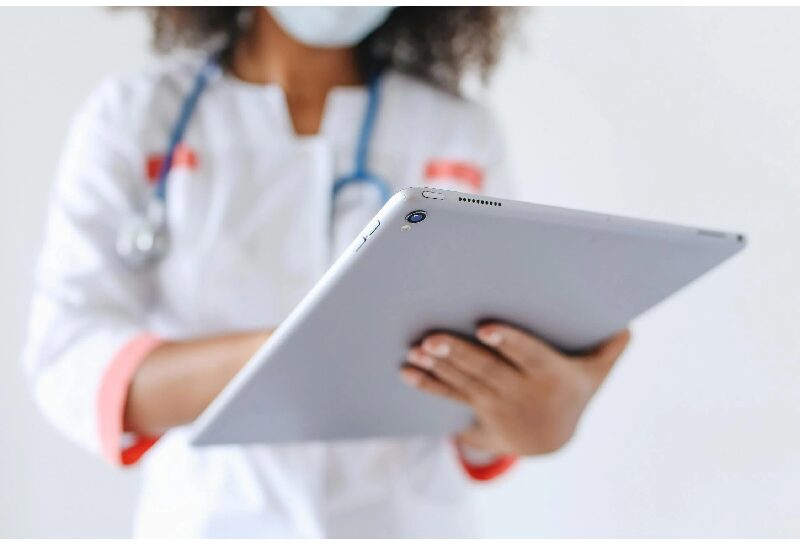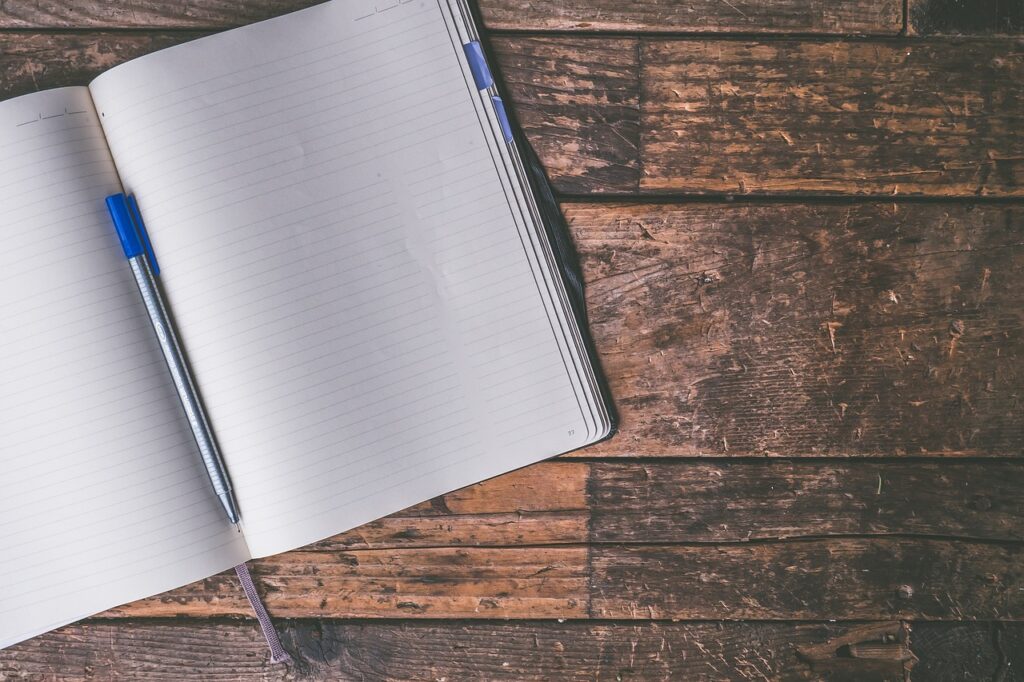鳥取県の看護教育を牽引する鳥取看護専門学校の特徴と受験対策について、詳しくご紹介します。本校は1952年の設立以来、確かな技術と豊かな人間性を備えた看護師を多数輩出してきました。
充実した実習環境と手厚い就職支援体制を備え、地域医療に貢献できる看護師の育成に力を入れています。この記事では、入試情報から学校生活、就職状況まで、受験生の皆さんに必要な情報を徹底的に解説します。
この記事で分かること
- 教育理念・特徴・施設設備と充実のカリキュラム・実習内容
- 2025年度入試情報と受験対策、学費・奨学金制度
- 就職状況と手厚い就職支援体制の詳細
この記事を読んでほしい人
・看護師を目指す受験生と地域医療に貢献したい方
・充実した実習環境で確かな看護技術を習得したい方
・就職支援と学費サポートを活用したい方
鳥取看護専門学校の学校情報と特徴

鳥取看護専門学校は、1952年の創立以来、地域医療の発展に大きく貢献してきた歴史ある看護教育機関です。
充実した実習施設と連携病院網を活かした実践的な教育、そして地域に根ざした看護師育成を特徴としています。このセクションでは、学校の基本情報から教育内容、施設設備まで、詳しくご紹介していきます。
学校の基本情報
鳥取看護専門学校は、鳥取市の中心部に位置し、主要な医療機関へのアクセスが良好な立地を誇ります。JR鳥取駅からバスで15分という便利な場所にあり、県内外から多くの学生が通学しています。看護第一学科の一学年定員は80名で、クラス担任制を採用し、きめ細やかな指導を実現しています。
沿革と実績
1952年の開校以来、7,000名以上の卒業生を輩出し、その多くが鳥取県内の医療機関で活躍しています。2020年には新校舎が完成し、最新の設備を備えた実習室や図書館など、学習環境が大幅に強化されました。
令和5年度の看護師国家試験では合格率98.7%を達成し、全国平均を大きく上回る実績を残しています。
教育理念と特色
本校は「豊かな人間性と確かな技術を持つ看護師の育成」という教育理念のもと、三つの教育目標を掲げています。一つ目は「科学的根拠に基づいた看護実践能力の育成」、二つ目は「生命の尊厳を理解し、人権を尊重できる豊かな人間性の育成」、三つ目は「地域社会に貢献できる看護師の育成」です。
教育方針の特徴
教育課程は、基礎分野から専門分野へと段階的に学びを深める構成となっています。各学年で到達目標を明確に設定し、理論と実践を効果的に組み合わせた教育を展開しています。特に臨地実習では、実践力強化のため、1年次から段階的に実習時間を増やしていく独自のカリキュラムを採用しています。
施設・設備の詳細
2020年に完成した新校舎は、最新の教育設備を完備しています。シミュレーション実習室には高機能シミュレーターを複数台配備し、実践的な技術習得が可能です。図書館には医療・看護関係の専門書を20,000冊以上所蔵し、電子ジャーナルも利用可能となっています。
実習室の設備
基礎看護実習室、成人・老年看護実習室、母性・小児看護実習室、在宅看護実習室を備え、各専門分野に特化した実習環境を整備しています。すべての実習室に録画システムを導入し、学生の技術習得をサポートしています。実習室は放課後も20時まで使用可能で、自主的な技術練習に活用できます。
図書館と学習環境
図書館は平日21時まで開館しており、試験期間中は土曜日も利用可能です。個人学習スペースとグループ学習室を備え、それぞれの学習スタイルに対応しています。全館無線LANを完備し、タブレット端末の貸出も行っています。
教員体制と指導方針
専任教員は20名以上在籍し、全員が看護師としての臨床経験を持っています。さらに、専門分野ごとに実務経験豊富な非常勤講師を招聘し、現場の最新知識を学べる体制を整えています。教員一人当たりの学生数は約12名と、きめ細やかな指導を実現しています。
教員のサポート体制
クラス担任制に加え、実習グループごとに担当教員を配置し、学習面と生活面の両方からサポートを行っています。オフィスアワーを設定し、学生の質問や相談に随時対応できる体制を整えています。国家試験対策では、個別指導も実施しています。
年間行事と学校生活
4月の入学式から始まり、5月の戴帽式、10月の学園祭、3月の卒業式まで、様々な行事を通じて充実した学校生活を送ることができます。6月には球技大会、12月には文化祭を開催し、学年を超えた交流の機会を設けています。
課外活動の充実
看護研究会やボランティアサークルなど、10以上の部活動・サークルが活動しています。特に、地域の健康イベントでの血圧測定や高齢者施設での봉사활동など、専門性を活かした活動が活発です。これらの活動を通じて、専門知識の応用力と社会性を養うことができます。
2025年度入試情報と対策

鳥取看護専門学校の入学試験は、一般入試、推薦入試、社会人入試の3種類が設けられています。このセクションでは、各入試区分の詳細な情報と、合格に向けた具体的な対策方法をご紹介します。
長年の指導実績に基づく効果的な受験対策と、過去の合格者の経験を踏まえた実践的なアドバイスを解説していきます。
入試概要と特徴
2025年度入試では、一般入試の募集人員を40名、推薦入試を20名、社会人入試を若干名としています。一般入試は1月下旬、推薦入試と社会人入試は11月中旬に実施される予定です。近年の傾向として、一般入試では基礎学力に加えて看護職としての適性も重視されており、面接試験の比重が増加しています。
出願資格と募集人員
一般入試の出願資格は、高等学校を卒業した者(見込み含む)または同等以上の学力があると認められる者となっています。推薦入試は、高等学校からの推薦が必要で、評定平均値3.5以上が条件となっています。社会人入試は、高等学校卒業後の実務経験が3年以上ある方が対象です。
一般入試の試験科目と対策
一般入試では、国語総合、数学Ⅰ・A、英語、面接の4科目が課されます。試験時間は各教科60分で、午前中に学科試験、午後に面接試験を実施します。昨年度の実績では、合格最低点は350点満点中270点程度でした。
国語総合の試験傾向と対策
国語総合では、現代文と古文の出題があり、特に医療や看護に関連する文章の読解問題が重視されています。配点は100点満点で、現代文から70点、古文から30点の出題となっています。
対策としては、医療系の文章に慣れることが重要で、看護専門誌や医療に関する新聞記事を日常的に読むことをお勧めします。
数学Ⅰ・Aの試験傾向と対策
数学の試験では、医療現場で必要となる数的処理能力を測る問題が多く出題されます。特に、方程式、確率、図形の計算が頻出です。
配点は100点満点で、基礎的な計算問題から応用問題まで幅広く出題されます。日々の学習では、基本的な計算練習に加えて、医療現場で使用する単位換算や濃度計算にも取り組むことが効果的です。
英語試験の特徴と準備方法
英語試験は、医療英語の基礎的な知識も問われます。長文読解、英作文、医療用語の理解度を確認する問題が出題されます。
配点は100点満点で、リーディングとライティングの比率は7:3となっています。対策としては、医療英語の基礎用語を習得しつつ、看護・医療に関する英文記事の読解練習を継続的に行うことが重要です。
面接試験の評価基準と対策
面接試験は50点満点で、看護師としての適性や志望動機の明確さが重点的に評価されます。個人面接方式で、約15分間実施されます。
質問内容は、志望理由、看護師を目指すきっかけ、将来の目標など、看護職への意欲と理解度を確認するものが中心です。面接練習では、自己分析を深め、具体的なエピソードを交えながら答えられるよう準備することが大切です。
推薦入試の試験内容と準備
推薦入試では、小論文試験と面接試験が実施されます。小論文は90分間で800字程度、医療や看護に関するテーマについて、自身の考えを論理的に展開することが求められます。評価の重点は、文章力よりも、看護職としての視点や考え方にあります。
小論文試験の対策方法
小論文試験では、医療や看護に関する時事問題がテーマとして取り上げられることが多く、医療ニュースや社会問題への関心が重要です。
構成は、序論、本論、結論の三部構成を基本とし、自分の考えを具体的な例を挙げながら論理的に展開することが求められます。普段から新聞やニュースに目を通し、医療・看護に関する問題について自分の意見を整理する習慣をつけることをお勧めします。
社会人入試の特徴と準備
社会人入試も推薦入試と同様に、小論文と面接が課されます。ただし、社会人としての経験を踏まえた内容が期待されるため、実務経験を活かした記述や発言が評価のポイントとなります。特に面接では、これまでの職務経験と看護師を目指す動機との関連性が重視されます。
効果的な受験対策スケジュール
受験までの学習計画は、志望する入試区分によって異なりますが、一般的な準備スケジュールをご紹介します。
一般入試の場合、夏休み明けから本格的な受験勉強を開始し、11月頃からは過去問演習を中心とした対策に移行することをお勧めします。推薦入試の場合は、小論文対策を3か月前から開始し、面接練習は1か月前から集中的に行うのが効果的です。
入試に向けた学習環境の整備
自宅学習に加えて、学校の補習授業や予備校の活用も検討すると良いでしょう。本校では、オープンキャンパスや入試説明会で、実際の試験問題や面接のポイントについて詳しい説明を行っています。これらの機会を積極的に活用することで、より具体的な対策を立てることができます。
実習カリキュラムの詳細
鳥取看護専門学校の臨地実習は、基礎から応用へと段階的に進む体系的なプログラムとなっています。このセクションでは、3年間の実習カリキュラムの全体像から、各実習の具体的な内容、実習記録の書き方まで、詳しくご説明します。
実践的な看護技術の習得を重視する本校の特徴が最もよく表れているのが、この実習プログラムです。
実習の全体像と特徴
実習は1年次から3年次まで、段階的にステップアップする形で構成されています。1年次では基礎看護学実習を中心に、看護の基本を学びます。
2年次からは各専門分野の実習が始まり、3年次では総合的な実習を行います。実習施設は鳥取大学医学部附属病院を始めとする県内の主要医療機関と連携し、充実した実習環境を整えています。
実習時間と単位数
実習は3年間で合計23単位、1035時間を確保しています。1単位は45時間の実習時間に相当し、講義や演習と組み合わせながら効果的な学習を進めます。実習時間は午前8時30分から午後4時30分までを基本とし、3年次には夜間実習も経験します。
1年次の実習プログラム
1年次の実習は、基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱを中心に展開されます。まず、医療機関での見学実習から始まり、基本的な看護技術の実践へと進みます。患者さんとのコミュニケーションの取り方や、バイタルサインの測定など、看護の基本となる技術を習得します。
基礎看護学実習の内容
基礎看護学実習Ⅰでは、病院の機能と看護師の役割について理解を深めます。病棟見学や患者さんとの交流を通じて、医療現場の雰囲気を体感します。基礎看護学実習Ⅱでは、受け持ち患者さんの日常生活援助を実践し、基本的な看護技術を身につけます。
2年次の専門分野別実習
2年次からは、各専門分野の実習が本格的に始まります。成人看護学実習、老年看護学実習、小児看護学実習、母性看護学実習、精神看護学実習など、様々な領域の実習を通じて、専門的な知識と技術を習得します。
成人看護学実習
成人看護学実習は、急性期と慢性期の2つの領域で実施します。急性期実習では手術前後の患者さんの看護を学び、慢性期実習では生活習慣病や長期療養が必要な患者さんの看護を実践します。各実習で2週間ずつ、計4週間の実習期間を設けています。
老年看護学実習
高齢者の特性を理解し、その人らしい生活を支援するための看護を学びます。病院での実習に加えて、介護老人保健施設でも実習を行い、多様な場面での高齢者看護を経験します。認知症ケアや終末期ケアについても学習します。
小児看護学実習
小児病棟での実習に加えて、保育所での実習も行います。健康な子どもの成長発達の理解から、疾病を持つ子どもの看護まで、幅広く学習します。家族支援の視点も重視しています。
母性看護学実習
産科病棟で、妊婦・産婦・褥婦の方々の看護を学びます。正常分娩の見学や産褥期の母子への援助を通じて、母性看護の特徴を理解します。母子保健センターでの実習も含まれます。
精神看護学実習
精神科病院での実習を通じて、精神疾患を持つ方々への看護を学びます。コミュニケーション技術の向上と、精神疾患に対する理解を深めることを目標としています。
3年次の統合実習
3年次の統合実習では、これまでの学びを総合的に活用します。複数の患者さんを受け持ち、優先順位を考えながら看護を実践します。夜間実習も経験し、24時間の看護の継続性について理解を深めます。
チーム医療の実践
医師、薬剤師、理学療法士など、多職種との連携を実践的に学びます。カンファレンスへの参加や、看護計画の立案・実施を通じて、チーム医療における看護師の役割を理解します。
実習記録の書き方とポイント
実習記録は看護過程の展開に沿って作成します。患者さんの情報収集、アセスメント、看護計画の立案、実施、評価という一連のプロセスを記録します。記録の書き方は実習オリエンテーションで詳しく説明し、教員が個別指導も行います。
実習記録の構成
実習記録は日々の記録と看護過程の記録に分かれます。日々の記録では、その日の実習内容と学びを整理します。看護過程の記録では、受け持ち患者さんの看護について体系的にまとめます。記録用紙は実習項目ごとに専用のものを使用します。
実習施設との連携体制
実習施設とは定期的な連絡会を開催し、実習内容の充実を図っています。各実習施設には実習指導者が配置され、学生の指導にあたります。教員は実習施設を巡回し、学生の学習状況を確認しながら、きめ細かな指導を行います。
就職状況と支援体制
鳥取看護専門学校は開校以来、高い就職率を維持しており、地域医療を支える看護師を多数輩出しています。このセクションでは、直近の就職実績データと充実した就職支援体制についてご説明します。
本校の特徴である手厚い就職支援により、学生一人ひとりが希望する進路を実現できるよう、サポートを行っています。
就職実績データ
2024年3月卒業生の就職実績では、就職希望者の就職率は100%を達成しています。県内就職率は75%となっており、地域医療への貢献という観点からも、高い実績を残しています。残りの25%は、出身地での就職や、より専門的な医療を学ぶため、首都圏などの大規模病院への就職を選択しています。
主な就職先医療機関
鳥取大学医学部附属病院をはじめとする、県内の主要医療機関との強い連携関係を築いています。鳥取県立中央病院、鳥取市立病院、鳥取赤十字病院など、地域の中核病院への就職実績が豊富です。
また、訪問看護ステーションや介護老人保健施設など、地域包括ケアを支える施設への就職実績も増加傾向にあります。
職種別就職状況
卒業生の約90%が病院の看護師として就職しています。その他、訪問看護ステーションや介護老人保健施設など、様々な施設で活躍しています。近年は、大学院への進学を選択する卒業生も増加しており、より専門的な知識とスキルの習得を目指す傾向も見られます。
キャリア支援プログラム
就職支援は2年次後半から本格的に開始します。進路ガイダンスを皮切りに、履歴書作成指導、面接対策、就職試験対策など、段階的にプログラムを展開します。個別相談にも随時対応し、学生一人ひとりの希望に沿ったきめ細かな支援を行っています。
就職支援スケジュール
2年次12月から3年次にかけて、計画的な就職支援プログラムを実施しています。2年次12月の進路ガイダンスでは、就職活動の流れや準備について説明します。3年次4月からは、履歴書・小論文の書き方講座、面接対策講座を開催し、実践的なトレーニングを行います。
就職情報の提供体制
キャリアセンターには、県内外の医療機関からの求人票や病院案内パンフレットを常時設置しています。また、就職情報検索用のパソコンを設置し、インターネットを活用した情報収集も可能です。求人情報は随時更新され、学生が最新の情報にアクセスできる環境を整えています。
病院説明会・インターンシップ
年2回、学内での病院説明会を開催しています。県内外の主要医療機関の採用担当者から直接説明を受けることができ、具体的な就職イメージを形成する機会となっています。また、夏季休暇中には、希望する医療機関でのインターンシップも実施しています。
卒業生との連携
就職支援の特徴の一つとして、卒業生との密接な連携があります。卒業生による就職体験談発表会を開催し、実際の職場の様子や就職活動のアドバイスを聞く機会を設けています。また、卒業生が勤務する医療機関との連携により、在学生の病院見学や就職相談もスムーズに行えます。
国家試験対策との両立
就職活動と国家試験対策の両立をサポートするため、効率的なスケジュール管理を支援しています。模擬試験や補講のスケジュールを就職活動の時期と調整し、両方に十分な時間を確保できるよう配慮しています。
個別相談では、学習進度や就職活動の状況を確認しながら、適切なアドバイスを提供しています。
学費・奨学金情報

鳥取看護専門学校では、質の高い教育環境を提供しながら、できるだけ多くの学生が経済的な不安なく学業に専念できるよう、様々な支援制度を設けています。このセクションでは、学費の詳細から各種奨学金制度、さらには利用可能な経済的支援制度について詳しくご説明します。
学費の詳細
2025年度入学生の学費は、入学時納付金と年間納付金に分かれています。入学時には入学金と初年度納付金を、2年次以降は年間納付金を納入していただきます。それぞれの金額と納付時期について、詳しく解説します。
入学時納付金の内訳
入学金は200,000円で、合格通知受領後2週間以内に納入が必要です。この入学金は、入学手続き完了後、いかなる理由があっても返還されません。その他、教科書代や実習衣代などの初年度諸経費として、約150,000円が必要となります。
年間納付金の内訳
授業料は年額600,000円で、前期と後期の2回に分けて納入できます。実習費として年額100,000円、施設設備費として年額80,000円が必要です。これらの納付金は、前年度末までに納入していただきます。
奨学金制度の活用
本校では、日本学生支援機構奨学金をはじめ、様々な奨学金制度を利用することができます。特に、鳥取県の医療を支える看護師の育成という観点から、県や医療機関による独自の奨学金制度も充実しています。
日本学生支援機構奨学金
第一種奨学金(無利子)と第二種奨学金(有利子)が利用可能です。第一種奨学金は、自宅通学の場合月額20,000円から54,000円、自宅外通学の場合月額20,000円から64,000円から選択できます。第二種奨学金は、月額20,000円から120,000円までの間で、10,000円単位で選択が可能です。
鳥取県看護師等修学資金
鳥取県内の医療機関等で看護師として勤務することを条件に、月額32,000円の修学資金が貸与されます。卒業後、県内の医療機関で5年間勤務すると、返還が免除される制度です。
各種支援制度の活用
授業料の分割納付制度や、経済的理由による授業料減免制度など、様々な支援制度を設けています。また、アルバイトと学業の両立についても、個別に相談に応じています。
授業料減免制度
経済的理由により授業料の納入が困難な方を対象に、授業料の一部を減免する制度を設けています。前年度の世帯収入や学業成績などを考慮して、減免額を決定します。
学生寮の活用
自宅からの通学が困難な学生のために、学生寮を完備しています。寮費は月額45,000円(食事込)で、一般のアパート等と比べて経済的な負担を抑えることができます。また、防犯面でも安心して生活することができます。
合格者の声とアドバイス
一般入試合格者からのメッセージ
合格者の声とアドバイス1
鳥取看護専門学校の一般入試を経て入学した山田明日香さんは、高校3年生の夏休みから本格的な受験勉強を開始しました。基礎的な学力を固めることを意識しながら、特に面接対策に力を入れて準備を進めました。
祖父の介護体験をきっかけに看護師を志望するようになった経緯を、自分の言葉で具体的に説明できるよう準備したことが、合格につながったと語ります。
毎日の学習では時間割を作成して科目ごとに学習時間を確保し、特に苦手だった数学は毎日30分以上の演習時間を設けて基礎力の向上に努めました。通学時間を活用して英単語の暗記を行うなど、隙間時間の有効活用も意識して取り組んだそうです。
合格者の声とアドバイス2
一般入試合格者の佐藤健一さんは、模擬試験の結果を詳細に分析することで効率的な学習を実現しました。特に理数系科目の対策として、看護の現場で必要となる薬用量の計算や点滴の滴下速度など、実践的な問題に重点を置いて勉強を進めました。
面接試験では高校でのボランティア活動の経験を具体的に語り、その中で感じた医療従事者への憧れと使命感について自分の言葉で表現できたことが評価につながったと振り返ります。日々の準備では、新聞の医療関連記事を読んで要約する習慣をつけ、医療や看護に関する知識と考えを深めていきました。
合格者の声とアドバイス3
一般入試を突破した田中美咲さんは、過去問題の徹底分析から学習をスタートさせました。特に英語は医療用語に関連する単語を重点的に学習し、長文読解では医療関連の文章を多く取り入れて練習を重ねました。
数学の学習では、計算問題の反復練習に加えて、実際の医療現場で使用される単位換算や濃度計算にも取り組んだことで、より実践的な力を身につけることができました。
面接では自身のスポーツ経験を通じて培ったチームワークの大切さと、それを看護の現場でどう活かしていきたいかを具体的に語ることができました。
推薦入試合格者からのメッセージ
合格者の声とアドバイス4
推薦入試で合格した鈴木香織さんは、小論文対策の重要性を強調します。医療や看護に関する新聞記事を毎日読み、記事の要約と自分の意見を書く練習を3か月間継続して行いました。
高校の先生に添削指導をお願いし、論理的な文章の組み立て方を徹底的に学んだことが、合格への大きな力となりました。面接試験では、高校の看護部での活動経験を具体的に話すことができ、オープンキャンパスで得た情報と併せて自分の言葉で志望動機を伝えることができたと話します。
合格者の声とアドバイス5
推薦入試合格者の中村太郎さんは、部活動での経験を看護師という職業にどう活かせるのかを具体的に考えて準備しました。特に陸上部のキャプテンとして培ったリーダーシップと、怪我をした部員のケアを通じて芽生えた医療への関心について、エピソードを交えながら説明することができました。
小論文では医療現場における看護師の役割の変化について考察し、自身の体験と結びつけながら論じることで、独自の視点を示すことができたと振り返ります。
合格者の声とアドバイス6
推薦入試で入学を果たした木村美香さんは、高校時代のボランティア活動での経験を中心に面接準備を進めました。特別養護老人ホームでの活動を通じて感じた高齢者医療の課題と、それに対する自身の考えを整理し、具体的なエピソードを交えながら説明できるよう準備しました。
小論文対策では、医療に関する時事問題を週1回テーマとして取り上げ、800字の意見文を作成する練習を継続的に行ったことが、論理的な文章力の向上につながったと語ります。
社会人入試合格者からのメッセージ
合格者の声とアドバイス7
社会人入試を経て入学した伊藤由美さんは、事務職としての経験を活かした受験対策を行いました。仕事と学習の両立は大変でしたが、通勤時間や休憩時間を利用して少しずつ準備を進めました。
特に小論文では、前職での患者さんとの関わりを通じて感じた医療現場の課題について、具体的な経験を基に論じることができました。面接試験では、社会人としての経験が看護師としてどのように活かせるのかを明確に説明できたことが合格につながったと振り返ります。
合格者の声とアドバイス8
社会人入試合格者の小林健二さんは、製造業での品質管理経験を看護師の仕事と結びつけて考えました。安全管理や正確性の重視など、前職で培った視点が医療現場でも活かせると考え、その具体例を面接で詳しく説明することができました。
小論文では医療安全の観点から看護師の役割について論じ、製造現場での経験と関連付けた独自の視点を展開できたことが評価につながったと語ります。
合格者の声とアドバイス9
社会人入試を通じて入学を果たした斎藤美咲さんは、介護職員としての経験を強みとして受験に臨みました。現場で感じた医療と介護の連携の重要性について、具体的な事例を基に小論文で展開することができました。
面接試験では、介護の現場で培ったコミュニケーション能力や観察力が、看護師としてどのように活かせるのかを具体的に説明し、自身の経験を効果的にアピールすることができたと振り返ります。
入学後の学習アドバイス
合格者の声とアドバイス10
1年生として学んでいる渡辺梨花さんは、入学後の学習で大切なことは基礎医学の理解だと語ります。解剖生理学や生化学などの基礎科目は、後の専門科目の理解に直結するため、初めから丁寧に学習することを心がけています。
特に図や表を活用してノートを作成し、視覚的に理解を深める工夫をしています。また、実習室での技術練習は放課後も積極的に行い、基本的な看護技術の習得に力を入れているそうです。
合格者の声とアドバイス11
2年生の山本晴香さんは、1年次の基礎看護学実習での経験を踏まえ、患者さんとのコミュニケーションの重要性を実感したと話します。専門分野の実習が始まる前から、医療用語の理解と正確な使用を心がけ、実習記録の書き方も指導を受けながら丁寧に練習を重ねました。
グループでの学習時間を有効に活用し、実習での学びを共有することで、より深い理解につながったと振り返ります。
合格者の声とアドバイス12
3年生の加藤裕太さんは、国家試験対策と並行して総合実習に取り組む中で、時間管理の重要性を感じています。定期的な模擬試験を通じて自身の弱点を把握し、効率的な学習計画を立てることで、実習と試験対策の両立を図っています。
特に、グループでの学習会を定期的に開催し、互いの知識を共有しながら理解を深めていく方法が効果的だったと語ります。
就職活動のアドバイス
合格者の声とアドバイス13
就職活動を終えた高橋真由さんは、早期からの情報収集の重要性を強調します。2年次の臨地実習で関わった医療機関の特徴や雰囲気を細かくメモに残し、就職先選びの参考にしました。
病院説明会やインターンシップには積極的に参加し、実際の職場の雰囲気や看護体制について具体的に理解を深めることができました。面接では実習での経験を具体的に話すことができ、志望する病院の特色に合わせた自己アピールができたと振り返ります。
合格者の声とアドバイス14
卒業を控えた大野智子さんは、実習先での学びを就職活動に活かすことができました。各実習で経験した看護ケアや患者さんとの関わりを詳細に記録し、面接での具体的なエピソードとして活用しました。
就職説明会では積極的に質問をし、病院の理念や看護体制について理解を深めました。特に、夜間実習を経験したことで、三交代制の勤務についても具体的なイメージを持って就職活動に臨むことができたと語ります。
合格者の声とアドバイス15
内定を獲得した松田健一さんは、具体的な将来のキャリアプランを持って就職活動に臨みました。急性期医療に興味があり、救急看護の認定看護師を目指したいという目標を持って、それに適した就職先を選びました。
病院見学では教育体制や研修制度について詳しく質問し、自身のキャリアプランと照らし合わせて検討を重ねました。面接では、明確な目標を持って入職後の具体的なビジョンを説明できたことが評価につながったと振り返ります。
よくある質問と回答
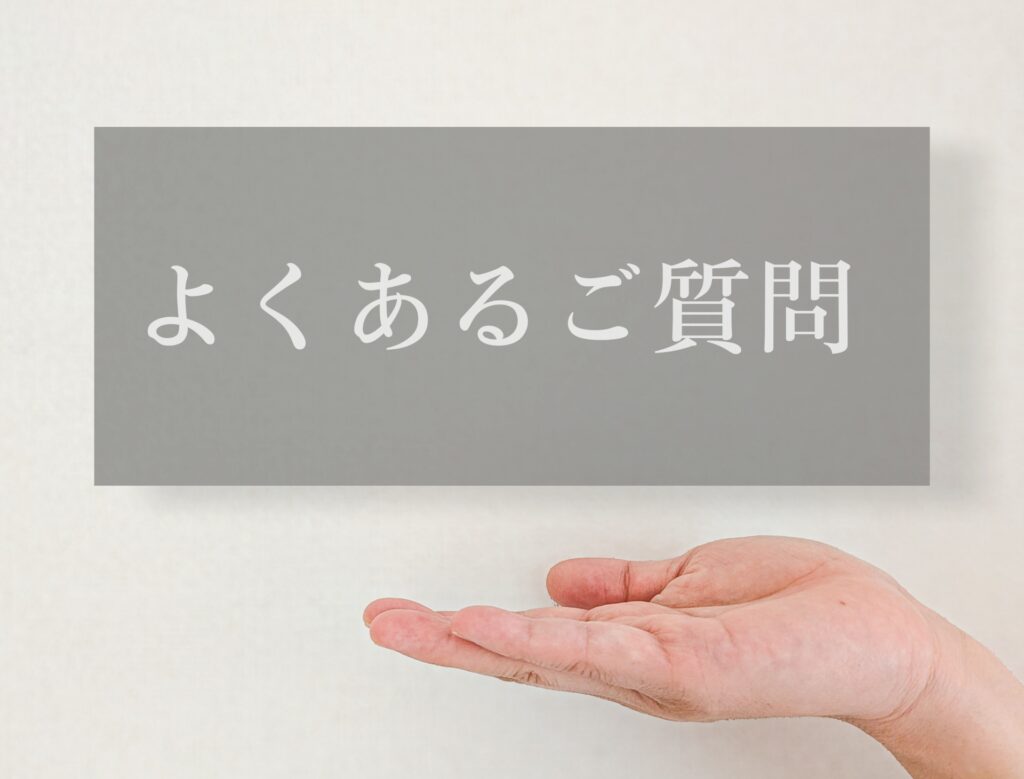
入試・受験について
Q1. 入試の出願資格について教えてください
一般入試の出願資格は、高等学校を卒業した者または2025年3月卒業見込みの者、もしくは高等学校卒業程度認定試験合格者となります。推薦入試については、学校長の推薦が必要で、評定平均値が3.5以上であることが条件となります。
社会人入試は、高等学校卒業後の実務経験が3年以上ある方を対象としています。いずれの入試区分でも、看護師として医療に貢献したいという強い意志を持つ方を求めています。出願時には、入学願書の他に、調査書や推薦書など、入試区分に応じた必要書類の提出が求められます。
Q2. 入試の試験内容と対策方法を詳しく教えてください
一般入試では、国語総合、数学Ⅰ・A、英語の3教科と面接試験が実施されます。国語は現代文と古文から出題され、特に医療や看護に関連する文章の読解力が重視されます。
数学では、医療現場で必要となる計算力を測る問題が多く出題され、特に単位換算や濃度計算などの実践的な問題に備える必要があります。
英語は長文読解と医療英語の基礎知識を問う問題が中心です。面接試験では、志望動機や将来の目標について、具体的なエピソードを交えながら説明できることが重要となります。
Q3. 推薦入試の選考方法について教えてください
推薦入試では、小論文試験と面接試験が実施されます。小論文は90分で800字程度、医療や看護に関するテーマについて、自身の考えを論理的に展開することが求められます。
過去には「高齢化社会における看護師の役割」や「医療技術の進歩と看護の在り方」などのテーマが出題されています。面接では、高校生活での具体的な活動内容や、その経験を看護師としてどのように活かしていきたいかなど、より具体的な視点での質問がなされます。
Q4. 社会人入試の特徴を教えてください
社会人入試では、小論文試験と面接試験に加えて、これまでの職務経験を活かした考察が重視されます。小論文では医療や看護に関する社会的な課題について、実務経験に基づいた具体的な考察が求められます。
面接試験では、これまでの職務経験と看護師を目指す動機との関連性が重点的に評価されます。社会人としての経験を看護の現場でどのように活かしていきたいか、具体的なビジョンを持って臨むことが重要です。
学校生活について
Q5. 学生寮の設備や生活環境について教えてください
学生寮は、安全で快適な学生生活を支援するため、24時間体制の管理人が常駐しています。各部屋は個室で、エアコン、ベッド、机、椅子、クローゼットが標準装備されています。共用施設として、食堂、浴室、ランドリールーム、自習室があり、Wi-Fi環境も完備しています。
食事は朝夕2食が提供され、栄養バランスの取れた食事メニューが用意されます。寮費は月額45,000円で、食費込みの料金となっているため、一般のアパート暮らしと比べて経済的です。
Q6. 通学方法と所要時間について教えてください
JR鳥取駅から路線バスが運行されており、バス停「看護学校前」で下車、徒歩1分でアクセスできます。通学定期券を利用することで、経済的な負担を抑えることができます。
自転車通学も可能で、屋根付きの駐輪場が完備されています。また、自動車通学を希望する学生のために、学生専用の駐車場も用意されています。駐車場の利用には事前申請が必要で、月額3,000円の利用料がかかります。
Q7. 学内の施設設備について教えてください
2020年に完成した新校舎には、最新の教育設備が整っています。各実習室には高機能シミュレーターを配備し、実践的な技術習得が可能です。
図書館には医療・看護関係の専門書を20,000冊以上所蔵し、電子ジャーナルも利用可能です。学生ホールやカフェテリアなどの憩いのスペースも充実しており、快適なキャンパスライフを送ることができます。全館Wi-Fi完備で、タブレット端末の貸出サービスも行っています。
カリキュラムと実習について
Q8. 実習スケジュールと内容について教えてください
実習は1年次から3年次まで、段階的にステップアップする形で構成されています。1年次では基礎看護学実習を中心に、看護の基本を学びます。2年次からは各専門分野の実習が始まり、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学などの実習を行います。
3年次では統合実習として、複数の患者を受け持ち、優先順位を考えながら看護を実践する総合的な実習を行います。実習時間は原則として8時30分から16時30分までです。
Q9. 国家試験対策について教えてください
3年次から本格的な国家試験対策が始まります。定期的な模擬試験の実施に加え、弱点分野を強化するための補講も行われます。過去の出題傾向を分析し、的確な対策を立てられるよう、専門の教員が個別指導を行います。
また、グループ学習を支援するための自習室も完備されており、仲間と協力しながら試験対策に取り組むことができます。令和5年度の看護師国家試験では98.7%という高い合格率を達成しています。
Q10. 授業と実習の両立について教えてください
授業と実習の両立をスムーズに進められるよう、カリキュラムが工夫されています。実習期間中は講義科目を設定せず、実習に専念できる環境を整えています。
また、実習記録の作成時間を確保するため、実習室や図書館の利用時間を延長するなどの配慮もなされています。教員による個別指導も充実しており、学習や実習に関する不安や悩みにも丁寧に対応します。
学費・奨学金について
Q11. 学費の詳細と納付時期について教えてください
2025年度入学生の学費は、入学時納付金と年間納付金に分かれています。入学時には入学金200,000円と教科書代・実習衣代などの諸経費約150,000円が必要です。年間納付金として、授業料600,000円、実習費100,000円、施設設備費80,000円が必要となります。
授業料は前期と後期に分けて納入することができ、経済的な事情がある場合は、分割納付制度を利用することも可能です。すべての費用は、指定された期日までに納入する必要があります。
Q12. 利用可能な奨学金制度について教えてください
日本学生支援機構の奨学金をはじめ、様々な奨学金制度を利用することができます。第一種奨学金(無利子)は、自宅通学の場合月額20,000円から54,000円、自宅外通学の場合月額20,000円から64,000円から選択可能です。
鳥取県看護師等修学資金は、月額32,000円が貸与され、卒業後に県内の医療機関で5年間勤務すると返還が免除される制度となっています。これらの奨学金制度は入学前から申請することができ、経済的な支援を受けながら学業に専念することができます。
Q13. 経済的支援制度について教えてください
授業料の分割納付制度や、経済的理由による授業料減免制度など、様々な支援制度が設けられています。授業料減免制度は、前年度の世帯収入や学業成績などを考慮して、減免額が決定されます。
また、学内でのアルバイトとして、図書館業務や実習室の整備補助などの機会も提供されています。これらの支援制度を活用することで、経済的な負担を軽減しながら学業に取り組むことができます。
就職支援について
Q14. 就職支援プログラムの内容について教えてください
就職支援は2年次後半から本格的に開始します。進路ガイダンスを皮切りに、履歴書作成指導、面接対策、就職試験対策など、段階的にプログラムを展開していきます。また、年2回開催される学内病院説明会では、県内外の主要医療機関の採用担当者から直接説明を受けることができます。
キャリアセンターには、求人情報や病院案内パンフレットが常時設置されており、最新の就職情報にアクセスすることができます。
Q15. 就職実績と主な就職先について教えてください
2024年3月卒業生の就職率は100%を達成しています。主な就職先として、鳥取大学医学部附属病院、鳥取県立中央病院、鳥取市立病院、鳥取赤十字病院などの地域の中核病院があります。
また、訪問看護ステーションや介護老人保健施設など、地域包括ケアを支える施設への就職実績も増加傾向にあります。卒業生の約75%が県内の医療機関に就職し、地域医療の担い手として活躍しています。
Q16. インターンシップ制度について教えてください
夏季休暇中には、希望する医療機関でのインターンシップを実施しています。実際の医療現場を体験することで、職場の雰囲気や業務内容を具体的にイメージすることができます。
インターンシップ先は、連携医療機関を中心に幅広い選択肢が用意されています。また、インターンシップを通じて就職につながるケースも多く、貴重な就職活動の機会となっています。参加希望者には、事前のオリエンテーションも実施されます。
学校行事・課外活動について
Q17. 年間行事について教えてください
4月の入学式から始まり、5月の戴帽式、10月の学園祭、3月の卒業式まで、様々な行事が計画されています。6月には球技大会、12月には文化祭が開催され、学年を超えた交流の機会となっています。
戴帽式は看護学生としての自覚を深める重要な儀式として位置づけられ、保護者の方々も参加されます。学園祭では、健康相談コーナーや救急法の体験コーナーなど、看護の専門性を活かした企画も実施されます。
Q18. 部活動・サークル活動について教えてください
看護研究会やボランティアサークルなど、10以上の部活動・サークルが活動しています。地域の健康イベントでの血圧測定や高齢者施設での봉사활動など、専門性を活かした活動が特徴です。
運動系のサークルとしては、バレーボール部やバドミントン部があり、放課後や休日を利用して活動しています。文化系のサークルでは、茶道部や写真部なども活発に活動しており、学業との両立を図りながら、充実した課外活動を楽しむことができます。
Q19. 学校のクラス運営について教えてください
クラス担任制を採用しており、一学年80名の学生を2クラスに分けて運営しています。各クラスには2名の担任が配置され、学習面と生活面の両方からきめ細かな指導を行います。
クラス内でのグループ学習や実習グループの編成なども、学生の特性を考慮しながら効果的に行われています。また、定期的なクラスミーティングを通じて、学生同士のコミュニケーションも深めることができ、協力して学び合える環境が整っています。
Q20. ボランティア活動の機会について教えてください
地域の医療機関や福祉施設と連携し、様々なボランティア活動の機会が提供されています。地域の健康フェスティバルでの健康相談や血圧測定、高齢者施設での介護支援、小児病棟での遊び支援など、専門性を活かした活動に参加することができます。
これらの活動は、将来の看護師として必要なコミュニケーション能力や実践力を養う貴重な機会となっています。ボランティア活動への参加は単位としても認定され、多くの学生が積極的に参加しています。
また、地域の方々との交流を通じて、医療者としての視野を広げ、看護の意義をより深く理解することができます。定期的に活動報告会も開催され、学生同士で体験を共有し、互いに学び合う場となっています。
鳥取看護専門学校で叶える看護師への道

鳥取看護専門学校は、充実した実習環境と手厚い就職支援を特徴とし、70年以上にわたって地域医療を支える看護師を育成してきました。2025年度入試においても、一般入試、推薦入試、社会人入試の3つの入試区分を設け、多様な学習背景を持つ方々に門戸を開いています。
受験に向けたアクションプラン
これから受験を考えている皆様に、具体的な準備のステップをご提案します。まずは6月と9月に開催されるオープンキャンパスに参加し、実際の学習環境や雰囲気を体感してください。
夏休み期間には、過去問題を入手して学習計画を立てることをお勧めします。推薦入試を考えている方は、小論文対策と面接練習を早めに開始することが重要です。
入学後の目標設定
看護師国家試験の合格を最終目標として、3年間の学習プランを段階的に組み立てることができます。1年次は基礎的な医療知識と看護技術の習得、2年次は専門分野の理解と実践力の向上、3年次は総合的な実践能力の完成と国家試験対策という具体的な目標を持って学習を進めていくことができます。
本校は、皆様の看護師になるという夢の実現に向けて、充実したサポート体制を整えて皆様をお待ちしています。さらに詳しい情報については、学校説明会やオープンキャンパスでご確認ください。
まとめ
鳥取看護専門学校は、1952年設立以来7,000名以上の看護師を輩出してきた歴史ある教育機関です。2020年に新校舎が完成し、高機能シミュレーターを備えた実習室や20,000冊以上の専門書を所蔵する図書館など、最新の教育環境が整備されています。
入試は一般・推薦・社会人の3区分で、2025年度は計80名の募集を予定。令和5年度の看護師国家試験では98.7%の合格率を達成し、就職率は100%を維持。
特に県内就職率75%と地域医療への貢献度も高く、充実した実習環境と手厚い就職支援体制が特徴です。学費面では各種奨学金制度も整備され、経済面でのサポートも充実しています。
より詳しい看護学校の情報や、実際に働く看護師さんのリアルな声が気になる方は、看護師専門メディア「はたらく看護師さん」をご覧ください。現役看護師による学校選びのアドバイスや、職場での体験談など、これから看護師を目指す方に役立つ情報が満載です。
[はたらく看護師さん – 看護学生・看護師のための情報サイト]
参考文献
- 鳥取看護専門学校 (2024). 「奨学金制度案内2025」