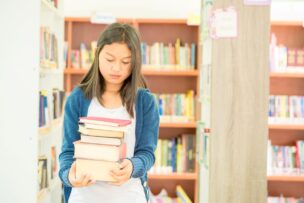現役の看護師長と教育担当看護師50名以上への取材をもとに、新人看護師の皆さんに最適な診療科選択の方法をお伝えします。
この記事では、各診療科の特徴から実際の業務内容、さらには先輩看護師の経験談まで、診療科選択に必要な情報を網羅的にご紹介します。
この記事で分かること
- 各診療科の特徴と求められる適性について
- 自分に合った診療科の選び方のポイント
- 診療科別の具体的な業務内容と年間スケジュール
- 先輩看護師の経験談と実践的アドバイス
- 診療科選択後のキャリアアッププラン
この記事を読んでほしい人
- 診療科選択を控えた新人看護師の方
- 配属先の希望を考えている看護学生の方
- 配属後のキャリアパスを考えている若手看護師の方
- 診療科の特徴を詳しく知りたい方
- 将来の転職を見据えてスキルアップを考えている方
新人看護師の診療科選択:基本の考え方

診療科選択は看護師としてのキャリアを大きく左右する重要な決断です。
この章では、選択に際して押さえるべき基本的な考え方と、選択のための具体的なステップについてご説明します。
診療科選択の重要性と意義
新人看護師にとって診療科の選択は、将来のキャリアの方向性を決める重要な分岐点となります。
適切な選択は、看護師としての成長を加速させる一方で、ミスマッチは早期離職のリスクにもつながります。
看護キャリアへの影響
診療科選択は単なる配属先の決定以上の意味を持ちます。
それは看護師としての専門性の基盤を形成し、将来のキャリアの可能性を広げる重要な一歩となります。
スキル形成への影響
新人時代に経験する診療科での業務内容は、基礎的な看護スキルの習得に大きな影響を与えます。
特に入職後1年間で習得する技術や知識は、その後の看護師人生における重要な基盤となります。
選択時の重要ポイント
診療科選択では、自己分析、環境分析、将来展望の3つの視点から総合的に判断することが重要です。
これらの要素を丁寧に検討することで、より適切な選択が可能となります。
自己分析の重要性
自分自身の特性や志向を正確に把握することは、適切な診療科選択の第一歩です。
性格特性、コミュニケーションスタイル、体力面での特徴など、多角的な自己理解が必要となります。
環境要因の検討
勤務する病院の特性や各診療科の体制を理解することも重要です。
教育システムの充実度、勤務シフトの特徴、チーム医療の在り方など、実務環境に関する情報収集が必要です。
診療科選択のタイミング
診療科選択のタイミングは、就職活動時から入職直後まで、病院によって様々です。それぞれの時期に応じた準備と判断が求められます。
就職活動時の選択
就職活動の段階で診療科を選択する場合、病院見学や先輩看護師への質問を通じて、可能な限り多くの情報を収集することが重要です。インターンシップなどの機会も積極的に活用しましょう。
入職後の選択
入職後に診療科を選択する病院では、オリエンテーション期間中に各診療科の特徴を学ぶ機会が設けられています。
この期間を有効活用し、実際の現場の雰囲気を感じ取ることが大切です。
選択前の準備と心構え
診療科選択を成功させるためには、十分な準備と適切な心構えが必要です。
焦らず、じっくりと情報収集と自己分析を行うことで、より良い選択が可能となります。
情報収集の方法
診療科に関する情報は、病院の説明会や見学会、先輩看護師へのインタビュー、専門書や医療雑誌など、様々な源から収集できます。
それぞれの情報源の特徴を理解し、総合的に判断することが重要です。
メンタル面での準備
診療科選択に際しては、不安や迷いを感じることも自然なことです。
そのような感情と向き合いながら、自分の目指す看護師像を明確にしていくことが大切です。
相談体制の活用
多くの病院では、診療科選択に関する相談体制が整備されています。
教育担当看護師や先輩看護師、看護部の担当者など、適切な相談相手を見つけることで、より良い選択が可能となります。
主要診療科の特徴と適性

新人看護師の皆さんが選択可能な主要な診療科について、その特徴や必要とされる適性、業務内容、キャリアパスまでを詳しくご説明します。
各診療科の特徴を理解することで、自分に合った選択が可能となります。
内科系診療科の特徴と業務
内科系診療科は、新人看護師の方が最も多く配属される部署の一つです。
基本的な看護技術を幅広く習得できる環境であり、看護師としての基礎を築くのに適しています。
総合内科での看護業務
総合内科では、多様な症状や疾患を持つ患者さんの看護を経験できます。バイタルサインの測定から服薬管理、生活指導まで、看護の基本となる業務を幅広く学ぶことができます。
また、患者さんとのコミュニケーション能力を高める機会も豊富です。
循環器内科の特徴
循環器内科では、心臓や血管に関連する疾患を持つ患者さんの看護を担当します。
心電図モニターの管理や急変時の対応など、より専門的なスキルが求められます。
緊急性の高い症状への対応力も身につけることができます。
消化器内科での実践
消化器内科では、消化管や肝臓、胆のうなどの疾患に関する看護を行います。
経管栄養の管理や腹部症状の観察など、専門的な知識と技術が必要となります。
また、食事指導や生活指導も重要な業務となります。
外科系診療科における看護
外科系診療科では、手術前後の患者さんの看護が中心となります。迅速な判断力と確実な技術が求められる現場です。
一般外科の基本
一般外科では、手術前の準備から術後管理まで、周術期看護の基礎を学ぶことができます。
創傷管理や疼痛コントロール、早期離床の支援など、外科看護の基本となる技術を習得できます。
整形外科の特徴
整形外科では、骨折や関節疾患の患者さんの看護を担当します。
ギプス固定の管理やリハビリテーション看護など、運動器に関する専門的なケアが必要となります。患者さんの ADL 向上を支援する技術も重要です。
脳神経外科での実践
脳神経外科では、意識レベルの観察や神経症状の評価など、より高度な観察力が求められます。
急性期から回復期まで、継続的な看護care計画の立案と実施が必要となります。
救急領域の特徴
救急領域は、緊急性の高い患者さんの看護を担当する部署です。
高度な判断力とストレス耐性が求められますが、やりがいも大きい部署となります。
救急外来の特徴
救急外来では、様々な緊急症例への対応が求められます。トリアージの技術や初期対応の能力が重要となります。
多職種との連携も密接に行われ、チーム医療の実践を学ぶことができます。
救急病棟での看護
救急病棟では、緊急入院された患者さんの集中的な管理を行います。
バイタルサインの継続的な観察や急変時の対応など、高度な看護技術が必要となります。
夜勤での緊急対応も多くなります。
小児・母性看護領域
小児科や産婦人科では、それぞれの年齢や状態に応じた特殊な看護技術が求められます。
家族を含めた看護計画の立案が重要となります。
小児科看護の特徴
小児科では、年齢や発達段階に応じた看護care計画が必要です。
家族への支援も重要な業務となります。また、感染対策や安全管理にも特に注意が必要です。
産婦人科での実践
産婦人科では、妊娠期から産褥期までの母子支援を行います。
分娩時の対応や新生児のケア、母乳育児支援など、専門的な知識と技術が必要となります。
精神科看護の特徴
精神科では、患者さんの精神状態の観察と支援が中心となります。コミュニケーション能力と共感性が特に重要視される診療科です。
急性期病棟での看護
急性期病棟では、症状の観察と適切な介入が求められます。
患者さんの安全確保と治療的な関係性の構築が重要です。
療養病棟での実践
療養病棟では、長期的な視点での看護care計画が必要となります。
社会復帰に向けた支援や生活指導が重要な業務となります。
その他の特殊診療科
特殊な診療科では、それぞれの分野に特化した専門的な知識と技術が求められます。
将来的なキャリアパスを考える上で重要な選択肢となります。
透析室での看護
透析室では、透析患者さんの管理と支援が中心となります。
透析技術の習得や合併症の予防など、専門的なスキルが必要です。
また、長期的な患者教育も重要な役割となります。
手術室看護の特徴
手術室では、手術進行の補助や患者さんの安全管理が主な業務となります。
清潔操作や医療機器の取り扱いなど、特殊な技術の習得が必要です。
チーム医療の中心として、高度な連携能力も求められます。
ケーススタディ:先輩看護師の経験から

実際に診療科を選択し、新人期を過ごした先輩看護師たちの経験をご紹介します。
それぞれの選択理由や成長過程、直面した課題とその克服方法から、皆さんの診療科選択のヒントを見つけていただければと思います。
Case A:内科系選択の事例
総合内科を選択したAさんの場合
入職1年目の女性看護師Aさん(25歳)は、幅広い症例を経験できる総合内科を選択しました。基礎的な看護技術の習得を重視し、じっくりと患者さんと関わりたいという思いが選択の決め手となりました。
1年目の具体的な経験
入職直後は、バイタルサイン測定や基本的な検査介助から始まり、徐々に採血や点滴管理などの技術を習得していきました。
教育担当の先輩看護師からマンツーマンで指導を受け、基礎的な看護技術を着実に身につけることができました。
直面した課題と克服方法
業務の優先順位付けに苦労する日々が続きましたが、先輩看護師と振り返りを重ね、次第にペースをつかめるようになりました。
患者さんとのコミュニケーションも、最初は戸惑うことが多かったものの、日々の経験を通じて自然に対応できるようになっていきました。
Case B:外科系選択の事例
消化器外科を選択したBさんの場合
入職1年目の男性看護師Bさん(23歳)は、手術室看護に興味があり、消化器外科を選択しました。アクティブな業務内容と、手術前後の患者さんのケアに携わりたいという思いが選択の理由でした。
成長のプロセス
手術前後の患者さんの観察や創部管理など、外科特有の看護技術を学ぶ中で、アセスメント能力が向上していきました。
チーム医療の現場で、多職種との連携の重要性も実感することができました。
予想外の発見
術後せん妄への対応など、予想以上に患者さんの精神面のケアが重要であることを学びました。
また、家族への支援も重要な業務であることを実感し、コミュニケーション能力の向上にも努めました。
Case C:救急領域選択の事例
救急外来を選択したCさんの場合
入職1年目の女性看護師Cさん(24歳)は、やりがいのある救急領域を選択しました。
急性期看護に興味があり、様々な症例を経験したいという思いから、救急外来への配属を希望しました。
現場での学び
トリアージの技術や急変時の対応など、救急特有の専門的なスキルを習得する機会が多くありました。
時間的制約がある中での適切な判断力も、経験を重ねることで向上していきました。
ストレス管理の重要性
緊急性の高い業務が続く環境下でのストレス管理の重要性を学びました。
先輩看護師のサポートや、同期との情報共有が、精神面での支えとなりました。
Case D:小児科選択の事例
小児科を選択したDさんの場合
入職1年目の女性看護師Dさん(26歳)は、子どもが好きという理由から小児科を選択しました。
発達段階に応じた看護の実践に興味があり、家族を含めた看護展開にやりがいを感じていました。
特殊性への対応
年齢や発達段階に応じたコミュニケーション方法の習得に苦労しましたが、先輩看護師のアドバイスを受けながら、徐々に対応できるようになっていきました。
家族への支援方法も、経験を重ねることで身についていきました。
成長の実感
子どもたちの笑顔や回復する姿に励まされながら、小児看護の専門性を深めることができました。
また、家族との信頼関係構築の重要性も実感することができました。
Case E:産婦人科選択の事例
産婦人科を選択したEさんの場合
入職1年目の女性看護師Eさん(28歳)は、命の誕生に関わる仕事がしたいという思いから産婦人科を選択しました。
妊婦さんや新生児のケアに興味があり、女性の一生に寄り添う看護に魅力を感じていました。
専門性の習得
分娩時の対応や新生児のケア、母乳育児支援など、産婦人科特有の専門的なスキルを習得していきました。
妊婦健診での保健指導や産後ケアなど、予防的な関わりの重要性も学ぶことができました。
喜びと責任
新しい命の誕生に立ち会える喜びとともに、母子の命を預かる責任の重さも実感しました。先輩看護師のサポートを受けながら、確実な技術の習得に努めることができました。
実践的アドバイス:診療科別の業務とスキル

新人看護師の皆さんが各診療科で必要となる具体的な業務内容とスキルについて、現場での実践に即してご説明します。
それぞれの診療科における1日の流れや、身につけるべき技術、注意点などを詳しく解説します。
診療科別の1日の流れ
内科病棟の1日
内科病棟での1日は、早朝の申し送りから始まります。
その後、バイタルサイン測定、採血、点滴準備と投与、朝の内服管理などの業務が続きます。
日中は処置や検査介助、患者さんの観察と記録が中心となります。
夕方には夜勤者への申し送りを行い、翌日の準備を整えて業務を終えます。
特に重要となるのが、患者さんの些細な変化を見逃さない観察力です。
外科病棟の特徴
外科病棟では、手術前後の患者さんのケアが中心となります。
手術前の準備から、術後の全身管理、創部の観察とケア、ドレーン管理など、専門的な技術が必要となります。
また、術後の離床支援や疼痛管理も重要な業務です。
時間管理と優先順位の判断が特に求められる現場となります。
必要なスキルと習得方法
基本的な看護技術の確実な習得
新人看護師にとって最も重要なのは、バイタルサイン測定や与薬、基本的な処置などの確実な習得です。これらの技術は、どの診療科でも必須となる基礎的なスキルです。
教育担当の先輩看護師に確認しながら、一つ一つ丁寧に習得していくことが大切です。
コミュニケーションスキルの向上
患者さんやご家族との信頼関係構築には、適切なコミュニケーション能力が不可欠です。
傾聴の姿勢や共感的な対応、状況に応じた説明力など、日々の実践を通じて向上を図ることが重要です。
注意点とトラブル対処法
インシデント予防の基本
医療安全は全ての診療科に共通する最重要事項です。
患者さんの確認、与薬時の確認、転倒転落予防など、基本的な安全確認を確実に行うことが求められます。
特に新人時期は、確認作業を省略せず、基本に忠実に業務を行うことが大切です。
心身の健康管理
新人看護師にとって、業務によるストレスや体力的な負担は避けられません。
規則正しい生活リズムの維持や、適度な運動、十分な休息の確保など、自己管理を意識的に行うことが重要です。困ったことがあれば、早めに先輩看護師や上司に相談することをお勧めします。
記録と報告の重要性
看護記録は法的な文書であり、チーム医療における重要な情報共有ツールです。観察した内容や実施したケアを正確に記録し、必要な報告を確実に行うことが求められます。
特に状態の変化や気になる点は、速やかに先輩看護師に報告する習慣をつけることが大切です。
看護師さんからのQ&A「おしえてカンゴさん!」

新人看護師の皆さんからよく寄せられる質問について、経験豊富な先輩看護師が丁寧にお答えします。
診療科選択に関する具体的な疑問や不安について、実践的なアドバイスをお届けします。
診療科選択の基準について
新人でも救急は選べますか
救急での勤務を希望する新人看護師も多くいらっしゃいます。
教育体制が整っている病院であれば、新人でも救急科を選択することは可能です。
ただし、急性期看護に対する強い意欲とストレス耐性が求められます。入職前に救急外来の見学や、救急関連の研修への参加をお勧めします。
夜勤の少ない診療科を知りたいです
外来や検査部門は、夜勤が比較的少ない部署として知られています。
また、一部の専門クリニックでは日勤のみの勤務体制を採用しているところもあります。
ただし、病棟勤務では基本的に夜勤があることを理解しておく必要があります。
キャリアプランについて
産休・育休後の復帰に適した診療科は
ワークライフバランスを重視する場合、外来や慢性期病棟がお勧めです。勤務時間が比較的規則的で、急変対応も少なめです。
また、多くの病院では、育児との両立支援制度を整備しています。復帰後のキャリアプランについては、看護部との相談を早めに行うことをお勧めします。
専門・認定看護師を目指すなら
専門・認定看護師の資格取得を考えている場合、目指す分野に関連する診療科での経験が重要です。
例えば、がん看護専門看護師を目指す場合は腫瘍内科や外科、感染管理認定看護師であれば感染症内科での経験が有利となります。早い段階から目標を持って経験を積むことで、効率的なキャリアアップが可能です。
転職を見据えた選択
将来の転職を考えた場合の有利な診療科
内科系や外科系の基本的な経験は、どの医療機関でも高く評価されます。特に急性期病院での経験は、多くの医療機関で求められるスキルとなります。
また、救急や集中治療室での経験も、転職時の強みとなることが多いです。
教育体制について
新人教育の充実した診療科の選び方
教育体制は病院や診療科によって大きく異なります。
病院見学の際には、プリセプター制度の有無、新人教育プログラムの内容、教育担当看護師の配置状況などを確認することが重要です。
また、配属後の研修機会やキャリアアップ支援についても確認しておくと良いでしょう。
ワークシートと実践ツール
診療科選択をより具体的に進めるために、実践的なワークシートとツールをご用意しました。これらのツールを活用することで、自己分析や診療科の比較検討がより効果的に行えます。
自己分析シートの活用法
適性診断の進め方
自己分析シートでは、ご自身の性格特性や興味、価値観などを多角的に分析することができます。
各項目について、具体的なエピソードを思い出しながら記入することで、より正確な自己理解につながります。
看護学生時代の実習での経験や、これまでの生活での出来事なども参考にしながら記入してみましょう。
診療科比較表の使い方
情報整理の方法
診療科比較表を用いることで、各診療科の特徴や自分との相性を客観的に評価することができます。
病院見学や先輩看護師への取材で得た情報を整理し、自分なりの評価基準で各診療科を比較検討してみましょう。
気になる点や不明な点は、メモを取りながら情報収集を進めることをお勧めします。
その他のツール活用
キャリアプランニングシート
長期的なキャリア形成を視野に入れた診療科選択を行うために、キャリアプランニングシートを活用することをお勧めします。
3年後、5年後、10年後の自分をイメージしながら、必要な経験やスキルを書き出してみましょう。.
まとめ:新人看護師の診療科選択
診療科選択は、看護師としてのキャリアの第一歩となる重要な決断です。
自己の適性と興味を見極め、教育体制やキャリアパスを考慮しながら、慎重に選択を進めることが大切です。
不安や迷いがある場合は、一人で抱え込まず、先輩看護師や教育担当者に相談することをお勧めします。
より詳しい情報や、先輩看護師への相談、キャリア相談などをご希望の方は、【はたらく看護師さん】看護師のためのサイト・キャリア支援サイトをご活用ください。
40,000名以上の看護師が利用する当サイトでは、診療科選択に関する詳細な情報や、経験豊富なキャリアアドバイザーによる無料相談、先輩看護師との交流の場を提供しています。
【はたらく看護師さん】でできること
会員登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます:
- 診療科別の詳細な業務解説と体験談
- 現役看護師によるキャリア相談
- 診療科選択お役立ちツール
- 看護師専門のキャリアアドバイザーによる無料相談
- 転職サポート
▼ 詳しくは【はたらく看護師さん】をチェック [【はたらく看護師さん】看護師のためのサイト・キャリア支援サイト]