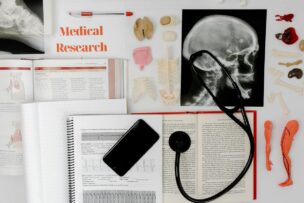医療機関における人材確保の競争が激化する中、魅力的な採用動画の制作が採用成功の鍵となっています。
本記事では、看護師採用に特化した動画制作の企画から効果測定まで、実践的なノウハウを詳しくご紹介します。
2025年の最新トレンドを踏まえた制作技術と、視聴者の心を掴むコンテンツ戦略をお伝えします。
この記事で分かること
- 効果的な採用動画の企画立案から制作までの具体的な手順とノウハウ
- 視聴者の心を掴む最新の動画制作テクニックとクリエイティブ手法
- データに基づく効果測定と継続的な改善プロセスの実践方法
- 成功医療機関に学ぶ、採用動画制作の具体的な事例とポイント
- SNSを活用した効果的な動画の拡散戦略とエンゲージメント向上策
- 2025年の看護師採用市場で求められる革新的なアプローチ手法
この記事を読んでほしい人
医療機関の採用担当者や人事部門のスタッフの方々、特に看護師採用に課題を感じている方にお読みいただきたい内容です。具体的には以下のような方々に最適な情報をお届けします。
- 看護師採用の効果を高めたい採用担当者や人事部門の方々
- 採用動画の制作を検討している医療機関の広報担当者
- 既存の採用動画の改善を目指す人材採用チーム
- 看護部門の管理職として採用強化を考えている方
- 採用コストの効率化を図りたい経営層の方々
効果的な企画立案の実践手法

採用動画の成功は、綿密な企画立案から始まります。このセクションでは、効果的な企画の立て方から、具体的な実施計画まで、詳しくご説明します。
ターゲット層の明確な定義と分析
採用動画の効果を最大化するためには、視聴者となる看護師層の正確な理解が不可欠です。新卒看護師、経験者、復職希望者など、それぞれの層が求める情報や価値は大きく異なります。
新卒看護師向けの訴求ポイント
就職活動を行う看護学生の特徴として、職場の雰囲気や教育体制への関心が高いことが挙げられます。彼らは自身の成長機会や、先輩看護師との関係性に強い興味を持っています。
経験者向けの重要要素
キャリアを積んだ看護師は、専門性の向上や、ワークライフバランスに関する具体的な情報を求めています。給与体系や福利厚生についても、より詳細な情報提供が効果的です。
視聴者を引きつける制作のポイント

採用動画の成功は、視聴者の心を掴む魅力的なコンテンツ制作にかかっています。このセクションでは、具体的な制作テクニックから、視聴者の興味を引き付けるための演出方法まで、実践的なノウハウをご紹介します。
シーン構成の基本テクニック
視聴者の関心を最後まで維持するためには、効果的なシーン構成が重要です。全体の尺を3〜5分に設定し、核となるメッセージは冒頭90秒以内に配置することで、視聴完了率を高めることができます。
オープニングの重要性
最初の15秒で視聴者の興味を引くことが、動画の成功を左右します。インパクトのある映像やサウンド、魅力的なメッセージを組み合わせることで、視聴者の関心を高めることができます。
ストーリー展開の工夫
視聴者の感情に訴えかけるストーリー展開が効果的です。看護師の日常や成長ストーリー、チームワークの様子など、共感を呼ぶ要素を織り交ぜることで、視聴者との心理的な距離を縮めることができます。
撮影・編集の実践テクニック
質の高い映像制作には、適切な撮影・編集技術が不可欠です。病院という特殊な環境下での撮影における注意点と、効果的な編集手法について解説します。
院内撮影のポイント
医療現場での撮影には、細心の注意と配慮が必要です。患者のプライバシー保護を最優先としながら、実際の業務の様子を自然に切り取ることがポイントとなります。
照明とカメラワーク
病院特有の蛍光灯環境下でも、適切な補助光とカメラ設定により、質の高い映像を撮影することができます。自然光を活用したインタビューシーンの撮影方法など、実践的なテクニックをご紹介します。
音声・BGMの効果的な活用
適切な音声とBGMの選択は、動画の印象を大きく左右します。視聴者の感情に働きかける音楽の選び方から、クリアな音声収録のテクニックまでをお伝えします。
音声収録のコツ
院内特有の環境音に配慮しながら、クリアな音声を収録するためのテクニックを解説します。ピンマイクの活用や、エコー対策など、現場で活用できる具体的な方法をご紹介します。
BGM選曲のポイント
視聴者の感情に働きかける効果的なBGM選曲について解説します。著作権に配慮しながら、医療現場にふさわしい楽曲を選定する方法をお伝えします。
テロップ・グラフィック効果の活用
視覚的な情報伝達を強化するテロップやグラフィック効果の活用方法について解説します。重要なメッセージの強調や、データの可視化など、効果的な表現技法をご紹介します。
テロップデザインの基本
読みやすさと視認性を重視したテロップデザインのポイントを解説します。フォントの選択から、画面上の配置まで、具体的なテクニックをお伝えします。
データビジュアライゼーション
看護師の勤務環境や福利厚生に関するデータを、分かりやすく魅力的に表現する方法をご紹介します。グラフやチャートの効果的な活用方法について解説します。
スマートフォン視聴への最適化
現代の視聴環境を考慮し、スマートフォンでの視聴に最適化された制作手法を解説します。縦型動画の特性を活かした構図設計から、テロップサイズの調整まで、実践的なテクニックをお伝えします。
モバイルファーストの構図設計
スマートフォン画面での視認性を重視した構図設計のポイントをご紹介します。文字の大きさや、画面分割の方法など、モバイル視聴に最適化された表現技法を解説します。
SNS展開を見据えた制作
主要なSNSプラットフォームごとの最適な動画フォーマットについて解説します。再生時間や画面比率など、プラットフォームの特性に応じた制作のポイントをお伝えします。
最新のトレンドと革新的なアプローチ
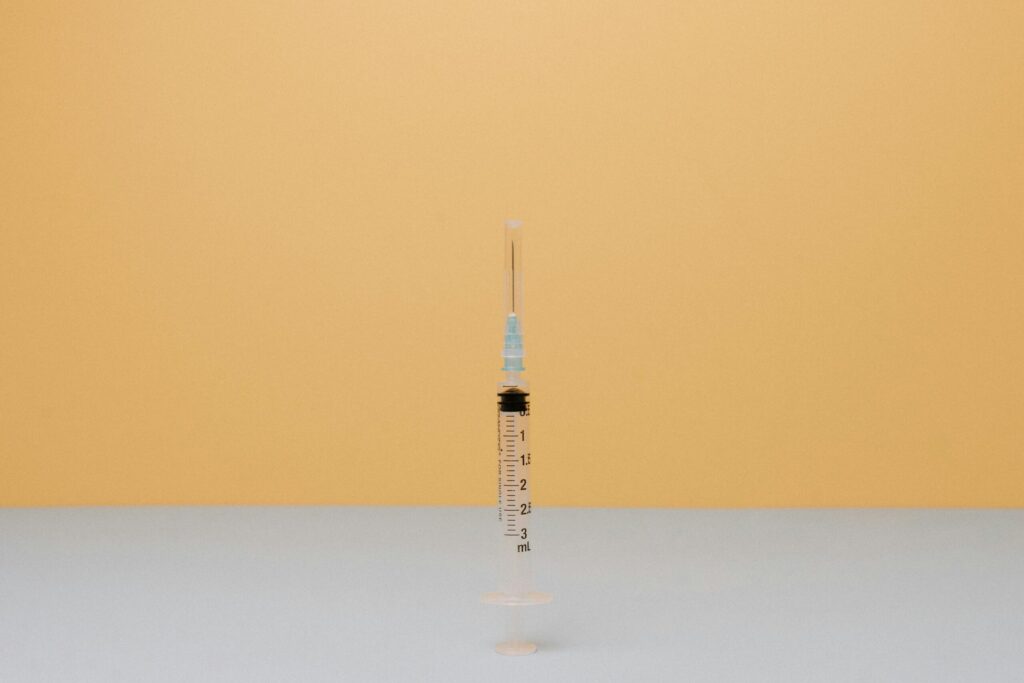
2025年の看護師採用市場では、従来の手法に加えて、最新のテクノロジーやトレンドを取り入れた革新的なアプローチが求められています。このセクションでは、各プラットフォームの特性を活かした展開方法から、最新技術の効果的な活用法まで、詳しくご紹介します。
プラットフォーム別の最適な展開戦略
現代の動画コンテンツは、配信プラットフォームによって求められる要素が大きく異なります。それぞれのプラットフォームの特性を理解し、最適な展開方法を選択することが重要です。
TikTokを活用した採用戦略
若手看護師の採用において、TikTokの活用が注目を集めています。15秒から60秒の短尺コンテンツで、看護師の日常や職場の雰囲気を切り取り、視聴者の興味を引くことができます。
音楽やエフェクトを効果的に活用することで、より魅力的なコンテンツを制作することが可能です。
Instagramリール活用のポイント
Instagramのリール機能を活用することで、若手看護師層へのリーチを高めることができます。看護師の一日の様子やチームワークの雰囲気など、90秒以内の魅力的な動画コンテンツを制作することが効果的です。
最新技術の効果的な活用方法
テクノロジーの進化により、看護師採用動画の表現方法も大きく広がっています。最新技術を活用することで、より魅力的なコンテンツを制作することが可能です。
VR/AR技術の採用動画への応用
バーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)技術を活用することで、よりリアルな職場体験を提供することができます。施設見学や職場体験をバーチャルで実現することで、地理的な制約を超えた採用活動が可能となります。
360度動画の活用テクニック
360度カメラを使用することで、病院施設や職場環境をより詳細に伝えることができます。視聴者が自由に視点を変えながら職場の様子を確認できる没入感のある体験を提供することが可能です。
インタラクティブ要素の効果的な導入
視聴者の能動的な参加を促すインタラクティブ要素の導入が、採用動画の新しいトレンドとなっています。従来の一方向的な情報提供から、双方向のコミュニケーションへと進化を遂げています。
ライブ配信の活用方法
定期的なライブ配信を実施することで、リアルタイムでの質疑応答や職場の雰囲気伝達が可能となります。視聴者からの質問にその場で回答することで、より深い理解と信頼関係を築くことができます。
インタラクティブ動画の制作テクニック
視聴者が選択肢を選ぶことで、ストーリーが分岐していくインタラクティブ動画の制作が可能です。看護師の一日の様々な場面を、視聴者の興味に応じて詳しく見ることができる仕組みを提供することができます。
データドリブンなコンテンツ最適化
視聴データの分析に基づいた継続的な改善が、効果的なコンテンツ制作には不可欠です。視聴者の行動パターンを理解し、より効果的なコンテンツを制作することが可能です。
AIを活用した視聴者分析
人工知能(AI)を活用することで、視聴者の興味関心や視聴パターンをより深く理解することができます。この分析結果を基に、より効果的なコンテンツを制作することが可能となります。
パーソナライズされたコンテンツ配信
視聴者の属性や興味関心に応じて、最適なコンテンツを提供する仕組みづくりが重要です。経験年数や専門分野などに応じて、それぞれに最適化されたコンテンツを提供することで、より高い効果を得ることができます。
具体的な成功事例

採用動画の効果を最大限に引き出すためには、他院の成功事例から学ぶことが有効です。このセクションでは、実際に採用成果を上げた4つの医療機関の事例を詳しく解説します。それぞれの施設が直面した課題と、その解決に向けた具体的な取り組みをご紹介します。
A総合病院の採用動画改革事例
首都圏に位置するA総合病院では、従来の堅いイメージを一新し、若手看護師の日常に焦点を当てた動画シリーズを展開することで、応募数を前年比180%に増加させることに成功しました。
課題と取り組みの背景
慢性的な看護師不足に悩むA総合病院では、特に若手看護師の採用に苦戦していました。従来の採用動画は病院の施設や制度の説明が中心で、視聴完了率が30%程度に留まっていたことが課題でした。
具体的な改善施策
現役の若手看護師による企画チームを結成し、SNSでトレンドの演出手法を取り入れた90秒の動画シリーズを制作しました。教育体制や職場の雰囲気を、看護師の等身大の視点で切り取ることで、より親近感のある内容となりました。
B病院の視聴率向上への取り組み
地方都市に位置するB病院では、採用動画の平均視聴率を30%から75%に改善することに成功しました。視聴者分析に基づいた改善サイクルの確立が、この成果につながっています。
データ分析に基づく改善
視聴データの詳細な分析により、視聴者の離脱が多い場面を特定し、コンテンツの改善を行いました。特に動画の冒頭15秒での離脱が多かったことから、オープニングの構成を大幅に見直しています。
効果的なコンテンツ設計
看護師の成長ストーリーを中心に据え、先輩看護師からの具体的なアドバイスや、実際の業務シーンを交えた構成としました。シリーズ全体で88%の視聴完了率を達成し、応募者からの評価も高い結果となっています。
C専門病院のSNS活用事例
専門性の高い医療を提供するC専門病院では、InstagramとTikTokを活用した採用動画の展開により、専門志向の強い看護師からの応募増加に成功しました。
SNSプラットフォームの戦略的活用
それぞれのSNSプラットフォームの特性を活かし、Instagramではより詳細な専門知識や技術の紹介を、TikTokでは職場の雰囲気や日常的な業務シーンの紹介を行いました。
効果的な情報発信
専門性の高い医療現場ならではの魅力を、分かりやすく伝えることに注力しました。実際の手術室や専門外来での業務シーンを、プライバシーに配慮しながら効果的に切り取ることで、志望者の興味を引くことに成功しています。
D医療センターの地域特性活用事例
地方の中核病院であるD医療センターでは、地域の特性を活かした採用動画により、地域医療に関心の高い看護師の採用に成功しました。
地域密着型のアプローチ
地域医療の重要性と、その中で看護師が果たす役割を丁寧に描き出すことで、地域医療に携わりたい看護師からの応募増加につながりました。地域の文化や生活環境も含めた総合的な魅力発信が、効果を高めています。
長期的な定着率の向上
採用動画で示した地域医療の実態と、実際の業務内容が一致していたことで、入職後の定着率も向上しています。採用から1年後の定着率は前年比で15%向上し、95%を達成しました。
成功事例から学ぶ重要ポイント
これら4つの事例に共通する成功要因として、以下の点が挙げられます。まず、ターゲットとなる看護師層を明確に定義し、その層に響く内容を重点的に発信していること。次に、現場の看護師の声を積極的に取り入れ、より実態に即した情報発信を行っていること。
そして、データに基づく継続的な改善を行っていることです。これらの要素を組み合わせることで、より効果的な採用動画の制作が可能となります。
リスク管理と法的考慮事項

採用動画の制作においては、適切なリスク管理と法的配慮が不可欠です。医療機関ならではの特殊性を踏まえながら、安全かつ効果的な動画制作を実現するために必要な対策について解説します。
法的リスクへの対応策
医療機関における採用動画の制作では、患者のプライバシー保護や医療情報の取り扱いなど、特有の法的リスクが存在します。これらのリスクを適切に管理することで、安全な動画制作が可能となります。
肖像権と個人情報の保護
撮影に協力いただく職員や患者の肖像権については、特に慎重な配慮が必要です。撮影前の同意取得や、個人が特定されないような撮影アングルの工夫など、具体的な対策を講じる必要があります。
著作権への配慮
BGMや素材の使用においては、適切な権利処理が不可欠です。著作権フリーの素材を活用する際も、ライセンス条件を確認し、適切な記載を行うことが重要です。
医療情報の適切な取り扱い
医療機関特有の情報管理について、具体的な注意点と対策をご説明します。
機密情報の保護
医療記録や診療情報が映り込まないよう、撮影場所や角度の選定には細心の注意が必要です。編集段階でのチェック体制を整備し、情報漏洩を防止することが重要です。
コンプライアンスの徹底
医療広告ガイドラインに準拠した内容となるよう、制作段階から法務部門との連携を図ることが推奨されます。誇大広告や不適切な表現を避け、適切な情報提供を心がけます。
SNS活用時の留意点
ソーシャルメディアを活用した情報発信では、特有のリスクと対策について理解しておく必要があります。
炎上リスクの予防
投稿内容の事前チェック体制を整備し、不適切な表現や誤解を招く可能性のある内容を防止します。緊急時の対応マニュアルを整備し、迅速な対応が可能な体制を構築することが重要です。
投稿ガイドラインの整備
SNSでの情報発信に関する明確なガイドラインを策定し、担当者間で共有することが重要です。投稿可能な内容や表現方法について、具体的な基準を設けることで、安全な運用が可能となります。
リスク管理体制の構築
効果的なリスク管理のためには、組織的な体制構築が重要です。制作から公開後のモニタリングまで、一貫した管理体制を整備することが求められます。
チェック体制の確立
制作過程における複数の確認ポイントを設定し、各段階でのリスクチェックを実施します。法務、広報、医療安全の各部門と連携し、多角的な視点でのチェックを行うことが重要です。
定期的な見直しと更新
法規制や社会情勢の変化に応じて、定期的なガイドラインの見直しと更新を行います。新たなリスクに対する対応策を随時追加し、安全な運用を継続することが可能となります。
効果測定と改善サイクル

採用動画の効果を最大化するためには、適切な効果測定と継続的な改善が不可欠です。このセクションでは、具体的な測定指標の設定から、データに基づく改善プロセスまでをご説明します。
KPI設定と分析手法
効果的な改善を行うためには、適切な重要業績評価指標(KPI)の設定が重要です。採用動画の目的に応じた指標を設定し、定期的な測定と分析を行うことで、より効果的な改善が可能となります。
視聴データの測定指標
動画の視聴完了率や平均視聴時間、エンゲージメント率など、基本的な視聴データの測定方法について解説します。視聴者の行動パターンを理解し、より効果的なコンテンツ制作につなげることが可能です。
採用への影響度測定
エントリー数や面接希望者数、最終的な採用数など、採用プロセスにおける具体的な効果測定の方法をご紹介します。動画視聴から採用までの導線を分析することで、より効果的な施策の立案が可能となります。
データ活用の実践手法
収集したデータを効果的に活用し、具体的な改善につなげるための手法について解説します。データの可視化から、意思決定への活用まで、実践的なアプローチをご紹介します。
データの可視化テクニック
収集したデータを分かりやすく可視化し、関係者間で共有するための手法をご説明します。ダッシュボードの作成や、定期的なレポーティングの方法など、具体的なテクニックをお伝えします。
改善ポイントの特定
視聴データの分析から、具体的な改善ポイントを特定する方法をご紹介します。視聴者の離脱が多い場面や、エンゲージメントが高い場面を分析し、効果的な改善につなげることが可能です。
継続的な改善プロセス
効果測定の結果を基に、継続的な改善を行うためのプロセスについて解説します。PDCAサイクルの確立から、具体的な改善施策の実施まで、実践的なアプローチをご紹介します。
改善サイクルの確立
定期的なデータ分析と改善施策の実施を、組織的な取り組みとして確立する方法をご説明します。関係部署との連携や、改善プロセスの標準化など、具体的な手法をお伝えします。
効果検証の実施
実施した改善施策の効果を適切に検証し、さらなる改善につなげるための方法をご紹介します。A/Bテストの実施や、比較分析の手法など、具体的なアプローチを解説します。
組織的な改善体制の構築
効果的な改善を継続的に行うためには、組織的な体制の構築が重要です。部門間の連携や、改善プロセスの標準化など、具体的な体制づくりについて解説します。
改善チームの編成
効果測定と改善を担当するチームの編成方法について、具体的なアプローチをご紹介します。メンバーの役割分担や、必要なスキルセットなど、実践的な情報をお伝えします。
定期的な振り返りの実施
改善活動の効果を定期的に振り返り、次のアクションにつなげるための方法をご説明します。ミーティングの運営方法や、議論のポイントなど、具体的なテクニックを解説します。
看護師さんからのQ&A「おしえてカンゴさん!」
採用動画制作に関して、実際によく寄せられる質問について、具体的な解決策とともにご紹介します。現場の声を反映した実践的なアドバイスを、カンゴさんがお答えします。
予算・リソースに関する質問
Q1: 予算が限られている場合の効果的な制作方法は?
採用動画は必ずしも高額な予算を必要としません。スマートフォンでの撮影でも、適切な機材選びと撮影技術があれば、十分な品質のコンテンツを制作することが可能です。三脚やピンマイクなど、必要最小限の機材を揃えることをお勧めします。
また、無料や低価格の編集ツールを活用することで、コストを抑えながら質の高い動画を制作することができます。
Q2: 内製化と外注、どちらを選ぶべきでしょうか?
この判断は、予算、人員のスキル、制作の継続性などを総合的に考慮する必要があります。内製化の場合は、機動的な制作や細かな修正が可能という利点がありますが、スタッフの育成や機材の準備が必要です。
外注の場合は、プロフェッショナルな品質が期待できますが、予算面での考慮が必要です。まずは簡単な動画から内製で始め、重要な採用シーズンの本格的な動画は外注するなど、ハイブリッドなアプローチも効果的です。
制作プロセスに関する質問
Q3: 撮影の協力を得やすい声かけのコツは?
撮影協力を依頼する際は、目的と活用方法を明確に説明することが重要です。特に若手看護師の場合、自身の経験が後輩のキャリア選択に役立つという点を強調すると、協力を得やすくなります。
また、撮影スケジュールは業務に支障が出ないよう十分な余裕を持って調整し、必要に応じてインセンティブを用意することも検討してください。
Q4: 効果的な動画の長さはどれくらいですか?
基本的には3〜5分を目安としますが、プラットフォームや目的によって最適な長さは異なります。YouTubeでの完全版は5分程度、Instagram ReelsやTikTokでは60秒以内のダイジェスト版を制作するなど、プラットフォームの特性に応じた尺の設定が重要です。
特に冒頭15秒で視聴者の興味を引くことが、視聴継続率を高めるポイントとなります。
配信と拡散に関する質問
Q5: 効果的な拡散方法について教えてください
SNSの特性を活かした拡散戦略が効果的です。たとえば、職員の個人アカウントでの共有を促進したり、施設公式アカウントでの定期的な情報発信を行ったりすることで、より広いリーチが期待できます。
また、採用イベントでの上映や、就職情報サイトへの掲載など、オフラインとオンラインを組み合わせた展開も検討してください。
Q6: どのプラットフォームで公開すべきですか?
ターゲット層の利用傾向に応じてプラットフォームを選択することが重要です。新卒採用であればTikTokやInstagram、経験者採用であればYouTubeやLinkedInなど、それぞれの特性を活かした展開が効果的です。
また、複数のプラットフォームで展開する場合は、各プラットフォームの特性に合わせてコンテンツを最適化することをお勧めします。
コンテンツ企画に関する質問
Q7: 差別化されたコンテンツを作るコツは?
自施設の独自の強みや特色を明確にし、それを具体的に伝えることが重要です。たとえば、教育プログラムの特徴や、ワークライフバランスの実現方法、チーム医療の実践例など、他施設との違いを具体的に示すことで、視聴者の興味を引くことができます。
Q8: 評価を高める演出のポイントは?
視聴者の感情に訴えかける要素を取り入れることが効果的です。看護師の成長ストーリーや、やりがいを感じる瞬間、チームワークの様子など、共感を呼ぶ要素を織り交ぜることで、より印象的なコンテンツとなります。
効果測定に関する質問
Q9: 具体的な効果測定の方法は?
視聴データの分析から、実際の採用につながった数まで、多角的な測定が重要です。視聴回数、視聴完了率、エンゲージメント率などの基本指標に加え、採用エントリー数や面接参加率など、採用プロセスにおける具体的な数値も測定することをお勧めします。
Q10: 改善のためのPDCAサイクルの回し方は?
定期的なデータ分析と、それに基づく改善施策の実施が重要です。月次でのデータ確認を行い、四半期ごとに大きな改善施策を実施するなど、計画的な改善サイクルの確立をお勧めします。
最新トレンドに関する質問
Q11: 2025年の採用動画トレンドは?
インタラクティブ要素の導入やAR/VR技術の活用など、より没入感のある体験の提供がトレンドとなっています。また、ショート動画の重要性が増しており、プラットフォームごとに最適化されたコンテンツ制作が求められています。
Q12: 今後の採用動画の展望は?
テクノロジーの進化により、よりパーソナライズされた体験の提供が可能となります。AIを活用した視聴者分析や、リアルタイムでのインタラクションなど、新しい可能性が広がっています。
一方で、コンテンツの真正性や共感性は今後も重要な要素として残り続けるでしょう。
まとめ
効果的な看護師採用動画の制作には、明確な戦略と継続的な改善が不可欠です。視聴者である看護師の方々の視点に立ち、共感を呼ぶコンテンツを作ることで、採用効果を最大化することができます。
ターゲット層の理解、適切な制作手法の選択、そして効果測定に基づく改善サイクルの確立により、魅力的な採用動画の制作が可能となります。
さらに詳しい情報は【はたらく看護師さん】で
より詳しい採用動画の事例や、看護師のキャリアに関する情報は、【はたらく看護師さん】でご覧いただけます。
今すぐ【はたらく看護師さん】に登録して、あなたの看護師としてのキャリアをさらに充実させてみませんか?