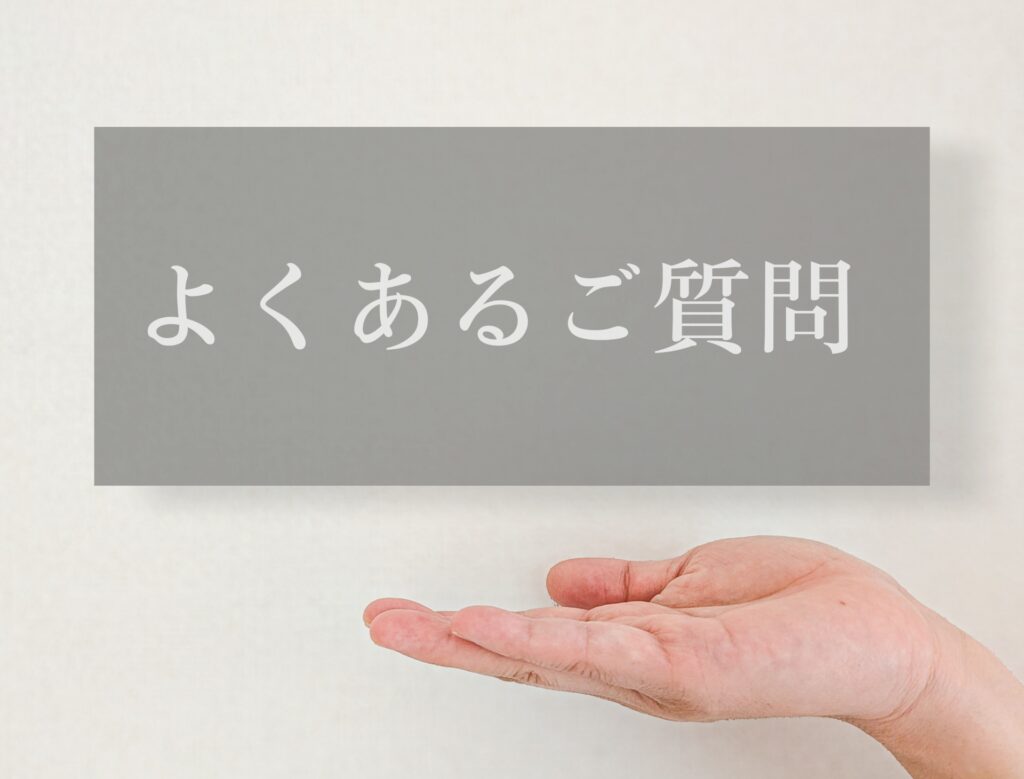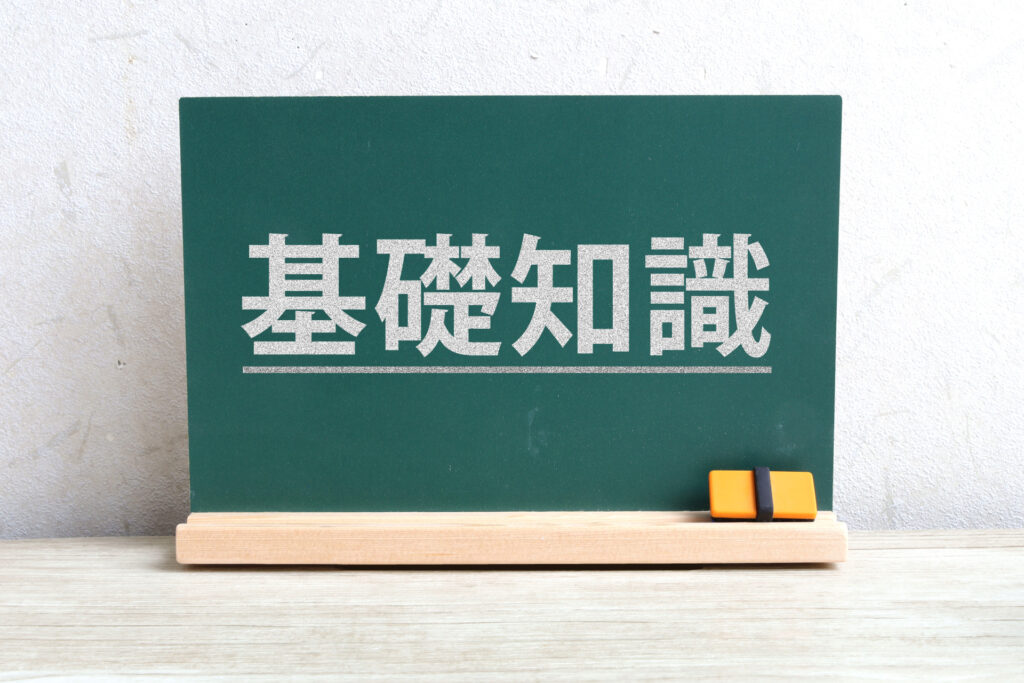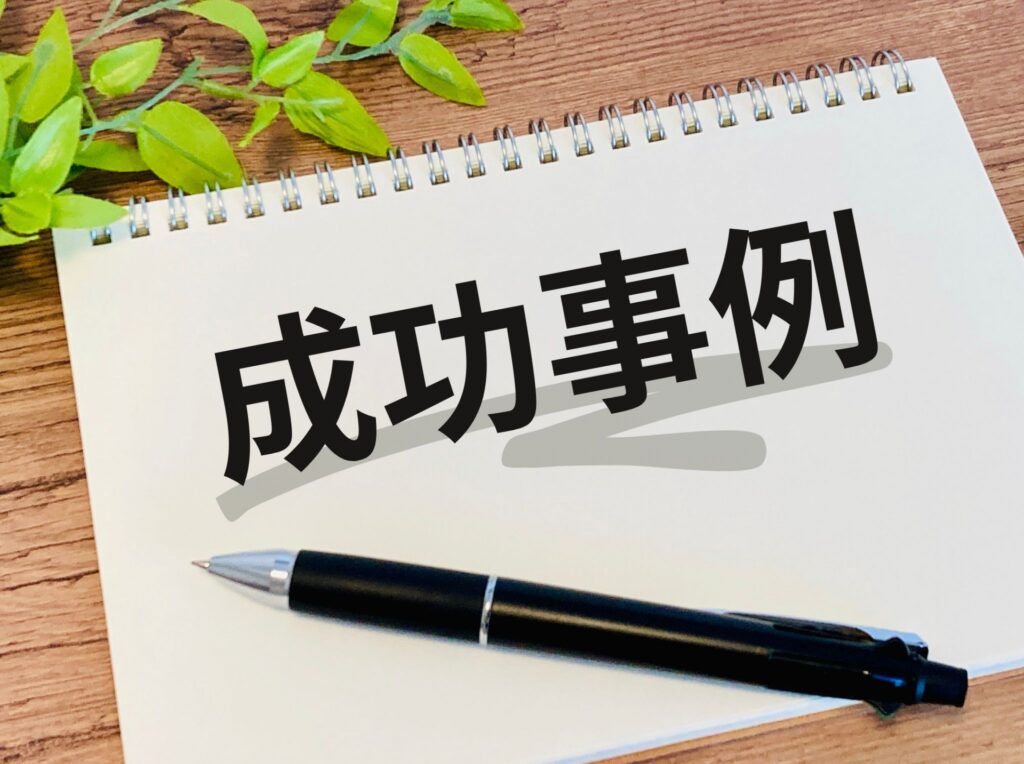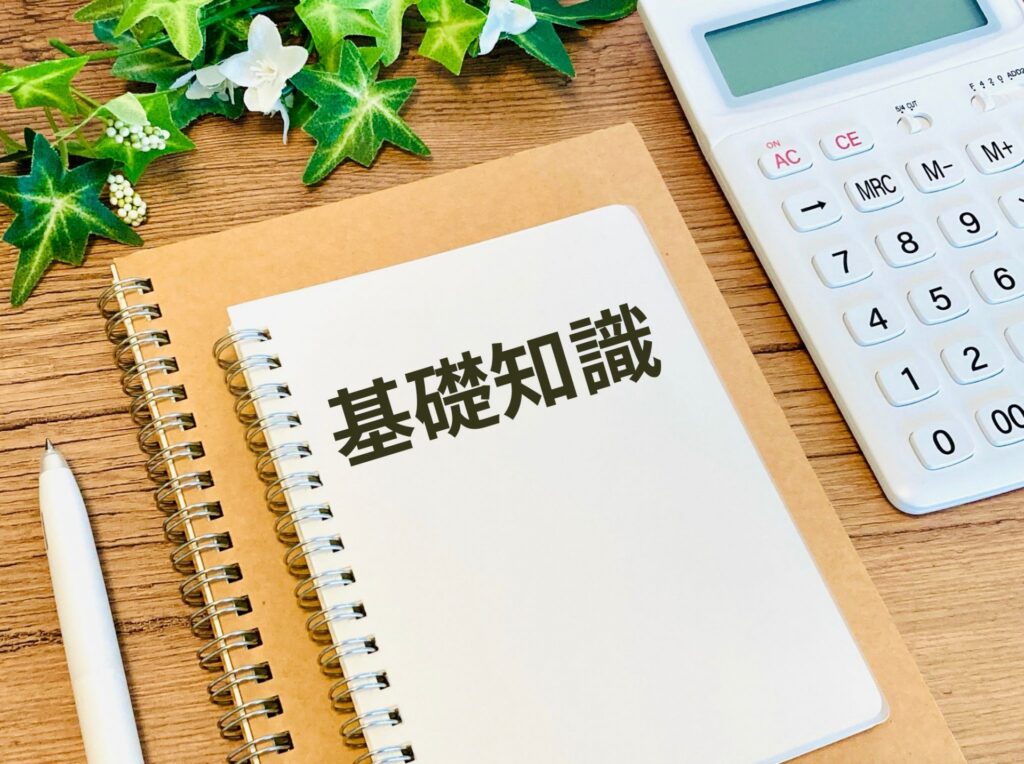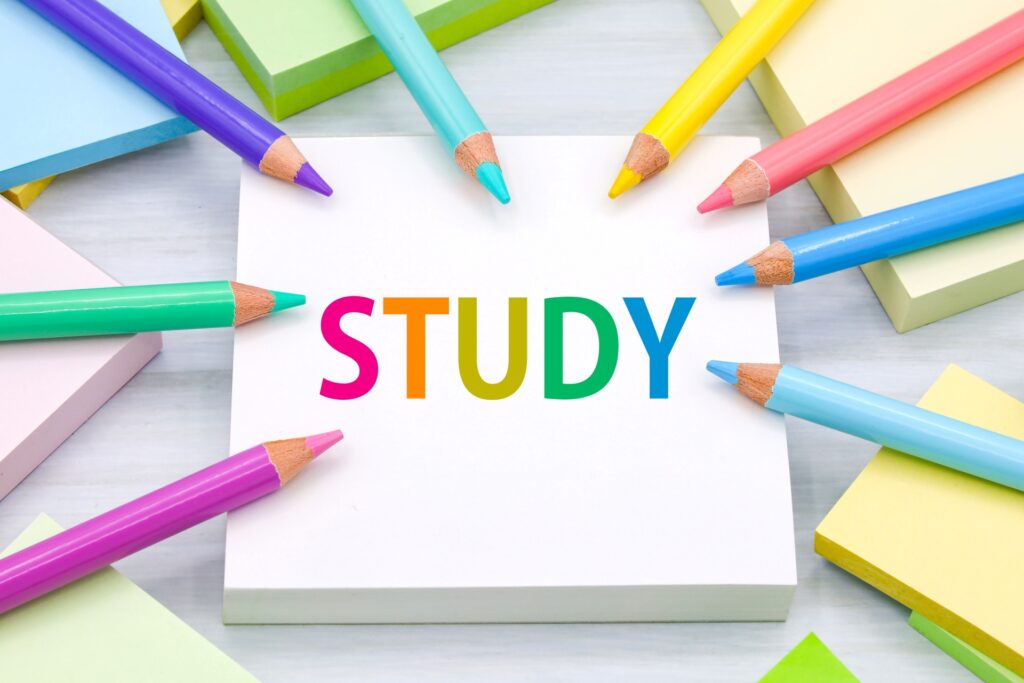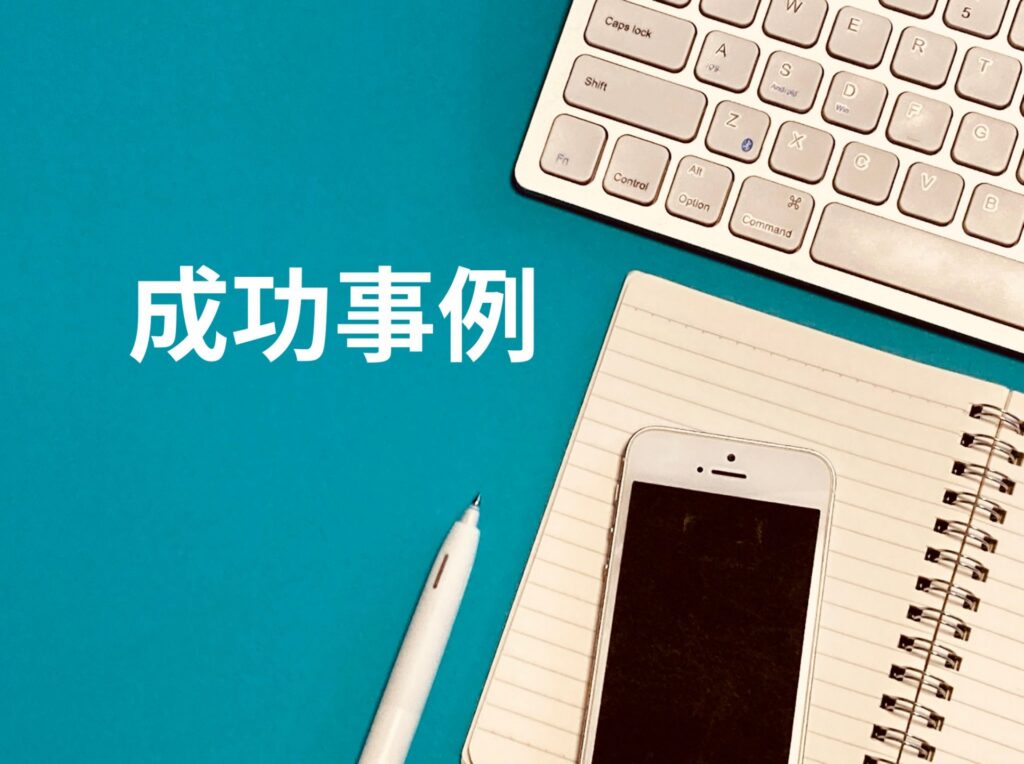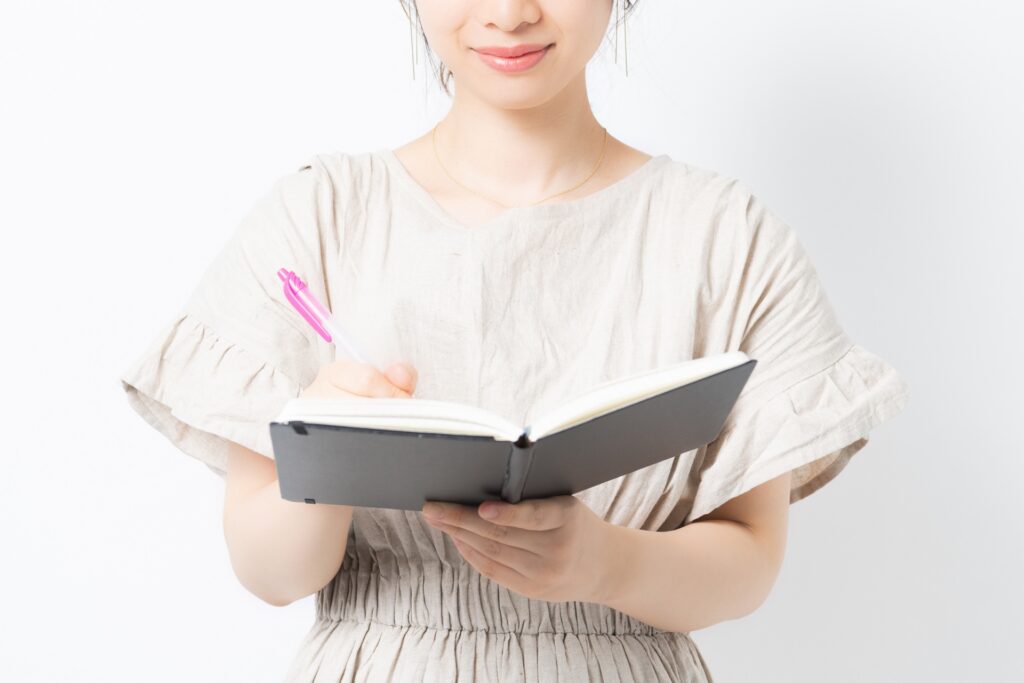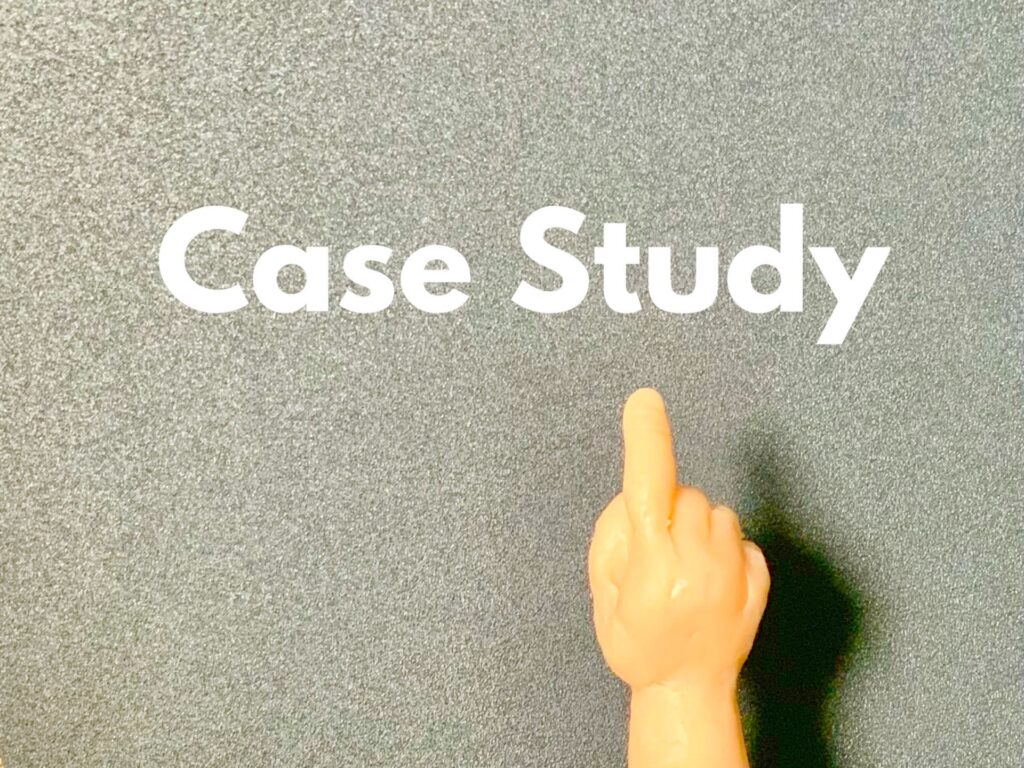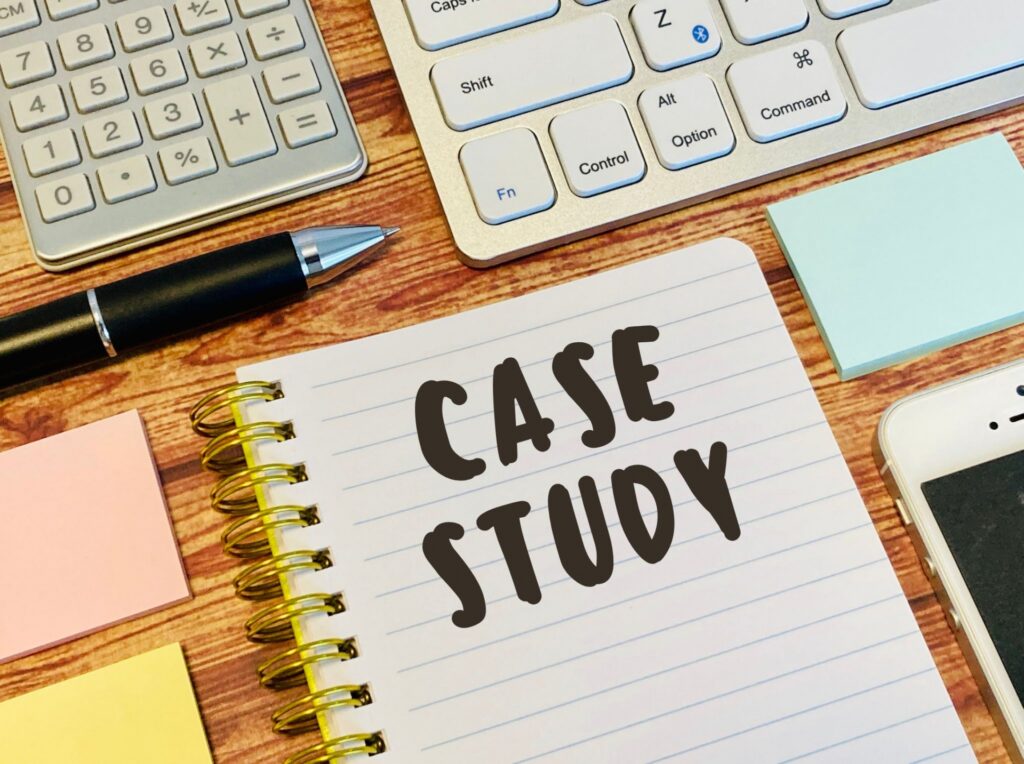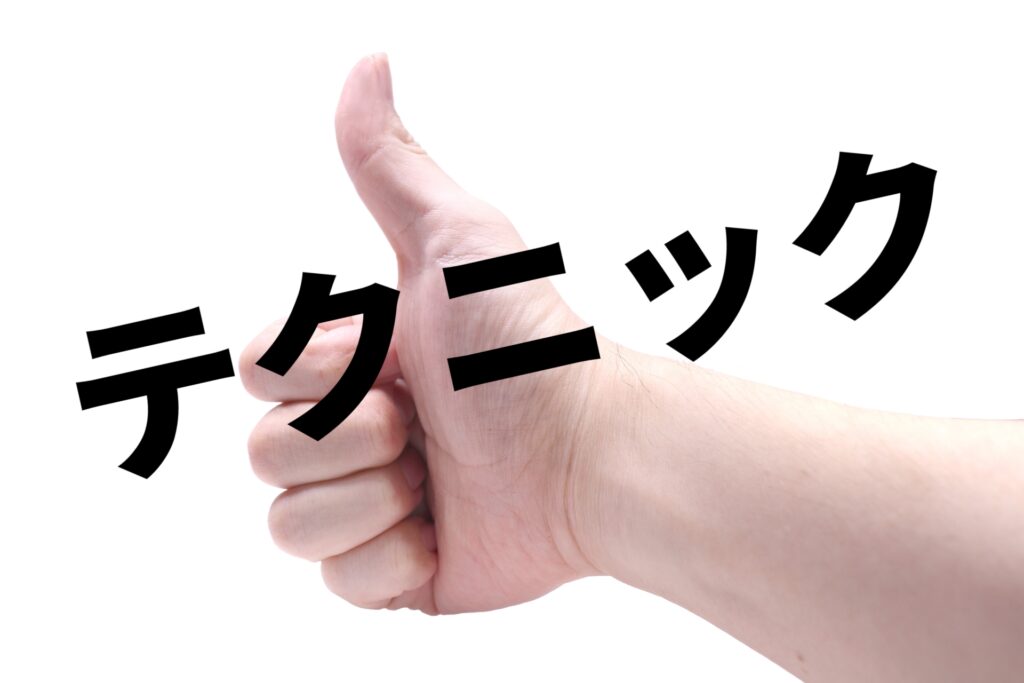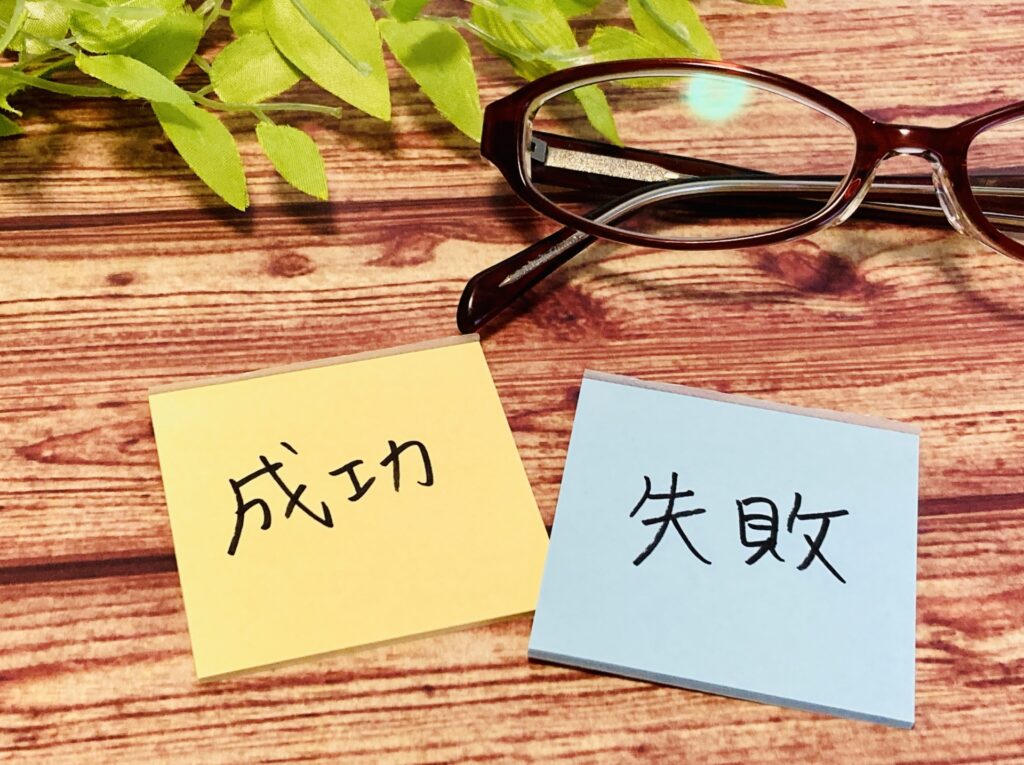岐阜市立看護専門学校の魅力と特徴を詳しく紹介した入試ガイドです。
昭和41年の開校以来、4,000名以上の卒業生を輩出してきた伝統校である本校の教育理念、カリキュラム、実習プログラム、入試情報、学費・奨学金制度、就職状況まで、これから看護師を目指す方に必要な情報を網羅的に解説しています。
岐阜市民病院を主たる実習施設とし、早期から臨床現場での実践的な学びを重視した教育を展開している本校で、あなたも看護の夢を叶えてみませんか。
この記事を読んでほしい人
- 岐阜市立看護専門学校への進学・看護師を目指す方
- 実習や学校生活について知りたい方
- 受験対策の方法を学びたい方
この記事で分かること
- 教育理念とカリキュラムの詳細情報、入試対策と学習計画
- 実習スケジュールと準備、学生生活の支援体制
- 就職状況と卒業後の進路支援
岐阜市立看護専門学校の特徴と魅力

伝統ある教育機関としての基盤
歴史と実績
岐阜市立看護専門学校は、昭和41年の開校以来、地域医療の最前線で活躍する4,000名以上の看護師を輩出してきた伝統ある教育機関である。岐阜市民病院を主たる実習施設とし、早期から臨床現場での実践的な学びを重視した教育を展開することで、即戦力となる看護師の育成に成功している。
教育理念と目標
人間性豊かな看護実践者の育成を教育理念として掲げ、科学的根拠に基づいた確かな看護実践力の育成と、患者の心に寄り添える豊かな人間性の涵養を重視している。
また、地域医療に貢献できる専門職としての使命感の醸成にも力を入れており、理論と実践のバランスの取れた教育プログラムを展開している。
充実した教育環境
最新の施設設備
岐阜市民病院に併設された立地を活かし、最新の医療現場で使用される機器や設備を用いた実践的な学習が可能である。
シミュレーション教育を重視しており、高機能患者シミュレータを使用した演習や、最新のICT機器を活用した遠隔授業にも対応している。図書室には医療・看護に関する専門書や学術雑誌が豊富に揃えられ、24時間利用可能な自習室も完備されている。
実践的な学習環境
シミュレーション教育センターでは、複数台の高機能シミュレータを活用し、基本的なフィジカルアセスメントから高度な救急処置まで、段階的な技術習得を可能にしている。実施後には必ずデブリーフィングを行い、実践した看護ケアの振り返りと改善を行うことで、より効果的な学習を実現している。
体系的なカリキュラム
段階的な学習プログラム
1年次では看護の基礎となる医学的知識と基本的な看護技術の習得に重点を置いており、解剖生理学や生化学などの基礎医学を学ぶとともに、看護学概論や基礎看護技術などの専門基礎分野を学習している。
2年次からは専門分野の学習が本格化し、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学などの各専門領域について深く学習する。3年次では、より高度な専門知識と技術の習得を目指し、医療安全や災害看護、国際看護など、現代の医療ニーズに対応した内容も含まれている。
充実した実習プログラム
岐阜市民病院を中心とした実習環境により、高度急性期医療から在宅支援まで幅広い医療現場での実習が可能である。臨床経験豊富な専任教員と実習指導者による密接な連携のもと、きめ細かな指導を実施している。
基礎看護学実習から始まり、各専門分野の実習へと段階的に進む構成により、確実な技術の習得と看護実践能力の向上を図っている。
手厚い学習支援体制
個別指導とサポート
専任教員によるオフィスアワーの設定や、定期的な到達度確認テストの実施により、学生一人ひとりの理解度に応じた支援を提供している。図書室には専門の司書が常駐し、文献検索や資料収集のサポートも充実している。
また、グループ学習を促進するための支援も行っており、学習スペースの提供や教材の貸出、ディスカッションの機会を設けるなど、学生同士が学び合える環境を整えている。
国家試験対策
3年次から本格的な国家試験対策を開始し、定期的な模擬試験の実施や弱点分野の個別指導、外部講師による特別講座などを通じて、高い合格率を維持している。学生の理解度に応じた個別指導も実施しており、確実な合格を目指したサポート体制を確立している。
充実した経済支援制度
奨学金と学費サポート
日本学生支援機構の奨学金に加え、岐阜県看護職員修学資金や各医療機関独自の奨学金制度など、複数の経済的支援制度を利用することができる。公立校ならではの経済的な学費設定も特徴であり、授業料の分割納付制度や緊急支援制度も整備されている。
キャリア支援と就職サポート
就職支援は2年次後半から本格的に開始され、個別相談や履歴書添削、面接指導などのきめ細かなサポートを提供している。インターンシップや病院見学の機会も豊富に設けられており、学生が自身の進路を具体的にイメージしながら就職活動を進められる環境が整っている。
将来性とキャリア展開
確かな就職実績
直近5年間の就職率は100パーセントを維持しており、多くの卒業生が岐阜県内の主要医療機関で活躍している。特に岐阜市民病院への就職実績が多く、高度急性期医療の最前線で即戦力として活躍している。認定看護師や専門看護師を目指すなど、さらなるキャリアアップを目指す卒業生も多い。
地域医療への貢献
地域包括ケア教育の一環として、在宅療養者への訪問看護演習や地域の健康教室での実践的な学習機会を提供している。地域医療の担い手として、確かな実践力を持つ看護師の育成に力を入れており、今後も時代のニーズに応じた教育プログラムの改善と充実を図っていく方針である。
カリキュラムと学習内容
岐阜市立看護専門学校のカリキュラムは、基礎から応用へと段階的に進む体系的な構成となっている。3年間の課程を通じて、確かな看護実践力と豊かな人間性を育むための科目が効果的に配置されている。
1年次の学習内容
1年次では看護の基礎となる医学的知識と基本的な看護技術の習得に重点を置いている。解剖生理学や生化学などの基礎医学を学ぶとともに、看護学概論や基礎看護技術などの専門基礎分野を学習する。
前期では主に座学を通じて基礎的な知識を習得し、後期からは基礎看護学実習を通じて実践的なスキルの向上を図る。専門基礎分野では人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度などについて学ぶ。
2年次の学習内容
2年次からは専門分野の学習が本格化する。成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学などの各専門領域について深く学習する。
各領域の特性に応じた看護過程の展開方法を学び、事例検討や演習を通じて実践力を養う。臨床実習も本格的に開始され、学内で学んだ知識と技術を実践の場で統合していく。実習では受け持ち患者の看護過程の展開を通じて、アセスメント力や看護実践力を磨いていく。
3年次の学習内容
最終学年となる3年次では、より高度な専門知識と技術の習得を目指す。各専門領域の実習を深化させるとともに、統合分野として在宅看護論や看護の統合と実践を学ぶ。医療安全や災害看護、国際看護など、現代の医療ニーズに対応した内容も含まれる。
また、看護研究の基礎を学び、実際に研究計画の立案から実施、まとめまでを行う。卒業前には総合的な実習を通じて、これまでの学びを統合し、臨床現場で即戦力として活躍できる実践力を養成する。
単位取得と進級要件
各学年で定められた必要単位数を取得することが進級の要件となる。1年次では基礎分野17単位、専門基礎分野13単位の計30単位以上が必要である。2年次では専門分野を中心に35単位以上、3年次では統合分野を含む32単位以上の取得が求められる。
実習科目については全て合格することが必須となっており、欠席時間数が規定を超えた場合は単位認定試験の受験資格を失うことがある。
特色ある授業と教育プログラム
本校では通常のカリキュラムに加え、現代の医療ニーズに対応した特色ある教育プログラムを実施している。多職種連携教育では、医師や薬剤師、理学療法士などの他職種と協働で事例検討を行い、チーム医療の実践力を養う。
また、シミュレーション教育センターでは高機能シミュレータを用いた実践的な演習を行い、臨床現場で必要とされる判断力と技術を磨く。さらに、地域包括ケア教育として、在宅療養者への訪問看護演習や地域の健康教室での実践的な学習機会も提供している。
学習支援体制
学生の学習をサポートするため、充実した支援体制を整備している。専任教員による個別指導や学習相談に加え、図書室での文献検索指導、国家試験対策講座なども実施している。また、eラーニングシステムを導入し、授業の予習復習や自己学習をサポートしている。
定期的に実施される学習到達度確認テストでは、各学生の理解度を把握し、必要に応じて補習や個別指導を行っている。学生同士の学び合いを促進するためのグループ学習室も完備されており、放課後や休日も利用可能となっている。
充実した実習プログラム
岐阜市立看護専門学校の実習プログラムは、附属の岐阜市民病院を中心に、地域の多様な医療施設と連携して実施される。段階的に実践力を養成する体系的なプログラム構成により、確実な技術の習得と看護実践能力の向上を目指している。
実習の全体像と特徴
本校の実習は、基礎看護学実習から始まり、各専門分野の実習へと段階的に進んでいく。実習施設である岐阜市民病院は、高度急性期医療から在宅支援まで幅広い医療を提供する地域の中核病院であり、様々な症例や看護場面を経験できる環境が整っている。
実習指導は、臨床経験豊富な専任教員と実習指導者が連携して行い、きめ細かな指導体制を確立している。
基礎看護学実習の詳細
1年次から開始される基礎看護学実習は、看護の基本となる観察力とコミュニケーション能力の育成を目的としている。実習開始前には、学内演習を通じて基本的な看護技術の習得を確認する。
実習では、患者とのコミュニケーションを通じて情報収集を行い、日常生活援助の実践を通じて基本的な看護技術を習得する。また、看護記録の書き方や報告の仕方など、看護実践に不可欠な基本的スキルも学ぶ。
専門分野別実習の展開
2年次から始まる専門分野別実習では、各領域の特性に応じた看護実践能力を養う。成人看護学実習では急性期から慢性期まで様々な健康段階にある患者の看護を学び、老年看護学実習では高齢者の特性を理解した上での看護実践を行う。
小児看護学実習では成長発達段階に応じた援助方法を、母性看護学実習では妊産褥婦や新生児への看護を学ぶ。精神看護学実習では、対象者の心理状態を理解し、治療的コミュニケーションを実践する。
統合実習と在宅看護実習
3年次の統合実習では、これまでの学びを統合し、チーム医療の一員としての役割を実践的に学ぶ。複数の患者を受け持ち、優先順位を考えた看護計画の立案と実施を行う。
また、夜間実習も経験し、24時間継続する看護の特性について理解を深める。在宅看護実習では、訪問看護ステーションでの実習を通じて、地域で生活する療養者とその家族への支援方法を学ぶ。
実習記録の作成と指導
実習記録は看護実践力を育成する重要なツールとして位置づけられている。看護過程の展開に基づき、情報収集、アセスメント、看護計画立案、実施、評価の各段階を詳細に記録する。
記録の作成にあたっては、実習指導者による個別指導が行われ、論理的思考力と看護実践力の向上を図る。また、カンファレンスを通じて、学生同士での学びの共有も積極的に行っている。
実習における感染対策と安全管理
医療安全と感染対策は実習において最も重視される要素である。実習開始前には必ずオリエンテーションを実施し、標準予防策や各種感染対策について徹底した指導を行う。
また、実習中は毎日の健康チェックと報告を義務付け、感染症の予防と早期発見に努めている。医療事故防止については、インシデント・アクシデントレポートの作成と検討会を通じて、安全な医療の提供について学びを深めている。
入試対策と準備
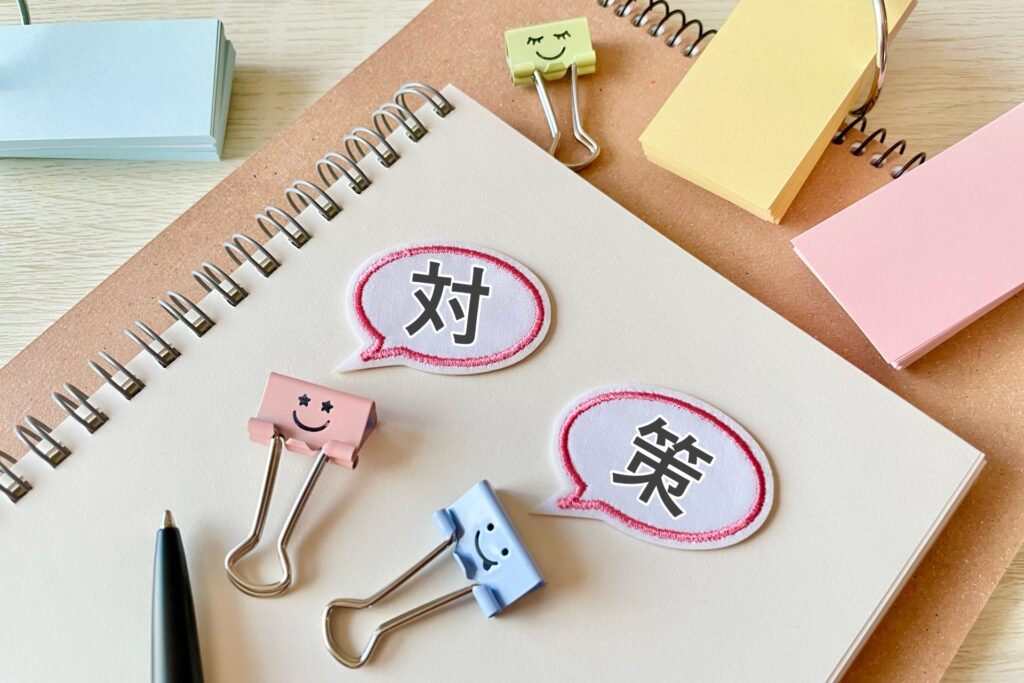
岐阜市立看護専門学校の入学試験は、学科試験と面接試験によって実施される。合格のためには、各試験科目の特性を理解し、計画的な準備を進めることが重要である。ここでは、試験科目ごとの対策方法と、効果的な学習計画の立て方について詳しく解説する。
入試概要と試験科目
一般入試では国語(現代文)、数学Ⅰ、英語の3科目と面接試験が実施される。試験時間は各科目60分で、全科目の得点と面接評価を総合して合否が判定される。特に国語は医療現場でのコミュニケーション能力を測る重要な科目として位置づけられており、記述問題も出題される。
国語の学習方法と対策
国語の試験では、医療や看護に関連する文章の読解力と、論理的な文章表現力が問われる。過去問分析によると、説明文や論説文からの出題が中心となっている。効果的な対策としては、医療系の文章や科学的な文章に慣れることが重要である。
新聞の医療関連記事や医学書の序文なども、良い練習教材となる。記述問題では、要約力と論理的な表現力が求められるため、日頃から文章をまとめる練習を重ねることが必要である。
数学の重点分野と演習方法
数学Ⅰの範囲からの出題となるが、特に医療現場で必要となる計算力を重視した問題が多い。数と式、二次関数、図形と計量の分野からの出題頻度が高く、特に単位換算や濃度計算に関する問題は毎年のように出題される。
学習にあたっては、基本的な計算力の向上を第一に考え、問題演習を通じて解法パターンを身につけていく。医療現場で使用される単位についても理解を深め、確実に計算できるようにしておく必要がある。
英語試験への取り組み方
英語試験では、医療や看護に関連する英文を含む長文読解と、基本的な文法・語彙の理解が問われる。過去の出題傾向を見ると、医療用語や看護場面での会話文などが頻出している。
対策としては、医療英語の基礎的な用語を押さえながら、長文読解の練習を積み重ねることが効果的である。リーディング力の向上には、医療関係の英文記事や看護系の英語教材を活用すると良い。
面接試験対策と準備
面接試験では、志望動機や看護師としての適性、医療・看護に対する理解度などが評価される。質問項目としては、志望理由、看護師を目指したきっかけ、将来の目標などが定番となっている。また、時事問題や医療に関する基本的な知識を問われることもある。
効果的な準備としては、自己分析を深め、志望動機を論理的に説明できるようにすることが重要である。医療や看護に関する時事問題にも日頃から関心を持ち、自分なりの考えを持っておくことが望ましい。
学習計画の立て方
受験までの期間を効果的に活用するため、計画的な学習が不可欠である。一般的な準備期間は6か月から1年程度が望ましく、この期間を基礎固めの期間と実践期間に分けて計画を立てる。基礎固めの期間では、各科目の基本的な内容の理解と基礎力の向上に重点を置く。
実践期間では、過去問演習や模擬試験を通じて実践力を養成する。特に夏季休暇期間は、集中的な学習が可能な重要な時期として位置づけ、苦手分野の克服と得意分野の更なる強化を図る。
受験直前期の過ごし方
試験2週間前からは、それまでの学習内容の総復習と、各科目の要点整理に時間を充てる。この時期は新しい範囲の学習は避け、確実に得点できる分野の再確認を中心に進める。また、実際の試験を想定した時間配分の練習も重要である。
体調管理にも十分注意を払い、規則正しい生活リズムを維持することが大切である。試験前日は無理な学習は避け、持ち物の確認と必要な準備を整えて、心身ともにリラックスした状態で試験に臨めるようにする。
学費・奨学金情報

岐阜市立看護専門学校では、充実した教育環境を提供しながらも、公立校ならではの経済的な学費設定を実現している。また、様々な奨学金制度や経済的支援制度を整備し、学生が安心して学業に専念できる環境づくりに力を入れている。
学費の詳細と納付時期
入学金は282,000円で、入学手続き時に一括での納付が必要となる。年間授業料は535,800円で、前期と後期の2回に分けて納付することができる。
その他、実習費として年間約50,000円、教科書・教材費として初年度約150,000円、2年次以降は年間約50,000円程度が必要となる。実習用のユニフォームや靴などの費用は初年度のみ約80,000円程度が必要である。教科書については、学内の購買部で一括購入することができ、分割払いにも対応している。
利用可能な奨学金制度
日本学生支援機構の奨学金は、第一種(無利子)と第二種(有利子)が利用可能である。第一種奨学金は、自宅通学の場合月額20,000円から54,000円、自宅外通学の場合月額20,000円から64,000円の範囲で選択できる。第二種奨学金は、月額20,000円から120,000円までの中から選択可能である。
また、入学時特別増額貸与奨学金として、100,000円から500,000円までの追加支援を受けることもできる。
岐阜県看護職員修学資金
岐阜県では、将来県内の医療機関などで看護職員として働く意思のある学生を対象に、月額32,000円の修学資金を貸与している。卒業後、県内の指定医療機関などで5年間勤務することで返還が免除される制度となっている。この制度は、地域医療への貢献と経済的支援を両立させた特徴的な支援制度である。
病院奨学金制度の活用
岐阜市民病院をはじめ、県内の多くの医療機関が独自の奨学金制度を設けている。これらの制度は、月額30,000円から50,000円程度の奨学金を貸与し、卒業後に当該医療機関で一定期間勤務することで返還が免除されるものが多い。
入学後に各医療機関の説明会が開催され、詳細な情報提供と個別相談の機会が設けられる。
分割納付制度と緊急支援
授業料については、経済的な事情に応じて分割納付制度を利用することができる。また、家計の急変などにより修学が困難となった場合には、授業料の減免制度を申請することも可能である。
これらの制度利用にあたっては、学生課での個別相談に応じており、それぞれの状況に合わせた支援策を提案している。
就職状況と進路

岐阜市立看護専門学校は開校以来、高い就職率を維持し続けている。充実した臨床実習と実践的な教育プログラムにより、即戦力として活躍できる看護師を多数輩出してきた実績がある。ここでは、具体的な就職状況や充実した就職支援体制について詳しく解説する。
就職実績と主な就職先
直近5年間の就職率は100パーセントを維持しており、多くの卒業生が岐阜県内の主要医療機関で活躍している。就職先の内訳としては、国公立病院が約45パーセント、私立病院が約35パーセント、診療所が約15パーセント、その他の医療施設が約5パーセントとなっている。
特に附属の岐阜市民病院には毎年20名程度が就職し、高度急性期医療の最前線で活躍している。岐阜県総合医療センターや岐阜大学医学部附属病院といった地域の基幹病院への就職実績も多数ある。
キャリア支援体制
就職支援は2年次後半から本格的に開始される。専任の就職支援担当者が配置され、個別相談や履歴書添削、面接指導などのきめ細かなサポートを提供している。また、定期的に就職ガイダンスを開催し、就職活動の進め方や医療機関の選び方についての具体的なアドバイスを行っている。
3年次には、卒業生による就職体験談発表会も実施され、実際の職場の様子や就職活動のポイントを直接聞くことができる。
インターンシップと病院見学
夏季休暇期間中には、県内外の主要医療機関でインターンシップを実施している。これは実際の職場環境を体験し、自身の進路選択に活かすための貴重な機会となっている。また、随時病院見学の機会も設けられており、希望する医療機関の雰囲気や特色を直接確認することができる。
インターンシップや病院見学の調整は就職支援室が一括して行っており、学業との両立を図りながら効率的に参加することが可能である。
国家試験対策と就職支援の連携
就職活動と並行して行われる国家試験対策も、本校の特徴的な支援体制の一つである。3年次には模擬試験を定期的に実施し、弱点分野の把握と対策を行う。また、国家試験対策講座を開講し、試験科目ごとの重点ポイントを確認する機会を設けている。
就職が内定した学生に対しても、安定した学習時間が確保できるよう、就職支援室と教務課が連携してサポートを行っている。
卒業後のキャリア展開
本校の卒業生は、基礎教育で培った実践力を活かし、様々な分野で活躍している。急性期病棟や手術室などの専門領域でスペシャリストとして働く卒業生も多く、認定看護師や専門看護師の資格取得にチャレンジする卒業生も年々増加している。
また、訪問看護ステーションや介護施設など、地域医療の現場で活躍する卒業生も多数輩出している。卒業後も継続的な学習を支援するため、卒後研修プログラムや同窓会ネットワークを通じた情報交換の機会を提供している。
おしえてカンゴさん!よくある質問
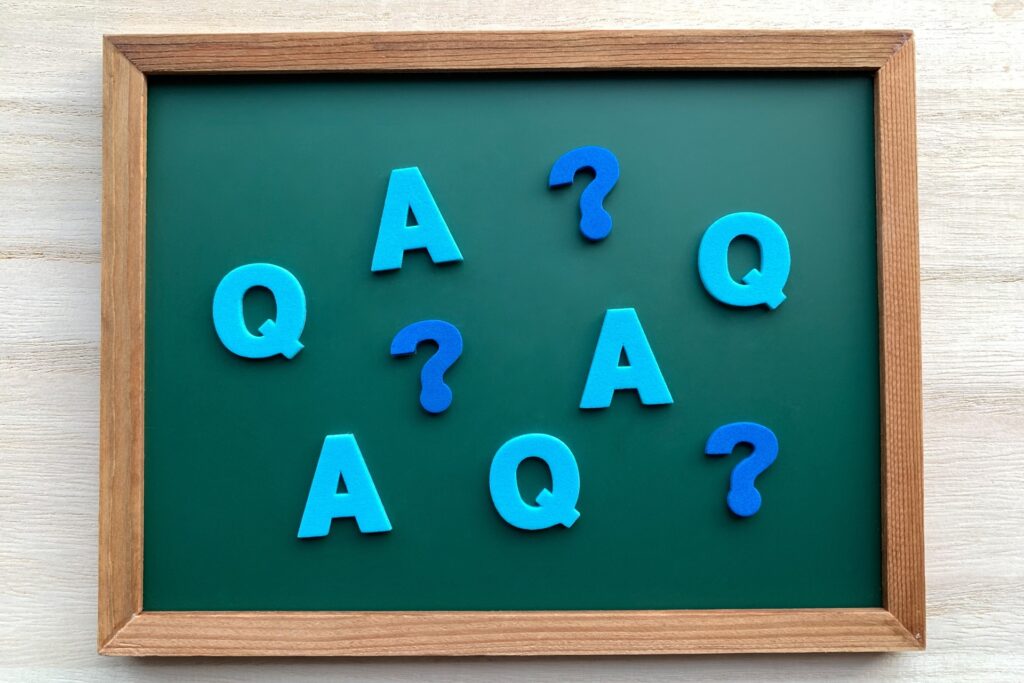
入試・受験に関する質問
Q1:推薦入試の選考基準と対策について詳しく教えてください
推薦入試では、高校での学習成績が重要な評価基準となります。評定平均値3.5以上という基準に加えて、特に看護に関連する科目(生物、化学、保健体育など)での優れた成績が求められます。
また、課外活動やボランティア活動なども評価の対象となり、特に医療や福祉に関連する活動経験は高く評価されます。面接試験では、看護師を志望する明確な動機と、医療や看護に対する深い理解が問われます。
小論文試験対策としては、医療や看護に関する新聞記事やニュースを日頃から読み、自分の考えをまとめる習慣をつけることが重要です。事前に複数の模擬小論文を作成し、論理的な文章構成力を磨くことをお勧めします。
Q2:一般入試の試験科目ごとの配点と合格ラインについて教えてください
一般入試における試験科目の配点は、国語が200点、数学が200点、英語が200点の合計600点満点で実施されます。これに面接試験の評価が100点分加わり、総合700点満点で判定が行われます。過去の実績から、合格者の得点率は総合点で約75%以上となっています。
特に国語は医療現場でのコミュニケーション能力を測る重要な科目として位置づけられており、合格者の平均点は80%以上と高めに設定されています。
数学と英語については、基礎的な計算力や読解力が重視され、それぞれ70%以上の得点率が求められます。面接試験では、受験生の人間性や看護師としての適性が総合的に評価され、合否判定に大きな影響を与えます。
学校生活に関する質問
Q3:1日の授業スケジュールと自己学習の時間配分について教えてください
本校の授業は原則として平日の8時30分から16時30分まで行われます。1コマ90分の授業が1日に4~5コマ設定されており、昼休みは50分間確保されています。授業の間には10分間の休憩時間があり、この時間を活用して次の授業の準備や復習を行うことができます。
多くの学生は放課後の時間を活用して自己学習を行っており、平均して1日2~3時間程度の学習時間を確保しています。
図書室や自習室は19時まで利用可能で、グループ学習室も完備されているため、クラスメートと協力しながら効率的に学習を進めることができます。実習期間中は実習記録の作成に時間を要するため、より計画的な時間配分が必要となります。
Q4:寮生活について詳しく教えてください
本校の学生寮は、岐阜市民病院に隣接して設置されており、女子学生専用の施設となっています。個室タイプの居室には、ベッド、机、椅子、クローゼット、エアコンが標準装備されており、インターネット環境も完備されています。
共用施設として、キッチン、ランドリールーム、シャワールーム、談話室があり、24時間利用可能です。寮費は月額30,000円で、これには光熱水費も含まれています。寮内では寮生同士の交流も活発で、上級生から学習面でのアドバイスを受けることもできます。
通学時間を気にすることなく学習に集中できる環境が整っており、特に実習期間中は早朝からの準備や夜間の学習にも対応しやすいという利点があります。
キャリアプランに関する質問
Q5:卒業後の進路選択について具体的に教えてください
本校の卒業生は、その95%以上が看護師として医療機関に就職しています。就職先としては急性期病院が最も多く、特に岐阜市民病院をはじめとする県内の基幹病院への就職実績が豊富です。診療科別では、内科系、外科系、救急部門、手術室など、様々な部署で活躍しています。
また、近年は訪問看護ステーションや介護施設など、地域医療の現場で活躍する卒業生も増加傾向にあります。進学を選択する卒業生も一定数おり、看護系大学への編入学や、認定看護師・専門看護師の資格取得を目指してキャリアアップを図るケースもあります。
本校では卒業後のキャリア形成についても継続的な支援を行っており、定期的な情報提供や相談対応を実施しています。
学習支援に関する質問
Q6:学習支援体制について具体的に教えてください
本校の学習支援は、個別指導を基本として、学生一人ひとりの理解度と進度に合わせたきめ細かなサポートを提供しています。専任教員によるオフィスアワーが週に数回設定されており、授業内容の質問や学習方法の相談に応じています。
また、定期的に実施される到達度確認テストの結果を基に、必要に応じて補習授業や個別指導を実施します。図書室には専門の司書が常駐しており、文献検索や資料収集のサポートも充実しています。
グループ学習を促進するための支援も行っており、学習スペースの提供や教材の貸出、ディスカッションの機会を設けるなど、学生同士が学び合える環境を整えています。
Q7:国家試験対策の支援内容について詳しく教えてください
本校の国家試験対策は、3年次から本格的に始動し、段階的かつ計画的なプログラムを展開しています。まず、定期的な模擬試験を実施し、個々の学生の弱点分野を早期に把握します。その結果を基に、個別の学習計画を立案し、必要に応じて補習や個別指導を実施します。
また、外部講師を招いての特別講座や、過去問題の分析会なども定期的に開催しています。さらに、グループ学習を推進し、学生同士で問題を出し合ったり、解説し合ったりする機会も設けています。直前期には、弱点克服のための集中講座や、本番を想定した模擬試験を実施し、実践力の向上を図ります。
実習に関する質問
Q8:臨床実習の1日のスケジュールについて教えてください
臨床実習は通常、朝8時から始まります。まず、実習室で朝のカンファレンスを行い、その日の行動計画や注意点を確認します。8時30分からは病棟での実習が始まり、受け持ち患者さんのバイタルサインの測定や清潔ケアなどの日常生活援助を行います。
午前中は主に患者さんのケアや処置の見学・実施に充てられ、昼休憩を挟んで午後は看護記録の作成や新たな看護計画の立案などを行います。16時からは病棟でのカンファレンスがあり、1日の振り返りと翌日の計画を確認します。その後、実習記録の作成に取り組み、通常18時頃に実習が終了します。
Q9:受け持ち患者さんとの関わり方について教えてください
受け持ち患者さんとの関わりでは、まず信頼関係の構築が最も重要となります。初日は自己紹介から始まり、患者さんの基本情報や現在の状態について、カルテや申し送りなどから情報収集を行います。
日々の関わりでは、バイタルサインの測定や清潔ケアなどの基本的な看護技術を提供しながら、患者さんの気持ちや要望に耳を傾けることを大切にします。
得られた情報は看護記録に詳細に記載し、患者さんの変化や反応を丁寧に観察・記録します。また、受け持ち患者さんの疾患や治療について深く学び、個別性を考慮した看護計画を立案・実施していきます。
Q10:実習記録の書き方のコツを教えてください
実習記録は看護実践の根拠と評価を明確にするための重要なツールです。記録の基本は、客観的事実と主観的情報を明確に区別して記載することです。情報収集では、患者さんの言動や表情、バイタルサインなどの客観的データを正確に記録し、それに対する自己の気づきや解釈を区別して記載します。
アセスメントでは、収集した情報を関連づけながら、科学的根拠に基づいて患者さんの状態を分析します。看護計画は具体的な表現で、誰が見ても理解できる内容にすることが重要です。実施した看護とその結果、患者さんの反応についても詳細に記録し、計画の評価と修正に活かします。
学費・経済支援に関する質問
Q11:奨学金の選択と申請方法について具体的に教えてください
本校で利用可能な奨学金は、日本学生支援機構、岐阜県看護職員修学資金、各医療機関の奨学金など、複数の選択肢があります。日本学生支援機構の奨学金は、第一種(無利子)と第二種(有利子)があり、世帯収入や学業成績によって選考されます。
岐阜県看護職員修学資金は、卒業後に県内医療機関で一定期間勤務することで返還が免除される制度です。各医療機関の奨学金も同様のシステムが多く、就職先と連動した経済支援を受けることができます。
申請手続きは入学前から開始できるものもあり、学生課で個別相談に応じながら、最適な支援制度の選択をサポートしています。
設備・施設に関する質問
Q12:図書室の利用方法と開室時間について教えてください
図書室は平日8時から19時まで、土曜日は9時から17時まで開室しています。蔵書数は専門書を中心に約20,000冊を有し、医学・看護系の学術雑誌も定期購読しています。パソコンコーナーには10台のPCが設置され、文献検索やレポート作成に活用できます。
閲覧席は50席あり、個人学習スペースとグループ学習室も完備されています。図書の貸出は1回につき5冊まで、2週間借りることができます。
また、他の医療機関の図書室との相互利用システムも整備されており、より専門的な文献も入手可能です。専任の司書が常駐しており、文献検索や資料収集のサポートも充実しています。
入学後の生活に関する質問
Q13:サークル活動について詳しく教えてください
本校には文化系と運動系合わせて10のサークルが活動しています。看護研究サークル、ボランティアサークル、スポーツサークルなどがあり、それぞれ週1回程度の活動を行っています。
特に看護研究サークルでは、最新の医療技術や看護ケアについての勉強会を定期的に開催し、専門知識の向上を図っています。ボランティアサークルは地域の健康イベントや高齢者施設での活動に参加し、実践的なコミュニケーション能力を養っています。
運動系サークルは体育館や近隣の体育施設を利用して活動し、他校との交流戦なども行っています。サークル活動は学業との両立を前提としており、実習期間中は活動を調整して行います。
教育内容に関する質問
Q14:シミュレーション教育の具体的な内容を教えてください
シミュレーション教育センターには、最新の高機能シミュレータが複数台設置されています。これらのシミュレータは、心肺音の聴取や血圧測定、呼吸音の確認など、基本的なフィジカルアセスメントの練習に活用されます。
また、急変時の対応や救急処置のトレーニングも行うことができ、実際の医療現場で遭遇する可能性のある様々な状況を安全に体験することができます。
シミュレーション演習は少人数グループで実施され、実施後には必ずデブリーフィング(振り返り)を行い、実践した看護ケアの意図や判断の根拠について討議します。
また、録画機能を活用して自身の動きを客観的に確認し、より効果的な技術の習得を目指します。専任教員が常駐しており、基本的な看護技術から高度な救急処置まで、段階的な学習を支援しています。
Q15:多職種連携教育の内容について具体的に教えてください
多職種連携教育は、実際の医療現場を想定したチーム医療の実践力を養うプログラムです。医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士など、様々な医療専門職の役割と連携方法について学びます。
具体的には、複数の職種が参加するカンファレンスの実施方法や、他職種とのコミュニケーションスキル、情報共有の重要性などについて、事例を用いて学習します。
また、岐阜市民病院の各部門の専門職を講師として招き、実践的な連携方法についての講義や演習も行われます。実習では実際のチームカンファレンスに参加し、多職種連携の実際を体験的に学ぶことができます。
Q16:在宅看護学実習の具体的な内容について教えてください
在宅看護学実習では、訪問看護ステーションを拠点として、実際の在宅療養者宅を訪問し、看護ケアを実践します。実習開始前には、在宅看護の特性や訪問マナー、感染予防対策などについて詳しく学びます。
訪問看護では、療養者の生活環境を理解し、その人らしい暮らしを支援するための看護計画を立案します。また、家族支援の方法や在宅でのリスクマネジメント、他職種との連携方法についても実践的に学びます。
在宅での医療処置や日常生活援助の実際を体験し、病院とは異なる在宅ならではの看護の視点や工夫について理解を深めます。地域包括ケアシステムにおける訪問看護の役割についても学習します。
Q17:成人看護学実習の内容と特徴について教えてください
成人看護学実習は、急性期と慢性期の二つの領域で実施されます。急性期実習では、手術を受ける患者さんの周手術期看護を中心に学びます。術前の不安への対応から、術後の観察、早期離床の援助まで、周手術期に必要な看護技術を実践します。
慢性期実習では、生活習慣病や慢性疾患を持つ患者さんの看護を学び、セルフケア能力の向上を支援する方法や患者教育の実際について理解を深めます。
両領域とも、受け持ち患者さんの看護過程を展開し、個別性を重視した看護計画の立案と実施を行います。また、チーム医療の一員として、多職種との連携や情報共有の重要性についても学びます。
Q18:ICTを活用した学習支援システムについて教えてください
本校のICT学習支援システムは、時間や場所を問わず効率的な学習を可能にする環境を提供しています。オンライン学習プラットフォームでは、授業で使用する資料や動画教材がいつでも閲覧可能で、予習・復習に活用できます。
また、小テストやレポート提出もオンラインで行うことができ、教員からのフィードバックも迅速に受けることができます。
実習期間中は、電子カルテの模擬システムを使用して記録方法を学んだり、シミュレーション教育の振り返り動画を視聴したりすることができます。さらに、学生同士のディスカッションフォーラムも設置されており、意見交換や情報共有も活発に行われています。
Q19:老年看護学実習の具体的な内容について教えてください
老年看護学実習は、高齢者の特性を理解し、その人らしい生活を支援するための看護実践能力を養うことを目的としています。実習は、急性期病棟、回復期リハビリテーション病棟、介護老人保健施設など、様々な場所で行われます。
高齢者の身体的・精神的・社会的特徴を理解し、適切なアセスメントに基づいた看護計画を立案します。認知症ケアや終末期ケア、生活リハビリテーション、転倒予防など、高齢者特有の看護技術についても実践的に学びます。
また、高齢者とその家族への支援方法や、多職種との連携による包括的なケアの提供についても理解を深めます。
Q20:母性看護学・小児看護学実習の特徴について教えてください
母性看護学実習は、妊娠期から産褥期までの母子とその家族への看護を学びます。産科病棟での実習では、妊婦健診や分娩介助の見学、産褥期の母子への看護ケアを実践します。また、新生児室での実習も行い、新生児の観察方法やケア技術を習得します。
小児看護学実習では、小児病棟や小児科外来、保育所などで実習を行います。子どもの成長発達段階に応じた看護ケアの方法や、家族への支援、プレパレーションの実際について学びます。両実習とも、対象者の特性を理解し、安全で安楽なケアの提供方法について実践的に学習を進めます。
岐阜市立看護専門学校の総合案内
歴史と実績ある教育機関としての基盤
伝統と実績
岐阜市立看護専門学校は、昭和41年の開校以来、地域医療の最前線で活躍する4,000名以上の看護師を輩出してきた歴史ある教育機関である。岐阜市民病院を主たる実習施設とし、早期から臨床現場での実践的な学びを重視した教育を展開することで、即戦力となる看護師の育成に成功している。
教育理念と目標
「人間性豊かな看護実践者の育成」を教育理念として掲げ、科学的根拠に基づいた確かな看護実践力の育成、患者の心に寄り添える豊かな人間性の涵養、地域医療に貢献できる専門職としての使命感の醸成を重点的に追求している。
充実した教育環境と施設設備
最新の教育設備
岐阜市民病院に併設された立地を活かし、最新の医療機器や設備を用いた実践的な学習環境を提供している。高機能患者シミュレータを使用した演習や、最新のICT機器を活用した遠隔授業にも対応し、24時間利用可能な自習室や充実した図書室も完備されている。
シミュレーション教育の実践
シミュレーション教育センターでは、複数台の高機能シミュレータを活用し、基本的なフィジカルアセスメントから高度な救急処置まで、段階的な技術習得を可能にしている。実施後のデブリーフィングを通じて、実践した看護ケアの振り返りと改善を行っている。
体系的なカリキュラム構成
1年次教育
1年次では看護の基礎となる医学的知識と基本的な看護技術の習得に焦点を当てている。解剖生理学や生化学などの基礎医学、看護学概論や基礎看護技術などの専門基礎分野を学習し、後期からは基礎看護学実習を通じて実践的なスキルの向上を図る。
2年次教育
2年次からは専門分野の学習が本格化し、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学などの各専門領域について深く学習する。臨床実習も本格的に開始され、学内で学んだ知識と技術を実践の場で統合していく。
3年次教育
3年次では、より高度な専門知識と技術の習得を目指し、各専門領域の実習を深化させるとともに、在宅看護論や看護の統合と実践を学ぶ。医療安全や災害看護、国際看護など、現代の医療ニーズに対応した内容も含まれる。
実践的な実習プログラム
実習施設との連携
岐阜市民病院を中心とした実習環境により、高度急性期医療から在宅支援まで幅広い医療現場での実習が可能である。臨床経験豊富な専任教員と実習指導者による密接な連携のもと、きめ細かな指導を実施している。
段階的な実習展開
基礎看護学実習から始まり、各専門分野の実習へと段階的に進む構成により、確実な技術の習得と看護実践能力の向上を図っている。3年次の統合実習では、チーム医療の一員としての役割を実践的に学ぶ。
充実した学習支援体制
個別指導体制
専任教員によるオフィスアワーの設定や、定期的な到達度確認テストの実施により、学生一人ひとりの理解度に応じた支援を提供している。図書室には専門の司書が常駐し、文献検索や資料収集のサポートも充実している。
国家試験対策
3年次から本格的な国家試験対策を開始し、定期的な模擬試験の実施や弱点分野の個別指導、外部講師による特別講座などを通じて、高い合格率を維持している。
経済的支援と就職支援
奨学金制度
日本学生支援機構の奨学金に加え、岐阜県看護職員修学資金や各医療機関独自の奨学金制度など、複数の経済的支援制度を利用することができる。公立校ならではの経済的な学費設定も特徴である。
キャリア支援
就職支援は2年次後半から本格的に開始され、個別相談や履歴書添削、面接指導などのきめ細かなサポートを提供している。インターンシップや病院見学の機会も豊富に設けられている。
卒業後の進路とキャリア展開
就職実績
直近5年間の就職率は100パーセントを維持しており、多くの卒業生が岐阜県内の主要医療機関で活躍している。特に岐阜市民病院への就職実績が多く、高度急性期医療の最前線で活躍している。
キャリアアップ支援
卒業後も認定看護師や専門看護師の資格取得にチャレンジする卒業生が増加しており、継続的な学習を支援するための卒後研修プログラムや同窓会ネットワークを通じた情報交換の機会を提供している。
地域医療への貢献
地域との連携
地域包括ケア教育の一環として、在宅療養者への訪問看護演習や地域の健康教室での実践的な学習機会を提供している。地域医療の担い手として、確かな実践力を持つ看護師の育成に力を入れている。
将来展望
今後も地域医療の中核を担う看護師の育成機関として、時代のニーズに応じた教育プログラムの改善と充実を図り、より質の高い看護教育を提供していく方針である。
まとめ
岐阜市立看護専門学校は、昭和41年の開校以来4,000名以上の看護師を輩出してきた伝統校です。岐阜市民病院を主たる実習施設とし、早期から臨床現場での実践的な学びを重視した教育を展開しています。
充実したシミュレーション教育センターや最新のICT機器を活用した教育環境、段階的な実習プログラム、手厚い学習支援体制が特徴です。3年間の課程では、基礎医学から専門分野まで体系的なカリキュラムを通じて、確かな看護実践力と豊かな人間性を育みます。
直近5年間の就職率100%、充実した奨学金制度、きめ細かな国家試験対策など、将来のキャリアを見据えたサポート体制も整っています。看護師を目指す方へ より詳しい看護学校の情報や、現役看護師の生の声、就職活動のアドバイスなどは「はたらく看護師さん」でご覧いただけます。
看護師として働くイメージをより具体的に掴みたい方は、ぜひご登録ください。実務経験豊富な看護師による記事や、看護学生向けの特集も随時更新中です!
→「はたらく看護師さん」で看護の仕事の実際をチェック!
参考文献
- 岐阜市民病院看護部資料
- 日本学生支援機構奨学金案内