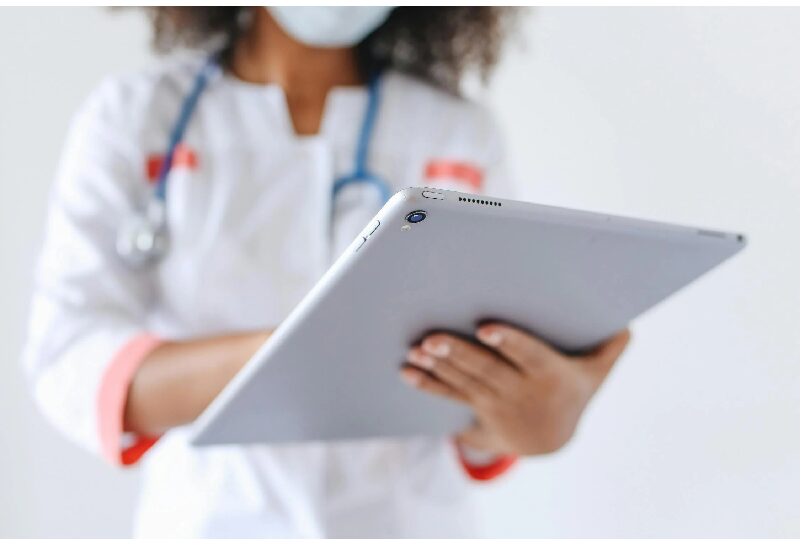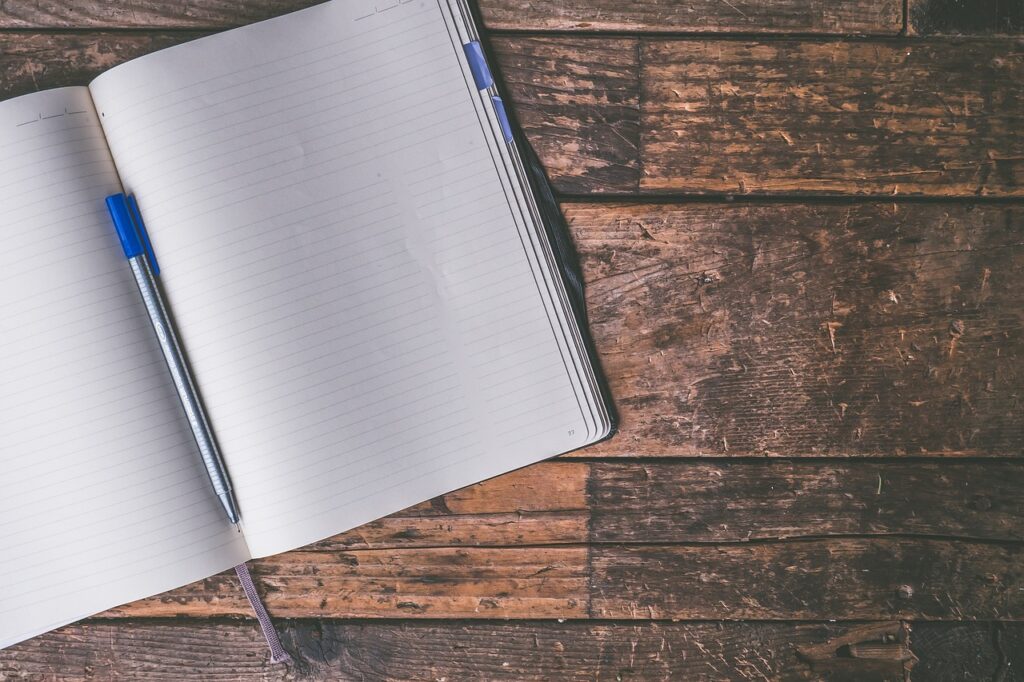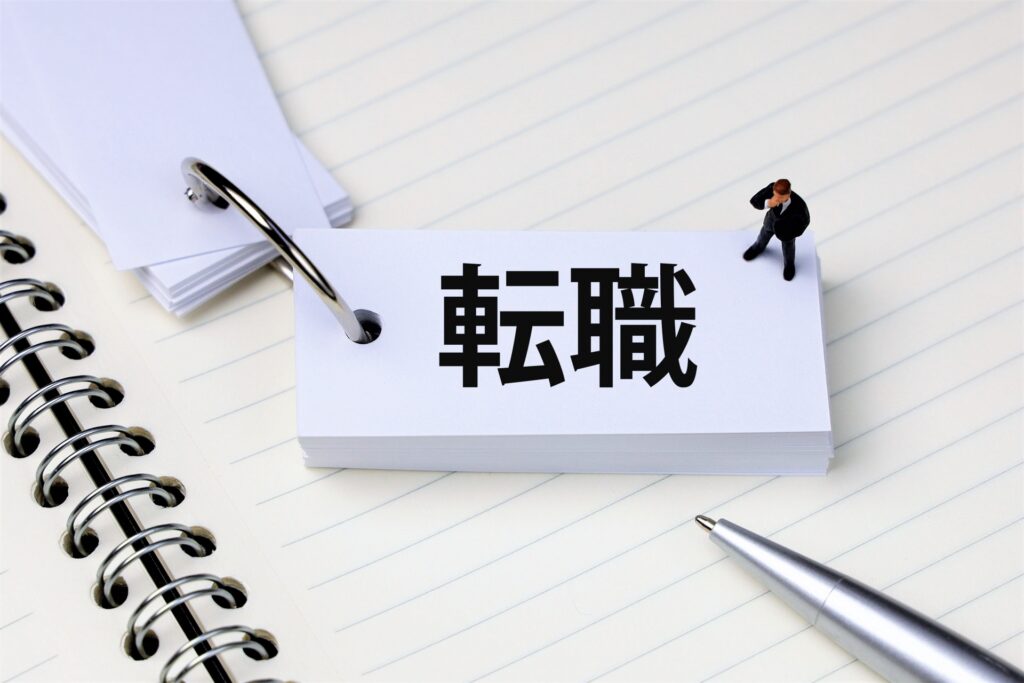訪問看護指示書における傷病名コードの管理と運用は、医療事務職員と訪問看護師の重要な業務課題となっています。
本記事では、15年以上の医療事務経験を持つ筆者が、傷病名コードの基本的な考え方から具体的な運用方法まで、実務に即した知識とノウハウを詳しく解説していきます。2024年の制度改定に対応した最新情報も含め、現場で実践できる具体的な手順とポイントをお伝えしていきます。
この記事を読んでほしい人
- 訪問看護指示書の作成業務を担当している医療事務職員の方
- 傷病名コードの基礎から実践的な運用方法までを学びたい訪問看護師の方
- 医療機関でレセプト業務の効率化を目指している実務担当者の方
- 傷病名コードの管理体制の見直しを検討している管理職の方
この記事で分かること
- 2024年の制度改定を踏まえた最新の傷病名コードの体系と構造
- 訪問看護指示書における傷病名コードの正しい記載方法とチェックポイント
- 現場で活用できる効率的な運用手順とベストプラクティス
- レセプト請求を見据えた確認方法と一般的なミスの防止策
- 多職種連携を考慮した傷病名コードの効果的な管理方法
はじめに
今回は以下の構成で、傷病名コードに関する実践的な知識を体系的に解説していきます。
第1章では傷病名コードの基本体系について、制度の背景や目的から、具体的なコードの構造まで詳しく説明します。
続く第2章では、訪問看護指示書における実際の記載方法を、具体例を交えながら解説します。第3章以降では、実務における運用手順や、システムを活用した効率的な管理方法、さらには事例別の対応方法まで、段階的に理解を深めていけるよう構成しています。
本記事の内容は、実際の医療現場での経験と、最新の制度に基づいて作成されています。日々の業務における具体的な課題解決に役立つ情報を提供することで、医療事務職員や訪問看護師の皆様の業務効率化をサポートしていきます。特に、2024年の制度改定による変更点については、実務への影響を考慮しながら丁寧に解説しています。
各章では、単なる知識の解説だけでなく、実際の医療現場で活用できる具体的なテクニックやノウハウもお伝えしていきます。また、よくある質問やトラブルへの対処方法についても、実例を交えながら詳しく説明していきます。
傷病名コードの基本体系

傷病名コードは、医療機関における診療報酬請求や患者情報の管理を標準化するための重要な識別システムです。
このセクションでは、2024年の制度改定を踏まえた最新の傷病名コードの体系について、基礎から実践的な知識まで詳しく解説していきます。医療事務職員や訪問看護師の方々が、日常業務で確実に活用できるよう、具体例を交えながら説明していきます。
傷病名コードの概要と重要性
医療現場において、傷病名コードは患者さんの診断情報を正確に伝達し、適切な診療報酬請求を行うための基盤となっています。
2024年の診療報酬改定では、より効率的な医療情報の管理と多職種連携の促進を目指し、傷病名コードの体系が一部見直されました。特に訪問看護の分野では、在宅医療の推進に伴い、正確な傷病名コードの運用がこれまで以上に重要となっています。
コードの基本構造と体系
傷病名コードは、基本分類コード、補助分類コード、修飾語コードという三つの要素で構成されています。基本分類コードは4桁の数字で表され、疾患の基本的な分類を示します。
これに1桁の補助分類コードが加わることで、疾患の詳細な状態や経過を表現することができます。さらに、2桁の修飾語コードを組み合わせることで、より具体的な病態や症状を正確に記録することが可能となります。
基本分類コードの詳細
基本分類コードは、国際疾病分類(ICD-10)に準拠しており、アルファベットと数字の組み合わせで構成されています。例えば、高血圧症の場合はI10という基本分類コードが割り当てられています。
このコードは、循環器系の疾患を表すIで始まり、その後に続く数字で具体的な疾患を特定します。2024年の改定では、新たな疾患概念や治療法の進歩を反映し、いくつかのコードが追加または変更されました。
補助分類コードの役割
補助分類コードは、疾患の性質や状態をより詳細に表現するために使用されます。急性や慢性といった経過の違い、右側や左側といった部位の特定、さらには疾患の重症度なども、この補助分類コードによって表現されます。医療現場での正確な情報共有のために、適切な補助分類コードの選択が重要となります。
修飾語コードの活用方法
修飾語コードは、疾患の状態や症状をより具体的に表現するために使用される2桁の数字です。例えば、「重症」「軽症」といった重症度の表現や、「術後」「急性増悪」といった状態の変化を示すために活用されます。適切な修飾語コードの選択により、患者さんの状態をより正確に記録することができます。
2024年改定におけるの主要な変更点
2024年の診療報酬改定では、医療の高度化や在宅医療の推進に対応するため、傷病名コードにいくつかの重要な変更が加えられました。特に訪問看護に関連する部分では、在宅医療で頻繁に使用される傷病名のコードが整理され、より実務に即した体系となっています。
新規追加されたコード
今回の改定では、特に在宅医療の分野で使用頻度の高い傷病名について、新たなコードが追加されました。これにより、訪問看護の現場でより正確な病態の記録が可能となっています。また、医療技術の進歩に伴う新しい治療法や診断基準にも対応できるよう、関連するコードが整備されました。
統合・廃止されたコード
医療の実態に合わせて、一部のコードが統合または廃止されました。特に、類似した病態を示す複数のコードが一つに統合されるなど、より効率的な運用が可能となる改定が行われています。これにより、コードの選択がより明確になり、実務での運用効率が向上することが期待されます。
コード体系の基本原則
傷病名コードの運用において最も重要な原則は、正確性と一貫性です。同じ疾患に対して常に同じコードが使用されることで、医療機関間での情報共有がスムーズになり、適切な診療報酬請求が可能となります。また、電子カルテシステムやレセプトコンピュータとの連携においても、この原則が重要な役割を果たします。
主傷病と副傷病の区別
訪問看護指示書には、主傷病と副傷病を明確に区別して記載する必要があります。主傷病は、その時点で最も医療資源を投入している病態を示し、副傷病はそれ以外の関連する病態を示します。この区別は、適切な診療報酬請求と、多職種間での情報共有において重要な役割を果たします。
コード選択の基本ルール
傷病名コードの選択には、いくつかの基本的なルールがあります。まず、できるだけ具体的な病態を示すコードを選択することが重要です。また、複数の病態が存在する場合は、それぞれの関連性を考慮しながら、適切なコードの組み合わせを選択する必要があります。2024年の改定では、このような選択の判断基準がより明確化されています。
訪問看護指示書における記載方法

訪問看護指示書への傷病名コードの記載は、診療報酬請求の正確性と多職種連携の基盤となる重要な業務です。このセクションでは、実務経験に基づいた具体的な記載方法と、日常業務でよく遭遇する事例への対応方法を詳しく解説していきます。2024年の制度改定による変更点にも触れながら、確実な実務遂行のためのポイントをお伝えします。
基本的な記載手順とルール
訪問看護指示書における傷病名コードの記載には、明確なルールと手順があります。まず、診療録から適切な傷病名を選択し、それに対応する正確なコードを特定します。
その際、主傷病と副傷病を明確に区別し、それぞれの重要度に応じた適切な記載順序を考慮する必要があります。2024年の改定では、特に在宅医療に関連する傷病名の記載方法について、いくつかの重要な変更点が加えられています。
診療録からの傷病名選択
診療録から傷病名を選択する際は、患者さんの現在の状態を最も適切に表現する傷病名を選ぶことが重要です。医師の記載した診療録の内容を正確に理解し、標準病名マスターに収載されている適切な傷病名との対応を確認します。特に、略語や慣用的な表現が使用されている場合は、正式な傷病名への変換を慎重に行う必要があります。
コードの正確な転記方法
選択した傷病名に対応するコードの転記は、細心の注意を払って行います。基本分類コード、補助分類コード、修飾語コードのそれぞれについて、誤記や脱字がないよう、必ず複数回の確認を行います。特に、似通ったコード番号が存在する場合は、より慎重な確認が必要となります。
電子カルテシステムでの入力手順
電子カルテシステムを使用している場合の入力手順について説明します。システムの傷病名マスターから適切な傷病名を検索し、対応するコードを選択します。この際、システムの補助機能を活用することで、入力ミスを防ぐことができます。また、定期的なマスターの更新確認も重要な業務となります。
手書き記載での注意点
紙の訪問看護指示書に手書きで記載する場合は、さらに慎重な対応が必要です。数字とアルファベットの判別が容易となるよう、明確な文字で記載します。特に、数字の「0」と英字の「O」、数字の「1」と英字の「I」など、紛らわしい文字については特に注意が必要です。
主傷病と副傷病の記載順序
主傷病と副傷病の記載順序には、明確な基準があります。主傷病は、現在の訪問看護サービス提供において最も重要な病態を示すものを選択します。続いて、治療上考慮すべき順序で副傷病を記載していきます。この順序付けは、多職種での情報共有や診療報酬請求の観点からも重要となります。
重症度による優先順位付け
傷病名の記載順序を決定する際は、各疾患の重症度を考慮します。生命に関わる重要な病態や、現在の医療資源投入量が多い病態を上位に記載します。また、治療の優先順位や、患者さんの日常生活への影響度なども考慮に入れる必要があります。
関連する傷病名のグループ化
複数の傷病名が相互に関連している場合は、それらをグループとして記載することで、病態の全体像をより分かりやすく示すことができます。例えば、基礎疾患とそれに起因する合併症は、連続して記載することが望ましいとされています。
記載内容の確認方法
記載した内容の確認は、複数の視点から行う必要があります。まず、選択した傷病名とコードの対応関係が正確であることを確認します。次に、記載順序の適切性や、必要な修飾語の付加が適切に行われているかを確認します。
一次確認のポイント
一次確認では、基本的な記載内容の正確性を確認します。具体的には、コードの桁数や形式が正しいか、必要な修飾語が適切に選択されているか、主傷病と副傷病の区別が明確になっているかなどを確認します。この段階での確認は、記載者自身が責任を持って行います。
二次確認の実施方法
二次確認は、可能な限り別の担当者が行うことが望ましいとされています。特に、診療報酬請求に直接影響する部分については、複数の目でのチェックが重要です。確認者は、単にコードの正確性だけでなく、医学的な整合性についても注意を払う必要があります。
よくある記載ミスとその防止策
実務において発生しやすい記載ミスには、いくつかの典型的なパターンがあります。これらを事前に理解し、適切な防止策を講じることで、より確実な業務遂行が可能となります。
コードの誤転記防止
コードの誤転記を防ぐためには、システムによるチェック機能の活用や、定期的な確認作業の実施が効果的です。特に、手書き記載の場合は、数字の判別ミスを防ぐための工夫が必要となります。また、よく使用する傷病名については、コード一覧表を作成して参照することも有効です。
最新マスターとの整合性確認
傷病名マスターは定期的に更新されるため、常に最新版との整合性を確認する必要があります。特に、改定時期には注意が必要です。マスターの更新情報を定期的にチェックし、必要に応じて使用しているコードの見直しを行います。
修飾語の適切な使用
修飾語の使用には特に注意が必要です。過剰な修飾語の使用や、不適切な組み合わせによるエラーを防ぐため、定期的な研修や確認作業が重要となります。また、よく使用する修飾語については、適用の基準を明確化しておくことが望ましいでしょう。
運用手順とベストプラクティス
傷病名コードの効率的な運用は、医療事務業務の質と生産性を大きく左右します。このセクションでは、実務経験から得られた効果的な運用手順と、現場で実践されているベストプラクティスについて解説していきます。2024年の制度改定に対応した新しい運用方法も含めて、実践的なノウハウをお伝えします。
標準的な運用フローの確立
効率的な傷病名コード管理には、明確な運用フローの確立が不可欠です。診療録の確認から、コードの選択、記載、確認までの一連の流れを標準化することで、ミスを防ぎつつ業務効率を向上させることができます。特に、複数のスタッフが関わる場合は、統一された手順の徹底が重要となります。
日次業務の基本フロー
朝礼での申し送り事項の確認から始まり、新規患者の傷病名登録、既存患者の傷病名更新、そして夕方のデータ確認まで、一日の業務の流れを明確に定めることが重要です。特に、医師からの新たな指示や変更指示への対応は、可能な限り即日処理することが望ましいとされています。
朝礼での情報共有
朝礼では、前日からの継続案件や新規案件の確認を行います。特に注意が必要な症例や、複雑な傷病名の登録が必要なケースについては、担当者間で認識を共有します。また、その日の業務量を把握し、必要に応じて担当の調整を行います。
診療時の即時対応
医師の診療中に発生する傷病名の追加や変更については、可能な限りリアルタイムでの対応を心がけます。これにより、後回しにすることによる記載漏れや誤記を防ぐことができます。特に、重要度の高い変更については、優先的に対応する体制を整えます。
週次・月次の確認業務
週に一度は全患者の傷病名登録状況を確認し、月末には請求前の最終チェックを行います。特に、長期に渡って変更のない傷病名については、現状との整合性を確認する必要があります。また、定期的なバックアップも重要な業務となります。
効率化のためのツール活用
傷病名コードの運用効率を高めるために、様々なツールやシステムを活用することができます。電子カルテシステムの機能を最大限に活用することはもちろん、補助的なツールの導入も検討に値します。
マスター管理ツール
傷病名マスターを効率的に管理するためのツールを活用することで、コードの検索や更新作業を効率化できます。特に、頻用する傷病名については、カスタマイズした簡易検索機能を設定することも有効です。
チェックリストの活用
日常的な確認作業を確実に行うため、専用のチェックリストを作成して活用します。特に、新規登録時や変更時には、必要な確認項目を漏れなくチェックすることが重要です。
多職種連携のための運用ポイント
傷病名コードの運用には、医師、看護師、医療事務職員など、多くの職種が関わります。それぞれの立場や役割を理解し、円滑な連携を実現するための工夫が必要です。
職種間のコミュニケーション
医師からの指示内容を正確に理解し、適切なコードに変換するためには、必要に応じて確認や質問ができる関係性を構築することが重要です。また、看護師との情報共有も、患者さんの状態を正確に把握する上で不可欠となります。
情報共有の仕組み作り
定期的なカンファレンスや申し送りの機会を活用し、傷病名に関する情報を共有します。特に、複雑なケースや新規の運用ルールについては、全員が同じ認識を持てるよう、丁寧な説明と確認が必要です。
教育・研修体制の確立
新人教育から継続的なスキルアップまで、計画的な教育・研修体制を確立することが重要です。特に、制度改定時には、全スタッフが新しいルールを確実に理解できるよう、適切な研修機会を設けることが必要です。
新人教育プログラム
新しく配属されたスタッフに対しては、基本的な知識から実践的なスキルまで、段階的に学べる教育プログラムを用意します。実際の業務に即した演習を含めることで、より効果的な学習が可能となります。
継続的なスキルアップ
実務経験者に対しても、定期的な研修機会を設けることが重要です。特に、制度改定や新しいシステムの導入時には、十分な学習時間を確保する必要があります。また、日常業務の中で発生した課題や疑問点について、随時相談できる体制を整えることも重要です。
定期的な運用手順の見直し
業務の効率性と正確性を維持するために、定期的に運用手順の見直しを行うことが重要です。現場からのフィードバックを基に、より良い業務フローを検討し、必要に応じて改善を加えていきます。
現状分析と課題抽出
現在の運用手順における課題や非効率な部分を洗い出し、改善の余地がないか検討します。特に、ミスが発生しやすいポイントや、時間がかかる作業については、重点的に見直しを行います。
改善策の検討と実施
抽出された課題に対して、具体的な改善策を検討します。新しい運用手順を導入する際は、試験運用期間を設けるなど、慎重に進めることが望ましいでしょう。また、改善後の効果測定も忘れずに行います。
システムとツールの活用

医療現場における傷病名コードの管理には、様々なシステムやツールが活用されています。このセクションでは、2024年現在で利用可能な主要なシステムの特徴や、効果的な活用方法について解説していきます。特に、訪問看護指示書の作成・管理における具体的な運用方法を中心に、実践的な活用のポイントをお伝えします。
電子カルテシステムの活用
現代の医療機関では、電子カルテシステムが傷病名コード管理の中心的な役割を果たしています。システムの基本機能を理解し、効果的に活用することで、業務の正確性と効率性を大きく向上させることができます。
基本機能の確認
電子カルテシステムには、傷病名の検索機能、コードの自動変換機能、チェック機能など、多くの便利な機能が搭載されています。これらの機能を十分に理解し、活用することで、日常業務の効率を大きく向上させることができます。特に、傷病名の検索機能では、キーワードやコードからの逆引きなど、様々な検索方法が用意されています。
検索機能の効率的な使用
傷病名の検索では、部分一致検索や類似語検索などの機能を活用することで、必要な傷病名を素早く見つけることができます。また、よく使用する傷病名をお気に入りとして登録しておくことで、さらに検索時間を短縮することが可能です。
コード自動変換の活用
多くのシステムには、一般的な病名から適切なコードへの自動変換機能が搭載されています。この機能を活用することで、手入力による誤りを防ぎ、効率的なコード登録が可能となります。
データ連携の設定
電子カルテシステムと他のシステムとのデータ連携は、業務効率を大きく左右します。特に、レセプトコンピュータとの連携設定は重要です。適切な連携設定により、二重入力の手間を省き、データの整合性を保つことができます。
レセプトシステムとの連携
レセプトシステムとの効果的な連携は、診療報酬請求の正確性を確保する上で非常に重要です。特に、傷病名コードに関するデータの連携については、細心の注意を払う必要があります。
データ送受信の確認
レセプトシステムとのデータ送受信は、定期的に正常に行われていることを確認する必要があります。特に、新規登録や変更を行った場合は、確実にデータが反映されているか確認することが重要です。
エラーチェック機能の活用
レセプトシステムには強力なエラーチェック機能が搭載されています。この機能を活用することで、傷病名とレセプト請求の整合性を事前に確認することができます。特に、医学管理等の特定疾患の登録漏れなど、請求に直接影響する項目については、重点的にチェックを行います。
補助的なツールの活用
主要なシステムに加えて、様々な補助的なツールを活用することで、業務の効率をさらに向上させることができます。これらのツールは、特定の業務に特化した機能を提供することで、メインシステムを補完する役割を果たします。
マスター管理ツール
傷病名マスターを効率的に管理するための専用ツールを活用することで、コードの検索や更新作業を効率化できます。特に、頻用する傷病名については、カスタマイズした簡易検索機能を設定することも有効です。
データバックアップツール
重要なデータを確実に保護するため、定期的なバックアップは欠かせません。自動バックアップ機能を備えたツールを活用することで、確実なデータ保護を実現することができます。
システム導入時の注意点
新しいシステムの導入や更新時には、様々な準備と対策が必要となります。特に、既存データの移行や、スタッフの教育については、十分な時間と労力を確保する必要があります。
導入前の準備
新システムの導入に際しては、現在の業務フローを詳細に分析し、新システムでの運用方法を具体的に検討する必要があります。また、データ移行の方法や、移行後の検証方法についても、事前に計画を立てておくことが重要です。
スタッフ教育の実施
新システムの導入時には、全てのスタッフが新しい操作方法を確実に習得できるよう、十分な教育期間を設ける必要があります。特に、キーとなる機能については、実践的な演習を含めた研修を実施することが望ましいでしょう。
システムトラブルへの対応
システムトラブルは、業務に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、予防的な対策と、トラブル発生時の対応手順を事前に確立しておくことが重要です。
予防的な対策
定期的なシステムチェックやメンテナンスを実施することで、トラブルを未然に防ぐことができます。また、システムの使用状況を監視し、潜在的な問題を早期に発見することも重要です。
緊急時の対応手順
システムトラブル発生時の対応手順を明確化し、全スタッフに周知しておくことが必要です。特に、データのバックアップ方法や、代替的な業務手順については、定期的な確認と訓練を行うことが望ましいでしょう。
事例別対応ガイド

訪問看護指示書における傷病名コードの運用では、様々な事例に遭遇します。このセクションでは、現場でよく遭遇する具体的な事例とその対応方法について、実務経験に基づいた詳細な解説を行います。2024年の制度改定による変更点も踏まえながら、確実な実務遂行のためのポイントをお伝えします。
新規患者の登録対応
新規患者の傷病名コード登録は、その後の継続的な管理の基礎となる重要な業務です。初回の登録時には、診療情報提供書や診療録から必要な情報を正確に収集し、適切なコードを選択する必要があります。
情報収集のポイント
新規患者の情報収集では、まず主治医からの診療情報提供書や診療録を丁寧に確認します。特に、現在の主たる傷病名と、その経過や状態について、詳細な情報を収集することが重要です。また、既往歴や合併症についても、漏れなく確認を行います。
診療情報の確認手順
診療情報の確認では、まず診断名の確定日や病期、重症度などの基本情報を確認します。特に、がん患者さんの場合は、がんの部位や進行度、現在の治療状況などについて、詳細な情報収集が必要となります。医師の記載した診療録と、看護記録の両方を確認することで、より正確な情報収集が可能となります。
既往歴の確認方法
既往歴の確認では、過去の診療情報を遡って確認する必要があります。特に、現在の病態に影響を与える可能性のある既往歴については、発症時期や治療経過などを詳細に確認します。また、手術歴や処置歴についても、漏れなく確認を行います。
傷病名の追加・変更時の対応
患者さんの状態変化に伴う傷病名の追加や変更は、日常的に発生する重要な業務です。特に、新たな症状や合併症が発生した場合の対応には、迅速さと正確性が求められます。
追加・変更の判断基準
傷病名の追加や変更が必要となる状況としては、新たな症状の出現や、病状の進行、治療方針の変更などが考えられます。これらの変更を行う際は、医師の指示内容を正確に理解し、適切なコードを選択する必要があります。
緊急性の判断
傷病名の追加や変更が必要となった場合、その緊急性を適切に判断することが重要です。特に、診療報酬請求に直接影響する変更については、可能な限り即日対応することが望ましいとされています。
関連する傷病名の確認
新たな傷病名を追加する際は、既存の傷病名との関連性を必ず確認します。特に、合併症や続発症として追加される傷病名については、原疾患との関係性を明確にしておく必要があります。
複数傷病名がある場合の対応
複数の傷病名が存在する場合、それらの優先順位付けや関連性の整理が重要となります。特に、主傷病の選定や、傷病名の記載順序については、明確な基準に基づいて判断を行う必要があります。
優先順位の決定方法
複数の傷病名の優先順位は、現在の医療資源の投入量や、患者さんの生活への影響度などを総合的に判断して決定します。特に、訪問看護サービスの提供において重要となる傷病名を適切に選定することが求められます。
関連性の整理方法
複数の傷病名間の関連性を整理する際は、原疾患と合併症、続発症などの関係性を明確にします。また、治療の優先順位や、症状の管理方法なども考慮に入れながら、適切な整理を行います。
特定疾患の場合の対応
特定疾患の患者さんの場合、診療報酬請求上の特別な配慮が必要となります。特に、医学管理等に関連する傷病名については、正確なコードの選択と管理が重要です。
特定疾患の登録手順
特定疾患の登録では、まず疾患の診断基準への適合性を確認します。また、必要な検査データや診断書類が揃っているかどうかも確認が必要です。登録後は、定期的な更新要件にも注意を払う必要があります。
管理料算定の確認
特定疾患の管理料算定に関しては、算定要件を満たしているかどうかの確認が重要です。特に、病期や重症度による算定区分の違いや、併算定の可否などについては、細心の注意を払う必要があります。
トラブルケースへの対応
実務では様々なトラブルケースに遭遇することがあります。これらの状況に適切に対応するためには、事前の準備と、正確な判断基準が必要となります。
記載ミスの修正対応
記載ミスが発見された場合は、速やかに適切な修正手順に従って対応します。特に、レセプト請求に影響する可能性がある場合は、優先的に対応を行う必要があります。
システムトラブル時の対応
システムトラブルが発生した場合の代替的な業務手順を、事前に確立しておくことが重要です。特に、手書きでの運用が必要となる場合の手順や、データの再入力方法などについて、明確なルールを設けておく必要があります。
コンプライアンスと監査対策

傷病名コードの運用において、法令遵守と適切な監査対応は非常に重要な要素となります。このセクションでは、2024年の制度改定を踏まえた最新のコンプライアンス要件と、実践的な監査対策について解説します。医療機関における適切な記録管理と、監査時の効果的な対応方法をお伝えします。
記録保管の基本要件
医療記録の保管には、法令で定められた明確な基準があります。特に傷病名コードに関連する記録については、診療報酬請求の根拠となるため、より厳格な管理が求められます。
保管期間と保管方法
診療報酬請求に関連する記録は、法令により5年間の保管が義務付けられています。電子データでの保管は認められていますが、システムの安全性や、データのバックアップ体制についても、明確な基準を満たす必要があります。定期的なバックアップの実施と、そのログの保管も重要な要件となります。
電子保管の要件
電子データでの保管を行う場合は、データの改ざん防止対策や、アクセス権限の管理など、セキュリティ面での対策が特に重要となります。システムへのアクセスログを適切に保管し、誰がいつどのような操作を行ったかを追跡できる体制を整える必要があります。
紙媒体保管の注意点
紙媒体での保管を併用する場合は、適切な保管場所の確保と、整理方法の確立が重要です。特に、湿気や直射日光を避け、災害時の対策も考慮した保管環境を整える必要があります。
監査時の対応手順
監査が実施される際は、要求される資料を速やかに提示できる体制を整えておくことが重要です。事前の準備と、実際の監査時の対応手順を明確化しておくことで、スムーズな監査対応が可能となります。
事前準備の重要性
監査の通知を受けた際は、まず必要な資料の特定と準備を行います。特に、傷病名コードの登録履歴や、変更記録などについては、監査で頻繁に確認される項目となるため、重点的な確認が必要です。
実地監査への対応
実地監査時には、要求された資料を迅速に提示できるよう、資料の配置場所や検索方法を事前に確認しておきます。また、監査担当者からの質問に対して、適切な回答ができるよう、関連する規定や運用ルールについても、十分な理解を深めておく必要があります。
自己点検の実施方法
定期的な自己点検の実施は、コンプライアンス違反を未然に防ぎ、監査対策としても有効です。特に、傷病名コードの運用に関する重要なポイントについては、定期的な確認が必要です。
点検項目の設定
自己点検では、コードの記載内容や保管状況、アクセス管理など、多岐にわたる項目を確認します。特に、診療報酬請求に直接関わる部分については、より詳細な確認が必要となります。
点検結果の活用
自己点検の結果は、必ず記録として残し、改善が必要な項目については具体的な対策を立案します。また、点検結果を踏まえた職員教育や、運用ルールの見直しなども重要です。
コンプライアンス教育の実施
職員のコンプライアンス意識を高めるため、定期的な教育研修の実施が重要です。特に、新入職員や異動者に対しては、重点的な教育が必要となります。
教育内容の設計
コンプライアンス教育では、法令の基本的な要件から、具体的な運用ルールまで、段階的な学習が可能となるよう内容を設計します。特に、実際の業務に即した事例を用いた研修は、理解を深める上で効果的です。
フォローアップの実施
教育実施後は、理解度の確認とフォローアップが重要です。特に、日常業務の中で疑問点が生じた場合に、気軽に相談できる体制を整えておくことが望ましいでしょう。
効率化とベストプラクティス

傷病名コードの運用において、業務の効率化は生産性向上の重要な鍵となります。このセクションでは、現場で実践されている効果的な業務改善の方法と、2024年の制度改定に対応した最新のベストプラクティスについて解説します。日々の業務をより効率的に進めるためのヒントを、具体的な実践例とともにお伝えします。
業務フローの最適化
効率的な業務遂行には、明確で合理的な業務フローの確立が不可欠です。特に、傷病名コードの登録から確認までの一連の流れについて、ムダを省き、効率を高める工夫が重要となります。
タイムスタディの活用
業務改善の第一歩は、現状の業務にかかる時間を正確に把握することです。各作業にどの程度の時間がかかっているか、どの部分に時間的なムダが生じているかを分析することで、効果的な改善策を見出すことができます。特に、繰り返し行われる定型業務については、細かな時間分析が有効です。
作業時間の測定方法
作業時間の測定は、一定期間にわたって継続的に行うことが重要です。日によって作業量や所要時間に変動があることを考慮し、平均的な時間を把握することが必要です。また、作業者による個人差も考慮に入れる必要があります。
改善ポイントの特定
時間分析の結果から、特に時間がかかっている作業や、ムダな待ち時間が発生している部分を特定します。これらの課題に対して、具体的な改善策を検討していきます。
チェックリストの活用
日常的な確認作業を効率的に行うため、効果的なチェックリストの活用が重要です。特に、新規登録時や変更時には、確認項目を漏れなくチェックすることが必要です。
チェックリストの設計
チェックリストは、必要な確認項目を網羅しつつ、使いやすさを考慮して設計する必要があります。特に、よくあるミスや重要度の高い項目については、重点的なチェックが可能な設計とすることが望ましいです。
運用ルールの設定
チェックリストの効果的な活用のためには、明確な運用ルールを設定することが重要です。チェックのタイミングや実施者、記録の保管方法などについて、具体的なルールを定めておく必要があります。
タイムマネジメント術
限られた時間を効果的に活用するため、適切なタイムマネジメントが重要です。特に、優先順位の設定と、効率的な作業の進め方について、具体的な方法を理解しておく必要があります。
優先順位の設定方法
業務の優先順位は、緊急性と重要性の両面から判断します。特に、診療報酬請求に直接影響する作業や、期限の定められた作業については、優先的な対応が必要となります。
集中時間の確保
効率的な業務遂行には、まとまった集中時間の確保が重要です。特に、新規登録や複雑な変更作業などは、中断を避けて集中的に行うことが望ましいです。
テンプレートの活用
定型的な作業を効率化するため、効果的なテンプレートの活用が重要です。特に、頻繁に使用する傷病名の組み合わせや、定型的な確認項目については、テンプレート化することで作業効率を向上させることができます。
テンプレートの作成方法
テンプレートは、実際の業務での使用頻度や重要度を考慮して作成します。特に、エラーが起こりやすい部分については、チェック機能を組み込むなどの工夫が必要です。
定期的な見直し
テンプレートは、制度改定や運用ルールの変更に合わせて、定期的な見直しと更新が必要です。特に、2024年の改定では、いくつかの重要な変更点があり、それらを反映したテンプレートの更新が必要となっています。
看護師さんからのQ&A「おしえてカンゴさん!」

傷病名コードの運用に関して、現場でよく寄せられる質問とその回答をまとめました。このセクションでは、実務で直面しやすい疑問点について、具体的な対応方法を解説していきます。カンゴさんが、皆様からの質問に丁寧にお答えします。
基本的な運用に関する質問
Q1. 新規患者さんの傷病名コード登録で特に注意すべき点を教えてください。
新規患者さんの傷病名コード登録では、まず診療情報提供書や診療録の内容を正確に確認することが重要です。特に、診断確定日や病期、重症度などの基本情報を漏れなく収集する必要があります。
また、主傷病と副傷病の区別を明確にし、適切な順序で登録を行うことがポイントとなります。さらに、特定疾患等の場合は、算定要件を満たしているかどうかの確認も必要です。
Q2. 傷病名の修飾語の選択に迷うことが多いのですが、どのように判断すればよいでしょうか。
修飾語の選択は、医師の診療録の記載内容に基づいて判断する必要があります。特に、「急性」「慢性」といった経過を表す修飾語や、「重症」「軽症」といった重症度を表す修飾語については、医師の判断を正確に反映することが重要です。不明な点がある場合は、必ず医師に確認を取るようにしましょう。
システム運用に関する質問
Q3. 電子カルテシステムでの傷病名コードの検索方法について、効率的な方法はありますか。
電子カルテシステムでは、キーワード検索や部分一致検索などの機能を効果的に活用することができます。例えば、漢字での検索が該当しない場合は、ひらがなやカタカナでの検索を試みることも有効です。また、よく使用する傷病名については、お気に入り登録機能を活用することで、検索時間を短縮することができます。
Q4. システムトラブル時の対応手順について教えてください。
システムトラブル発生時は、まず定められた緊急連絡体制に従って報告を行います。その後、手書きでの運用に切り替える必要がある場合は、あらかじめ用意された代替手順に従って対応します。特に重要な点は、システム復旧後のデータ入力を正確に行うことです。そのため、手書き記録は特に丁寧に行い、必要な情報を漏れなく記録しておくことが重要です。
請求関連の質問
Q5. 傷病名の追加や変更が診療報酬請求に与える影響について教えてください。
傷病名の追加や変更は、特定疾患療養管理料などの医学管理等の算定要件に直接影響を与える可能性があります。そのため、変更を行う際は、関連する診療報酬項目の算定要件を必ず確認する必要があります。また、変更を行った場合は、レセプトの記載内容との整合性も確認することが重要です。
Q6. 月途中での傷病名変更時の請求について注意点を教えてください。
月途中での傷病名変更時は、変更前と変更後の期間を明確に区別して記録することが重要です。特に、医学管理等の算定に影響がある場合は、算定期間との整合性を確認する必要があります。また、変更に伴って新たな管理料等が算定可能となる場合は、算定開始日を正確に記録することが重要です。
監査対策に関する質問
Q7. 傷病名コードの監査対策として、日常的に気をつけるべきことは何ですか。
日常的な監査対策として最も重要なのは、記録の正確性と一貫性の確保です。具体的には、診療録の記載内容と傷病名コードの整合性を常にチェックすること、変更履歴を適切に管理すること、定期的な自己点検を実施することなどが挙げられます。また、関連する資料の保管方法についても、法令に従った適切な管理を行うことが重要です。
Q8. 自己点検の効果的な実施方法について教えてください。
効果的な自己点検を行うためには、チェックリストを活用した体系的な確認が有効です。点検項目には、コードの正確性、修飾語の適切性、算定要件との整合性など、重要なポイントを漏れなく含める必要があります。また、定期的な点検結果の記録と、発見された課題への対応策の検討も重要です。
教育・研修に関する質問
Q9. 新人スタッフへの教育で特に重視すべきポイントを教えてください。
新人スタッフの教育では、まず傷病名コードの基本的な体系と構造の理解を徹底することが重要です。その上で、実際の業務に即した具体的な演習を行い、特に頻出するケースについての対応方法を習得させます。また、エラーが起こりやすいポイントについても、実例を用いて丁寧に説明することが効果的です。
Q10. 継続的なスキルアップのために、どのような取り組みが効果的ですか。
継続的なスキルアップのためには、定期的な研修会の開催や、事例検討会の実施が効果的です。特に、実際に発生したエラーケースや複雑な事例について、関係者で共有し検討することで、実践的な知識とスキルを身につけることができます。また、制度改定時には、変更点について重点的な学習機会を設けることも重要です。
まとめ
この記事では、2024年の制度改定に対応した傷病名コードの基本から実践的な運用方法まで、詳しく解説してきました。傷病名コードの正確な運用は、適切な診療報酬請求の基盤となるだけでなく、多職種間での円滑な情報共有にも重要な役割を果たします。
特に重要なポイントは、基本的なコード体系の理解、正確な記載方法の習得、そして効率的な運用手順の確立です。また、システムやツールを効果的に活用し、コンプライアンスを意識した運用を行うことで、より確実な業務遂行が可能となります。
日々進化する医療現場において、最新の知識とスキルを維持することは非常に重要です。「はたらく看護師さん」では、この記事で解説した内容に加えて、さらに詳しい実践例や、現場で役立つ具体的なテクニック、最新の制度改定情報などを随時更新しています。
より詳しい情報や、実践的なノウハウについては、「はたらく看護師さん」の会員登録(無料)で、いつでも最新情報にアクセスいただけます。
参考文献
- 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」
- 日本看護協会「看護業務基準」
- 医療情報システム開発センター「MEDIS 標準マスター総合サイト」
- 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」
- 社会保険研究所ブックストア「訪問看護業務の手引 令和6年6月版」