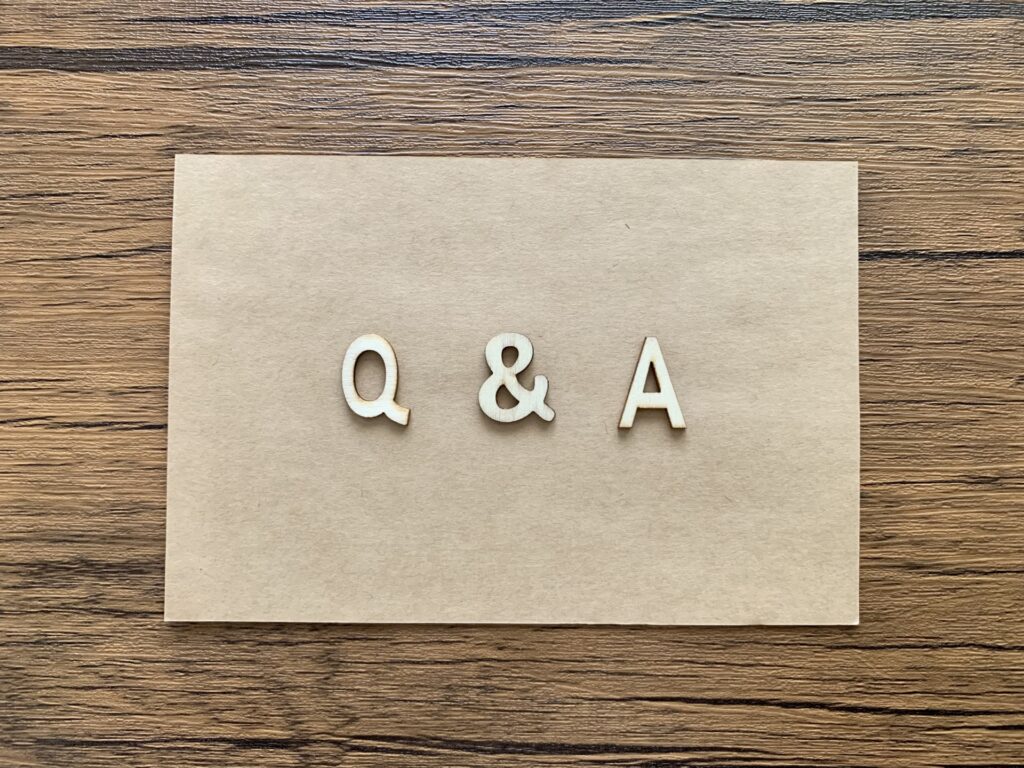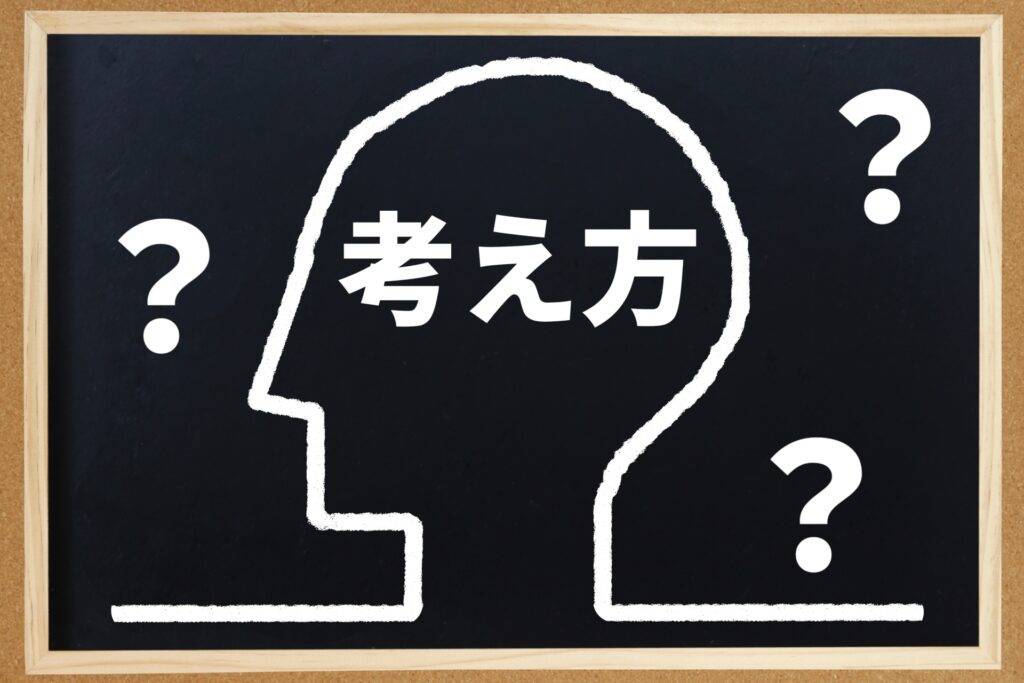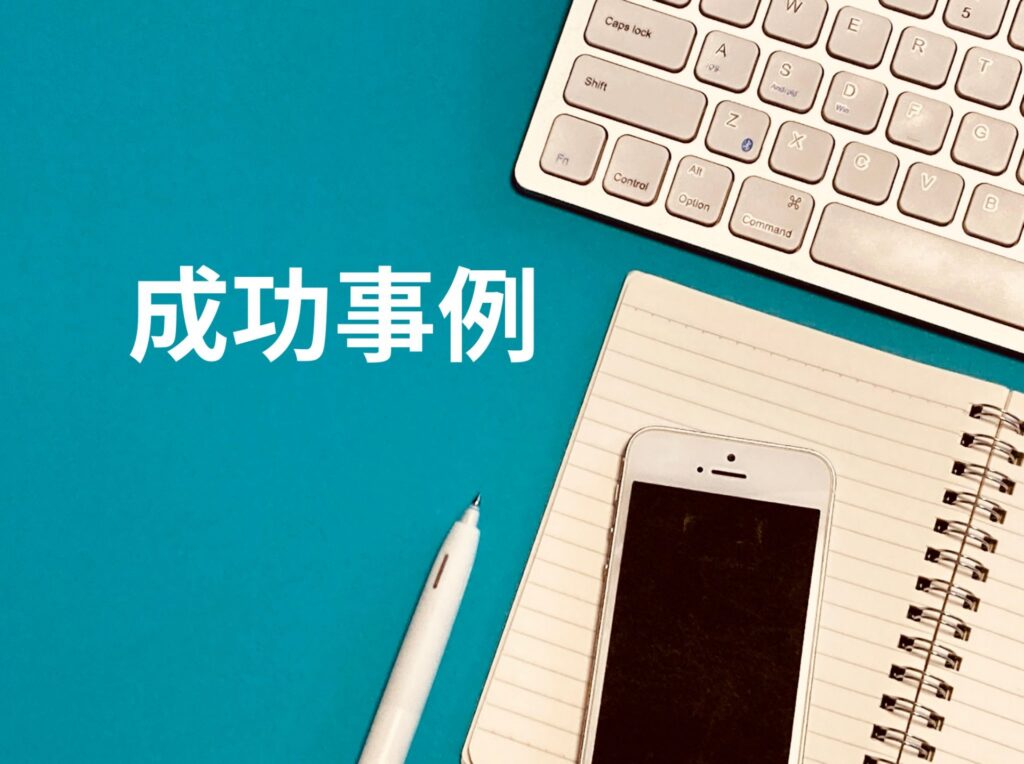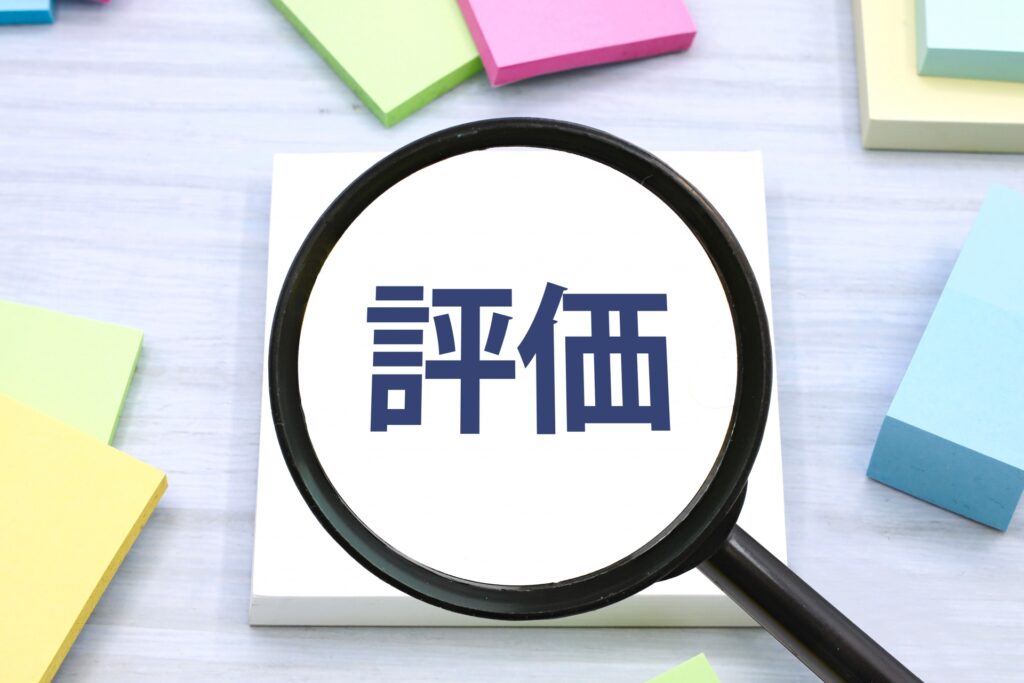実習期間中の睡眠の乱れや精神的な不調に悩んでいませんか?
この記事では、現役の看護師と看護教員の経験をもとに、実習を乗り切るための具体的な対策方法をご紹介します。
あなたの睡眠の質を改善し、心身の健康を取り戻すためのヒントが見つかるはずです。
この記事で分かること
- 看護実習中の睡眠障害とメンタルヘルスの関係性
- 即実践できる睡眠の質を改善する具体的な方法
- ストレスと上手く付き合うためのセルフケア技術
- 実習記録と睡眠時間を両立させるための時間管理術
この記事を読んでほしい人
- 実習中の睡眠障害に悩んでいる看護学生
- 実習のストレスで精神的な不調を感じている方
- 実習記録と睡眠時間の確保に苦心している学生
- これから実習が始まる看護学生
- 睡眠の質を改善したい医療系学生
看護実習中の睡眠障害の原因を探る

看護実習中の睡眠の問題は、単なる寝不足だけでなく、複雑な要因が絡み合っています。
まずは問題の本質を理解することから始めましょう。
心理的要因による睡眠への影響
実習中は様々な心理的なプレッシャーにさらされます。患者さんとの関わりや記録物の作成、指導者からの評価など、日々のストレスが蓄積していきます。
さらに、グループ内での人間関係や、自身の看護実践に対する不安も重なり、心理的な負担が増大します。
不安とストレスのメカニズム
心配事が多いと、交感神経が優位な状態が続き、なかなか眠れない状態に陥ります。
特に実習中は次の日の出来事を考えすぎてしまい、寝つきが悪くなることがあります。
身体的要因と環境要因
早朝からの実習や長時間の立ち仕事は、身体に大きな負担をかけます。
ここでは、身体的な疲労が睡眠に与える影響と、それを取り巻く環境要因について詳しく見ていきましょう。
生活リズムの乱れがもたらす影響
実習期間中は普段より早い時間に起床する必要があります。それに伴い就寝時間も早めなければならないのですが、記録物の作成などで深夜まで作業することも少なくありません。
このような不規則な生活リズムが体内時計を狂わせ、睡眠の質を低下させる原因となります。
食事時間の変化による影響
実習中は昼食時間が不規則になりがちです。患者さんのケアや処置が重なると、ゆっくり食事を取る時間が確保できないこともあります。
また、夜遅くまで記録を書くことで夕食時間が遅くなり、胃腸の働きに影響を与えることもあります。
運動不足による影響
実習中は立ち仕事が多いものの、それは適度な運動とは異なります。むしろ同じ姿勢での作業が続くことで、肩こりや腰痛といった身体的な不調を引き起こす可能性があります。
このような身体的な不調は、良質な睡眠を妨げる要因となります。
環境変化によるストレス
慣れない病院環境での実習は、それだけでもストレス要因となります。特に初めての実習では、環境の変化に適応するまでに時間がかかることがあります。
通勤時間の変化
実習先への通勤時間が普段の学校よりも長くなることもあります。
その結果、起床時間を更に早める必要が生じ、睡眠時間の確保が難しくなります。
実習環境での緊張
病院という特殊な環境での緊張感は、自律神経系に影響を与えます。常に緊張状態が続くことで、リラックスして眠ることが難しくなることがあります。
心身の疲労蓄積
実習期間中は心身ともに大きな負担がかかります。この疲労が適切に解消されないまま蓄積されていくと、睡眠の質が更に低下するという悪循環に陥ることがあります。
免疫機能への影響
睡眠不足が続くと免疫機能が低下し、実習中の感染リスクが高まる可能性があります。特に病院という環境では、様々な感染症に触れる機会が増えるため、より一層の注意が必要です。
ホルモンバランスの乱れ
不規則な生活は体内時計に影響を与え、メラトニンやコルチゾールなどのホルモンバランスを崩します。
その結果、より一層睡眠が取りにくくなる状態に陥ることがあります。
記録作成による負担
実習記録の作成は大きな身体的・精神的負担となります。パソコンやスマートフォンの画面を長時間見続けることで、目の疲れやブルーライトの影響を受けやすくなります。
デジタル機器使用の影響
夜遅くまで記録を作成することで、ブルーライトの影響により睡眠ホルモンの分泌が抑制されます。また、画面を見続けることによる目の疲労は、頭痛の原因にもなります。
姿勢による身体への負荷
記録作成時の不適切な姿勢は、首や肩、腰に負担をかけます。長時間同じ姿勢を続けることで、筋肉の緊張が増し、それが睡眠の質に影響を与えることがあります。
社会的要因による影響
実習期間中は、普段の生活とは異なる社会的環境に置かれることになります。これらの変化も睡眠に大きな影響を与える要因となっています。
対人関係のストレス
実習中は患者さん、指導者、他の学生など、多くの人々との関わりが生じます。それぞれの関係性において感じるストレスは、心身の緊張を高める原因となります。
コミュニケーションの負担
患者さんとの関わりや、指導者への報告など、常に適切なコミュニケーションを求められる環境は、精神的な緊張を引き起こします。この緊張が夜間まで続くと、睡眠に支障をきたすことがあります。
グループダイナミクスの影響
実習グループ内での人間関係や役割分担なども、ストレス要因となることがあります。グループメンバーとの関係性に悩むことで、睡眠前も余計な思考が巡ってしまうことがあります。
個人生活との両立
実習期間中は、アルバイトや趣味の時間が制限されることで、ストレス解消の機会が減少します。また、家族や友人との時間も取りにくくなり、精神的なサポートを得る機会も限られてきます。
これらの要因は互いに関連し合い、複雑な影響を及ぼしています。次のセクションでは、これらの問題に対する具体的な対処法について詳しく見ていきましょう。
効果的な対処法と実践テクニック

実習中の睡眠障害に対しては、計画的かつ体系的なアプローチが必要です。
ここでは、現場で実際に効果を上げている具体的な対処法をご紹介します。
睡眠環境の最適化
質の良い睡眠を得るためには、適切な睡眠環境を整えることが重要です。環境を整えることで、自然な眠りへの導入がスムーズになります。
温度と湿度の調整
就寝時の室温は18-22度、湿度は50-60%が理想的です。これらの条件を整えることで、体温調節がスムーズになり、良質な睡眠を促進することができます。
エアコンや加湿器を活用し、快適な環境作りを心がけましょう。
光環境の整備
就寝時は可能な限り暗い環境を作ることが大切です。完全な暗闇が難しい場合は、アイマスクの使用も効果的です。また、朝は自然光を取り入れることで、体内時計のリセットを促すことができます。
音環境への配慮
周囲の騒音は睡眠の質に大きく影響します。耳栓の使用や、心地よい白色雑音を流すことで、外部の音を遮断することができます。ただし、目覚まし時計の音は確実に聞こえる設定にしておくことが重要です。
就寝前のルーティン確立
就寝前の行動パターンを整えることで、スムーズな入眠を促すことができます。
以下では効果的なルーティンについて詳しく説明します。
リラックスタイムの確保
就寝1時間前からは、心身をリラックスさせる時間を設けましょう。温かい入浴やストレッチ、軽い読書などが効果的です。この時間帯はスマートフォンやパソコンの使用は避けることが望ましいです。
入浴のタイミング
就寝の2-3時間前に38-40度のぬるめのお湯に20分程度つかることで、深部体温を下げ、自然な眠気を促すことができます。
ただし、熱いお湯での入浴は逆効果となることがあります。
軽い運動の活用
就寝2-3時間前の軽いストレッチや、ヨガのリラックスポーズは睡眠の質を高めます。激しい運動は避け、身体をほぐす程度の運動を心がけましょう。
食事と栄養管理
適切な食事管理は、良質な睡眠を支える重要な要素です。実習期間中は特に注意が必要です。
夕食のタイミング
就寝の3時間前までには夕食を済ませることが理想的です。遅い夕食は胃腸に負担をかけ、睡眠の質を低下させる原因となります。
夜間の飲食管理
夜遅い時間の飲食は最小限に抑えましょう。特にカフェインを含む飲み物は、就寝6時間前までに控えることが推奨されます。
どうしても夜食が必要な場合は、バナナやヨーグルトなど、消化の良い食品を選びましょう。
睡眠を促す食品の活用
トリプトファンを含む食品は、睡眠ホルモンであるメラトニンの生成を助けます。牛乳、チーズ、豆類、魚類などを意識的に取り入れることで、自然な眠気を促すことができます。
タイムマネジメントの実践
実習期間中は時間の使い方が特に重要になります。効率的な時間管理により、睡眠時間を確保することができます。
記録時間の確保
実習記録は可能な限り実習中や直後に作成することを心がけましょう。カンファレンスの時間や休憩時間を有効活用し、夜遅くまで記録を残すことを避けます。
優先順位の設定
その日に必ず終わらせる必要のある記録と、翌日に回せる作業を明確に区別します。時間配分を意識し、必要な睡眠時間を確保できるよう計画を立てましょう。
効率的な記録方法
メモアプリやボイスレコーダーを活用し、実習中のメモ取りを効率化します。これにより、夜間の記録作成時間を短縮することができます。
ストレス解消法の確立
実習によるストレスを適切に解消することは、良質な睡眠を得るために不可欠です。
心身のリラックス法
呼吸法や瞑想、アロマセラピーなど、自分に合ったリラックス方法を見つけることが重要です。就寝前のリラックスタイムに組み込むことで、より効果的に活用できます。
呼吸法の実践
4-7-8呼吸法など、簡単な呼吸エクササイズを就寝前に行うことで、自律神経を整え、リラックス状態に導くことができます。
マインドフルネスの活用
5分程度の短い瞑想でも、心を落ち着かせる効果があります。就寝前のルーティンに組み込むことで、よりスムーズな入眠を促すことができます。
サポートリソースの活用
一人で抱え込まずに、周囲のサポートを適切に活用することも重要です。実習期間中は特に、支援体制を把握し活用することが推奨されます。
実習指導者への相談
睡眠の問題が実習に影響を及ぼしている場合は、早めに実習指導者に相談しましょう。多くの指導者は学生時代の経験があり、具体的なアドバイスをくれる可能性があります。
相談のタイミング
問題が深刻化する前に、早めの段階で相談することが重要です。指導者との定期的な面談時間を活用し、現状を伝えましょう。
効果的な相談方法
具体的な症状や影響を整理して伝えることで、より適切なアドバイスを得ることができます。睡眠日誌をつけておくと、状況説明がしやすくなります。
同期との情報共有
実習グループのメンバーと情報を共有することで、互いにサポートし合える関係を築くことができます。
グループ学習の活用
記録物の作成を共同で行うことで、作業時間を短縮できる場合があります。
ただし、コピーや丸写しは避け、あくまでも意見交換や情報共有に留めましょう。
メンタルサポート
同じ立場の仲間との対話は、精神的な支えとなります。困っていることを共有し、解決策を一緒に考えることで、ストレスの軽減につながります。
体調管理の徹底
実習期間中は特に、体調管理に気を配ることが重要です。疲労の蓄積を防ぎ、健康的な状態を維持しましょう。
定期的な運動習慣
可能な範囲で軽い運動を継続することで、身体的なストレス解消と良質な睡眠を促進することができます。
運動の選択
実習の疲労を考慮し、ウォーキングやストレッチなど、負担の少ない運動を選択します。激しい運動は逆効果となる可能性があります。
運動のタイミング
朝型の生活リズムを作るため、可能であれば朝の運動を心がけましょう。夜の運動は就寝2-3時間前までには終えるようにします。
生活リズムの再構築
実習期間中は、通常の生活リズムが大きく変化します。この変化に適応するための具体的な方法を見ていきましょう。
朝型生活への移行
実習開始の2週間前から少しずつ就寝時間と起床時間を早めていくことで、身体への負担を軽減することができます。
起床時間の固定
休日も含めて起床時間を一定にすることで、体内時計を整えることができます。目覚まし時計は複数セットし、確実に起きられる工夫をしましょう。
光環境の活用
起床後すぐに太陽の光を浴びることで、体内時計のリセットを促進できます。カーテンを開けるか、短時間の外出を心がけましょう。
休日の過ごし方
休日も平日と同じような生活リズムを維持することが重要です。生活リズムが大きく乱れると、実習再開時の適応が困難になります。
休息の取り方
休日は積極的な活動を控え、心身の回復を優先しましょう。ただし、一日中寝ているのは避け、適度な活動レベルを維持します。
記録作成の計画
休日に記録の遅れを取り戻す場合は、午前中から取り掛かることをお勧めします。
夜遅くまで作業を行うことは、翌日の実習に影響を及ぼす可能性があります。
メンタルヘルスケアの実践
精神的な健康を保つことは、良質な睡眠を得るための重要な要素です。
ストレスマネジメント
ストレスを完全に避けることは難しいですが、適切な対処法を身につけることで、その影響を最小限に抑えることができます。
セルフモニタリング
日々の心身の状態を観察し、ストレスのサインを早期に発見することが大切です。疲労感や不安感が強くなったときは、早めの対処を心がけましょう。
リラクゼーション技法
自分に合ったリラックス方法を見つけることが重要です。音楽鑑賞、アロマテラピー、入浴など、様々な方法を試してみましょう。
実習記録との向き合い方
記録作成は実習における重要な学習活動ですが、睡眠時間を圧迫する主な要因でもあります。効率的な記録作成の方法を身につけましょう。
記録作成の時間管理
効率的な記録作成のために、時間配分を工夫することが重要です。
優先順位の設定
その日のうちに完成させるべき記録と、翌日に回せる記録を明確に区別します。
特に、翌日のカンファレンスで使用する記録は優先的に仕上げましょう。
時間配分の目安
記録作成は原則として2時間以内を目標とします。それ以上かかる場合は、記録の書き方を見直すか、指導者に相談することをお勧めします。
効率的な情報収集
実習中の情報収集を効率化することで、夜の記録作成時間を短縮することができます。
メモの取り方
短時間で要点をまとめられるよう、あらかじめ記録用紙の項目に沿ってメモを取る習慣をつけましょう。
スマートフォンのメモ機能やボイスレコーダーの活用も検討してください。
情報の整理方法
収集した情報は、その場で可能な限り整理します。カンファレンスの時間や休憩時間を活用し、記録の下書きを進めることで、夜の作業を減らすことができます。
緊急時の対応策
深刻な睡眠障害に陥った場合の対処方法について理解しておくことも重要です。
危険信号の把握
以下のような症状が現れた場合は、要注意サインとして捉えましょう。
身体的症状
極度の疲労感、めまい、吐き気、頭痛などの症状が続く場合は、休息を取る必要があります。
精神的症状
強い不安感、イライラ、集中力の著しい低下、記憶力の減退などが現れた場合は、早めの対処が必要です。
実践的なストレス管理技法

実習期間中のストレスを効果的に管理することは、良質な睡眠を得るための重要な要素です。
ここでは、すぐに実践できる具体的な技法をご紹介します。
マインドフルネスの実践
看護実習中のストレスを和らげるため、マインドフルネスを日常的に取り入れることをお勧めします。
基本的な呼吸法
呼吸に意識を向けることで、心を落ち着かせることができます。忙しい実習中でも、短時間で実践できる技法です。
呼吸法の実践方法
鼻から4秒かけて息を吸い、7秒間息を止め、8秒かけてゆっくりと口から息を吐きます。この呼吸法を3-4回繰り返すことで、自律神経を整えることができます。
ボディスキャン瞑想
就寝前に全身の緊張を解きほぐす瞑想を行います。足先から順に身体の各部分に意識を向け、緊張を和らげていきましょう。
認知行動療法的アプローチ
考え方のパターンを見直すことで、ストレスへの対処力を高めることができます。
ネガティブ思考への対処
完璧主義的な考えや極端な思い込みに気づき、より柔軟な思考パターンを身につけます。
思考の記録
不安や心配事を具体的に書き出し、それらが現実的かどうかを客観的に検討します。多くの場合、書き出すことで問題が整理され、解決の糸口が見えてきます。
視点の転換
失敗を学びの機会として捉え直すなど、状況を異なる視点から見る練習を行います。これにより、ストレスの軽減につながります。
身体を活用したストレス解消法
身体を動かすことで、精神的なストレスを軽減することができます。実習の疲労を考慮した、適度な運動方法をご紹介します。
ストレッチングの活用
短時間でも効果的なストレッチを行うことで、身体の緊張を和らげることができます。
デスクワーク時のストレッチ
記録作成の合間に、首や肩、腰のストレッチを行います。血行を促進し、疲労の蓄積を防ぐことができます。
就寝前のリラックスストレッチ
全身の筋肉をゆっくりと伸ばすことで、身体の緊張を解きほぐし、良質な睡眠を促進します。
アロマセラピーの活用
香りの力を借りて、心身をリラックスさせる方法も効果的です。
睡眠を促す香り
ラベンダー、カモミール、スイートオレンジなどの精油は、リラックス効果が高いとされています。
アロマの使用方法
ディフューザーやアロマスプレー、入浴剤などを活用し、就寝前の環境づくりに役立てましょう。
香りの選び方
自分に合う香りを見つけることが重要です。複数の香りを試してみて、心地よく感じるものを選びましょう。
音楽療法の実践
音楽には心身をリラックスさせる効果があります。実習中のストレス管理に活用してみましょう。
音楽の選び方
60-80BPMの穏やかな曲調の音楽が、リラックス効果が高いとされています。
就寝前の音楽活用
就寝30分前から心地よい音楽を聴くことで、スムーズな入眠を促すことができます。
通勤時の音楽活用
実習先への通勤時間を活用し、気持ちを切り替えるための音楽を聴くことも効果的です。
実習記録の効率的な管理

記録作成の効率を上げることは、十分な睡眠時間を確保するための重要なポイントです。
ここでは、実践的な時間管理術と記録作成のコツをお伝えします。
タイムマネジメントの基本
限られた時間を有効活用するためには、計画的な時間配分が不可欠です。
時間の使い方の見直し
実習中の時間の使い方を客観的に分析し、効率化できる部分を見つけ出します。
時間記録の活用
1週間程度、実習中の行動を時間単位で記録してみましょう。無駄な時間を発見し、改善につなげることができます。
優先順位の明確化
その日のうちに終わらせるべき作業と、翌日に回せる作業を明確に区別します。緊急性と重要性のバランスを考慮しましょう。
効率的な情報収集法
実習中の情報収集を効率化することで、夜の記録作成時間を大幅に短縮することができます。
メモの取り方のコツ
必要な情報を素早く、正確に記録する技術を身につけましょう。
テンプレートの活用
よく使う項目や表現をまとめたテンプレートを作成しておくと、メモの効率が上がります。
デジタルツールの利用
スマートフォンのメモ機能やボイスレコーダーを活用し、すばやい情報記録を心がけます。
記録作成の効率化
限られた時間内で質の高い記録を作成するためのテクニックをご紹介します。
記録作成の基本ステップ
効率的な記録作成のために、作業を段階的に進めていくことが重要です。
下書きの活用
カンファレンスや休憩時間を利用して、その日の記録の下書きを進めておきましょう。メモを整理し、記録の骨格を作ります。
推敲の時間配分
記録の推敲は30分程度を目安とします。完璧を求めすぎず、重要なポイントを押さえることを意識しましょう。
看護過程の展開方法
看護過程の各段階を効率的に展開することで、記録作成時間を短縮することができます。
アセスメントの効率化
情報収集と分析を効率的に行うためのポイントです。
情報の整理方法
収集した情報をゴードンの機能的健康パターンなどの枠組みに沿って整理します。重要な情報を見落とさないよう、システマティックに進めましょう。
関連図の活用
患者さんの問題点や症状の関連性を視覚的に整理することで、アセスメントの質を向上させることができます。
記録の質の向上
効率化を図りながらも、記録の質を保つことが重要です。
看護計画の立案
具体的で実行可能な看護計画を立案することを心がけます。
目標設定のポイント
具体的で測定可能な目標を設定します。実習期間内に達成可能な目標を意識しましょう。
個別性の反映
患者さんの個別性を考慮した計画立案を心がけます。画一的な計画にならないよう注意が必要です。
メンタルヘルスケアの実践

看護実習中のメンタルヘルスケアは、良質な睡眠を得るための重要な要素です。
ここでは具体的なセルフケア方法についてご説明します。
セルフケアの基本
メンタルヘルスを維持するために、日常的なセルフケアが欠かせません。
心身の状態把握
自分の心身の状態を定期的にチェックすることが重要です。
ストレスサインの認識
イライラ、不安感、食欲不振、頭痛などの症状は、ストレスのサインかもしれません。早期発見が重要です。
気分の記録
毎日の気分や体調を簡単に記録することで、状態の変化を把握しやすくなります。
予防的アプローチ
問題が深刻化する前に、予防的な対策を講じることが大切です。
ストレス耐性の向上
日常的なストレス対処能力を高めることで、実習中のストレスにも対応しやすくなります。
レジリエンスの強化
困難な状況から立ち直る力を養うため、小さな成功体験を積み重ねていきます。
サポート体制の構築
家族や友人、同級生など、信頼できる人々とのつながりを大切にします。
具体的な対処法の実践
日々の実習生活で活用できる、具体的なメンタルヘルスケア方法をご紹介します。
感情のコントロール
強いストレスを感じたときの対処方法を身につけましょう。
クールダウンの方法
その場で実践できるクールダウン方法として、深呼吸や数を数えるなどの技法があります。
気分転換の工夫
短時間でできる気分転換活動を見つけておくことが大切です。音楽を聴く、散歩をするなど、自分に合った方法を見つけましょう。
支援リソースの活用
一人で抱え込まず、適切な支援を受けることも重要です。
相談窓口の利用
実習中に利用できる相談窓口について把握しておきましょう。
教員への相談
実習担当教員は、学生の心身の健康について相談に乗ってくれます。困ったときは早めに相談しましょう。
学生相談室の活用
多くの教育機関には学生相談室が設置されています。専門家に相談できる機会を積極的に活用しましょう。
課題との向き合い方
実習中の様々な課題に対して、建設的な姿勢で取り組むことが重要です。
スモールステップの設定
大きな課題を小さな目標に分割することで、達成感を得やすくなります。
目標の具体化
「頑張る」ではなく、具体的な行動目標を設定します。例えば「今日は患者さん一人のケアを丁寧に行う」といった具体的な目標設定が効果的です。
ケーススタディ

実際の看護学生の事例を通じて、睡眠の問題とその改善方法について具体的に見ていきましょう。
ケース1:睡眠時間が確保できないAさんの場合
状況
看護学生のAさん(20歳)は、実習開始後から睡眠時間が3-4時間に減少。記録作成に時間がかかり、深夜2時頃まで起きている状態が続いていました。
問題点
- 記録作成に4-5時間かかっていた
- 情報の整理ができていなかった
- 完璧主義的な傾向があった
- 実習中のメモ取りが不十分だった
改善策と結果
実習中のメモ取りを工夫し、フォーマットを作成。
カンファレンス時間を活用して下書きを進めることで、記録時間が2時間程度に短縮。就寝時間を23時に設定できるようになりました。
ケース2:不安で眠れないBさんの場合
状況
Bさん(21歳)は実習への不安が強く、就寝前も翌日の実習のことを考えて眠れない状態が続いていました。
問題点
- 就寝前に翌日の実習の心配で頭がいっぱいになっていた
- 身体は疲れているのに、考え事が止まらなかった
- 休日も実習のことを考えて休めていなかった
- 指導者への質問や相談ができていなかった
改善策と結果
就寝前の30分をリラックスタイムとして確保し、アロマオイルを使用したり、静かな音楽を聴いたりする時間を作りました。
また、実習指導者に不安なことを相談するようにしたところ、具体的なアドバイスをもらえ、不安が軽減。約1週間で入眠がスムーズになりました。
ケース3:生活リズムが乱れているCさんの場合
状況
Cさん(19歳)は実習前から昼夜逆転の生活を送っており、実習開始後も体内時計が整わず、朝の目覚めが非常に悪い状態でした。
問題点
- 夜型の生活習慣が定着していた
- 実習中の居眠りが目立っていた
- 休日に生活リズムが大きく乱れていた
- カフェインへの依存度が高かった
改善策と結果
実習2週間前から少しずつ就寝時間を早めていき、光療法(朝日を浴びる)を取り入れました。
また、夜のカフェイン摂取を控え、代わりにハーブティーを飲用。約3週間で朝型の生活リズムが定着し、実習にも集中できるようになりました。
ケース4:記録とアルバイトの両立に悩むDさんの場合
状況
Dさん(20歳)は学費のために週3回のアルバイトを継続。実習記録との両立が難しく、慢性的な睡眠不足に陥っていました。
問題点
- アルバイトと実習記録の両立でストレスが蓄積
- 睡眠時間が平均2-3時間と極端に不足
- 集中力の低下が目立つようになった
- 免疫力が低下し、体調を崩しがちになった
改善策と結果
実習期間中はアルバイトを週1回に調整。実習記録は集中力のある昼休みの時間を活用し、効率的な作成を心がけました。
その結果、平均6時間の睡眠が確保でき、実習にも集中して取り組めるようになりました。
ケース5:環境の変化に適応できないEさんの場合
状況
Eさん(22歳)は実習先が自宅から遠く、慣れない環境での一人暮らしを始めました。新しい環境への不適応から不眠が続いていました。
問題点
- 慣れない一人暮らしでの不安
- 新しい環境での孤独感
- 実習先までの通勤時間が長い
- 自炊と生活管理の両立が困難
改善策と結果
オンラインで定期的に家族と連絡を取り、精神的なサポートを得られるようにしました。
また、同じ実習グループの仲間と食事会を開催するなど、新しいコミュニティを作ることで、徐々に環境に適応。睡眠の質も改善していきました。
Q&A「おしえてカンゴさん!」

実習中の睡眠に関する、よくある質問にベテラン看護師がお答えします。
Q1:実習前日は緊張して全く眠れません。どうすればよいでしょうか?
実習前日の不眠は多くの学生が経験することです。就寝2時間前からスマートフォンの使用を控え、ぬるめのお風呂でリラックスすることをお勧めします。
また、「眠れない」という不安にとらわれすぎないことも大切です。
1日目は誰でも緊張するものですから、その気持ちを自然なものとして受け入れてみましょう。
Q2:実習記録が深夜までかかってしまいます。時間を短縮するコツはありますか?
記録時間の短縮には、実習中のメモ取りが重要です。患者さんの情報や看護ケアの内容を、その場でできるだけ詳しくメモしておきましょう。
また、カンファレンスの時間を利用して記録の下書きを進めることで、夜の作業時間を大幅に減らすことができます。
完璧を求めすぎず、要点を押さえることを意識してください。
Q3:夜勤実習の前日、昼間にうまく眠れません。良い方法はありませんか?
夜勤実習前の仮眠は慣れが必要です。部屋を暗くし、アイマスクの使用も検討してみましょう。
また、昼食後すぐに横になると自然と眠りやすくなります。目覚まし時計は必ず複数セットし、焦らず休むことを心がけてください。
Q4:休日に生活リズムが乱れてしまいます。どう対処すればよいでしょうか?
休日も平日とできるだけ同じ時間に起きることをお勧めします。起床時間が2時間以上ずれると、月曜日の実習に支障が出やすくなります。休日も同じ時間に起き、自然光を浴びることで体内時計を整えましょう。
ただし、休日は午後に30分程度の短い昼寝を取り入れるのも良い方法です。
Q5:実習中、患者さんのことが気になって夜中に目が覚めてしまいます。
患者さんへの責任感の表れですが、適度な距離感を保つことも大切です。就寝前に、その日の看護ケアを振り返り、できたことと課題を整理してノートに書き出してみましょう。
また、指導者に相談し、アドバイスをもらうことで不安が軽減されることもあります。
Q6:カフェインに頼りすぎている気がします。どうすれば減らせますか?
カフェインへの依存は睡眠の質を低下させる原因となります。代替として、午前中は軽い運動や深呼吸で目を覚ます習慣をつけてみましょう。
また、眠気覚ましにはレモンウォーターやハーブティーも効果的です。カフェインの摂取は午後3時までを目安にし、徐々に量を減らしていくことをお勧めします。
Q7:実習のストレスで夜中に何度も目が覚めます。改善方法はありますか?
ストレスによる中途覚醒には、就寝前のリラックスタイムの確保が効果的です。入浴後にストレッチやリラクゼーション呼吸法を取り入れてみましょう。
また、寝室の温度を18-22度に保ち、適度な湿度を確保することで、睡眠の質が改善されることもあります。
まとめ:実習を乗り切るための睡眠管理のポイント
実習期間中の睡眠の質を向上させるためには、計画的なアプローチが重要です。生活リズムの調整、効率的な記録作成、そしてストレス管理を組み合わせることで、充実した実習生活を送ることができます。
実習は確かに大変ですが、これらの方法を実践することで、心身の健康を保ちながら学びを深めることが可能です。一つひとつできることから始め、自分に合った睡眠管理の方法を見つけていきましょう。
体調管理は実習を成功させる大切な要素です。不安なことがあれば、一人で抱え込まず、指導者や仲間に相談することをお勧めします。この経験は、将来看護師として働く際にも必ず活かされるはずです。
より詳しい情報や、現役看護師の体験談、奨学金情報など、看護師を目指す方々へのキャリアサポート情報は【ナースの森】でご覧いただけます。経験豊富な先輩看護師たちがあなたの悩みにお答えします。就職情報や最新の医療トレンド、継続的な学習サポートなど、看護師としてのキャリアをトータルでサポートいたします。
会員登録いただくと、以下のような特典もご利用いただけます。
- 看護学生向けの学習支援コンテンツ
- 現役看護師によるキャリア相談
- 奨学金情報の優先案内
- 実習お役立ち情報
- 就職活動サポート
▶︎【ナースの森】看護師のためのキャリア支援サイトはこちら