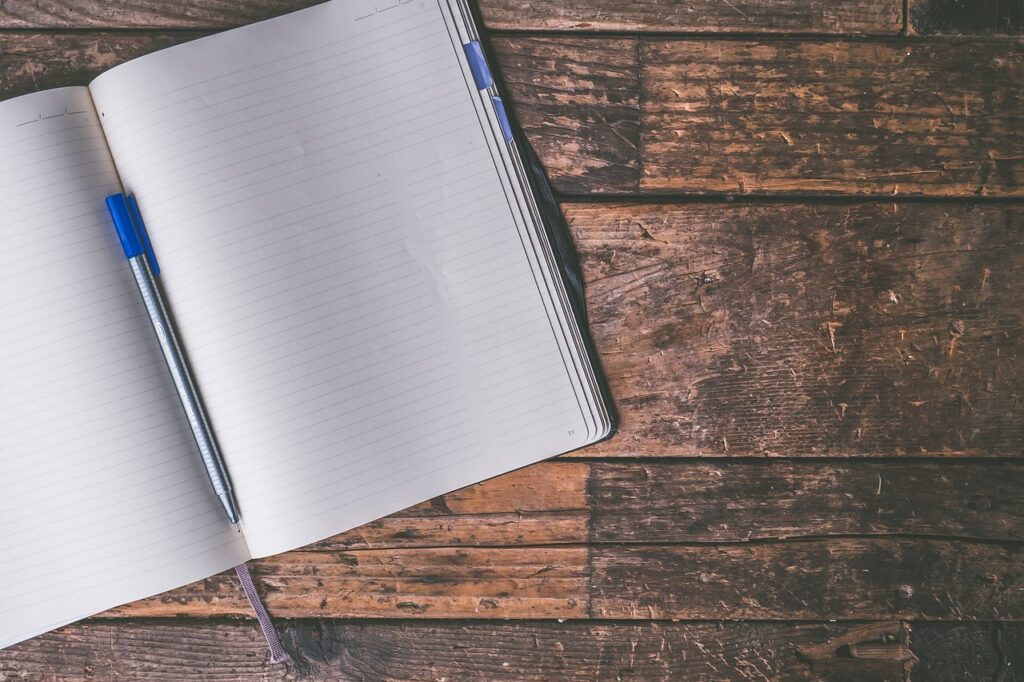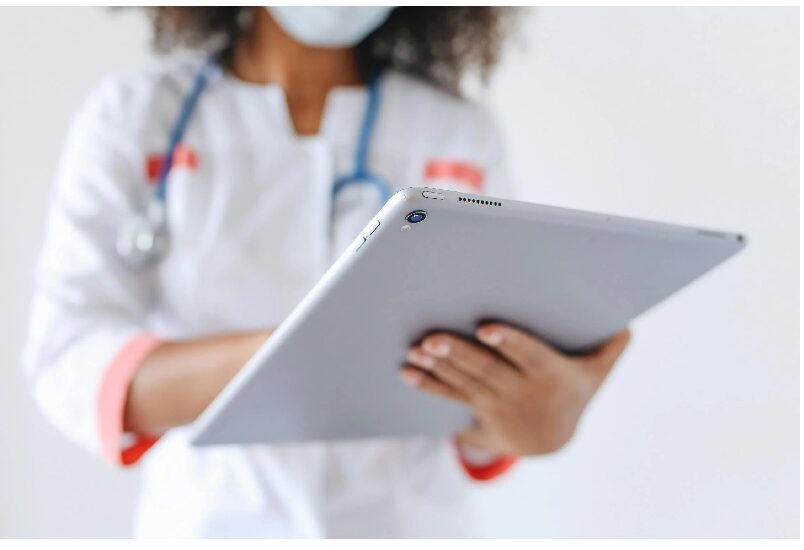看護師国家試験の難易度は年度によって大きく変動します。本記事では、過去15年間の試験を徹底分析し、難関年度の特徴と効果的な対策方法をご紹介します。実際の合格者の声と共に、あなたの合格への道筋を示していきます。
この記事で分かること
- 看護師国家試験の過去15年間の難易度変化について
- 合格率が特に低かった年度の特徴について
- 各科目の年度別難易度と変化のポイントについて
- 時期別の具体的な対策方法について
- 実際の合格者が実践した効果的な学習法について
この記事を読んでほしい人
- 看護師国家試験の受験を控えている看護学生の方
- 再受験に向けて効率的な対策を考えている方
- 試験の傾向を把握して計画的に学習したい方
- 過去の難関年度から学びたいと考えている方
[ PR ]

看護師国家試験の難易度推移:年度別分析

看護師国家試験の難易度は、社会情勢や医療制度の変化に応じて年々変動しています。ここでは過去15年間の試験を詳細に分析し、各年度の特徴的な傾向や難易度の変化について詳しくご説明します。
令和5年度(第113回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
令和5年度の試験では、在宅医療と地域包括ケアに関する出題が顕著に増加しました。合格率は93.7%となり、例年と比較して標準的な難易度を維持していました。
特徴的な出題分野
必修問題では感染管理と医療安全に関する出題が目立ち、特にCOVID-19後の新しい医療体制についての理解を問う問題が増加しました。また、一般問題では高齢者の在宅ケアに関する実践的な判断を問う問題が多く出題されています。
令和4年度(第112回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
合格率が92.2%と、やや低めの水準となった年度です。特に状況設定問題において、複数の観点からの判断を要する問題が増加しました。
特徴的な出題分野
在宅看護論と看護の統合と実践の分野からの出題が増加し、特に多職種連携に関する理解を問う問題が目立ちました。また、電子カルテシステムや医療情報の取り扱いに関する問題も新たに登場しています。
令和3年度(第111回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
合格率は91.3%を記録し、近年では比較的難しい年度となりました。COVID-19の影響を強く受けた試験として注目されています。オンライン診療や遠隔看護に関する新しい知識を問う問題が初めて登場し、多くの受験生が戸惑いを見せました。
特徴的な出題分野
感染症対策に関する問題が大幅に増加し、特に個人防護具(PPE)の適切な使用方法や感染経路別の予防策について詳細な知識を問う問題が目立ちました。
また、メンタルヘルスケアに関する問題も増加し、医療従事者自身のストレスマネジメントについての出題も見られました。
令和2年度(第110回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
合格率93.7%と、標準的な難易度を維持した年度でした。しかし、問題の形式や内容に大きな変化が見られ、より実践的な判断力を問う傾向が強まりました。
特徴的な出題分野
地域包括ケアシステムに関する問題が増加し、特に多職種連携における看護師の役割について深い理解を問う問題が多く出題されました。
また、医療安全に関する問題では、インシデント・アクシデントレポートの分析や改善策の立案など、より実践的な内容が問われています。
令和元年度(第109回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
合格率95.4%を記録し、比較的平均的な難易度となりました。ただし、必修問題の形式に変更が加えられ、より基本的な知識の確実な定着を確認する傾向が強まっています。
特徴的な出題分野
高齢者看護に関する問題が増加し、特に認知症ケアや終末期医療に関する出題が目立ちました。また、医療制度や関係法規に関する問題も増加し、社会保障制度の理解を深く問う傾向が見られました。
平成30年度(第108回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
合格率94.7%と、前年度から大きく回復した年度です。しかし、問題の難易度そのものは決して低くなく、むしろ複合的な思考力を要する問題が増加しています。
出題形式の特徴
状況設定問題において、一つの事例から複数の観点での判断を求める問題が増加しました。特に、患者の状態アセスメントから看護計画の立案、実施、評価までの一連のプロセスを総合的に問う問題が特徴的でした。
平成29年度(第107回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
近年で最も難しいとされる年度で、合格率は89.3%まで低下しました。新しい出題形式の導入や、より実践的な判断力を問う問題の増加が特徴となっています。
問題傾向の変化
必修問題では、基礎的な知識を複合的に活用する問題が増加し、単純な暗記だけでは対応できない問題が多く出題されました。また、一般問題では、臨床現場での優先順位の判断や、患者の心理面へのアプローチを問う問題が増えています。
平成28年度(第106回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
合格率91.0%を記録し、やや難易度の高い年度となりました。特に、在宅看護に関する問題の比重が増加し、地域医療における看護師の役割について深い理解が求められました。
特徴的な出題分野
医療安全に関する問題では、チーム医療におけるコミュニケーションやリスクマネジメントの視点が重視されました。また、フィジカルアセスメントの技術に関する問題も増加し、より実践的な臨床判断能力が問われる傾向が強まっています。
平成27年度(第105回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
合格率96.3%と、比較的高い合格率を記録した年度です。しかし、この年度から問題の質的な変化が始まり、現在の出題傾向の基礎となる要素が多く見られました。
出題形式の特徴
状況設定問題において、患者の背景情報をより詳細に提示し、それらを総合的に判断する力を問う問題が増加しました。特に、患者の社会的背景や生活環境を考慮した看護計画の立案が重視されています。
平成26年度(第104回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
合格率95.5%で、標準的な難易度を維持しつつも、問題の質的な変化が見られた年度です。特に、チーム医療や多職種連携に関する問題が増加し始めました。
特徴的な変化
この年度から、電子カルテや医療情報システムに関する基礎的な知識を問う問題が登場し始めました。また、災害看護に関する問題も増加し、より幅広い知識が必要とされるようになっています。
平成25年度(第103回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
合格率94.1%を記録し、それまでの出題傾向を踏襲しつつも、新しい医療の動向を反映した問題が増加し始めた年度です。
問題内容の特徴
在宅医療の推進を反映し、訪問看護や在宅ケアに関する問題が増加しました。また、高齢者の権利擁護や倫理的配慮に関する問題も目立つようになり、より包括的な看護の視点が求められるようになっています。
平成24年度(第102回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
合格率93.2%で、基本的な知識と実践力の両方を重視する出題傾向が確立された年度といえます。特に、臨床判断能力を問う問題の質が向上しています。
問題形式の変化
状況設定問題では、より具体的な臨床場面を想定した問題が増加し、アセスメント能力と看護計画立案能力を総合的に評価する傾向が強まりました。また、医療安全に関する問題では、システムとしての安全管理の視点が重視されるようになっています。
平成23年度(第101回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
合格率91.8%を記録し、必修問題の導入後、安定した出題形式が確立された年度となりました。基礎的な知識を確実に問う姿勢が明確になり、現在の試験形式の原型が完成しています。
特徴的な出題分野
基礎看護技術に関する問題では、より具体的な手順や根拠の理解を問う傾向が強まりました。また、看護倫理に関する問題も増加し、患者の権利や自己決定の尊重について、より深い理解が求められるようになっています。
平成22年度(第100回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
記念すべき第100回となった本年度は、合格率89.5%と比較的低い結果となりました。出題形式や内容に大きな変更が加えられ、多くの受験生が戸惑いを見せた年度です。
問題形式の変革
この年度から、より実践的な臨床判断を問う問題が増加し、単なる知識の暗記では対応できない問題が多く出題されるようになりました。特に、状況設定問題では、複数の情報を統合して判断を下す能力が重視されています。
平成21年度(第99回)の特徴と分析
全体的な試験傾向
合格率92.6%で、従来の出題スタイルから新しい形式への移行期として位置づけられる年度です。基礎的な知識を問う問題と実践的な判断力を問う問題のバランスが特徴的でした。
出題内容の特徴
この年度から、チーム医療や多職種連携に関する問題が徐々に増加し始め、看護師の役割の拡大を反映した出題傾向が見られるようになりました。また、医療安全に関する問題も体系的に出題されるようになっています。
年度別分析から見える15年間の変化
出題傾向の変遷
この15年間で、試験の性質は大きく変化してきました。初期は基礎的な知識の確認が中心でしたが、徐々に実践的な判断力や応用力を問う問題が増加しています。
特に、地域包括ケアシステムの導入や在宅医療の推進など、社会の変化を反映した問題が増えている傾向が顕著です。
求められる能力の変化
近年の試験では、単なる知識の暗記だけでなく、以下のような総合的な能力が求められるようになっています。臨床現場での実践力を重視する傾向が強まり、患者の状態を総合的に判断する力や、多職種との連携能力の重要性が増しています。
また、医療安全や感染管理など、システムとしての医療提供体制への理解も重視されるようになっています。さらに、在宅医療の推進に伴い、地域における看護師の役割についての理解も深く問われるようになってきています。
このように、看護師国家試験は時代とともに進化を続けており、より実践的で総合的な能力を評価する試験へと変化してきていることが分かります。
科目別の難易度推移

看護師国家試験の各科目における難易度は、医療環境の変化や社会のニーズに応じて変動しています。ここでは各科目の難易度推移を詳しく分析し、それぞれの特徴と対策のポイントをご説明します。
基礎看護学の難易度推移
全体的な傾向
基礎看護学は近年、より実践的な判断力を問う問題が増加しています。特に看護過程の展開や看護理論の適用に関する問題では、単なる暗記ではなく、状況に応じた適切な判断が求められるようになっています。
正答率の推移を見ると、令和3年度は78.2%、令和4年度は76.8%と、やや低下傾向にあります。
出題傾向の変化
看護技術の基本原則に関する問題は依然として重要ですが、その出題方法が変化しています。技術の手順だけでなく、その根拠や患者の状態に応じた修正の必要性を問う問題が増えています。
特に、フィジカルアセスメントや看護記録に関する問題の出題頻度が上昇しており、より実践的な知識が求められています。
重点的な学習が必要な分野
バイタルサインの測定や基本的な看護技術については、より詳細な観察点や判断基準が問われるようになっています。
また、看護理論の実践への応用や、エビデンスに基づく看護実践(EBN)に関する理解も重視されています。臨床現場での判断プロセスを意識した学習が必要とされています。
成人看護学の難易度推移
全体的な傾向
成人看護学では、慢性疾患の管理や生活習慣病に関する問題が増加しています。令和4年度の正答率は75.3%で、特に複合的な病態の理解を要する問題での正答率が低い傾向にあります。急性期から回復期、慢性期まで、継続的な看護の視点が重視されています。
出題傾向の変化
周手術期看護に関する問題では、術前から術後までの一連のケアについて、より詳細な知識が求められるようになっています。
また、がん看護や緩和ケアに関する問題も増加し、心理的支援や家族ケアの視点も重要視されています。最近では、治療の選択や意思決定支援に関する問題も増加傾向にあります。
重点的な学習が必要な分野
循環器疾患や呼吸器疾患などの主要な疾患については、病態生理の理解に加えて、患者教育や生活指導の視点が重要です。また、化学療法や放射線療法などの治療に伴う看護についても、より実践的な知識が求められています。
老年看護学の難易度推移
全体的な傾向
高齢化社会を反映し、老年看護学の問題数と重要度は年々増加しています。令和4年度の正答率は77.4%で、特に認知症ケアや多職種連携に関する問題での正答率が低い傾向にあります。実際の臨床現場を想定した複合的な判断を要する問題が増えています。
出題傾向の変化
フレイル予防や生活機能の維持向上に関する問題が新しく登場し、予防的な視点からのアプローチが重視されるようになっています。
また、高齢者の権利擁護や倫理的配慮に関する問題も増加しています。特に注目すべき点として、サルコペニアやロコモティブシンドロームなど、新しい概念に関する問題が頻出しています。
重点的な学習が必要な分野
高齢者特有の症候群や疾患に関する知識はもちろんのこと、生活機能の評価方法や転倒予防、褥瘡予防などの日常生活援助技術についても、より実践的な理解が求められています。
また、認知症高齢者とのコミュニケーション方法や、家族支援に関する問題も重要度が増しています。
小児看護学の難易度推移
全体的な傾向
小児看護学では、令和4年度の正答率が79.8%と比較的高い水準を維持していますが、発達障害や医療的ケア児に関する問題では正答率が低下する傾向にあります。家族支援や地域連携に関する問題が増加し、より包括的な理解が求められています。
出題傾向の変化
従来の成長発達に関する基本的な問題に加えて、小児の権利擁護や医療における意思決定支援について、より深い理解が求められるようになっています。
特に、小児在宅医療や学校生活支援に関する問題が増加傾向にあり、地域社会での継続的な支援体制についての理解も重視されています。
重点的な学習が必要な分野
小児の発達段階別の特徴と看護については、より実践的な場面での判断が求められています。
また、予防接種スケジュールや小児期特有の疾患についても、最新のガイドラインに基づいた理解が必要です。家族支援においては、育児不安や虐待予防の視点も重要となっています。
母性看護学の難易度推移
全体的な傾向
母性看護学の令和4年度の正答率は81.2%と比較的高い水準にありますが、不妊治療や周産期のメンタルヘルスに関する問題では正答率が低下する傾向にあります。特に、生殖医療の進歩に伴う新しい知識や、メンタルヘルスケアの重要性が増しています。
出題傾向の変化
妊娠期から産褥期までの継続的なケアに関する問題が増加し、より実践的な判断力が求められています。近年は特に、ハイリスク妊娠や高齢出産に関する問題、産後うつのスクリーニングや支援体制に関する問題の出題が増えています。
また、女性のライフステージ全般にわたる健康支援の視点も重視されています。
重点的な学習が必要な分野
妊娠・分娩・産褥期の生理的変化と異常の見分け方について、より実践的な理解が必要です。
また、母乳育児支援や新生児のケア、育児技術指導についても、エビデンスに基づいた最新の知識が求められています。DV被害者への支援や、多様な家族形態に対応した支援についても重要度が増しています。
精神看護学の難易度推移
全体的な傾向
精神看護学の令和4年度の正答率は76.8%で、特にリエゾン精神看護や地域精神保健に関する問題での正答率が低い傾向にあります。医療観察法に基づく医療や、依存症患者への支援など、社会的な課題に関連した問題も増加しています。
出題傾向の変化
従来の精神疾患の症状や治療に関する知識に加えて、リカバリーの視点や地域生活支援に関する問題が増加しています。
また、COVID-19の影響もあり、ストレスマネジメントや危機介入に関する問題も重視されるようになっています。認知行動療法などの心理療法や、精神科薬物療法の副作用管理についても、より実践的な理解が求められています。
重点的な学習が必要な分野
主要な精神疾患の症状や治療法については、最新のガイドラインに基づいた理解が必要です。
また、精神科救急や自殺予防、虐待への対応など、危機介入に関する知識も重要度が増しています。さらに、精神障害者の権利擁護や、地域での生活支援システムについても深い理解が求められています。
在宅看護論の難易度推移
全体的な傾向
在宅看護論は令和4年度の正答率が74.6%と、比較的低い水準となっています。地域包括ケアシステムの推進に伴い、問題の難易度と重要性が年々増しています。特に医療依存度の高い在宅療養者への支援や、多職種連携に関する問題での正答率が低い傾向にあります。
出題傾向の変化
在宅での医療管理や終末期ケアに関する問題が増加し、より実践的な判断力が求められています。特に、在宅人工呼吸療法や在宅中心静脈栄養法などの医療処置に関する問題、介護保険制度や医療保険制度の活用に関する問題が増加しています。
また、家族支援や介護者支援、地域の社会資源の活用に関する問題も重要度が増しています。
重点的な学習が必要な分野
在宅での医療処置や緊急時の対応について、より実践的な理解が必要です。また、各種制度やサービスの理解、ケアマネジメントの視点も重要となっています。さらに、多職種連携やチームアプローチ、地域連携パスの活用などについても深い理解が求められています。
看護の統合と実践の難易度推移
全体的な傾向
看護の統合と実践は令和4年度の正答率が75.8%で、特にマネジメントや医療安全に関する問題での正答率が低い傾向にあります。医療事故防止や感染管理、災害看護に関する問題が増加し、より実践的な判断力が求められています。
出題傾向の変化
チーム医療におけるリーダーシップや看護管理に関する問題が増加しています。また、医療安全管理体制や感染管理体制の構築、災害時の医療提供体制に関する問題も重視されています。
さらに、看護研究や看護情報学、国際看護に関する問題も出題されるようになっています。
重点的な学習が必要な分野
医療安全管理や感染管理については、組織的な取り組みの視点からの理解が必要です。また、災害看護では災害サイクル各期の対応や、トリアージの考え方についても重要です。さらに、看護管理や医療経済、医療制度改革についても深い理解が求められています。
科目別難易度の総合的な変化
共通する傾向
全科目を通じて、基礎的な知識を問う問題は依然として重要ですが、より実践的な判断力や応用力を問う問題が増加しています。特に以下の点が重視されています:
第一に、患者の権利擁護や倫理的配慮に関する問題が増加しています。インフォームドコンセントや意思決定支援、個人情報保護などについて、より実践的な場面での判断が求められています。
第二に、多職種連携やチーム医療に関する理解が重要視されています。各職種の役割や連携方法、情報共有の方法などについて、具体的な場面での判断が問われています。
第三に、地域包括ケアシステムの推移に伴い、地域連携や継続看護の視点が重要となっています。医療機関と地域、施設間の連携について、より実践的な理解が必要とされています。
科目間の関連性
近年の出題傾向として、複数の科目の知識を統合して解答する必要がある問題が増加しています。例えば、高齢者の周手術期看護では、成人看護学と老年看護学の知識が必要とされ、精神疾患を持つ患者の在宅支援では、精神看護学と在宅看護論の知識が求められます。
このように、科目別の学習に加えて、科目横断的な視点での理解と、実践的な判断力の養成が重要となっています。特に、看護の統合と実践の分野は、他の科目の知識を統合して活用する能力が試される傾向が強まっています。
効果的な対策方法:合格者の声から

実際に看護師国家試験に合格した先輩たちの経験は、これから受験される皆様にとって貴重な道しるべとなります。ここでは、特に難関とされた年度を乗り越えた合格者の方々の具体的な学習方法と、そこから得られる実践的なアドバイスをご紹介します。
Aさん(第112回合格)の学習アプローチ
基本情報
現役看護学生として受験し、模擬試験では全国平均を大きく下回る成績からスタートしながら、最終的に高得点で合格を果たしました。
学習スケジュール
朝型の学習スタイルを確立し、毎朝5時から2時間の集中学習を行いました。授業のある平日は、この朝学習で過去問題を100問ずつ解き、夜は授業の復習に充てていました。休日は図書館で8時間の学習を行い、特に苦手科目の克服に時間を使っていました。
効果的だった学習方法
問題を解くだけでなく、解説をノートにまとめる作業を徹底して行いました。特に間違えた問題については、関連する内容も含めて深く掘り下げて学習することで、似たような問題にも対応できる応用力を養うことができました。
Bさん(第111回合格)の学習アプローチ
基本情報
社会人経験を経て看護学校に入学し、仕事と学業の両立をしながら合格を勝ち取りました。限られた時間の中で効率的な学習方法を確立したことが、合格への鍵となりました。
学習スケジュール
平日は仕事後の2時間を必ず学習時間として確保し、電車での通勤時間も教材アプリを活用して学習に充てていました。休日は午前中を集中学習の時間とし、午後は仲間とのグループ学習を行っていました。
効果的だった学習方法
スマートフォンのメモ機能を活用し、通学中や休憩時間に確認できる要点ノートを作成していました。特に必修問題については、いつでもどこでも確認できるように工夫することで、隙間時間を有効活用することができました。
Cさん(第110回合格)の学習アプローチ
基本情報
看護専門学校の学生として、3年次の4月から本格的な受験勉強を開始しました。特に、模擬試験を活用した計画的な学習が功を奏し、安定した得点を維持して合格を果たしました。
学習スケジュール
実習期間中も含めて、毎日最低4時間の学習時間を確保していました。模擬試験は月1回必ず受験し、その結果を基に学習計画を見直していました。特に、苦手科目である成人看護学と在宅看護論には重点的に時間を配分していました。
効果的だった学習方法
模擬試験で間違えた問題を分析し、なぜその選択肢を選んでしまったのかを詳細に記録していました。この分析により、自分の思考パターンの傾向や弱点を把握することができ、本番での判断ミスを減らすことができました。
Dさん(第109回合格)の学習アプローチ
基本情報
看護師として10年の実務経験があり、准看護師からの進学コースで学びながら合格を果たしました。臨床経験を活かしつつ、新しい知識の習得にも力を入れた学習が特徴です。
学習スケジュール
夜勤がある勤務シフトに合わせて、柔軟な学習計画を立てていました。日勤の日は夜に2時間、夜勤明けの日は午後に3時間、休日は午前中に4時間というように、その日の状況に応じて学習時間を確保していました。
効果的だった学習方法
実務経験があるからこそ陥りやすい「経験則での判断」を避けるため、教科書の内容を基本から見直すことに注力しました。特に、最新のガイドラインや治療法については、実務での知識が古くならないよう意識的に学習を進めていました。
合格者の学習方法から見える成功のポイント
時間管理の工夫
合格者に共通していたのは、自分のライフスタイルに合わせた無理のない学習時間の確保です。朝型や夜型、平日と休日での学習時間の使い分けなど、各自の生活リズムに合わせた学習スケジュールを確立することで、継続的な学習を実現していました。
学習方法の最適化
単に問題を解くだけでなく、解説の理解や関連知識の習得にも時間を使っていた点が特徴的です。特に、間違えた問題については徹底的に分析し、同じ間違いを繰り返さないよう工夫していました。
また、暗記に頼るのではなく、理解を深めることで応用力を養う学習方法を実践していました。
モチベーション管理
長期間の学習を継続するために、小さな目標を設定して達成感を得ながら進めていた点も共通しています。模擬試験の結果を具体的な指標として活用し、弱点の克服や得意分野の強化に取り組むことで、モチベーションを維持していました。
合格者からのアドバイス
効率的な学習法について
教科書や参考書を何周も繰り返し読むのではなく、一度学習した内容を自分の言葉でまとめ直すことが重要です。また、問題を解く際は、なぜその選択肢が正解なのか、他の選択肢が不正解なのかを理解することで、知識の定着が図れます。
体調管理について
試験勉強と日常生活のバランスを保つことが、長期戦を戦い抜くためには不可欠です。適度な運動や休息を取り入れ、睡眠時間を確保することで、学習効率を維持することができます。特に試験直前期は、普段の生活リズムを崩さないよう注意が必要です。
メンタル面での準備
不安や焦りを感じることは自然なことですが、それらに支配されないことが重要です。仲間との情報交換や励まし合いを通じて、精神的な支えを得ることも効果的です。
また、定期的に自己の学習状況を振り返り、計画を修正することで、着実な進歩を実感することができます。
このように、合格者の経験から学ぶことで、より効果的な試験対策を立てることができます。それぞれの状況に合わせて、これらの方法を参考にしながら、自分に合った学習スタイルを確立していくことが重要です。
時期別の学習計画

看護師国家試験の合格には、計画的な学習が不可欠です。ここでは、試験1年前から直前期までの具体的な学習計画と、各時期で重点を置くべきポイントをご紹介します。
1年前からの準備期間(4月~7月)
学習の重点ポイント
この時期は基礎力の確立が最も重要です。特に解剖生理学や病態生理学など、すべての科目の土台となる分野を徹底的に学習します。また、必修問題の対策も並行して始めることで、確実に得点できる分野を作っていきます。
具体的な学習方法
毎日30分から1時間程度の時間を確保し、基礎的な教科書の読み込みを行います。この時期は暗記に頼らず、しっかりと理解することを重視します。また、授業で学ぶ内容と国家試験の出題傾向を照らし合わせながら、重要ポイントを把握していきます。
実力養成期間(8月~11月)
学習の重点ポイント
基礎固めができた後は、各科目の重要項目を体系的に学習していく時期です。この時期から過去問題を本格的に活用し始め、出題傾向や問題形式に慣れていきます。また、模擬試験も定期的に受験し、自己の実力を把握します。
具体的な学習方法
1日2~3時間の学習時間を確保し、科目別の学習を進めていきます。過去問を解く際は、単に答え合わせをするだけでなく、関連する項目も含めて幅広く理解を深めることが重要です。また、苦手科目を把握し、克服のための対策を立てていきます。
実践強化期間(12月~1月中旬)
学習の重点ポイント
この時期は知識の整理と応用力の強化に重点を置きます。各科目の重要項目を横断的に学習し、実践的な問題にも対応できる力を養います。特に、状況設定問題への対応力を高めることが重要になってきます。
具体的な学習方法
1日4~5時間の学習時間を確保し、体系的な復習と問題演習を行います。この時期は特に、出題頻度の高いテーマについて、様々な角度からの出題に対応できるよう訓練します。また、模擬試験の結果を詳細に分析し、弱点を克服していきます。
直前期(1月中旬~試験当日)
学習の重点ポイント
試験直前のこの時期は、それまでの学習内容の総仕上げと、必修問題の完全習得を目指します。新しい内容の学習は控えめにし、既に学習した内容の確認と整理に重点を置きます。また、本番を想定した時間配分の練習も重要になってきます。
具体的な学習方法
1日の学習時間は6時間程度を目安とし、実際の試験時間に合わせた問題演習を行います。ただし、深夜までの学習は避け、規則正しい生活リズムを維持することが重要です。
特に、試験の1週間前からは無理な詰め込みを避け、これまでの学習内容を整理する時間を十分に確保します。
各時期に共通する注意点
効果的な復習方法
どの時期においても、定期的な復習が重要です。学習した内容は、その日のうちに簡単なまとめを作成し、週末にまとめて見直す習慣をつけることで、知識の定着を図ります。特に、間違えた問題や理解が不十分な項目については、必ず複数回の復習を行います。
健康管理の重要性
長期間の学習を継続するためには、適切な休息と規則正しい生活リズムの維持が不可欠です。特に、睡眠時間の確保と適度な運動を心がけることで、学習効率を高く保つことができます。
また、休日には気分転換の時間を設けることで、メンタル面での疲労を防ぐことができます。
学習の進捗管理
自己評価の方法
各時期において、定期的に学習の進捗状況を確認することが重要です。模擬試験の結果や日々の問題演習の正答率を記録し、弱点分野を明確にしていきます。また、学習計画と実際の進捗状況を比較し、必要に応じて計画の修正を行います。
モチベーション維持の工夫
長期間の学習を継続するためには、適切な目標設定とモチベーション管理が重要です。各時期で達成可能な具体的な目標を設定し、それを達成することで自信をつけていきます。また、学習仲間との情報交換や励まし合いも、モチベーション維持に効果的です。
このように、時期別の学習計画を立てることで、効率的かつ効果的な試験対策が可能になります。ただし、これはあくまでも基本的な計画であり、個人の状況や学習の進捗状況に応じて、柔軟に調整していくことが重要です。
参考書・問題集の選び方

看護師国家試験の学習において、適切な教材選びは合格への重要な鍵となります。ここでは、効果的な学習を実現するための参考書・問題集の選び方と、その活用方法についてご説明します。
基礎学習用参考書の選定
選定のポイント
基礎学習用の参考書は、まずその年度の出題基準に準拠しているものを選びましょう。内容が体系的に整理されており、図表や解説が分かりやすいものを選ぶことで、効率的な学習が可能になります。
また、持ち運びのしやすさも考慮に入れると、日々の学習がより継続しやすくなります。
科目別のおすすめ参考書
基礎看護学では、看護の基本概念から看護技術まで幅広くカバーしている教材を選びます。特に看護過程の展開については、具体的な事例を用いて解説しているものが効果的です。
また、解剖生理学については、カラー図版が豊富で理解しやすい教材を選ぶことをおすすめします。
問題集の選び方
問題集のタイプ
問題集は大きく分けて、基礎固め用、実力養成用、直前対策用の3種類があります。
基礎固め用は解説が詳しく、学習初期に最適です。実力養成用は実際の試験に近い形式で、応用力を養うのに適しています。直前対策用は短時間で重要ポイントを確認できる構成になっています。
効果的な活用方法
問題集は学習の進度に合わせて使い分けることが重要です。学習初期は基礎固め用で丁寧に解説を読み込み、中期は実力養成用で応用力を身につけ、直前期は要点整理用で総復習を行うという段階的な活用が効果的です。
科目別教材の選び方
成人看護学の教材
成人看護学は範囲が広いため、疾患別に整理された参考書が有効です。特に、病態生理から看護までの流れが一連で理解できる教材を選びましょう。また、臨床現場での対応が具体的に記載されている問題集は、実践的な理解を深めるのに役立ちます。
老年看護学の教材
老年看護学では、高齢者の特徴や疾患の特性を踏まえた教材を選びます。特に、事例を用いた解説が豊富な教材は、実際の看護場面をイメージしながら学習するのに適しています。また、最新の制度やガイドラインに対応した教材を選ぶことも重要です。
小児看護学の教材
小児看護学では、成長発達段階に応じた特徴が理解しやすい教材を選びましょう。特に、発達段階別の看護ポイントが明確に示されている参考書が効果的です。
また、小児特有の疾患や症状について、イラストや図表を用いて分かりやすく解説している教材を選ぶことで、理解が深まります。
母性看護学の教材
母性看護学では、妊娠期から産褥期までの経過が系統的に学べる教材を選びます。特に、正常・異常の判断基準が明確に示されている参考書が有用です。
また、新生児のケアや母乳育児支援など、実践的な内容が充実している問題集を活用することで、実際の試験に対応する力が養えます。
効果的な教材の組み合わせ方
基本セットの構成
基本的な学習セットとしては、体系的な参考書1冊と、詳細な解説付きの問題集1冊を軸に組み立てることをおすすめします。これに加えて、弱点分野については補助的な教材を活用することで、より効果的な学習が可能になります。
使用時期による使い分け
学習の進度に応じて教材を使い分けることが重要です。初期は基本的な参考書で概念や理論を理解し、中期には問題演習を中心に応用力を養います。直前期には要点をまとめた教材で総復習を行うという段階的な活用が効果的です。
教材の最新情報の確認方法
改定情報の把握
医療や看護の分野は常に進歩しているため、教材の改定情報をこまめにチェックすることが重要です。出版社のウェブサイトや看護系の情報サイトで、最新の教材情報を確認することをおすすめします。また、改定があった場合は、重要な変更点を優先的に確認しましょう。
補足資料の活用
教材の改定サイクルに合わない最新情報については、出版社が提供する補足資料や正誤表を活用します。また、看護系の専門誌や学会のガイドラインなども、適宜参照することで最新の知識を補完することができます。
教材の活用における注意点
学習の効率化
複数の教材を並行して使用する場合は、内容の重複に注意が必要です。効率的な学習のために、各教材の特徴を把握し、目的に応じて使い分けることが重要です。
また、過去問題集を活用する際は、出題年度や改定情報を確認し、最新の基準に照らして学習することが大切です。
経済的な教材選び
必要以上に多くの教材を購入することは避け、基本的な教材を確実に使いこなすことを優先しましょう。また、先輩から譲り受けた教材を使用する場合は、内容が最新のものであるかを必ず確認します。図書館の活用も、経済的な学習を実現する有効な方法です。
このように、適切な教材選びと効果的な活用方法を理解することで、より効率的な試験対策が可能になります。ただし、教材はあくまでも学習のツールであり、実際の理解と応用は学習者自身の努力にかかっていることを忘れないようにしましょう。
学習方法詳細解説

看護師国家試験の合格には、効果的な学習方法の確立が不可欠です。ここでは、試験対策における具体的な学習アプローチと、各手法の活用方法について詳しく解説します。
基礎的な学習方法の確立
理解と暗記のバランス
基礎的な学習では、単純な暗記ではなく、内容の理解を重視することが重要です。特に解剖生理学や病態生理学については、なぜそうなるのかという理解を深めることで、長期的な記憶定着が可能になります。
また、理解した内容を自分の言葉で説明できるようになることで、より確実な知識の定着が図れます。
ノートの作成方法
効果的なノート作成は学習効率を大きく左右します。重要なポイントを簡潔にまとめ、図や表を活用して視覚的に理解しやすい形にすることをおすすめします。特に、関連する内容をつなぎ合わせて整理することで、横断的な理解が深まります。
問題演習の効果的な進め方
時間配分の工夫
問題演習では、本番の試験を意識した時間配分で取り組むことが重要です。1問あたり1分から1分30秒を目安に解答し、時間内に問題を処理する習慣をつけていきます。
また、時間を計りながら一定量の問題を解くトレーニングを重ねることで、本番での時間管理がスムーズになります。
解答の分析方法
問題を解いた後の振り返りが非常に重要です。正解した問題についても、なぜその選択肢が正解なのかを確認し、他の選択肢が不正解である理由も含めて理解を深めます。
特に、迷った問題や間違えた問題については、関連する内容も含めて詳しく学習することで、同様の問題に対応できる力が身につきます。
応用力を高める学習方法
状況設定問題への対応
状況設定問題では、与えられた情報を正確に読み取り、優先順位を判断する力が求められます。実際の臨床場面をイメージしながら問題に取り組むことで、より実践的な判断力を養うことができます。
また、一つの事例について複数の視点から考察することで、より深い理解が可能になります。
知識の統合方法
個別の知識を横断的につなげることで、より応用力の高い理解が得られます。例えば、疾患の病態生理と看護ケアの関連性を理解することで、様々な状況に対応できる実践力が身につきます。
グループ学習の活活用法
効果的なグループ作り
グループ学習では、3から5人程度の少人数で構成することが効果的です。メンバーそれぞれの得意分野や学習スタイルを活かしながら、互いに補完し合える関係を築くことが重要です。また、定期的な学習会の開催により、継続的なモチベーション維持が可能になります。
ディスカッションの進め方
グループでのディスカッションでは、一つのテーマについて多角的な視点で検討することができます。特に、状況設定問題を題材にした場合、それぞれの考え方や臨床経験を共有することで、より深い理解につながります。
また、互いに説明し合うことで、知識の定着度を確認することもできます。
効果的な復習方法
定期的な振り返り
学習した内容は、記憶の定着度に応じて計画的に復習することが重要です。新しく学習した内容は、当日中に一度復習し、その後1週間以内、1ヶ月以内というように段階的に復習することで、長期的な記憶定着が図れます。
弱点克服のアプローチ
苦手分野の克服には、まず基本的な理解から見直すことが重要です。特に、なぜ理解が困難なのかを分析し、自分に合った学習方法を見つけることで、効果的な克服が可能になります。
また、定期的に弱点分野の問題に取り組むことで、徐々に自信をつけていくことができます。
学習環境の整備
効率的な学習スペース
集中して学習できる環境を整えることは、学習効率を高める重要な要素です。適度な明るさ、温度、騒音レベルの管理など、自分に合った環境づくりを心がけましょう。また、スマートフォンなどの気が散る要素は、可能な限り排除することをおすすめします。
デジタルツールの活用
スマートフォンやタブレットの学習アプリを効果的に活用することで、隙間時間での学習も可能になります。ただし、SNSなどの娯楽との境界線を明確にし、学習に集中できる環境を維持することが重要です。
このように、様々な学習方法を組み合わせながら、自分に最適な学習スタイルを確立することが、看護師国家試験合格への近道となります。ただし、これらの方法はあくまでも基本的なアプローチであり、個人の特性や状況に応じて柔軟に調整していくことが大切です。
おしえてカンゴさん!よくある質問

看護師国家試験に関して、多くの受験生から寄せられる質問について、経験豊富なカンゴさんが分かりやすく回答します。ここでは、試験対策における疑問や不安について、具体的なアドバイスをご紹介します。
学習スケジュールについて
Q1:いつから本格的な試験対策を始めるべきでしょうか?
通常は実習が一段落する9月頃から本格的な対策を開始することをおすすめします。ただし、基礎的な学習は日々の授業からしっかりと行うことが重要です。特に必修問題については、早い段階から意識的に学習を進めていくと良いでしょう。
Q2:1日どのくらいの学習時間を確保すべきですか?
学習時間は個人の状況によって異なりますが、平日は2~3時間、休日は4~6時間程度を目安にすると良いでしょう。ただし、時間の長さよりも、集中して取り組める環境を整えることの方が重要です。また、こまめに休憩を入れることで、効率的な学習が可能になります。
学習方法について
Q3:苦手科目の効果的な対策方法を教えてください
苦手科目の克服には、まず基本的な部分から学び直すことをおすすめします。特に、なぜ理解できないのかを具体的に把握することが重要です。
また、1日30分でも良いので、毎日その科目に触れる時間を作ることで、徐々に苦手意識を克服することができます。関連する分野の学習と組み合わせることで、より理解が深まることもあります。
Q4:状況設定問題の解き方のコツはありますか?
状況設定問題では、まず設問を先に読んでから事例を読むことをおすすめします。その上で、患者の基本情報、現在の状態、治療内容などを整理しながら読み進めていきます。
また、優先順位を考える際は、生命の危険性、緊急性、重要性の3点を意識すると判断しやすくなります。
試験対策の進め方について
Q5:模擬試験はどのように活用すれば良いですか?
模擬試験は、自己の実力を把握し、弱点を発見するための重要なツールです。毎回の結果を分析し、間違えた問題や迷った問題については、関連する内容も含めて深く学習することをおすすめします。また、本番と同じ時間配分で解くことで、時間管理の練習にもなります。
Q6:過去問題はどのように活用すれば効果的ですか?
過去問題は、出題傾向を把握し、実践力を養うための貴重な教材です。単に解くだけでなく、各問題について、なぜその選択肢が正解なのか、他の選択肢が不正解なのかを理解することが重要です。
また、関連する内容についても学習を広げることで、より深い理解につながります。
試験直前期の対策について
Q7:試験直前に気をつけることはありますか?
試験1週間前からは、新しい内容の学習は控えめにし、既習内容の確認に重点を置くことをおすすめします。
また、睡眠時間を確保し、規則正しい生活リズムを維持することが重要です。試験前日は、軽い復習程度にとどめ、心身をリフレッシュさせることを心がけましょう。
精神面のケアについて
Q8:不安が強くて眠れないのですが、どうすれば良いですか?
試験に対する不安を感じることは自然なことです。学習の合間に適度な運動を取り入れたり、リラックスできる時間を確保したりすることが大切です。
また、同じ目標を持つ仲間との交流も、精神面でのサポートとなります。睡眠時間が確保できない場合は、一度学習計画を見直してみることをおすすめします。
このように、試験対策には様々な疑問や不安がつきものですが、一つ一つ着実に解決していくことで、より効果的な学習が可能になります。カンゴさんの回答を参考に、自分に合った学習方法を見つけていきましょう。
まとめ

本記事では、看護師国家試験の年度別難易度の推移と特徴的な変化、そして効果的な対策方法についてご紹介しました。
近年の傾向として、実践的な判断力を問う問題が増加し、特に在宅医療や地域包括ケアに関する出題が重視されています。試験対策においては、基礎的な知識の確実な習得に加え、状況に応じた判断力を養うことが重要です。
合格への近道は、計画的な学習とともに、自分に合った効果的な学習方法を見つけることです。一人ひとりの状況は異なりますが、本記事で紹介した時期別の学習計画や、先輩たちの体験談を参考に、着実な準備を進めていただければと思います。
さらに詳しい試験対策情報や、現役看護師による試験合格体験記をお探しの方は、「はたらく看護師さん」をご覧ください。
会員登録(無料)いただくと、毎月更新される過去問解説や、科目別の詳細な学習ガイド、そして先輩看護師への質問機能など、より充実したコンテンツをご利用いただけます。あなたの夢への第一歩を、私たちがしっかりとサポートいたします。