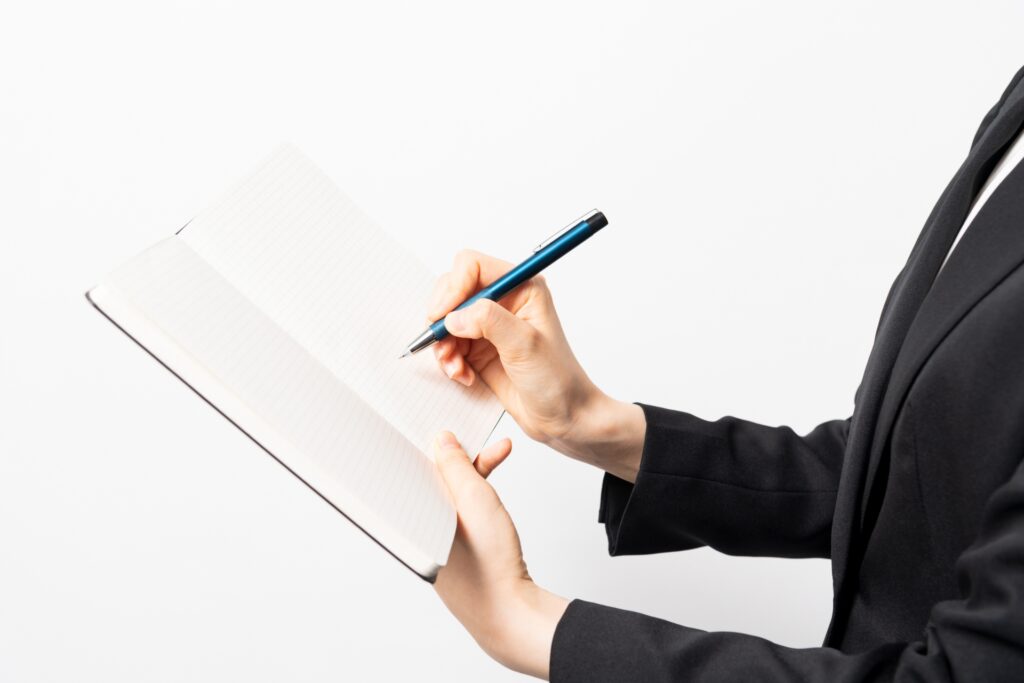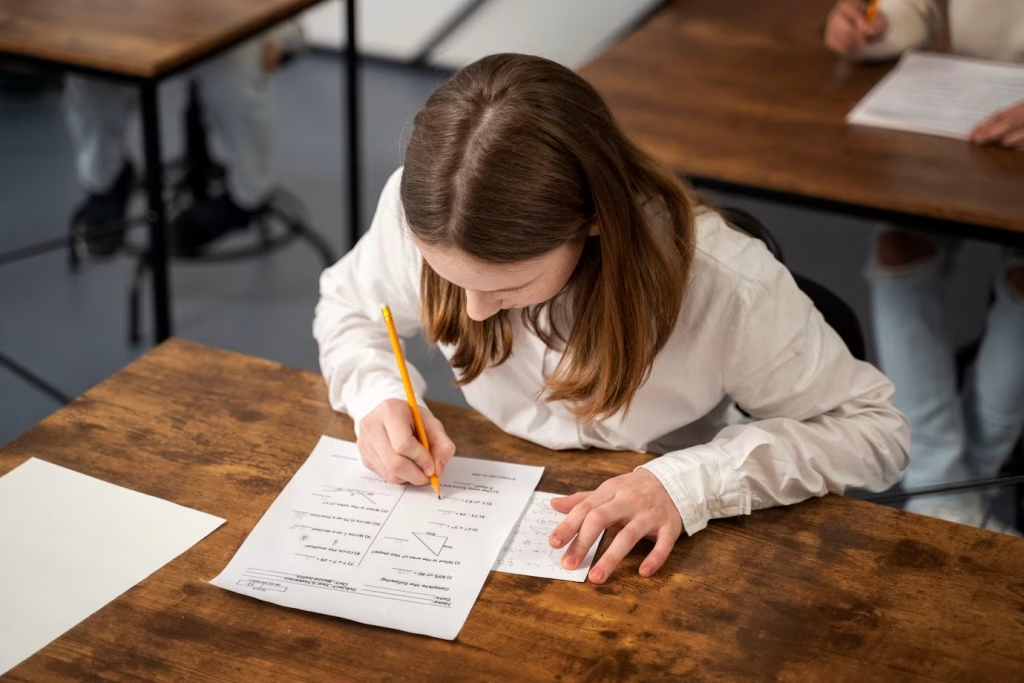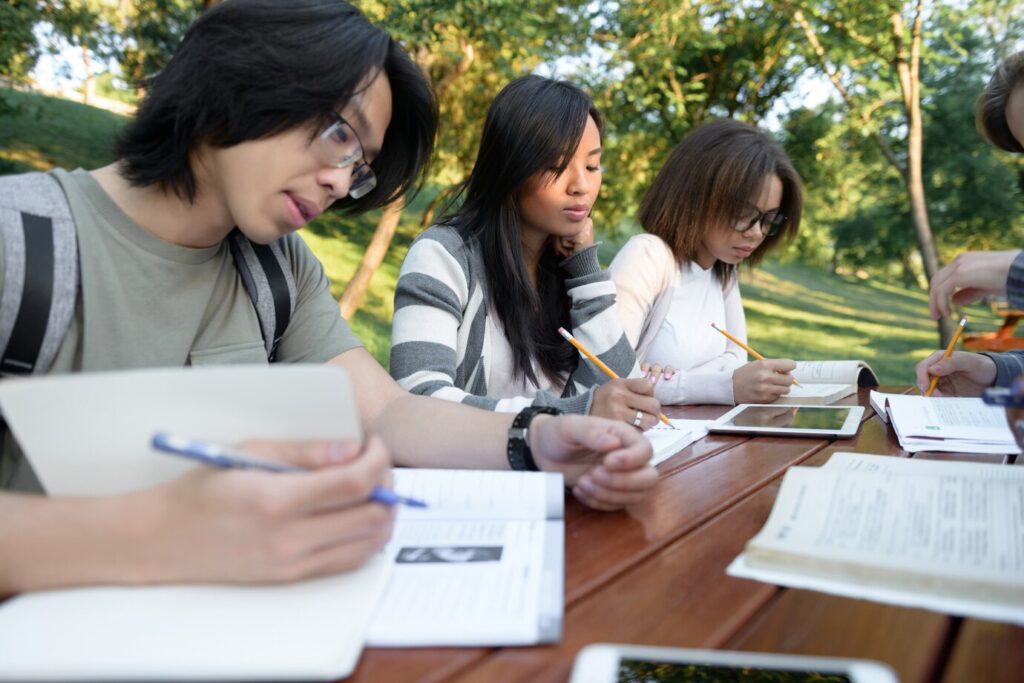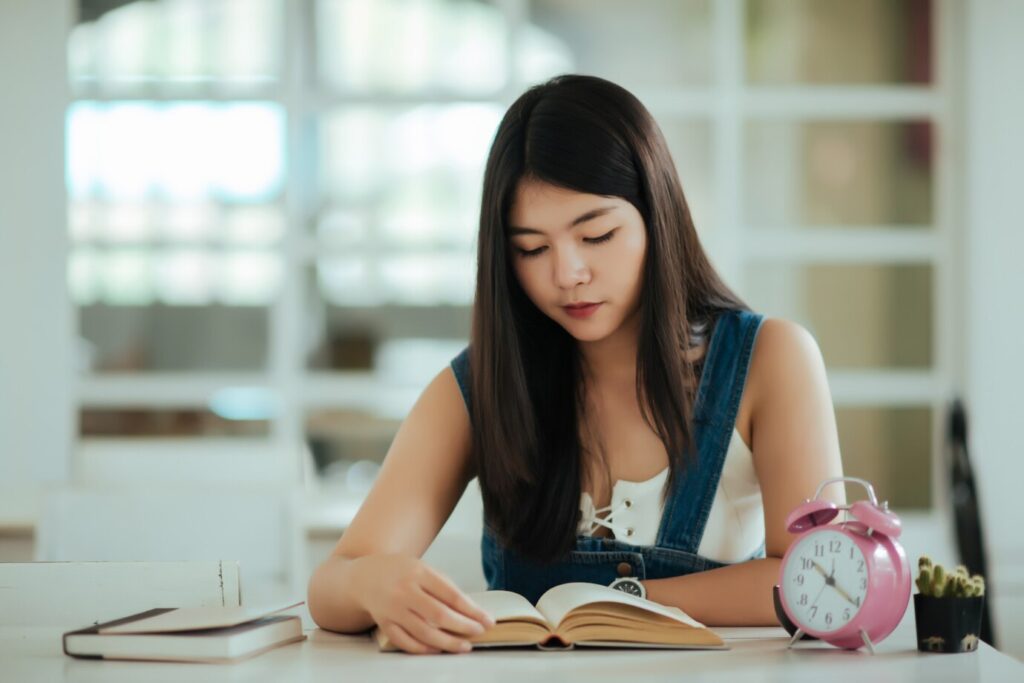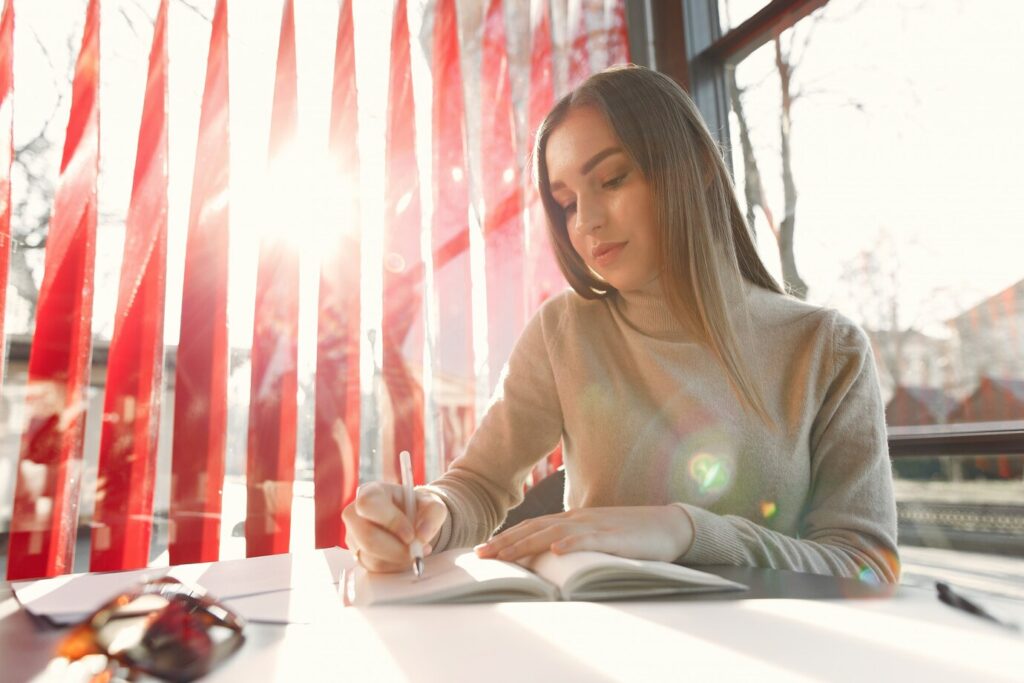看護ケアの質を高める基本となるのが、正確な患者観察です。
この記事では、臨床実習や将来の看護実践で活用できる観察技術について、最新の知見を交えながら詳しく解説します。患者の些細な変化も見逃さない観察力を身につけ、アセスメントから記録・報告まで、一連のプロセスを効果的に実践できるようになりましょう。
この記事を読むと患者観察のポイントを網羅できます。
この記事で分かること
- 系統的な患者観察の手順とポイント、および症状把握と早期発見方法
- 効果的な記録の書き方と報告基準
- 実習現場での観察アプローチと精度向上テクニック
この記事を読んでほしい人
- 臨床実習前の看護学生、および基礎看護技術の復習を希望する1-2年生の方
- 観察力とアセスメント能力の向上を目指す学生の方
- 記録・報告に不安を感じている実習生の方
系統的な患者観察の基本

患者観察は看護ケアの出発点であり、その精度は看護実践の質を大きく左右します。
ここでは、効果的な観察を行うための基本的な考え方と具体的な技術について解説します。
観察の3つの基本姿勢
観察の質を高めるためには、まず適切な観察姿勢を身につけることが重要です。ここでは看護実践における3つの重要な観察姿勢について詳しく説明します。
客観的な視点の保持
患者観察において最も重要なのは、客観的な視点を持つことです。先入観や思い込みにとらわれることなく、目の前の事実を正確に捉える必要があります。
具体的な数値やデータを重視し、主観的な印象と客観的な所見を明確に区別することで、より正確な観察が可能となります。また、他者と共有可能な表現を用いることで、チーム医療における情報共有の質も向上します。
継続的な観察の実施
患者の状態は刻々と変化するため、一時点の観察だけでは不十分です。定期的な再評価と経時的な変化の把握が重要となります。
前回の観察結果と比較することで、わずかな変化も見逃さず、早期発見につなげることができます。特に急性期の患者さんでは、vital signsの変動や症状の進行を細かく観察することが求められます。
全体像の把握
患者さんを理解する際には、身体的な側面だけでなく、精神面や社会的背景も含めた全体像を把握することが重要です。
患者の生活環境や家族関係、社会的役割なども考慮に入れることで、より適切なケアの提供が可能となります。また、患者さんの価値観や希望を理解することで、個別性の高い看護計画を立案することができます。
観察の基本技術
基本的な観察技術には、視診、触診、聴診、打診があります。それぞれの技術を正しく理解し、適切に実施することが重要です。以下、各技術の具体的な実施方法について解説します。
視診の実施方法
視診は最も基本的な観察技術です。全身の状態から局所の変化まで、系統的に観察を行います。まず全体的な印象を捉え、次に部位ごとの詳細な観察へと進みます。左右差の有無や色調の変化、腫脹の有無などを確認します。また、表情や動作からも多くの情報を得ることができます。
触診のテクニック
触診では、手指の感覚を最大限に活用します。温度、硬度、振動、脈拍など、多くの情報を得ることができます。触診を行う際は、患者さんに声をかけ、適切な圧で優しく触れることが重要です。また、左右差の確認や深部触診など、目的に応じて適切な手技を選択します。
聴診の基本
聴診器を使用する際は、周囲の騒音に注意を払い、適切な聴診部位を選択します。呼吸音や心音、腸蠕動音など、目的に応じて聴診部位や聴診時間を調整します。また、正常音と異常音の違いを理解し、わずかな変化も見逃さないよう注意を払います。
打診の実施手順
打診は主に胸部や腹部の検査で用います。適切な強さと角度で打診を行い、得られた音の性質から臓器の位置や大きさ、内部の状態を判断します。打診音の違いを正確に判断できるよう、繰り返し練習することが重要です。
バイタルサイン測定と評価

バイタルサインは患者の生命徴候を示す重要な指標です。正確な測定技術と適切な評価能力は、看護師として必須のスキルとなります。
ここでは、各バイタルサインの測定方法と評価のポイントについて詳しく解説します。
体温測定の実践
体温測定は患者の健康状態を把握する基本的な指標です。デジタル体温計が主流となった現在でも、測定部位の選択や測定時の注意点を理解することが重要です。
測定部位の選択
腋窩温度は最も一般的な測定方法です。測定時は腋窩を十分に乾燥させ、体温計の感温部を確実に腋窩中心に密着させます。舌下温や直腸温など、状況に応じて適切な測定部位を選択することも重要となります。
正確な測定のためのポイント
測定値に影響を与える要因として、運動後、食事後、入浴後などの体温変動を考慮する必要があります。また、測定環境の温度や、患者の体動なども測定値に影響を与えるため、これらの要因を適切にコントロールすることが求められます。
脈拍測定の技術
脈拍測定では、回数だけでなく、リズム、緊張度、左右差なども重要な観察項目となります。
触診による脈拍測定
橈骨動脈での脈拍測定が最も一般的です。第2-3指の指腹を使用し、適度な圧で触知します。15秒間の測定値を4倍して1分間の脈拍数を算出しますが、不整脈が疑われる場合は1分間通して測定を行います。
脈拍の質的評価
脈拍の大きさ、リズム、緊張度を評価します。特に不整脈の有無や、脈拍の欠損の確認は重要です。また、末梢循環不全の早期発見のため、四肢の脈拍触知も定期的に実施します。
血圧測定のテクニック
血圧測定は循環動態を評価する上で重要な指標です。正確な測定値を得るためには、適切な手技と環境整備が不可欠です。
測定環境の整備
安静時の血圧を測定するため、測定前に5分程度の安静を確保します。測定環境の温度や騒音にも配慮が必要です。また、患者の体位や腕の位置にも注意を払い、心臓の高さで測定することが重要です。
測定手順と注意点
カフの巻き方や加圧の程度、減圧速度など、基本的な手技を確実に実施します。また、白衣高血圧や機器の特性による誤差なども考慮に入れ、状況に応じて複数回の測定を行います。
呼吸の観察と測定
呼吸の観察は、回数だけでなく、呼吸の質や呼吸パターンの評価も重要です。患者の状態を正確に把握するため、複合的な視点での観察が必要となります。
呼吸数の測定方法
呼吸数の測定は患者に意識させないよう、脈拍測定時などに合わせて実施します。胸腹部の動きを観察しながら、30秒間の呼吸回数を数えて2倍し、1分間の呼吸数を算出します。呼吸が不規則な場合は1分間通しての測定が必要です。
呼吸の質的評価
呼吸の深さ、リズム、呼吸様式(胸式呼吸か腹式呼吸か)を観察します。また、呼吸音の性状や左右差、呼吸補助筋の使用有無なども重要な観察項目となります。チアノーゼの有無や呼吸困難の程度についても併せて評価を行います。
症状別観察ポイント

症状に応じた的確な観察は、患者の状態変化を早期に発見し、適切な対応につなげるために不可欠です。
このセクションでは、各症状の特徴や、重点的に観察すべきポイントについて紹介します。この内容を理解することで、より効果的な看護ケアが可能となります。
呼吸器系症状の観察
呼吸器系の症状は生命に直結する重要な観察項目です。呼吸困難や咳嗽、喀痰など、それぞれの症状について詳細な観察と適切な評価が求められます。
呼吸困難の評価
呼吸困難の程度は、会話や日常生活動作への影響から判断します。また、体位による症状の変化や、酸素飽和度の値との関連性も重要な評価項目となります。呼吸困難を訴える患者には、速やかに楽な体位を確保し、必要に応じて酸素投与の準備を行います。
咳嗽と喀痰の観察
咳嗽の性状(乾性か湿性か)や発生時期、増悪因子などを確認します。喀痰については、量、性状、色調、臭気などを詳細に観察し、記録します。血痰の有無は特に重要な観察項目となります。
循環器系症状の観察
循環器系の症状は、緊急性の高い状態につながる可能性があるため、迅速な観察と評価が必要です。胸痛や動悸、浮腫など、各症状の特徴を理解し、適切な観察を行います。
胸痛の詳細な観察
胸痛の性状、部位、持続時間、放散痛の有無などを詳しく確認します。また、増悪因子や軽快因子、随伴症状の有無についても聴取します。狭心症を疑う場合は、バイタルサインの測定と心電図モニタリングを速やかに実施します。
動悸の評価方法
動悸の発生状況や持続時間、随伴症状について詳しく観察します。特に意識状態の変化や血圧低下などの危険な徴候がないかを確認します。また、日常生活での誘因や生活習慣との関連性についても評価を行います。
消化器系症状の観察
消化器系の症状は患者のQOLに大きく影響します。適切な観察と評価により、早期の対応と症状緩和が可能となります。
嘔気・嘔吐の観察
嘔気・嘔吐の発生時期や頻度、性状、量について詳細に観察します。また、食事との関連性や、脱水症状の有無についても注意深く評価します。嘔吐物の性状は、原因疾患の推測や重症度の判断に重要な情報となります。
腹痛の評価
腹痛の部位、性状、強度を詳しく観察します。また、痛みの移動の有無や、体位による症状の変化についても確認します。腹部の触診所見や腸蠕動音の聴取結果も併せて評価し、緊急性の判断を行います。
神経系症状の観察
神経系の症状は、迅速な対応が求められる場合が多く、系統的な観察と正確な評価が特に重要です。
意識レベルの評価
意識レベルの評価はJCSやGCSなどの評価スケールを用いて客観的に行います。また、瞳孔径や対光反射、運動機能、感覚機能についても詳細に観察します。意識レベルの変化は、経時的な評価と記録が特に重要となります。
運動・感覚機能の観察
麻痺や筋力低下、感覚障害の有無を確認します。上下肢の動きや握力、歩行状態など、具体的な機能評価を行います。また、しびれや痛みなどの感覚症状についても、部位や程度を詳しく観察します。
運動器系症状の観察
運動器系の症状は、患者の日常生活動作に直接影響を与えます。適切な観察と評価により、効果的なリハビリテーション計画の立案が可能となります。
関節可動域の評価
関節の可動域制限や疼痛の有無を確認します。また、日常生活動作への影響度や、補助具の必要性についても評価します。リハビリテーションの進行状況に応じて、定期的な再評価を行います。
重症度評価とアセスメント
患者の状態を適切に評価し、必要な看護介入を判断するためには、系統的な重症度評価とアセスメントが不可欠です。
ここでは、臨床現場で活用できる具体的な評価方法について解説します。
重症度評価の基準
重症度評価は患者の状態を客観的に判断し、適切な看護ケアを提供するための基礎となります。生理学的指標や日常生活動作の自立度など、多角的な視点での評価が必要です。
フィジカルアセスメントの実際
バイタルサインの測定結果や身体症状の有無、検査データの推移など、客観的な指標を総合的に評価します。特に呼吸・循環動態の安定性や意識レベルの変化には注意を払い、異常の早期発見に努めます。
生活機能の評価
食事、排泄、清潔保持など、基本的な日常生活動作の自立度を評価します。また、疾患や治療が生活機能に与える影響についても考慮し、必要な援助の程度を判断します。
優先順位の決定
複数の問題を抱える患者のケアでは、適切な優先順位の決定が重要です。生命への危険度や症状の緊急性を考慮しながら、効果的なケア計画を立案します。
緊急性の判断
生命に直結する症状や急激な状態変化には、最優先で対応する必要があります。バイタルサインの異常や意識レベルの低下、重篤な症状の出現などは、即座に医師への報告と必要な対応が求められます。
患者ニーズの把握
患者の訴えや希望を傾聴し、QOL向上のために必要なケアの優先度を判断します。また、家族の意向や社会的背景なども考慮に入れ、総合的な視点でケア計画を立案します。
アセスメントツールの活用
客観的な評価を行うため、各種アセスメントツールを適切に活用することが重要です。状況に応じて最適なツールを選択し、正確な評価を心がけます。
スケールの選択と使用方法
疼痛評価のNRSやVAS、褥瘡リスク評価のブレーデンスケール、せん妄評価のCAM-ICUなど、目的に応じた適切なスケールを選択します。各スケールの特徴と限界を理解し、適切に活用することが重要です。
経時的評価の重要性
患者の状態は刻々と変化するため、定期的な再評価と記録が重要となります。特に急性期の患者や状態が不安定な患者では、より頻回な観察と評価が必要です。
評価間隔の設定
患者の状態や治療段階に応じて、適切な評価間隔を設定します。急性期では数時間ごと、安定期では1日1回など、状況に応じて柔軟に対応します。また、症状の変化や新たな治療開始時には、評価頻度を見直す必要があります。
変化の記録と分析
経時的な変化を正確に記録し、傾向分析を行います。バイタルサインの推移や症状の変化、治療への反応など、客観的なデータの蓄積と分析が重要です。
効果的な記録方法

看護記録は医療の質を保証し、チーム医療を支える重要な文書です。
ここでは、正確で効果的な記録の作成方法について解説します。
基本的な記録の書き方
看護記録には客観性、正確性、簡潔性が求められます。事実に基づいた記述と、必要十分な情報の記載を心がけます。
記録の基本原則
主観的情報と客観的情報を明確に区別して記載します。また、時系列に沿った記録と、重要な情報の漏れがないよう注意を払います。医療者間で共通認識を持てるよう、標準化された用語や略語を適切に使用します。
記録の構成要素
患者の訴え、観察結果、実施したケア、患者の反応など、必要な情報を漏れなく記載します。特に異常の発見や状態変化時には、発見時の状況や対応内容を詳細に記録します。
SOAPの活用方法
SOAP形式の記録は、問題志向型の記録方式として広く普及しています。各項目の特徴を理解し、適切な記載を心がけます。
主観的情報(S)の記載
患者の訴えや感覚、家族からの情報など、主観的な情報を記載します。会話内容はできるだけ患者の言葉をそのまま用い、より正確な情報伝達を心がけます。
客観的情報(O)の記載
観察結果やバイタルサイン、検査データなど、客観的に確認できる情報を記載します。測定値や観察事項は具体的な数値や状態を明記し、あいまいな表現は避けます。
アセスメント(A)の記載
収集した情報を分析し、患者の状態や問題点を評価します。アセスメントには看護師の専門的判断を含め、その根拠となる情報も併せて記載します。
計画(P)の記載
アセスメントに基づいて立案した看護計画や、実施予定の看護介入について記載します。具体的な目標設定と介入方法を明確にし、評価計画も含めて記録します。
電子カルテの使用
電子カルテシステムでの記録には、システムの特性を理解し、効率的な記録方法を身につけることが重要です。
テンプレートの活用
よく使用する記録項目はテンプレート化し、効率的な記録を心がけます。ただし、個別性を考慮し、必要に応じて追加・修正を行います。
システム操作の注意点
誤入力や入力モレを防ぐため、入力後の確認を徹底します。また、システムトラブル時の対応方法についても、あらかじめ理解しておく必要があります。
記録の法的側面
看護記録は法的文書としての側面も持ちます。記録の作成と保管には、法的要件を満たす必要があります。
記録の要件
日時、記録者、実施者を明確にし、事実に基づいた客観的な記載を心がけます。訂正が必要な場合は、定められた方法で適切に対応します。
個人情報の保護
患者の個人情報保護に十分注意を払い、記録の閲覧や取り扱いには慎重を期します。また、記録の開示請求への対応についても理解しておく必要があります。
報告・連絡・相談
医療チームでの効果的なコミュニケーションは、安全で質の高い医療を提供するために不可欠です。
ここでは、適切な報告・連絡・相談の方法について解説します。
SBAR手法の詳細
SBAR(エスバー)は、医療現場での簡潔で効果的なコミュニケーション手法です。状況、背景、評価、提案の順で情報を整理し、伝達します。
状況(Situation)の伝え方
まず患者の現在の状況を簡潔に説明します。患者の基本情報と、報告が必要となった直接の理由を明確に伝えます。伝える内容は要点を絞り、重要な情報から優先的に報告します。
背景(Background)の説明
患者の既往歴や現病歴、これまでの経過など、状況の理解に必要な背景情報を提供します。特に現在の状況に関連する重要な情報を選択して伝えます。
評価(Assessment)の共有
現状のアセスメント結果を伝えます。観察結果や検査データに基づく判断、予測される展開について、自身の見解を述べます。根拠となる情報も併せて報告します。
提案(Recommendation)の実施
状況改善のために必要と考える対応や支援を具体的に提案します。緊急性の判断も含め、実行可能な選択肢を示します。
緊急時の報告
緊急時には、より簡潔で的確な報告が求められます。状況の重大性を適切に伝え、必要な対応を迅速に実施することが重要です。
緊急度の判断
バイタルサインの急激な変化や意識レベルの低下など、生命に関わる徴候を見逃さず報告します。躊躇することなく、速やかに上級医や指導者への報告を行います。
簡潔な情報伝達
緊急時の報告では、最も重要な情報を最初に伝えます。患者の状態、必要な対応、現在実施している処置など、優先度の高い情報から順に報告します。時間の経過とともに状態が変化する場合は、変化の推移も含めて報告します。
多職種連携
チーム医療において、多職種間での効果的なコミュニケーションは必要不可欠です。それぞれの専門性を理解し、適切な情報共有を行うことが重要となります。
職種間の情報共有
医師、看護師、理学療法士、薬剤師など、各職種との円滑な情報共有を心がけます。専門用語の使用は相手に応じて適切に調整し、誤解のない communication を図ります。
カンファレンスでの発言
多職種カンファレンスでは、看護の視点からの観察結果や評価を簡潔に伝えます。患者の生活面での情報や、ケアの実施状況なども重要な共有事項となります。
申し送りのコツ
申し送りは、継続的な看護ケアを提供するための重要な情報伝達の機会です。必要な情報を漏れなく、効率的に伝達することが求められます。
重要事項の優先順位
患者の状態変化や新たな指示事項など、特に注意が必要な情報を優先的に伝えます。ルーチン業務に関する情報は、重要度に応じて簡潔に要約します。
継続課題の明確化
次勤務帯で継続して観察や対応が必要な事項を明確に伝えます。観察のポイントや、予測される状態変化についても情報共有を行います。
ケーススタディ:臨床実践における患者観察の実際
ここまで解説したポイントを実際にどのような形で使用していくのかを知ることはとても効果的です。
ここでは、さまざまな場面において患者観察をどのように行っていくのかを紹介していきます。
急性期看護における観察とケア
ケース1:術後早期のバイタルサイン管理
68歳の山田太郎さんは胃がんによる幽門側胃切除術を受けた直後である。術前から高血圧症と2型糖尿病があり、術後の血圧変動と血糖値管理が課題となっている。術直後のバイタルサインは、血圧156/92mmHg、脈拍92回/分、体温37.2℃、SpO2 95%(酸素2L/分投与下)であった。
腹部正中創からの浸出液は淡血性で、腹腔ドレーンからの排液量は術後2時間で80mlである。疼痛スケールはNRS7であり、硬膜外麻酔による疼痛管理を実施中である。手術侵襲による生体反応と疼痛による血圧上昇が予測されるため、15分間隔でのバイタルサイン測定と疼痛評価を継続している。
ケース2:呼吸器合併症予防の観察
74歳の佐藤花子さんは肺炎による呼吸不全で入院し、人工呼吸器管理となっている。COPDの既往があり、長期の喫煙歴を有する。人工呼吸器の設定はAC mode、FiO2 0.4、PEEP 5cmH2O、PS 8cmH2Oである。呼吸数は22回/分、SpO2は94%で推移している。
両側の呼吸音は減弱しており、断続的な湿性ラ音を聴取する。気管内吸引では黄緑色の粘稠痰を認め、1回の吸引で約3mlの喀痰を吸引している。
体位変換時にSpO2の一過性低下がみられ、吸入酸素濃度の一時的な上昇を要することがある。人工呼吸器関連肺炎の予防と早期離脱に向けて、呼吸状態の綿密な観察を継続している。
ケース3:循環動態不安定患者の管理
62歳の鈴木一郎さんは急性心筋梗塞で緊急カテーテル治療を受けた。右冠動脈#2に99%狭窄を認め、薬剤溶出性ステントを留置した。治療後、血圧88/52mmHg、脈拍112回/分とショック状態を呈している。心電図モニターではII、III、aVFでST上昇が残存し、時折PVCを認める。
末梢冷感が著明で、尿量は0.3ml/kg/hrと乏尿傾向にある。ドパミン5γの持続投与を開始し、輸液負荷を実施している。心原性ショックの進行が懸念されるため、血行動態の継続的なモニタリングと組織灌流の評価を重点的に行っている。
7.2 慢性期看護における継続観察
ケース4:糖尿病患者の自己管理支援
55歳の田中正子さんは2型糖尿病のコントロール不良で教育入院となった。HbA1c 10.2%、空腹時血糖値280mg/dlと著明な高値を示している。糖尿病性網膜症と早期腎症を合併しており、両下肢には軽度の浮腫を認める。食事摂取量は不規則で、運動習慣はない。
職場でのストレスが強く、自己血糖測定も不定期である。食事療法と運動療法の習慣化、ストレスマネジメントを含めた包括的な生活指導を実施している。合併症の進行予防と自己管理能力の向上を目指し、継続的な観察と支援を行っている。
ケース5:透析患者の水分管理
70歳の渡辺和子さんは慢性腎不全で週3回の血液透析を受けている。透析間の体重増加が著しく、しばしば5kgを超える。高血圧と心不全の既往があり、下肢浮腫と労作時呼吸困難を認める。食事制限への理解は不十分で、特に塩分制限が守れていない。
透析中は血圧低下を起こしやすく、除水に難渋することが多い。心胸比は58%で心拡大を認め、心エコーでは左室肥大と壁運動低下を指摘されている。水分制限の重要性と適切な食事管理について、理解度に合わせた指導を継続している。
7.3 高齢者看護における観察の特徴
ケース6:認知症患者の転倒予防
83歳の中村良子さんは、アルツハイマー型認知症のため介護老人保健施設に入所している。HDS-R 12点、MMSE 15点と認知機能の低下を認め、見当識障害と短期記憶障害が顕著である。夜間の徘徊があり、過去3ヶ月で2回の転倒歴がある。
両下肢の筋力低下と歩行時のふらつきを認め、TUGテストは18秒と延長している。必要な介助を拒否する傾向があり、転倒リスクの高い行動がみられる。生活リズムの調整と安全な環境整備を行いながら、ADLの維持と転倒予防に向けた観察と支援を継続している。
ケース7:終末期患者の緩和ケア
78歳の木村美智子さんは、膵臓がん末期で在宅療養中である。疼痛コントロールのためモルヒネ持続皮下注射を使用しているが、breakthrough painが出現している。食事摂取量は著しく低下し、1日あたり200ml程度の水分摂取も困難となっている。
全身倦怠感が強く、PS4の状態である。夜間の不眠と不安を訴え、家族の疲労も顕著になってきている。緩和ケアチームと連携しながら、症状マネジメントとQOL維持に向けた支援を実施している。定期的な訪問看護で、患者と家族の心身両面のケアを継続している。
7.4 周術期看護における観察とケア
ケース8:大腸がん術後患者の回復支援
65歳の小林健一さんは、上行結腸がんに対して腹腔鏡下結腸右半切除術を受けた術後3日目である。創部の疼痛はNRS4程度で、硬膜外麻酔による疼痛管理を継続している。腸蠕動音は弱いが聴取可能で、少量の排ガスを認める。術後イレウス予防のため、早期離床を進めている。
硬膜外麻酔による血圧低下と起立性低血圧に注意しながら、リハビリテーションを段階的に進めている。腹部正中創の状態は良好で、浸出液や発赤は認めていない。創部の観察と疼痛管理を継続しながら、術後合併症の予防に努めている。
ケース9:心臓手術後の呼吸循環管理
72歳の高橋正夫さんは、大動脈弁置換術後ICUに入室中である。人工呼吸器管理下で、Swan-Ganzカテーテルによる循環動態モニタリングを実施している。心拍数80回/分、心房細動、CI 2.2L/min/m2、CVP 12mmHg、PCWP 15mmHgである。
胸腔ドレーンからの排液量は術後12時間で350mlで、淡血性である。利尿薬の持続投与により、尿量は1.0ml/kg/hrを維持している。循環動態の安定化と呼吸状態の改善を目指し、バイタルサインと各種パラメータの継続的なモニタリングを行っている。
ケース10:整形外科術後のリハビリテーション
58歳の山本京子さんは、変形性膝関節症に対して人工膝関節置換術を受けた術後5日目である。術後の疼痛コントロールは良好で、CPMによる関節可動域訓練を実施中である。膝関節の可動域は屈曲95度、伸展-5度まで改善している。
創部の状態は良好で、膝関節周囲の腫脹は軽度である。深部静脈血栓症の予防のため、間欠的空気圧迫法を実施し、下肢の腫脹や疼痛の有無を定期的に確認している。理学療法士と連携しながら、歩行器を使用した歩行訓練を段階的に進めている。
特殊な状況における看護観察
ケース11:精神疾患患者の自殺リスク管理
42歳の斎藤真理さんは、うつ病の増悪により精神科病棟に入院している。希死念慮が強く、入院前に過量服薬の既往がある。不眠と食欲低下が顕著で、1日の食事摂取量は3割程度である。自室に引きこもりがちで、他者とのコミュニケーションを避ける傾向にある。
表情は暗く、自責的な発言が多い。24時間の観察体制で自殺企図の予防に努めており、定期的な面談を通じて心理状態の評価を行っている。薬物療法の効果判定と副作用モニタリングも並行して実施している。
ケース12:重症熱傷患者の全身管理
35歳の井上太郎さんは、火災による40%熱傷(II度深達性・III度混在)で救命センターに入院している。気道熱傷を合併し、人工呼吸器管理となっている。Parkland’s formulaに基づく大量輸液療法を実施中で、尿量は0.8ml/kg/hrを維持している。
熱傷創は銀含有創傷被覆材でドレッシングを行い、感染予防に努めている。体温38.8℃、WBC 15,000/μl、CRP 8.5mg/dlと炎症反応の上昇を認める。熱傷創の状態観察と感染兆候の早期発見、適切な輸液管理を継続している。
ケース13:救急搬送された多発性外傷患者
25歳の加藤健司さんは、バイク事故による多発性外傷で救急搬送された。右大腿骨骨折、左血気胸、肝損傷(II型)を認める。来院時のバイタルサインはBP 95/60mmHg、HR 118/分、RR 24/分、GCS E3V4M6であった。
左胸腔ドレナージを実施し、大量輸液とRBC輸血を開始している。腹部エコーでは少量の腹腔内出血を認めるが、保存的加療の方針となっている。全身状態の継続的な評価と、出血性ショックの進行予防に重点を置いた観察を実施している。
ケース14:感染症患者の隔離管理
45歳の野田健一さんは、新型コロナウイルス感染症の重症化により人工呼吸器管理となっている。P/F比 150、PEEP 10cmH2O、FiO2 0.6の設定で、SpO2 93%を維持している。38.5℃の発熱が持続し、両側肺野のすりガラス影が拡大傾向である。
プロンポジションを1日2回実施し、酸素化の改善を図っている。感染対策を徹底しながら、呼吸状態の観察と全身管理を継続している。隔離環境下でのケア提供と心理的支援にも配慮している。
ケース15:小児救急患者の観察管理
3歳の伊藤さくらちゃんは、熱性けいれんで救急搬送された。来院時の体温39.8℃、けいれん発作は5分程度で自然停止した。既往歴として、1歳時に熱性けいれんの経験がある。バイタルサインは安定しているが、不機嫌で機嫌が悪く、水分摂取も不良である。
解熱剤の投与と冷罨法による体温管理を実施している。再度のけいれん発作に備え、気道確保の準備と酸素投与の準備を整えている。家族の不安も強く、精神的支援も含めた観察と管理を継続している。
よくある質問と回答「おしえてカンゴさん!」

基本的な観察技術について
Q1:フィジカルアセスメントの基本的な流れを教えてください
フィジカルアセスメントを行う際は、まず意識レベル、呼吸状態、循環動態といった生命に直結する項目から観察を始めます。次に全身状態を把握し、系統別の詳細な観察へと進みます。視診、触診、打診、聴診を組み合わせながら、効率的かつ系統的に進めることが重要です。
特に初学者は解剖学的な位置関係を意識しながら、頭部から足部へと順序立てて観察を進めると漏れがなく、効率的です。また、患者さんの羞恥心に配慮し、露出を最小限に抑えるよう心がけましょう。
Q2:バイタルサイン測定で気をつけることは何ですか
バイタルサイン測定では、まず適切な測定環境を整えることから始めます。体温測定では、運動や食事、入浴後は避け、安静時の体温を測定します。血圧測定では、カフの大きさや巻き方、測定姿勢に注意を払い、正確な値を得るよう心がけます。
脈拍測定では、不整脈の有無を確認するため、必要に応じて1分間通しての測定を行います。呼吸数の測定は患者さんに意識させないよう、さりげなく行うことがポイントです。
Q3:患者さんとのコミュニケーションで大切なことは何ですか
患者さんとのコミュニケーションでは、まず信頼関係の構築が重要です。挨拶や自己紹介を丁寧に行い、これから行う処置や観察について分かりやすく説明します。患者さんの話には傾聴の姿勢で臨み、言葉だけでなく表情や態度からも情報を読み取ります。
質問は開放型と閉鎖型を適切に使い分け、患者さんが話しやすい環境を整えることで、より詳細な情報収集が可能となります。また、専門用語は避け、患者さんの理解度に合わせた説明を心がけます。
記録と報告について
Q4:看護記録で気をつけるべきポイントを教えてください
看護記録では、客観的な事実と主観的な情報を明確に区別して記載することが重要です。出来事の経過や観察結果は時系列に沿って記載し、実施したケアとその結果、患者さんの反応まで漏れなく記録します。
特に異常の発見時には、発見時の状況、実施した対応、その後の経過を具体的に記載します。また、医療者間で共通認識を持てるよう、標準化された用語や略語を適切に使用することも大切です。
Q5:医師への報告で緊張してしまいます。どうすればよいですか
医師への報告時の緊張は多くの学生が経験することです。SBAR形式を活用し、状況(Situation)、背景(Background)、評価(Assessment)、提案(Recommendation)の順で整理して報告することで、必要な情報を漏れなく伝えることができます。
報告前にメモを準備し、優先度の高い情報から順に伝えることも効果的です。また、分からないことは正直に伝え、必要に応じて確認することも重要です。
症状観察のポイント
Q6:呼吸音の聴取で迷うことが多いのですが、コツはありますか
呼吸音の聴取では、まず適切な聴診部位の選択が重要です。前胸部では第2肋間、側胸部では第4-5肋間、背部では第7肋間付近を基準に、左右対称に聴診を進めます。聴診時は静かな環境を整え、患者さんには深呼吸をしてもらいます。
正常呼吸音と副雑音の違いを理解し、左右差の有無や呼吸音の性状の変化に注意を払います。不明な音があれば、指導者に確認することも大切です。
Q7:浮腫の観察方法について詳しく教えてください
浮腫の観察では、まず視診で左右差や皮膚の色調、緊満感などを確認します。次に圧痕テストを実施し、圧迫による陥凹の程度と、その戻り時間を評価します。浮腫の部位や範囲、日内変動の有無なども重要な観察ポイントです。
また、浮腫に伴う疼痛や熱感の有無、日常生活への影響度についても確認します。観察結果は数値化や図示により、経時的な変化が分かりやすいよう記録することが大切です。
急変時の対応
Q8:急変時の対応で気をつけることは何ですか
急変時には、まず生命徴候の確認と安全確保を最優先します。意識レベル、呼吸、循環動態を迅速に評価し、必要に応じて応援要請や救急カートの準備を行います。バイタルサインの変化や症状の進行を詳細に観察し、医師への報告を速やかに行うことが重要です。
また、患者さんの不安軽減にも配慮し、落ち着いた態度で対応することを心がけます。記録は時系列で詳細に残し、発見時の状況から対応の経過まで漏れなく記載します。
Q9:輸液ラインのトラブルが心配です。確認のポイントを教えてください
輸液ラインの管理では、定期的な滴下確認と刺入部の観察が基本となります。点滴の滴下速度、残量、薬液の性状を確認し、ライン類の接続部や固定状態も確実にチェックします。刺入部は発赤、腫脹、疼痛などの炎症所見がないか注意深く観察します。
また、輸液ポンプ使用時は設定値と実際の滴下状況が一致しているか確認し、アラーム設定も適切に行います。トラブル発生時の対応手順も事前に確認しておくことが重要です。
実習での学び方
Q10:効果的な実習記録の書き方について教えてください
実習記録では、その日の学びや気づきを具体的に記載することが重要です。患者さんの状態や実施したケア、その結果得られた反応を客観的に記録し、そこから考察したことや新たな課題を明確にします。文献を用いて理論的な裏付けを行うことで、より深い学びにつなげることができます。
また、指導者からのアドバイスや、カンファレンスでの学びも重要な記録内容となります。記録は次の実習に活かせるよう、整理して保管しておきましょう。
Q11:カンファレンスでの発言が苦手です。どうすれば良いですか
カンファレンスでの発言には、事前準備が重要です。その日の実習で経験したことや疑問点を整理し、自分の考えをまとめておきます。発言する際は、具体的な場面や状況を示しながら、自分の意見や気づきを述べることで、より分かりやすい発表となります。
また、他の学生の意見にも耳を傾け、自分の考えと比較することで、新たな気づきや学びを得ることができます。発言に自信がない場合は、まず質問から始めるのも良い方法です。
Q12:受け持ち患者さんとの関係づくりで困っています。アドバイスをください
受け持ち患者さんとの関係づくりは、まず信頼関係の構築から始めます。挨拶や自己紹介を丁寧に行い、学生という立場を明確にしながら、これから一緒に過ごさせていただくことへの理解を得ます。
日々のケアを通じて患者さんの好みや生活習慣を理解し、できる範囲でニーズに応えていくことで、徐々に関係性を深めることができます。また、患者さんの体調や気分に配慮しながら、コミュニケーションの時間を適切に設けることも大切です。
専門的な技術について
Q13:褥瘡の予防と観察について教えてください
褥瘡予防では、定期的な体位変換と適切な除圧が基本となります。褥瘡ハイリスク部位の観察を丁寧に行い、発赤や皮膚の変化を早期に発見することが重要です。スキンケアや栄養状態の管理も予防には欠かせません。
褥瘡発生時は、大きさや深さ、滲出液の性状、周囲の皮膚状態を詳細に観察し、適切なドレッシング材の選択と処置を行います。また、褥瘡の発生要因を分析し、予防策の見直しも必要です。
Q14:清潔ケアの優先順位はどのように決めればよいですか
清潔ケアの優先順位は、患者さんの全身状態と日常生活動作の自立度を考慮して決定します。発熱や発汗が多い場合、皮膚トラブルがある場合は、より頻回な清潔ケアが必要となります。
また、患者さんの希望や生活習慣も考慮に入れ、無理のない範囲でケアを計画します。清潔ケアは単なる身体の清潔保持だけでなく、皮膚の観察や患者さんとのコミュニケーションの機会としても重要です。
Q15:術後患者さんの観察ポイントを教えてください
術後患者さんの観察では、まず意識レベル、呼吸・循環動態の安定性を確認します。創部の状態、ドレーンからの排液量と性状、疼痛の程度も重要な観察項目です。また、麻酔からの回復に伴う悪心・嘔吐の有無や、腸蠕動音の回復状況も注意深く観察します。
術後合併症の予防に向けて、早期離床の進行状況や深部静脈血栓症の予防措置の実施状況も確認が必要です。バイタルサインの変化や症状の出現時は、速やかに報告することが重要です。 Copy
まとめ
患者観察は看護ケアの質を左右する基本的かつ重要なスキルです。正確な観察のためには、客観的な視点の保持、継続的な観察の実施、患者の全体像の把握という3つの基本姿勢が不可欠です。
バイタルサインの測定では、体温、脈拍、血圧、呼吸の正確な測定と評価が求められ、各症状に応じた観察ポイントを押さえることが重要です。
また、SOAPを活用した効果的な記録方法やSBARによる適切な報告・連絡・相談のスキルも、チーム医療において欠かせません。これらの技術は、実践を通じて継続的に向上させていく必要があります。
より詳しい看護技術や実践的なノウハウについては、現役ナースの体験談や最新の医療情報が満載の「はたらく看護師さん」をご覧ください。
日々の看護業務に役立つ情報や、キャリアアップのためのヒントが満載です!会員登録(無料)いただくと、さらに充実した看護師向けコンテンツにアクセスできます。
→ 「はたらく看護師さん」で最新の看護情報をチェック![はたらく看護師さんの最新コラムはこちら]
参考文献
- 医学書院 (2023) 『基礎看護技術』第8版
- 厚生労働省 (2023) 『看護師等養成所の運営に関する指導要領』