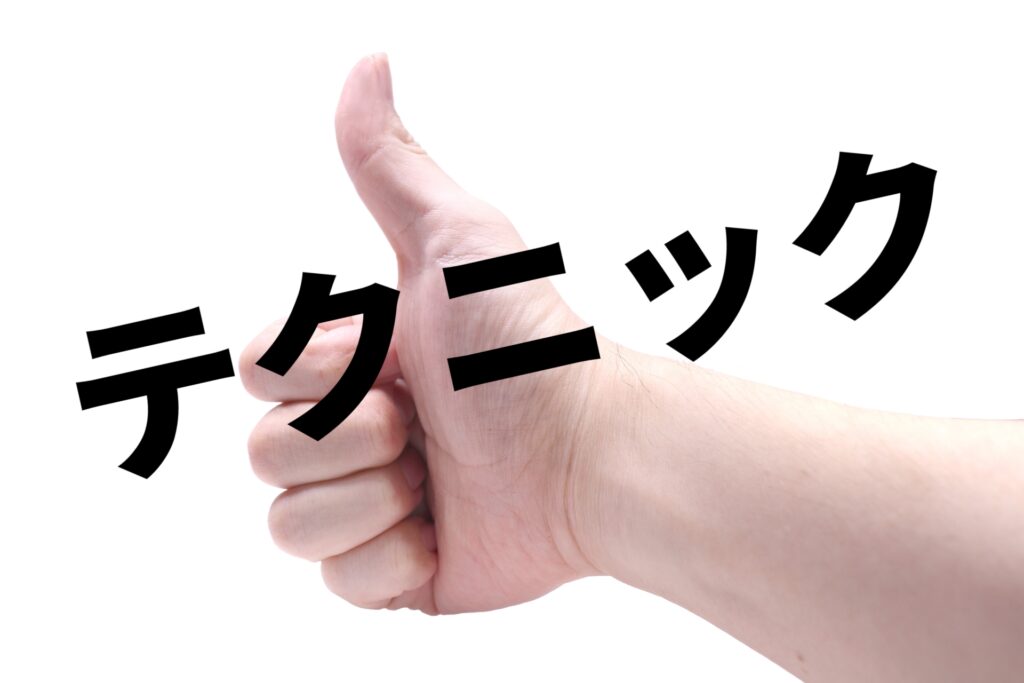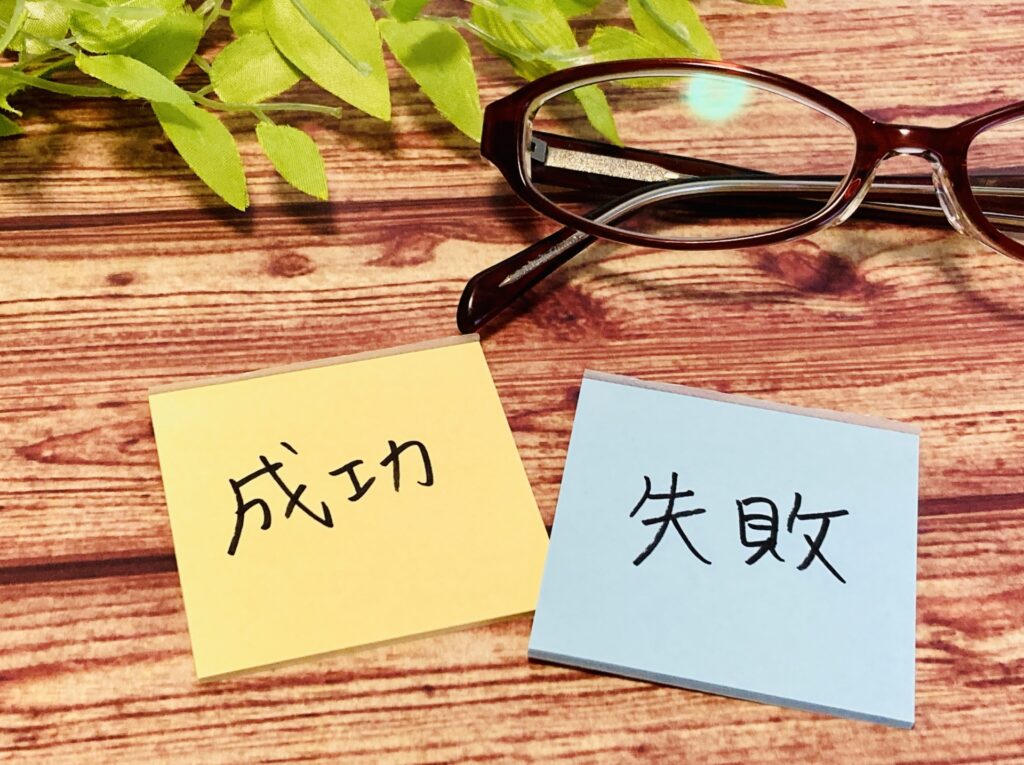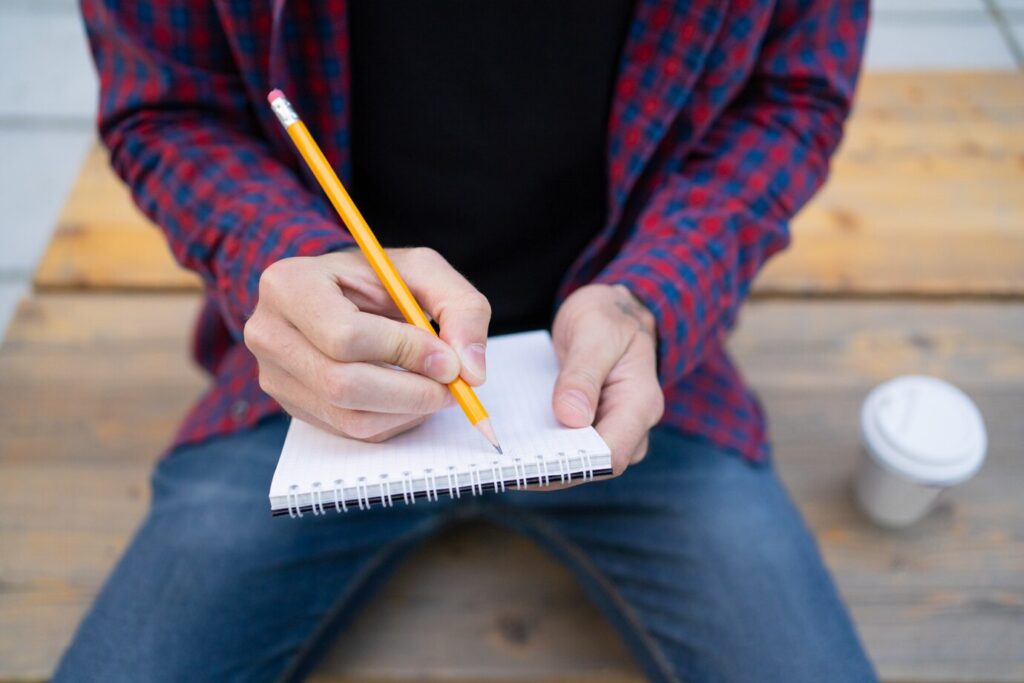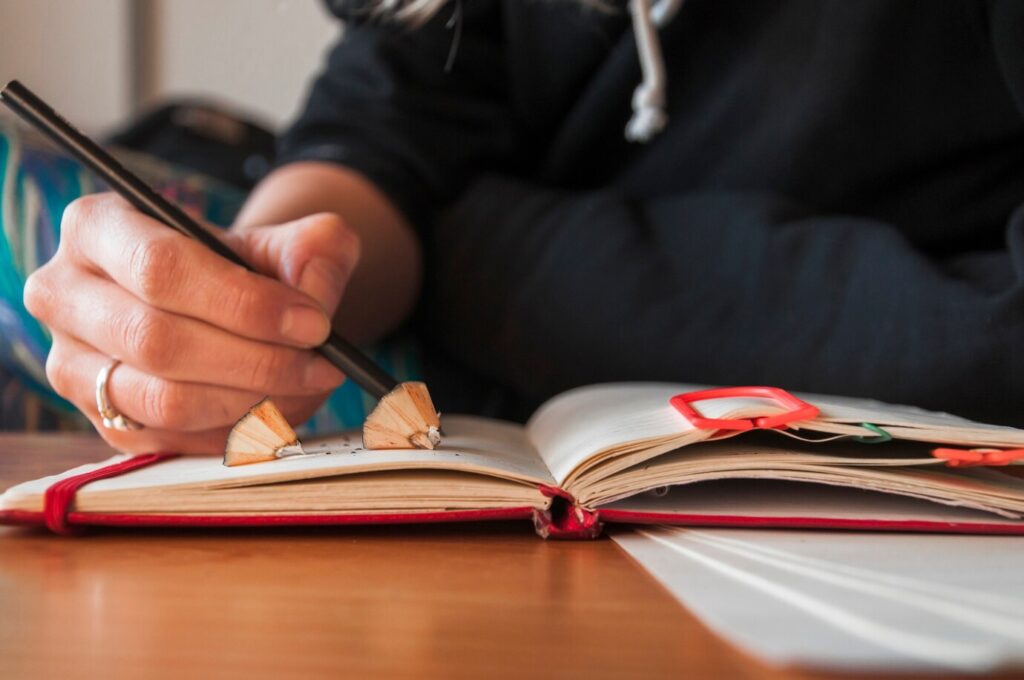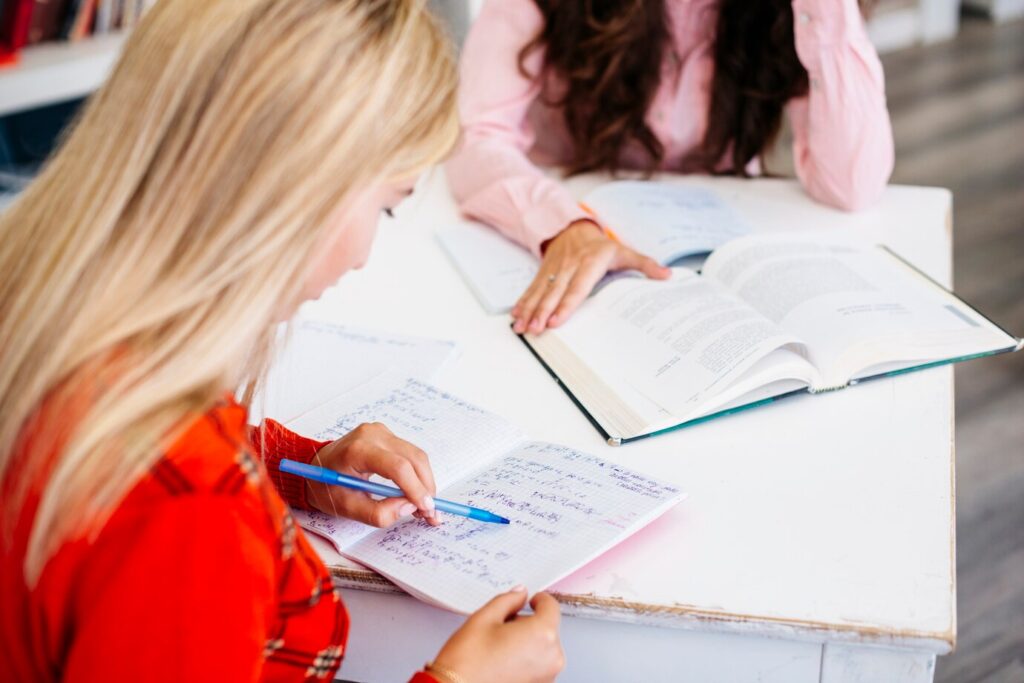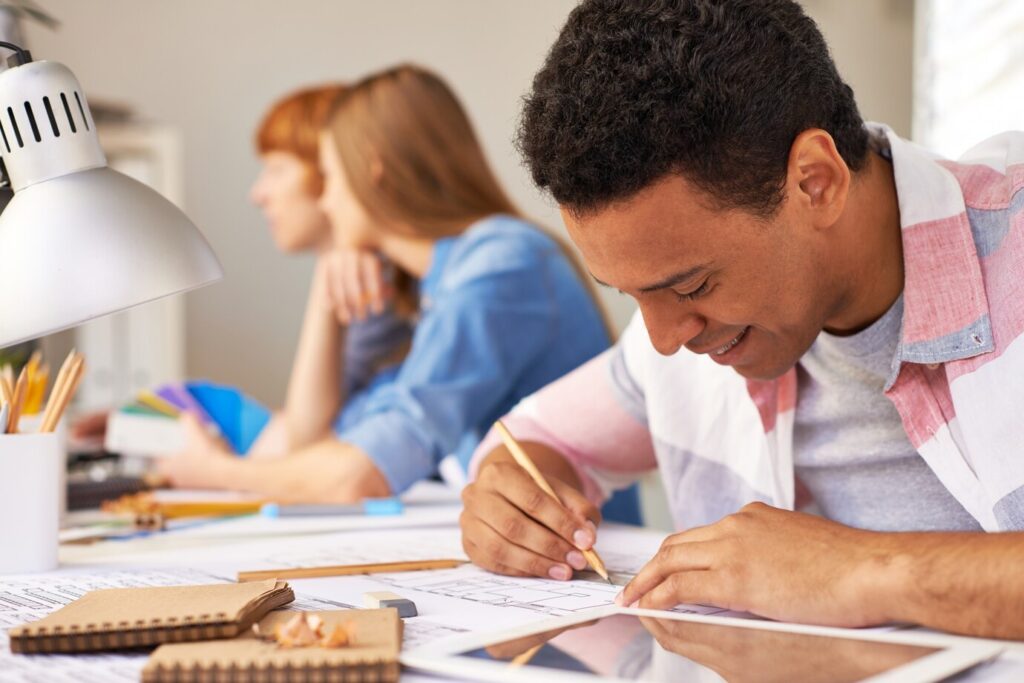神奈川県横浜市の中心部に位置する横浜中央看護専門学校は、創立以来50年以上の歴史を持つ看護師養成校です。充実した実習環境と手厚い就職支援で知られ、これまでに3,000人を超える卒業生を医療の現場へ送り出してきました。
特に注目すべきは98.2%という高い国家試験合格率と99.5%という就職率の高さです。2025年度の入試情報から、カリキュラムの特徴、実習施設、就職実績まで、これから看護師を目指す方に向けて総合的な情報をお届けします。
本校の特徴である実践的な教育システムと充実した学習支援体制により、即戦力として活躍できる看護師を育成しています。横浜駅から徒歩10分という好立地に位置し、最新のシミュレーション設備を備えた実習室や図書館など、充実した学習環境が整っています。
さらに、神奈川県内の主要医療機関との強固な連携により、様々な専門分野での実習機会を提供しています。
この記事でわかること
- 神奈川県内トップクラスの国家試験合格実績と就職支援体制
- 2025年度入試の選考方法と試験対策のポイント
- 充実した実習環境と教育カリキュラムの特徴
- 在校生と卒業生の具体的な学習体験と就職実績
この記事を読んでほしい人
- 神奈川県内で看護師を目指している高校生の方
- 看護師への転職を検討している社会人の方
- 実践的な臨床実習を重視して学校選びをしている方
- 都心部での通学を考えている方
横浜中央看護専門学校の特徴と強み

横浜中央看護専門学校は、充実した教育環境と実践的な学習プログラムを提供することで、即戦力となる看護師の育成に力を入れています。立地の良さと最新の設備、そして経験豊富な教員陣による手厚い指導体制が、本校の大きな特徴となっています。
抜群のアクセスと最新の教育施設
通学の利便性を重視した都心部の立地
横浜駅西口から徒歩10分という好立地に位置し、神奈川県内はもとより、東京都内からの通学も可能です。京浜急行線、相鉄線、JR線、東急東横線など、複数の路線からアクセスできるため、多くの学生が1時間以内での通学圏内から通っています。
駅周辺には大型商業施設も多く、学生生活を快適に過ごせる環境が整っています。
最新のシミュレーション設備
2023年に全面リニューアルされた実習室には、最新のシミュレーション機器を完備しています。
高機能患者シミュレーターを使用した実践的なトレーニングにより、臨床現場で必要とされる技術を効果的に習得することができます。演習室は放課後も利用可能で、自主的な技術練習の場としても活用されています。
充実した教育環境と学習支援体制
ICT教育の積極的な導入
全館に高速Wi-Fiを完備し、タブレット端末を活用した授業を展開しています。電子教材やオンライン学習システムの導入により、効率的な学習環境を実現しています。また、図書館には医療・看護分野の専門書を20,000冊以上所蔵し、電子ジャーナルも利用可能です。
経験豊富な教員による指導
専任教員の80%以上が修士号以上を取得しており、臨床経験も豊富な教員が揃っています。教員一人当たりの学生数も少人数に抑えられており、きめ細かな指導を受けることができます。
さらに、臨床現場で活躍する看護師を特別講師として招き、最新の医療現場の知識や技術を学ぶ機会も設けています。
充実した実習体制
多彩な実習施設との連携
神奈川県内の主要な医療機関と密接に連携し、様々な専門分野での実習機会を提供しています。大学病院での高度医療から地域医療まで、幅広い実習体験を通じて、実践的な看護スキルを身につけることができます。
実習先は横浜市内を中心に20以上の医療機関と提携しており、学生の希望や通学時間も考慮した実習配置を行っています。
手厚い実習サポート体制
実習期間中は専任の実習指導者が常駐し、学生一人一人の学習進度に合わせた指導を行います。
また、実習記録の作成指導や技術面のフォローアップも充実しており、安心して実習に臨むことができます。実習前後のカンファレンスでは、グループディスカッションを通じて学びを深め、実践力の向上を図っています。
2025年度入試情報
横浜中央看護専門学校の2025年度入学試験では、多様な受験機会を提供しています。推薦入試、一般入試、社会人入試の3つの入試区分があり、それぞれの特性に合わせた選考方法を採用しています。
ここでは各入試区分の詳細と、準備に必要な情報を詳しくご説明します。
入試概要と募集人員
募集定員と各入試区分の募集人数
2025年度の募集定員は80名です。推薦入試では25名程度、一般入試では40名程度、社会人入試では15名程度を予定しています。ただし、成績や応募状況により、各区分の募集人数は若干の変動がある可能性があります。
出願資格と要件
高等学校を卒業している方、もしくは2025年3月までに卒業見込みの方が出願できます。また、高等学校卒業程度認定試験合格者も出願資格を有します。社会人入試については、高等学校졸業後の職務経験が3年以上ある方を対象としています。
各入試区分の詳細情報
推薦入試の特徴と出願要件
推薦入試は10月に実施され、高等学校からの学校推薦が必要です。評定平均値3.5以上が推薦の基準となっており、面接試験と小論文試験が課されます。また、専願制となるため、合格した場合は必ず入学することが条件となります。
一般入試の実施時期と試験内容
一般入試は11月、1月、3月の3回実施されます。試験科目は英語、国語、数学の3科目と面接です。各回の試験内容は同一ですが、募集人員は第1回が20名程度、第2回が15名程度、第3回が5名程度となっています。
社会人入試の特別選考
社会人入試は11月と1月の2回実施されます。小論文と面接を中心とした選考となり、職務経験や社会人としての実績も評価の対象となります。また、夜間部での就学を希望する場合は、別途相談に応じています。
試験科目と対策のポイント
各科目の出題傾向
英語は医療現場で必要となる基礎的な英語力を測るため、医療用語や看護に関連する内容が出題されます。国語は読解力と論理的思考力を重視し、医療や看護に関する文章を題材とすることが多くなっています。
数学は基礎的な計算力と論理的思考力を確認する問題が中心です。
面接試験の評価ポイント
面接では、志望動機や看護師としての適性、コミュニケーション能力などを総合的に評価します。過去の受験者からは、自己PRや志望理由を具体的に説明できるよう、事前準備が重要とのアドバイスが寄せられています。
学費・奨学金制度
初年度納入金の詳細
入学金は200,000円、授業料は年間800,000円です。その他、実習費や施設設備費などを含めると、初年度の納入金総額は約1,500,000円となります。納入は分割払いにも対応しており、具体的な支払いスケジュールについては、合格後に詳細な案内があります。
利用可能な奨学金制度
日本学生支援機構の奨学金をはじめ、神奈川県看護師等修学資金、病院奨学金など、複数の奨学金制度を利用することができます。特に、指定の医療機関への就職を条件とする返還免除制度付きの奨学金は、経済的な支援として人気があります。
また、本校独自の授業料減免制度もあり、成績優秀者や経済的支援が必要な学生をサポートしています。
カリキュラムの特徴
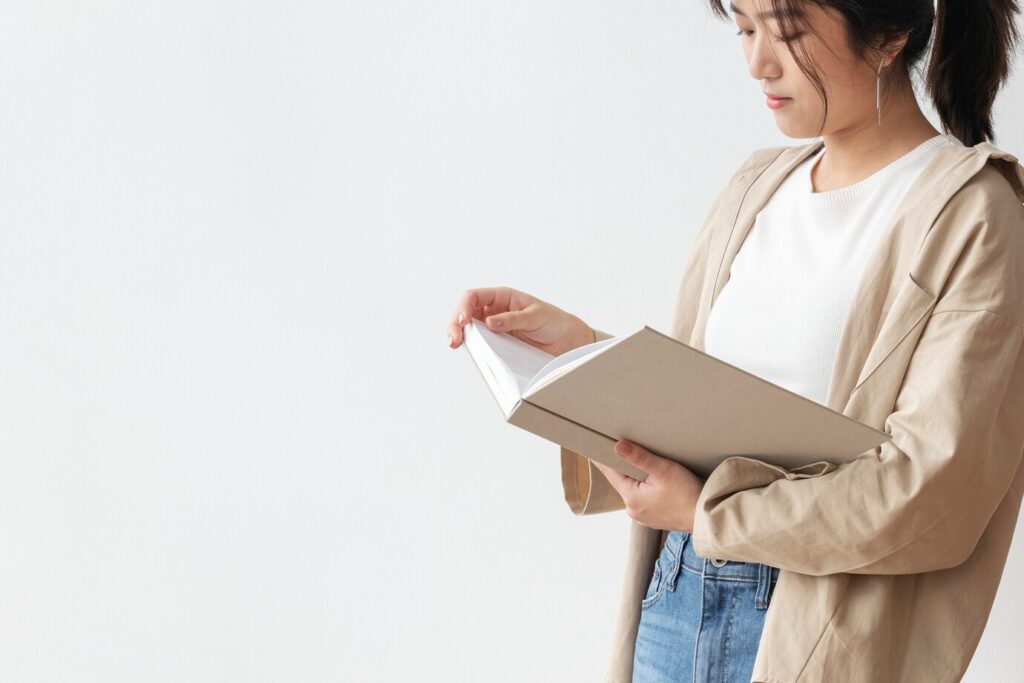
横浜中央看護専門学校のカリキュラムは、看護の基礎から高度な専門知識まで、段階的に学習できるよう設計されています。理論と実践のバランスを重視し、3年間で確実に看護師として必要な知識と技術を身につけることができます。
3年間の段階的学習プログラム
1年次:基礎的な知識と技術の習得
1年次では、解剖生理学や基礎看護学など、看護の土台となる科目を中心に学習します。基礎看護技術の演習も並行して行われ、早期から実践的なスキルの習得を開始します。また、コミュニケーション技術や医療倫理なども重要な学習項目となっています。
2年次:専門知識の充実と実習開始
2年次からは、成人看護学、老年看護学、小児看護学などの専門分野の学習が本格的に始まります。各専門分野での実習も開始され、学内で学んだ知識を臨床現場で実践する機会が増えていきます。
基礎看護学実習での経験を活かしながら、より専門的な看護技術の習得を目指します。
3年次:総合的な実践力の完成
3年次では、これまでの学習内容を統合し、より高度な看護実践能力を養成します。精神看護学実習や在宅看護論実習など、様々な場面での看護を経験することで、総合的な判断力と実践力を身につけます。また、統合実習では、チーム医療の一員としての役割も学びます。
特色ある授業内容
シミュレーション教育の活用
最新のシミュレーターを使用した実践的な演習を重視しています。高機能な患者シミュレーターを用いることで、実際の医療現場に近い環境での学習が可能です。緊急時の対応や基本的な看護技術の習得に効果を発揮しています。
少人数制グループ学習
10名程度の少人数グループによる演習や討議を多く取り入れています。これにより、一人一人が十分な実技練習の機会を得られるとともに、グループでの意見交換を通じて思考力や判断力を養うことができます。
実習スケジュールと内容
基礎看護学実習の展開
1年次後期から開始される基礎看護学実習では、患者とのコミュニケーションや基本的な看護技術の実践を学びます。実習前には十分な事前学習と技術練習の時間が設けられ、安心して実習に臨むことができます。
領域別実習の特徴
2年次からの領域別実習では、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学など、各専門分野での実践的な学習を行います。それぞれの領域で特徴的な看護技術や患者対応を学ぶことができます。
国家試験対策プログラム
計画的な試験対策カリキュラム
2年次後半から段階的に国家試験対策を開始します。定期的な模擬試験の実施や弱点分野の補強など、個々の学習進度に合わせた支援を行います。特に3年次では、週に1回の国試対策講座を開講し、系統的な学習を進めます。
個別指導とサポート体制
成績管理システムを活用し、各学生の学習進度や弱点を把握しています。必要に応じて個別指導を実施し、学習方法の見直しや精神的なサポートも行っています。また、卒業生による試験対策アドバイスの機会も設けられています。
実習環境
横浜中央看護専門学校の実習環境は、神奈川県内でも特に充実していることで知られています。連携医療機関との強固な関係性を基盤に、学生一人一人が実践的な看護技術を習得できる環境を整えています。
実習施設は横浜市内を中心に、様々な専門分野をカバーする医療機関と提携しています。
提携病院の概要と特徴
総合病院での実習体制
横浜市立大学附属病院をはじめとする大規模総合病院との連携により、高度医療から一般診療まで幅広い症例を経験することができます。各病院には専任の実習指導者が配置されており、学生の学習進度に合わせた指導を行っています。
また、最新の医療機器や電子カルテシステムに触れる機会も多く、現代の医療現場に即した実践的な学習が可能です。
専門医療施設での学び
がん専門病院や循環器専門病院など、特定の診療分野に特化した医療施設での実習も行います。専門性の高い看護技術を間近で学ぶことができ、将来のキャリアプランを考える上でも貴重な経験となっています。
実習施設の特色と学習内容
急性期病院での実習
急性期医療を担う病院での実習では、重症度の高い患者さんへの看護や、手術前後の患者ケアなど、より専門的な看護技術を学びます。救急外来や集中治療室での実習も含まれており、緊急時の対応や迅速な判断力を養うことができます。
地域医療連携と在宅看護
地域の中核病院や診療所での実習を通じて、地域医療における看護師の役割を学びます。在宅看護論実習では、訪問看護ステーションに同行し、実際の在宅医療の現場を体験します。地域包括ケアシステムの中での看護の役割について、実践的に学ぶことができます。
実習指導体制と支援
指導者との連携体制
各実習施設には経験豊富な実習指導者が配置されており、学校の教員と密接に連携しながら指導を行います。実習開始前には施設ごとのオリエンテーションが実施され、実習目標や評価基準について明確な説明があります。
また、実習中は毎日カンファレンスを行い、その日の学びを振り返り、課題を明確にしています。
学生へのメンタルサポート
初めての実習や難しい症例に直面した際のストレスに対しても、手厚いサポート体制を整えています。実習グループごとに担当教員が付き、個別の相談にも応じています。また、実習記録の書き方指導や技術面のフォローアップなど、きめ細かな支援を行っています。
実習評価とフィードバック
形成的評価の実施
実習期間中は、日々の実習記録や実技試験、カンファレンスでの発言などを通じて、継続的な評価とフィードバックを行います。これにより、学生は自身の成長過程を確認しながら、課題を明確にすることができます。
総括的評価と今後の課題
実習終了時には、実習目標の達成度を総合的に評価します。実習指導者と教員による評価会議を経て、個別面談でフィードバックを行います。ここでの評価は、次の実習に向けた具体的な課題設定にも活用されます。
就職支援体制
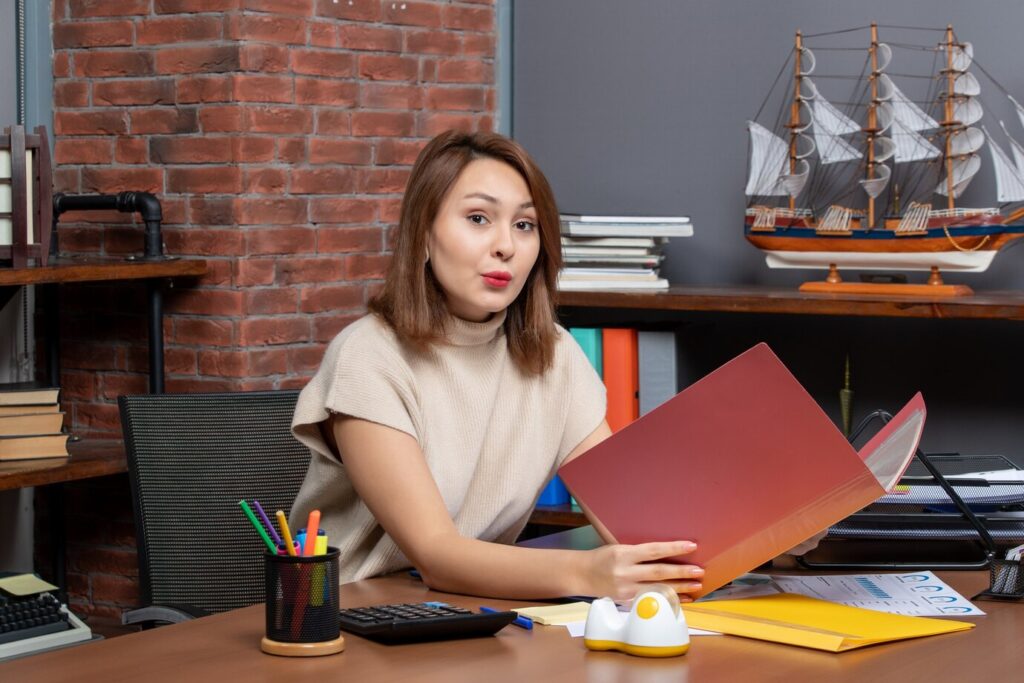
横浜中央看護専門学校では、開学以来培ってきた医療機関とのネットワークを活かし、充実した就職支援を提供しています。就職支援室を中心に、個々の学生の希望や適性に合わせたキャリアサポートを行い、例年99%以上の就職率を維持しています。
キャリアサポートの特徴
専任アドバイザーによる個別支援
経験豊富なキャリアアドバイザーが常駐し、一人一人の希望や適性に合わせた就職相談を行っています。履歴書の書き方から面接対策まで、きめ細かなアドバイスを提供します。また、就職活動の進め方や志望動機の整理など、具体的なガイダンスも実施しています。
多彩な就職支援プログラム
3年次には定期的な就職ガイダンスを開催し、病院の選び方や就職活動のスケジュール管理について詳しく説明します。さらに、実際の採用担当者を招いての模擬面接や、卒業生による就職活動体験談発表会なども実施しています。
就職実績データ
主な就職先と実績
連携医療機関を中心に、神奈川県内外の主要な医療機関への就職実績があります。
大学病院や総合病院、専門病院など、様々な特色を持つ医療機関からの求人があり、学生の希望に応じた就職先選択が可能です。過去5年間の就職率は平均99.5%を維持しており、高い実績を誇っています。
卒業生の活躍状況
卒業生の多くは、神奈川県内の主要医療機関で活躍しています。救急看護や集中治療など、専門性の高い分野でキャリアを積む卒業生も増えており、認定看護師や専門看護師を目指す方も少なくありません。
また、訪問看護ステーションや介護施設など、地域医療の分野でも多くの卒業生が活躍しています。
求人情報の提供体制
豊富な求人情報へのアクセス
就職支援室では、年間800件以上の求人情報を取り扱っています。学内専用の求人情報システムを通じて、最新の求人情報にいつでもアクセスすることができます。また、各医療機関の詳細な情報や、過去の採用実績なども閲覧可能です。
医療機関との密接な連携
実習先となっている医療機関との強い連携により、多くの求人を確保しています。特に実習での評価が高い学生に対しては、実習先からの採用オファーも多く寄せられています。
また、卒業生が活躍している医療機関からの求人も多数あり、先輩からの具体的な情報を得ることもできます。
卒業生ネットワークの活用
卒業生との交流機会
年に2回、卒業生を招いての就職相談会を開催しています。現場で活躍する先輩看護師から、直接アドバイスを受けることができます。また、各医療機関での働き方や職場の雰囲気など、具体的な情報を得られる貴重な機会となっています。
継続的なキャリアサポート
卒業後も、転職相談や進学相談などのキャリアサポートを受けることができます。認定看護師や専門看護師を目指す卒業生への支援も行っており、長期的なキャリア形成をサポートしています。また、同窓会組織を通じた情報交換も活発に行われています。
在校生・卒業生の声

横浜中央看護専門学校での学びや経験は、在校生や卒業生からの生の声を通じてより具体的に理解することができます。ここでは、実際に学校で学ぶ在校生たちの日々の体験や、現場で活躍する卒業生たちの貴重な体験談をお届けします。
現役学生の学習体験
充実した学習環境での日々(Aさんの場合)
1年生のAさんは、基礎看護技術の習得に励んでいます。
「最新のシミュレーション機器を使った実習は、とても実践的で学びが多いです。分からないことがあれば、先生方が丁寧に指導してくださるので、安心して技術を磨くことができています。また、図書館には豊富な専門書が揃っていて、課題学習にも活用しています」と語ってくれました。
グループ学習での学び(Bさんの場合)
2年生のBさんは、グループでの学習体験について次のように話します。
「10人程度の少人数グループで行う演習では、一人一人が実践的な技術を確実に身につけることができます。また、グループでのディスカッションを通じて、様々な視点からの意見を聞くことができ、自分の考えも深まっていくのを感じます」
実習体験レポート
総合病院での実習経験(Cさんの場合)
3年生のCさんは、総合病院での実習について語ってくれました。
「実習では、講義で学んだ知識を実際の臨床現場で活用する機会が多くあります。指導者の先生方は実践的なアドバイスをくださり、患者さんとのコミュニケーションの取り方など、教科書だけでは学べない多くのことを学ばせていただいています」
在宅看護実習での気づき(Dさんの場合)
3年生のDさんは、在宅看護実習での経験を次のように振り返ります。
「訪問看護の実習では、病院とは異なる在宅での看護の特徴を学ぶことができました。患者さんやご家族の生活環境に合わせた看護の重要性を実感し、看護師として大切な視点を得ることができました」
卒業生インタビュー
急性期病院での活躍(Eさん:卒業3年目)
大学病院の救急外来で働くEさんは、学校での学びが現在の仕事にどのように活きているかを教えてくれました。
「学生時代に徹底的に学んだフィジカルアセスメントの知識と技術は、現在の救急看護の現場で大いに役立っています。また、シミュレーション教育で培った緊急時の対応力は、実際の現場でも大きな支えとなっています」
地域医療での実践(Fさん:卒業5年目)
訪問看護ステーションで働くFさんは、学校での経験を次のように振り返ります。
「実習で学んだ在宅看護の基礎が、今の仕事の土台となっています。特に、患者さんやご家族との信頼関係を築くコミュニケーション能力は、学生時代からしっかりと養うことができました。また、卒業後も学校の就職支援室に相談できる環境があり、心強く感じています」
おしえてカンゴさん!Q&A
受験生や入学希望者の皆さまから多く寄せられる質問について、本校の入試アドバイザー「カンゴさん」が詳しく回答します。入試や学校生活、実習、就職に関する疑問点を分かりやすく解説していきます。
入試に関する質問
入試の難易度について
Q.「入試の合格ラインはどのくらいですか?」
A.「一般入試の競争率は例年2〜3倍程度です。特に数学と英語の基礎的な学力が重視されます。面接では志望動機や看護師としての適性を総合的に評価していますので、自分の言葉で思いを伝えられるよう準備することが大切です。」
社会人入試について
Q.「社会人でも入学は可能でしょうか?」
A.「はい、可能です。社会人入試では、職務経験を活かした小論文と面接を中心に選考を行っています。また、働きながら学ぶ方のために、学習支援体制も整えていますので、安心して受験していただけます」と回答しています。
学生生活に関する質問
学習と仕事の両立
Q.「アルバイトと学業の両立は可能ですか?」
A.「カリキュラムはかなり密度が高く、特に実習期間中は学習に専念する必要があります。ただし、週末のみのアルバイトであれば、多くの学生が両立できています。学校として禁止はしていませんが、学業に支障が出ない範囲でお考えください」とアドバイスしています。
通学時間について
Q.「どのくらいの通学時間の人が多いですか?」
A.「学生の約7割が通学時間1時間以内の地域から通っています。横浜駅から徒歩10分という立地を活かし、神奈川県内はもちろん、東京都内からも多くの学生が通学しています」と説明しています。
実習関連の質問
実習先の選択について
Q.「実習先は自分で選べますか?」
A.「基本的に学校が実習施設を指定しますが、通学時間などの条件は考慮します。また、希望する専門分野がある場合は、可能な範囲で対応していますので、担当教員に相談してください」と回答しています。
実習のサポート体制
Q.「実習に不安があるのですが、サポートはありますか?」
A.「各実習施設に専任の実習指導者を配置し、きめ細かな指導を行っています。また、学内では事前の技術練習や個別指導の時間も設けていますので、安心して実習に臨むことができます」と説明しています。
就職関連の質問
就職率について
Q.「就職状況はどうですか?」
A.「直近5年間の就職率は99.5%を維持しています。特に実習先からの採用オファー率が高く、学生の希望に沿った就職先が選べるよう、きめ細かなサポートを行っています」と回答しています。
県外就職について
Q.「県外での就職は可能ですか?」
A.もちろん可能です。全国の医療機関からの求人情報を豊富に取り扱っており、県外就職を希望する学生のサポートも行っています。特に東京都内の医療機関への就職実績も多数あります」と説明しています。
まとめ
横浜中央看護専門学校は、充実した教育環境と実践的なカリキュラム、そして手厚い就職支援体制を備えた看護師養成校として、多くの優秀な看護師を輩出してきました。
最後に本校の特徴と入学を検討される方への重要なポイントをまとめてご説明します。
本校の特徴と強み
教育環境の充実度
横浜駅から徒歩10分という優れた立地条件に加え、最新のシミュレーション設備を完備した実習室や、充実した図書館施設など、学習環境が整っています。また、経験豊富な教員による少人数制の指導体制により、確実な知識と技術の習得が可能です。
実践的な学習機会
神奈川県内の主要医療機関との強固な連携により、充実した実習プログラムを提供しています。大学病院での高度医療から地域医療まで、幅広い実習体験を通じて、実践的な看護スキルを身につけることができます。
次のステップに向けて
入学検討者へのアドバイス
本校への入学をご検討の方は、まずはオープンキャンパスにご参加いただくことをお勧めします。実際の施設見学や在校生との交流を通じて、本校の雰囲気や学習環境を直接体感していただけます。
また、入試説明会では、より詳細な入試情報や学校生活についての説明を聞くことができます。
準備すべきこと
入学後の学習をスムーズに進めるため、高校での基礎学力、特に数学と英語の復習を推奨します。また、医療や看護に関する情報にも日頃から関心を持ち、看護師を目指す意志を明確にしておくことが重要です。
以上が横浜中央看護専門学校の概要となります。本校は、皆様の看護師への夢の実現を全力でサポートいたします。ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽に入試事務局までお問い合わせください。
横浜中央看護専門学校は、充実した教育環境と実践的なカリキュラム、そして手厚い就職支援体制を特徴とする看護師養成校です。98.2%という高い国家試験合格率と99.5%の就職率が示すように、看護師を目指す皆様の夢の実現をしっかりとサポートしています。
オープンキャンパスや入試説明会にご参加いただき、本校の雰囲気や学習環境を直接体感していただければ幸いです。
さらに詳しい看護学校の情報や、看護師のキャリアプランについて知りたい方は、【ナースの森】看護師のためのサイト・キャリア支援サイトをご覧ください。在学中から卒業後まで、看護師としてのキャリアを長期的にサポートする情報が満載です。
【ナースの森】 看護師のためのサイト・キャリア支援サイト