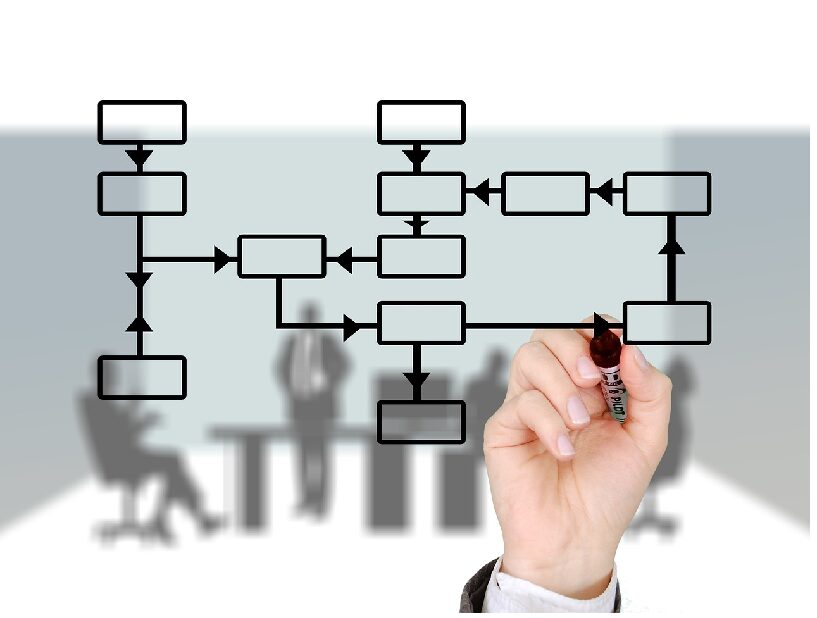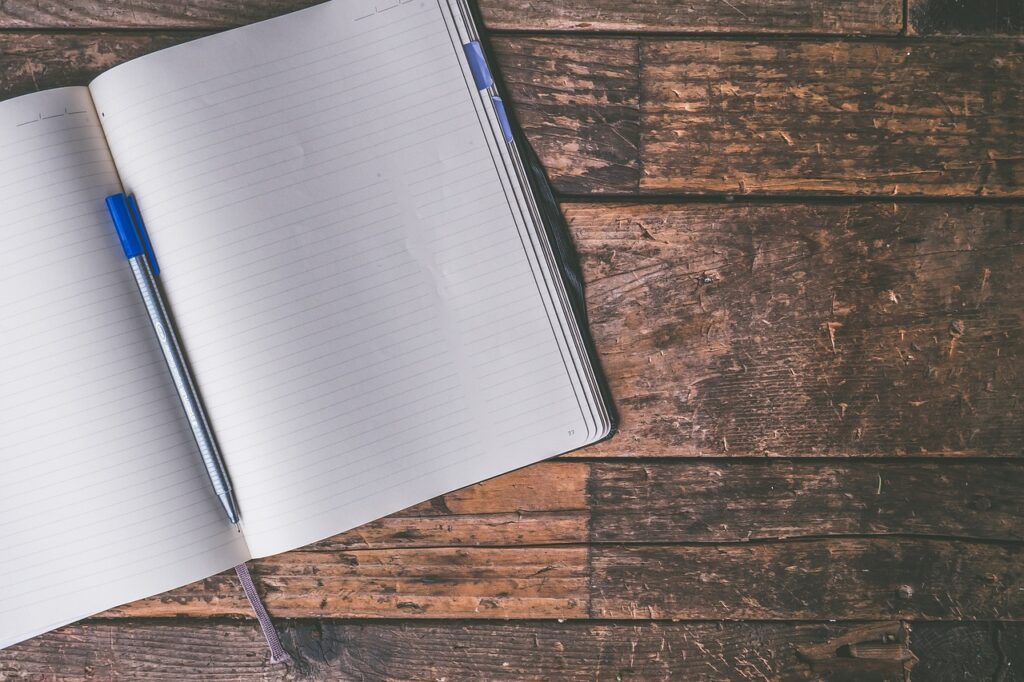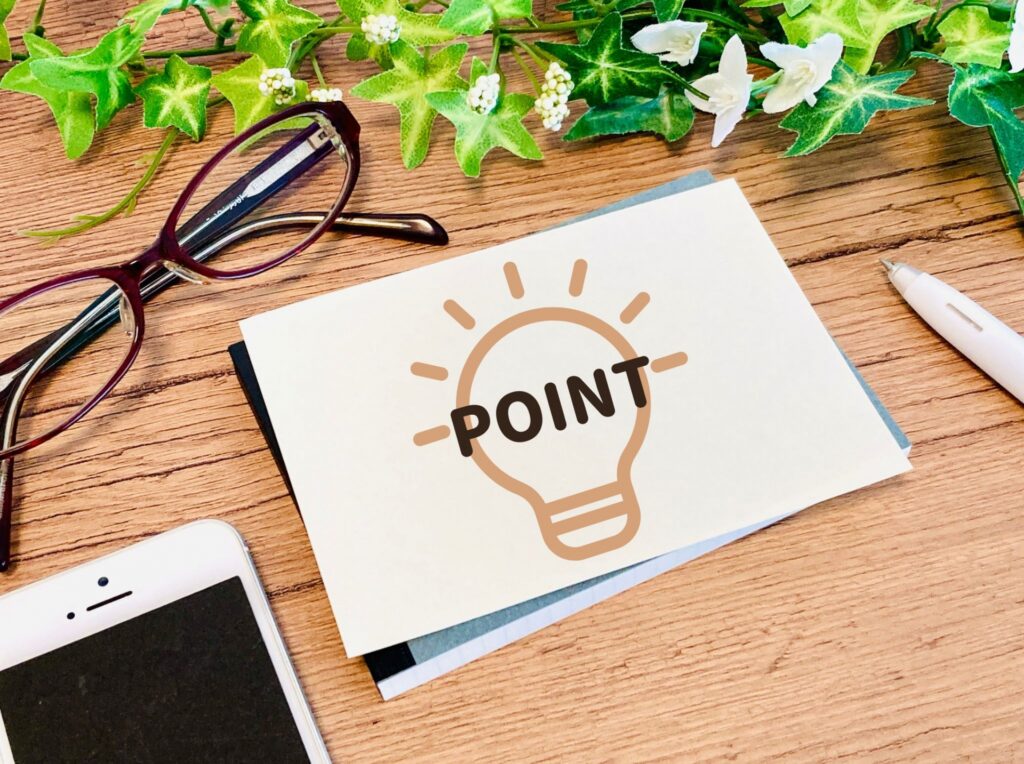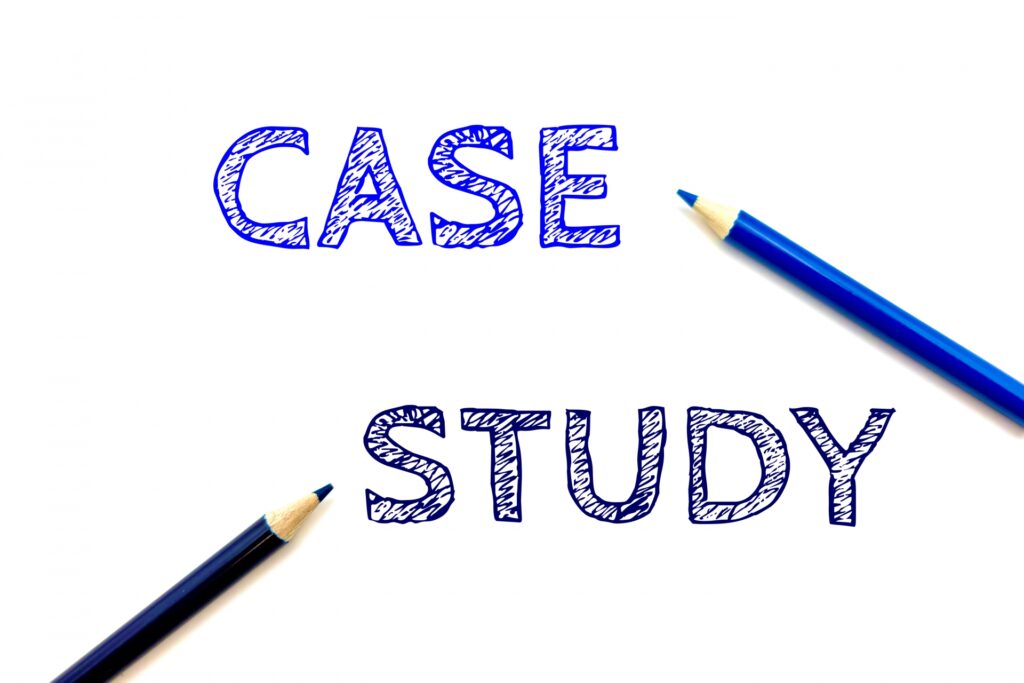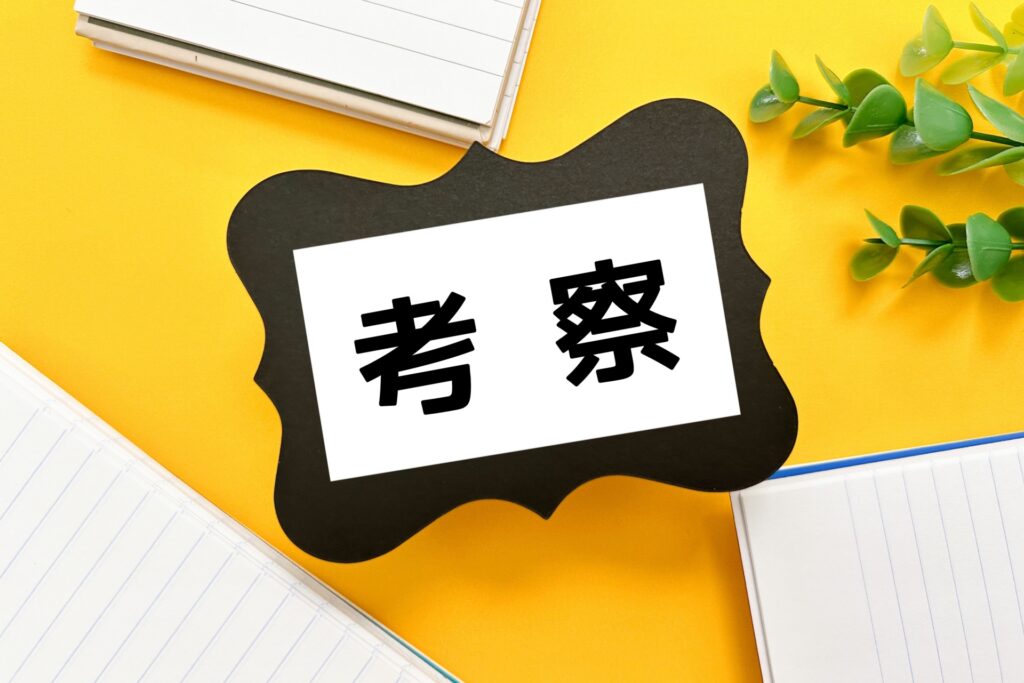在宅療養者の生活を24時間365日支える定期巡回・随時対応型訪問介護看護。このサービスは、医療と介護を一体的に提供できる画期的な仕組みとして注目を集めています。
しかし、人材確保や運営ノウハウ、多職種連携など、実際の運営には様々な課題があるのが現状です。
本記事では、制度の基礎知識から実践的な運営方法、医療・介護の連携手法まで、現場で本当に必要な情報を、具体的な事例を交えて詳しく解説します。運営責任者から現場スタッフまで、すべての医療・介護従事者の方に役立つ内容となっています。
この記事で分かること
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の制度概要と運営要件
- 効果的な医療・介護連携の具体的な手法
- 24時間対応体制の構築方法と適切な人員配置のポイント
- サービス品質向上のための実践的なアプローチ
- 運営上の課題と具体的な解決策
この記事を読んでほしい人
- 定期巡回・随時対応型サービスの立ち上げを検討している医療・介護の専門職の方
- 現在のサービス運営の改善を目指している管理者やリーダーの方
- 医療・介護連携の強化を図りたい現場スタッフの方
- 24時間対応体制の効率化を検討している運営責任者の方
- 制度や運営方法について体系的に学びたい医療・介護従事者の方
制度の基本理解

地域包括ケアシステムの重要な構成要素として位置づけられる定期巡回・随時対応型訪問介護看護。
このセクションでは、制度の基本的な枠組みから、実際の運用に必要な要件まで、体系的に解説します。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要
サービスの定義と目的
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護保険法に基づく地域密着型サービスの一つです。高齢者の在宅生活を24時間365日支える仕組みとして、2012年度に創設されました。
定期的な巡回と随時の対応を組み合わせることで、利用者のニーズに柔軟に対応する新しい形のサービスです。
サービスの特徴と基本的な仕組み
このサービスの最大の特徴は、定期巡回による予防的なケアと、利用者からの要請に応じた随時対応を組み合わせている点です。24時間のオペレーター配置により、利用者やその家族の不安や緊急時の対応が可能となっています。
利用対象者の範囲
要介護1から要介護5までの方が利用できます。特に、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ中重度の要介護者や、看取り期の方への対応に強みを持っています。独居高齢者や高齢者のみの世帯の方にとっても、24時間の見守り機能として重要な役割を果たしています。
法的根拠と算定要件
介護保険法における位置づけ
本サービスは介護保険法第8条第15項に規定される地域密着型サービスとして位置づけられています。市町村による指定を受けることで、その市町村の被保険者にサービスを提供することができます。また、厚生労働省令で定める施設基準や運営基準を満たす必要があります。
基本報酬の構造
基本報酬は月単位の定額制となっています。利用者の要介護度や提供するサービスの類型によって報酬単位が設定されており、事業所の体制や利用者の状態に応じて各種加算を算定することができます。
加算体系の詳細解説
運営基準関連加算
事業所の体制や取り組みに応じて算定できる加算には、総合マネジメント体制強化加算や サービス提供体制強化加算などがあります。これらの加算を算定するためには、それぞれ定められた基準を満たす必要があります。
医療連携関連加算
看護職員の配置や医療機関との連携体制に応じて、特別管理加算や ターミナルケア加算などを算定することができます。医療ニーズの高い利用者への対応を評価する仕組みとなっています。
他のサービスとの違い
訪問介護・訪問看護との比較
従来の訪問介護や訪問看護は、決められた時間に決められたサービスを提供する仕組みでした。一方、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、必要なタイミングで必要なサービスを柔軟に提供できる点が大きな特徴です。
小規模多機能型居宅介護との違い
小規模多機能型居宅介護が「通い」を中心としたサービスであるのに対し、本サービスは「訪問」による支援を基本としています。在宅での生活を継続したい方にとって、より適したサービス形態となっています。
地域包括ケアシステムにおける役割
在宅生活の継続支援
医療と介護を一体的に提供できる特性を活かし、中重度の要介護者の在宅生活を支える中核的なサービスとして機能しています。24時間365日の支援体制により、在宅での看取りまで対応することができます。
地域との連携体制
地域の医療機関やケアマネジャー、他の介護サービス事業所との緊密な連携が不可欠です。地域ケア会議への参加や地域の医療・介護資源との協力関係の構築により、包括的な支援体制を整えています。
今後の展望と課題
サービスの普及に向けた取り組み
人材確保や運営ノウハウの蓄積、採算性の確保など、様々な課題がありますが、行政による支援策の充実や ICTの活用による効率化など、解決に向けた取り組みが進められています。
制度改正の動向
介護報酬改定や制度の見直しにより、より効果的なサービス提供体制の構築が目指されています。地域のニーズに応じた柔軟な運営が可能となるよう、継続的な制度の改善が行われています。
運営体制の構築
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の安定的な運営には、適切な人員配置と効率的な体制づくりが不可欠です。
このセクションでは、人材確保から業務の効率化まで、運営体制構築の具体的な方法をご紹介します。
人員配置と体制づくり
オペレーターの役割と配置基準
オペレーターは24時間のサービス提供体制の要となる職種です。常時1名以上の配置が必要で、看護師、介護福祉士、医療・福祉系の国家資格保持者などの専門職が担当します。利用者からの連絡を受け、適切なサービス提供につなげる重要な役割を担っています。
看護職員の確保と役割
一体型事業所では常勤換算2.5名以上の看護職員配置が必要です。医療的ケアの提供や健康管理、医療機関との連携など、専門性の高い業務を担当します。介護職員との密接な連携により、利用者の状態変化にも迅速に対応できる体制を整えます。
介護職員の配置と育成
定期巡回や随時対応のための介護職員を適切に配置する必要があります。日中・夜間の必要人数を算出し、効率的なシフト体制を構築します。また、計画的な研修実施により、職員のスキルアップを図ることが重要です。
計画作成責任者の選任
介護支援専門員などの資格を持つ計画作成責任者を配置します。利用者のアセスメントやケアプランの作成、サービス担当者会議への参加など、ケアマネジメントの中心的な役割を担います。
施設基準と設備要件
事務所の設置基準
利用者からの連絡を24時間受けられる場所に事務所を設置する必要があります。地域との連携や緊急時の対応を考慮し、アクセスの良い場所を選定することが望ましいです。
通信設備の整備
利用者との連絡体制を確保するため、必要な通信機器を整備します。固定電話やスマートフォン、緊急通報システムなど、状況に応じた適切な機器を選定します。
記録・管理システムの選定
効率的な情報共有と記録管理のため、ICTシステムの導入を検討します。訪問記録やケア記録、シフト管理など、業務全般をカバーするシステムを選定することで、業務の効率化を図ります。
業務マニュアルとシフト管理
標準業務手順書の作成
サービス提供の標準化と質の確保のため、詳細な業務マニュアルを整備します。定期巡回の手順や緊急時対応、感染対策など、必要な項目を網羅的に記載します。
効率的なシフト管理手法
24時間のサービス提供を支えるため、効率的なシフト管理が重要です。職員の希望も考慮しながら、サービス提供に支障が出ないよう適切なシフトを組み立てます。
緊急時対応フローの整備
夜間や緊急時の対応手順を明確にし、全職員が適切に対応できる体制を整えます。医療機関や協力事業所との連携体制も含め、具体的な対応フローを作成します。
記録システムと研修体制
記録方法の標準化
サービス提供記録や個別援助計画など、必要な記録の様式と記入方法を統一します。記録の電子化により、情報共有の効率化と記録業務の負担軽減を図ります。
効果的な研修プログラム
新人研修からステップアップ研修まで、体系的な研修プログラムを整備します。実地研修やケーススタディなど、実践的な内容を取り入れ、職員のスキル向上を支援します。
評価とフィードバック
定期的な業務評価とフィードバックにより、サービスの質の向上を図ります。職員の意見も積極的に取り入れ、より効果的な運営体制の構築を目指します。
コスト管理と経営効率化
収支バランスの管理
人件費や事務費など、運営に必要なコストを適切に管理します。加算の算定状況や利用者数の推移を把握し、安定的な経営基盤の確保に努めます。
業務の効率化
ICTツールの活用やマニュアルの整備により、業務の効率化を進めます。職員の負担軽減と同時に、サービスの質の向上を図ることが重要です。
効果的な連携手法

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の成功には、医療機関や他の介護事業所との緊密な連携が不可欠です。
このセクションでは、効果的な連携体制の構築方法と、実践的なコミュニケーション手法についてご説明します。
医療機関との連携
連携体制の基本構築
かかりつけ医や協力医療機関との良好な関係構築が重要です。定期的な情報共有の機会を設け、利用者の状態変化に迅速に対応できる体制を整えます。特に緊急時の対応手順については、あらかじめ明確な取り決めを行っておくことが大切です。
情報共有の仕組みづくり
医療機関との効果的な情報共有には、統一された様式や連絡ツールの活用が有効です。バイタルサインの変化や服薬状況など、必要な情報を簡潔かつ正確に伝達できる仕組みを整備します。ICTを活用した情報共有システムの導入も検討に値します。
カンファレンスの活用方法
定期的なカンファレンスを通じて、医療職と介護職の視点を共有します。利用者の状態変化や治療方針について協議し、より適切なケアの提供につなげます。オンラインツールを活用することで、参加者の時間的負担を軽減することも可能です。
介護事業所との連携
他サービスとの調整
居宅介護支援事業所やデイサービス、ショートステイなど、他の介護サービスを利用している場合の連携が重要です。サービス担当者会議を通じて情報を共有し、切れ目のないケアの提供を実現します。
サービス提供時の連携
サービス提供時の引き継ぎや申し送りを確実に行います。特に利用者の状態変化や新たなニーズが発生した場合は、速やかに関係者間で情報を共有し、適切な対応を検討します。
記録システムの統一
複数の事業所間での情報共有を円滑にするため、記録様式や用語の統一を図ります。電子記録システムの導入により、リアルタイムでの情報共有と記録の一元管理が可能となります。
連携における課題解決
コミュニケーション上の課題
多職種間でのコミュニケーションにおける課題を特定し、改善策を講じます。専門用語の使用や伝達方法の違いなど、職種間のギャップを埋める工夫が必要です。
情報共有の効率化
情報共有における時間的・物理的な制約を克服するため、ICTツールの効果的な活用を検討します。ただし、セキュリティ面への配慮も忘れてはいけません。
連携マニュアルの整備
連携に関する基本的な手順やルールをマニュアル化します。新人職員でも適切な連携が図れるよう、具体的な事例を交えて解説することが効果的です。
地域との連携強化
地域包括支援センターとの協力
地域包括支援センターとの連携により、地域の高齢者支援ネットワークに参画します。地域ケア会議への参加を通じて、地域の課題解決に貢献することも重要です。
地域資源の活用
民生委員や自治会など、地域の様々な資源との連携を図ります。利用者の生活を地域全体で支える体制づくりを目指します。
地域への情報発信
サービスの内容や実績について、地域に向けて積極的に情報発信を行います。住民向けの説明会や広報活動を通じて、サービスの理解促進を図ります。
利用者受け入れから終了までのプロセス

利用者一人ひとりに適切なサービスを提供するためには、受け入れから終了まで、各段階での丁寧な対応が求められます。
このセクションでは、利用開始時のアセスメントから、サービス提供、終了時の対応まで、一連のプロセスについて解説します。
アセスメントとケアプラン
初回アセスメントの実施
利用開始前に、利用者の心身状態や生活環境、医療ニーズなどを詳細に評価します。家族の介護力や既存のサービス利用状況なども含め、総合的なアセスメントを行います。特に医療ニーズの把握では、主治医や訪問看護との連携が重要となります。
ケアプランの作成プロセス
アセスメントの結果に基づき、具体的なケアプランを作成します。定期巡回と随時対応の組み合わせ方、医療的ケアの必要性、緊急時の対応方法など、きめ細かな計画立案が必要です。利用者や家族の意向を十分に反映させることも大切です。
サービス担当者会議の開催
関係者が一堂に会し、ケアプランの内容を共有します。各職種からの専門的な意見を集約し、より効果的なサービス提供につなげます。特に医療と介護の連携が重要な利用者については、医療機関からの参加も求めます。
モニタリング方法
日常的な状態観察
定期巡回や随時対応の際に、利用者の状態を細かく観察します。バイタルサインの変化や生活状況の変化を記録し、必要に応じてケアプランの見直しにつなげます。特に医療的ケアが必要な方については、より慎重な観察が求められます。
定期的な評価の実施
月1回以上の定期的なモニタリングを実施し、サービスの提供状況や目標の達成度を評価します。利用者や家族からの意見も聴取し、満足度の確認も行います。評価結果は記録に残し、次回のケアプラン見直しに活用します。
多職種による情報共有
介護職と看護職が日々の観察結果を共有し、利用者の状態変化に迅速に対応できる体制を整えます。ICTツールを活用することで、リアルタイムでの情報共有が可能となります。
サービス終了時の対応
終了時の引き継ぎ
入院や施設入所などでサービスを終了する場合は、適切な引き継ぎを行います。それまでの経過や留意点を詳細に記録し、次のサービス提供者に確実に情報を伝達します。特に医療的な情報については、漏れのないよう注意が必要です。
記録の整理と保管
サービス提供に関する記録を適切に整理し、法定期間保管します。個人情報の取り扱いには十分注意を払い、必要に応じて速やかに取り出せるよう管理体制を整えます。
振り返りと改善
サービス終了後は、提供したケアの内容を振り返り、今後の改善点を検討します。得られた知見は、他の利用者へのサービス提供にも活かしていきます。
緊急時対応の実践ガイド

24時間365日のサービス提供において、緊急時の適切な対応は利用者の安全と安心を確保する上で極めて重要です。
このセクションでは、様々な緊急事態への具体的な対応方法と、その準備体制について詳しく解説します。
状況別対応マニュアル
急変時の基本対応
利用者の容態急変時には、まず基本的なバイタルサインの確認を行います。意識レベル、呼吸状態、脈拍、血圧などの情報を収集し、速やかにオペレーターへ報告します。状況に応じて救急要請の判断を行い、必要な応急処置を実施します。
転倒・転落時の対応
転倒や転落が発生した場合は、まず外傷の有無を確認します。頭部打撲の可能性がある場合は、特に慎重な観察が必要です。バイタルサインの確認と同時に、意識レベルの変化にも注意を払います。必要に応じて、速やかに医療機関への受診を検討します。
誤嚥・窒息時の対応
誤嚥や窒息の発生時には、速やかな応急処置が必要です。救急要請を行うとともに、適切な体位の確保や背部叩打法など、状況に応じた対応を実施します。日頃から職員への応急処置訓練を実施し、迅速な対応ができる体制を整えておくことが重要です。
医療機関との連携方法
救急搬送時の対応
救急搬送が必要な場合は、救急隊への正確な情報提供が重要です。既往歴や服薬情報、かかりつけ医の連絡先など、必要な情報をすぐに提供できるよう、情報シートを準備しておきます。
医療機関への情報提供
搬送先の医療機関に対して、普段の状態や変化の経過など、必要な情報を適切に提供します。特に医療的な処置が必要な利用者については、より詳細な情報提供が求められます。日頃から医療機関との良好な関係を築いておくことも大切です。
夜間・休日の連携体制
夜間や休日の緊急時に備え、連携医療機関との24時間対応体制を整備します。連絡方法や対応手順をあらかじめ確認し、スムーズな連携が図れるようにしておきます。
家族への連絡・対応
緊急連絡体制の整備
家族への連絡手順をあらかじめ明確にしておきます。優先順位や連絡方法、不在時の対応なども含め、具体的な手順を定めておくことが重要です。連絡先情報は定期的に更新し、最新の状態を保ちます。
説明と同意の取得
緊急時の対応方針について、あらかじめ家族と話し合い、同意を得ておくことが重要です。特に医療的な処置や救急搬送の判断基準については、事前に確認しておく必要があります。
心理的サポート
緊急事態が発生した際の家族の不安や心配に対して、適切な説明と心理的なサポートを行います。状況を分かりやすく説明し、必要な情報を提供することで、家族の安心感を確保します。
記録・報告の方法
緊急時記録の作成
緊急事態発生時の状況や対応内容を詳細に記録します。時系列での記録を心がけ、実施した処置や判断の根拠なども含めて記載します。この記録は、その後の検証や改善にも活用されます。
報告書の作成と提出
事業所の管理者や関係機関への報告書を作成します。発生状況や対応内容、結果などを明確に記載し、必要に応じて改善策も提案します。報告書は定められた期限内に確実に提出します。
サービス品質の管理
利用者に安心で質の高いケアを提供し続けるためには、計画的な品質管理の仕組みが不可欠です。
このセクションでは、具体的な品質管理の方法とリスク管理について解説します。
品質管理の具体策
定期的な研修実施
職員の知識とスキルの向上を目的とした研修プログラムを計画的に実施します。医療知識、介護技術、コミュニケーション能力など、様々な側面での能力向上を図ります。外部研修への参加機会も積極的に設けることで、新しい知識や技術の習得を促進します。
サービス評価の実施
定期的なサービス評価を通じて、提供しているケアの質を客観的に評価します。利用者満足度調査や第三者評価の活用により、サービスの強みと改善点を明確にします。評価結果は職員間で共有し、具体的な改善活動につなげていきます。
改善計画の策定と実行
評価結果に基づいて具体的な改善計画を策定します。目標設定、実施方法、評価指標などを明確にし、PDCAサイクルに基づいた改善活動を展開します。職員からの改善提案も積極的に取り入れ、現場の視点を活かした改善を進めます。
リスク管理
ヒヤリハット分析
日々の業務の中で発生したヒヤリハット事例を収集・分析します。発生要因を詳細に分析し、再発防止策を検討します。分析結果は職員間で共有し、類似事例の防止に活用します。
感染対策の徹底
標準予防策を基本とした感染対策を徹底します。手指衛生、個人防護具の適切な使用、環境整備など、基本的な対策を確実に実施します。感染症の流行期には、より強化した対策を講じます。
事故防止への取り組み
事故につながる可能性のあるリスク要因を事前に特定し、予防策を講じます。特に転倒・転落や誤薬などの発生頻度の高いリスクについては、重点的な対策を実施します。
質の評価指標
客観的評価基準の設定
サービスの質を定量的に評価するための指標を設定します。利用者の状態改善度、緊急時対応の適切性、サービス提供時間の遵守率など、具体的な評価項目を定めます。
継続的なモニタリング
設定した評価指標に基づき、定期的なモニタリングを実施します。データを経時的に分析することで、サービスの質の変化を把握し、必要な対策を講じます。
運営事例から学ぶ成功のポイント
現場での実践から得られた知見は、サービスの質向上に大きな示唆を与えてくれます。
このセクションでは、実際の運営事例を通じて、成功のための重要なポイントと課題解決の方法をご紹介します。
A事業所の取り組み事例
ICTを活用した効率的な運営
東京都内で展開するA事業所では、ICTツールを効果的に活用し、情報共有の効率化に成功しています。タブレット端末を活用した記録システムの導入により、職員間の情報共有がリアルタイムで可能となりました。
また、AIを活用した業務分析により、効率的な人員配置とルート設定を実現しています。
医療連携の強化
訪問看護ステーションとの密接な連携体制を構築し、医療ニーズの高い利用者への対応力を強化しています。定期的なカンファレンスの実施や、共通のアセスメントツールの活用により、医療と介護の シームレスな連携を実現しています。
B事業所の改善事例
人材育成システムの確立
地方都市で運営するB事業所では、独自の人材育成システムを構築し、サービスの質の向上に成功しています。経験豊富な職員によるOJTプログラムの実施や、定期的なケーススタディ会の開催により、職員のスキルアップを図っています。
地域との連携強化
地域包括支援センターや医療機関との連携を強化し、地域に根ざしたサービス提供を実現しています。地域ケア会議への積極的な参加や、地域住民向けの勉強会の開催により、サービスの認知度向上にも成功しています。
C事業所の経営改善事例
収支バランスの改善
開設当初は経営的な課題を抱えていたC事業所ですが、徹底的な業務分析と改善活動により、収支バランスの改善に成功しています。サービス提供時間の最適化や、加算算定の見直しなどにより、経営の安定化を実現しました。
職員満足度の向上
働きやすい職場環境づくりに注力し、職員の定着率向上に成功しています。柔軟なシフト管理システムの導入や、職員の声を活かした業務改善の実施により、職員満足度の向上を実現しています。
成功事例から学ぶポイント
効果的なICT活用
各事例に共通するのは、ICTツールの効果的な活用です。単なる機器の導入だけでなく、業務フローの見直しと組み合わせることで、真の効率化を実現しています。
人材育成の重要性
継続的な人材育成への投資が、サービスの質の向上と経営の安定化につながっています。体系的な研修プログラムの実施と、職員のモチベーション維持が重要です。
地域との関係構築
地域との良好な関係構築が、サービスの安定的な運営につながっています。地域のニーズを理解し、適切なサービス提供体制を構築することが成功の鍵となっています。
おしえてカンゴさん!よくある質問
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスについて、現場でよく寄せられる疑問や質問にお答えします。これらの質問は、実際の運営において多くの方が直面する課題を反映しています。
人員配置について
Q1: 夜間の人員配置は何名必要ですか?
夜間帯においても、オペレーターを常時1名以上配置する必要があります。また、随時の対応が可能な介護職員を1名以上確保することが求められます。オペレーターは、利用者からの連絡を受け、適切なサービス提供につなげる重要な役割を担います。
Q2: 看護職員の夜間オンコール体制は必須ですか?
一体型事業所では、看護職員の24時間連絡体制の確保が必要です。ただし、必ずしも事業所の看護職員が対応する必要はなく、連携する訪問看護ステーションとの協力体制でも構いません。
加算算定について
Q3: 総合マネジメント体制強化加算の算定要件は?
定期的なカンファレンスの開催や、随時の利用者の状態確認、計画の見直しなどが要件となります。具体的には、月に1回以上のカンファレンス開催と、それに基づく計画の見直しが必要です。
運営方法について
Q4: ICTツールの導入は必須ですか?
ICTツールの導入は必須ではありませんが、効率的な運営のために強く推奨されています。特に記録の管理や職員間の情報共有において、大きな効果を発揮します。
緊急時対応について
Q5: 利用者の容態急変時の対応手順は?
まず、オペレーターへの報告と状況確認を行います。その後、必要に応じて看護職員への連絡や救急要請を行います。あらかじめ対応手順をマニュアル化し、全職員が適切に対応できるようにしておくことが重要です。
医療連携について
Q6: 医療機関との連携方法で工夫すべき点は?
情報共有ツールの統一や、定期的なカンファレンスの開催が効果的です。特に利用者の状態変化時の報告ルールを明確にし、スムーズな連携体制を構築することが重要です。
サービス提供範囲について
Q7: サービス提供地域の設定方法は?
事業所から概ね30分以内で駆けつけられる範囲を目安に設定します。ただし、地域の特性や道路事情なども考慮して、適切な範囲を決定する必要があります。
まとめ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の運営には、適切な体制構築と多職種連携が不可欠です。24時間365日のサービス提供を支えるためには、人材育成、ICT活用、医療連携など、様々な要素に取り組む必要があります。本記事で紹介した実践的なアプローチを参考に、より良いサービス提供を目指していただければ幸いです。
より詳しい運営ノウハウや実践事例、スタッフ教育に活用できる資料は【ナースの森】で公開しています。訪問看護や在宅ケアに関する最新情報も随時更新中です。ぜひ会員登録して、実践で役立つ情報をご活用ください。
▼【ナースの森】看護師のためのサイト・キャリア支援サイト
・実践で使える運営マニュアル ・スタッフ教育用資料 ・事例で学ぶ医療連携 ・経験者インタビュー など、すぐに活用できる情報が満載です。