看護師として働く中で、退職を考えたことはありませんか?実は、厚生労働省の調査によると、看護職員の約60%が退職経験を持っています。しかし、多くの人が「どのように退職すればいいのか」「円満に退職できるだろうか」という不安を抱えています。
本記事では、看護師の退職までの流れを5つのステップで詳しく解説します。さらに、退職時の9つの注意点や、上司からの引き止めへの対処法まで、あなたの退職をスムーズに進めるために必要な情報を網羅しています。
看護師の退職理由トップ10の分析や、退職が通りやすい時期の情報など、実践的なアドバイスも満載です。この記事を読めば、あなたも自信を持って退職のプロセスを進められるはずです。円満退職を実現し、次のキャリアステップへ踏み出すための道筋をご案内します。
看護師の退職の実態

どれくらいの看護師が退職を経験しているかについては、2010年8月から2011年1月の間に厚生労働省が行った看護師及び准看護師、保健師、助産師の免許を持つ39,134名もの看護職員へのアンケート結果を見るとわかります。
これまでに勤務先を退職した回数としては、一度も退職していない0回が最も多く39.4%となっていながらも、1回退職した割合は26.5%、2回退職した割合は16.0%、その後は3回、4回、5回以上と割合は減少していきながらも少なからず退職した人は多数存在しています。
ちなみに無回答の割合は1.7%であるため、退職した経験のない割合39.4%と合算すると41.1%となり、結果的に残りの58.9%は1回以上退職経験があるということになります。
つまり、過半数以上の看護職員に退職経験があるのです。
参考資料:厚生労働省公式ホームページ「看護職員就業状況等実態調査結果p1、p7」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017cjh-att/2r98520000017cnt.pdf)
看護師が退職する理由トップ10

せっかく苦労して看護師になっても、退職せざるを得ない人がたくさんいることがわかりました。
多くの看護師が退職する理由としては、どのようなものが挙げられるのか気になるのではないでしょうか。
同じく厚生労働省のアンケートを元にトップ10をみていきましょう。
1位:出産・育児
2位:結婚
3位:他の施設への興味が強くなった
4位:人間関係がよくない
5位:超過勤務が多い
6位:通勤が困難
7位:休みが取れない
8位:夜勤が大変
9位:責任が重い・医療事故への不安がある
10位:健康問題
1位:出産・育児
看護師の退職理由として最も多いのは出産及び育児であり、その割合は22.1%となっています。
この回答をした人の性別のほとんどは女性であることが予想され、子育てとハードな看護師の仕事を両立することが難しい環境の人や、子育てに集中したいといった人が看護師を退職する選択をしているものと思われます。
2位:結婚
出産・育児に次いで看護師の退職理由として多く挙げられているのは結婚であり、17.7%もの人が結婚を機に退職しています。
アンケートが取られたのは2010年8月から2011年1月であり、2023年現在の社会情勢とは少し異なるとは思いますが、寿退社として専業主婦になるため、あるいはポジティブな結婚にかこつけてあまりよくない環境の職場から退職した人が多いのではないでしょうか。
3位:他の施設への興味が強くなった
他の施設への興味というのも15.1%もの人が挙げている看護師の退職理由です。働いている事業所よりも魅力的な施設を知り、転職したいと思った人が挙げている理由ではないかと推測されます。
もちろん今の職場環境がよくないという人もいるかもしれませんが、他の施設で働きたいという気持ちが垣間見えるのでポジティブな退職理由の1つとも捉えられるでしょう。
4位:人間関係がよくない
看護師の退職理由に限らず、どのような職種でも人間関係がよくないから退職するというのはよくあるケースです。看護師の退職理由としても12.8%の割合を占めることから、多くの看護師が人間関係を重視していることがわかります。
特に責任やプレッシャーの大きい医療現場で神経を尖らせて働く看護師は、人間関係までよくないとなると体力も精神力もすり減ってしまい、仕事を続けることが困難になることも多い傾向にあるのです。
5位:超過勤務が多い
超過勤務が多いという退職理由は10.5%の人が回答しています。クリニックや診療所など小さな規模の事業所ならともかく、入院施設を構えるような大きな病院の場合、夜勤シフトも多いはずです。
その上、人員が不足していたりする環境だと、どうしても残業が増えてしまい、プライベートの時間がほとんどなくなってしまうという悩みが生じ、ライフバランスを考慮して退職というパターンが多いでしょう。
6位:通勤が困難
看護師の退職理由で6番目に多いのは、通勤が困難であるということです。
アンケート内でさらに掘り下げられてはいませんが、おそらく配偶者の転勤や親の介護などで引越しをする必要があり、仕事は続けたいけど物理的に通勤することが難しく、やむを得ず退職するということかと思われます。
7位:休みが取れない
看護師はやりがいのある仕事ではありますが、人員が不足していることなどから、職場で思うように休みを取れない場合があり、退職理由としても10.3%の人が挙げるほどです。
特に看護師の勤務体制としては、シフト制かつ4週8休制が敷かれていることが多いため、かろうじて4週間で8休み取れたとしても、GWをはじめ、夏期・冬期などの長期休暇は取得しにくい傾向にあります。
「趣味や家族との時間を大切にしたい」「旅行が好き」「ライブに行きたい」「実家に定期的に帰省したい」などといった希望がある場合、ライフスタイルと合わずどうしても退職せざるを得ないこともあるでしょう。
8位:夜勤が大変
入院施設があるなど、夜勤がシフトに組み込まれている事業所で働いている看護師の場合、夜勤が大変なことが退職理由になることがあります。
実際にアンケートでは、9.7%もの人が夜勤が大変と回答していて、夜勤は生活リズムが取りにくかったり、ホルモンバランスが崩れたり、自律神経が乱れたりと体に良いことが少なく、年を重ねれば重ねるほど負担になることが多い傾向にあります。
給与が割り増しになることを加味しても、体力の限界を感じた時に退職せざるを得ないのかもしれません。
9位:責任が重い・医療事故への不安がある
看護師は患者の生死に関わる重要な仕事を担うため、出世していくにつれ、一般企業とは異なる責任の重さを痛感することになります。
アンケートでは実に9.6%もの人が退職理由として掲げており、看護師という仕事に就く前から理解していても、背負いきれない責任や医療事故の不安を感じてしまい、退職に至ってしまうことがあるのです。
10位:健康問題
患者の健康をケアする看護師の立場でも、自分自身が健康を損ない、働き続けることが難しいと感じてしまう場合にも退職という道を選択することがあります。
健康問題は8.6%の人が退職理由として挙げており、身体的な病気や怪我はもちろん、ストレスによってメンタルを病んでしまうなどして退職しているはずです。
参考資料:厚生労働省公式ホームページ「看護職員就業状況等実態調査結果p28」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017cjh-att/2r98520000017cnt.pdf)
看護師を退職するまでの流れ
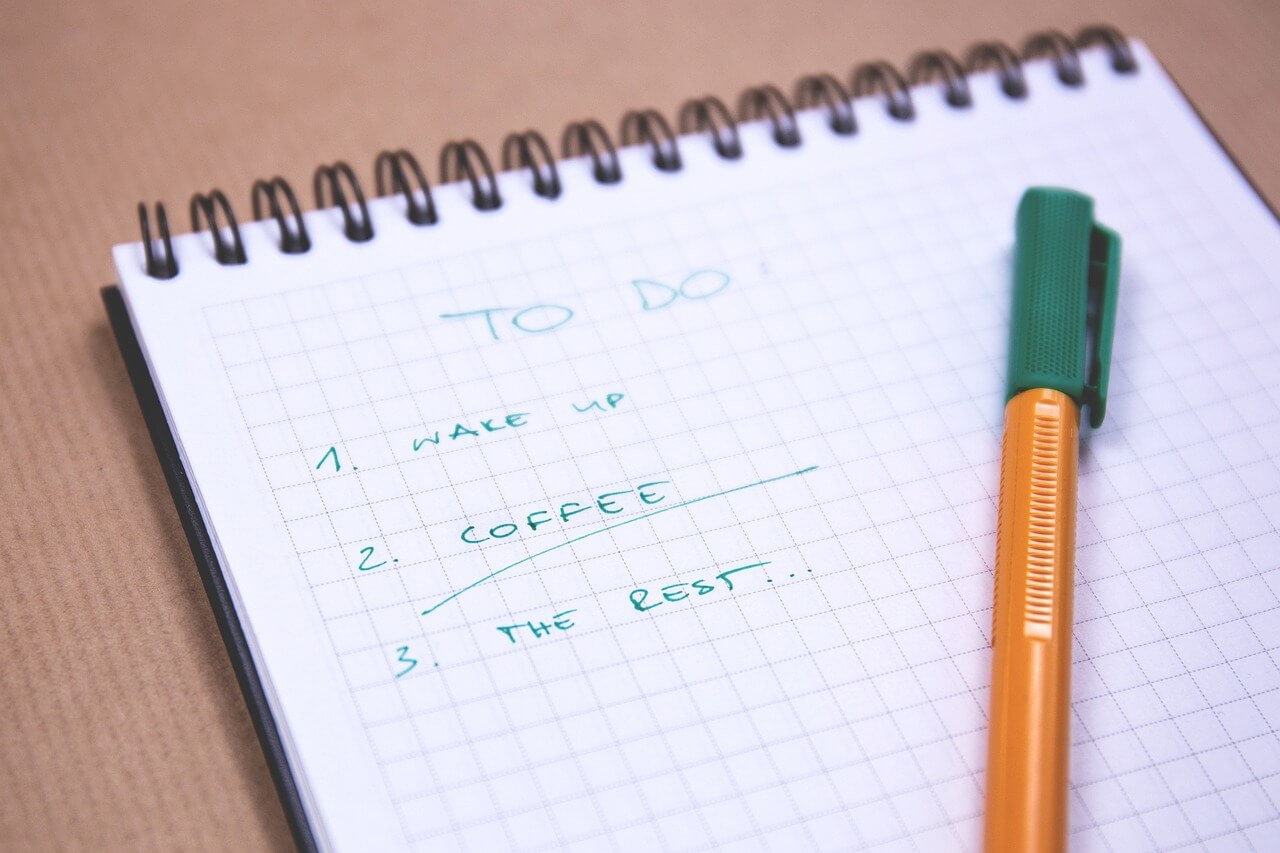
世の中の看護師の退職事情及び退職理由を理解したところで、ここでは肝心の看護師を退職するまでの流れについて解説していきます。
1.就業規則や奨学金の規約を確認
2.就業規則に則り退職希望日と上司に伝える日を決める
3.退職希望であることを直属の上司に伝える
4.上司などと相談しながら退職日を決定
5.退職届を提出
1.就業規則や奨学金の規約を確認
様々な理由で退職する意思をかためたら、何よりも先に勤務先の就業規則を確認してください。
雇用期間の定めない従業員、つまり無期雇用の看護師の場合、労働基準法によれば退職の14日前に口頭や文書で退職の意思を申し出れば退職できるとされていますが、就業規則で退職に関わるルールが定められている場合があるからです。
就業規則によっては「1ヶ月前まで」「2ヶ月前まで」などと明記されていることもあるので、隅々までチェックしましょう。
また、看護学生時代に病院(看護)奨学金を利用していたという場合には、奨学金制度の規約にも目を通し、退職後の奨学金の返済についての見通しも立てておかなければなりません。
2.就業規則に則り退職希望日と上司に伝える日を決める
就業規則を確認した後は、就業規則に反しないように退職希望日と、退職の意思や希望日を直属の上司に伝える日を決めましょう。
ただし、就業規則で退職の申し出の時期に特に定めがなかったとしても、2週間前にいきなり退職の意思を伝えることは推奨されません。自分が退職した後のシフトや、退職するまでの引き継ぎなど様々な部分に配慮した上で、どんなに遅くとも1ヶ月前には直属の上司に申し出るようにしましょう。
もちろん早めに申し出る分には問題ありません。3ヶ月前などに申告できれば、勤務先も人員補充や配置転換などをどうするかなどを考える時間が多く取れるため、より円満退職となるはずです。
3.退職希望であることを直属の上司に伝える
次に退職の意思があること、そして退職希望はいつなのかについて、直属の上司に口頭で伝えます。この際、間違っても直属の上司を飛び越えて伝えたり、いきなり退職届を出したりすることのないようにしてください。
また、上司に伝える際にも忙しい時間帯を避けるなどして、業務に支障のないように配慮することが大切です。
4.上司などと相談しながら退職日を決定
直属の上司に退職の意思を伝えてから数日後、一般的に看護部長や事務長などと退職についての面談の場が設けられることが多い傾向にあります。この面談では引き止めに合うかもしれませんが、退職の意思がかたいことを一貫して伝えます。
退職希望日や残っている有給休暇の消化、奨学金などについて話し合い、自分の希望を主張しつつも勤務先の状況に配慮しながら協力的な姿勢であることもアピールしておいてください。
5.退職届を提出
退職届については、事業所によって指定のフォーマットがあるかどうかを確認した上で作成し、直属の上司に直接手渡しで提出してください。
もしフォーマットがないという場合には、郵便番号枠のない白無地の二重封筒や便箋などを自分で用意し、退職届を作成しましょう。
ちなみに退職届は手書きでなくともパソコンで作成しても問題ないことを覚えておいてください。
また、直属の上司に退職届を提出するからといって、宛先が直属の上司ではない点にも注意しましょう。
看護師が退職する際の注意点

看護師の退職までの流れを一通り見てきました。しかし、実際には様々な点に注意する必要があり、注意を怠ると円満退職が実現できない可能性があります。
ここでは看護師が退職する際の9つの注意点をピックアップしましたので、無用なトラブルを避けるためにも、それぞれしっかりと目を通しておきましょう。
- 退職希望日は職場の状況に配慮する
- 最初に退職の意思を伝える相手を間違えない
- 忙しい時間帯に退職の話し合いをしない
- 退職に関わる決め事は書面に残す
- ネガティブな退職理由を伝えないようにする
- 退職の意思は相談ではなく報告として伝える
- 後任者へもれなく引き継ぐ
- 備品は全て返却する
- 退職に関わる書類の受け取り方法を確認する
退職希望日は職場の状況に配慮する
退職希望日については、多少前後しても問題ないように余裕を持って設定しておくと安心です。
看護部長や事務長などとの面談時には、こちらの退職希望日を伝えても人員体制などによって希望日をずらせないかといった打診を受ける場合があるからです。
その際、頑なにずらせないとなると勤務先としても困ってしまうため、この日でも大丈夫という日の候補を事前に持っておくと、勤務先の状況も考慮してくれていると思ってもらえます。
最初に退職の意思を伝える相手を間違えない
看護師だけに当てはまることではありませんが、退職の意思を伝える相手は原則直属の上司です。直属の上司を飛び越えて看護部長や事務長などにいきなり伝えてしまうと、直属の上司の面目が丸潰れになるだけでなく、退職までの期間引き継ぎなどの業務に支障を与えかねないからです。
直属の上司からひどいハラスメントを受けているなど、どうしても直属の上司に伝えることができないといった特別な理由がない限り、円満退職を実現するためにも報告順序は守りましょう。
忙しい時間帯に退職の話し合いをしない
自分の中でもう退職するからと心が決まっているからといって、今の仕事をおざなりにしてはいけません。退職の意思を伝える際など、自分や相手の業務の忙しい時間帯を避けるように配慮しましょう。
落ち着いて話すことのできる時間を見計らって声をかけ、忙しい中私事で時間を取ってもらったことに感謝をしつつ話し合いしてください。
退職に関わる決め事は書面に残す
退職するまでは、退職に関する決め事(退職日や最終出社日、有休消化日数)などは書面に残しておくことが大切です。言った言わないと勤務先とトラブルが発生しないように、証拠を残しておき、何か食い違いが起きそうな時には、書面を見せながら話し合うようにしてください。
ネガティブな退職理由を伝えないようにする
退職理由の中には、「人間関係が悪い」などといったネガティブな理由も含まれるかもしれません。しかし、直属の上司はもちろんのこと、仲の良い同僚などに退職する理由を聞かれた際にはこのようなネガティブな理由は言わないようにした方が懸命です。
ネガティブな退職理由を正直に伝えてしまうと、退職までの残り僅かな時間の中でも上司や同僚との関係がギクシャクするなどしてストレスがたまりやすくなってしまうためです。
医療業界のネットワークは非常に強固なので、最悪の場合には、次の転職先にもネガティブな情報が伝わってしまうかもしれませんので、特に注意することをおすすめします。
退職の意思は相談ではなく報告として伝える
退職の意思を直属の上司や看護部長、事務長に伝えると、引き止めに合う場合があります。特に曖昧な言い回しで相談のような切り出し方で伝えると、まだ引き止めれば残ってくれるのではないかと勤務先も思ってしまいがちです。
そのため、退職の意思を伝える際には「絶対に退職する」という強い意思を持って、退職することが前提での報告ベースで伝えるようにしましょう。
後任者へもれなく引き継ぐ
当たり前のことですが、最終出勤日まで、あるいは退職日までは自分の業務を引き継いでくれる後任者に必ず引き継ぐ必要があります。
ただし、日々の忙しい業務の中では、なかなか引き継ぎが思うように進まないことがあるかもしれません。そのため、自分の連絡先を伝えておいてやむを得ない時には連絡をもらって答えたり、用紙に引き継ぎ内容を細かく記載するなどしたりすることが大切です。
備品は全て返却する
最終出勤日には基本的に勤務先から貸与されていた備品は全て返却することになります。
- 健康保険証
- 社員証などの身分証明書
- ネームバッジ
- 名刺
- 通勤定期券
- 制服
- ロッカーの鍵
もちろん上記以外にも経費で購入した文房具など、色々な備品の返却が必要になります。返却し忘れると、最終出勤日以降また勤務先に足を運ぶ必要があったり、郵送で送ったりする手間が出てくるので、漏れないようにしましょう。
退職に関わる書類の受け取り方法を確認する
退職すると勤務先から重要な各種書類を受け取ることになります。最終出勤日に手渡しで受け取れるのか、それとも自宅に郵送されるのかなど、事前に受け取り方法を確認しておくのも忘れないでください。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 年金手帳
これらの重要書類は転職先での提出が必要となるため、いつ確実に受け取れるのかを確認しておかないと、後で困る場合があります。
退職希望が通りやすい傾向にある時期

スムーズに退職したければ、ある程度退職希望が通りやすい傾向にある時期を選ぶのもポイントです。
例えば、年度末をはじめ、ボーナス支給後や勤務先の大きな役割がひと段落するタイミングなどといった時期は、そもそも看護師の退職が多い時期であるため勤務先も見越して人員計画を立てている場合が多いためです。
ただし、こうしたキリの良いタイミングで退職しようと考えるのは自分だけではなく、複数人の退職希望者が同時に集中することがあるので、なるべく早く申し出ておくと安心でしょう。
看護師が退職の意思を伝えて直属の上司から引き止めにあった際の対処法

最後に、看護師が退職の意思を伝えて直属の上司から引き止めにあった際の対処法を3つご紹介します。
- 一旦時間をおく
- 直属の上司よりも上長に相談
- 退職届を内容証明郵便で送付
一旦時間をおく
勤務先の人員体制によっては、直属の上司から強く引き止めにあい、退職についての話し合いが進まなくなってしまうことがあります。人手不足だったり、直属の上司が自分の評価を気にしていたりと理由は様々です。
その際には、一旦引き止めについて考えてみるとしてから、後日やはり色々考えてみたが退職の意思は変わらないという切り出し方にしてみましょう。
直属の上司よりも上長に相談
一旦時間をおいてから直属の上司に話しても埒が開かないという場合には、直属の上司のさらに上の立場の上長に相談してみるという手段もあります。
もちろんこれは奥の手であり、直属の上司との関係性が悪くなってしまうかもしれませんが、どうしても退職しないといけない理由があるというならなりふり構っていられないので、看護部長や事務長に退職する意思があること、直属の上司が聞き入れてくれないことを報告しましょう。
退職届を内容証明郵便で送付
直属の上司だけでなく、看護部長や事務長などに退職の意思を伝えても引き止めにあい、話が進まないという場合、こちらに非がないのであれば、最終手段として退職届を内容証明郵便で送付するという手段を取ることもできます。
勤務先は退職届を受理せざるを得ないため、退職することはできますが、この方法でも円満退職は実現しないので覚悟が必要です。
まとめ
看護師の退職ガイド・退職までの流れと注意点について、この記事では看護師が退職する際の注意点とポイントをはじめ、引き止めにあった際の対処法について解説してきました。
医療現場という人の命を預かる過酷な条件下で看護師が退職する際には、退職の意思を伝える時期はもちろん、退職時期なども配慮する必要があります。
円満退職を実現するためにも、要点を抑えて確実に退職までの道筋に沿って進んでいってください。





































