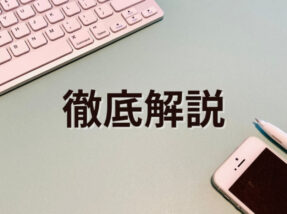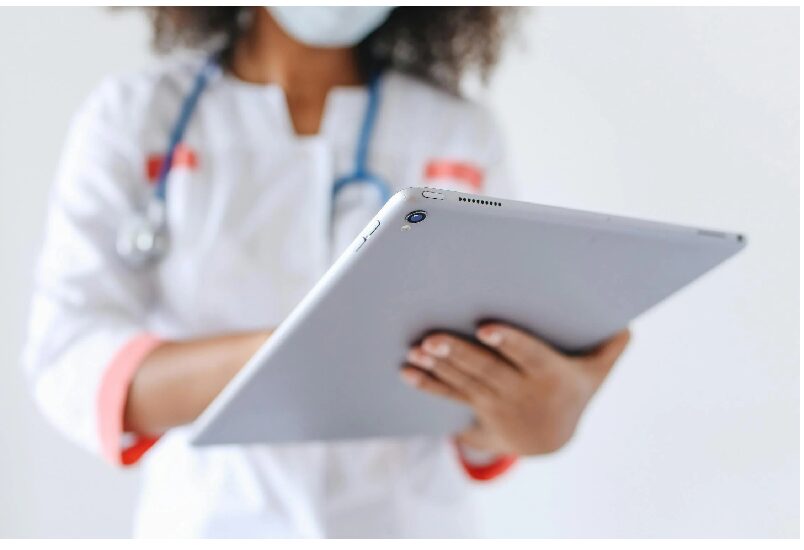医療機関における採用活動は大きな転換期を迎えています。
特に看護師採用においては、従来の紙媒体や静的なウェブコンテンツから、よりダイナミックで魅力的な採用動画の活用へとシフトしています。
2025年に注目される採用動画の最新トレンドについて、実践的な視点から解説していきます。
この記事でわかること
- 2025年の看護師採用動画における最新トレンドと効果的な活用方法
- AIやメタバースなど先端技術を活用した制作手法とそのポイント
- 大規模病院から地域密着型まで、実際の成功事例と具体的な施策内容
- 採用動画の費用対効果と具体的な予算計画の立て方
- 医療現場特有の撮影における法的配慮とコンプライアンス対策
この記事を読んでほしい人
- 医療機関の採用担当者や人事部門の方々
- 看護師採用に携わる方
- 医療機関の採用担当者や看護部の管理職の方々
- 採用戦略の立案に関わる経営層の皆様
- 看護師の採用活動に直接携わり、採用動画の制作や活用を検討されている方
- 医療機関の広報担当者
- 採用プロセスの改善を検討している人事部門の方々
2025年の看護師採用動画における最新トレンド

AI技術の活用による個別化対応
パーソナライズされたコンテンツ配信
採用動画視聴者の興味や経験に基づき、AIが最適なコンテンツを選択して提示する仕組みが主流となっています。
たとえば、救急看護に興味がある応募者には救急病棟の詳細な業務紹介が、ワークライフバランスを重視する応募者には福利厚生や勤務体制に関する情報が優先的に表示されます。これにより、応募者一人ひとりに最適化された情報提供が可能となっています。
リアルタイムの質問対応システム
AIチャットボットを活用することで、動画視聴中に生じた疑問にリアルタイムで回答することが可能になっています。
視聴者の質問に対して、事前に用意された回答データベースから最適な情報を提供し、必要に応じて人事担当者への連絡もスムーズに行えるようになっています。
インタラクティブ要素の強化
360度バーチャル病院見学
従来の一方向的な動画配信から、視聴者が自由に視点を変えながら病院内を探索できるインタラクティブな体験へと進化しています。手術室や病棟、スタッフステーションなど、実際の勤務環境を臨場感たっぷりに体験することができます。
リアルタイム質疑応答セッション
定期的にライブ配信を実施し、現役看護師や採用担当者との直接対話の機会を設けることで、より深い理解と信頼関係の構築を促進しています。参加者からの質問にリアルタイムで回答することで、双方向のコミュニケーションを実現しています。
ソーシャルメディア連携
マルチプラットフォーム展開
TikTokやInstagramなど、各SNSプラットフォームの特性を活かした動画コンテンツの制作が標準となっています。特に若手看護師の日常や成長ストーリーを短編動画として発信することで、より身近な視点から職場の雰囲気を伝えることができます。
ユーザー生成コンテンツの活用
現役の看護師スタッフが自身の経験や働きがいについて語る動画を自主制作し、公式アカウントで共有する取り組みが増加しています。等身大の視点から語られる職場環境や業務内容は、応募検討者にとって貴重な情報源となっています。
データ分析と効果測定
視聴行動の詳細分析
動画のどの部分で視聴者の興味が高まり、どの部分で離脱が起きやすいのかを詳細に分析することで、より効果的なコンテンツ制作が可能になっています。これらのデータは次回の動画制作に活かされ、継続的な改善サイクルを生み出しています。
応募行動との相関分析
動画視聴から実際の応募までの動線を追跡し、どのようなコンテンツが応募確度の向上に貢献しているのかを分析することで、採用活動全体の最適化が図られています。
この最新トレンドは、単なる技術の進化だけでなく、応募者とのより深い関係構築を目指す医療機関の姿勢を反映したものとなっています。
制作手法とポイント

看護師採用動画の制作には、医療現場特有の配慮事項と専門的な制作技術が求められます。このセクションでは、効果的な採用動画を制作するための具体的な手法とポイントについて、実践的な視点から解説していきます。
撮影テクニック
医療現場における撮影基礎
医療現場での撮影では、患者様のプライバシーへの配慮と医療従事者の業務妨害を避けることが最優先事項となります。
撮影機材はコンパクトなものを選択し、必要最小限の人数で素早く撮影を行うことが重要です。また、院内感染対策の観点から、機材の消毒や撮影スタッフの感染対策も徹底する必要があります。
自然な表情の引き出し方
看護師の皆さまは普段カメラの前で演技をする機会が少ないため、緊張しがちです。そのため、本番前の十分なコミュニケーションと、リラックスした雰囲気づくりが重要になります。
インタビューシーンでは、質問を事前に共有し、回答の要点を整理しておくことで、自然な発言を引き出すことができます。
効果的なカメラワーク
医療現場の雰囲気を伝えるためには、固定ショットだけでなく、適度な動きのあるカメラワークが効果的です。
ただし、過度な動きは視聴者の不快感につながるため、安定性を重視したスムーズな動きを心がけましょう。特にスタッフステーションや処置室などでは、業務の妨げにならない角度からの撮影が求められます。
編集のベストプラクティス
ストーリー構成の組み立て
採用動画は単なる施設紹介ではなく、視聴者の感情に訴えかけるストーリー性が重要です。導入部分で視聴者の興味を引き、中盤で具体的な情報を提供し、終盤で応募への動機付けを行うという基本構造を意識しましょう。
また、現役看護師の成長ストーリーを織り交ぜることで、より説得力のある内容となります。
テンポ感のある編集
視聴者の集中力を維持するために、適度なテンポ感のある編集が求められます。一つのカットの尺は3-5秒を基本とし、インタビューシーンでは10-15秒を目安とします。ただし、重要な情報を伝える場面では、視聴者が理解できる十分な時間を確保することも必要です。
音声・BGMの活用
クリアな音声収録
医療現場特有の背景音(モニター音や放送など)に配慮した収録が必要です。ピンマイクやガンマイクを使用し、できるだけクリアな音声を収録することで、視聴者に確実に情報が伝わります。
必要に応じて、防音設備の整った面談室などでのインタビュー収録も検討しましょう。
効果的なBGM選択
BGMは視聴者の感情に大きく影響を与える要素です。医療機関にふさわしい落ち着いた雰囲気の楽曲を選択し、音量レベルは台詞が聞き取りやすい程度に抑えることが重要です。著作権処理済みの楽曲を使用することは言うまでもありません。
字幕・テロップの効果的使用
視認性の高いデザイン
視聴環境に関わらず情報が確実に伝わるよう、視認性の高い字幕デザインを心がけます。フォントサイズは動画の解像度に応じて適切に設定し、背景との色差にも配慮が必要です。医療機関のブランドカラーを活用することで、統一感のある仕上がりになります。
情報の最適な表示
重要な情報は字幕とナレーションの両方で伝えることで、確実な情報伝達を実現します。特に数値データや勤務条件など、正確な伝達が求められる情報については、視覚的な強調表現を活用することも効果的です。
各部署での撮影時の注意点
病棟での撮影ポイント
病棟での撮影では、患者様のプライバシー保護が最優先事項です。廊下や看護ステーションなど、患者様の映り込みが少ないエリアを中心に撮影を行います。また、夜勤帯の撮影では、患者様の睡眠を妨げないよう、特に細心の注意が必要です。
特殊部門での配慮事項
手術室やICUなどの特殊部門では、厳格な感染対策が求められます。撮影スタッフの入室制限や機材の滅菌処理など、各部門の規定に従った対応が必要です。また、高度医療機器への影響を考慮し、使用する撮影機材にも制限がかかる場合があります。
ケーススタディ

採用動画の効果を最大限に引き出すためには、実際の成功事例から学ぶことが重要です。このセクションでは、規模や特性の異なる3つの医療機関における採用動画の活用事例をご紹介します。
それぞれの事例から、効果的な実施のポイントと得られた成果について詳しく解説していきます。
大規模総合病院Aの事例
課題と目標設定
1000床を超える大規模総合病院Aでは、2024年度の新卒看護師採用において応募者数の減少傾向が続いていました。特に若い世代への訴求力不足が課題となっており、職場の雰囲気や実際の業務内容をより魅力的に伝えることが求められていました。
実施した施策
同院では、若手看護師を中心とした採用動画プロジェクトチームを結成し、現場の声を直接反映させた内容作りを行いました。
特に注目すべき点として、各専門領域の若手看護師が自身のキャリア形成過程や日常業務を紹介する「My Nursing Story」シリーズを制作し、SNSでの展開を積極的に行いました。
得られた成果
この取り組みにより、新卒応募者数が前年比150%に増加し、特に若手看護師からの共感を得られたことで、採用後の定着率も向上しています。
地域密着型病院Bの事例
地域特性を活かした展開
200床規模の地域密着型病院Bでは、地域における認知度向上と、地元看護学生への魅力的な情報発信が課題となっていました。
独自のアプローチ
同院では、地域医療に特化した魅力を前面に出し、在宅医療支援や地域連携に関する具体的な取り組みを詳細に紹介する動画を制作しました。
特に、地域住民や連携施設の方々からの声を取り入れることで、地域における同院の存在意義を効果的に伝えることに成功しています。
実現した成果
地域の看護学校との連携が強化され、実習生からの就職希望者が増加するという具体的な成果が得られています。採用数の増加だけでなく、地域医療に興味を持つ看護師の応募が増えたことで、病院の理念に合致した人材の確保にもつながっています。
専門医療施設Cの事例
専門性の発信
がん専門病院である医療施設Cでは、高度な専門性を持つ看護師の確保が課題となっていました。そこで、専門看護師や認定看護師の活躍に焦点を当てた採用動画の制作を行いました。
特徴的な取り組み
同院では、がん看護の専門性や、キャリア形成支援制度の詳細を、実際の症例対応やチーム医療の現場を通じて紹介しています。また、研究活動や学会発表などの学術的な活動についても積極的に取り上げ、専門職としての成長機会を具体的に示しています。
達成された目標
この取り組みにより、がん看護に特化したキャリアを目指す看護師からの応募が増加し、専門性の高い人材の確保に成功しています。また、既存スタッフのモチベーション向上にもつながり、院内全体の活性化にも寄与しています。
これらの事例から、採用動画の効果を最大化するためには、各医療機関の特性や強みを明確に打ち出し、ターゲットとする層に適切に訴求することが重要であることがわかります。
予算計画と費用対効果

採用動画の制作には適切な予算配分と投資対効果の検証が不可欠です。このセクションでは、2025年における採用動画制作の具体的な費用構造と、その効果測定の方法について解説していきます。
制作費用の内訳
基本制作費
制作費用の中核となる基本制作費には、企画立案から撮影、編集までの一連の工程が含まれます。標準的な5分程度の採用動画では、150万円から300万円程度の予算が必要となります。
この費用には、ディレクター、カメラマン、編集者などの人件費が含まれており、クオリティを決定する重要な要素となります。
追加オプション費用
インタラクティブ要素の実装やAI機能の追加など、先進的な機能を盛り込む場合には、追加の予算が必要となります。
バーチャル病院見学機能の実装には50万円から100万円程度、AIチャットボット機能の導入には100万円から200万円程度の追加費用が発生することが一般的です。
ROIの計算方法
定量的効果の測定
採用動画の投資対効果を測定する際は、応募者数の増加率や内定承諾率の変化などの定量的指標を活用します。たとえば、採用動画導入前後で応募者数が1.5倍に増加し、採用にかかる総コストが20%削減できた場合、具体的なROIを算出することが可能です。
定性的効果の評価
数値化が難しい効果として、病院ブランドイメージの向上や、応募者の質の向上などが挙げられます。これらの効果は、応募者アンケートや面接時の反応などを通じて評価していきます。
コスト削減のテクニック
効率的な撮影計画
撮影日数を最小限に抑えるため、事前の入念な撮影計画が重要です。複数の部署の撮影を同日に効率よく行うことで、機材レンタル費用や人件費を抑制することができます。また、院内スタッフの協力を得ることで、エキストラ費用なども削減可能です。
素材の有効活用
制作した動画素材は、採用動画以外の用途にも活用することで、総合的なコストパフォーマンスを高めることができます。病院紹介動画や研修用動画など、複数の目的で素材を共有することで、制作コストの分散が可能となります。
このように、採用動画の制作には相応の投資が必要となりますが、適切な予算計画と効果測定を行うことで、長期的な採用コストの削減につながる重要な施策となります。
法的配慮とコンプライアンス

医療機関における採用動画の制作では、一般企業以上に慎重な法的配慮とコンプライアンスへの対応が求められます。このセクションでは、制作時に注意すべき法的事項と、具体的な対応方法について解説していきます。
肖像権・個人情報保護
撮影対象者への配慮
医療現場での撮影では、患者様や医療従事者の肖像権保護が最も重要な課題となります。撮影時には必ず書面での同意を取得し、使用目的や公開範囲を明確に説明する必要があります。
特に患者様が映り込む可能性がある場合は、撮影エリアを制限するか、完全にぼかし処理を施すなどの対応が必要です。
個人情報の取り扱い
電子カルテの画面やホワイトボードなど、個人情報が写り込む可能性のある箇所については、細心の注意を払う必要があります。編集時には、これらの情報が判読できないよう、適切なモザイク処理やぼかし処理を施すことが重要です。
医療情報の取り扱い
医療機器・設備の撮影
最新の医療機器や設備を撮影する際は、メーカーや取引先との契約内容を確認し、必要に応じて撮影許可を取得します。また、医療安全の観点から、機器の使用方法や設定画面などの詳細が特定できないよう、適切なアングルでの撮影を心がけます。
診療情報の保護
診療内容や治療方針など、医療に関する専門的な情報を扱う際は、医療法や個人情報保護法に基づいた適切な情報管理が必要です。特に、特定の症例や治療方法を紹介する場合は、患者様の特定につながる情報を完全に排除する必要があります。
必要な同意書類
撮影協力者用同意書
撮影に協力いただく職員や患者様からは、必ず書面での同意を取得します。同意書には、撮影目的、使用用途、公開期間、公開媒体などを明確に記載し、撮影後のデータ管理方法についても説明を加えます。
二次利用に関する同意
制作した動画を採用活動以外の目的で使用する可能性がある場合は、その旨を事前に説明し、別途同意を取得する必要があります。特にSNSでの展開やウェブサイトでの公開など、インターネット上での使用については、具体的な条件を明示することが重要です。
これらの法的配慮とコンプライアンス対応は、採用動画の制作において決して軽視できない重要な要素となります。
おしえてカンゴさん!〜採用動画に関するQ&A〜
看護師採用動画の制作に関して、現場の採用担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。ベテラン看護師のカンゴさんが、実践的な視点からアドバイスをお届けします。
動画制作の基本について
Q1:採用動画の最適な長さはどのくらいですか?
視聴者の集中力を考慮すると、メインとなる採用動画は5分程度が理想的です。ただし、用途に応じて、SNS向けの30秒ダイジェスト版や、詳細な職場紹介用の10分版など、複数の尺で展開することをお勧めします。
特に若い世代向けには、1-2分程度の短編動画を複数制作し、シリーズ化することで、継続的な情報発信が可能となります。
Q2:撮影の準備期間はどのくらい必要ですか?
企画から完成まで、通常2〜3ヶ月程度の期間を想定する必要があります。特に医療現場での撮影では、感染対策や患者様への配慮が必要なため、入念な事前準備が重要です。
撮影場所の選定、スタッフのスケジュール調整、必要な許可申請など、準備に1ヶ月、撮影に2〜3日、編集に3〜4週間程度を見込んでください。
コンテンツと演出について
Q3:動画に盛り込むべき必須要素は何ですか?
病院の基本情報、看護体制、研修制度、福利厚生に加えて、実際の職場の雰囲気や先輩看護師の声を含めることが重要です。
特に、実際の業務の様子や、プリセプター制度などの教育体制、ワークライフバランスに関する情報は、応募検討者の関心が高い要素となっています。
Q4:スタッフの緊張をほぐすコツはありますか?
カメラに不慣れなスタッフが自然な表情で撮影に臨めるよう、事前のコミュニケーションが重要です。本番前に質問内容を共有し、リハーサルを行うことで、緊張を軽減することができます。
また、普段の業務風景を撮影する際は、カメラを意識させないよう、ある程度の距離を保って撮影することをお勧めします。
効果測定と活用について
Q5:採用動画の効果をどのように測定すればよいですか?
動画の視聴回数やエンゲージメント率に加えて、応募者アンケートで動画の影響度を確認することが効果的です。面接時に「動画を見て応募を決めた」という声が多く聞かれるようになれば、採用動画が効果的に機能していると判断できます。
また、内定承諾率や入職後の定着率なども、長期的な効果測定の指標となります。
Q6:完成した動画をどのように活用すればよいですか?
採用サイトやSNSでの公開はもちろん、合同説明会での上映や、看護学校への訪問時の資料として活用することができます。
また、動画の一部を切り出して、インターンシップの案内や、部署紹介など、様々な用途に展開することも可能です。定期的な更新と、視聴者の反応に応じた改善を行うことで、より効果的な採用活動につながります。
最新技術の活用について
Q7:VRやAR技術を採用動画に取り入れるメリットはありますか?
VRやAR技術を活用することで、よりリアルな職場体験を提供することが可能です。特にコロナ禍以降、オンラインでの病院見学や職場体験の需要が高まっており、これらの技術を活用することで、場所や時間の制約なく、臨場感のある情報提供が可能となります。
ただし、導入コストと効果を十分に検討する必要があります。
Q8:ソーシャルメディアでの展開のコツは?
各プラットフォームの特性に合わせたコンテンツ制作が重要です。InstagramやTikTokでは、看護師の日常や職場の雰囲気を切り取った短い動画が効果的です。
一方、YouTubeでは、より詳細な情報を含む長尺の動画も視聴できます。また、現役スタッフが自身の言葉で語る動画は、特に高い共感を得られる傾向にあります。
効果測定と改善
採用動画の効果を最大限に引き出すためには、継続的な効果測定と改善が不可欠です。このセクションでは、具体的な測定方法と、データに基づく改善プロセスについて解説していきます。
KPIの設定方法
定量的指標の設定
採用動画の効果を客観的に評価するためには、適切なKPIの設定が重要です。主要な指標として、動画の視聴回数、視聴完了率、エンゲージメント率(いいねやコメントの数)などが挙げられます。
また、採用プロセスにおける指標として、応募者数の増減、内定承諾率、採用コスト削減率なども重要な評価基準となります。
定性的指標の活用
数値化が難しい効果についても、適切な評価方法を設定することが重要です。応募者アンケートや面接時のヒアリングを通じて、動画の印象や影響度を確認します。特に、志望動機における動画の影響や、病院の理念・価値観の理解度は、重要な評価ポイントとなります。
データ分析手法
視聴者行動の分析
動画配信プラットフォームが提供する分析ツールを活用し、視聴者の行動パターンを詳細に分析します。
どの時点で視聴を中断する人が多いか、どのセクションに特に関心が集まっているかなど、具体的な視聴傾向を把握することで、効果的な改善につなげることができます。
クロスチャネル分析
採用サイトやSNSなど、複数のチャネルでの成果を総合的に分析することで、より効果的な配信戦略を立案することができます。各プラットフォームでの反応の違いや、視聴者層の特徴を把握し、チャネルごとに最適化されたコンテンツ制作を行います。
改善サイクル
PDCAサイクルの実践
効果測定の結果を次の施策に活かすため、定期的なPDCAサイクルの実践が重要です。計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)の各段階で、具体的なアクションプランを設定し、継続的な改善を図ります。
フィードバックの収集と活用
視聴者からのコメントや応募者からのフィードバックを積極的に収集し、改善に活かします。特に、現役看護師や看護学生からの意見は、より効果的なコンテンツ制作のためのヒントとなります。
また、採用担当者や現場スタッフからの意見も、重要な改善の視点となります。
まとめ
2025年の看護師採用動画は、AIやメタバース技術の活用により、よりパーソナライズされた採用体験を提供できるようになっています。効果的な採用動画の制作には、適切な予算計画、法的配慮、そして継続的な効果測定が不可欠です。
特に医療現場ならではの配慮事項を踏まえつつ、応募者に魅力的な職場環境を伝えることが重要です。
より詳しい看護師のキャリア情報や、実践的な転職アドバイスをお求めの方は、『はたらく看護師さん』の各種サービスをご活用ください。
▼会員登録はこちら [はたらく看護師さん 会員登録ページ]