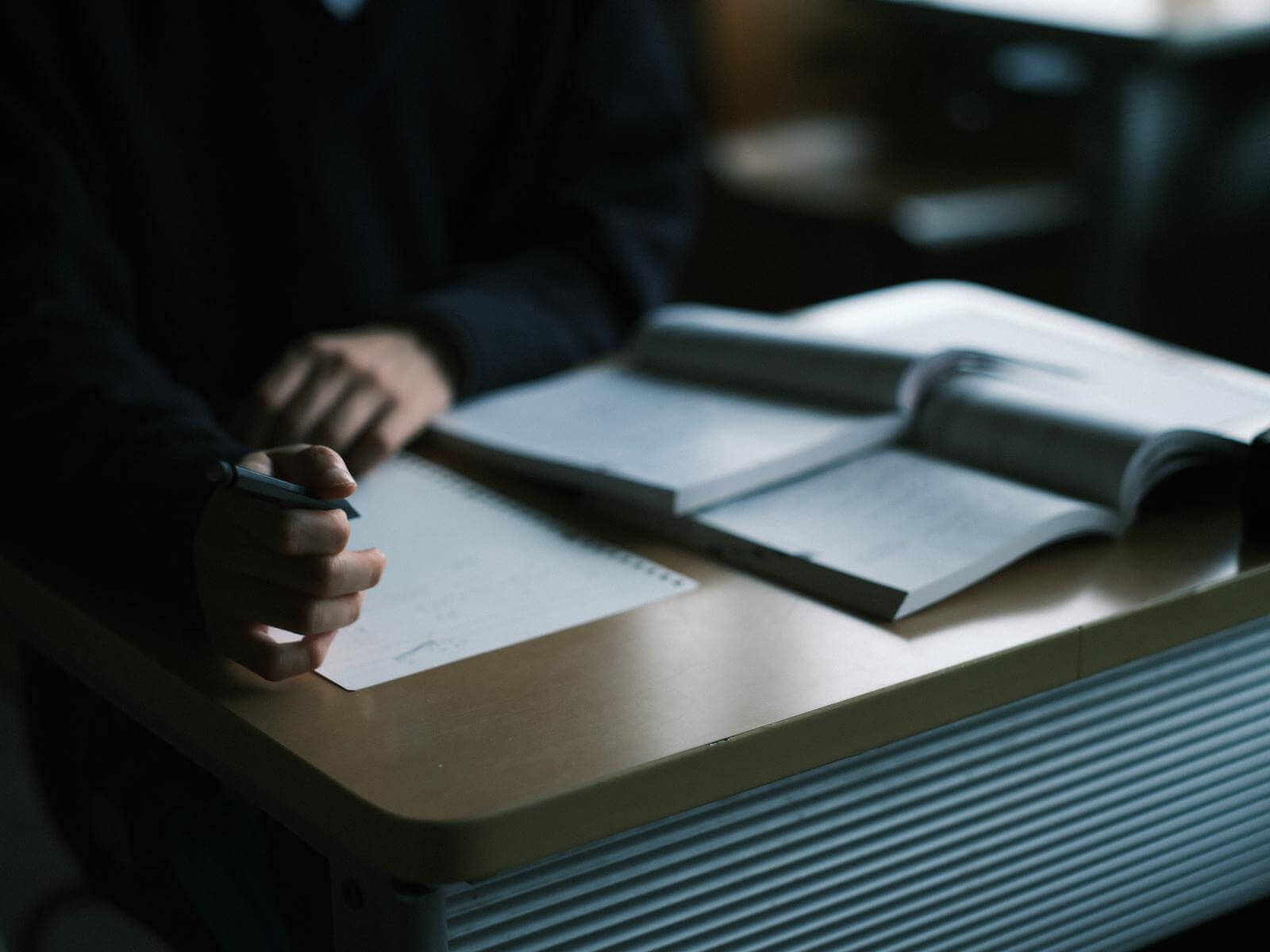看護師として働く中で、「つらい」と感じる瞬間は誰にでもあります。人間関係の難しさ、ミスへの不安、激務による疲労…。
でも、あなたは一人じゃありません。本記事では、現役看護師の声をもとに、つらいと感じる7つの状況とその乗り越え方を詳しく解説します。新人看護師の悩みにも触れ、仕事を辞めたくなった時の効果的な対処法まで網羅。看護師としてのキャリアを前向きに続けるためのヒントが見つかるはずです。
意外と多い!仕事がつらいと思う看護師
多くの人が看護師の仕事を誇りに思い、患者の健康と命を支えるために日夜努力しています。しかし、その一方で、多くの看護師たちが仕事をつらいと感じる瞬間が存在します。
現実に、看護師たちは仕事を通じてさまざまな困難に直面しています。こうした感情は、あなただけでなく多くの看護師が同じように感じているかもしれません。
看護師が仕事をつらいと感じる瞬間

看護師のほとんどの方が経験しているつらいと感じる瞬間。一生懸命仕事をやっているのに、報われないと感じる瞬間が多くあります。その理由は、看護師の方であれば共感できることばかり。それでは、「もう仕事に行きたくない」と感じるほどの、つらい瞬間とはいったいどんな内容なのか見ていきましょう。
人間関係がうまくいかない
病院や医療機関は、多くのスタッフが協力して成り立っていますが、その中でも看護師の役割は特に重要です。しかし、様々な人と関わり合いながら仕事をしていくことは、コミュニケーションの難しさを伴います。
そのため、誤解や意見の不一致が生じ、ストレスが蓄積されることにより、看護師の仕事を困難にしてしまう要因になります。また、看護師の多くは女性です。女性ばかりの職場というところに、特有の難しさを感じる方も多くいるようですね。無視やパワハラなどの経験をされている方も少なくないようです。
ミスに対しての不安
真面目な性格の人ほど陥りやすいのがミスに対しての不安です。看護師の仕事は、正確さと注意力を要求される業務です。しかし、人間誰しもミスをする可能性があります。
看護師の業務には、薬剤の誤投与、診断のミス、手順の過ちなど、看護師がミスを犯すことは避けられない場合もあります。このような責任感からくる不安から、体調を崩してしまう看護師さんも多くいます。
「医療ミスを起こしたらどうしよう」という不安を持ち続けることで、仕事に行きたくないと感じてしまう看護師さんも多いようです。
激務による過労
看護師たちは24時間体制で患者のケアに当たることが求められます。急患の増加や予期せぬ状況への対応など、緊急性の高い状況に直面することが多いため、激務は避けられないのが現実です。
長時間の勤務や連日の夜勤により、体力の消耗や精神的な疲労が蓄積され、看護師たちは自身の健康を犠牲にしがちです。激務による過労がストレスとなり、看護師の生活に疲れ果ててしまうという方も多くいます。
夜勤がつらい
看護師のシフト勤務の中で特につらいとされるのが夜勤です。普通の生活と逆の生活になる夜勤勤務は、生活リズムの乱れを引き起こし、睡眠不足や疲労感を招いてしまいます。
また夜勤は、患者の急変や緊急事態への対応が求められるため、高い集中力と判断力が要求されます。しかし、深夜の静けさや孤独感が、看護師たちの心にプレッシャーや孤独感をもたらすこともあります。通常業務が激務の上に、夜勤のつらさが合わさることで、心身の不調を訴える方もいます。
仕事に対してのプレッシャー
看護師の仕事は高度な専門知識や正確性を求められるため、プレッシャーを感じることが少なくありません。患者の命にかかわる業務に従事しているため、業務の中で「患者の容態が急変して死に直面したとき」には、責任を感じてしまう方も多く、気持ちをうまく切り替えられないという方も多くいます。
また中堅看護師になってくると、リーダーという立場にプレッシャーを感じてしまう方も多くいるようですね。精神的な疲労は、仕事に対するパフォーマンスの低下を招いてしまいます。
そもそも仕事が合わない
看護師として働き始めても、実際の業務内容や職場の雰囲気が自分に合わないと感じることがあります。特に希望していない診療科に配属になった場合や、看護以外の業務に追われると、看護師になった理由を見失ってしまうこともあります。
どんな業種でも、理想通りの仕事ができるわけではありませんが、仕事内容が想像と全く違っていたときや、理想の看護師生活が送れない場合は、仕事に対するモチベーションの低下を招いてしまうこともあるようです。
患者からのハラスメント
患者を助けることが業務でもある看護師ですが、残念ながら心無い言葉を浴びせてくる患者も中にはいます。
患者の中には、病気やストレスによって感情が不安定になっているケースもあり、その影響を看護師にぶつけることがあるため、このような状況に直面することは、看護師たちにとって精神的に負担がかかることがあるようです。
新人が感じるつらいと感じる瞬間

夢と希望をもって職場に配属になった新人看護師。そんな新人看護師には、新人ならではのつらいと感じる瞬間があるようですね。新人期間を過ぎた方は、当時を思い出してみてください。
理想と現実のギャップ
新人看護師のうちは、看護学校や研修で学んだことと、実際の現実とのギャップに直面することがあります。実務では想像していなかった課題やトラブルが生じることもあり、これが理想との違いを感じさせ、つらさを抱えることがあります。
これは「リアリティショック」と呼ばれる現象で、自分が描いていたイメージと実際の現場がの違いを消化しきれず、モチベーションの低下を引き起こしてしまうそうです。
知識が足りない
新人看護師は経験が浅いため、まだまだ知識が足りないと感じることがあります。複雑な医療行為や治療に対する知識の不足によって、自分はこの仕事に向いていないという、自信の喪失や不安を引き起こす要因となっています。
指導が厳しい
新人看護師は、ベテラン看護師や上司からの指導を受けながら成長していく段階にあります。しかし、中には厳しい指導や厳しい指導を受けることがあり、それによってプレッシャーやつらさを感じることがあります。
つらい時にやってはいけないこと
このように、看護師の仕事をしていると「つらい」と感じる場面は多くあります。そんな時に、その現状を何とかしようと、いろいろ試す方もいると思いますが、つらい時にだからこそやってはいけないことというのがあります。ここでは、3つの行動をご紹介します。
仕事がつらいのを自分のせいにしない
つらい状況に直面したとき、自分自身を責めたり罪悪感を感じたりすることは避けましょう。真面目な性格の人ほど自分のせいだと思い込んでしまいがちになります。自分を責めるとさらに我慢を積み重ねてしまい、状況が悪化する可能性があります。
看護師としての道は、経験を通じて成長していく過程です。つらい瞬間を経て学びを得ることは、成長の一環として前向きに捉えることが大切です。
無理をして仕事をする
つらい状況に対処するために無理をして仕事を続けることは、身体的・精神的な健康を害する可能性があります。適切な休息やストレス解消を怠らないようにしましょう。
体の不調を見ないふりをする
仕事が忙しくつらい時には、体調を無視して働き続けることがあります。しかし、体の不調を無視することは、病気や疲労の悪化を招く可能性があります。体のサインを無視せず、適切なケアを行いましょう。
つらいと感じたときにするべき対処法

看護師としての仕事は、尊い使命を担う一方で、時にはつらい瞬間も訪れることがあります。最後に、看護師の仕事を辞めたくなったと感じる場合、どのように対処すればいいのかご紹介していきます。
一度自分を見つめなおす
仕事に疲れや不満を感じるとき、まずは自分自身と向き合ってみましょう。なぜ仕事がつらいと感じるのか、どの部分が辛いのかを考えることで、具体的な問題点を把握することができます。また、自身の目標や価値観と照らし合わせて、今の仕事が本当に自分に合っているのかを再評価しましょう。
数年先を考えてみる
仕事が辛い瞬間があるとき、現在の状況だけに囚われず、数年後の自分をイメージしてみることも大切です。今の辛い状況が将来の成長やキャリアに繋がる可能性があるかを考え、今の苦労が将来の自分をより強くするための一歩であるかもしれません。
リフレッシュする
仕事のストレスから解放されるために、定期的なリフレッシュが必要です。休暇を取る、趣味に時間を割く、自然の中で過ごすなど、仕事から離れて心身をリセットすることで、新たなエネルギーを得ることができます。
上司に相談する
仕事がつらいと感じたとき、上司との面談を通じて問題を共有することも一つの方法です。上司はあなたのキャリアをサポートする立場にあり、改善策やサポートを提案してくれる可能性があります。コミュニケーションを通じて解決策を見つけることができるかもしれません。
看護師の資格を活かせる職場に転職する
もし看護師の仕事を続けても辛さが解消されない場合、看護師の資格を活かせる別の職場への転職も考慮してみてください。医療機関以外でも、訪問看護や在宅介護、保健師としての活動など、看護師のスキルを活かせる職場はさまざま存在します。
まとめ\
この記事では、看護師の仕事をつらいと感じる瞬間についてご紹介してきました。看護師の仕事は充実感と責任を伴う一方で、つらさやストレスを感じる瞬間も存在します。人間関係の複雑さや肉体的・精神的な負荷に直面したとき、適切な対処法を実践することが重要です。
コミュニケーションの改善、ワークライフバランスの確保、感情のケア、ミスへの向き合い方、ストレス管理など、どのように対処していくかが、看護師として重要なポイントとなってくるでしょう。今回の記事を参考に、看護師としての充実したキャリアを築いてみてください。