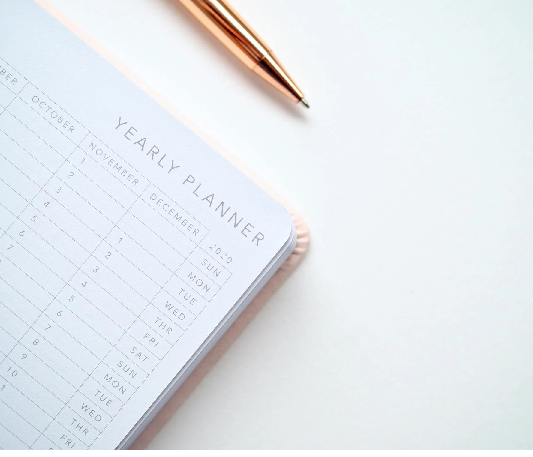「看護師の給料はいいのに、なかなか貯金が貯まらない…」 そんな悩みを抱える看護師さんは多いのではないでしょうか。実は、忙しい看護師だからこそできる効率的な貯金術があります。この記事では、実際に年間100万円の貯蓄を達成した看護師さんたちの具体的な方法や、無理なく続けられる資産形成の戦略をご紹介します。給与体系や夜勤手当の活用など、看護師ならではの収入の特徴を活かした貯金術を、分かりやすく解説していきます。
この記事で分かること
・看護師の平均貯蓄額と年代別の目標貯金額
・無理なく毎月10万円以上貯められる具体的な方法
・看護師の給与体系を活かした効率的な資産形成戦略
この記事を読んでほしい人
・毎月の貯金額を増やしたい看護師
・将来の資金計画に不安がある看護師
・効率的な資産形成の方法を知りたい看護師
看護師の貯金事情を徹底解説

看護師の貯金事情は、一般的な会社員とは大きく異なる特徴があります。夜勤手当や各種手当を含む独特の給与体系、不規則な勤務形態による支出パターン、そして年代や職場によって大きく変化する貯蓄傾向。このセクションでは、2024年の最新データを基に、看護師の貯金事情の実態と傾向を詳しく解説していきます。あなたの貯金計画の参考となる具体的な数字とともに、現状を把握していきましょう。
看護師の年代別平均貯蓄額とその特徴
2024年現在、看護師の貯金事情は大きく変化しています。日本看護協会の最新調査によると、看護師の平均貯蓄額は年々増加傾向にあるものの、年代や勤務形態によって大きな差が見られます。
特に注目すべきは、20代後半から30代前半の看護師の貯蓄額です。この年代の平均貯蓄額は約320万円となっており、同年代の全職種平均と比較して約1.2倍高い水準となっています。これは、夜勤手当や各種手当が充実している看護師の給与体系が大きく影響しています。
年代別の平均貯蓄額を見ると、20代前半の看護師の平均貯蓄額は約180万円です。これは初期キャリアでありながら、基本給に加えて夜勤手当などの収入が得られることが要因となっています。30代後半になると平均貯蓄額は約450万円まで増加し、40代では約650万円となっています。
職場形態別の貯蓄傾向の違い
勤務先によって貯蓄額に大きな差が生まれるのが、看護師の特徴です。大学病院、総合病院、クリニックなど、それぞれの職場環境によって収入構造や貯蓄のしやすさが異なります。勤務形態による違いを理解することで、自身の環境に合った効果的な貯蓄方法が見えてきます。
職場形態による貯蓄傾向の違いは顕著です。大学病院勤務の看護師は、豊富な夜勤機会と充実した手当制度により、比較的高額な貯蓄を実現できています。一方、クリニックなど日勤のみの施設で働く看護師は、基本給は安定しているものの、特別手当が少ないため、計画的な貯蓄がより重要となっています。
勤務形態別の特徴を詳しく見ると、大学病院などの3交代制勤務の看護師は、月平均の貯蓄額が一般病院勤務の看護師と比べて約1.5倍高くなっています。これは夜勤手当に加え、休日出勤手当や特殊勤務手当など、複数の手当が組み合わさることで収入が増加するためです。
しかし、収入の高さだけが貯蓄額を決定づける要因ではありません。クリニック勤務の看護師の中には、安定した勤務時間を活かして副業に取り組んだり、規則正しい生活リズムによって支出を抑制したりすることで、着実な貯蓄を実現している例も多く見られます。
2024年の看護師の収入・支出の実態調査
2024年に入り、看護師の収入・支出状況には新たな傾向が見られるようになりました。働き方改革の影響や、デジタル化の進展による支出傾向の変化など、貯蓄環境は大きく変化しています。ここでは最新の調査データから、現代の看護師が直面している経済状況を紐解いていきます。
2024年の実態調査では、看護師の収入と支出に関する興味深い傾向が明らかになりました。看護師全体の約65%が定期的な貯蓄習慣を持っており、そのうち約40%が給与の30%以上を貯蓄に回しているという結果が出ています。
特に注目すべきは、夜勤専従看護師の貯蓄率の高さです。夜勤手当を効率的に運用することで、月収の40%以上を貯蓄に回している事例も少なくありません。一方で、支出面での課題も浮き彫りになっています。不規則な勤務時間による外食費の増加や、疲労回復のためのリフレッシュ費用など、看護師特有の支出項目が貯蓄の障壁となっているケースが報告されています。
さらに、デジタル化の進展による新たな支出傾向も見られます。オンラインショッピングの利用増加や、スマートフォンアプリを活用した食事宅配サービスの利用など、利便性を重視した支出が増加傾向にあります。これらの支出は、忙しい看護師の生活を支える一方で、適切な管理が必要となっています。
ワークライフバランスと貯蓄の関係も見逃せません。2024年の調査では、残業時間を効率的にコントロールできている看護師ほど、安定した貯蓄習慣を確立できている傾向が明らかになりました。特に、時間管理と収支管理を連動させている看護師は、より効果的な貯蓄を実現できています。
この現状を踏まえると、看護師の貯蓄において重要なのは、個々の状況に応じた適切な貯蓄戦略の選択です。次のセクションでは、効率的な貯金を実現するための3つの柱について詳しく見ていきましょう。
効率的な貯金を実現する3つの柱

看護師の収入は、基本給に加えて様々な手当で構成されており、一般的なサラリーマンとは異なる特徴があります。効率的な貯金を実現するには、この独特の収入構造を理解し、活用することが重要です。このセクションでは、看護師の収入を最大限に活かすための3つの重要な要素について、実践的な方法を解説していきます。
給与構造を理解した収入管理
看護師の給与は、一見すると複雑に見えるかもしれません。しかし、その構造を正しく理解することで、効率的な貯金が可能になります。給与明細に記載される様々な項目には、それぞれ重要な意味があります。
基本給は安定収入の土台となりますが、これに加えて夜勤手当、通勤手当、住宅手当、扶養手当など、様々な手当が付加されます。2024年の調査によると、看護師の月収に占める手当の割合は平均して30〜40%にも及びます。これらの手当を効果的に活用することが、貯金を増やすカギとなります。
特に注目すべきは、資格手当です。専門看護師や認定看護師などの資格を取得することで、月額1万円から3万円程度の手当が追加されます。これらの資格取得は、長期的なキャリアアップだけでなく、収入増加による貯蓄額の向上にもつながります。
また、給与支給日と固定費の支払い日を適切に調整することも重要です。例えば、家賃や光熱費の引き落とし日を給与日直後に設定することで、手残りの金額が明確になり、計画的な貯金が可能になります。実際に、この方法を実践している看護師の中には、月の貯金額を安定して確保できている事例が多く報告されています。
夜勤手当の効果的な活用法
夜勤手当は看護師の収入アップに大きく貢献する要素です。一般的に深夜勤務手当は基本給の25%以上が上乗せされ、これに加えて夜勤専門手当が設定されている施設も多くあります。この貴重な収入源を計画的に活用することで、貯蓄を大きく増やすことが可能です。
多くの看護師が夜勤手当を「臨時収入」のように考えがちですが、これを定期的な収入として捉え直すことが重要です。例えば、月に4回の夜勤で得られる手当は、おおよそ4〜6万円程度になります。この金額を最初から貯金額として確保しておくことで、安定的な貯蓄が可能になります。
ただし、夜勤による身体的負担を考慮することも忘れてはいけません。過度な夜勤シフトは健康を損なう可能性があり、結果として医療費などの支出増加につながる可能性があります。2024年の調査では、月の夜勤回数が6回を超えると、体調管理のための支出が増加する傾向が報告されています。
夜勤手当の効果的な活用例として、「手当専用口座」の設定が挙げられます。夜勤手当を受け取ったら、即座にこの専用口座に振り替えるようにします。この方法を実践している看護師からは、「手当が生活費に紛れ込まない」「貯金額が視覚的に分かりやすい」といった好評の声が寄せられています。
さらに、夜勤シフトの選択も戦略的に行うことが重要です。例えば、祝日や特別な期間の夜勤は、通常よりも高額な手当が設定されていることが多いため、体調と相談しながら、こうした機会を活用することも検討に値します。
ある大学病院の看護師は、夜勤手当を活用した貯金術について次のように語っています。「月の夜勤回数を4回に固定し、その手当を全額投資信託に回しています。始めて2年で約120万円の資産形成ができました。無理のない範囲で続けることが、長期的な貯蓄成功のポイントだと実感しています。」
賞与・特別手当の賢い運用方法
看護師の年間収入において、賞与や特別手当は大きな割合を占めています。多くの医療機関では、年2〜3回のボーナスに加え、様々な特別手当が設定されています。これらの「まとまった収入」を計画的に運用することは、資産形成の重要なポイントとなります。
賞与の平均的な支給額は、一般的な病院で基本給の3〜4ヶ月分程度です。大学病院などではさらに高額となる場合もあります。2024年の調査によると、看護師の賞与の使い道として最も多いのは「預貯金」で全体の45%を占めていますが、その運用方法には改善の余地があることも分かっています。
効果的な賞与運用の第一歩は、受け取る前から具体的な配分計画を立てることです。ベテラン看護師の多くが実践している「3分割法」は、参考になる方法の一つです。具体的には、受け取った賞与を「将来への投資(40%)」「生活費の補填(30%)」「自己投資(30%)」に分けて管理します。
将来への投資としては、定期預金や投資信託、iDeCoなどの金融商品が選択肢として挙げられます。特に、確定拠出年金は所得控除の対象となるため、税制面でもメリットがあります。ある総合病院の主任看護師は、「賞与の40%を必ずiDeCoと投資信託に回すことで、5年間で約500万円の資産を形成できました」と語っています。
生活費の補填については、年間の固定費を12ヶ月で割った額の3〜4ヶ月分を確保しておくことをお勧めします。これにより、月々の給与からより多くの金額を貯蓄に回すことが可能になります。実際に、この方法を実践している看護師からは、「月の貯金額が安定し、家計管理の精度が上がった」という声が多く聞かれます。
自己投資の部分は、単なる消費ではなく、将来的な収入増加につながる使い方を意識することが重要です。例えば、専門看護師の資格取得のための学費や、語学力向上のための教材費など、キャリアアップにつながる支出に充てることで、長期的な収入増加が期待できます。
特別手当については、その性質に応じた活用方法を考えることが賢明です。たとえば、年末年始手当は、確定申告の準備や新年度の支出に備えた資金として確保しておくことをお勧めします。また、特殊業務手当は、その業務に関連する技能向上や資格取得の費用に充てることで、さらなるキャリアアップにつなげることができます。
以上のように、賞与や特別手当の運用は、単なる貯蓄にとどまらず、将来的な収入増加も視野に入れた戦略的な活用が重要です。次のセクションでは、看護師のライフステージ別貯金戦略について詳しく見ていきましょう。
看護師のライフステージ別貯金戦略
人生の各段階で、私たちの生活環境や経済的なニーズは大きく変化します。看護師としてのキャリアも同様に、年代によって収入構造や貯金の目的が変わってきます。このセクションでは、各ライフステージにおける効果的な貯金戦略を、実際の成功例を交えながら詳しく解説していきます。
【20代】将来設計と資産形成の始め方
看護師としてのスタートを切った20代は、貯金習慣の基礎を築く重要な時期です。この時期の特徴は、基本給こそ低めですが、夜勤手当などの追加収入を得やすく、また独身者が多いため、貯蓄に回せる金額が比較的大きいことです。
新人看護師の多くは、初めての給与管理に戸惑いを感じます。特に夜勤手当が加算された月の収入は、予想以上に大きくなることがあります。ある大学病院の3年目看護師は、「最初の1年は給与管理がうまくいかず、手当が入った月は使い過ぎてしまい、結果的に貯金が思うように増えませんでした」と振り返ります。
このような状況を改善するには、まず固定費と変動費を明確に分けることから始めましょう。家賃、光熱費、通信費などの固定費は、給与の50%以内に抑えることを目標とします。残りの金額から、毎月の貯金額を決めて自動引き落としに設定することで、継続的な貯蓄が可能になります。
20代での資産形成は、将来の大きな支出に備える意味も持ちます。結婚資金、住宅購入の頭金、さらには留学や資格取得など、キャリアアップのための資金も視野に入れる必要があります。2024年の調査では、20代看護師の平均貯蓄目標額は月10万円となっていますが、これは決して高すぎる目標ではありません。
実際に、ある26歳の看護師は次のような貯金計画を実践しています。「基本給の20%を普通預金、夜勤手当の全額を投資信託に回しています。加えて、3ヶ月に1度はまとまった額を定期預金に預け入れることで、3年間で約350万円の貯蓄ができました。最初は無理かと思いましたが、習慣化することで十分達成可能でした」
【30代】結婚・出産を見据えた貯蓄プラン
30代は、結婚や出産、住宅購入など、人生の大きなイベントが集中する時期です。同時に、看護師としてのキャリアも充実し、収入面では20代と比べて基本給が上昇し、役職手当が加わることも多くなります。このライフステージでは、長期的な視点での資産形成が重要になってきます。
結婚後の世帯年収は、配偶者の収入も加わることで大きく変化します。ある総合病院の主任看護師は、「結婚を機に、夫婦での家計管理を始めました。二人の収入を『生活費』『住宅費』『貯蓄・投資』の3つに分け、特に住宅購入を見据えた貯蓄を重視しました」と語ります。この方法により、3年間で頭金600万円の貯蓄に成功したそうです。
子育てとの両立は、30代看護師の大きな課題となります。保育費用や教育費の確保に加え、時短勤務による収入減少も考慮する必要があります。2024年の調査によると、子育て中の看護師の約60%が、収入が減少する中でも毎月の貯蓄を継続しています。
具体的な戦略として、「教育費専用の積立預金」の設定が効果的です。毎月の給与から一定額を自動的に振り替えることで、将来の教育費に備えます。ある34歳の看護師は、「第一子の出産後、月3万円ずつ教育費の積立を始めました。子どもの年齢に応じて積立額を調整し、現在は月5万円に増額しています」と説明します。
また、この時期は保険の見直しも重要です。医療保険や生命保険の見直しにより、月々の支出を最適化することで、その分を貯蓄に回すことができます。実際に、保険の見直しにより月々の支出を2万円削減し、その金額を投資信託の積立に回している例も見られます。
キャリアアップによる収入増加も、30代の貯蓄を支える重要な要素です。専門看護師や認定看護師の資格取得により、月額1〜3万円の手当が追加されます。この追加収入を確実に貯蓄に回すことで、資産形成のペースを加速させることができます。
住宅ローンを組む場合は、返済額と貯蓄のバランスが重要です。総返済額が年収の5倍を超えないことを目安とし、毎月の返済額は手取り収入の25%以内に抑えることが推奨されます。これにより、住宅ローンの返済をしながらも、継続的な貯蓄が可能となります。
【40代以降】老後資金の確保と資産運用
40代以降は、看護師としての経験と実績が評価され、収入が最も安定する時期です。一方で、老後の生活設計や子どもの進学費用など、長期的な視点での資金計画が必要になります。この時期の資産形成は、「貯める」だけでなく、「増やす」という視点も重要になってきます。
キャリア面では、管理職への昇進や専門性の向上により、基本給に加えて役職手当や資格手当が加算される看護師が増えます。ある総合病院の看護師長は、「40代からは収入の30%を老後資金として確保し、その半分を投資信託で運用しています。残りは定期預金や個人年金保険に振り分けることで、リスクの分散を図っています」と説明します。
特に注目すべきは、退職金を見据えた資産運用です。公立病院や大規模病院では、25年以上の勤続で2,000万円を超える退職金が支給されるケースもあります。しかし、この金額をただ預金するだけでは、将来的な生活水準の維持は困難かもしれません。実際に、ある45歳の看護師は「退職金の運用を見据えて、40代前半から投資の勉強を始めました。少額から投資信託を始めることで、運用のノウハウを学んでいます」と語ります。
資産運用の具体的な方法としては、以下のような組み合わせが効果的です。まず、給与の20%を国債や定期預金などの安全資産に、10%を投資信託やNISAなどの成長資産に配分します。これにより、安定性と収益性のバランスを取ることができます。2024年の調査では、この方法を実践している看護師の約70%が、年間5%以上の運用収益を達成しています。
また、この時期は保険の見直しも重要です。子どもの成長に伴い、教育費用保険や医療保険の見直しが可能になります。削減できた保険料を投資や貯蓄に回すことで、資産形成をさらに加速させることができます。
職場の福利厚生制度も、積極的に活用すべきです。確定拠出年金(企業型DC)や財形貯蓄など、税制優遇を受けられる制度を最大限活用することで、より効率的な資産形成が可能になります。ある大学病院の副看護部長は、「企業型DCの制度を活用し、毎月の拠出額を上限まで設定しています。20年間続けることで、約2,000万円の資産形成を目指しています」と話します。
このように、40代以降の資産形成は、安全性と収益性のバランスを考慮しながら、複数の方法を組み合わせることが重要です。次のセクションでは、実際に年間100万円の貯蓄を達成した看護師たちの具体的な事例を見ていきましょう。
看護師の貯金成功事例:年間100万円達成者に学ぶ

実際に高額な貯蓄を実現している看護師たちは、どのような工夫をしているのでしょうか。このセクションでは、異なるライフステージにある3名の看護師の貯金術を詳しく分析します。それぞれの事例から、具体的な戦略とその成功のポイントを学んでいきましょう。
[ケース1] 20代後半・大学病院看護師の場合
Aさん(27歳)は、大学病院で4年目の看護師として働いています。3交代制勤務で、年収は450万円。入職時から計画的な貯金を心がけ、昨年は年間156万円の貯蓄を達成しました。
「最初は貯金なんて無理だと思っていました。でも、先輩看護師に相談したことをきっかけに、収支を細かく管理するようになりました」とAさんは振り返ります。
具体的な収支内訳を見てみましょう。月の手取り収入は、基本給で23万円、これに夜勤手当が月4回で約6万円加算されます。支出は、ワンルームマンションの家賃6.5万円、光熱費・通信費2万円、食費3万円が主な固定費です。
特筆すべきは、Aさんの徹底した収支管理です。「給与明細が出たら、すぐにスマートフォンの家計簿アプリに入力します。夜勤手当は全額を別口座に振り替え、投資信託の積立に回しています」
また、Aさんは院内の職員食堂を積極的に活用しています。「夜勤の前後の食事は必ず職員食堂で済ませます。栄養バランスが良く、一食400円程度と経済的です。外食費を月1万円以内に抑えられています」
休日の過ごし方も工夫があります。「以前は休日にショッピングモールで時間を潰していましたが、今は近くの図書館で過ごすことが多いです。趣味の読書を楽しみながら、支出を抑えることができています」
貯金の内訳は以下の通りです:
- 給与の30%(約7万円)を財形貯蓄へ
- 夜勤手当(約6万円)を投資信託の積立に
- 賞与(年2回計120万円)の50%を定期預金に
「貯金を始めて2年目からは、投資も少しずつ始めました。投資信託を選ぶ際は、病院の先輩に相談したり、セミナーに参加したりして、慎重に検討しました」
[ケース2] 30代・子育て中の共働き看護師の場合
Bさん(34歳)は、2児の母として育児をしながら、クリニックで週4日勤務の看護師として働いています。世帯年収は850万円で、昨年は夫婦で年間240万円の貯蓄を達成しました。
「育児と仕事の両立は大変ですが、だからこそ計画的な貯蓄が重要だと考えています」とBさんは話します。保育園の送り迎えがしやすい職場を選んだことで、仕事と育児の両立が可能になりました。
Bさんの世帯収入は、本人の年収380万円と配偶者の年収470万円で構成されています。「共働き夫婦の強みは、二人の収入を明確に役割分担できること。私たちは『教育費』『住宅費』『生活費』『貯蓄』の4つに分けて管理しています」
特に効果的だったのは、手取り収入を「二人の生活費:50%」「教育費:20%」「住宅ローン:15%」「貯蓄:15%」と明確に区分したことです。「配偶者の収入は主に生活費と住宅ローンに、私の収入は主に教育費と貯蓄に充てています」
子育て世帯ならではの工夫も見られます。「子どもの服は『おさがり』を活用し、食材は週末にまとめ買いをして平日の夕食を計画的に準備します。これにより、食費を月5万円以内に抑えることができています」
保険の見直しも重要なポイントでした。「子どもが生まれた際に加入した学資保険を見直し、月々の掛け金を減額。その分を投資信託の積立に回すことにしました。将来の教育費は、投資による資産形成で対応する計画です」
収支管理においては、夫婦で月1回の「家計会議」を欠かしません。「その月の支出を振り返り、翌月の予算を立てます。特別な支出がある月は、どこで調整するか話し合います。二人で目標を共有することで、モチベーションも保てています」
貯蓄の内訳は以下の通りです:
- 教育費積立(月7万円)
- 投資信託の積立(月5万円)
- iDeCo(夫婦で月7万円)
- 賞与からの定期預金(年間100万円)
「子育て中は予期せぬ支出も多いですが、基本的な貯蓄額は確保するように心がけています。特に教育費の積立は最優先事項として考えています」
[ケース3] 40代・ベテラン看護師の場合
Cさん(42歳)は、総合病院で15年のキャリアを持つベテラン看護師です。主任として2交代制勤務をこなしながら、看護学校の非常勤講師としても活動しています。年収580万円で、昨年は貯蓄と投資を合わせて300万円の資産形成に成功しました。
「40代になって、老後の生活設計を真剣に考えるようになりました。収入を増やしながら、効率的な資産運用を心がけています」とCさんは語ります。
主任としての基本給に加え、資格手当や役職手当が収入を押し上げています。「認定看護師の資格を取得したことで月額2万円の手当が追加されました。また、非常勤講師の収入は年間で約60万円になります」
Cさんの特徴は、収入源の多様化と計画的な資産運用です。「給与は生活費と定期的な貯蓄に、夜勤手当は投資に、非常勤講師の収入は全額を積立NISAに回すという具合に、収入の種類によって使い道を明確に分けています」
医療知識を活かした副業選びも成功のポイントです。「看護学校での講師活動は、自身のスキルアップにもつながっています。また、勤務先の許可を得た上で、医療系セミナーの講師も引き受けています」
資産運用については、年齢に応じたリスク管理を徹底しています。「投資信託は、インデックスファンドを中心に選んでいます。50代に向けて徐々にリスクを下げていく予定ですが、いきなり運用をやめるのではなく、バランスを取りながら調整していきます」
また、確定拠出年金(iDeCo)も最大限活用しています。「毎月の拠出額は上限いっぱいの6.8万円に設定しています。所得控除のメリットを考えると、老後資金形成の核として最適だと考えています」
具体的な資産形成の内訳は以下の通りです:
- 給与からの定期預金(月10万円)
- 投資信託の積立(月8万円)
- iDeCo(月6.8万円)
- 積立NISA(非常勤収入から月5万円)
- 賞与からの運用(年間100万円)
「資産形成は、単なる貯蓄から運用への転換が重要です。ただし、急激な変更は避け、段階的に移行することを心がけています」とCさんは助言します。
次のセクションでは、これらの成功事例から学んだ具体的な節約術について、詳しく見ていきましょう。
看護師にオススメの具体的な節約術
看護師の生活は不規則で忙しいからこそ、効率的で継続可能な節約方法が重要です。このセクションでは、現役看護師たちが実践している効果的な節約術を、生活の場面ごとに詳しく解説していきます。
固定費の見直しポイント
固定費の削減は、確実な貯蓄につながる重要な要素です。特に、看護師の生活スタイルに合わせた見直しが効果的です。大手総合病院の看護師長は「固定費の見直しは、年に2回の賞与支給時に行うことをルーティンにしています」と話します。
住居費の最適化は、固定費削減の大きな柱となります。病院の寮や職員住宅を利用することで、家賃を抑えることができます。ある中堅看護師は「病院の寮に入ることで、家賃を月々3万円に抑えています。光熱費も含まれているため、固定費全体で月5万円以上の節約になっています」と説明します。
通信費の見直しも効果的です。夜勤が多い看護師の場合、固定回線を解約してモバイルルーターに切り替えることで、月々の支出を削減できます。「以前は固定回線とスマートフォン契約で月1.5万円かかっていましたが、現在は両方合わせて8,000円程度です」という声も聞かれます。
保険の見直しも重要なポイントです。医療従事者という立場を活かし、必要な保障を見極めることで、過剰な契約を避けることができます。「職場の福利厚生と基本的な医療保険のみとし、それ以外の保険は見直しました。月々2万円の支出削減につながっています」という事例もあります。
変動費のコントロール方法
看護師の不規則な勤務形態は、ともすると変動費の増加につながりやすいものです。しかし、適切な管理方法を身につけることで、無理のない節約が可能になります。
食費の管理は特に重要です。夜勤明けの食事や休憩時の間食など、不規則な生活による余分な出費が発生しやすい項目です。ベテラン看護師は「夜勤用の食事は必ず自前で用意し、タッパーに小分けして持参します。月の食費を5万円以内に抑えることができています」とアドバイスします。
病院の職員食堂やカフェテリアを賢く活用することも、食費節約の重要なポイントです。「夜勤の前後は必ず職員食堂を利用します。栄養バランスが良く、一食500円程度と経済的です。月に約2万円の食費削減につながっています」と、ある中堅看護師は説明します。
衣服費も看護師特有の課題があります。ユニフォームのクリーニング代や、通勤用の服装など、見過ごせない支出項目です。経験豊富な看護師は「ユニフォームは毎日持ち帰って自宅で洗濯し、週末にまとめてアイロンがけをしています。クリーニング代を月1万円以上節約できています」と話します。
交通費の管理も重要です。特に夜勤明けや早朝勤務時のタクシー利用は、支出を大きく押し上げる要因となります。「夜勤の際は同じシフトの同僚と相乗りするようにしています。一人当たりの負担が半分になり、月の交通費を約1.5万円抑えることができています」という工夫も聞かれます。
職場での賢い節約習慣
職場環境を活用した節約も、看護師ならではの方法です。病院という特殊な環境だからこそできる、効果的な節約方法があります。
まず、職場の福利厚生制度を最大限に活用します。職員割引のある提携店舗や、職員向けの各種サービスを積極的に利用することで、支出を抑えることができます。「病院の提携スポーツジムを利用することで、月々の会費が半額になっています。年間で約6万円の節約になります」という声もあります。
休憩時間の過ごし方も工夫のしどころです。「休憩室に電子レンジと電気ケトルを置かせてもらい、コーヒーやお茶は自分で用意しています。コンビニでの購入と比べると、月に約8,000円の節約になっています」と、ベテラン看護師は説明します。
また、シフト制を活用した賢い買い物も効果的です。平日の空いている時間帯にまとめ買いをすることで、セール品を効率的に購入できます。「早番の帰りに食材の見切り品を購入したり、夜勤明けにスーパーの開店直後に行ったりすることで、食費を大幅に削減できています」
このように、看護師の働き方に合わせた節約術を実践することで、無理なく継続的な支出削減が可能になります。重要なのは、自分のライフスタイルに合った方法を選び、長期的に続けられる習慣を作ることです。
次のセクションでは、これらの節約を確実に貯金につなげるための、具体的な収支管理の方法について解説していきます。
収支管理の具体的な手法
看護師の収入は、基本給に加えて夜勤手当や各種手当が加算される複雑な構造を持っています。効果的な貯金を実現するには、これらの収入を適切に管理し、計画的な支出につなげることが重要です。このセクションでは、実践的な収支管理の方法について詳しく解説します。
おすすめの家計簿アプリと使い方
デジタル化が進む現代では、スマートフォンの家計簿アプリを活用することで、効率的な収支管理が可能になります。ベテラン看護師は「夜勤中の空き時間にアプリで収支をチェックし、リアルタイムで家計の状況を把握できることが大きなメリットです」と語ります。
特に効果的なのは、レシート読み取り機能を持つアプリです。「忙しい勤務の合間でも、レシートを撮影するだけで支出を記録できます。月末の集計も自動で行われるため、残業や夜勤が多い月でも継続的な管理が可能です」と、ある主任看護師は説明します。
また、複数の口座を一元管理できる機能も重要です。「給与用、貯金用、投資用など、目的別に分けた口座の残高をまとめて確認できます。特に夜勤手当を別口座で管理する際に便利です」という声も聞かれます。
カテゴリー分析機能を活用することで、支出の傾向も把握しやすくなります。「夜勤が多い週は外食費が増える傾向にあることが分かり、お弁当を作り置きするなど、対策を立てることができました」というように、データに基づいた改善が可能になります。
給与明細の読み方と活用法
看護師の給与明細は、一般企業と比べてより複雑な構成になっています。基本給、夜勤手当、通勤手当、住宅手当など、様々な項目が含まれているため、その内容を正確に理解することが収支管理の基本となります。
「入職当初は給与明細の細かい項目の意味がわからず、手当の計算方法も理解できていませんでした。しかし、先輩看護師に教わりながら一つずつ理解していくことで、より効率的な収入管理ができるようになりました」と、ある中堅看護師は振り返ります。
特に重要なのは、変動する手当の把握です。夜勤手当は勤務回数によって変動し、祝日や年末年始の勤務では割増率が上がります。ベテラン看護師は「シフト表と給与明細を照らし合わせることで、手当の計算方法を理解できました。これにより、次月の収入予測が立てやすくなり、計画的な貯蓄が可能になりました」と説明します。
また、年間の収入サイクルを理解することも大切です。賞与の支給月や昇給時期、各種手当の見直し時期などを把握することで、長期的な収支計画が立てやすくなります。「6月と12月のボーナス時期を見据えて、大きな支出や投資のタイミングを調整しています」という工夫も聞かれます。
税金や社会保険料の理解も欠かせません。「確定申告で医療費控除を活用するため、関連する領収書は全て保管するようにしています。年間で10万円以上の還付を受けられることもあります」と、主任看護師は話します。
さらに、給与明細を活用した目標設定も効果的です。「基本給の20%は必ず貯金、夜勤手当は全額投資、という具合にルールを決めています。明細を見ながら毎月の振り分けを行うことで、計画的な資産形成ができています」
この方法により、多くの看護師が着実な貯蓄を実現しています。「給与明細の理解を深めることで、自分の収入構造が明確になり、より戦略的な資産形成が可能になりました」というように、給与明細は単なる収入の確認書類ではなく、財務管理の重要なツールとなっています。
支出を「見える化」する具体的な方法
看護師の不規則な生活リズムの中で、支出を正確に把握し管理することは容易ではありません。しかし、支出を「見える化」することで、より効果的な家計管理が可能になります。
「はじめは支出管理が苦手で、月末になると『お金がどこに消えたのか分からない』という状態でした。しかし、見える化の手法を取り入れてからは、無駄な支出が減り、月10万円以上の貯金が可能になりました」と、ある大学病院の看護師は語ります。
具体的な見える化の第一歩は、キャッシュレス決済の活用です。クレジットカードや電子マネーを使用することで、支出の履歴が自動的に記録されます。「夜勤明けの疲れた状態でも、支出の記録が残るため、後から確認して分析できます。特に、アプリと連携したクレジットカードを使うことで、カテゴリー別の支出が自動で分類されます」
ただし、現金支出も完全になくすことはできません。職場の自動販売機や小額の支払いなど、現金が必要な場面も多くあります。このような支出に対しては、「財布の中に領収書を入れるポケットを作り、必ず領収書をもらうようにしています。週末にまとめて家計簿アプリに入力することで、現金支出も管理下に置いています」という工夫も見られます。
支出のパターン分析も重要です。「夜勤の前後は外食が増える傾向にあることが分かったため、夜勤用の食事は前日に準備するようにしました。この習慣づけで、月の食費が2万円ほど削減できています」というように、データに基づいた改善が可能になります。
月単位の予算管理も効果的です。「月初めに、その月のシフトを確認しながら予算を立てます。夜勤が多い週は外食費の予算を多めに設定するなど、柔軟な調整を行っています」と、ベテラン看護師は説明します。
このような見える化の取り組みは、単なる支出管理にとどまらず、より良い生活習慣の形成にもつながります。「支出データを見返すことで、自分の生活パターンが明確になりました。無駄な支出を減らすだけでなく、より健康的な生活リズムを作ることができました」
次のセクションでは、これらの収支管理を基礎とした、看護師向けの資産形成の方法について詳しく見ていきましょう。
看護師向け資産形成の基礎知識
看護師の収入構造は、基本給に加えて様々な手当があり、資産形成においても独自の特徴があります。このセクションでは、看護師の立場を活かした効果的な資産形成の方法について、実践的な視点から解説していきます。
初心者でも始められる投資の方法
投資は多くの看護師にとって馴染みの薄い分野かもしれません。「最初は投資に対して不安がありましたが、少額から始めることで徐々に理解を深めることができました」と、ある総合病院の主任看護師は語ります。
初めての投資としておすすめなのが、積立投資信託です。毎月の夜勤手当から一定額を投資に回すことで、平均取得単価を抑えながら資産形成を進めることができます。「月の夜勤手当5万円を全額、インデックスファンドの積立に回しています。3年続けることで、予想以上の運用成果が出ています」という成功例も見られます。
特に、つみたてNISAは非課税メリットがあり、看護師の資産形成に適しています。「20年間非課税で運用できる点に魅力を感じました。毎月2万円を限度額いっぱいまで積み立てることで、将来の資金づくりを進めています」と、中堅看護師は説明します。
また、職場の確定拠出年金制度も積極的に活用すべきです。「iDeCoを始めてから、所得控除のメリットを実感しています。年末調整での還付金も、そのまま投資に回すことで資産形成を加速させています」という声もあります。
投資を始める際の重要なポイントは、自分の生活リズムに合わせた運用計画を立てることです。「夜勤明けは判断力が低下するため、投資の判断は必ず休日に行うようにしています。また、急な出費に備えて、投資額は手取り収入の30%を上限としています」
保険の見直しと活用方法
医療従事者である看護師だからこそ、保険の必要性を適切に判断できる立場にあります。「医療の現場を知っているからこそ、本当に必要な保障と過剰な保障を見極めることができます」と、ベテラン看護師は指摘します。
保険の見直しで最も重要なのは、すでに加入している保険の内容を精査することです。「入職時に勧められるまま加入した医療保険がありましたが、実は職場の共済で十分カバーできていることが分かりました。解約により月3万円の支出削減ができました」という経験を持つ看護師も少なくありません。
職場の福利厚生制度も見逃せません。多くの医療機関では充実した共済制度や団体保険が用意されています。「病院の団体保険に加入することで、個人で加入するより30%以上保険料を抑えることができました。その分を投資に回すことで、資産形成を加速させています」
生命保険については、収入保障保険の活用を検討する価値があります。「看護師は比較的安定した収入が見込めるため、死亡保障は収入保障保険で必要最小限に抑え、その分を資産形成に向けています」と、主任看護師は説明します。
また、医療保険は職種的な特性を考慮する必要があります。「看護師は医療費の実態を理解しているため、必要な保障を見極めやすい立場にあります。私の場合、入院給付金は日額5,000円程度に抑え、その分を積立型の保険に回しています」
特に注目したいのが、介護保険の考え方です。「現場で介護の実態を見ているからこそ、将来の介護リスクに備える重要性を実感しています。ただし、保険料の負担が重くなりすぎないよう、60歳以降開始の介護保険を選択しました」
保険の見直しによって削減できた支出は、必ず資産形成に回すことが重要です。「保険の見直しで月々4万円の支出削減ができました。この金額を全額投資信託の積立に回すことで、より効果的な資産形成が可能になっています」
将来設計に基づいた資産配分
看護師のキャリアは、一般企業と比べて長期的な展望が立てやすい特徴があります。「資格を活かして様々な働き方ができる看護師だからこそ、将来設計に合わせた計画的な資産配分が重要です」と、総合病院の看護師長は説明します。
資産配分を考える際の基本は、ライフステージごとの目標設定です。「20代は結婚・住宅資金、30代は教育費、40代以降は老後資金と、人生の節目ごとに必要な資金を明確にしています。それぞれの目標に応じて、安全資産と成長資産の配分を調整しています」
具体的な配分例として、ある中堅看護師は次のような戦略を実践しています。「給与の50%を生活費、30%を安全資産(定期預金・財形貯蓄)、20%を成長資産(投資信託・株式)に振り分けています。さらに、夜勤手当は全額を成長資産に回すことで、リスクの調整を図っています」
年代による配分の変更も重要です。「30代前半までは積極的な投資配分でしたが、出産を機に安全性を重視する配分に切り替えました。ただし、インフレに負けない資産形成のため、成長資産の比率は20%程度は維持しています」と、子育て中の看護師は語ります。
特に注目すべきは、看護師特有の収入構造を活かした配分方法です。「基本給からの積立は安全資産中心、夜勤手当からの積立は成長資産中心という配分により、収入源ごとにリスク管理を行っています。賞与は、その時々の目標に応じて柔軟に配分を決めています」
また、キャリアアップによる収入増加を見据えた配分調整も効果的です。「認定看護師の資格取得後は、増額された手当を全額投資に回すことにしました。既存の生活水準は変えずに、将来の資産形成を加速させることができています」
退職金を見据えた資産配分も忘れてはいけません。「公立病院勤務の場合、20年以上の勤続で相当額の退職金が期待できます。それを考慮して、現役時代の資産配分はやや積極的な姿勢を取っています」というベテラン看護師の声もあります。
次のセクションでは、これらの資産形成を実現する上で重要な、税金対策と各種制度の活用法について詳しく見ていきましょう。
税金対策と各種制度の活用法

看護師には、一般的な給与所得者とは異なる税制上の特徴があります。夜勤手当や各種手当の課税方法、医療従事者特有の控除など、理解して活用すべき制度が多くあります。このセクションでは、看護職に特化した税金対策と、活用できる制度について解説します。
確定申告のポイント
「最初は確定申告が難しく感じましたが、制度を理解することで年間10万円以上の還付を受けられるようになりました」と、ある主任看護師は語ります。
看護師の確定申告で特に重要なのが、医療費控除の活用です。医療従事者である看護師は、健康管理のために定期的な検査や予防接種を受けることが多く、これらの費用も医療費控除の対象となります。「職場の健康診断の自己負担分や、インフルエンザの予防接種費用なども含めて申告することで、より多くの還付を受けられています」
また、看護師の場合、ユニフォームのクリーニング代や専門書の購入費用なども、特定支出控除の対象となる可能性があります。「領収書は必ず保管し、年末に整理する習慣をつけています。特に、資格取得のための学費や教材費は、確実に申告するようにしています」
さらに、自己啓発費用も重要な控除項目です。「認定看護師の資格取得費用や、専門的なセミナー参加費用も申告対象になります。年間で相当額の控除を受けられる場合もあります」というベテラン看護師の声も聞かれます。
交通費に関する控除も見逃せません。「夜勤時のタクシー代は、通常の通勤経路とは別に控除対象となる場合があります。特に、深夜の公共交通機関が運休している時間帯の移動費用は、必ず記録を残すようにしています」
医療従事者向け優遇制度の活用
医療従事者には、一般的にはあまり知られていない様々な優遇制度が用意されています。「制度を知らないために利用機会を逃している看護師が多いのが現状です」と、総合病院の看護部長は指摘します。
住宅ローンについては、医療従事者専用の優遇金利を設定している金融機関が多くあります。「一般の金利より0.2〜0.3%優遇されるケースもあり、30年の住宅ローンで考えると、数百万円の差になることもあります」と、マイホームを購入した看護師は説明します。
医療従事者専用のクレジットカードも活用価値が高いツールです。「医療従事者カードは年会費が永年無料で、さらに保険が自動付帯されています。また、病院内での支払いにポイント還元率が上がるなど、職種特有の特典もあります」
資格取得に関する支援制度も見逃せません。「認定看護師や専門看護師の資格取得には多額の費用がかかりますが、都道府県や医療機関による補助金制度を利用することで、負担を大幅に軽減できました」という経験者も多くいます。
特に注目すべきは、医療従事者向けの財形貯蓄制度です。「一般の財形貯蓄に加えて、医療従事者専用の優遇制度があり、より有利な条件で資産形成ができます。特に非課税枠が拡大されている点は大きなメリットです」
また、年金関連の制度も重要です。「医療保険者が運営する年金制度に加入することで、将来の年金受給額を増やすことができます。掛け金も所得控除の対象となるため、税制面でもメリットがあります」とベテラン看護師は語ります。
職場の福利厚生を活用した節約術
医療機関の福利厚生制度は意外に充実していますが、十分に活用できていない看護師も多いのが現状です。「制度を詳しく知ることで、年間で50万円以上の支出削減につながりました」と、大学病院の主任看護師は語ります。
院内保育所の活用は、子育て中の看護師にとって大きなメリットとなります。「一般の保育所と比べて保育料が3割程度安く、夜勤対応の延長保育もあります。さらに、病児保育も利用できるため、急な子どもの体調不良でも安心して勤務を継続できます」
医療費の職員割引制度も見逃せません。「自院での診療や健康診断は大幅に割引されます。家族の医療費も対象となるため、年間で相当な支出削減になっています。また、提携医療機関でも割引が適用される場合があります」とベテラン看護師は説明します。
住宅補助も重要な制度の一つです。「病院の職員寮は、民間の賃貸と比べて家賃が半額以下です。光熱費も含まれている場合が多く、単身者なら月々の住居費を5万円以上節約できます」という声も聞かれます。
食事補助も効果的な節約につながります。「職員食堂は一般価格の半額程度で、栄養バランスも考えられた食事が提供されます。夜勤時の食事も補助があるため、月の食費を2万円以上抑えることができています」
さらに、職員向けの各種割引制度も充実しています。「提携スポーツジムやカルチャースクールの利用料が割引されるほか、旅行パッケージや家電量販店での購入も職員価格が適用されます。これらをうまく活用することで、趣味や自己投資の費用を抑えることができています」
また、職場の共済会や互助会による支援制度も活用価値が高いものです。「結婚祝い金や出産祝い金、子どもの入学祝い金など、ライフイベントごとに給付金が支給されます。これらは非課税所得となるため、そのまま貯蓄に回すことができます」と、中堅看護師は話します。
このように、職場の福利厚生を最大限に活用することで、効果的な支出削減が可能になります。重要なのは、利用可能な制度を正確に把握し、計画的に活用することです。
次のセクションでは、よくある疑問に答えるQ&Aコーナー「おしえてカンゴさん!」に移りたいと思います。
看護師さんからのQ&A「おしえてカンゴさん!」

現役看護師の皆さんから寄せられる、貯金や資産形成に関する疑問にお答えします。実践的なアドバイスと共に、具体的な解決方法をご紹介します。
Q1:夜勤手当は貯金に回すべき?
A:夜勤手当は貯金や投資に回すことをお勧めします。ベテラン看護師の多くが実践している方法は、「夜勤手当は生活費に組み込まない」というものです。
「夜勤手当は臨時収入ではなく、定期的な収入として捉えることが重要です。私の場合、手当を自動的に別口座に振り分け、その全額を積立投資に回しています。3年続けることで、約300万円の資産を形成できました」と、総合病院の主任看護師は語ります。
ただし、夜勤による身体的負担を考慮することも大切です。「無理な夜勤シフトは避け、自身の健康管理とのバランスを取ることを心がけています。適度な夜勤回数を維持しながら、継続的な資産形成を目指すことをお勧めします」
Q2:住宅ローンと資産形成のバランスは?
A:基本的な考え方として、住宅ローンの返済と資産形成は並行して進めることをお勧めします。
「住宅ローンの借入時は、返済額を手取り収入の25%以内に抑えることがポイントです。私の場合、35年返済で借入額を抑え、残りの収入から毎月10万円を投資に回しています」と、中堅看護師は説明します。
また、医療従事者向けの優遇金利を活用することも重要です。「医療従事者向けの住宅ローンは金利が0.2〜0.3%優遇されることが多く、この差額分を投資に回すことで、より効果的な資産形成が可能になります」
Q3:独身看護師の老後資金の目安は?
A:独身看護師の場合、65歳までに最低でも2,500万円程度の資産形成を目標にするとよいでしょう。
「独身者は配偶者からの収入補填が期待できないため、より計画的な資産形成が必要です。私の場合、35歳から月々15万円の積立を始め、投資と組み合わせることで目標達成のペースを保っています」と、40代のベテラン看護師は語ります。
具体的な準備方法として、「給与の20%を財形貯蓄に、夜勤手当の全額を投資信託に、賞与の50%をNISAでの投資に」というように、収入源ごとに貯蓄・投資先を決めている例も多く見られます。
Q4:貯金と投資のバランスはどうすべき?
A:年齢やライフステージによって適切な配分は変わりますが、基本的な目安として「安全資産7:成長資産3」からスタートすることをお勧めします。
「20代後半までは積極的に投資にも取り組んでいましたが、30代で結婚・出産を控えてからは、安全性を重視する配分に切り替えました。ただし、インフレ対策として、投資信託での積立は継続しています」と、主任看護師は説明します。
また、経験を積むことで徐々に投資の比率を上げていく方法も効果的です。「最初は給与の10%から投資を始め、運用に慣れてきたら20%まで増やしていきました。急激な変更は避け、段階的に移行することが重要です」
Q5:貯金を続けるモチベーション維持のコツは?
A:具体的な目標設定と、小さな成功体験の積み重ねが重要です。
「毎月の目標額を達成したら、その1%を趣味に使えるようルールを決めています。小さな楽しみを組み込むことで、長期的なモチベーション維持につながっています」と、中堅看護師は語ります。
また、同僚との情報交換も効果的です。「月1回、同期の看護師と『貯金会』を開いています。お互いの工夫を共有し、励まし合うことで、継続的な貯蓄が可能になっています」という声も聞かれます。
まとめ:看護師のための効果的な貯金・資産形成戦略

本記事では、看護師ならではの収入構造を活かした貯金術と資産形成の方法について、詳しく解説してきました。ここでは、重要なポイントを整理し、具体的なアクションプランをご提案します。
看護師の貯金術で最も重要なのは、収入の特徴を理解し、それぞれの手当を効果的に活用することです。特に夜勤手当は、多くの成功事例で貯蓄の核として位置づけられています。
実践するためのポイントは以下の3つです。
1つ目は、収入源ごとの明確な配分ルールを設定することです。基本給、夜勤手当、賞与など、それぞれの収入に対して具体的な使途を決めることで、計画的な貯蓄が可能になります。「基本給の20%は定期預金、夜勤手当は全額投資、賞与の50%は長期貯蓄」というように、明確なルールを持つことが重要です。
2つ目は、ライフステージに応じた柔軟な戦略の見直しです。20代では積極的な資産形成、30代では結婚・出産に備えた安定重視、40代以降では老後資金の確保など、年代ごとの目標に合わせて戦略を調整していく必要があります。
3つ目は、職場の制度や優遇措置を最大限に活用することです。医療従事者向けの特別な金融商品や、病院の福利厚生制度など、看護師だからこそ利用できる制度を積極的に活用することで、より効率的な資産形成が可能になります。
これらの戦略を実践することで、多くの看護師が年間100万円以上の貯蓄を実現しています。重要なのは、無理のない範囲で継続できる方法を見つけることです。
明日からできるアクションプランとして、まずは以下の3つのステップから始めることをお勧めします:
- 給与明細を見直し、各種手当の金額を正確に把握する
- 夜勤手当専用の口座を開設し、自動振り分けを設定する
- 職場の福利厚生制度を確認し、利用可能な制度をリストアップする
看護師という職業は、安定した収入と様々な手当を得られる恵まれた環境にあります。この環境を活かし、計画的な貯蓄と資産形成を進めることで、より安定した将来を築くことができるでしょう。
本記事が、皆さんの効果的な貯金術の実践につながれば幸いです。
参考文献・引用
本記事の作成にあたり、以下の文献・資料を参考にいたしました。
統計・調査データ
- 『2023年 病院看護実態調査』 日本看護協会
https://www.nurse.or.jp/nursing/assets/100.pdf - 『医療経済実態調査 結果報告に関する分析(健康保険組合連合会)』 厚生労働省 令和5年度版
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001173503.pdf
金融・投資関連
- 『つみたてNISA・一般NISAの概要』 金融庁
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/ - 『確定拠出年金(iDeCo)の制度案内』 国民年金基金連合会
https://www.ideco-koushiki.jp/
医療従事者向け制度
- 『看護職員確保対策』 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/
看護師の働き方改革関連
- 『夜勤・交代制勤務に関するガイドライン』 日本看護協会
https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/yakinkotai/guideline/index.html
- 『医師の働き方改革・医療従事者の勤務環境の改善について』 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/quality/