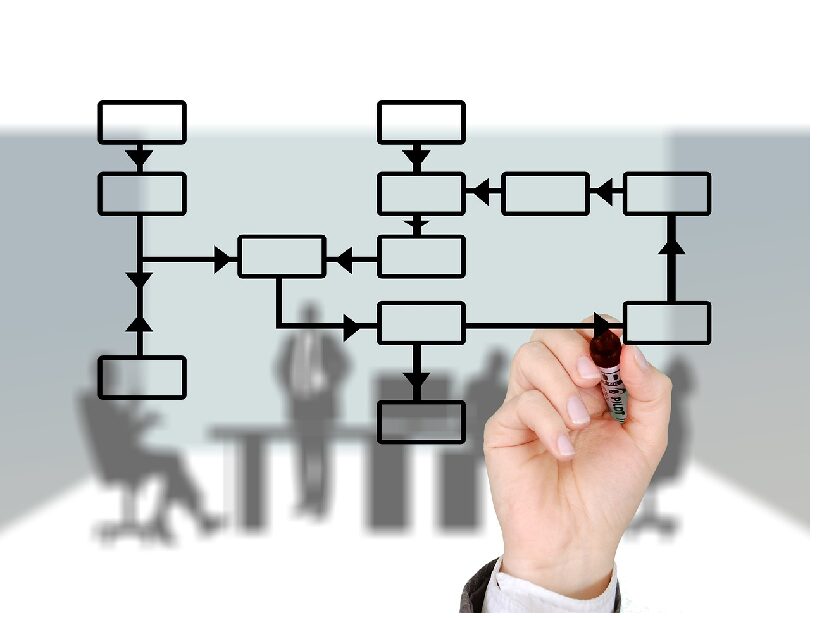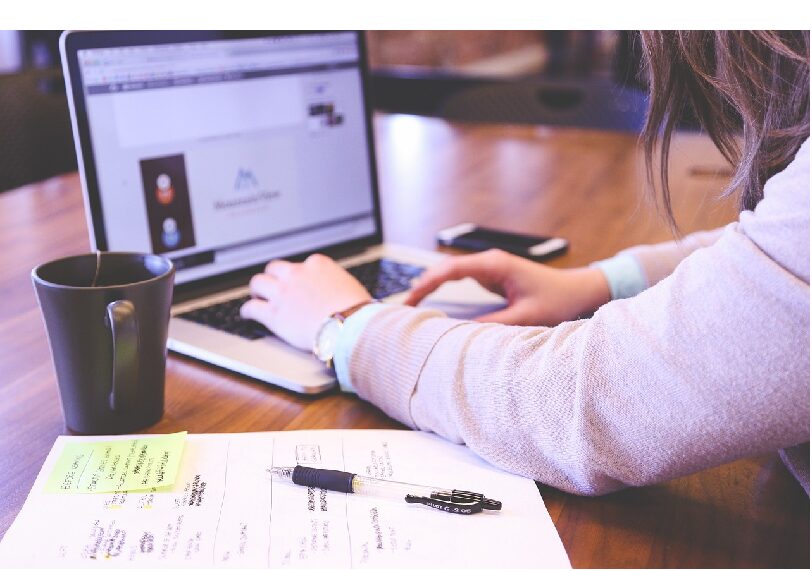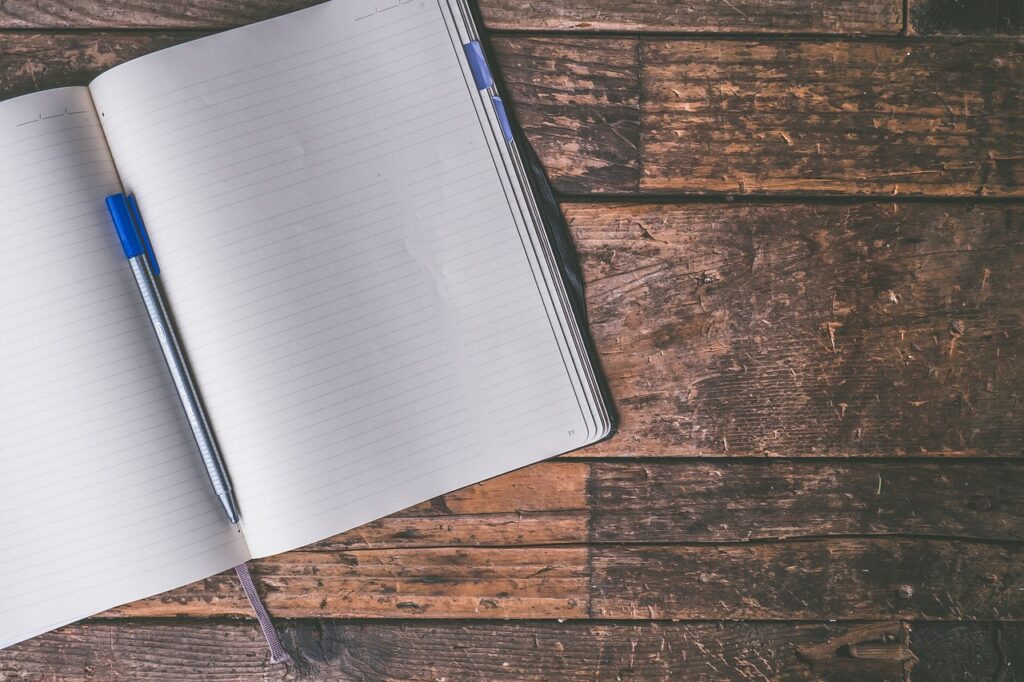看護学校への進学を考えている皆様にとって、具体的な費用計画の立て方から利用可能な支援制度まで、すべての疑問にお答えします。看護教育の第一線で活躍する専門家と共に、あなたの夢への第一歩をサポートしていきましょう。
この記事で分かること
- 看護学校の総費用(入学金・授業料・実習費など)の詳細な内訳と計算方法
- 国や自治体、医療機関が提供する支援制度の具体的な活用方法
- 各種奨学金制度の特徴と申請手順の詳細
- 在学中の生活費を含めた具体的な資金計画の立て方
- 返済負担を軽減するための実践的な予算管理術
この記事を読むべき人
- 看護学校への進学を検討している高校生の方
- 社会人からの転職で看護師を目指している方
- お子様の看護学校進学をサポートする保護者の方
- 奨学金や支援制度の活用を考えている方
- 具体的な費用計画を立てたい方
看護学校の費用総額と詳細な内訳

看護学校にかかる費用は、学校の種類や地域によって大きく異なります。入学から卒業までにかかる費用を詳しく理解することで、より現実的な進学計画を立てることができます。
ここでは、実際の数値をもとに、必要となる費用の全体像を具体的に解説していきます。
看護学校の種類別にみる費用体系
看護学校は設置主体や教育課程によって費用が異なります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
国立看護大学の費用体系
国立看護大学の年間授業料は一般的な国立大学と同様で、約54万円となっています。入学金は約28万円で、4年間の総費用は教材費や実習費を含めて約300万円前後となります。国立大学は初期費用を抑えられる一方で、入学試験の競争率が高いという特徴があります。
公立看護専門学校の費用構造
公立の看護専門学校は自治体からの補助があるため、比較的費用が抑えられています。入学金は15〜30万円程度、年間授業料は40〜60万円程度で、3年間の総額は約250万円となります。ただし、設置している自治体によって費用は変動します。
私立看護専門学校の費用詳細
私立の看護専門学校は入学金が30〜50万円、年間授業料が80〜120万円程度と、公立と比べて高額になります。3年間の総額は約400万円程度ですが、学校の特色や立地によって大きく異なります。
私立看護大学の費用水準
私立看護大学は4年制で、入学金が20〜50万円、年間授業料が100〜150万円程度と最も高額です。4年間の総費用は450〜600万円程度になりますが、充実した設備や教育内容が特徴となっています。
入学時に必要となる費用の詳細
入学時には複数の費用が同時に必要となります。計画的な準備が重要になりますので、具体的な項目を見ていきましょう。
入学金の地域差
入学金は地域によって差があり、都市部の学校は地方と比べて10〜20万円ほど高額になる傾向があります。例えば、東京都内の私立看護専門学校の場合、入学金は40〜50万円程度ですが、地方では30〜40万円程度となっています。
施設設備費の内訳
施設設備費には実習室の使用料や図書館費用、情報処理実習室の利用料などが含まれます。初年度は10〜30万円程度が必要で、2年目以降は年間5〜15万円程度に抑えられます。
実習用具・教科書代の詳細
実習用具には白衣や実習靴、聴診器などの医療器具が含まれ、15〜25万円程度が必要です。教科書代は年間で5〜8万円程度かかり、特に1年次は基礎医学や看護学の教科書が多いため、費用が嵩む傾向にあります。
年間にかかる経常的な費用
毎年必要となる費用について、具体的な金額と特徴を解説します。
授業料の支払い方法
授業料は通常、年2回もしくは4回の分割払いが可能です。一括払いの場合は割引制度がある学校もあります。年間の授業料は50〜120万円で、分割の場合は1回あたり15〜30万円の支払いとなります。
実習費の内容と金額
実習費には病院での臨地実習にかかる費用や保険料が含まれます。年間10〜20万円程度で、実習先への交通費や宿泊費は別途必要となる場合があります。実習の時期や回数によって費用は変動します。
教材費と学習環境整備費
教材費には定期的に必要となる参考書や演習で使用する消耗品費が含まれます。年間5〜10万円程度を見込む必要があります。また、オンライン学習システムの利用料なども含まれる場合があります。
生活費を含めた総合的な費用計画
学費以外にも、生活を維持するための費用が必要です。ここでは月額での具体的な試算を示します。
住居費の地域別比較
アパートの家賃は地域によって大きく異なります。東京23区内では6〜8万円、政令指定都市で4〜6万円、地方都市で3〜5万円程度が目安です。初期費用として敷金・礼金も必要となります。
食費と日用品費の目安
1ヶ月の食費は自炊中心で3〜5万円、日用品費は1〜2万円程度が一般的です。実習期間中は不規則な生活になりやすいため、食費が増加する傾向にあります。
通学費と実習交通費
通学定期代は路線や距離によって異なりますが、月額1〜3万円程度です。実習先への交通費は実習期間中の追加支出として、月額1〜2万円程度を見込む必要があります。
その他の必要経費
携帯電話代やインターネット料金、保険料などで月額2〜3万円程度が必要です。また、課外活動や親睦会の費用なども考慮に入れておく必要があります。
予備費の重要性と計画方法
予期せぬ支出に備えるため、予備費の確保も重要です。
急な出費への備え
実習器具の破損や修理、体調不良時の医療費など、突発的な支出に備えて年間20〜30万円程度の予備費を確保することをお勧めします。
行事費用の準備
卒業アルバム代や謝恩会費用、国家試験の受験料など、最終学年には特別な支出が増えます。これらの費用として15〜20万円程度を見込んでおく必要があります。
地域別の費用比較と特徴
地域によって学費や生活費に大きな差があります。主要な地域ごとの特徴を見ていきましょう。
首都圏の費用特性
首都圏では学費・生活費ともに高額となる傾向にあります。私立看護専門学校の場合、3年間の総額は450〜550万円程度となり、全国平均と比べて約50万円ほど高くなります。
政令指定都市の費用水準
政令指定都市では首都圏ほどではありませんが、やはり費用は比較的高めです。3年間の総額は400〜500万円程度で、地方都市と首都圏の中間的な位置づけとなっています。
地方都市の費用事情
地方都市では学費・生活費ともに比較的抑えめとなり、3年間の総額は350〜450万円程度です。特に家賃や食費などの生活費が首都圏の6〜7割程度で済むことが特徴です。
費用の支払い時期と方法
費用の支払いは計画的に行う必要があります。支払い時期と方法について詳しく見ていきましょう。
入学前の支払いスケジュール
入学金は合格通知から2週間程度で支払いが必要となります。また、施設設備費や前期授業料なども入学前に支払う必要があり、2〜3月に集中して大きな支出となります。
在学中の支払いパターン
授業料は通常、前期(4月)と後期(10月)の2回に分けて支払います。実習費や教材費は実習や授業の開始時期に合わせて請求されることが多く、春と秋に支出が集中する傾向にあります。
分割払いのメリットとデメリット
分割払いを選択すると1回あたりの支払い額は少なくなりますが、手数料が発生する場合があります。一括払いでは手数料が不要で、割引制度のある学校もありますが、まとまった金額の準備が必要です。
学費値上げへの対応策
近年の物価上昇に伴い、学費の値上げも懸念されています。対応策について考えていきましょう。
値上げの傾向と予測
過去5年間の推移を見ると、年間0.5〜1%程度の値上げが一般的です。特に実習費や教材費は物価上昇の影響を受けやすく、今後も緩やかな上昇が予想されます。
予備費の確保方法
値上げに備えて、年間の支出予定額の5〜10%程度を予備費として確保することをお勧めします。奨学金の増額申請も検討に入れておくとよいでしょう。
親元を離れて暮らす場合の追加費用
実家を離れて進学する場合は、追加の費用が必要となります。具体的な費用を見ていきましょう。
引越し費用の詳細
引越し費用は距離や荷物の量によって異なりますが、一般的に10〜20万円程度が必要です。この中には、運送費用の他に、新生活に必要な家具や電化製品の購入費用も含まれます。
帰省費用の計算
帰省費用は距離によって大きく異なります。例えば、東京-大阪間で往復2〜3万円、東京-福岡間で4〜5万円程度となります。長期休暇中の帰省を年3回程度と想定すると、年間で6〜15万円程度の費用が必要です。
一人暮らしの初期費用
敷金・礼金などの初期費用は家賃の3〜4ヶ月分程度が一般的です。さらに、家具や家電の購入費用として30〜50万円程度、生活用品の購入費用として10〜15万円程度が必要となります。
活用できる支援制度と奨学金

看護学校での学びをサポートする様々な支援制度や奨学金が用意されています。ここでは、利用可能な制度とその特徴、申請方法について詳しく解説していきます。
国の教育支援制度
国が提供する支援制度は、返済不要の給付型と返済が必要な貸与型があります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
修学支援新制度の概要
修学支援新制度では、世帯収入に応じて授業料と入学金の免除や減額を受けることができます。年収380万円未満の世帯を対象に、最大で年間91万円の支援を受けることが可能です。
日本学生支援機構の奨学金制度
第一種奨学金は無利子で、月額2万円から12万円までの中から選択できます。第二種奨学金は有利子で、月額2万円から12万円までの中から1万円単位で選択可能です。
看護師を目指す人向けの専門支援制度
看護師育成に特化した支援制度について説明します。
看護師等修学資金貸与制度
都道府県が実施する制度で、月額3万円から10万円程度の支援を受けられます。指定された医療機関で一定期間勤務すると、返済が免除される特徴があります。
病院奨学金制度の活用法
多くの医療機関が独自の奨学金制度を設けており、月額5万円から15万円程度の支援を提供しています。卒業後の就職先は限定されますが、手厚い支援を受けることができます。
地域別の支援制度
地域によって利用できる支援制度が異なります。主な地域ごとの特徴を見ていきましょう。
都道府県独自の支援制度
各都道府県が独自に実施している支援制度があり、地域の医療需要に応じて支援内容が設定されています。特に医療過疎地域では、より手厚い支援を受けられる可能性があります。
市区町村level支援プログラム
地域の医療機関確保を目的として、市区町村独自の支援制度を設けているところもあります。地域限定の制度は競争率が低く、採用されやすい傾向にあります。
民間の支援制度
民間団体や企業が提供する支援制度についても紹介します。
民間育英団体の奨学金
各種財団や企業が提供する奨学金制度があり、月額2万円から10万円程度の支援を受けることができます。返済不要の給付型が多いのが特徴です。
企業による看護師育成支援
医療関連企業が提供する奨学金制度もあり、月額3万円から8万円程度の支援を受けられます。企業との接点ができ、将来のキャリアにつながる可能性もあります。
特別支援制度
特定の条件を満たす場合に利用できる支援制度について説明します。
社会人学生向け支援
社会人経験者を対象とした支援制度があり、年齢制限が緩和されていたり、給付額が上乗せされたりする特徴があります。
ひとり親世帯向け支援
ひとり親世帯を対象とした追加支援があり、通常の支援に加えて月額1万円から3万円程度の上乗せ支給を受けられる場合があります。
複数の支援制度の組み合わせ方
支援制度は条件を満たせば複数を組み合わせることができます。効果的な活用方法を解説します。
給付型と貸与型の併用
給付型の支援と貸与型の奨学金を組み合わせることで、より安定した学資を確保することができます。返済の必要がない給付型を優先的に活用することがポイントです。
支援額の最適化方法
必要以上の借り入れを避けるため、学費と生活費を詳細に計算し、適切な支援額を設定することが重要です。将来の返済負担も考慮に入れて検討しましょう。
支援制度選択のポイント
どの支援制度を選ぶべきか、判断のポイントを解説します。
将来の進路との関連性
就職先が限定される制度の場合、その医療機関や地域で働くことへの適性を十分に検討する必要があります。
返済条件の比較
返済が必要な制度の場合、返済期間や金利条件を慎重に比較検討することが重要です。返済免除の条件がある場合は、その条件を満たせるかどうかも考慮に入れましょう。
支援制度の申請時期と準備
支援制度を確実に活用するためには、適切な時期に必要な準備を整えることが重要です。
申請時期の年間スケジュール
日本学生支援機構の奨学金は入学前年の春から申請が可能です。修学支援新制度は10月から申請を受け付けており、早めの準備が必要となります。
必要書類の準備
申請には世帯の所得証明書や住民票、学校からの推薦書などが必要です。特に所得に関する書類は取得に時間がかかる場合があるため、余裕を持って準備しましょう。
支援制度の利用実績と採用率
各支援制度の実際の利用状況について解説します。
制度別の採用実績
日本学生支援機構の奨学金は申請者の約80%が採用されています。一方、給付型奨学金は比較的競争率が高く、採用率は40%程度となっています。
採用されやすい時期と条件
4月入学の場合、前年度の10月から12月頃の申請で採用されやすい傾向にあります。世帯収入や学業成績に加えて、看護師を目指す明確な意思も評価の対象となります。
支援制度の継続条件と注意点
支援を継続して受けるための条件と注意点について説明します。
継続審査の基準
多くの支援制度では、毎年の成績評価や出席率などが継続条件となっています。一定の基準を下回ると支援が打ち切られる可能性があるため、学業との両立が重要です。
資格喪失のリスク管理
休学や退学の場合は支援が停止されます。また、アルバイト収入が一定額を超えると支援額が減額される場合もあるため、注意が必要です。
緊急時の支援制度
予期せぬ事態に備えた支援制度についても知っておくと安心です。
家計急変時の対応
保護者の失業や病気など、家計が急変した場合に利用できる緊急支援制度があります。通常の申請時期以外でも随時申請が可能です。
災害時の支援制度
自然災害により被災した場合、授業料の減免や特別な支援金の給付を受けられる制度があります。被災状況に応じて支援内容が決定されます。
卒業後の返済計画
貸与型の支援を利用する場合、卒業後の返済計画も重要です。
返済シミュレーション
平均的な看護師の初任給は月額21万円程度です。返済額は月収の8%以内に抑えることが推奨されており、具体的な返済計画を立てる必要があります。
返済免除の条件と手続き
医療過疎地域での勤務や、特定の医療機関での一定期間の勤務により、返済が免除される制度があります。条件を満たすための計画的なキャリア設計が重要です。
支援制度の選考過程
支援制度がどのように選考されるのか、詳しく解説します。
学力基準の詳細
多くの支援制度では、高校の評定平均値が3.5以上であることが求められます。ただし、社会人経験者の場合は、実務経験や志望動機を重視する制度も増えてきています。
所得基準の計算方法
世帯所得の計算では、両親の収入に加え、同居している家族の収入も考慮されます。所得には各種控除が適用され、実際の支援対象となる所得額は収入総額よりも低くなることが一般的です。
面接審査のポイント
給付型奨学金では面接審査が実施されることがあります。看護師を目指す明確な動機、将来のキャリアプラン、学習意欲などが評価の対象となります。
支援制度の併用ルール
複数の支援制度を組み合わせる際の具体的なルールについて説明します。
給付型支援の組み合わせ
給付型の支援制度は、原則として併用が制限されています。ただし、緊急支援や特別支援については、既存の支援との併用が認められる場合があります。
貸与型支援の利用限度
貸与型の奨学金は、総額で学費と生活費の実需要額を超えない範囲で、複数の制度を利用することが可能です。ただし、返済時の負担を考慮し、必要最小限の額に抑えることが推奨されます。
支援制度の最新動向
看護師を目指す学生への支援は年々拡充されています。最新の動向を見ていきましょう。
コロナ禍での特別支援
新型コロナウイルスの影響を受けた学生向けに、特別支援制度が設けられています。授業料の減免や特別給付金の支給など、様々な支援策が実施されています。
地域医療支援の強化
地域医療の担い手確保を目的として、地方自治体による支援が強化されています。特に、医療過疎地域での就業を条件とする返済免除型の奨学金が増加傾向にあります。
支援制度の活用事例
実際の支援制度活用例を見ていきましょう。
給付型中心のケース
修学支援新制度と地域の看護師育成支援制度を組み合わせることで、月額15万円程度の支援を受けているケースがあります。学業に専念できる環境を整えることができます。
貸与型活用のケース
日本学生支援機構の第一種奨学金と病院奨学金を組み合わせ、月額20万円程度の支援を受けているケースもあります。ただし、返済計画の慎重な検討が必要です。
国際的な支援制度
グローバルな視点での学びを支援する制度についても紹介します。
海外研修支援制度
海外の医療機関での研修機会を提供する支援制度があります。渡航費用や滞在費用の補助を受けることができ、国際的な視野を広げることができます。
留学生向け支援制度
日本で看護を学ぶ留学生向けの支援制度も充実しています。学費の減免や生活支援など、様々な形での支援を受けることが可能です。
よくある疑問と対応
支援制度に関してよく寄せられる疑問について回答します。
支援額の変更について
在学中に家計状況が変化した場合、支援額の増額や減額を申請することが可能です。ただし、審査があり、変更が認められない場合もあります。
休学時の取り扱い
病気や怪我などで休学する場合、支援は一時停止されます。復学後に支援を再開することができますが、支援期間の延長には制限があります。
支援制度の申請方法と手順

支援制度を利用するためには、正確な申請手続きと適切な書類の準備が必要です。ここでは、各支援制度の具体的な申請方法と注意点を解説します。
修学支援新制度の申請手順
修学支援新制度は入学前から申請が可能です。スムーズな手続きのために、具体的な流れを確認しましょう。
申請書類の入手方法
申請書類は進学予定の看護学校か日本学生支援機構のウェブサイトから入手できます。入学予定の学校に確認し、最新の様式を使用することが重要です。
所得証明書の準備
世帯全員の所得を証明する書類が必要です。市区町村役場で発行される所得証明書は発行に数日かかることがあるため、早めに準備を始めましょう。
日本学生支援機構奨学金の申請
日本学生支援機構の奨学金は、第一種と第二種で申請手順が異なります。それぞれの特徴を踏まえて準備を進めましょう。
スカラネットの登録方法
オンライン申請システム「スカラネット」への登録が必要です。入力にはID・パスワードが必要で、学校を通じて取得することができます。
収入に関する証明書類
保護者の源泉徴収票や確定申告書の写しが必要です。マイナンバーを利用する場合は、専用の申告書の提出も必要となります。
看護師修学資金の申請手続き
都道府県や市区町村が実施する看護師修学資金は、地域によって申請方法が異なります。
地域ごとの申請窓口
申請窓口は各自治体の医療人材課や看護協会となっています。事前に電話で確認し、必要書類を揃えることが重要です。
推薦書の取得手順
多くの場合、学校長の推薦書が必要です。推薦書の発行には1週間程度かかることがあるため、余裕を持って依頼しましょう。
病院奨学金の申請方法
医療機関が提供する奨学金は、各病院の採用計画に基づいて募集が行われます。
病院への応募手順
希望する病院の看護部や人事課に直接問い合わせを行います。見学会や説明会への参加が応募の条件となっている場合もあります。
面接試験の準備
多くの病院奨学金では面接試験が実施されます。志望動機や将来のキャリアプランについて、具体的に説明できるように準備しましょう。
申請時の注意点
支援制度の申請では、いくつかの重要な注意点があります。
提出期限の管理
各支援制度には明確な提出期限が設定されています。締切に間に合わないと、その年度の支援を受けられなくなる可能性があります。
書類の記入方法
記入漏れや押印忘れがないよう、チェックリストを作成して確認することをお勧めします。特に金額の記入には注意が必要です。
オンライン申請システムの使い方
最近では多くの支援制度でオンライン申請が導入されています。効率的な申請のためのポイントを解説します。
システムへのアクセス方法
各支援制度の専用ポータルサイトにアクセスするためには、事前に利用登録が必要です。登録には本人確認書類やメールアドレスが必要となります。
入力時の注意事項
入力途中でのタイムアウトを防ぐため、事前に必要な情報を整理しておくことが重要です。特に収入に関する情報は正確な入力が求められます。
申請後の流れ
申請書類の提出後、どのような流れで審査が進むのか把握しておきましょう。
審査状況の確認方法
多くの場合、オンラインシステムで審査状況を確認することができます。不備があった場合は早めに対応することが重要です。
採用通知への対応
採用が決定した場合は、指定された期限内に採用手続きを完了する必要があります。必要書類の準備を計画的に進めましょう。
申請書類の事前準備
スムーズな申請のために、必要書類を事前に準備しておくことをお勧めします。
本人確認書類の準備
マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証などの本人確認書類のコピーが必要です。有効期限の確認も忘れずに行いましょう。
成績証明書の取得
高校の成績証明書は発行に時間がかかる場合があります。複数の支援制度に申請する場合は、余分に取得しておくと便利です。
申請スケジュールの管理
複数の支援制度に申請する場合は、スケジュール管理が特に重要です。
年間スケジュールの立て方
各支援制度の申請時期を一覧表にまとめ、準備開始時期から採用通知までの流れを把握しておきましょう。
優先順位の決定方法
給付型の支援制度を優先的に申請し、その結果を見て貸与型の申請を検討するなど、戦略的な申請計画を立てることが重要です。
返済計画と予算管理

奨学金の返済は卒業後の生活に大きな影響を与えます。ここでは、無理のない返済計画の立て方と、在学中から卒業後までの効果的な予算管理について解説します。
返済計画の基本
看護師として働き始めてからの収入を見据えた、現実的な返済計画を立てましょう。
返済額の設定方法
月々の返済額は手取り収入の20%以内に抑えることが推奨されています。新人看護師の平均的な月収は手取りで18万円程度のため、返済額は3万6千円以内が目安となります。
返済期間の検討
標準的な返済期間は15年から20年です。返済期間を長くすると月々の負担は減りますが、総返済額は増加します。ライフプランに合わせて適切な期間を設定しましょう。
収支シミュレーション
卒業後の具体的な収支計画を立てていきます。
初任給の試算
看護師の初任給は地域や施設によって異なりますが、基本給で20万円から23万円程度です。夜勤手当や資格手当を含めると、月収は25万円から30万円程度となります。
生活費の見積もり
家賃、食費、光熱費、交通費など、基本的な生活費は月額12万円から15万円程度必要です。これに返済額を加えた支出総額を収入内に収める計画が重要です。
返済方法の選択
返済方法には複数の選択肢があります。自身の状況に合った方法を選びましょう。
定額返済方式
毎月の返済額が一定の方式です。計画が立てやすく、多くの奨学生が選択しています。ただし、返済開始時の負担は大きくなります。
段階的返済方式
初めは返済額を抑え、徐々に増やしていく方式です。キャリアの成長に合わせて返済額を増やすことができます。
予算管理の実践
効果的な予算管理により、返済を確実に行う基盤を作ります。
家計簿の活用方法
デジタル家計簿アプリを使用すると、支出の傾向を把握しやすくなります。特に変動費の管理に効果的です。
支出の優先順位
返済は固定費として最優先で確保します。その上で、生活必需品の支出、貯蓄、自己投資の順に予算を配分していきましょう。
緊急時の対応準備
予期せぬ支出に備えた計画も必要です。
貯蓄目標の設定
最低でも月収の3倍、理想的には6倍程度の金額を緊急用資金として確保することをお勧めします。毎月の収入から定額を積み立てる習慣をつけましょう。
減額返還制度の理解
収入が大幅に減少した場合や失業した場合に利用できる、返還額の減額制度があります。事前に条件を確認しておくことが重要です。
返済負担の軽減方法
計画的な返済により、負担を軽減する方法があります。
繰り上げ返済の活用
余裕がある時期に繰り上げ返済をすることで、総返済額を抑えることができます。ボーナスや臨時収入を活用するのが効果的です。
返済免除制度の利用
医療過疎地域での勤務や、特定の医療機関での継続勤務により、返済が免除される制度があります。キャリアプランと合わせて検討しましょう。
在学中からの資金管理
在学中から計画的な資金管理を始めることで、卒業後の返済負担を軽減できます。
アルバイト収入の活用
実習や学業に支障のない範囲でアルバイトを行い、返済に向けた貯蓄を始めることができます。医療関連のアルバイトは経験にもなります。
支出の見直し方法
定期的に支出内容を見直し、無駄な出費を削減することが重要です。特に、サブスクリプションサービスなどの継続的な支出は要注意です。
将来設計との調整
返済計画は将来の生活設計と密接に関連します。長期的な視点での調整が必要です。
ライフイベントへの備え
結婚や出産、住宅購入などのライフイベントを考慮に入れた返済計画を立てましょう。必要に応じて返済期間の見直しも検討します。
キャリアアップとの連動
認定看護師や専門看護師などの資格取得により収入増を図ることで、返済負担の軽減につながります。継続的な自己投資も重要です。
定期的な計画の見直し
環境の変化に応じて、柔軟に計画を見直すことが大切です。
見直しのタイミング
昇給や異動、生活環境の変化などのタイミングで計画を見直します。最低でも年1回は収支状況を確認しましょう。
調整の具体的方法
収入が増えた場合は返済額の増額を検討し、支出が増える場合は他の経費の見直しを行います。常に収支バランスを意識することが重要です。
税金と社会保険の管理
返済計画には税金や社会保険料も考慮する必要があります。
所得控除の活用
奨学金の返済額は所得控除の対象となる場合があります。確定申告を行うことで、税負担を軽減できる可能性があります。
社会保険料の把握
看護師として就職すると、健康保険、厚生年金、雇用保険などの社会保険料が給与から天引きされます。手取り額を正確に把握することが重要です。
金融リテラシーの向上
効果的な資金管理のために、基本的な金融知識を身につけましょう。
複利の理解と活用
貯蓄や投資において、複利の効果を理解することが重要です。早期から計画的な資産形成を始めることで、将来の経済的な余裕を作ることができます。
リスク管理の基礎
収入保障保険や医療保険など、必要な保障を適切に選択することで、不測の事態に備えることができます。
デジタルツールの活用
様々なデジタルツールを活用することで、効率的な資金管理が可能になります。
家計簿アプリの選び方
自動記帳機能や予算管理機能など、自分のニーズに合った機能を持つアプリを選びましょう。継続的に利用できるシンプルなものがおすすめです。
資産管理アプリの活用
複数の口座やクレジットカードの利用状況を一元管理できるアプリもあります。セキュリティ面にも配慮して選択しましょう。
金融機関との関係構築
返済を確実に行うために、金融機関との良好な関係を築くことが重要です。
返済に関する相談方法
返済に不安がある場合は、早めに金融機関の窓口に相談することをお勧めします。多くの場合、状況に応じた対応策を提案してもらえます。
口座管理の重要性
返済用の口座残高を確実に確保し、引き落とし日には必要額が不足しないよう注意が必要です。
将来の経済設計
返済計画は将来の経済設計の一部として考える必要があります。
資産形成の基礎
給与の振り込みと同時に、貯蓄や投資信託などへの自動積立を設定することで、計画的な資産形成が可能になります。
職場の福利厚生活用
財形貯蓄や企業年金など、職場で利用できる制度を積極的に活用することで、将来の経済的基盤を強化できます。
情報収集と相談窓口
最新の制度や支援策についての情報収集も重要です。
情報源の確認方法
日本学生支援機構のウェブサイトや看護師向けの専門サイトなど、信頼できる情報源から定期的に情報を収集しましょう。
専門家への相談活用
ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士などの専門家に相談することで、より適切な資金計画を立てることができます。
地域別・学校種別の費用比較

看護学校の費用は、地域や学校の種類によって大きく異なります。ここでは、主要な地域ごとの特徴と、学校種別による違いを具体的な数値とともに解説します。
首都圏の看護学校費用
首都圏の看護学校は、全国で最も費用が高額となる傾向にあります。
私立看護大学の費用水準
東京都内の私立看護大学では、4年間の総額が550万円から650万円程度となります。入学金は30万円から50万円、年間授業料は120万円から150万円が一般的です。
専門学校の費用構造
首都圏の私立看護専門学校では、3年間の総額が400万円から500万円程度です。入学金は30万円から45万円、年間授業料は90万円から120万円となっています。
関西圏の教育機関
関西圏は首都圏に次ぐ費用水準となっていますが、やや抑えめの傾向があります。
私立大学の特徴
関西圏の私立看護大学では、4年間の総額が500万円から600万円程度です。入学金は25万円から40万円、年間授業料は110万円から130万円が標準的です。
専門学校の実態
関西圏の私立看護専門学校の3年間の総額は350万円から450万円程度で、入学金は25万円から40万円、年間授業料は80万円から100万円となっています。
地方都市の学費事情
地方都市では、首都圏や関西圏と比べて比較的費用が抑えられています。
地方私立大学の費用
地方の私立看護大学では、4年間の総額が450万円から550万円程度です。入学金は20万円から35万円、年間授業料は100万円から120万円が一般的です。
地方専門学校の特徴
地方の私立看護専門学校では、3年間の総額が300万円から400万円程度となっています。入学金は20万円から30万円、年間授業料は70万円から90万円が標準的です。
公立校と私立校の比較
設置主体による費用の違いは、進路選択の重要な要素となります。
公立看護大学の特徴
公立看護大学の4年間の総額は350万円から400万円程度です。入学金は15万円から25万円、年間授業料は50万円から60万円と、私立の半分程度に抑えられています。
公立専門学校のメリット
公立看護専門学校は最も費用が抑えられており、3年間の総額が250万円から300万円程度です。入学金は10万円から20万円、年間授業料は40万円から50万円となっています。
総合的な学習環境の比較
費用だけでなく、教育環境も含めた総合的な比較が重要です。
施設設備の充実度
私立大学は一般的に施設設備が充実しており、シミュレーション機器や図書館なども最新のものが導入されています。その分、施設設備費として年間10万円から15万円程度が必要です。
実習環境の違い
大学付属病院を持つ学校では、実習環境が充実している反面、実習費用として年間15万円から20万円程度が必要となります。一方、公立専門学校では実習費用が年間8万円から12万円程度に抑えられています。
学校選びのための費用効果分析
総費用と教育内容のバランスを考慮した学校選びのポイントを見ていきます。
国家試験合格率との関連
一般的に、費用の高い私立大学では国家試験対策が充実しており、合格率も90%以上を維持している学校が多くなっています。一方、公立校でも80%以上の合格率を維持しており、費用対効果は高いと言えます。
就職実績の特徴
大学付属病院を持つ学校では、就職率が100%に近い水準となっています。ただし、初期費用が高額となるため、長期的なキャリアプランとの整合性を確認する必要があります。
地域特有の支援制度
地域によって利用できる支援制度が異なります。
地方自治体の独自支援
医療過疎地域では、地域の医療機関への就職を条件に、学費の全額または一部を補助する制度を設けています。月額5万円から10万円程度の支援が一般的です。
地域医療機関との連携
地域の基幹病院が看護学校と連携し、独自の奨学金制度を設けているケースもあります。年間100万円程度の支援を受けられる場合もあります。
進学先選択のための費用分析手法
効果的な進学先の選択には、総合的な費用分析が重要です。
初期費用の比較方法
入学金、施設設備費、実習用具費など、入学時に必要な費用を学校ごとに一覧表にまとめて比較することをお勧めします。地域による物価の違いも考慮に入れる必要があります。
総支出の試算方法
学費に加えて、生活費や交通費なども含めた総支出を算出します。首都圏では月額20万円程度、地方都市では月額15万円程度を目安として計算すると良いでしょう。
オンライン学習環境の比較
コロナ禍以降、オンライン学習環境の整備状況も重要な検討要素となっています。
デジタル設備の充実度
オンライン授業のための設備が充実している学校では、デジタル教材費として年間5万円から8万円程度が必要です。一方で、通学の負担が軽減され、交通費の節約にもつながります。
遠隔実習の実施状況
一部の実習をオンラインシミュレーターで代替している学校もあります。この場合、実習費用は従来より2万円から3万円程度抑えられますが、実践的な経験を補完するための追加実習が必要となる場合もあります。
学校選択時の費用効率化戦略
限られた予算で最大限の教育効果を得るための戦略を考えます。
通学圏内での学校選び
自宅から通学可能な範囲で学校を選ぶことで、住居費を大きく節約できます。首都圏では年間100万円以上の差額が生まれる可能性があります。
編入学制度の活用
看護系短期大学や専門学校から四年制大学への編入学を目指す場合、総費用を50万円から100万円程度抑えることができます。ただし、編入試験の準備も必要となります。
在学中の費用節約術

看護学校在学中の支出を効果的に管理することで、学生生活の経済的な負担を軽減できます。ここでは、実践的な費用節約のポイントを、具体的な金額と共に解説します。
教材費の節約方法
教材費は工夫次第で大きく節約することが可能です。
教科書の購入戦略
上級生から中古の教科書を購入することで、新品価格の40%から60%程度で入手できます。年間で2万円から3万円の節約が可能となります。
実習用具の選び方
実習用具は質を確保しながらも、セット販売などを利用することで費用を抑えることができます。標準的な15万円のセットが、12万円程度で購入可能です。
住居費の最適化
住居費は支出の中で大きな割合を占めます。
シェアハウスの活用
一人暮らしの場合、シェアハウスを選択することで、月額の家賃を通常の6万円から4万円程度に抑えることができます。
学生寮の利用
学生寮を利用する場合、月額2万円から3万円程度で住居費を抑えることが可能です。食事付きの寮であれば、さらに食費も節約できます。
日常生活での工夫
毎日の生活費を見直すことで、着実な節約が可能です。
食費の管理方法
自炊を中心とした食生活を送ることで、月額の食費を5万円から3万円程度に抑えることができます。実習期間中は特に計画的な食事管理が重要です。
通学費の削減
自転車通学が可能な場合、月額1万円から2万円かかる通学定期代を節約できます。雨天時のみ公共交通機関を利用するなど、柔軟な対応が効果的です。
学習関連費用の効率化
学習に関する支出も工夫次第で節約可能です。
オンライン学習の活用
無料の学習アプリやウェブサイトを活用することで、月額5千円から1万円程度かかる参考書代を節約できます。
グループ学習の効果
仲間とグループ学習を行うことで、参考書や問題集を共有でき、一人当たりの費用を半分程度に抑えることが可能です。
アルバイト収入の確保
効率的なアルバイト選びも重要です。
医療関連のアルバイト
病院や介護施設でのアルバイトは、時給が1,200円から1,500円程度と比較的高く、実践的な経験も積むことができます。
学内ワークスタディ
学内での事務アルバイトは、通勤時間が不要で、時給も1,000円程度と安定しています。学業との両立がしやすいのが特徴です。
実習期間中の費用管理
実習期間は特別な支出が増える時期となります。
実習先での費用
実習先での昼食代は、お弁当を持参することで一日800円から1,000円程度の節約が可能です。また、交通費も事前に経路を確認することで最適化できます。
体調管理の経済性
実習期間中の体調管理は、予防的な対策が重要です。栄養補助食品などに月額5千円程度の投資をすることで、体調不良による追加実習の費用を防ぐことができます。
長期休暇の有効活用
長期休暇は収入確保と費用節約の好機となります。
集中的な収入確保
夏季休暇などを利用して集中的にアルバイトを行うことで、月額15万円から20万円程度の収入を得ることが可能です。
帰省時の工夫
帰省時期を早めに計画し、交通費の割引チケットを活用することで、往復費用を通常の7割程度に抑えることができます。
デジタルツールの活用
スマートフォンアプリなどを活用した効率的な節約も可能です。
家計簿アプリの活用
家計簿アプリを使用することで、支出の傾向を把握し、月額の無駄な支出を3千円から5千円程度削減できます。
ポイント活用の工夫
キャッシュレス決済とポイントカードを組み合わせることで、月額の支出の1%から3%程度をポイントとして還元することが可能です。
健康管理による費用抑制
健康管理は学業の継続と費用抑制の両面で重要です。
予防医療の活用
学生健康保険を活用した定期健診や予防接種により、年間の医療費を2万円から3万円程度抑えることが可能です。
メンタルヘルスケア
学校の無料カウンセリングサービスを活用することで、メンタルヘルスケアの費用を月額1万円程度節約できます。
サークル活動での工夫
サークル活動も工夫次第で費用を抑えることができます。
用具の共同購入
サークルメンバーと用具を共同購入することで、一人当たりの負担を半額程度に抑えることが可能です。
イベント参加の選択
年間のイベント参加費用を計画的に管理し、重要度の高いものを選択することで、支出を3割程度削減できます。
季節ごとの節約対策
季節に応じた対策により、年間を通じて効果的な節約が可能です。
光熱費の管理
夏季は扇風機の活用、冬季は重ね着の工夫により、月額の光熱費を2千円から3千円程度抑えることができます。
衣類の購入時期
セール時期を活用した衣類の購入により、年間の衣類費を4万円程度から2万円程度に抑えることが可能です。
緊急時の支出対策
予期せぬ支出に備えた対策も重要です。
貯金目標の設定
毎月の収入から5千円から1万円程度を緊急用資金として確保することをお勧めします。実習器具の破損や体調不良時の対応に備えましょう。
保険の活用方法
学生総合保険に加入することで、年間1万円程度の保険料で、思わぬ事故や怪我による出費を抑えることができます。
情報収集による節約
効果的な情報収集により、様々な節約機会を見つけることができます。
学内の支援制度
学内の経済支援制度を活用することで、教材費の補助や実習費の一部免除など、年間5万円程度の支援を受けられる可能性があります。
地域の支援情報
地域の看護学生向け支援制度を利用することで、実習用具の割引購入や無料の学習支援を受けることができます。
卒業を見据えた費用管理
卒業年次には特別な支出が必要となります。
国家試験対策費用
早期から計画的に準備することで、模試や参考書の費用を分散させ、月々の負担を3千円から5千円程度に抑えることが可能です。
就職活動費用
オンライン説明会の活用や早期からの準備により、就職活動費用を通常の半額程度に抑えることができます。
コミュニティを活用した節約
同級生やシニア学生とのネットワークを活用した節約方法を紹介します。
情報交換の活用
先輩からの情報提供により、効果的な教材の選び方や実習準備の無駄を省くことができ、年間で3万円から5万円程度の節約につながります。
グループ活動の効果
グループでの学習会や実習準備を行うことで、参考書や実習用具の共有が可能となり、一人当たりの費用を2割から3割程度削減できます。
学業とアルバイトのバランス
効率的な時間管理により、学業を維持しながら収入を確保することができます。
時間配分の最適化
週12時間から15時間程度のアルバイトであれば、学業への影響を最小限に抑えながら、月額5万円程度の収入を得ることが可能です。
学習効率の向上
空き時間を効果的に活用することで、追加の学習費用を抑えながら、必要な学習時間を確保することができます
長期的な視点での節約
将来を見据えた効果的な支出管理について説明します。
資格取得の計画
在学中から計画的に関連資格の取得を進めることで、卒業後の追加費用を抑えることができます。BLSやACLSなどの資格は、学生料金を利用することで通常の6割程度の費用で取得可能です。
キャリアパスの設計
早期から将来のキャリアプランを考えることで、必要な学習投資を効率的に行うことができます。特定の分野に特化した参考書や講習会への参加を計画的に行うことで、年間の支出を2万円から3万円程度に抑えることが可能です。
ケーススタディ

実際の看護学生の事例を通じて、具体的な費用計画と支援制度の活用方法を見ていきましょう。ここでは、異なる背景を持つ3名の学生の事例を詳しく解説します。
高校新卒者の事例
高校を卒業してすぐに看護学校へ進学したAさんの事例を紹介します。
基本情報と家庭状況
18歳のAさんは、東京都内の私立看護専門学校に進学を決意しました。両親の年収は合計で420万円、兄が大学生という家庭環境です。
費用計画の詳細
3年間の総費用は450万円を見込んでいます。入学金40万円、年間授業料110万円、実習費・教材費が年間20万円となっています。
支援制度の活用方法
日本学生支援機構の第一種奨学金(月額5.3万円)と第二種奨学金(月額5万円)を組み合わせて活用しています。また、修学支援新制度により授業料の3割減免を受けることができました。
社会人経験者の事例
5年間の営業職を経て看護師を目指すBさん(28歳)の事例です。
就学までの準備
2年前から月額5万円ずつ貯金を始め、120万円の学費を準備しました。前職での経験を活かし、週末は医療事務のアルバイトを行っています。
学費と生活費の構成
国立看護大学に進学し、4年間の総費用は380万円を予定しています。貯蓄と両親からの支援50万円、奨学金を組み合わせて資金を確保しました。
収支計画の実際
アルバイト収入が月額8万円、奨学金が月額8万円、生活費が月額12万円で、収支のバランスを保っています。
ひとり親家庭の事例
母子家庭のCさん(17歳)は、地方の公立看護専門学校への進学を選択しました。
経済状況と支援制度
母親の年収は280万円で、修学支援新制度の対象となりました。授業料の全額免除に加え、給付型奨学金(月額7万円)を受給しています。
生活面での工夫
学生寮を利用することで住居費を月額2万円に抑え、食費も寮の共同キッチンでの自炊により月額3万円程度に節約しています。
長期的な計画
卒業後は地域の基幹病院での勤務を予定しており、病院からの奨学金(月額5万円)も利用しています。この奨学金は、卒業後3年間の勤務で返還が免除される制度となっています。
各事例からの学び
三つの事例から、効果的な学費計画のポイントを考察します。
早期からの準備の重要性
社会人経験者のBさんのように、計画的な貯蓄により初期費用の確保が可能です。在学中の収支計画も含めた総合的な準備が重要となります。
複数の支援制度の組み合わせ
Cさんの例のように、給付型奨学金と病院奨学金を組み合わせることで、より安定した学業生活を送ることができます。支援制度の eligibility(適格性)を早めに確認することが重要です。
支援制度活用の実践例
それぞれの事例における具体的な支援制度の活用方法を詳しく見ていきます。
給付型支援の最大化
Aさんの場合、家計基準を確認することで修学支援新制度の対象となり、年間授業料110万円のうち33万円が免除となりました。さらに、給付型奨学金との組み合わせにより、年間で70万円程度の支援を受けることができています。
貸与型支援の活用
Bさんは第一種奨学金の月額8万円を活用していますが、返還時の負担を考慮して第二種奨学金は利用せず、アルバイト収入で補完する選択をしました。
実践的な費用管理の例
各事例での具体的な費用管理方法を解説します。
収支管理の実際
Cさんは家計簿アプリを活用し、毎月の収支を細かく記録しています。固定費を除いた生活費を週単位で管理することで、月額15万円の予算内で生活を維持できています。
予期せぬ支出への対応
Aさんは毎月の奨学金から3万円を貯蓄に回し、実習器具の更新や急な交通費増加などに備えています。半年で18万円の緊急用資金を確保することができました。
将来を見据えた計画例
各事例における長期的な視点での計画を見ていきます。
返済計画の具体例
Bさんは卒業後の返済額を月額2万円に設定し、頭金として50万円を確保することで、返済期間を12年に抑える計画を立てています。
キャリアプランとの連動
Cさんは地域医療に貢献することを志望しており、その意向に沿った病院奨学金を選択することで、将来のキャリアパスと経済的支援を効果的に組み合わせることができました。
看護師さんからのQ&A「おしえてカンゴさん!」

現役の看護師や看護学生からよく寄せられる質問について、経験豊富な看護師が詳しく回答します。費用に関する不安や疑問を解消し、充実した学生生活を送るためのヒントをお伝えしていきます。
Q1:看護学校の初年度にかかる費用の総額はどのくらいですか?
初年度は入学金や設備費など初期費用が加わるため、最も支出が多くなります。私立看護専門学校の場合、入学金(30〜50万円)、授業料(80〜120万円)、実習費(10〜20万円)、教材費(15〜25万円)を合わせると、年間で150〜200万円程度が必要となります。
Q2:奨学金はいつから申し込めますか?
日本学生支援機構の奨学金は、入学前年の春から申し込みが可能です。特に予約採用を利用する場合は、高校3年生の5月頃から募集が始まります。入学後の申し込みも可能ですが、予約採用の方が採用されやすい傾向にあります。
Q3:アルバイトと学業の両立は可能でしょうか?
看護学校では実習や課題が多いため、週12〜15時間程度のアルバイトが現実的です。特に病院での看護助手や医療事務のアルバイトは、時給が1,200〜1,500円程度と比較的高く、実践的な経験も積めるためおすすめです。
Q4:実習にかかる追加費用はどのくらいですか?
実習では、ユニフォーム代(2〜3万円)、シューズ代(5千円〜1万円)、実習器具一式(10〜15万円)などの初期費用が必要です。その後も実習先への交通費(月1〜2万円)や昼食代(月1万円程度)などの経費が発生します。
Q5:家族の収入が少ない場合、どのような支援が受けられますか?
修学支援新制度では、世帯年収に応じて授業料の免除や減額を受けることができます。年収380万円未満の世帯では最大で年間91万円の支援を受けられます。また、各都道府県の看護師修学資金など、地域独自の支援制度も利用可能です。
Q6:病院の奨学金制度を利用する際の注意点は?
病院奨学金は返済免除の条件として、卒業後の一定期間(通常3〜5年)の勤務が必要となります。奨学金の月額(5〜15万円)と勤務条件を複数の病院で比較検討し、将来のキャリアプランに合った制度を選択することが重要です。
Q7:教科書や実習器具の節約方法はありますか?
上級生から中古の教科書を購入したり、実習器具を共同購入したりすることで、費用を抑えることができます。教科書は新品価格の50〜60%程度、実習器具は定価の70〜80%程度で入手可能です。
Q8:一人暮らしの場合の生活費はどのくらい必要ですか?
東京都内の場合、家賃(6〜8万円)、食費(3〜5万円)、光熱費(1〜2万円)、通学費(1〜2万円)、その他生活費(2〜3万円)で、月額13〜20万円程度が必要です。地方都市では家賃が3〜5万円程度と低くなります。
Q9:予期せぬ出費に備えていくら貯金が必要ですか?
実習器具の破損や体調不良による追加実習などに備えて、最低でも30万円程度の予備費を確保することをお勧めします。毎月の収入から3〜5万円程度を貯蓄に回すことで、1年目の終わりまでに準備できます。
Q10:奨学金の返済額はどのように設定すればよいですか?
看護師の初任給は月額21〜25万円程度です。返済額は手取り収入の20%以内に抑えることが推奨されており、月額3〜4万円程度が適切な設定となります。
Q11:学費の支払いは一括と分割どちらがお得ですか?
多くの看護学校では、一括払いの場合2〜5%程度の割引が適用されます。年間授業料100万円の場合、一括払いで2〜5万円の節約が可能です。
ただし、まとまった金額の準備が難しい場合は、学期ごとの分割払い(前期・後期各2回)を選択することで、1回あたりの負担を抑えることができます。
Q12:在学中に看護師の資格以外に取得しておくべき資格はありますか?
BLS(一次救命処置)やACLS(二次救命処置)の資格は、学生のうちに取得しておくと費用面でお得です。一般的に学生割引が適用され、通常15〜20万円の講習費用が8〜10万円程度で受講できます。また、医療事務の資格も就職後に活かせる実践的なスキルとなります。
Q13:看護学校の学費ローンについて教えてください。
教育ローンは、一般の銀行ローンと比べて金利が低く(年1.5〜3%程度)、返済期間も長めに設定できる(最長15〜20年)のが特徴です。日本政策金融公庫の教育ローンでは、年収基準(世帯年収200万円以上)を満たせば、最大450万円まで借り入れが可能です。
Q14:看護学校の編入学制度を利用する場合の費用はどうなりますか?
看護専門学校から看護大学への3年次編入の場合、通常の4年制大学と比べて1〜2年分の学費が節約できます。編入学試験の受験料(2〜3万円)や入学金(15〜30万円)は必要ですが、総額で100〜200万円程度の費用削減が可能です。
Q15:看護学校在学中の保険はどのようなものに加入するべきですか?
学生総合保険への加入がお勧めです。年間1〜2万円の保険料で、実習中の事故や針刺し事故の補償、通学中の怪我の保障が受けられます。また、加入必須の場合も多いため、入学前に必要な保険の種類と費用を確認しておくことが重要です。
まとめ
看護学校への進学には相応の費用が必要ですが、様々な支援制度を適切に活用することで、経済的な負担を大きく軽減できます。早めの情報収集と計画的な準備が重要です。
具体的な費用や支援制度の詳細は、お住まいの地域や志望校によって異なりますので、気になる学校には積極的に問い合わせてみましょう。
より詳しい情報や、現役看護師さんの体験談は【はたらく看護師さん】でご覧いただけます。 看護師専用のキャリアプランニングツールや、奨学金シミュレーター、先輩看護師への相談機能など、あなたの夢への一歩を全力でサポートいたします。
はたらく看護師さんの最新コラムはこちら