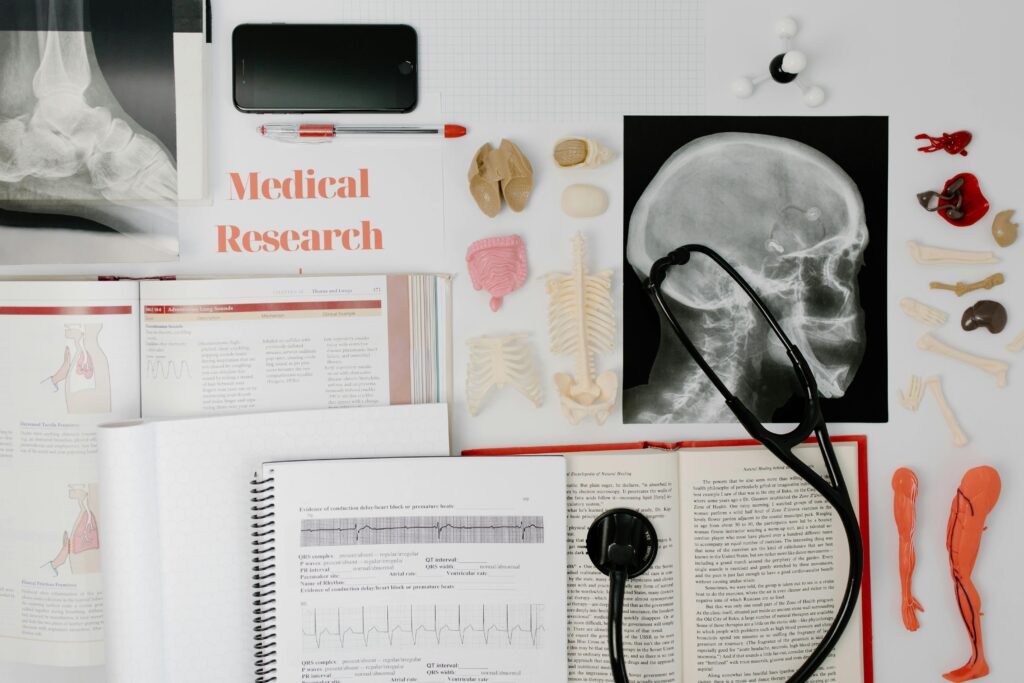医療・介護現場における個人情報保護の重要性が高まる中、具体的にどのような対策が考えられるか、多くの看護師が悩みを抱えています。
本ガイドでは、2025年の法改正に対応した最新の保護対策から、日常業務での具体的な実践方法、インシデント対応まで、現場で即活用できる情報を体系的に解説します。
デジタル化が進む医療現場で、確実な個人情報保護を実現するための実践的なガイドとしてご活用ください。
この記事で分かること
- 医療・介護現場における個人情報保護の基本的な考え方と実践方法
- デジタル時代に対応した具体的な情報管理とセキュリティ対策
- インシデント発生時の適切な対応手順と予防策
- 継続的な改善のための評価方法と教育研修の進め方
- 2025年の法改正に対応した最新の規制対応方法
この記事を読んでほしい人
- 医療機関や介護施設で働く看護師、
- 介護職員の方々、
- 医療情報管理者、
- 個人情報保護責任者、
- 医療機関の管理者の方々
基本的な保護体制の確立

医療機関における個人情報保護の基盤となる体制づくりについて解説します。
組織全体での取り組みと、個々の職員の役割を明確にし、実践的な保護体制の構築方法を示していきます。
現場で直接活用できる具体的な方針から、組織としての体制作りまで、体系的に説明していきます。
個人情報の定義と範囲
医療現場で扱う個人情報について、その定義と範囲を正確に理解することは、適切な保護対策を講じる上で最も基本的な要件となります。
医療における個人情報の特徴
医療分野における個人情報は、一般的な個人識別情報に加えて、診療情報や検査結果など、より機密性の高い情報を含んでいます。
患者さまの氏名、生年月日、住所などの基本情報に加えて、現在の病状や治療経過、既往歴などの医療情報も重要な保護対象となります。
これらの情報は、患者さまの人生に大きな影響を与える可能性があるため、特に慎重な取り扱いが求められます。
保護対象となる情報の種類
診療記録には、患者さまの症状や診断結果、処方内容、検査データなどが含まれます。
さらに、看護記録にはバイタルサインや日々の観察記録、ケア内容なども記載されています。
これらに加えて、患者さまの生活習慣や家族歴、心理社会的情報なども、重要な保護対象となります。
法的根拠と遵守事項
医療機関における個人情報保護は、各種法令やガイドラインによって規定されています。
これらの法的要件を理解し、確実に遵守することが求められます。
関連法規の理解
個人情報保護法の基本原則に加えて、医療・介護分野特有の規制についても理解が必要です。
2025年の法改正により、より厳格な管理体制が求められるようになっています。
特に要配慮個人情報としての医療情報の取り扱いについては、特別な注意が必要となります。
ガイドラインへの対応
厚生労働省から発行される医療・介護関係事業者向けのガイドラインに基づき、適切な情報管理体制を構築する必要があります。
また、各専門職の倫理規定や行動指針なども考慮に入れる必要があります。
組織体制と責任範囲
個人情報保護を効果的に実施するためには、明確な組織体制と責任範囲の設定が不可欠です。
保護管理体制の構築
個人情報保護責任者の選任から、部門ごとの管理者の配置まで、体系的な管理体制を整備します。
それぞれの職位における役割と責任を明確化し、組織全体として一貫した保護体制を確立します。
職員の役割と責任
看護師をはじめとする医療従事者一人一人が、個人情報保護の重要性を理解し、その役割を適切に果たすことが求められます。
日常的な情報管理から、インシデント発生時の対応まで、具体的な行動指針を示す必要があります。
基本方針の策定と周知
組織として個人情報保護に取り組む姿勢を明確にし、全職員に周知徹底することが重要です。
保護方針の明文化
医療機関としての個人情報保護方針を具体的に文書化し、全職員が参照できる形で提示します。
方針には、基本的な考え方から具体的な実践方法まで、明確に記載する必要があります。
教育研修体制の確立
定期的な研修会の実施や、新人教育プログラムへの組み込みなど、継続的な教育体制を整備します。
実践的なケーススタディを用いた研修により、実効性の高い教育を実現します。
評価と改善の仕組み
保護体制の有効性を定期的に評価し、必要な改善を行う仕組みを構築します。
定期的な評価の実施
保護体制の運用状況を定期的に確認し、問題点や改善すべき事項を明確にします。
評価結果に基づき、具体的な改善計画を策定します。
継続的な改善活動
PDCAサイクルに基づく改善活動を継続的に実施し、より効果的な保護体制の構築を目指します。
現場からのフィードバックを積極的に取り入れ、実践的な改善を進めます。
具体的な保護対策

医療現場における個人情報保護を確実に実施するため、物理的、技術的、運用面からの総合的な対策について解説します。
日常業務の中で実践できる具体的な方法と、組織として取り組むべき施策を体系的に示していきます。
物理的セキュリティ
医療情報の物理的な保護は、情報セキュリティの基本となります。
施設や設備の面から確実な対策を講じることで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。
施設における対策
建物や部屋の入退室管理を徹底し、権限のない人物が情報にアクセスできない環境を整備します。
特に、診療記録の保管場所や電子カルテの端末設置場所には、施錠可能なドアを設置し、入室権限を持つ職員を明確に定める必要があります。
また、防犯カメラの設置や警備員による巡回など、複合的な防犯対策も重要となります。
文書管理の具体策
紙媒体の診療記録や看護記録は、専用の保管庫で確実に管理します。
保管庫は耐火性能を備え、施錠可能なものを使用し、鍵の管理責任者を明確に定めます。
また、記録の持ち出しや返却の手順を明確化し、台帳による管理を徹底する必要があります。
機器・媒体の管理
電子カルテ端末やモバイル機器、USBメモリなどの記録媒体は、厳重な管理下に置く必要があります。
特に、持ち運び可能な機器については、盗難や紛失のリスクが高いため、使用記録の管理や保管場所の指定を徹底します。
技術的セキュリティ
デジタル化が進む医療現場において、技術的なセキュリティ対策は極めて重要です。
システムやネットワークの面から、確実な保護対策を実施します。
アクセス制御の実装
電子カルテシステムやその他の医療情報システムへのアクセスは、IDとパスワードによる認証を基本とします。
さらに、指紋認証やICカードなど、多要素認証の導入も推奨されます。各職員の職務や権限に応じて、適切なアクセス権限を設定することも重要です。
ネットワークセキュリティ
医療情報を扱うネットワークは、外部からの不正アクセスを防ぐため、ファイアウォールやウイルス対策ソフトの導入が必須となります。
また、通信の暗号化やVPNの使用など、データ転送時のセキュリティ確保も重要です。
データバックアップと復旧
システム障害や災害時のデータ損失を防ぐため、定期的なバックアップの実施が必要です。
バックアップデータの保管場所は、本番環境とは物理的に離れた場所に設定し、確実な復旧手順を確立します。
運用面での対策
日常業務における具体的な運用ルールと手順を確立し、確実な情報保護を実現します。
職員一人一人が実践できる具体的な方法を示します。
業務手順の標準化
情報の取り扱いに関する標準的な手順を明確に定め、文書化します。
診療記録の作成から保管、閲覧、廃棄に至るまで、一連の流れを明確にし、すべての職員が同じ基準で業務を行えるようにします。
情報持ち出しの管理
診療記録や患者情報の院外持ち出しは、原則として禁止とします。
やむを得ず持ち出しが必要な場合は、責任者の承認を得る手順を確立し、持ち出し記録の管理を徹底します。
また、持ち出し時の安全対策についても、具体的な指針を示す必要があります。
外部委託時の対応
清掃業務や保守点検など、外部業者に業務を委託する際は、個人情報保護に関する契約条項を明確にします。
委託業者の従業員に対する教育要件や、情報漏洩時の責任範囲についても、明確な取り決めが必要です。
リスク管理と監査
定期的なリスク評価と内部監査を実施し、保護対策の実効性を確保します。
リスクアセスメント
定期的にリスク評価を実施し、新たな脅威や脆弱性を特定します。
特に、新しい医療機器や情報システムの導入時には、セキュリティリスクの評価を確実に行います。
内部監査の実施
保護対策の実施状況を定期的に確認するため、内部監査を実施します。
監査結果に基づき、必要な改善策を講じることで、継続的な改善を図ります。
日常業務における実践ポイント

看護業務の現場で実際に活用できる個人情報保護の具体的な実践方法について解説します。
患者さまとの関わりの中で、確実な情報保護を実現するための具体的な手順と注意点を示していきます。
患者対応時の情報保護
患者さまとの直接的なコミュニケーションにおいて、個人情報を適切に保護するための実践的な方法を説明します。
面談・問診時の配慮
診察室や面談室での会話は、周囲に内容が漏れないよう、適切な音量で行います。
患者さまの症状や治療内容について話す際は、パーティションや個室を活用し、プライバシーの保護に努めます。
また、患者さまの呼び出しの際は、診察番号を使用するなど、氏名を直接呼ばない工夫も必要です。
病室での情報管理
複数の患者さまが入院している病室では、処置や看護ケアの際に特別な配慮が必要です。
カーテンやスクリーンを適切に使用し、会話の内容が他の患者さまに聞こえないよう注意を払います。
また、ベッドサイドでの申し送りや処置の説明は、特に慎重に行う必要があります。
記録作成時の注意点
診療記録や看護記録の作成時における、具体的な情報保護の方法を示します。
電子カルテの使用
電子カルテの使用時は、画面が他者から見えない位置に端末を設置します。
また、離席時には必ずログアウトを行い、他者による不正アクセスを防止します。
パスワードは定期的に変更し、他者との共有は絶対に行わないようにします。
紙媒体の記録管理
紙カルテやメモ類は、使用後直ちに所定の場所に返却します。
不要となったメモ類は、シュレッダーで確実に廃棄します。
また、記録の記入は、他者の目に触れない場所で行うよう心がけます。
情報共有時の実践
医療チーム内での情報共有において、確実な情報保護を実現するための具体的な方法を説明します。
申し送り時の注意点
看護師間の申し送りは、専用の場所で行うことを原則とします。
廊下や詰所など、他者が通行する場所での申し送りは避けます。
また、申し送り時の資料は、使用後直ちに適切に管理します。
カンファレンスでの配慮
多職種カンファレンスでは、参加者の範囲を必要最小限に限定します。
また、カンファレンスで使用する資料は、会議終了後に回収し、確実に管理します。
オンラインでカンファレンスを行う場合は、通信の暗号化など、セキュリティ面での配慮も必要です。
外部とのやり取り
他の医療機関や関係機関との情報のやり取りにおける、具体的な保護対策を示します。
文書の送受信
診療情報提供書などの文書送付時は、宛先の確認を複数回行います。
FAXを使用する場合は、誤送信防止のため、送信前に宛先を声に出して確認し、送信後は到着確認を行います。
また、電子メールでの情報送信は、原則として禁止とします。
電話での問い合わせ対応
電話での問い合わせに対しては、相手の身元確認を確実に行います。
特に、患者さまの家族や関係者を名乗る場合は、事前に登録された情報との照合を行い、本人確認を確実に実施します。
緊急時の対応
緊急時においても、個人情報保護を確実に実施するための具体的な方法を示します。
救急対応時の配慮
救急搬送時など緊急の場合でも、患者さまの個人情報保護には十分な注意を払います。
特に、公共の場所での情報のやり取りは必要最小限に留め、周囲への配慮を忘れないようにします。
災害時の対応
災害発生時など、通常の体制が維持できない状況でも、可能な限り情報保護に努めます。
避難所などでの診療情報の取り扱いには特別な配慮が必要です。
インシデント対応

個人情報に関するインシデントが発生した際の具体的な対応手順と、その予防策について解説します。
迅速かつ適切な対応により、被害を最小限に抑え、再発を防止するための実践的な方法を示していきます。
発生時の対応手順
情報漏洩などのインシデントが発生した際の、組織的な対応手順について説明します。
初期対応の実施
インシデントを発見した場合は、直ちに上司に報告し、被害の拡大防止に努めます。
具体的には、情報漏洩の経路を特定し、それを遮断する措置を講じます。
また、関係部署への連絡を速やかに行い、組織全体での対応体制を確立します。
状況調査と記録
発生したインシデントの詳細な状況調査を実施します。
漏洩した情報の範囲、影響を受ける患者さまの数、漏洩の経路など、できる限り正確な情報を収集します。
調査結果は文書として記録し、後の分析や報告に活用します。
関係者への通知
影響を受ける患者さまへの通知を行います。
通知の内容には、発生した事象の説明、考えられる影響、医療機関としての対応状況を含めます。
また、行政機関への報告が必要な場合は、定められた手順に従って報告を行います。
予防的対応
インシデントの発生を未然に防ぐための、具体的な予防策について説明します。
リスクアセスメントの実施
定期的なリスク評価を実施し、潜在的な脆弱性を特定します。
業務プロセスの各段階におけるリスクを分析し、必要な対策を講じることで、インシデントの発生を予防します。
予防策の具体化
特定されたリスクに対する具体的な予防策を実施します。
技術的対策、物理的対策、人的対策を組み合わせた総合的なアプローチにより、効果的な予防を実現します。
再発防止策の策定
発生したインシデントの分析に基づき、効果的な再発防止策を策定します。
原因分析の実施
インシデントの直接的な原因だけでなく、組織的・構造的な問題点も含めて分析を行います。
システムの不備、手順の不明確さ、教育の不足など、様々な観点から原因を特定します。
改善計画の立案
分析結果に基づき、具体的な改善計画を策定します。
システムの改修、業務手順の見直し、教育プログラムの強化など、必要な対策を計画的に実施します。
組織的な体制強化
インシデント対応を通じて、組織全体の対応能力を強化します。
教訓の共有
発生したインシデントから得られた教訓を、組織全体で共有します。
事例研究として活用し、職員の意識向上と実践的な対応能力の強化を図ります。
訓練の実施
定期的なインシデント対応訓練を実施し、職員の対応能力を向上させます。
実際のインシデントを想定したシミュレーションを通じて、具体的な対応手順を確認します。
教育・訓練

医療機関における個人情報保護を確実に実施するため、職員への教育・訓練は極めて重要です。
効果的な教育プログラムの実施方法と、その評価方法について具体的に解説していきます。
定期的な教育内容
継続的な教育により、職員の個人情報保護に関する知識と意識を高めていきます。
基本的な教育プログラム
新入職員向けの基礎教育では、個人情報保護の重要性と基本的な取り扱い方法について学びます。
具体的には、法的要件の理解、組織の方針や規程の確認、日常業務における具体的な実践方法などを含みます。
また、実際の事例を用いたケーススタディを通じて、実践的な理解を深めます。
専門的な教育内容
管理職や情報管理責任者向けには、より専門的な内容の教育を実施します。
リスク管理手法、インシデント対応手順、部下への指導方法など、責任者として必要な知識とスキルを習得します。
また、最新の法改正や技術動向についても、定期的に情報提供を行います。
実践的な訓練の実施
知識の習得だけでなく、実践的なスキルを向上させるための訓練を行います。
ロールプレイング訓練
実際の業務場面を想定したロールプレイングを実施します。
患者さまとの対応場面や、インシデント発生時の対応など、具体的な状況を設定して訓練を行います。
訓練後は、参加者間で気づきを共有し、改善点を明確にします。
シミュレーション訓練
情報漏洩などのインシデント発生を想定したシミュレーション訓練を実施します。
初期対応から、関係者への通知、再発防止策の策定まで、一連の流れを実践的に学びます。
評価と改善
教育・訓練の効果を適切に評価し、継続的な改善を図ります。
理解度の評価
定期的なテストや確認テストにより、職員の理解度を評価します。
評価結果は、個人別に記録し、継続的な教育計画に反映させます。
特に、理解が不十分な項目については、個別のフォローアップを実施します。
実践状況の確認
日常業務における個人情報保護の実践状況を定期的に確認します。
チェックリストを用いた自己評価や、管理者による観察評価を実施し、教育内容の実践度を確認します。
教育記録の管理
教育・訓練の実施記録を適切に管理し、効果的な教育計画の立案に活用します。
実施記録の作成
教育・訓練の実施日時、内容、参加者、講師、評価結果などを記録します。
これらの記録は、教育効果の分析や、次回の教育計画立案の基礎資料として活用します。
個人別の履歴管理
職員個人ごとの教育履歴を管理し、計画的な能力開発を支援します。
特に、役職や担当業務の変更時には、必要な追加教育を確実に実施できるよう、履歴を活用します
評価と改善サイクル

個人情報保護の取り組みを継続的に向上させるため、定期的な評価と改善活動は不可欠です。
組織全体での PDCAサイクルの実践方法と、具体的な改善活動の進め方について解説していきます。
定期的な評価の実施
組織的な評価活動を通じて、現状の把握と課題の特定を行います。
自己評価の実施
部門ごとに定期的な自己評価を実施します。
評価項目には、日常的な情報管理の状況、教育・訓練の実施状況、インシデントの発生状況などを含めます。
評価結果は文書化し、改善活動の基礎資料として活用します。
外部評価への対応
第三者機関による評価や監査を定期的に受け入れ、客観的な視点からの評価を得ます。
外部評価で指摘された事項については、優先的に改善に取り組みます。
改善活動の推進
評価結果に基づき、具体的な改善活動を展開します。
改善計画の策定
特定された課題について、具体的な改善計画を策定します。
計画には、目標、実施項目、担当者、期限などを明確に定め、実行可能な内容とします。
実施状況の確認
改善活動の進捗状況を定期的に確認します。
予定通り進んでいない項目については、原因を分析し、必要な支援や計画の修正を行います。
継続的な改善の仕組み
組織全体で継続的な改善活動を推進する仕組みを構築します。
改善提案の促進
職員からの改善提案を積極的に受け付け、活用する仕組みを整備します。
現場の声を活かすことで、より実践的で効果的な改善活動を実現します。
好事例の展開
効果的な改善事例を組織全体で共有し、水平展開を図ります。
他部門の成功事例を参考にすることで、効率的な改善活動を推進します。
おわりに
本ガイドでは、医療現場における個人情報保護の実践方法について、具体的な手順と注意点を解説してきました。
個人情報保護は、医療の質と患者さまとの信頼関係を支える重要な基盤です。
日々の業務の中で、本ガイドの内容を実践していくことで、より安全で信頼される医療サービスの提供が可能となります。
医療を取り巻く環境は、デジタル化の進展とともに日々変化しています。
新たな技術やサービスの導入に伴い、個人情報保護の方法も進化していく必要があります。
本ガイドは定期的に更新され、最新の要件や実践方法を反映していきます。
すべての医療従事者が個人情報保護の重要性を理解し、具体的な実践を重ねることで、患者さまにより良い医療を提供できる環境を築いていきましょう。
付録
実践的な活用のための補足資料として、具体的なチェックリストと関連資料を掲載します。
A. 実践チェックリスト
日常業務における個人情報保護の実践状況を確認するためのチェックリストです。
A.1 日常点検項目
始業時と終業時に確認すべき項目を示します。
診療記録の保管状況、電子カルテのログアウト確認、情報機器の管理状況などが含まれます。
定期的なセルフチェックにご活用ください。
A.2 定期点検項目
月次、四半期、年次で実施する点検項目を示します。
教育記録の確認、機器の保守点検、規程類の見直しなど、計画的な点検を支援します。
B. 関連規程・様式
業務で必要となる各種規程や様式の例を示します。
B.1 基本規程
個人情報保護方針、情報管理規程、セキュリティポリシーなど、基本となる規程類を掲載します。
各医療機関の状況に応じて、適切にカスタマイズしてご活用ください。
B.2 各種様式
情報開示請求書、誓約書、持ち出し申請書など、実務で必要となる様式類を掲載します。
実際の運用に合わせて、必要な修正を加えてご活用ください。
C. 参考資料
関連する法令やガイドライン、技術情報などの参考資料を示します。
C.1 関連法令
個人情報保護法、医療法など、関連する法令の概要と参照先を示します。
定期的に最新の改正内容を確認し、適切な対応を進めてください。
C.2 技術情報
情報セキュリティに関する技術情報や、最新のトレンドについての情報を掲載します。
デジタル化の進展に合わせて、定期的に内容を更新していきます。
おしえてカンゴさん!個人情報保護Q&A

現場で働く看護師の皆さまからよくいただく質問について、ベテラン看護師のカンゴさんが分かりやすく解説します。
Q1:「患者さんの家族を名乗る方から電話で容態について問い合わせがありました。どこまで回答して良いでしょうか?」
カンゴさん:電話での問い合わせは、相手の身元確認が難しいため、特に慎重な対応が必要です。
まずは、患者さまが事前に情報提供を許可している方かどうかを確認します。
許可されている場合でも、あらかじめ決められた確認事項(例:患者さまの生年月日や住所など)で本人確認を行ってから、必要最小限の情報提供に留めましょう。
不安な場合は、必ず上司に確認してください。
Q2:「申し送り中に他の患者さんが近づいてきました。どのように対応すべきですか?」
カンゴさん:申し送りには多くの個人情報が含まれるため、他の患者さまに聞こえないよう特別な配慮が必要です。
まず、申し送りは専用の場所で行うことを原則とします。
やむを得ず病棟で行う場合は、一時的に申し送りを中断するか、場所を移動して続けましょう。
また、声の大きさにも注意を払い、必要に応じてカーテンやパーティションを活用することをお勧めします。
Q3:「実習生への指導で、患者さんの情報をどこまで共有して良いか迷います。」
カンゴさん:実習生も医療チームの一員として、必要な範囲内での情報共有は可能です。
ただし、事前に患者さまから実習生への情報提供の同意を得ることが重要です。
また、実習生には個人情報保護に関する誓約書の提出を求め、守秘義務について十分な説明を行います。
カンファレンスなどでの情報共有は、教育目的に必要な範囲内に限定しましょう。
Q4:「患者さんの写真を含む記録を作成する際の注意点を教えてください。」
カンゴさん:医療目的での写真撮影は、事前に患者さまの同意を得ることが必須です。
撮影の目的、使用範囲、保管方法について明確に説明し、文書での同意を得ましょう。
撮影したデータは、決められた方法で電子カルテに取り込み、個人のスマートフォンなどには絶対に保存しないでください。
また、創傷部位などの写真は、必要最小限の範囲のみを撮影するよう心がけます。
Q5:「オンライン会議システムを使用したカンファレンスの際の注意点は?」
カンゴさん:オンラインでのカンファレンスでは、通常の対面での注意点に加えて、システム面での対策も重要です。
必ず許可された会議システムを使用し、URLの取り扱いには十分注意を払います。
参加者は限定し、画面共有を行う際は個人情報の写り込みに注意が必要です。
また、会議の録画は原則として禁止し、メモを取る場合も個人情報の取り扱いには細心の注意を払いましょう。
Q6:「個人情報が漏洩してしまった場合、どのような対応が必要ですか?」
カンゴさん:情報漏洩に気づいたら、まず直ちに上司に報告することが重要です。
その後、情報管理責任者の指示のもと、漏洩の範囲の特定と影響の調査を行います。
患者さまへの説明と謝罪、再発防止策の策定など、組織として定められた手順に従って対応を進めます。
特に初期対応が重要ですので、日頃から対応手順を確認しておくことをお勧めします。
まとめ
個人情報保護は、医療現場において最も重要な責務の一つです。
本ガイドで解説した基本的な考え方と具体的な実践方法を日々の業務に活かすことで、より安全で信頼される医療サービスの提供が可能となります。
特に、デジタル化が進む現代の医療現場では、新しい課題に対する継続的な学習と対策の更新が欠かせません。
より詳しい情報や、看護師の皆さまの実践的なキャリアサポートについては、【はたらく看護師さん】をご活用ください。
個人情報保護に関する最新の事例や、実践的な研修情報、経験豊富な先輩看護師からのアドバイスなど、現場で役立つ情報が満載です。
会員登録いただくと、オンラインセミナーやeラーニング教材など、さらに充実したコンテンツをご利用いただけます。
【はたらく看護師さん】でできること
- 医療現場の実践的な知識やスキルアップ情報
- キャリアアップに役立つ研修・セミナー情報
- 経験豊富な先輩看護師との情報交換
- 最新の医療トレンドと対策方法の習得
ぜひ【はたらく看護師さん】に会員登録して、あなたのキャリアアップにお役立てください。